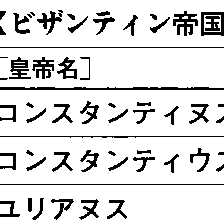改訂新版 世界大百科事典 「ビザンティン帝国」の意味・わかりやすい解説
ビザンティン帝国 (ビザンティンていこく)
古代ローマ帝国の中世における連続体(ただし首都はコンスタンティノープル。旧称ビュザンティウム,現イスタンブール)に対して,前者と区別する意味で後代につけられた名称。英語ではByzantine Empire。日本では東ローマ帝国と呼ばれることもある。両者はとぎれなき連続体であり,また正式の国名そしてまたこの国家の自己了解は,あくまでもローマ帝国Politeia tōn Rhōmaiōn(ギリシア語),Res Publica Romana(ラテン語)であった。
研究史
この国家と,その文化を対象とする専門研究分野はビザンティン学Byzantinologie(フランス語),Byzantinistik(ドイツ語)と呼ばれる。その誕生は,H.ウォルフをはじめとする16世紀のルネサンス人文主義者たちにさかのぼるが,研究対象が同じギリシア語文献だった関係もあって,ビザンティン学はいまだ古典文献学とは別の専門領域を形づくらなかった。
続いて,すべてを理性の光に照らして見る18世紀の啓蒙主義者ボルテール,モンテスキュー,なかんずくギボンによって,ビザンティン帝国は,近代ヨーロッパの生活理想を先取り的に実現したと彼らが考える古代ギリシア・ローマとは対照的な,野蛮と宗教が勝利を収めたその堕落形態という評価を与えられた。今日なお,煩瑣(はんさ)な(儀式),狡猾(こうかつ)な(外交),阿(おもね)った(美辞麗句),枝葉末節の(論議),そして旧套(きゆうとう)墨守の(態度)等々の意味で用いられる〈ビザンティン式〉という形容詞は,そこに発している(それらはいずれも,この歴史的一国家の特性として,事実,否定しえない)。
歴史的個体を,他によって置き換えることができない固有の価値として理解しようとする19世紀の歴史主義のもとで,ビザンティン学もまた,独自の自覚と厳密な方法を備えた歴史研究の一専門領域として確立された。しかし近代化に焦点を合わせた明治以来の日本における歴史研究・教育のシステムでは,ビザンティン学は存在の場をもたなかったといえよう。
時代的境界
ビザンティン帝国の終末を,オスマン帝国のスルタン,メフメト2世によるコンスタンティノープル攻略(1453年5月)に置くことに見解の分れはない(ただしビザンティン帝国の名目的宗主権下にあったモレア公国のミストラは1460年に,ギリシア人を支配者とする1204年以来の分裂国家の一つ,トレビゾンド帝国の首都は1461年に開城)。ビザンティン帝国は1453年に滅びたといえるとしても,オスマン帝国支配下および独立後のギリシアのみならず,それを越えて広く後代に,〈ビュザンティウムなき後のビュザンティウム〉という問題を残した。これに対し,その開始時点を設定することは,同帝国が古代ローマ帝国の延長である以上,そもそも問題たりえず,仮に叙述の便宜上なんらかの発足時点を設けなければならないとしても,一義的に行うことはできない。たとえば,それを,コンスタンティヌス1世による〈第二のローマ〉としてのコンスタンティノープル開都式(330年5月)に置くことは,この首都が,続く歴史において,文字どおり帝国の中心として比類なき役割を果たした点で,決して不当ではないが,それにはなお1世紀近くを要したのであって,むしろ4世紀は,アレクサンドリア,アテナイ,アンティオキア,エルサレムなど,古い伝統をもった帝国東半部の諸都市の並存によって特色づけられる時代であった。また統治機構の点からみれば,ビザンティン帝国の礎は,コンスタンティヌス1世よりも,ディオクレティアヌス帝にさかのぼり,テオドシウス1世の死(395)後に始まる東西分治も,広大な領土を治めるためディオクレティアヌスが定めた四分治制に基づく行政措置の適用例にすぎない。そして文化の点でも,たとえば文学史上,4世紀はヘレニズムの延長としてまとまった単位をなさず,キリスト教教父の文学活動という点では,すでに3世紀前から始まっていた。
地理的条件と民族・言語分布
ビザンティン帝国の支配が現実に及んだ地域は,その時々の国際政治関係を反映して,時代とともに大きく変わったが(後述),領土が縮小した最後の数世紀を除けば,地理的自然条件を異にしたさまざまな部分から構成されていたことが大きな特徴としてあげられる。
テオドシウス1世死後のローマ帝国分治の際の東半分領土は,6世紀前半のユスティニアヌス1世の再征服の結果,ダルマティア北部からイタリア半島,シチリア,サルディニア,コルシカ,バレアレス諸島,アフリカ北岸,そして一時的にはイベリア半島南東部にまで及んだ。続くランゴバルド族の南下にもかかわらず,イタリア南部は,ノルマン人が進出する11世紀後半までビザンティン帝国支配下にとどまった。7世紀以後のアラブ・イスラム教徒の地中海進出で,エジプト以西のアフリカ北岸は最終的に失われたが,10世紀には,クレタとアラブとの共同統治下にあったキプロスが奪回され,11世紀にはシチリア再征服さえ部分的に遂行された。他方,シリアからアナトリア東部にかけての地帯も,10~11世紀に再びビザンティン支配下に編入された。こうして,イタリア半島以東の地中海の島嶼と海岸地帯,黒海沿岸およびその北のかなめとして南ロシアのステップをにらむクリミア半島,高い山脈が森林で覆われたバルカン半島,アナトリア高原とそれに続くアルメニア山岳地帯,そして中東の砂漠までの異なった景観をもつ諸地域から成るのがビザンティン帝国領土であった。これら地域間のコミュニケーションも,当時に与えられた手段をもってしては容易でなく,9世紀にコンスタンティノープルから海路イタリアに向かうビザンティン使節は,日和にめぐまれた夏季でも優に2ヵ月を要した。
さまざまな民族が住み,その帰依する宗教や所属する教会,使用する言語が異なる点で,ビザンティン帝国はまた典型的な多民族国家の一つである。その政治,宗教,文化において指導的役割を果たしたのは,いうまでもなくギリシア人であるが,ビザンティン帝国はそれ以外の民族を多数抱えていた。
ユダヤ教徒は非キリスト教徒として,しばしば迫害と弾圧の対象になった。コンスタンティノープルから援軍を得られないままに,自力でランゴバルド族と対抗しなければならなかった西境のイタリアの都市住民の間には,7世紀のうちに地域主義的独立意識が成長した。東境のコプト人,シリア人,アルメニア人はいずれも,それぞれ固有の文字で自分たちの最初の民族文学としてキリスト教文学を展開させ始め,カルケドン公会議(451)で異端とされた単性論を奉じて,コンスタンティノープルの政府への同調を拒否した。その他東部国境地帯には,シリアの山地を基地に略奪をこととしたキリスト教徒マルダイト人Mardaitai,アナトリア東部に勢力を張っていた異端キリスト教徒パウロ派など,コンスタンティノープル政府の命令に服さない集団がいた。
他方ビザンティン帝国は,古代ペルシア帝国の再興を旗印にかかげた唯一の文化国家たるササン朝ペルシア帝国との対抗関係を別とすれば,その全期間を通じて,次々と国境に押し寄せる民族移動と直面しなければならなかった。バルカンでは,4世紀末にはゴート族(続いて彼らが移動した先のイタリアは,ユスティニアヌス1世の再征服後,6世紀末ランゴバルド族が侵入),5世紀にはフン族,6世紀以後にはスラブ人,6世紀末~7世紀前半にはアバール族,続いてセルビア人,クロアチア人,そしてブルガール族が現れた。7世紀中葉にはアラビア半島から地中海沿岸に到達したアラブが,パレスティナ,シリアを席捲してアルメニア,アナトリアに侵入する一方,エジプトからアフリカ北岸を西進するとともに,海軍力をもってコンスタンティノープル目ざしてエーゲ海を北上した。9世紀中葉以後にはバイキング(ルーシ)が黒海からコンスタンティノープル攻撃を繰り返した。カスピ海・黒海北岸のステップ地帯からは,9世紀末にはマジャール人,11世紀にはペチェネグ,クマンが相次いで現れ,11世紀後半にはセルジューク・トルコのアナトリア侵入が始まった。
11世紀末以降ビザンティン帝国は西ヨーロッパからの新たな勢力と対応しなければならなくなった。ノルマン人の侵入を先ぶれとした十字軍騎士の遠征,経済的活力にあふれたベネチア,ピサ,ジェノバなどのイタリア商業都市のレバント貿易進出がそれであり,その帰結が,ビザンティン領土での,十字軍封建諸国家(ラテン帝国)の建設,ならびにイタリア都市国家の植民地設定であった。そして,ヨーロッパの大砲鋳造技術者を雇い入れたオスマン・トルコによって,ついにコンスタンティノープルは陥落した。
以上の諸民族の一部はビザンティン帝国領土に住みついてその統治に服する帝国民となった(続いて彼らは,しばしば国内の人口過疎地帯に植民のため移住させられた)ほか,国境外に住む者も,集団的に,あるいは個々に国境を越えてビザンティン帝国の軍隊に傭兵として編入された。国家高位の文武官職や爵位の保持者となったこれら諸民族の出身者も決して少なくなく,彼らはビザンティン帝国の正統信仰を受け入れ,ギリシア的教養を急速に身につけた。その点でとくに顕著なのが,7~11世紀ではアルメニア人,12世紀以後には,フランク人と呼ばれた西ヨーロッパ人であった。以上の諸民族との関係を律するにあたってのビザンティン帝国の外交基本原則は,キリスト教ローマ帝国理念から発していた。
キリスト教ローマ帝国理念
コンスタンティヌス1世の時代にカエサレアの司教エウセビオスによって提唱されたこの理念の内容は次のようであった。すなわち,ローマ帝国初代の皇帝アウグストゥスは,神の摂理で世界をキリスト降誕のそのときに統一し,それによってキリストの福音がひろまるべき政治的な枠組みをつくり上げた。その300年後にコンスタンティヌス1世が現れ,同じく神の摂理で自らキリスト教に改宗するとともに,ローマ世界帝国のなかにキリストの教えを有機的に植えつけた。こうして出現したキリスト教ローマ帝国は,全世界を包括し,全人類をキリストの再来までまとめ上げておくべき唯一の秩序として,神の人類救済計画の最後の,必然的な一環である。天上のキリストの帝国の,不完全な模像であるこの帝国に君臨するのは,天上の唯一の〈全能の神(パントクラトルPantokratōr)〉に相当する〈全能の皇帝(アウトクラトルAutokratōr)〉であり,彼は世俗的な事がらだけでなく,精神的な事がらについても,最高の権限を神から委託された代理人である。この皇帝の臣民たる〈ローマ人(ロマイオイRhōmaioi)〉は,天上の秩序の模像たるローマ法の秩序に守られ,その保障する平和のもとで文化の名に価する生活を独占的に享受する。そして,天使の階層秩序を範として序列づけられた皇帝役人によって統治される。このローマ人に属さないのが〈野蛮な(バルバロスbarbaros)〉民族(エトネethnē)である。彼らはローマ皇帝の支配下にたまたま立ってこそいないが,いつの日かそれに服すべき,潜在的なその臣民である。その彼らに対しては,皇帝の二重の使命,つまり支配権(インペリウム)によって世界を統轄すべき政治的使命と,布教によって世界をキリスト教化すべき宗教的使命とが,相携えて遂行される。こうして,歴史的偶然にすぎない一国家を必然化する一つの政治神学が誕生した。
この〈ローマ人と蛮族〉という句によって表明されたのは,ビザンティン帝国民の政治的独占意識である。ここでいうローマとは,テベレ河畔の都市の名称ではもはやなく,人類史上最後のものとしての帝国の名称であり,その名を称しうるのは地上で自分たちの国家しかありえなかった。それを物語るのが,カール大帝がローマ皇帝を称したとき,彼らが示した拒否反応である。そして,この〈ローマ人〉が独占的に所有していると彼らが考える文化とは,内容的には古典ギリシア文化にほかならなかったことを,たとえば,ラテン語を蛮族用語とみなす,ギリシア語中心のその言語観が裏書きしている。いずれにせよ,かかる意識の背後にあるのは,地中海周辺の全域にわたる民族移動のただなかにあって,ひとりビザンティン帝国でのみその名に価する国家と文化が存続したのに反し,その国境地帯に定住した諸民族が,例外なしに,初めてその国家と文化の建設に向かわなければならなかったという,中世初期の現実である。
しかしビザンティン帝国はそのキリスト教ローマ帝国理念の国際関係への適用にあたっては,驚くほど柔軟であった。それを示すのが,ビザンティン皇帝を家父長とし,諸国の支配者たちをその兄弟,息子,友人などにみたてる,霊(プネウマ)をきずなとした擬制的家の理論であり,ビザンティン帝国は,自らが唯一の世界帝国だという基本理念は下ろさないままに,この理論によって,現実に対等の政治勢力となったフランク王国やアラブ・イスラム国家のその支配者を,ビザンティン皇帝との兄弟関係に位置づける平和共存の道も心得ていた。また,その支配権の妥当する範囲が全世界に及ぶとする主張にもかかわらず,自らの力の限界をわきまえていたビザンティン帝国は,対外関係において,多くの場合,お家芸の外交手段を尽くして問題の処理に努めたのであり,少数の皇帝を別とすれば,せっぱ詰まらなければ,軍事力の投入に踏み切らなかった。まして宗教のための十字軍という思想のごときは,この帝国には無縁であった。ビザンティン帝国が力こぶを入れたのはキリスト教化の使命の方であり,周辺諸民族へのキリスト教布教は,ビザンティン皇帝を洗礼の名付け親として,まずその支配者とその宮廷を取り込むというかたちで端緒が切られ,民族ぐるみの改宗への道が開かれることになった。こうして南スラブ諸族やキエフ・ロシアのキリスト教化がおこり,東方正教圏が成立した。異民族宮廷のキリスト教改宗としばしば組み合わされたビザンティン皇女の〈降嫁〉も,少なくとも一時的な国際的緊張緩和に役立った。相次いでコンスタンティノープルを訪れる周辺〈蛮族〉からの使節の応対にいとまない迎賓館マグナウラMagnaura宮殿の謁見の間では,彼らが3度跪拝(きはい)する間に,皇帝は天井まで引き上げられ,〈機械じかけの神〉が実演された。彼らの列席のもとに繰り広げられる宮廷儀式への参加を通じて,コンスタンティノープル市民は,自分たちが選ばれたシオンの町の民であることを自己確認した。
帝国の政治と社会
皇帝制
政治神学によって,この世における神の代理人にまで高められたビザンティン皇帝の地位は,対内的にはきわめて不安定であった。皇帝支配の政体そのものを変革しようという企ては起こらなかったが,帝位に就いた個々の皇帝個人が絶えざる批判にさらされたばかりでない。この帝国の1000年余の歴史で,主帝として文字通り統治を行った88人のうち,43人を下回らない者が革命で失脚し,そのうちの30人もが非業の最期を遂げた。しかもこの数字は,たまたま革命が成功した例外ケースにすぎず,不首尾に終わった大部分の例は枚挙にいとまがない。帝位に一族出身者を送り続けた支配者家族,いわゆる王朝を数えれば,30に達する。しかも4~5という少数によってカバーされたビザンティン帝国最後の300年においてさえ,血統カリスマの観念が,支配の正統化の原理として自らを貫徹させたわけではなかった。これは,国民が皇帝を選挙する権利を有するというコンセンサスが,ビザンティン帝国の書かれざる憲法として人々の意識のなかに定着していたからである。ただ選挙といっても,それは投票ではなく,候補者として新たに名のりをあげた者を国民が歓呼して受け入れるというかたちで,換言すれば,自分たちの同意を儀式として演出し,それを法的に拘束力あるものとして表明することを通じて行われた。あるいは,現皇帝が自分の息子を後継者候補として国民の前に提示し,同じ手続きで彼らから承認を取り付けるかたちで行われた。つまりビザンティン帝国では,革命たると父から子への帝位継承たるとを問わず,皇帝たらんとする者はこうして合憲性を得たのであり,そのどちらになるかは,時の政府に対する世論の動向や,その時々の力関係とかかわっていた。手続きの省略は必ずといっていいほど批判を呼んだ。これを要するにビザンティン帝国では,皇帝とは,共同体の主人ではなく,共同体のメンバーからその管理をゆだねられた存在だったのであり,事実,何人ものビザンティン人自身の口を通してそのことが語られている。それは,ローマ古来の国家(レス・プブリカ)の伝統が,アウグストゥスがそのかたわらに設置した皇帝権(元首政)によっても,またその強化(独裁政)にもかかわらず,包摂され尽くすことなく生き続けたからである。
皇帝選挙権者として国民を代表する勢力は時代とともに変遷した。皇帝が軍団を率いて国境地帯を転戦していた3~4世紀には,皇帝候補を軍隊宿営地で,歓呼によって信任するのは軍隊であった。だが4世紀末以来皇帝は新首都コンスタンティノープルを常住の地とするようになった。首都で帝国統治のための中央政府の官僚機構が形成されるに伴って,皇帝は高官や元老院議員によって取り巻かれる一方,その頃属州各地から急速に集まった大都会住民のまっただなかにおかれることになった。この変化に見合って皇帝選挙権者として新たに登場するのが元老院および市民という2要素であり,軍隊と相まって,この3者による選挙が合憲的な皇帝をつくり出すことになった。総主教による新皇帝戴冠はかかる憲法行為の意味をもたなかった。帝国行政の最高幹部から成る元老院はもはや古ローマのように古い家がらの議員から成ってはいなかったが,その後継者をもって任じ,かつて共和政的諸特権の移譲を通じて皇帝権を設けたのは自分たちの祖先だということを決して忘れなかった。これに反して,雑多な構成から成る市民は,依拠すべきかかる伝統をもたなかった。しかし社会的流動性に富み,ことのほか政治に関心を寄せるレバント的な大都市住民として,彼らはただ数だけがたよりであり,衆をたのんで皇帝選挙への参加をかちとるとともに,全帝国民を代表する首都市民という自意識を急速に身につけ,この最高の国家儀式への参加を通じて,そのつど皇帝選挙権者としての自らの地位を身をもって再確認した。これに反して軍隊はますます背後に退き,儀仗兵としてそれに加わるシンボル的一要素にすぎなくなった。
11世紀以後,首都聖職者層の皇帝選挙への介入という新傾向がおこった。その担い手の一つは,総主教が主催する,〈滞在者宗教会議(シュノドス・エンデムサ)〉に参加する首都滞在の主教たちであり,アナトリアの大半がアラブ,トルコのために失われた結果,管轄区を失って首都に逗留する彼らの数は増し,会議は恒常的になった。いま一つの担い手は,同会議の本来の議事進行者である,ハギア・ソフィア教会の輔祭や管理職のスタッフであり,彼らはエクソカタコイロイと呼ばれ,法学的知識を学び,首都の名家と同族関係にあった。なお皇帝と教会の関係については〈皇帝教皇主義〉の項目を参照されたい。
行政運営
〈ヨーロッパ中世におけるビザンティン帝国の独自性は,13世紀以前にはこの帝国がただひとり,中央集権的な国家のタイプを提示したところに由来する。ここでは,中央から発した衝撃は最遠隔の属州に達し,国家は,言語の点で異なり,ときに利害の分かれる諸民族にただ一つの意志を強制することができた〉(ビザンティン学者ブレイエの言葉)といわれる。しかしビザンティン帝国の行政組織は,官僚の権限が指揮命令系統や職務分掌関係の上で一分のすきもなく整然と統合された状態からはほど遠く,反対に,以下のような諸特色がみられた。
それぞれ別個に設けられた官職体系と爵位体系との間には,通常,対応関係がみられたが,その際,皇帝との緊密な関係を表す爵位の方が,官職にまさる社会的評価を与えられた。特定の官職をもたない爵位保持者も存在した。その上,本来両体系のいずれにも属さず,自らは所轄庁をもたず,ビザンティン人歴史家によってオスマン・トルコの大ワジールと比較された皇帝補佐(メサゾンmesazōn)があって,諸官庁の職務遂行を調整,統轄,監督した。その他宮廷内の職務を担当した宦官は,皇帝に最も近い場所にいた関係上,しばしばその特命をじきじきにうけた。こうしたさまざまな手段で皇帝は,固有の自意識をもった官僚勢力を統御しながらその政策の実現をはかった。
官僚は文官,武官から成っていたが,文官はコンスタンティノープルを牙城として全国の行政,財政,司法をその手におさめるとともに,皇帝から特定の軍事的職務を付託される場合がまれでなく,また肩書以外の,他の特定の文官職務の遂行に起用されることも多かった。武官が特定の文官職務を委託される例も存在するが,彼らは概して本来の職務に専念する場合が多かった。その他,兼職はしばしば行われた。売官,売位は広く普及した慣行であった。国家財政役人による徴税と並んで,租税徴集の請負制が大幅に採用された。軍隊司令官や財政役人に任ぜられた輔祭や修道士の個別例にもかかわらず,社会通念上,聖職者身分は国家官職就任の不適格者とみなされた。ビザンティン官僚の典型は,ギリシア的教養を身につけた〈マンダリン〉(原義はヨーロッパ人が,読書人であることを必須とした中国の士大夫官僚を指した呼称)であった。4世紀における官僚制の急速な展開に伴って,帝国行政での仕官によって身を立てようとする若者向けに,ローマ帝国東半部でもローマ法学教育が普及したが,時代とともにギリシア的一般教養に基づく教育理念が勝利をおさめ,この理念を体現したビザンティン文人により官僚層が構成された。コンスタンティノープルのいわゆる帝国大学法学部が目標としたのも,国家行政の専門職としての高級官僚の養成ではない。
古代ローマ帝国から受け継がれた国家行政機構(その起源は,共和政の共同体的役職(マギストラトゥス)よりは,元首政下で皇帝がつくりあげた家産的な役職に発する)は,時代の変化に柔軟に順応した。その代表的事例がテマ制である。ディオクレティアヌス帝は,属州駐屯の諸軍団が相次いで革命を起こし,それぞれの司令官を皇帝に推戴した3世紀の教訓にかんがみて,軍民両政を分離するとともに,従来の属州単位を細分化した。しかし続いて異民族侵入の圧力が増大するなかで,例外措置を再び設けなければならない事態が到来する。6世紀末ラベンナとカルタゴに設置され,コンスタンティノープルの皇帝から〈副王〉にも近い大幅な独立的権限を与えられて軍民両政をつかさどる総督(エクサルクス)制がそれであり,ことに7世紀にアナトリアで開始するテマ制がそれである。軍民両政の権限は再び駐屯軍の司令官(ストラテゴスstratēgos)の手に帰するとともに,その管轄領域として,より広い地域が定められる。こうして侵入アラブ軍に対する在地の軍事抵抗組織ができるが,他面その結果,独断専行権を中央政府から認められたこの軍人属州知事は,皇帝に対し反乱を起こす。そこで属州の規模は縮小され,一人の軍人の手に集中されていた軍民両政の権限は再び分離されて,その一部は文官に戻されるとともに,地方に分散されていた軍隊指揮権は新たに中央に集中されなければならない。事実,東方ならびに西方軍総司令官のような大指揮権が現れ,続いてこの二つを合わせた統一的指揮権の保持者が帝位に就くことになる。
社会経済事情
全行政・文化機能を自らに集中させたコンスタンティノープルはまた商工業活動の最大の中心地であり,それへの課税は重要な国庫収入を生む一方,全国農村人口から国家財政機構を通じて徴収される地租がここに流入した。これら条件のもとで,首都は全帝国をも巻き込む社会的流動性の主舞台となり,下層に属する者たちの上昇と,上層に属する者の転落という,社会的対流現象が大規模に繰り返された。その起動力となったのは皇帝である。皇帝は,しばしば最下層の属州民家族の生れであり,無一物のまま幸運を求めて都に上り,高官,高爵位の権門勢家を渡り歩いて奉仕を行いながら,社会的に上昇してやがて自らもそれに列し,ついに革命で帝位に就いた。彼は自らの従者団を用いてそれを行ったのであり,成功の暁には,そのメンバーに論功行賞として利権がらみの官職と爵位を配分し,統治機構の中枢部を自派で固めた。これは裏を返せば,同一の手順で皇帝権を獲得した先行皇帝のもとで要職を占めていたその従者団メンバーの上層からの転落と,その財産の没収が同時に進行したことを意味する。同一支配者家族内での政権交代の際でも,先行皇帝の政府首脳部が新皇帝によって引き継がれるとは限らず,事情に応じてそれなりの交代が起こった。上層から追われた先行皇帝の従者団は,中層の商工業者の段階に踏みとどまることができなければ,最下層の無産都市労働者になるか,属州民のなかに姿を消したが,その結果,首都のこれら中層には政治的要素が流入し,彼らが現政府に対する明確な批判意識の持主として,革命の企てに参加する要因ともなった。
社会上層のこのような不安定性から,ビザンティン帝国では世襲貴族身分の形成は現実にきわめて困難であった。反対に,社会の最下層から身を興して位人臣を極めた例がまれでなく,成上り者は社会通念上,蔑視の対象とならなかった。ビザンティン帝国では,上層とは国家という巨大な〈再分配〉(K. ポランニーの用語)の機構のかなめに,あるいは官職,あるいは爵位を媒介として身を置き,権威をたてに,たとえば特定商品の独占販売制を実施して,そこから利益を引き出す機会を手にした,アルコンテスarchontesと呼ばれた社会層である。そこには属さない者たちも,彼らと〈コネ〉をつけることによって,自らもそれなりにこのような機会にあずかろうと狂奔した。このことは,上記の再分配への関与がビザンティン帝国ではいかに〈うまみ〉あるものだったかを裏書きしており,売官,売位の普及もこれと関係している。社会的上層所属者の土地所有は,基本的には,こうして彼らが手にした利益の投資の結果である。中央政府は,在職中の(ことに首都の)高官の,属州における土地取得にさまざまな規則を設けて,中央集権的国家行・財政機構の運営に支障をきたさないよう配慮した。
12世紀以後,首都の社会的流動性は失われる一方,全土を覆っていた中央集権的行・財政機構には亀裂が生じた。それに代わって,ビザンティン帝国最後の300年には,西ヨーロッパの封建制の特色と類似した次のような,政治的,社会的,経済的現象が現れ,それをめぐって学界ではビザンティン封建制論争が起こった。その現象とは,(1)特定区域の徴税権を移譲されたプロノイア保有者,大行政地域をそこでの国家高権と一括して下賜された地方行政長官,その所領について不輸不入の特権を与えられた修道院,(2)皇帝に特別の私的誓約を行い,奉仕の代償として,皇帝からの一定の反対給付にあずかる家人(オイケイオイ)団,(3)大所領の隷属農民(パロイコイ),の登場である。これらの類似点は,しかしながら,歴史における合流現象convergenceではあっても,ビザンティン帝国と西ヨーロッパとが〈発展段階説〉上の同一発展段階に所属したことの表れと解釈することは,両者の歴史上の出発点,そしてまた帰着点の基本的差異にかんがみ,おそらく成り立たないであろう。また,新来スラブ人によるビザンティン帝国の再生という,西ヨーロッパ・ゲルマニスト学説ならびにエンゲルスの焼直しについても,同じことがいえる。
聖職者身分
ビザンティン帝国では,社会的,経済的に同質でないその構成員をまとめあげることができるような,固有の〈聖職者〉的団体意識も,西ヨーロッパ中世聖職者身分にとって精神的統一の基礎となったような神学的教養課程も欠如していた。反対に,この帝国の世俗セクターにおける上中下の社会層区分が聖職者身分にも該当し,たとえばその最上層であるコンスタンティノープル総主教は,皇帝奉仕の世俗高官の不安定性を分有し,皇帝はその人選に決定的役割を果たすとともに,意のままに彼らを罷免した(ユスティニアヌス1世からアレクシオス1世コムネノスに至る550年ほどの間に総主教座に上った52名中,19~20名を下回らない者が皇帝によって一時的ないし最終的に強制退位させられている)。多くの府主教は,その書簡が物語るように,皇帝の都から遠ざかり,その教区にとどまることを基本的には流刑と受け取ったのであり,世俗セクター上層の中央志向と軌を一にしていた。
ビザンティン帝国では初等教育は,聖職者,俗人を問わず,同一のギリシア的一般教養課程である。神学高等教育機関は存在しなかった。他方,神学は聖職者固有の身分特権でなく,それにかかわる俗人の割合は高い比率を占めていた。文筆活動に携わる聖職者層が服したのは,ギリシア的教養理想であり,この点で彼ら(ことに,首都の教会関係機関で書記職を務めた多数の聖職者)は,この理想を担う首都の文人層に属したのである。それと対照をなすのが,パパスと呼ばれた村の妻帯者司祭である。彼らは,告解を〈霊(プネウマ)を担う人〉とされた修道士によって奪われて,ミサと洗礼と埋葬の執行者にすぎなくなり,そのわずかな収入を補うために,しばしば商い,畑仕事や手仕事で糊口(ここう)をしのがなければならなかった。
ビザンティン帝国では,西ヨーロッパのように,具体的な生活目標と普遍拘束的な生活方法を掲げるところの,細部にまでわたる規則によって貫徹された統一的修道院団体は存在しなかった。各修道院ごとの個人主義が一般的であり,共同生活(コイノビオス)でなく,いくつもの小グループに分かれて,それぞれが自活する(イディオリュトモス)形態や,修道士が一修道院に定着せず,移動を繰り返す慣行まで現れる一方,聖書を読むことにさえ警告を発する荒野の苦行の達人や,柱頭行者(ステュリタイ)のような伝統が生まれた。西ヨーロッパと違って,ビザンティン修道士にとって神への帰依と文芸の奨励とは,調和ではなく,二者択一の対象であり,彼らは彼岸を目ざす瞑想生活(ビオス・テオレティコス)を理想に,完全なキリスト者という極限価値を社会で代表する存在となった。ビザンティン帝国では教養理想とは非修道士的であり,これは首都の文人層によって担われたのである。その他,修道士は,廃位,罷免された皇帝,高官に強制的に割り当てられた身分,あるいは主教職就任のための過渡的な修練者身分をも意味した。
歴史的経過
330年第二のローマとして出発したコンスタンティノープルは順調な発展を続け,文字どおり帝国の中心となった。ディオクレティアヌス,コンスタンティヌス1世両帝の行政機構改革は,全歴史を通じて国家生活の基礎となった。コンスタンティヌス1世の発行した金貨はノミスマnomismaの名で,中世の代表的国際通貨の地位を保った。テオドシウス1世のとき国家教会制が定まった。同帝死後の東西分治における東半部が,ビザンティン帝国の領土的基盤となった。
4~5世紀の民族移動の矛先は西に転じたが,ガイナス,アスパルなどの蛮族出身の軍隊指揮者が中央政府を牛耳り,前者とその一党が首都市民の反ゲルマン感情の爆発で400年に駆逐された後,後釜に座った後者をイサウリア人が一掃し(471),わが物顔にふるまうこの最後の軍人勢力をアナスタシオス1世(在位491-518)が平定するに及んで,文民政治体制が確立された。ニカエア(325),コンスタンティノープル(381)の両公会議ではアリウス派問題,エフェソス公会議(431)ではネストリウス派問題,カルケドン公会議(451)では単性論派問題が,いずれも〈政治的オーソドクシー〉原則(皇帝教皇主義)で処理され,同様の政治的結果を随伴した。ことに単性論問題では,非妥協的なカルケドン派のローマと,単性論を奉ずるエジプト,シリア,アルメニアなどの東方諸属州との板ばさみになってゼノン(在位474-475,476-491)は統一令(482)を発布したが対立を収拾できず,ローマとの教会関係断絶は519年まで続いた。
ユスティニアヌス1世(在位527-565)は,ゲルマン民族によって奪われた旧ローマ帝国西半部の再征服を行った(533-555)が,他方540年以降ササン朝ペルシアと交戦状態に入らねばならなかった。同帝は国内では,首都市民の反乱(競馬場での騒乱に端を発したニカの乱)や,単性論派の東方諸属州住民の反抗と直面した。同帝の死後,競馬場での騒乱はますます激化し,東方諸属州との宗教上の不一致は,これら属州がアラブ・イスラム教徒の手に落ちるまで続いた。同帝のもとで始まっていたスラブ人のバルカン南下は,その後継者たちの時代に激しさを増し,アバールはドナウ北岸に及ぶ大国家を建て,ペルシアとの戦闘も再開された。イタリアではランゴバルド族が侵入を開始し,これに対抗するためラベンナには大幅な軍民両政権を併せもつ総督府が設けられ,ベルベルの圧力が加わる北アフリカでも,いま一つの総督府がカルタゴに置かれなければならなかった。6世紀末~7世紀初め,事態は極度に悪化した。
登極してこの危機に直面したヘラクレイオス(在位610-641)はペルシア大遠征を試みて(622-628),占領された東部諸属州を奪回した。帝の不在中にペルシアと結んだアバールのコンスタンティノープル包囲(626)は失敗し,アバール大国家は壊滅した。しかしアラビア半島から興ったイスラム教徒のアラブ軍は同帝をヤルムークの戦(636)で破り,やがてイスラム教徒の地中海地域進出が始まった。マルマラ海のキュジコスを足場に,そこから毎年繰り返される彼らのコンスタンティノープル包囲攻撃(674-678)は,〈ギリシアの火〉でようやく撃退された。彼らの侵入が相次ぐアナトリアでは,現地防衛を組織化するために,テマ制が敷かれた。バルカンではブルガール族が,皇帝自らの指揮する遠征軍を破って(680)ドナウ川を渡り,数的に勝るスラブ人を支配下に収めた新国家を建てた。
7世紀末~8世紀初めの20年の政治的混乱に終止符を打ったレオ3世(在位717-741)は,コンスタンティノープルを包囲するアラブ・イスラム軍を撃退し(717-718),その後もアナトリアに繰返し侵入する彼らをアクロイノンで破って(740),対アラブ関係に転機を画し,息子コンスタンティノス5世(在位741-775)はシリア(746),アルメニア,メソポタミア(752)に遠征して,戦闘を国境戦に局地化する端緒を開き,ブルガリアに対しても遠征を行った。しかし両帝が開始した宗教政策イコノクラスム(第1期726-787,第2期813-843)は,対内的に混乱を招く一方,ローマ教皇庁との断絶を生み,報復措置としてビザンティン側はシチリア,カラブリア,イリュリアの教会管轄権をローマからコンスタンティノープルに所属替えした。またラベンナがランゴバルド族の手に落ちた(751)結果,コンスタンティノス5世は西方の実力者,フランク国王ピピン3世と結んでイタリアの事態を収拾しようとし,イコン崇拝を復活したイレネ(在位797-802)は,ローマ皇帝に戴冠されたピピンの息子カール大帝と新しい関係に立った(中世キリスト教世界の2皇帝問題)。
イコン崇拝の最終的復活(843)は,政治的,文化的にも,暗黒時代を乗り越えたビザンティン帝国の出発点を意味した。すでにコンスタンティノープルの文化的名声はバグダードのアッバース朝カリフ宮廷にとどろき,首都の帝国大学は〈再興〉された。スラブ人への使徒,キュリロスとメトディオスはキリスト教布教のためモラビアに旅立ち(863),キエフ・ロシアのコンスタンティノープル襲撃(860)は,ビザンティン政府に,彼らのキリスト教改宗を思いつかせた。コンスタンティノープル教会のこの威勢を背景におこったのが,総主教フォティオスの,ニコラウス1世およびその後継のローマ教皇たちとの対立である(860-879)。
バシレイオス1世(在位867-886)から,同2世に至るその後継者たちのもとで,ビザンティン帝国の軍事力は最も伸張した。地中海で猛威を振るうイスラム教徒に対しては,9世紀前半テオフィロス帝とカロリング朝のルートウィヒ1世の間の,対イスラム共同戦線締結の試みは実現をみなかったが,同世紀後半,イスラム教徒の占領する南イタリアの再征服が始まり,1世紀半も彼らの占領下にあったクレタも奪回され(961),またアドリア海のスラブ人海賊も掃討された。イスラム教徒との国境はティグリス,ユーフラテス両川まで押し戻され,シリア北部も再びビザンティン帝国の支配下にはいった。バルカンでは,30年近くの戦闘の後,第1次ブルガリア帝国が消滅した(1018)。こうした国際的緊張緩和のなかで,11世紀には〈文官派〉皇帝が相次いで即位した。しかし総主教ミハエル・ケルラリオスのローマ教皇庁との断絶(1054)は,南イタリアで台頭するノルマン人を押さえる切札の放棄を意味した。南イタリアにおける最後の拠点バリは彼らの手に落ち(1071),同じ年,ビザンティン軍は東境のマラーズギルドの戦で,アナトリアに侵入するセルジューク・トルコから壊滅的打撃を被った。3人の皇帝候補者がコンスタンティノープルの帝位をめぐって争う間に,トルコ勢はボスポラスまで進出した。
皇帝権の争奪に結着をつけて即位したアレクシオス1世(在位1081-1118)は,アドリア海を渡って侵入するノルマン人を,ベネチア艦隊の援助をうけて破るとともに,おりから始まった第1回十字軍のコンスタンティノープル通過を利用して,彼らと主従契約を結び,彼らの力でトルコ人からアナトリアの失地を回復するのにかなり成功した。同帝とその後継者たちのもとで,コンスタンティノープルは国際政治の一中心点であり,その輝きは訪れる者の眼を奪い,宮廷では西方の騎士的風習が流行した。しかし12世紀後半,コニヤの西ミュリオケファロンでのセルジューク・トルコ人に対する大敗北(1176),ノルマン人のテッサロニキ占領(1185)に加えて,ブルガリア国家は再建され,セルビア人も独立国家を建てた。ベネチア商人は,アレクシオス1世から上述の援助の代償として取りつけた,ビザンティン全土において免税で自由に取引を行う特権を手段に,特別の地位を築き上げ,これはビザンティン商人にとってたえ難いものとなった。1171年ビザンティン帝国に滞在する全ベネチア人が拘禁され,その全財産が差し押さえられた。ベネチア側の報復措置が,その艦隊による海岸地方襲撃と,キオス,レスボス両島焼打ちだった。そして最後に第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領し,ラテン帝国が出現した(1204)。落ち延びたビザンティン貴族はそれぞれ,トレビゾンド帝国,ニカエア帝国,エピロス帝国をつくった。
ニカエアのテオドロス1世(在位1204-22)とその後継者たちがしだいに支配を固めたのち,ミハエル8世(在位1259-82)が,ベネチアの対抗勢力ジェノバの援助をうけてコンスタンティノープルをラテン皇帝から奪回した(1261)。だが再建ビザンティン帝国に挑戦を試みるバルカンの両南スラブ人国家,コンスタンティノープルで権益を独占するベネチア人,ジェノバ人に加えて,国内的にはパラマス主義(ヘシュカスモス)をめぐる争いで当時の宗教・思想界は二分し,テッサロニキのゼーロータイ支配(1342-50)をはじめ,トラキア諸都市では社会的対立が激化した。その間オスマン・トルコは,ヨハネス5世パライオロゴス(在位1341-91)と争う同6世カンタクゼノスに招かれてアナトリアからトラキアへと渡り(1354),続いて宮廷をブルサからアドリアノープルに移して(1361ころ)バルカンで急速に領土をひろげる一方,コンスタンティノープルを圧迫した。これに対するニコポリスの十字軍(1396)も,バルナの十字軍(1444)も成功をみず,他方フェラーラ・フィレンツェ公会議(1438-39)でも西方からの救援を引き出せないままに,コンスタンティノープルは1453年オスマン・トルコ軍の手に落ちた。
→ギリシア →ビザンティン文学 →ローマ
執筆者:渡辺 金一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報