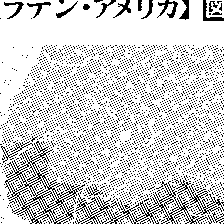精選版 日本国語大辞典 「ラテンアメリカ」の意味・読み・例文・類語
ラテン‐アメリカ
- ( [英語] Latin America ) 南アメリカ、中央アメリカ、メキシコおよび西インド諸島を含む地域の総称。ラテン語系の言語の、スペイン語・ポルトガル語・フランス語などが用いられ、ラテン文化を基調とする社会を構成している。アングロ‐アメリカに対していう語。〔万国新語大辞典(1935)〕
改訂新版 世界大百科事典 「ラテンアメリカ」の意味・わかりやすい解説
ラテン・アメリカ
Latin America
ラテン・アメリカは,アングロ・アメリカに対する概念であり,カナダ,アメリカ合衆国を除く北アメリカと南アメリカの諸地域,すなわちメキシコ以南の大陸部およびカリブ海地域の諸島の総称である。
総論
この地域においては,スペイン語,ポルトガル語,フランス語などラテン系言語が公用語として用いられ,文化伝統もラテン系であるため,ラテン・アメリカの名称が生まれた。ただし,カナダには多くのフランス語を話す住民がおり,アメリカ合衆国は2000万以上のスペイン語人口を擁する一方,ラテン・アメリカにも,英語,オランダ語を使用する地域があるから〈アングロ〉〈ラテン〉の区別は必ずしも厳密なものとはいえない。中南米という地理学的名称もあるが,メキシコは北アメリカに含まれる。また,メキシコ,グアテマラ,ペルー,ボリビアなどには,ナワトル(ナワ),オトミ,マヤ,ケチュア,アイマラなどの原住民言語を話す数百万の人々が住んでいる。
1997年の時点において,ラテン・アメリカには33の共和国と,カリブ海諸島中のいくつかの非自治地域,および南アメリカ大陸部にあるフランス植民地ギアナが含まれ,また,イギリス,アルゼンチン間で領有上の主張が対立しているフォークランド(マルビナス)諸島もその圏内に入る。ラテン・アメリカの総面積は約2053万km2で,日本の約54倍にあたり,世界の陸地面積の15%を占める。人口は約4億8200万(1995)だが,人口増加率が1.8%(1990-95)と高く,このままでいけば,2010年には5億8000万近くなるだろう。
旧イギリス領アメリカとの違い
ラテン・アメリカの名が示すように,基本的にはスペイン,ポルトガルによって代表されるラテン系ヨーロッパ文化がこの地域の文化的骨格をかたちづくっているが,コロンブス到着以前に長い歴史的展開を示した先住民文化や,16世紀以後奴隷として連れて来られたアフリカ人の文化も,それぞれの地域の文化に強烈な特色を与えている。同じくヨーロッパ人,先住民,アフリカ人によって人口構成の基礎がつくられたアメリカ合衆国の場合は,各民族集団間の隔離が特色であったのに対し,ラテン・アメリカでは,3者間に非常な血の混合が起こり,メスティソ(白人と先住民の混血),ムラート(白人と黒人の混血),サンボ(先住民と黒人の混血)などの集団が多数発生して,社会的に重要な意味をもっている点が注目される。先住民についていえば,アメリカ合衆国やカナダの狩猟民や小規模な農民社会と違い,アステカ,マヤ,インカなどの文明地帯には,安定した農村社会と密集した人口があり,また金銀などの鉱物資源が早くから発見されたため,スペイン人の征服後,彼らの労働力徴発による生産体系が急速に成立した。この点が,自営農民や商人が主体となって白人社会をつくり,先住民の存在を排除したアメリカ合衆国の場合とまったく事情が違っていた。スペイン王室は,副王(副王制)やその他の行政官を送ってアメリカの植民地を統制し,しばしば現地の征服者,植民者との間に軋轢(あつれき)を起こしたが,本国の絶対主義的体制は植民地における民主主義的体制の成立に強い牽制を加えた。これは,国王が総督を送って統治させながらも,本国における自由主義思想や議会制度の発展の強い影響のもとに植民地における自治組織や権利意識の発達がうながされたイギリス領アメリカの場合とまったく対蹠(たいしよ)的である。また,宗主国の重商主義的規制についても,スペイン植民地のほうがイギリス領植民地よりもはるかに強く,産業の発達が妨げられる結果となった。さらに,イギリス領アメリカには,有名なピルグリム・ファーザーズをはじめとして信仰の自由を求めて渡航した人々が多く,しかも彼らは自己自身の内部に宗教を守り,先住民に対する布教活動を重視しなかったのに対し,ラテン・アメリカでは,教皇から布教権を委託されたスペイン,ポルトガル国王が,その植民地経営の一環として修道会,教会の活動を重視し,植民者だけでなく,先住民の布教も強力に推進した。そして,文化,教育の多くの面において,神学的要素が長い間支配的な力を振るい,啓蒙的進歩思想の発達に抵抗した。
以上のように,封建制や絶対主義体制を知らず,近代市民社会に大きく傾斜しながら発足したアメリカ合衆国と比べて,ラテン・アメリカは,中世的,封建的な制度や文化の残滓(ざんし)を多分に残しながら出発し,しかもヨーロッパ近代社会の発展にとりのこされた宗主国の厳しい支配を300年以上にわたってうけた。そこで,19世紀初頭,ラテン・アメリカ各地に独立運動が起こり,諸共和国が成立したときにも,大きな社会的不正や不平等を伴った封建遺制が根づよく残り,大土地所有者やカウディーリョ(政治ボス)の寡頭政治が横行することになった。おりしも新市場を求めて進出してきた資本主義の先進諸国が,ラテン・アメリカの支配層と結びついて,産業や開発に手をつけたとき,この地域特有の政治・経済的従属形態が成立した。19世紀以来今日に至るまでのラテン・アメリカの歩みは,このような矛盾を解決するための苦闘とみることができよう。
執筆者:増田 義郎
歴史
スペインの統治機構
スペインの植民地経営の基礎は1492年から1550年に至るいわゆる発見・征服時代に築かれた。スペイン国王はコロンブス,コルテス,ピサロ,その他代表的なコンキスタドールたちに全面的な政治権力をゆだねたので,その結果,彼らは征服地においては君主のような存在となった。しかし,いったん征服地の重要性が明らかになると,王室はコンキスタドールの権力の削減に努め,中央集権化を図るためにスペインで採用した諸制度を同じ目的のもとに新たに発見・征服したインディアスへ移植した。16世紀半ばごろには,インディアスの政治組織は決定的な形を整え,それはわずかな変化を受けつつも18世紀後半のブルボン王朝による改革の時期まで存続した。
インディアス会議はもともとカスティリャ枢機会議内に常設された委員会であったが,1524年に枢機会議に昇格し,以後ほぼ植民地時代末期までインディアス統治の中枢機関として機能を果たした(インディアス枢機会議)。インディアスにおいて国王を代表した主要な官職,機関は副王,総監とアウディエンシアである。副王と総監は本質的にはほぼ同じ役割を有し,異なる点は副王にはより重要かつ広大な土地が管轄地として与えられたということにすぎない。総監は機構上は副王に従属していたが,実際上は副王から独立して副王領内の広大な土地を統治した。さらに長官領と呼ばれる下部の行政区画があり,これはアウディエンシアによって治められた。その際,アウディエンシアの長官は統治者として行動したが,一般に軍事的権威は副王に留保されていた。一方,地方行政は普通コレヒドールと呼ばれる王室官吏に任され,彼らはそれぞれの領域内で最高の司法および行政権を行使し,カビルドでは国王の利害を代表した。コレヒドールにはスペイン人の町を統轄するものと王室への貢納義務を負う先住民インディオの村や町を治めるものの2種類があり,後者はコレヒドール・デ・ロス・インディオスと呼ばれ,任期は3年で,白人による不正行為からインディオを保護することを主要な任務とした。しかし,彼らはインディオと直接接触できる権利を悪用して,スペイン人植民者や,ときにはインディオのカシケ(首長)とも共謀して,先住民を圧迫する存在となった。
スペイン王室は官吏の義務遂行を図るためさまざまな規則を作成した。レシデンシアと呼ばれる執務監察制度は官吏の任期末に行われる公聴会のようなもので,だれでも判事に対し当該官吏の不正行為を訴えたり,証言したりすることができた。それ以外にビシタ(巡察)と呼ばれる制度があり,これは国王もしくは副王に特別に任命された官吏(ビシタドール)が予告なしに行う役人の行動調査であった。一般にビシタは,レシデンシアと比較すると,官吏の不正行為を予防したり処罰したりするのに,さほど有効ではなかった。
各都市にはカビルドもしくはアユンタミエントと呼ばれる市参事会があり,それは自治権をもつ唯一の政治組織であった。初期は王室が市参事会を構成するレヒドールやアルカルデの任命権を握っていたが,フェリペ2世以後,スペイン経済の悪化にともない,それらの官職は入札によって売却されることになり,入札者は王室に税を支払うことによってその官職を再売却したり譲渡したりする権利が認められた。こうした官職売買は植民地時代を通じてあらゆる官職にわたって広く行われた。市政は概して閉鎖的で,裕福な土地所有者,鉱山所有者や大商人などによる寡頭政治が行われた。彼らはしばしば報酬を得ない代りに,その地位を利用して共有地を私有したり,インディオを使役したりして富を築いた。総督やコレヒドールの厳しい監視を受けた結果,カビルドはしだいにかつての自治権を喪失していった。しかし,その非民主的性格,効率の悪さや衰退する権威と自治権にもかかわらず,カビルドはかなり重要な組織であった。カビルドはクリオーリョ(クレオール)がその成員の大多数を占める唯一の政治組織として19世紀の独立戦争の時代に重要な役割を果たすことになったのである。
副王,アウディエンシアなどに代表された王権は副王領の中心地とその近隣地域では揺るぐことはなかったが,はるか遠方の孤立した地方では大土地所有者(アシエンダ)の権力が絶大であった。彼らは広大な所領を有し,まるで封建領主のごとく所領内で裁判権を行使し,裁判所や監獄までも設け,そのうえ私的な軍隊を養っていた。17世紀後半,スペインが政治的にも経済的にも衰落していくにつれて,スペインとインディアスの絆は弛緩し,権力の分散化はますます助長された。王室という中央政府への名ばかりの権力集中と地方レベルにおける大土地所有者の実際上の絶大な権力はきわだった対照をなし,その状況は植民地時代から独立以後のイスパノアメリカに受け継がれ,現在も多くの国々の政治活動を特徴づけている。
スペインの植民法(インディアス法)は遵守されないことが多かった。〈服すれど守らず〉という人口に膾炙(かいしや)した句は,法令の実施を任務とする王室官吏が,つねに経済的かつ社会的に密接につながりをもっていた植民地の強力な上層階級側から法令の停止を求められたときに抱いたジレンマを如実に示している。植民地時代当初からエンコミエンダをめぐる闘争にみられるように,キリスト教化のためのみならず,国庫収入の安定を図るためにもインディオ保護の立場をとらざるをえなかった王室は,インディオを利用して最大の利益の獲得をもくろむ植民者と対立し,それは植民地時代を通じて変わらなかった。そのうえ,地理的隔りや交通・通信手段の未発達が原因で,王室の発布するインディオ保護法はしばしば無視される結果になった。王室は往々にしてそのような違反行為に目をつむったが,それは強力な植民者との対立を回避しようとしたためばかりではなく,インディオ保護法がときどき王室自身が求める目先の利益--戦費の調達や寄生的な貴族の維持費の確保など--に反したからでもあった。
植民地社会の階層
植民地社会では,原理的には人種,職業および宗教が個人の社会的地位を決定する基準となった。肌が白いことは社会的優越性を示すシンボルであったが,すべての白人が特権的な経済集団に属していたわけではなく,放浪者や乞食などに身を落とした白人もかなり存在した。一方,裕福な白人の植民者を父にもち,嫡子として認知されたメスティソやムラートが植民地貴族になった例もある。したがって,高貴な出自とか人種的な純潔さよりも莫大な財産の所有が植民地貴族階級の顕著な特徴であった。とはいえ,植民地社会の最上層部が圧倒的に白人によって占められていたのは紛れもない事実である。特徴的なのは,その白人の支配階級内部に分裂,対立が生じたことである。クリオーリョと呼ばれる植民地生れのスペイン人とペニンスラールと呼ばれるヨーロッパ生れのスペイン人は法的には平等であったが,実際にはクリオーリョは植民地時代全般を通じてペニンスラールと区別されて,教会関係や行政上の高位の官職や大規模な交易からは除外されていた。しかし,クリオーリョは鉱山,プランテーション,牧畜などでしだいに富を蓄え,それにともないペニンスラールに対する憎しみも激しくなっていった。植民地上層階級内部におけるこうした対立はクリオーリョによる独立戦争を惹起させる最大の原因となった。
メスティソは大半が私生児で,インディオ社会にもスペイン人社会にも同化しえない根なし草のような存在で,普通インディオからもスペイン人からも軽蔑され社会的にはきわめて不安定な身分であった。それとは対照的にインディオは法律上その地位を明確に定められ,少なくとも法の保獲を受けていた。しかし,現実には貢納,賦役や教会税など大きな負担に苦しめられ,悲惨な生活を強いられた。インディオの村の中にはスペイン人の町と同じような市政(カビルド,レヒドール,アルカルデ)を備えたものもあった。白人が加える不正や侵略に対してインディオ共同体は土地のみならず,文化的アイデンティティ,言語,社会組織などを守るため激しい抵抗を示すこともあった。黒人,ムラート,サンボ(インディオと黒人の混血)は植民地社会の最下層におかれた。16世紀末,およそ90万の黒人奴隷が導入され,18世紀末には1500万ぐらいの奴隷がいたと推定される。奴隷ではない自由な身分の黒人やムラートも数多く,彼らは農業や手工芸に秀で,植民地経済の発展に寄与した。
植民地における社会生活の中心は植民都市(メキシコ市,リマなど)とアシエンダ,つまり広大な私有地である。都市はヨーロッパのように交易や産業の中心地として自然発生したのではなく,近隣地方の植民と管理のためや戦略上の必要から計画的に建設された。都市の周囲にはバリオと呼ばれるスラム街があり,多くのインディオやメスティソが居住していた。アシエンダは17世紀末には自給自足しうる大規模な経済・社会単位となり,しばしば近隣のインディオの村をも包みこんだ。こうしてかつてはその土地の所有者であったインディオが,実質的には農奴のような存在(ペオン)となってアシエンダで暮らすようになった。植民地社会の封建的側面を最も顕著に示したアシエンダは現在も暗い影を落としている。
18世紀以降ハプスブルク王朝に代わってスペインを治めたブルボン王朝は行政の効率化と国庫の増収を最大の目標として貿易の自由化などの商業上の改革や新しい副王領の設置やインテンデンシア制の導入をはじめとするさまざまな政治的改革に着手した。ブルボン王朝による自由主義的な改革は植民地の大土地所有者,商人や鉱山所有者を豊かにし,上層階級の青年たちの知的視野を拡大するのに役だちはしたが,一般大衆はなんら恩恵に浴さなかった。むしろ新税の賦課,特権的な会社の設立,政府による専売制などによって国庫の増収を図るブルボン王朝の努力は下層階級をさらにいっそう悲惨な状況へ追いつめた。その結果,1780-81年,ペルーやヌエバ・グラナダ(コロンビア)などで大規模な民衆蜂起が発生した。一方,改革は18世紀のヨーロッパ経済の高揚と結びついて数多くのクリオーリョの上層階級に物質的繁栄をもたらしたものの,新しい啓蒙思想に触れたクリオーリョたちは,植民地経営や教会関係の要職から除外されている状況にますます不満をつのらせていった。こうして植民地支配の強化を目的としたブルボン王朝による改革は皮肉なことにクリオーリョによる独立運動を早める結果になった。
執筆者:染田 秀藤
ポルトガル領ブラジル
1500年,P.A.カブラルによって〈発見〉され,ポルトガル領となったブラジルはしばらく放置されていたが,その重要性が認識されるにつれ,ポルトガルの統制がしだいに強化された。1530年,王室はソウザMartim Afonso de Sousa(1500-64)に探検と入植を命じ,植民地を15のカピタニア(カピタニア制)に分割した。サン・ビセンテとペルナンブコ以外のカピタニアの植民は失敗したので,49年サルバドルに総督府が置かれ,初代総督T.deソウザが派遣され,植民地支配に王室が直接乗り出すことになった。56年リオ・デ・ジャネイロを根拠地としていたフランス人が駆逐され,16世紀末にはブラジルはポルトガルにとって最も重要な植民地となっていた。スペインによるポルトガルの併合時代(1580-1640)にブラジルの一部は一時オランダ人に占領された。1627年,オランダ艦隊がバイアを,30年にはペルナンブコを攻撃し,レシフェを占領した。40年にポルトガルがスペインから離脱するころには,オランダは七つのカピタニアに166の砂糖工場をもっていたが,その後ポルトガル人の反乱が起こり,54年にレシフェのオランダ人は降伏した。
ブラジルには広大な土地が存在したが,スペイン領アメリカ植民地の高文化圏(メキシコ,ペルー)のように多数の定着農耕民が存在していなかったため,セズマリア制によって,資力をもつ入植者に大区画の土地が与えられ,内陸からバンデイラによって狩り集められたインディオや,アフリカから連れてこられた黒人からなる奴隷が労働力とされた。大規模生産によって,効率と収益率を引き上げようとしたため,砂糖や綿花などのヨーロッパ市場向けの特定商品のみが栽培された。ブラジルの農産物は,ポルトガルの輸出の3分の2を占めた。ある商品の国際競争力が低下すると,その栽培地は衰退し,別の輸出商品が見いだされると,人と資本がそこに移動するという現象が起こった。16世紀半ばから17世紀半ばまで,ブラジルはヨーロッパの全砂糖需要を満たしたが,その後カリブ海の砂糖に圧迫され,中心地であった北東部(ノルデステ)は衰退した。17世紀末ミナス・ジェライスで金が発見されると,空前のゴールドラッシュが起こり,植民地各地とポルトガルから移住者が殺到した。このため,内陸部に多くの集落がつくられ,17世紀末までほとんど無人の地であったミナス・ジェライスに,1世紀後には50万人が住むようになった。スペイン領アメリカで初期から鉱業が富の源泉となり,内陸に都市が建設されたのとは異なった過程がみられた。そしてスペインとの間で境界線を定めたトルデシーリャス条約の限界を越えてポルトガル人が西進した結果,今日の国土の姿がほぼ植民地時代に形づくられた。
1720年以降,ブラジル植民地の行政官は副王と呼ばれ,1763年植民地の首府がサルバドルからリオ・デ・ジャネイロに移った。1808年ブラガンサ王家はナポレオン軍の攻撃を避け,リオに遷都し,15年ブラジルはポルトガルと対等の王国となり,22年皇太子ペドロ1世により独立宣言がなされた。
→ブラジル
執筆者:山田 睦男
植民地経済の展開
スペイン,ポルトガル両国によって開始された新大陸における植民地経済の開発と新大陸貿易は,東インド航路の発見とも相まって新たな世界貿易体制を成立せしめた。この体制のもとで,トウモロコシ,カカオ,タバコ,ジャガイモなど,当時までヨーロッパでは知られていなかった農産物が新大陸から流入するが,とりわけヨーロッパ経済の発展にとり重要な役割を果たしたのは新大陸産の貴金属であった。金銀をはじめとする植民地商品の大々的な流入は西ヨーロッパ諸国に商業革命を引き起こすとともに,資本の蓄積と国民経済の成立を促し資本主義への移行の基礎的条件を提供した。この過程は,18世紀に最盛期を迎える奴隷貿易によって加速化される。一方,ヨーロッパからはサトウキビ,コムギ,綿花などの新たな農作物や,養蚕,牧畜,黒人奴隷のほか毛織物,金属製品などの製造工業品が新大陸にもたらされ,同時に進んだ農工技術も導入された。しかしながら,こうした新旧両大陸の経済交流は,基本的に新大陸からの一方的な富の流出を意味した。いわば新大陸における植民地経済の開発は,ヨーロッパ資本主義の形成に寄与する一方,ラテン・アメリカを将来にわたって後進地域として固定化するという歴史的性格を帯びていた。
新大陸における植民地経済の展開は,一般に(1)略奪期,(2)鉱山開発期,(3)停滞期の三つの時期に区分される。地域により時期的にある程度のずれがあるとはいえ,おおよそ第1期は征服直後から16世紀中ごろまでの時代で,先住民社会に蓄積されていた財宝の略奪と,先住民の奴隷化およびその労働力を基礎とする砂金開発を特徴としている。第2期はアンデス高地のポトシ銀山の発見(1545)とメキシコ北部のサカテカス銀山の発見(1546)を契機とする銀開発の隆盛期である。砂金開発とならんで銀開発も征服時代の初期から始まっていたが,二大鉱山の発見に加えアマルガム法の導入(1556)によって低品位鉱石の精製も可能となり,またポトシ近くのワンカベリカで銀の精製に不可欠な水銀の鉱脈が発見された結果,16世紀末には新大陸の銀生産は急激に増大し,世界全体の9割に達した。こうして銀は生産額,生産量の両面で金を上回り,スペインの国庫収入の大半を占めるに至った。鉱山開発の進展にともなって農業,牧畜も発展し,鉱山を核とする地域間の分業体制も整っていった。
一方,先住民保護運動の進展の結果,無償の強制労働は法的に禁止され新たにレパルティミエント制(アンデス地域ではミタ制)が確立されたが,実質上は奴隷労働と大差なく,先住民は引き続き過酷な労働を強いられた。征服による殺戮と居住地の強制的再編,たび重なる疫病のまんえんと過酷な労働の結果,先住民人口は征服後1世紀で10分の1以下に減少し,植民地経済は深刻な労働力不足に直面した。その解決策のひとつがアフリカ人奴隷の組織的な導入であったが,鉱山に奴隷が投入された例は比較的少なく,大半は農牧業とオブラヘと呼ばれる織物工場に向けられた。なおこの時期にはすでに植民者と先住民との間に生まれた混血(メスティソ)が徐々に増加しはじめ,一部は共同体を離脱した先住民とともに鉱山地帯に賃労働者層を形成した。
1600年を境として銀生産は下降しはじめ,大陸部の植民地経済は全般に停滞期に突入し,富の象徴も銀山から土地所有へと重点が移る。植民地における土地は基本的に王権に帰属するものとされ,功労に応じて恩領地として下臣に付与されたが,資力のない植民者はしだいに教会と特権階層に土地を吸収され,17世紀前半にはアシエンダ制を基盤とする植民地の階級構造が確立される。植民地経済が低迷を続ける間,オランダ,イギリス,フランスの新大陸への進出が活発化し,17世紀半ばにはカリブ海地域にこれら列強による奴隷貿易・密貿易の拠点が建設され,さらに砂糖を中心とするプランテーション経済が大量のアフリカ人奴隷を基礎に形成されていった。なおブラジルではカリブ海に先んじて,16世紀以来北東部で砂糖プランテーションが発展し,17世紀前半には最盛期を迎えるが,ヨーロッパ列強の進出に圧迫され,1698年に金,1729年にダイヤモンド鉱山が発見されるまで,経済は低迷を続けた。
18世紀後半に入りメキシコの銀生産は再興の兆しを見せ,ブラジルの金,ダイヤモンドも同世紀中ごろに最盛期を迎える。また同じころに始まる商業改革と1778年の貿易の自由化の結果,スペイン領のアシエンダの一部では商品生産も増加し始めた。しかし,1703年のメシュエン条約,1713年のユトレヒト条約を契機にカリブ海地域を地盤として確立された,イギリスをはじめとするヨーロッパ列強の絶対的優位のもとで,イベリア諸国の植民地経済はみずからの従属的地位を打破することは不可能であった。一方,この1世紀以上にも及ぶ停滞期に,植民地生れの白人の間に特権階層が徐々に台頭し,また混血を中心に中間層も形成され,本国人との間に経済利害の対立が顕在化していった。こうして植民地経済は,ヨーロッパ列強とそれに従属した植民母国に二重に従属するという国際環境のもとで,大土地所有制を基盤とし,先住民,黒人奴隷を最底辺とする社会構造を抱えたまま,独立期を迎えることとなる。
なお貿易については〈通商院〉の項目を参照されたい。
執筆者:清水 透
ラテン・アメリカの独立
18世紀の末から19世紀の初めにかけて,アメリカ大陸のスペイン領植民地の各地では,本国の統治に対する不満がしだいに強まっていたが,19世紀初めの四半世紀の間に,このスペイン領をはじめポルトガル領ブラジル,フランス領サン・ドマング(独立後のハイチ)の各植民地をいっせいに独立へと向かわせたのは,北アメリカでのアメリカ合衆国の独立,フランス大革命,それに続くナポレオン戦争という当時の激動した国際情勢であった。
ラテン・アメリカで最初に独立を達成したのはカリブ海の島サン・ドマングである。18世紀前半以来,砂糖やコーヒーを生産する黒人奴隷植民地として特異な発展を遂げていたサン・ドマングでは,フランス革命の影響で蜂起した黒人奴隷たちが白人プランター(大農場主)の支配層を打倒し,イギリスの侵略軍やナポレオンが差し向けた鎮圧軍を破って,1804年に黒人と混血による独立国家ハイチを樹立した。スペイン領アメリカでは,ナポレオンによる本国占領を機に,10年から本国からの分離,独立の動きが始まった。メキシコではM.イダルゴやJ.M.モレロスが率いた先住民や混血たちの反乱が起こり,ベネズエラやアルゼンチンではクリオーリョと呼ばれるスペイン系の植民地人が,自由な貿易を求めて反抗を開始した。その後スペイン領アメリカでの独立闘争は,本国での政治情勢の動きと関連しながら進んだが,南アメリカ大陸ではS.ボリーバルやJ.deサン・マルティンの傑出した軍事指導によって各地の解放が進められ,24年のアヤクーチョの戦でボリーバル軍が副王軍に大勝して南アメリカのスペイン領の独立はほぼ確定した。メキシコではイダルゴやモレロスの反乱が鎮圧されたあと,保守的なクリオーリョたちが1821年に独立へと踏み切り,その影響で中央アメリカ地域も本国から独立した。アメリカ大陸でスペイン領としてとどまったのは,キューバとプエルトリコのみであった。一方,ポルトガル領ブラジルではナポレオンによる本国占領でブラジルに避難していたポルトガル国王ジョアン6世が帰国したのち,ブラジルに残った息子のドン・ペドロが1822年に本国からの独立を宣言して,ここでは平和裏に独立を達成し,帝政国家ブラジルを樹立した。
多難な国家形成の道
独立後生まれたラテン・アメリカの国々は,当時のアメリカ合衆国の憲法やフランス革命の人権宣言,さらにスペインの1812年憲法を模範として憲法を制定し,新しい国家機構を定めた。ブラジルを除いた国々が共和政を採用し,国民主権や三権分立を定め,先住民や混血にも法律上平等な地位を与えた。しかし,各地で新しく生まれた国家は外見的には近代西欧民主主義的な国民国家であったが,その実態は権威主義的な寡頭支配国家であった。植民地時代の社会構造は独立後も基本的には変わらず,富裕な大土地所有者層を中心とする寡頭支配階級が国家や社会に君臨し,人口の大多数を占める先住民や混血たちは依然として社会の下層を占め,彼らは財産資格や文盲条項などにより政治参加から排除されていた。
独立後ラテン・アメリカの大部分の国は多難な国家形成の道を歩んだ。多くの国ではカウディーリョと呼ばれる軍人出身のボス政治家が国を統治し,カウディーリョたちによる権力闘争や,自由主義派と保守派との間の絶え間ない抗争で国内政治は混乱し続け,地方的な分裂,対立や国民意識の欠如が国家の統合を困難にした。このような混乱に乗じて欧米諸国による干渉や侵略がなされ,なかでもメキシコはアメリカ合衆国との戦争(米墨戦争,1846-48)で広大な領土を失ったり,フランスに占領されてナポレオン3世の傀儡(かいらい)であるマクシミリアン皇帝の統治下(1864-67)に置かれたりした(〈メキシコ干渉〉の項目参照)。
このような諸列強による干渉や侵略の脅威に対処するため,1823年にはアメリカ合衆国のモンロー大統領がモンロー宣言(モンロー主義)を発してヨーロッパ列強による干渉の動きを牽制しようとした。また26年にはボリーバルの提唱でラテン・アメリカ諸国の共同防衛同盟を結成するためのパナマ会議が開かれたが,この同盟は実現しなかった。独立直後の時期にラテン・アメリカの統一が最も重要であることを認識し,それを強く念願していたのはボリーバルであったが,その後のラテン・アメリカはボリーバルの念願とはますます逆の方向に進んだ。中央アメリカでは1830年代末に中央アメリカ連邦(中央アメリカ)が解体し,ボリーバルがつくったグラン・コロンビア共和国も同様の道をたどった。19世紀後半には,パラグアイ戦争(1865-70)や太平洋戦争(1879-83)のようにラテン・アメリカ諸国どうしが戦争を起こして統一からはますます遠ざかった。
〈近代化〉とその代償
1870年代から80年代を画期として,ラテン・アメリカ地域も新しい時代に入っていった。この時期,中央アメリカやカリブ海,チリを除いたアンデス地域の諸国では,依然として不安定な状態が続いていたが,南アメリカ大陸ではチリに続いてアルゼンチン,ウルグアイがこれまでになく安定した時代を迎え,89年に帝政から共和政へと移行したブラジルでも政治は基本的に安定し,メキシコではP.ディアスによる独裁のもとで政治の安定が続いた。このような政治の安定が大きな誘因となって,この時期にはこの地域に対する欧米諸国からの投資が活発に行われ,それによってこの地域の多くの国々では,輸出向けの食料や原料を生産する経済体制が確立した。アルゼンチンではパンパを舞台に農牧業が飛躍的な発展を遂げ,メキシコでも鉄道の建設や鉱山の開発が進められ,ブラジル,コロンビアや中央アメリカ諸国ではコーヒー経済が発達し,ペルーやチリでもグアノや硝石の開発によるブームが訪れた。経済の発展により労働力が必要となったアルゼンチン,ブラジル,チリ,ウルグアイの諸国にはヨーロッパから多数の移民が来た。
しかしこのようなモノカルチャー的な経済の発展は,外国からの投資に支えられたものであり,また生産物の輸出先を海外市場に大きく依存していたため,この地域の国々は欧米諸国に対して強く従属することになった。しかもこのような経済発展や物質的進歩の恩恵に浴したのは,主として寡頭支配階級や外国の資本家たちであり,大衆の生活は以前と変りないか,場合によっては悪化していった。先住民が多数存在していたメキシコや中央アメリカ,中央アンデスの諸国では,この経済発展と物質的進歩の時代は大土地所有化がますます進行した時代であり,村落共同体は破壊され,土地を奪われた彼らは大農園で働くペオン(隷農)や労働者に転落していった。鉄道や鉱山や軽工業での労働者たちも低賃金と長時間労働という過酷な労働条件のもとで働かされた。
変革への始動
20世紀に入るや,それまで疎外され,抑圧されていたこの地域の中間層や労働者農民大衆が,寡頭支配階級に挑戦して立ち上がり,より民衆的な基盤をもった政権の樹立と,そのもとで政治的・経済的・社会的改革を行うことを要求するようになった。メキシコでは,1910年に長年にわたるディアスの独裁や社会的不正に反対して中間層や労働者農民大衆が立ち上がって革命を起こした(メキシコ革命)。その成果となった1917年の憲法は,土地改革や労働者の権利の保障などについて定めていた。20世紀初頭から20年代にかけて,アルゼンチンやチリやウルグアイでは,メキシコのような革命という爆発的なかたちをとらずに,漸進的ながらも中間層による政治権力への参加や労働者階級の地位の向上を実現していった。30年代初めの世界恐慌はこの地域の諸国の経済に甚大な打撃を与え,その後,アルゼンチン,ブラジル,チリ,メキシコなどは輸入代替の工業化政策をとるようになり,また,メキシコやブラジル,アルゼンチンではそれぞれ,L.カルデナス,G.D.バルガス,J.D.ペロンのもとで30年代から40年代にかけて労働者階級の地位向上のため積極的な政策がとられるようになった。
一方,中央アメリカやカリブ海では20世紀初頭以来アメリカ合衆国がこの地域に積極的に進出し,この地域を自己の勢力圏とした。合衆国による軍事干渉に対してラテン・アメリカの側から強い反発や批判が起こったため,1930年代以降合衆国はこの地域に対して軍事干渉は行わなくなったが,代わってこの地域諸国には多くの独裁者が出現して合衆国による支配に協力した。1898年の米西戦争でキューバはスペインから独立したが,その後キューバは合衆国の〈保護国〉となり,植民地的な支配が強まった。それに対する反発はやがてカストロが指導する1959年のキューバ革命となって現れ,キューバはその後社会主義革命を宣言してラテン・アメリカで最初の社会主義国家となった。
混沌とした変革期
キューバ革命はこの地域の現状変革の動きにさまざまなかたちで影響を及ぼした。アメリカ合衆国はキューバ革命の拡大を阻止するために〈進歩のための同盟〉を打ち出して,この地域の諸国の社会構造の改革や経済発展や政治の民主化に積極的に乗り出した。また工業化を促進して経済の発展を図るために1960年代初めにはラテン・アメリカ自由貿易連合や中央アメリカ共同市場が創設された。60年代後半から70年代初めにかけて,この地域の広い範囲で軍事政権が出現したが,68年に登場したペルーの革命軍事政府のように,軍事政権が積極的に国内の構造改革を行うなど,一般的に保守の支柱とみなされてきた軍部からも変革のイニシアティブをとる動きが現れた。また60年代以降には同じく保守の支柱とみなされてきたカトリック教会の中からも〈解放の神学〉を唱えて現状の変革を求める聖職者たちが現れ,彼らは中米のニカラグアでの革命(1979)や,70年代後半から80年代にかけてのブラジルの反軍政民主化の過程で大きな役割を果たした。80年代に入ると,この地域では債務危機をきっかけとして大部分の国が厳しい経済不況に見舞われた。経済危機を解決できなかった軍部が相次いで政権の座を降り,この地域は民主化の時代を迎えるが,多くの文民政権は緊縮政策をとって不況脱出をはかり,さらに安定した経済成長を求めて,従来の保護主義的な工業化による経済の自立や,福祉主義の政策から一転して,貿易や外国投資の自由化,国営企業の民営化,各種規制の一掃などいわゆる新自由主義政策を採用して市場主義に基づいた自由競争による成長を目指すようになった。80年代末から90年代初めにかけての冷戦の終結とソ連・東欧での社会主義の崩壊は,この地域,とくに中米やカリブ海地域でのアメリカ合衆国の影響力を再び強めるとともに,キューバをはじめとするこの地域の社会主義勢力に大きな打撃を与える結果となった。80年代の経済不況でこの地域での貧富の格差はさらに広がり,広範な貧困層の存在が犯罪やテロリズムや麻薬取引きを生み出す温床となっている。この地域の政府にとって,民主的な政治体制のもとでいかに富の配分を伴った経済の成長を達成させることができるか,が大きな課題となっている。
執筆者:加茂 雄三
社会
文化領域からみた生活のタイプ
今日のラテン・アメリカ社会の現実は国により大きな差があるが,文化面からみれば,国民国家の枠を超えて共通ないくつかの生活のタイプがある。サービスE.Service,ワグリーC.Wagley,ハリスM.Harrisらの人類学者がラテン・アメリカの文化領域の分類を試みてきたが,それらを総合したオリアンM.Olienを参考にすると,次のような分類ができる。第1は先住民社会(インディオ)であり,メキシコ南部とグアテマラ,エクアドル高地,ペルー高地とボリビアに人口が集中しており,たいていは閉鎖的で協同的な農村共同体を形成しており,国民国家に容易には同化しなかった。しかし,1970年代後半から1990年代には,これらの人々の間でも都市に出稼ぎし,移住するものも増えた。また先住民の民族運動も盛んになってきた。ブラジルの部族レベルの先住民にも変化の波は押し寄せている。第2はメスティソ社会であり,基本的には先住民とイベリア系白人との混血文化を形成しており,現在ラテン・アメリカ社会の基調となる文化である。第3はアフロ・アメリカ社会で,プランテーション経済に立脚し,北東ブラジル,フランス領ギアナ,スリナム,ガイアナ,中央アメリカのカリブ海側やカリブ海にみられる。この地域には植民地時代にアフリカから奴隷が大量に運びこまれ,プランテーションの労働力となり,サトウキビ,綿,タバコ,カカオなどの換金作物が栽培されるようになった。現在のこの社会の特徴としては,(1)単一作物の栽培,(2)大きな階級差,(3)多人種社会,(4)弱小の共同体,(5)母親中心の家族,(6)アフロ的宗教,音楽,フォークロアがあげられる。カリブ海のアフロ・アメリカ社会の特徴は〈クレオール〉として,その文化的柔軟性が高く評価されるが,反面アイデンティティ形成の難しさも指摘されている。第4はヨーロッパ的アメリカ社会で,アルゼンチン,チリ,ウルグアイ,ブラジル南部にみられる。近代白人移民の形成した社会で,19世紀,とくに中葉にヨーロッパ各国から移民が大量に来た。中で目だつ現象をあげると,アルゼンチンにはイタリア移民とユダヤ移民が多く来た。ブラジルではドイツ移民は同化せず,民族文化を固持した。ウルグアイの人口の10分の9は移民で,とくにイタリアとスペインとからが多かった。第5は特殊な白人移民,政治的・宗教的理由による移民と東洋系民族の移民社会である。ポルトガル人はガイアナに奴隷として来た。トルコ人はラテン・アメリカ全土に散在し,小売業に従事している。ドイツ人はグアテマラのアルタ・ベラパス地域に入り,コーヒー産業をおこした。合衆国の南北戦争で敗れた南軍に参加した人々はブラジル,バハマ諸島,ベリーズに新天地を求めた。インド人やクエーカー教徒はコスタリカに移民した。東インドの人々はトリニダード,ガイアナ,ベリーズ,スリナムに来た。ジャワ人はスリナムに入った。中国人は労働者としてキューバ,ペルー,ジャマイカ,トリニダード,ガイアナに連れて来られ,徐々に商業に活路を求めた。日本人は農業移民としてペルー,ブラジル,コロンビア,パラグアイに住みついた。近年,これら日系人の日本への出稼ぎと逆移住が目立っている。また近年,韓国人の急増がブラジルなどで指摘されている。メンノー派教徒はパラグアイ,メキシコ,ベリーズに集団居住地をつくった。これら移民の社会では今でもそれぞれの民族文化が保持され,土地の文化と共存している。
以上五つのタイプの社会に共通な特徴を指摘することはむずかしいが,国民文化を代表するメスティソ社会を中核として考えると,ラテン・アメリカ社会の特徴として次の点があげられる。家族以上の親族関係としては構造性の弱い双系親族のネットワークがあるのみで,コンパドラスゴ,友人関係,隣近所の人間関係のネットワークがこれに加わる。このネットワーク型の社会では〈2者間の契約〉つまりフォスターG.M.Fosterのいうダイアディック・コントラクトdyadic contractに基づいて人間・社会関係が結ばれるしか方法がない。コンパドレはカトリックの秘跡を契機として選ばれ,本人と代親よりも代親と実の親,つまりコンパドレどうしの関係が強調されるのがラテン・アメリカの特徴で,異なった民族や階層にいる人間を結びつける役割を果たす。また友人関係はどの国でも重要である。ブラジルではパネリーニャpanelinha(小さなシチュー鍋)と呼ばれる友人のグループがあり,生活のあらゆる面で援助し合う。若者の友人関係としてはメキシコのアミーゴ(友人)やクアテcuate(双子),コロンビアやアルゼンチンのパンティーリャpantillaがあり,青年のおとなへの移行を容易にし,相互援助が可能になる。40歳を過ぎ中年になると男子は友だちづきあいから遠のき,家族中心の生活に入っていく。2者間のつながりが重要であるため,人間と人間の信頼が強調され,制度を無視しても援助し合える個人と個人の信頼関係が尊重される。この傾向が政治面でも働いてくると,カウディーリョ(政治ボス)が出現し,制度と官僚制を無視した独裁制が生まれがちである。
信頼に耐える人間は内的個性,つまり魂(アルマalma)をもっており,他人の侮辱をうけないように魂を男らしく守らねばならず,ここから男らしさの強調,つまりマチスモが生まれる。魂を守って孤独に生きる人間はフィエスタfiestaに安らぎを求める。広義のフィエスタとはパーティなどの個人的集りから共同体レベルの祭りに至る広範な儀礼のときを意味し,このときには,人と人,人と神や聖人との会話が成立し,心理的には人は孤独から逃れ,社会的には日常生活の活性化が実現する。
社会階層の変動
社会階層の変動や農村部人口の都市への流入は,新自由主義経済政策を採用している現代ラテン・アメリカの国々に顕著な現実である。既述の五つの伝統的生活のタイプと社会階層との関係の動態は国により異なり,概括しがたいが,例えば先住民とメスティソが人口の基本であるメキシコの場合,次のような特徴を指摘できる。まず第1に先住民やメスティソの農民はともに農業人口として都市の貧困層とともに経済的には下層階級を構成している。しかし,先住民社会やメスティソの農村内部にも細かいレベルでの階層差はあり,先住民社会の場合,小売・仲買業者,教師,政府機関関係者がエリート層となっている。しかし,全体として先住民社会はメスティソの町や小都市の経済的支配下にあり,ゴンサレス・カサノバP.González Casanovaらの社会学者のいう〈内なる植民地主義〉の状況がある。この状況では,個人としての先住民は社会的に上昇できても,先住民社会全体の下層階級からの脱出は困難である。特に,1980年代からの新自由主義経済下の先住民社会の没落は顕著であり,94年1月1日にチアパスで起こったサパティスタ民族解放軍の武装蜂起は,先住民や農民の救済を訴えている。第2の特徴として,大多数の下層の対極に少数の上流階級が存在する。ほとんどが首都に居住し,工業・商業経営者ないしは所有者,高級官僚,富裕な専門家(法律家,医師),大規模な地主で構成されている。軍人や教会人など,前時代の特権階級は国によってはすでに没落した。第3の特徴として,下層と上流の中間を占める中産階級の進出が近年とくに顕著にみられる。ウェトゥンN.Whettenによると,(1)前時代の土地所有者の子孫,(2)革命以降の新しい土地所有者,(3)教育エリートや専門家集団,(4)政府の役人,(5)工業経営者,所有者,(6)商業経営者,所有者,が中産階級を構成しており,地方都市や首都で社会的に進出している。第4にメキシコに限らずラテン・アメリカ全体の特徴として先住民やメスティソ農民の都市への大量流入がある。そのため都市の下層階級は年々増加し,スラムの出現(メキシコ市のベシンダードvecindadやバリオbarrio,リマのバリアーダbarriada,リオ・デ・ジャネイロのファベーラ,チリのカリャンパcallampa,ベネズエラのランチョranchoなど),失業,低賃金と問題が山積している。この人々の生活はアメリカの人類学者ルイスOscar Lewisのいう〈貧困の文化〉を一部は具現しており,その特徴は(1)制度への有効的参加の欠如,(2)核家族と拡大家族レベル以上の組織の少なさ,(3)家族の特徴として,子ども時代の欠如,家族成員の離別の多さ,母親中心の傾向,兄弟・姉妹間の争いの多さ,(4)運命主義,があげられる。しかし,積極的局面も多くあり,例えば,メキシコやペルーのスラム調査によると,居住区の計画,相互扶助,健全な上昇志向,教育熱心などがみられ,田舎から持ちこんだ儀礼,祝祭,音楽が生かされており,結構人間的生活が営まれている。
ラテン・アメリカ圏外への人口移動も顕著である。合衆国南西部諸州の大部分は19世紀中葉までメキシコ領であったため,メキシコ系の人口が多かったが,加えて,第1次,第2次大戦後に低賃金労働者として入国しそのまま残留した人口がある。さらに,現在でもかなりの数の不法入国や身分不安定のメキシコ人労働者が合衆国にいる。メキシコ系アメリカ人は16世紀以来の伝統を誇るニューメキシコ州のスペイン系アメリカ人と文化的に区別されうるが,政治的にはチカノとしてまとまる可能性があり(メキシコ系の人口は約1350万人,1990年),強力な民族票田を構成している。合衆国のプエルト・リコ人は273万人(1990年)とされ,ニューヨークに集中している。一部はハワイに渡り,砂糖園の労働者となっている。キューバ移民(104万人,1990年)はマイアミに集住している。カリブ海のアフロ系の人々で合衆国,カナダ,イギリスに移住する者も多いが,トリニダード・トバゴやジャマイカの人々はカーニバルを移住先で催している。
上に述べたように,各種の伝統的な生活のタイプが背景にありながら,社会階層面では先住民と農民の窮状は進み,中産階級が進出し,大都市での下層階級をめぐる諸問題が現れ,国内の人口の都市集中に加えて国際的にもラテン・アメリカ人口の北の先進国への絶えざる移動があるのが現状となっている。
→インディオ →メスティソ
執筆者:黒田 悦子
宗教
カトリック教会の歴史と役割
コロン(コロンブス)によるインディアス(新世界)の発見は,イスラム王国グラナダの崩壊というイベリア中世史の終幕と時を同じくした。だが,この場合,歴史の一時代は終わっても,戦いに勝ったキリスト教スペイン人の十字軍的メンタリティと価値観は消滅に向かうどころかかえって以前にも増して強固な伝統として彼らの心理に深く根を下ろした。カトリック両王に始まる近代スペインの発展の中で教会が時とともにその存在を大きくしていけば,インディアス史の第1段階が征服と宣教という中世的形態をとり,教会がきわめて重要な役割を担うのは必至だった。
イベリア出身の家系に生まれたローマ教皇アレクサンデル6世がカトリック両王に新しく発見された土地の領有権を認めたとき,同時に両王にはその住民のキリスト教化が付帯義務として課せられた。以後3世紀間,インディアス宣教はスペイン王権の責任に帰せられる高度に政治的な行為と受け止められた。それゆえにカトリック両王以降のスペイン王はローマ教皇庁から順次譲歩を引き出して王権教会保護体制(パトロナート・レアルpatronato real)の確立を目ざしたのであり,事実,これによってインディアスの教会はすべて完全に王権に従属し,ローマに対してさえその関係は間接的なものだった。一口に言って,教会はインディアス統治のための国家機関の一部と化した。だが,その見返りとして教会がインディアス統治のさまざまな点の是非をめぐって,国王とその代理者に対してしばしば仮借のない批判を加えることが容認された事実は注目されなければならない。
インディアスでの教会の役割とあり方はけっして終始一定でもなければまた一律でもなかった。教義に関しては一枚岩である教会--ここでいう教会とはむろんカトリック教会を指す--も時空間に従ってさまざまな変容をみせるし,その内部はつねに激しい葛藤の連続である。
教会のインディアスでの最初の仕事はおびただしい数の先住民の改宗だった。しかし,宣教はすぐに多くの障害にその行く手を阻まれた。次々と遭遇する新しい土着言語の習得,宣教とは正反対の利益を追求する先住民委託制度(エンコミエンダ)などの世俗的行為との対立,土着宗教の根強い抵抗,新しい植民地社会の生成などである。それでも中世以来の終末論,おりからスペイン教会に広く受け入れられていたエラスムスの人文主義,さらにはトマス・モアのユートピア思想などに鼓舞された宣教師は教会史上最も大規模な仕事のひとつに憶せず取り組んだ。彼らはこの過程で相当数の土着言語の辞書を作り,また消滅に追いこまれた土着文化に関する今日なお貴重な記述を残した。発明後まもない印刷機もいち早く導入される一方,先住民の子弟を対象としたヨーロッパ流の学校教育も試みられた。とりわけ先住民委託制度の下でのスペイン人入植者による苛烈な搾取は多くの宣教師から激しい口調で指弾され,ついには人間の尊厳と権利をめぐる近代史最初の感動的な論争へと発展した。
16世紀後半に入ると,先住民人口の激減や入植者を中心とした植民地社会の発展にともなって,教会も変化していった。初期の熱っぽい宣教への意欲はその対象を失って後退し,代わって都市部を中心に司教または大司教を長とした教会の組織化が進んだ。この推移の中で初期宣教の主役を担ったフランシスコ会やドミニコ会などの修道士に代わって,司教以下の教区付聖職者がインディアス教会の主導権を握った。この間,両者は司牧権の移行をめぐって激しく対立したが,独立性の強い修道会を敬遠する王権が人事権をはじめ統轄のより容易な教区付聖職者に荷担したために,抗争の勝敗はおのずから明らかであった。こうして都市部での司牧職から追われた修道会は,辺境や奥地であらためて宣教に取り組んだ。今日のチリ南部やアメリカ合衆国南西部への開拓や,パラグアイにおけるイエズス会士による大規模で特異な先住民集落化(レドゥクシオンreducción)などがこのときの修道会による代表的な活動例である。なお,この段階では修道士たちは辺境防衛に当たる軍隊と行動をともにした点で,武力の介入に強硬に反対した16世紀前半の修道士とは対照的な違いを示す。
宣教の初期,修道会は清貧を旨として世俗的富の所有を厳しく排した。だが,この姿勢も16世紀後半には揺らぎ始め,17世紀に入ると寄進や買収によって修道会を含む教会全体の大地主化が急速に進んだ。この結果,18世紀初頭の時点で教会はインディアス最大の地主であり,当然莫大な資本力を備える組織と化していた。こうした経済的・財政的基礎に立って,やがて各地の主要都市には今に残るバロック様式の司教座聖堂や修道院が建てられていった。これらの規模と圧倒的な装飾性はしばしば植民地に関する通念とは相入れないほどである。教会の富はこのほかにも病院や孤児院あるいは学校の経営といった社会事業,そして住民全体を対象とした宗教行事や祭りなどにも費やされた。大地主ではあっても教会の収入はけっして聖職者だけで独占される性格のものではなかった。
独立戦争期,教会は厳しい試練に立たされた。高位聖職者の多くがスペイン王の統治を支持する一方,メキシコの例にみるように独立派に身を投じる聖職者もこれまた珍しくはなかった。だが,いったん独立が達成されるや,教会は新国家の体制を支える重要な柱のひとつとなった。カトリック信仰はかつてのスペイン領インディアス人口の圧倒的多数派の宗教としてすでに政治権力の交替を超越した伝統になっていたからである。しかし,その一方では教会が所有する莫大な富は,教会と独立後のほぼ慢性的な財政危機に悩む政府との関係をしばしば緊張させ,メキシコにおいては激しい内乱までも引き起こした。その結果,社会の上層部の一部には教会に対する根強い反感ないしは宗教的無関心が認められる。それでも教会は今日なお誕生から死に至るまで大多数のイスパノアメリカ国民の一生に介入する。
執筆者:小林 一宏
インディオの宗教実践とその背景
メキシコで今日最も人気を集めるグアダルーペの聖母は,アステカの母神トナンツィンとの関連を想起させる。1人の農夫がテペジャクの丘のふもとを通っているときに丘上にマリアが出現したという。H.コルテスのアステカ王国征服後わずか10年後の1531年のできごとである。その丘にはかつてトナンツィンの神殿があったが,それを異教の巣窟としてコルテスが破壊したのである。出現の場所と時期から考えて,母神とマリアの同一視の公算はきわめて大きい。またアステカの軍神ウィチロポチトリは聖ヤコブ(サンチアゴ)の故事にちなんで同一視された。グアテマラのマヤ・インディオの居住するチチカステナンゴの町のサント・トマス教会では,公然とマヤ古来の宗教行事が教会の内外で行われている。こうした習合現象syncretismは,インカ帝国の版図であったペルー,ボリビア,エクアドルなどの高地住民の間にも顕著にみられ,人口集中地域でのキリスト教化が集団改宗の形をとらざるをえなかったことに,その原因の一端がうかがえる。強制と集団洗礼からは内実のある改宗を望むことは無理である。そこではアンデスの土着の習俗が温存されるだけにとどまらず,マリアをはじめとして多くの聖人,さらに悪魔(サタン)が彼らのパンテオンに加わり,以前にまして豊かな彩りを添えた。
インカの民の子孫ケチュア・インディオの大多数は農民で,地母神のパチャママへの信心を中心とする多神教polytheismである。アンデス地方にインカ帝国が君臨すると,太陽崇拝をインカの国教と定めたが,それは支配層と一部のエリートの宗教であったし,インカの後に到来したキリスト教も権力側からの押しつけの宗教であった。征服後,地母神はマリアと習合し,十字架の力に対する信仰は呪術と結びつき,十字架は呪具として受容された。現在,キリストやマリアの名によって呪術や治療が施されている。畏敬の念を寄せるのは三位一体の神にではなく,多くの神々に対してであり,祝祭日には教会で十字架とマリア像を称揚するが,病気の際には呪師の家を訪れる。呪師も洗礼を受けたカトリック教徒であり,ミサに参列する。アンデスの村のインディオの宗教実態はメキシコの村でも大同小異である。なお,征服によるキリスト教が中世の南部スペインの民俗化したカトリックの信仰体系であったことに留意する必要がある。
メスティソの宗教の都市的性格
4世紀という時の流れにあっても,依然として伝統的生活様式を脱し切れずに村の枠内にあるインディオの農民とは別に,外来の生活様式,なかでも生活技術を積極的に選択し受容していく〈開けた〉インディオに対しても,われわれはメスティソという名を付すのであるが,メスティソは農外職を求めることで伝統のしがらみの村を後にして,町,都市へと進出していった。インディオや黒人の都市への流入はブラジル,メキシコのみでなく,今日,全ラテン・アメリカにみられる。
都市化とメスティソ化は,ラテン・アメリカでは不可分の関係にある。しかし,この都市化現象の底流はすでに19世紀前半から始まっていて,地方出身の先輩格のメスティソらによって都市機能が担われてきた。したがってラテン・アメリカ諸都市の教会行事や祝祭礼には,メスティソの宗教習慣を端的に示すものが多い。その好例がグアダルーペの聖母である。マリア出現の奇跡をインディオ農民の信心の枠内にとどめることなく,聖母を〈メスティサ(混血の女性)〉ととらえたメスティソたちは広く都市的なマリア崇敬へと変容させた。1810年のメキシコの独立戦争では,聖母像を模した刺繡が反スペインのシンボルマークとして採用され,20世紀に入ってからは,国民統合のシンボルとなる。メスティソ化がラテン・アメリカで随一といわれるメキシコならではの経緯である。この聖母崇敬の浸透は外来宗教の刺激によって伝統宗教の各分野に活性化の気運を生み,新たな意味を付与することで信仰の組替え作業が漸次行われてきたことを物語る。インディオの宗教とメスティソのそれを分かつものは,後者では,市民的センスを獲得する過程で徐々にではあったが,主体的選択により自分なりのマリアへと変容させたのに対して,前者はキリスト教を受容したものの,伝統宗教を依然として保持し,その基盤の上にあっての受動的な変容にとどまったことである。
黒人の宗教
征服直後からとられた植民事業には,大量のインディオの労働力を必要とした。過酷な労働条件とヨーロッパから侵入した疫病によってインディオの大量死をきたし,それを補うべくアフリカから多くの黒人奴隷が投入された。現在,カリブ海諸島,ブラジル北東海岸,パナマ,ニカラグアに居住する黒人や混血のムラートは,アフリカ西海岸出身の奴隷の子孫である。
新大陸における黒人の宗教の性格は奴隷という境遇と固く結びつく。出身地のさまざまな部族宗教は幾多の屈折した経緯をたどりながらキリスト教と混合し,復古的信仰運動revivalism,千年王国論millenarianism,孤立主義isolationism,土着主義運動nativistic movementなどの形をとった。儀礼は秘儀的性格と反白人主義を強め,アフリカ要素の憑依(ひようい)現象の脱魂状態での恍惚感と呪術,さらにキリスト教の終末観や聖霊憑依感のなかでの慰めなどに共通に見いだされる。ハイチで盛んなブードゥー教もこの流れをくむ祭祀集団であり,キューバにはニャニーゴÑanigoという,荒々しい歌舞によってアフリカの神々が憑依する秘儀団があり,ブードゥーの神々と習合して複雑化している。ブラジルの黒人宗教も同じ傾向をもつが,なかでもサン・パウロ市に本部をもつウンバンダは1960年以降,都市中産階級に浸透し白人信徒を擁して反白人的色彩を稀薄化させている。19世紀にはフランスからカルデシスモkardecismoの心霊術の影響が現れ,ブラジル黒人宗教にオカルト的色彩が強まる。マクンバmacumbaはこの流れをくむ集団で都市下層の黒人の入信者が多い。
プロテスタント
プロテスタントの本格的布教は,ここ100年以来で,とくに第2次大戦後急速に勢力を伸ばしたのは新興セクトであり,なかでもペンテコステ派は聖霊降臨によって異言glossarariaを語るのを神の恵みと理解することから人気を集め,1950年代にブラジルで150万の信徒を獲得したという。メキシコでは,世の光教Luz del Mundoが都市へ移住してきた下級労働者に受容されている。都市化,工業化による都市の底辺にある地方出身者の〈孤独〉を,カトリックの教区制ではとうていすくい上げられないところに,憑依体験による連帯感を信仰体系へと組み込んだプロテスタント新興分派の成功の鍵が隠されている。
執筆者:佐藤 信行
法律
近代的諸法典に範を求める
19世紀初頭に相次いで独立を達成したラテン・アメリカ諸国でも,独立後の政治的混乱によって,近代的な法体制の確立は多くの場合約半世紀遅れ,その間は,基本的には植民地時代の法が行われていた(インディアス法)。
近代的な法制度の整備には,おもに法典化という方法がとられ,伝統的なイベリア法の要素を多分に温存しながらも,形式,内容ともに,欧米先進諸国の近代的な諸法典に範を求めた。こうした比較法的研究成果のあくなき摂取は,今日まで続くラテン・アメリカ法形成の基本的な特徴をなしている。その結果,ラテン・アメリカ諸国の法は,独自の社会主義の道を歩むキューバを除けば,キリスト教倫理,民主主義的政治形態,資本主義的経済・社会体制を反映する点で西欧法に属し,法典化の技術や法思考,法学教育などの面で,いわゆる大陸法系(ローマ法を基礎とする西ヨーロッパの法体系)の伝統に立つ。だが,後述するように,アメリカ合衆国を通じてコモン・ローの制度と法思考の浸透もみられ,この点で日本の法体系と類似する。
公法,とくに憲法に関しては,1788年のアメリカ合衆国憲法(およびその後の修正個条)の影響は絶大である。それは,この憲法が,ラテン・アメリカ諸国の独立の精神的支柱であったフランス政治思想や合衆国独立の法的・政治的マニフェストとみなされ,諸国の建国に際して模範とされたからである。こうしてラテン・アメリカ諸国の憲法は,おおむね制定当初から,国民主権,権力分立,大統領制,基本的人権の保障,そして裁判所による違憲立法審査権などの制度や原理を採用することとなった。だが,いずれの憲法においても,大統領への過度の権力集中(政令・規則の制定権,議会の立法権の委任,非常事態における憲法規定の効力停止権限など)がみられ,このことが,多くの諸国が経験してきた独裁制の原因とはいえないが,少なくともその手段を提供してきた事実は否めない。
政治的不安定とそれにともなう人権侵害という苦い体験から,人権保障のための優れた制度の発達もみられる。メキシコの保護請求amparoとブラジルの保障令状mandato de segurançaなどの制度がこれである。前者は英米の人身保護令状habeas corpusの制度をさらに発展させたもので,官憲または行政行為によるいっさいの基本的人権の侵害に拡大され,適用される救済制度であり,独創的かつ有効な法制度としてメキシコ人が誇るところのものである。この制度は,他のラテン・アメリカ諸国にも急速に広まってきた。後者は,メキシコの保護請求の制度と合衆国の令状writsの手続を結合させたもので,1934年憲法に設けられて以来,ブラジルにおいて広く用いられてきた人権保障手続である。
アメリカ法の影響は,ほかにも裁判所の組織,取引法の若干の分野(為替法,投資法など),そして信託trustの制度においてもみられるが,コモン・ローの思考様式そのものも徐々に浸透しつつある。
他の法分野,例えば民・商法,刑法,訴訟法などでは,西ヨーロッパ諸国の影響は圧倒的であるが,その影響のしかたは複雑である。法体制準備期においては,ほかに模範とすべきものがほとんどなかったこともあって,フランス法への傾倒がみられ,とくにナポレオン法典(民法典)は,直接,間接にラテン・アメリカ諸国の私法に多大な影響を与えた。その後,西ヨーロッパ諸国における法典編纂が進むにつれて,イタリア,スペイン,ドイツ,スイスの法も比較法的な取捨選択によって受容され,あるいは接木され,そうしてできた良法典がまた,他のラテン・アメリカ諸国における立法の模範とされた例も多い。
国際法は,ラテン・アメリカの独自性が発揮されてきた分野である。国際公法においてカルボ・ドクトリン(カルボ条項),ドラゴ・ドクトリンが唱えられ,また国際私法においては,諸国に先がけて法の統一が実現されてきた(モンテビデオ条約の批准,ブスタマンテ法典の採択など)。
法と社会の乖離
ところで,ラテン・アメリカの法と法学には克服さるべき問題が多い。まず,社会の階層間の落差が比較的に小さな若干の国々(アルゼンチン,ウルグアイ,コスタリカなど)を除けば,公式の法は,社会成員のごく限られた範囲にしか浸透していない。帰属社会の家父にあたるボスやパトロンによる紛争解決は,広くみられる現象であるが,法の保護と強制とはほとんど無縁の先住民インディオや貧農(非識字)人口も,国によっては最大の社会階層をなしている。また,観念的な法哲学の発達と,実証的・法社会学的研究の欠如に象徴されるように,立法および法学が社会の現実から遊離して,西欧の先進理論を無批判に受け入れる傾向がある。このことは,法と社会の乖離をもたらし,根本的な社会改革に代えて安易に立法に頼るあしき法律主義,形式主義と相まって,国民の法に対する信頼を損なっている。
執筆者:佐藤 明夫
政治
今日ラテン・アメリカにみられる政治現象の多くは,ペルソナリスモpersonalismo(直接的人間関係の原理)の部分的後退とポプリスモpopulismo(人民主義)の破綻という二つの要因によって理解することができる。
ペルソナリスモの後退
ラテン・アメリカのほとんどの国々は19世紀前半に独立を達成したが,植民地行政機構が消滅した後,住民によって正統と認められる政治組織を樹立することに失敗したために,政治参加を求めるクリオーリョ(植民地生れの白人)たちは,その手段として,非人格的な政治組織ではなく,拡大血縁関係,コンパドラスゴ,パトロン=クライアント関係など人間どうしの直接的関係に基づく集団に依存することになった。こうしたペルソナリスモは,例えばカウディーリョと呼ばれる独裁的政治指導者による支配の中に体現された。また政党に関しても,共通の綱領やイデオロギーを軸として結集する政治集団というよりも,有力政治家が率いる個人的集団ないしはそういった集団の集合体にすぎないことが多かったのである。
ペルソナリスモは,政治指導者と支持者との相互援助関係によって維持される。すなわち支持者は,選挙や武装反乱の際,あるいは政策の形成や実施の過程で,指導者に忠実に従う代りに,指導者から官職や補助金,利権の形で報酬を受けることを期待するのである。こうした関係は永続的な政治制度に対する忠誠とは異なり,短期的,個人的な利害勘定に基づくことが多いため,しばしばラテン・アメリカにおける政治不安の原因の一つと考えられてきた。メキシコやコロンビアのように,比較的安定した政治制度と上記のようなペルソナリスモを長い間共存させてきた国もみられるが,それは,長期にわたる流血をともなう抗争の末,政治指導者たちが政権の交替と運営について一種のカルテルを結んだ結果である。これらの国では,政策形成と実施の過程でペルソナリスモの影響が顕著であるが,どの政治指導者も一定の年限を超えては政権を維持しないこと,また自派以外の政治指導者にも政府への参画を許すことの2点で,ペルソナリスモの行過ぎを防ぐ制度ないしは慣行を確立している。
ペルソナリスモに基づく権力の独占は,経済的発展と社会構造の複雑化といった事情によっても困難になりつつある。輸出経済の発展,ついで工業化の進展によって都市化が進み,都市中間層や労働者の数が増大するにつれ,また交通・通信機関の発展や教育の普及が進むにつれ,カウンター・エリートによる政治宣伝や反政府運動の組織化が容易になった。その結果,今日のラテン・アメリカ諸国では,19世紀とは異なり1人のカウディーリョが長期にわたって政権を維持することが困難となっている。
1950年代以降軍部の専門職業化が進んだことも,国政のトップレベルにおけるペルソナリスモの後退を促す作用を果たしている。すなわち,専門職業化が進んだ軍部では,試験と年功序列とに基づく昇進制度,およびそれによって支えられる位階秩序が将校団によって広く受け入れられているばかりでなく,職業軍人としての共通の専門意識が将校団としての凝集性を高める作用を果たしている。このような軍部が政権を握った場合には,かつてペルーのオドリアManuel Odría将軍(1897-1974)やコロンビアのロハス・ピニーリャ将軍が試みたように,1人の有力軍人が公職を利用して政治的支持者を増やし,みずから政治家に転身していくという現象は起こりにくい。1960年代以降出現したブラジル,アルゼンチン,ペルー,チリ,ウルグアイの軍事政権は,採用すべき政策の内容をめぐる内紛をかかえながら,あくまでも将校団による政権担当というたてまえをくずさなかった。
中央アメリカ,とくにグアテマラとエルサルバドルの軍部も,以前のようにカウディーリョ型の指導者を輩出しなくなったという意味で,南アメリカの軍部と共通点をもっているが,中央アメリカにおいては,軍務という職業がそれだけでは社会的・経済的地位の安定と向上をもたらさないため,軍部の専門職業化が遅れている。そこでグアテマラやエルサルバドルの軍人は,政治的影響力を利用して個人の社会的・経済的地位を上昇させようとする。それが政権をめぐる,あるいは政府の職をめぐる軍内派閥間の抗争となって現れている。
以上のように,ペルソナリスモに基づく国政のトップレベルでの権力独占は困難になっているが,下位レベルでは,近年テクノクラート層(テクノクラシー)の拡大がみられるにせよ,いまだペルソナリスモによる政策の形成と実施が一般的である。
ポプリスモの危機
他方,ラテン・アメリカにおけるポプリスモとは,輸出経済の繁栄期に進んだ都市化と工業化を背景に,1920年代以降ラテン・アメリカ各地に出現した政治潮流で,都市中間層や労働者を動員することによって,寡頭支配層の経済的・政治的支配を覆そうとする運動である。この運動は,階級闘争よりも寡頭支配層に反対する諸社会階級間の同盟と協調を前提としており,さらに民族資本による国内市場向け工業化の推進を唱導していたため,多くの国で工業企業家の支持を獲得することにも成功している。しかし,その具体的な発現形態や持続性は,各国の輸出経済の性格,寡頭支配層の特質や彼らが新しい社会勢力に対してとった政策,寡頭支配層と工業企業家の関係,外国勢力による介入の有無などの事情を反映して,国によって異なっている。例えば輸出経済の発展度が比較的低かった中央アメリカ諸国やドミニカ共和国,ハイチ,パラグアイ,ボリビアといった国々では,ポプリスモを支える中間層,労働者,工業企業家の成長が遅れた。さらにコスタリカを除けば植民地期より大土地所有制が発達し,独立後も多数の土地なし農民や農業労働者が蓄積され続けたため土地をめぐる争いが絶えず,寡頭支配層の中核をなす地主を反動化させた。そのうえ,みずからの権益を守ろうとするアメリカ合衆国の企業や政府も,中央アメリカ・カリブ地域においては直接的・間接的干渉によって保守的な政権を維持する政策をとってきた。このような事情のため,上記の国々ではポプリスモ政権はまったく出現しないか,出現したにしてもごく短命に終わっている。ただ1950年代にポプリスモ政権の下で大規模な農地改革を実施することに成功したボリビアでは,農村部の安定性が増大した。そのためにボリビアでは,その後頻繁な政変を経験してきたにもかかわらず,反動化した地主の支援を受けた軍部が実権を握るグアテマラやエルサルバドルほど著しい社会的緊張はみられない。他方,ニカラグアでは,マルクス主義者とポプリスモ信奉者の双方を含む政権が1979年に成立し,レーガン政権の圧力に抗して,その基盤を固めようとした。
アルゼンチン,ブラジル,ウルグアイ,チリといった国々では,輸出経済の多様化や工業化が進んだ結果,中間層や労働者が政治的・経済的向上を求めて早くからさまざまな運動を展開する力量を身につけた。しかし寡頭支配層がきわめて強力で,かつ1930年代に非妥協的態度をとったアルゼンチンでは,ポプリスモが,軍の一部と労働者の広範な動員に支えられるペロン政権という明確な形をとって現れたのに対し,寡頭支配層が,議会制民主主義の枠内で動くことを条件に,中間層,労働者の政党に政治的自由を許したチリや,寡頭支配層の政党がいち早く社会福祉政策を実施することで中間層,労働者をとり込むことに成功したウルグアイでは,明確なポプリスモ政権が出現することはなく,むしろ長期にわたってさまざまな政府によってペロン政権がとったのと同様の政策(社会福祉立法,労働立法,輸入代替工業化政策など)が実施されることになった。ブラジルのコーヒー農園主・輸出業者も当初バルガス政府に対して武力による抵抗を試みたが,これに失敗するや,後者の工業化政策や社会福祉政策に協力する道を選んだ。
輸出経済の発展度が中程度であったメキシコ,ペルー,キューバといった国々は,それぞれ特殊事情のために特異な道を歩んできた。P.ディアス政権下で土地の急速な集積とインディオ共同体の解体が進んだメキシコでは,中間層,労働者の不満に農民の反乱が結びつき,〈メキシコ革命〉と呼ばれる大変動を経験することになった。その結果,中間層,労働者,農民の諸組織を中心に,事実上工業企業家の団体も加えた強力なポプリスモ同盟が1930年代後半に成立し今日に至っている。他方,ペルーのポプリスモ政党であるアプラは32年の武装蜂起によって軍部を敵に回してから政権に就くことができず,逆にこの軍部が68年に政権を奪い,文民のポプリスモ政権と同様の政策を推進した。キューバでも1944年から52年にかけて革命党と呼ばれるポプリスモ政党が政権を担当したが,バティスタのクーデタのために短命に終わった。その後ゲリラ戦に勝利したF.カストロの強力な指導の下でキューバは社会主義の道を歩み始めた。
→キューバ革命
ポプリスモ政権ないしはポプリスモ的な政権は,その経済的基礎となっていた輸入代替工業化が,国際収支の悪化や悪性インフレによって停滞するにつれ,危機に直面するに至った。工業化の停滞と外貨不足を外資導入によって切り抜けようとする努力もなされ,多国籍企業が多数進出したが,利潤や技術使用料などの形で逆に外貨流出をもたらすようになった。経済的な不安定性が増す中でポプリスモ同盟を維持するために,ペルソナリスモの網を通して多額の補助金や社会福祉予算の分配がなされた。ところが,それらは既得権益となり,経済が悪化し政府歳入が減っても削減することはむずかしかったので,いっそうインフレをあおることになった。恒常的インフレは,所得分配をめぐる諸階級・諸グループ間の対立を激化させ,1960年代から70年代にかけて,ポプリスモ的政権が支配的だった国はほとんど社会不安と政治的・経済的混乱にみまわれるようになった。
この混乱の中で,ポプリスモ型政府に見切りをつけ,さらにキューバ型社会革命への危機感を強めた軍部が,ブラジルでは1964年,アルゼンチンでは66年と76年,チリとウルグアイでは73年にクーデタを敢行し,工業の高度化を目ざす文民テクノクラート,〈法と秩序〉の回復を願う保守的な中間層メンバー,安定した投資環境を欲する工業企業家や外資系企業の支持を受けて,いわゆる〈官僚的権威主義体制〉を樹立した。しかし,このようにして成立した軍事政権の多くも,ポプリスモ政権が残した輸入代替工業化の矛盾や財政不均衡の問題への取組みは不十分であった。これらの政権は経済的矛盾を債務の取入れによって糊塗しようとしたが,80年代初めに累積債務危機に見舞われ,民政に席を譲らざるをえなくなる。
執筆者:恒川 恵市
土地制度
大土地所有制成立の歴史
ラテン・アメリカの農業構造は,一般に,輸出農畜産物のモノカルチャー(単一耕作)と,その基礎となる大土地所有制度ラティフンディオによって特徴づけられる。しかし,ラテン・アメリカ地域は,15世紀以来,おもにスペイン,ポルトガルなどの諸国の植民地支配下におかれた歴史をもち,文化的,社会経済的に一様性をもつものの,ラテン・アメリカと呼称されるにしても,植民地支配を受ける以前における先住民の土地占有の型の差およびその後の植民者の土地および先住民インディオの労働の支配の型の差異によって,現実には地域的多様性を包含している。したがって土地所有型態を社会経済的視点で類型化する場合,国によって,また地域によって差異がある。
植民地支配以前における先住民の土地占有の型によってみれば,それは征服前に土着の文化が高度に発達し,アステカやインカなど国家レベルまでの統治機構が形成されていたメキシコ,中央アメリカ,アンデス高原の諸地域,いわゆる核アメリカと,その他の地域に大別できよう。前者においては,人口稠密(ちゆうみつ)で集約的な定住耕作が行われ,アステカではカルプリcalpulli,インカではアイユと呼ばれていた土地の共有を基盤とした農村共同体が成立し,一定の賦役(インカではミタ),貢納制によって国家に統合されていた。それに対して,後者は,もっぱら焼畑耕作,または狩猟,採集経済で,社会集団の規模も小さく,孤立的であったところである。他方,スペインおよびポルトガルの植民者による土地および先住民労働の支配は,法制度的には植民地全域に及んだ。
スペイン植民地においては,土地については,レパルティミエントrepartimiento,グラシアgraciaないしメルセーmercedと呼ばれる分与地が植民者に分与された。この分与地はインディオの占有地を侵してはならないとされている。グラシアないしメルセーは,植民者の身分によってカバリェリアcaballeríaとペオニアpeonía(前者は後者の5倍)の2種に分けられるが,この制度はもともとスペイン本国(カスティリャ)における領主所領セニョリオseñoríoの土地経営を模範としたもので,植民,居住,耕作を義務づけてはいるが,当初から自営農民による植民を目的とするものではなかった。
先住民労働の支配については,エンコミエンダ制が施行された。エンコミエンダの権利は,土地に及ぶものではないが,エンコメンデーロは,また分与地メルセーの権利をも認められたので,彼らは,教化と賦役労働の収奪の便からインディオの土地の隣接地に分与地を受託した。このことは,エンコメンデーロの自己の所有地における生産の拡大に有利な条件を与え,同時にインディオの土地の蚕食の危険をはらむことになった。当初エンコミエンダの権利は,他人への譲渡は許されていなかったが,その後土地と一体化して家産的性格をもつようになった。このためエンコミエンダ制にラティフンディオの起源を求める説は,上述の事実に根拠を求めている。
このようなスペイン植民地の法制度の下にあって,現実の土地制度の展開は,労働力源であった先住民の社会の存在と植民地的商品生産の進展の度合によって,三つの地域的類型を生んだ。第1は,本国の植民地支配の中心的拠点となり,それゆえに商品生産が最も刺激されたカリブ海地域である。ここにおいては,先住民は白人の持ち込んだ流行病と過酷な労働によって激減し,それに代わって導入された黒人奴隷労働に依拠した大農園アシエンダ,例えばサトウキビ農場(インヘニオ)が成立する。第2は核アメリカにおける先住民の農村共同体の漸次的解体,土地の蚕食をともないながらも,他方それを温存しつつ住民の賦役労働に基礎をおくもの,第3はアルゼンチンのパンパにみられるような狩猟的生産様式をもつ先住民との抗争,ガウチョによる野生化した牛馬の捕獲,粗放的牧畜といった広大な土地の占有である。それとともに核アメリカにおいて鉱山開発にともなう小市場の形成による食料生産のための小生産者が成立した。ポルトガル植民地ブラジルにおいても,分与地制が施行され,その分与地はセズマリアと呼ばれる。この分与地の上に,黒人奴隷労働に依拠したエンジェーニョと呼ばれるサトウキビ大農場がとくにブラジル北東部海岸地帯に形成された。
19世紀初頭のラテン・アメリカ諸国の独立後,S.ボリーバルの啓蒙思想,資本主義のいっそうの浸透を背景に,各国は分与地制の廃止および土地の購入制,奴隷制の廃止,インディオの無償労役と貢租の廃止,教会領の廃止,農村共同体(独立後コムニダー,またはコムニダー・インディヘナと呼称)の共有地の廃止,未開発地の官有地への編入,売却による一連の私有地化を法制化した。その結果,核アメリカ地域では,コムニダーの共有地の私有地化が進行し,コムニダーの土地の繰込みをともなったアシエンダの拡大が顕著になった。それとともに,コムニダー農民の階層分化が進み,零細農化,隷農化が進行したが,メキシコにおいては,メキシコ革命後エヒードとして農村共同体の再建が推進された。カリブ海地域を含む熱帯低地への外国資本の土地投資,農業投資が活発になり,近代的プランテーションが成立した。とくに米西戦争後は,キューバをはじめとするカリブおよび中央アメリカ地域には,アメリカ合衆国の投資が顕著になる。
温帯に属するアルゼンチンでは,熱帯生産物に基づくプランテーションの成立はみられなかった。しかし,独立を契機として,国土の画定,国家財政の基盤としての地代収入を確保するために個人土地所有の決定を意図し,1826年の永代借地法を施行した。この法律による永代借地権は,牛肉,小麦など農畜産物の海外市場の拡大とともに,所有権に転化し,パンパの中心部における私有地化した広大なエスタンシア(大牧場)が生まれた。さらに私有権の未確定のフロンティアの土地(本来インディオの占有地である)は官有地化され,1876年のアベジャネーダ法に基づく移民の導入と官有地の分割払下政策が推し進められ,パンパの内陸周辺部には自営農が成立し,中心部では,大土地所有制下の借地形態が一般化した。ブラジルにおいては,セズマリア制は1850年の土地法によって完全に廃止され,さらに88年に奴隷制度も廃止された。この時期に南部のサン・パウロ州に発展したコーヒー生産は,前期においては奴隷労働に依拠する領主経営的大農場(ファゼンダ)で行われていたが,19世紀末からは,移民の導入による請負契約労働者(コロノ)に移行し,20世紀には,内陸フロンティアでは移民による,おもに家族労働に依拠する独立小生産者層と,その分化による大農場の成立をみるようになった。
ラテン・アメリカの大土地所有制ラティフンディオの起源を,19世紀における資本主義の発展期に求める説は,上述の歴史的事実に依拠している。
ラティフンディオ・ミニフンディオ構造
以上の歴史的背景の帰結として,ラテン・アメリカの土地所有形態を生産諸関係の視点から類型化すると次のようになる。(1)ラティフンディオ(巨大土地所有)型,(2)中農型,(3)ミニフンディオ(零細土地所有)型,(4)コムニダー(共同体的土地所有)型,(5)エヒード型。
ラティフンディオ型はさらに,植民地時代からの系譜を引くと考えられる伝統的・家父長制的支配と庇護の構造(パトロン・ペオン関係)下にある大農牧場,伝統的アシエンダ型と資本主義的経営体としての大農場,プランテーション型(資本主義的アシエンダ型)に分けられる。伝統的アシエンダ型は,歴史的系譜からみれば,(1)もっぱら黒人奴隷労働に依拠した,ブラジル北東部(ノルデステ)のサトウキビ大農場,カリブ海地域のサトウキビ大農場などによって代表されるもの,(2)ガウチョ労働に依拠したアルゼンチンのパンパの牧畜エスタンシア,(3)メキシコ,中央アメリカからペルー,ボリビアにかけてのアンデス高地およびカリブ海地域の一部にみられ,先住民の農村共同体の住民の労働力に基礎をおくものなど,三つの類型に細分することができる。これらは商品生産の発展に対応し,また19世紀における奴隷制度の廃止によって領主経営から資本主義的経営に転化する過程にあり,半農奴的傭役借地農および分益農といった隷農の労働に基礎をおいている。
それに対して,プランテーション型は,19世紀後半からヨーロッパ諸国,アメリカ合衆国の農業への直接投資が活発になるとともに,新農場主による大土地所有,大経営,賃労働の大量雇用に基づいて形成されたものである。しかし,海外市場に対応して,鉄道,港湾などの施設,加工部門や栽培部分に近代的技術を導入しながらも,この型も,ラテン・アメリカにおける旧来の半農奴的労働諸制度を最大限に利用している点で伝統的アシエンダ型とラテン・アメリカ的類似性をもつ。プランテーション型もまた,歴史的成立過程で,次の二つに分けられる。一つは一般にプランテーションといわれるもので,植民地的制度に組み込まれ,外国資本の支配下におかれている。中央アメリカやコロンビア,エクアドルのバナナ栽培,革命前のキューバのサトウキビ農場などがその代表例である。もう一つは,19世紀以降の公有地化された内陸植民の過程で現れた企業的大農場で,ブラジルのサン・パウロ州のコーヒー・ファゼンダ,ボリビアのユンガスやコロンビアのアンデス高地のコーヒー・アシエンダがその例である。
ラティフンディオ型農場は,個人所有の場合,土地所有者は農場内に居住せず,国内の主要都市,または外国に居住することが多く,場合によっては株式会社組織をもつ。したがって農・牧場経営は監理人(アドミニストラドール)に任せられ,その下にさらにマヨルドーモと呼ばれる中間管理人が介在することもある。監理農という類型は,一般にこれに属する。
アシエンダの構成をエクアドルにある約700haのアシエンダで例示しよう。
農場主はほかにもいくつかのアシエンダを所有し,外国に居住している。農場主の息子(農場内の唯一の白人)がこの農場の監理人で年間8ヵ月農場内に居住している。家事労働者5名,副監理補佐,畜産管理人(マヨルドーモ),農事管理人(マヨルドーモ),書記,資格のない獣医,トラクター運転手各1名,隷農(ワシプンゲーロ)12名,搾乳婦12名(ワシプンゲーロの家族),土地をもたない常雇い労働者(ペオン)8名,ヤナペーロ(農場外の村落に住み,農場内の道路,給水,その他の便益にあずかる代りに農場の労働に従事することを義務づけられている農民)48名,土地をもたない臨時雇い労働者(ペオン)8名。
このアシエンダはけっして特殊な事例ではない。隷農ワシプンゲーロ,広範に存在する土地から切り放された農業労働者ペオンだけではなく,ここではヤナペーロと呼称される周辺村落の零細農ミニフンディスタ(土地生産だけで生計の維持ができない小農)の労働力に強く依拠していることは明らかである。この点に注目した場合,ラティフンディオの対極に,経済外的強制下にある隷農,不完全就業のペオンとともにミニフンディスタ(メキシコのエヒード農民の多くもその中に含まれる)を対置し,ラテン・アメリカの土地制度をラティフンディオ・ミニフンディオ構造として特徴づけることができる。
土地所有の偏りの量的把握は,1963-64年に行われたCIDA(パン・アメリカ農業開発委員会)の調査によれば次のとおりである。農業構成の階層は次の四つに区分される。(1)ラティフンディオ(就業者12名以上),(2)多家族中農型(同4~12名),(3)家族農(同2~4名),(4)ミニフンディオ(同2名未満)。この分類に従えば,調査対象7ヵ国のうち,アルゼンチンを除けば,ラティフンディオの土地占有率は40%を超え,チリ,ペルーでは80%を超えている。また,エクアドル,グアテマラ,ペルーでは,ミニフンディオの数は90%に近い。そして,ブラジル,アルゼンチン,チリは比較的中間層が厚い。ラティフンディオは,広範に存在する不完全就業農業労働者,経済外的強制をともなう隷農,零細農の労働の収奪のうえに存在し,農業への再投資を阻害し,生産力の停滞につながる。それとともに土地の独占は社会的・政治的緊張につながり,農業改革は緊急のものと考えられている。
1944年のグアテマラのクーデタ,52年のボリビアの革命,52-65年のペルーのクスコ地方,ラ・コンベンシオンの農民運動,1955-64年のブラジル北東部の農民同盟の結成などは,土地問題にかかわる社会的政治的事例としてあげられよう。1959年のキューバ革命は,社会主義的土地改革の唯一にして最大の例外である。キューバ革命以後,各国政府は農業改革を政策の主要課題として取り上げているが,ペルーの行った海岸地帯における外資プランテーションの接収と国の管理化におく共同農場化,高原地帯におけるアシエンダの接収と周辺コムニダーへの帰属,共同経営化が最もラディカルな土地再配分的改革の事例であり,多くの場合,生産力増大の視点からする非生産的ラティフンディオの有償接収,再配分,中農層の育成・富農化,開拓・植民による土地の再配分という漸進的改革にとどまっている。
→アシエンダ →ファゼンダ
執筆者:西川 大二郎
経済
ラテン・アメリカは33の独立国をもち,総面積は世界地表面積の15%,日本国土の54倍に相当する2053万km2,総人口は世界人口の8.4%,日本の3.8倍に当たる4億8200万人(1995年,国連統計)で,人口密度はアフリカと並び開発途上地域中もっとも低い。人口増加率は世界平均の1.8%を下まわる1.6%(1985-94年平均,世界銀行)で,広大な面積に対して相対的に人口圧力が小さい恵まれた状況にある。またGNPは世界の6.0%,日本の3分の1に相当する1兆5034億ドル,1人当りGNPは世界平均の半分,日本の12分の1に相当する2935ドル(いずれも1994年,国連統計)で,開発途上地域の中では西アジアに次いで高く,そのためラテン・アメリカ諸国は中進国と呼ばれてきた。しかし所得分配は著しく不平等で,貧富の差が大きい。
ラテン・アメリカは豊かな天然資源に恵まれ,鉱産物ではニッケル,ボーキサイト,銅,錫,銀が世界の確認埋蔵量の20%以上のシェアを占めている。また農産物ではコーヒー,オレンジ,バナナが世界総生産の40%以上,大豆,カカオ豆,砂糖が20%以上のシェアを占める。牧畜業も盛んで,馬,牛の飼育頭数は世界全体の各30%,20%以上を占める。さらに近年開発が進んでいる水産業では,漁獲量が著しく増加し,1990年代初めには世界全体の18%に達した。他方林業は古くから開発されているが,アジアほど急速ではなく,世界の原木生産の10%強を占めるにとどまっている(いずれも1990年代初め)。
こうした1次産業の発展に支えられ,ラテン・アメリカは従来からモノカルチャー経済に依拠して発展してきたが,1929年恐慌を契機に1930年代以降工業育成政策が実施に移された。その過程でGDP,就業人口に占める工業部門の割合が増加してきたが,一部の国々を除き,現在なお工業は輸出力では第1次産業に及ばない。
次にラテン・アメリカ独立以降の経済変容についてみよう。
開放的な経済自由主義路線
独立後のラテン・アメリカ諸国においては,植民地遺制の克服と新たな経済開発路線の確定が最も緊要な課題となったが,19世紀半ばまでは国家建設の基本線をめぐる見解の対立から政治抗争が絶えず,政情の混迷状態が続いた。政治抗争の要因は多岐に及んだが,そのうち経済政策をめぐる対立は以下のとおりであった。すなわち一方に閉鎖的な経済保護主義を植民地遺制として排除し,国際分業体制を肯定して自由貿易政策を推進しようとするグループ,他方にヨーロッパ諸国との開放的な経済関係の進展を警戒し閉鎖的な経済政策を温存しようとするグループの間の対立抗争であった。19世紀前半においては両者の間で権力抗争が絶えず,全般的には後者が優位を占めていた。それに対して19世紀半ば以降になると,ヨーロッパ的な近代国家建設路線に立脚した開放的な経済自由主義政策が実施されるようになり,ラテン・アメリカ経済はイギリスを中心とする国際経済の分業体制の中に組み込まれていった。
このような19世紀半ば以降の経済開発路線はきわめて開放的な経済自由主義に基づくもので,貿易の自由化,積極的な外資・技術導入,ヨーロッパ移民受入れのための優遇措置などが実施に移された。また1870年代以降実現された輸送手段における画期的な技術進歩により,南半球とヨーロッパとの間の地理的距離が短縮され,交易関係が大幅に進展していった。さらに農産物の品種改良技術や畜産物の冷凍・冷蔵技術がヨーロッパから導入され,1880年以降において冷凍船(フリゴリフィコ)が実用化されるに至り,南アメリカ南部諸国からヨーロッパ向けの冷凍・冷蔵肉輸出が急増することになった。これに加えてブラジルからコーヒー,チリ・ボリビア・ペルーから鉱産物,エクアドル・コロンビア・中央アメリカ諸国からコーヒー,バナナ,カリブ地域から砂糖といった第1次産品の輸出が19世紀後半以降大きく伸び,こうしてラテン・アメリカ諸国は第1次産品輸出を経済成長のダイナミック・セクターとする経済構造を確立していった。このような経済成長路線は,一方で労働力源としての大量な移民流入,他方で鉄道・港湾建設,鉱山開発,土地売買,食品加工業などへの欧米資本の投下に支えられていた。
〈内向き〉の工業化型と輸出経済強化型
こうした第1次産品輸出に立脚した経済構造も,自由多角的な国際貿易構造の破局によりその存立基盤を失うことになった。すなわち1929年恐慌を契機として世界経済がブロック化傾向をたどる中で,ラテン・アメリカ諸国は輸出市場の狭隘化と輸出価格の低落に直面するところとなったのである。そしてこうした経済的打撃に対するラテン・アメリカ諸国の対応は次のように大きく二分された。一つはパン・アメリカ主義の下でアメリカの経済圏に組み込まれ,第1次産品輸出経済の強化に向かった国々,もう一つは一方で輸出市場の狭隘化打解策を目ざしながら他方で輸入代替工業化を推進していった国々である。後者のグループに含まれるのはアルゼンチン,チリ,ブラジル,メキシコといったラテン・アメリカ域内の先進諸国で,これらは繊維産業を中心とする軽工業に立脚した工業育成政策を導入し,外貨節約のための国内市場向け工業生産を拡大していった。世界経済のブロック化から第2次世界大戦に至る過程で,先進諸国からの工業製品流入が減少し〈内向き〉の工業化が進む中で,域内先進諸国の工業労働者層が強化され,その政治的影響力が拡大していった。それがこれらの国々におけるナショナリズム,ポピュリズムの台頭を支える重要な要因となったのである。そして第2次世界大戦後には〈内向き〉の工業化における軽工業から重化学工業への移行,さらには国内市場から国外に市場を求める〈外向き〉の工業化へと進んでいった。
それに対して輸出経済強化型の政策を導入したグループの中には,域内先進諸国を除く大半の国々が含まれ,国際市場における輸出産品価格の低落を輸出量の拡大によって補塡するため輸出用第1次産品の増産に努めた。これらの国々の多くはその人口規模が相対的に小さく国内市場が狭隘で,工業育成過程における大きな制約条件をかかえていた。輸出経済強化策は,対外競争力において相対的に有利な条件をもつ大土地所有に立脚した輸出向生産を優遇する形で進められ,そのことは大土地所有者層,貿易商の政治力の温存と独裁制を招く結果になった。第2次世界大戦後世界経済のブロック化が解かれたが,先進国間貿易の拡大,一部の第1次産品における代替品の開発と実用化,さらには第1次産品輸出国間相互の競合関係の激化などにより,第1次産品輸出市場の相対的な狭隘化が進んだ。こうした中で域内先進諸国以外の国々の多くは軽工業を手始めに初期段階の輸入代替工業化政策を採用することになった。
域内経済統合への歩み
こうした状況の下でラテン・アメリカ諸国は,工業化を基盤として域内協力を進展するため経済統合の結成に踏み切った。まず1960年の条約締結を経て61年にラテン・アメリカ自由貿易連合と中米共同市場が発足した。前者にはブラジル,メキシコ,アルゼンチンの三大国にチリ,ペルー,コロンビア,ベネズエラ,ボリビア,エクアドル,ウルグアイ,パラグアイが加盟,域内自由貿易市場の結成と産業補完協定による加盟諸国間の工業化政策の調整が主要目標とされた。そして発足後20年の歩みを経て81年に改組され,ラテン・アメリカ統合連合として再出発したが,停滞気味である。また中米共同市場はパナマを除く中央アメリカ5ヵ国(グアテマラ,エルサルバドル,ホンデュラス,ニカラグア,コスタリカ)によって構成され,域内共同市場の結成と統合産業計画の実施を目ざした。60年代には注目すべき進展がみられたが,70年代には中米紛争が泥沼化し,経済統合も足踏み状態に陥った。
1969年にはラテン・アメリカ自由貿易連合のサブ・リージョナルな経済統合組織としてアンデス共同市場が発足し,アンデス6ヵ国が加盟,域内加盟諸国間の発展格差是正,共同市場結成,統合産業計画・外資規制の実施などがおもな目標に掲げられた。アンデス共同市場は自立的共同市場の形成と域内格差是正の両立を目指したが,共通外資政策をめぐる加盟諸国間の利害対立が引金となって,76年チリが脱退した。加盟国の多様な条件の下で,統合の進展ははかばかしくない。さらに英語圏カリブ諸国によって1968年カリブ自由貿易連合が発足,73年にはカリブ共同体共同市場に改組された。これらの経済統合は1960年代にかなりの成果をあげたが,70年代以降停滞気味で,73年以来の石油危機からの打撃も大きく,こうした状況の打解策として域内協力関係の拡大が求められていった。73年22ヵ国が締結したリマ協定に基づいてラテン・アメリカ・エネルギー機構が結成され,エネルギー需給における域内協力の進展による石油危機対策が打ち出された。75年には25ヵ国によって締結されたパナマ協定に基づきラテン・アメリカ経済機構が結成され,イデオロギー抗争を排して実利主義に依拠したラテン・アメリカ全域の経済社会発展を目ざすことになった。
こうした域内経済社会開発を資金面で支える組織として1959年に米州開発銀行,61年中米経済統合銀行,70年アンデス開発公社およびカリブ開発銀行,78年ラテン・アメリカ準備基金など地域開発金融機関が次々と発足していった。
低開発性の打破を目ざして
以上のような変遷をたどってきたラテン・アメリカ諸国の経済は,次のような低開発性という共通の問題をかかえている。すなわちブラジル,メキシコなど一部の国々を除き工業の発展が遅れ,各国経済の第1次産業への依存度が高いこと,近代的な生産構造が確立しておらず生産力水準・生産効率が相対的に低いこと,所得の不平等分配が著しくかつ高額所得者層の投資意欲が低いため国内資本形成が遅れていること,資本,技術,生産財供給において先進諸国への依存度が高いことなどで,対外的に脆弱な経済構造が温存されていることなどである。こうした低開発性の根源を究明する経済理論として第2次世界大戦以降ラテン・アメリカの中からプレビッシュ理論(プレビッシュ報告),従属論,構造学派の理論などが提起され,対外従属的な低開発経済を改める戦略として,工業育成,国内の資本形成,技術開発,企業家養成,土地改革を含む制度改革,域内協力などの政策が提起された。これらの開発をめぐる理論や政策はラテン・アメリカだけでなく他の開発途上諸国にも大きな影響を及ぼした。
新自由主義への転換
しかし1973年に端を発する石油危機から,大半のラテン・アメリカ諸国が支払不能に陥った80年代の対外累積債務危機に至る過程で,ラテン・アメリカは深刻な経済危機に陥った。80年代のGDP実質成長率は1.2%という低率を記録,それに加えて高率インフレ,高失業,財政赤字,対外収支難,対外債務返済不能といった問題に苦しんだ80年代は,ラテン・アメリカにとってまさに〈失われた10年〉であり,早急にこの危機から脱することが迫られた。従来からの政府主導による輸入代替工業化政策にかわり,市場原理に基づく新自由主義政策への転換が断行された。すなわち財政赤字の解消による財政収支の均衡,産業保護政策の撤廃と貿易の自由化,金融の規制緩和と資本市場の自由化,公営企業の民営化,地方分権化などの政策が次々と実施された。競争をとおして経済の効率化をはかり,安定した経済成長の持続を目指すこの政策は,IMF・世界銀行が主導する構造調整計画に基づくもので,その実施成果に応じて債務削減を含む債務戦略(ブレイディ構想)の適用を受け,メキシコ,コスタリカ,ベネズエラ,ウルグアイ,アルゼンチンなどがその対象国とされた。
経済統合の進展
1990年代に入り経済統合においても新しい動きがみられる。一つは従来の域内統合にかわる域外先進諸国との統合で,アメリカ,カナダ,メキシコ3ヵ国を対象に,貿易,資本の自由化を軸に,94年北米自由貿易協定(NAFTA)が発効した。他方域内経済統合の活性化を目指す組織として,アルゼンチン,ブラジル,ウルグアイ,パラグアイ4ヵ国を加盟国とする南米南部共同市場(メルコスール(MERCOSUR))が95年,関税同盟として発足した。貿易の自由化,財・サービス,生産要素の自由な流通,経済政策協調を目的とし,共同市場の形成を目指している。その他にも中米共同市場,アンデス共同市場においても再活性化の動きがみられる。
執筆者:今井 圭子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラテンアメリカ」の意味・わかりやすい解説
ラテンアメリカ
らてんあめりか
Latin America
総論
アメリカ大陸の北半球中緯度から南半球にかけて大きく広がる、33の独立国と11の非独立領土からなる地域の総称。北はリオ・グランデ川とフロリダ海峡を隔ててアメリカ合衆国に面し、東は大西洋を隔ててアフリカ大陸とヨーロッパに比較的近い距離にあり、こうした地理的な位置がラテンアメリカの歴史の展開に大きな影響を与えてきた。
[中川文雄]
名称の由来と定義
16世紀から19世紀初めまでの植民地時代、この地域はインディアスあるいはアメリカとよばれていた。19世紀初頭にスペイン植民地の大部分が独立を遂げようとしたとき、独立指導者たちは、自分たちが解放しようとしている土地をアメリカの名でよんだ。独立後、植民地臭の強いインディアスの名は捨てられたが、共通の歴史を有するこの国家群を何とよぶかについて、一致した名はなかった。1850年代のなかば、旧スペイン領諸国の圧政と政争から逃れ、パリに移り住んだ知識人たちは、アメリカ合衆国の膨張の前に、それぞれの祖国の存立が危ぶまれていたことに憂慮し、自分たちの国家群をよぶのに、アングロ・サクソン列強の脅威に抵抗できる力を内に潜めた新しい名称、しかも、叙情的で文明の香りを感じさせ、自分たちが文明の中心フランスと一体であることを示す名称を求めた。それがラテンアメリカ(アメリカ・ラティーナ)であった。1856年、パリ在住のコロンビア人ホセ・マリア・トレス・カイセードJosé María Torres Caicedo(1830―1889)が書いた詩『二つのアメリカ』のなかでこの名称を使ったのが最初とされる。メキシコに帝国的拡大を図ったナポレオン3世とそれに近いフランスの知識人たちは、このラテンアメリカの名称を世界に広げるのに大きな役割を果たした。20世紀に入るとラテンアメリカの呼称はラテンアメリカ諸国でますます広く受け入れられていったが、スペインの知識人はこれに憤慨し、イスパノ・アメリカの名称の正当性を主張した。そうした抵抗にもかかわらず、ラテンアメリカの名称は普遍化し、国連などの国際機関もすべてこの名称を採用するに至った。
1960年ごろまで、ラテンアメリカの範囲は、ラテン文化の伝統を引き継ぐ20の共和国にほぼ限られていた。すなわち、スペイン系の18か国とブラジル、ハイチであり、それは「ラテン」の名と矛盾しない文化と伝統を有する国々であった。ところが、1962年以後旧イギリス領から12、旧オランダ領から一つの新興独立国が生まれ、これが国連などでラテンアメリカ地域の一員として扱われることになった。これらの新興独立国は、かつてスペインやフランスの支配を受けた時代があり、民俗文化にその影響をとどめているが、公式次元での言語、文化、制度は非ラテン系であり、その歴史的体験も本来のラテンアメリカ20か国とは異なっており、当事国自身の側でもラテンアメリカに加えられることを好まない傾向がある。そこでこうした新興独立国の立場を考慮して、これら諸国をラテンアメリカのなかに加えずに、別個にカリブ海地域とよび、それまで一つの地域として扱ってきたラテンアメリカを「ラテンアメリカとカリブ海」と分けて表現する傾向が近年強まっている。国連その他の国際機関や各国外務省、また、学究的な出版物もこの表現を使うことが多くなってきている。
[中川文雄]
歴史的・文化的特質
ラテンアメリカと世界のほかの地域とを対比したとき特徴的なことは、ラテンアメリカでは垂直的な断層があるものの、ほぼ均質な言語と文化が多数の国にまたがって広がっており、それが共有されていることである。ラテンアメリカでは域内国家間および国内地方間で、また、階層間で大きな違いがあるにもかかわらず、言語と宗教を中心とした文化伝統の面で、一つの共通軸が貫かれている。ラテンアメリカはヨーロッパ世界と非ヨーロッパ世界の両方の要素を内包している。ラテンアメリカはヨーロッパ世界の拡大の産物であり、ヨーロッパ文明の大きな影響を受けているが、一方では経済的な低開発と他地域への従属という点で、ほかの新大陸国家と異なり、むしろアジア、アフリカと共通の歴史的発展を遂げた。
[中川文雄]
歴史
特徴
ラテンアメリカはヨーロッパ世界と非ヨーロッパ世界の両方の要素を内包し、両者の掛け橋的存在である点で、世界の諸文明圏のなかで特異な地位にある。その歴史も、ヨーロッパ世界の拡大の過程という一面と、その拡大の結果生み出された周辺としてのラテンアメリカが陥った政治的・経済的従属から自らを解き放つため、それを支配するヨーロッパ的世界の中心に対する反逆の過程という他の一面とから成り立っている。
ラテンアメリカは近世・近代におけるヨーロッパ文明の拡大の直接の産物であり、その文化的・制度的母胎の最大のものをヨーロッパから受け、また、新大陸という共通の地理的環境での歴史的発展を遂げた点で、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの新大陸国家と共通した歴史を有する。しかし、他の新大陸国家と違って先住民社会の文化や制度を相当に残存させ、それを融合したこと、また、受け継いだヨーロッパ文明は主として近代合理主義以前のそれであったことから、産業文明とは異なった文明へと発展し、一方では経済的な低開発と他地域への従属が深化したことなどの点で、他の新大陸国家と明らかに違った歴史的発展を遂げた。アメリカ合衆国がヨーロッパ的世界の中心となったのと対比的に、ラテンアメリカはその周辺にとどまり、中心であるアメリカの支配に反逆、抵抗するというのがラテンアメリカ現代史の一つの基調であるといえる。
ラテンアメリカは、また、植民地化と従属、低開発の持続という点で、アジア、アフリカと共通の歴史的体験を有する。しかし、アジア、アフリカは主として19世紀の西欧列強の植民地主義の下で政治的・経済的支配を受けながらも、その固有の文化的伝統を残した。これに対して、ラテンアメリカの植民地化は15~16世紀のスペイン、ポルトガルが国民国家を建設した動きと理念をそのままに拡大する形でなされたから、言語・文化・宗教面での強力なヨーロッパ化を受けた。世界史の流れが、近代でのヨーロッパ世界の非ヨーロッパ世界への優越を終焉(しゅうえん)させ、現代に入って非ヨーロッパ世界が台頭し、世界がもはやヨーロッパ世界中心に動くのをやめるようになったとき、ラテンアメリカは台頭した。しかし、そこにはヨーロッパ世界への帰属感が多分に残されていた。現代におけるラテンアメリカの台頭は、非ヨーロッパ世界の巻き返しという一面をもち、基本的にはその流れに促されながら、他方では、同じヨーロッパ世界内部での、近代においては優位を占めた中心部に対する劣位だった周辺からの巻き返しが、現代になって進行し始めたという一面をもっている。
[中川文雄]
歴史の始まりと時代区分
従来、ラテンアメリカの歴史は、15世紀末、ヨーロッパ人がアメリカ大陸を「発見」し、それをヨーロッパ文明の枠の中に引き入れたときに始まると考えられていた。しかし、近年では、その歴史に、ヨーロッパ人到来以前の先住民社会の諸制度が及ぼした影響が再評価を受けるようになり、かつては歴史以前とよばれた新大陸の古代文明の歴史がむしろラテンアメリカ史そのものの必須(ひっす)の一章として扱われるべきだとの考えが強まってきている。一方、今日のラテンアメリカの諸制度を形成するにあたって、もう一つの、しかもより大きな母胎を提供したのはイベリア半島(スペイン、ポルトガル)であり、それゆえに、16世紀に至るまでのイベリア半島の歴史は、ラテンアメリカの淵源(えんげん)として顧みられねばならない。このような異種の文明が接触し、融合の過程が始まる15世紀末以後にラテンアメリカそのものは生まれるわけだが、それ以後の歴史は、まったく異なった大陸で互いに孤立して発展した前記二つの文明の歴史と直接につながっているのであり、そうした複数の、しかも互いに著しく異質な起点を有することこそが、ラテンアメリカ史の独特な性格といえよう。
時代区分に関しては、従来は、いかなる国家権力の下に置かれたかに従って、次の2時代に大別されていた。
(1)15世紀末から19世紀初めまでの植民地時代、すなわち、新大陸の植民地がスペイン、ポルトガル、フランスの王権の下で統治されていた時代
(2)19世紀初めより今日に至るまでの独立国時代、すなわち、カリブ海地域の少数の植民地・海外県を除いて、一般に新大陸のスペイン、ポルトガル、フランス領植民地は19世紀初めに独立を遂げ、以来、今日まで独立国の地位を保ってきたが、この独立国としての時代
である。これは共和国時代ともよばれる。ブラジル、メキシコ、ハイチで独立後のある期間存在した帝政を例外とみるならば、独立後のラテンアメリカはおおむね共和国であったからである。このように植民地時代と共和国時代に大別する区分の仕方は、もっとも便宜的なものとして広く用いられている。しかし、歴史を国家主権との関連だけでなく、広く経済、社会、文化との関連においてもみようとするときには、次のような区分が可能になろう。
(1)征服前のアメリカ大陸と中世イベリア半島(15世紀末まで)
(2)ヨーロッパ人の到来、先住民征服と植民地諸制度の成立(15世紀末~17世紀末)
(3)18世紀の改革、19世紀独立革命、独立後の混乱期(1700年ごろ~1850年ごろ)
(4)物質的進歩と西欧化の時代(1850年ごろ~1930年ごろ)
(5)現代(1930年代~現在)
[中川文雄]
征服前のアメリカ大陸と中世イベリア半島
アメリカ大陸古代文明の特色
アメリカ大陸の先住民インディオの祖先は、いまから3万5000年前から2万年前ぐらいにかけて北東アジアから、当時陸続きであった今日のベーリング海峡を経てアメリカ大陸に移った。こうした人口移動の波は、9000年前にはすでに南アメリカ大陸の南端にまで達していた。15世紀末までに新大陸のあちこちでさまざまな発展段階の文化が生まれたが、それらはその後の歴史との関連では、
(1)主として熱帯高地を中心として栄えた高度な農業生産力と比較的稠密(ちゅうみつ)な人口をもつ階層社会
(2)アメリカ大陸のその他の広大な地域(主として熱帯雨林・サバナと温帯草原)に存在した狩猟、採集または低度生産力の農業に依存する小部族社会
に大別されよう。
紀元前3500年ごろに、すでにメキシコ中央高原でトウモロコシの栽培が始まっていたが、前1500年ごろに農業生産力が高まり、非農耕階級が生まれた。南アメリカの中央アンデスにおいても前1200年ごろまでにトウモロコシとジャガイモの栽培が一般化した。こうしてアメリカ大陸の熱帯高原とその隣接地域で、生産性が高く保存がきく穀物であるトウモロコシあるいは凍結によって保存可能となるジャガイモの栽培に経済的基盤を置き、それによって非農耕階級である神官と職人の存在が可能となり、体系的な思想をもつ宗教と優れた芸術が生まれた。比較的稠密な人口集団のなかで経済分業と社会階層の分化が生じ、そうした分化した人口集団を統治するため、アステカ王国、インカ帝国のような高度に中央集権化された国家さえ出現した。
アメリカ大陸の高度文明は数学、天文学、建築、土木技術などで旧大陸に匹敵する水準を示しながら、冶金(やきん)は発達せず、役畜の使用や車輪の利用を思いつかなかったというような不つり合いな形での発展を遂げた。これは、アメリカ大陸の文明が旧大陸のいかなる文明からもほとんど完全に孤立して発展したためである。こうした不均衡な発展が、のちにアメリカ大陸の高度農業文明がスペイン人の征服の前に、もろくも蹂躙(じゅうりん)される大きな原因となった。階層社会を構成し、権力が集中していたこれら高度農業文明地帯は、スペイン人によって短期間に比較的容易に征服された。しかしその場合、スペイン人は先住民社会の支配機構の多くを残存させて、それを利用し、それとともに先住民の文化と血は、これらの熱帯高地では大きな割合で残された。
これと反対の運命をたどったのが(2)のその他の広大な地域の先住民であった。この地域の経済活動は元来、狩猟、採集であったが、アマゾン川流域、カリブ海に面した低地では前800年ごろまでに、根茎マニオク(キャッサバ)の栽培が一般化した。しかし、マニオクは保存がきかず、先住民社会で経済的分業は発展しなかったし、高度な階層社会や国家や都市をつくるには至らなかった。
階層社会が成立していた高度農業文明社会では、スペイン人が新しい支配者になったとき、住民の大多数は新支配者に従順であり、抵抗は少なかった。これと対照的に(2)のその他の広大な地域の小民族集団では、民族が一丸となってスペイン人の征服に抵抗することが多かったし、また、スペイン人から学んだ馬術を利用して戦闘力を高め、長期間にわたりスペイン支配に挑戦したチリのアラウカノ、メキシコ北部のコマンチェーやアパッチのような民族集団も存在した。そのためこれらの地域の先住民社会をイベリア半島人が征服するには長期間を要したし、これら先住民の多くは、イベリア半島人との抗争で絶滅するか、搾取と流行病で人口を激減させられるか、圧倒的なイベリア文明の前に自らの文化の特色を失っていくかの運命にたたされた。
[中川文雄]
ラテンアメリカの淵源としての中世イベリア半島
今日のラテンアメリカの諸制度を形成するにあたって、先住民文明よりも、さらに大きな母胎を提供したのはイベリア半島であった。それゆえ、16世紀に至るまでのイベリア半島の歴史は、ラテンアメリカ史の前史として顧みられねばならない。8世紀にアフリカから侵入したアラブ人、ベルベル人のイスラム教徒によってイベリア半島は征服された。半島北端に追い込められたキリスト教徒がイスラム教徒から徐々に国土を回復する運動が、15世紀末までのイベリア半島の歴史を特色づけた。しかし、国土回復運動(レコンキスタ)とよばれるこの運動の過程は、キリスト教徒とイスラム教徒の絶えざる抗争ではなく、むしろ中世のイベリア半島に支配的であったのは両者の共存と相互的な寛容であり、それを通じて両者の文化的・人種的混交がなされた。そのことは、のちにスペイン人、ポルトガル人がアメリカ大陸で先住民や黒人と人種的に混交することを容易にした。
イベリア半島は中世封建社会の萌芽(ほうが)の段階でイスラム教徒の征服を受けたため、ほかの西ヨーロッパに比べるとその封建制度の基盤が弱体であった。しかも、国土回復運動でキリスト教徒が回復した土地には、通常、新しい都市が建設されたが、この都市の多くは王権に直属した。こうして絶対君主の下に国民国家がほかのヨーロッパ諸国に先駆けてイベリア半島に誕生する気運が促された。まだ中世的秩序が強力な時代に国民国家が生まれ、その指導理念に多分に中世的な秩序や価値が仰がれたことは、その後のスペイン、ポルトガルとその植民地となるラテンアメリカの性格を、中世的秩序が崩壊したのちに本国からの植民がなされたイギリス領の北アメリカ植民地と根本的に異なったものにした。
1469年、イベリア半島のもっとも強力な2王国カスティーリャとアラゴンの王女と王子が結婚し、スペイン(原名エスパーニャ)という統一国家がほぼ成立した。スペインでは国民国家の成立という大事業を前にして、宗教的・文化的統一を図ろうとする姿勢が著しく強固になった。国民国家の精神的支柱としてカトリックが仰がれ、異端裁判が始まった。中世におけるイベリア半島の宗教的寛大さは捨てられ、ユダヤ人は追放され、また、イスラムからキリスト教徒に改宗した人々の多くも追放され、カトリック教会と王権を中心にして統一された国民国家をつくろうとする気運が15世紀末には著しく高まった。そのような時期にアメリカ大陸がヨーロッパ人によって「発見」され、その征服が開始されたのである。それは、スペイン人がアメリカ大陸の征服を、国土回復運動の、そして、その集大成としての国民国家形成の延長として行うことを意味した。このことが、19世紀のイギリス、フランスによるアジア、アフリカでの植民地経営と違って、16世紀のスペイン人に「新大陸植民地」の徹底したスペイン化、キリスト教化の政策をとらせ、300年という長期間の植民地時代を通じて、その言語、文化、制度を新大陸に深く植え付けさせた。
[中川文雄]
ヨーロッパ人の到来と植民地制度の確立
アメリカ大陸の「発見」
ヨーロッパ人のアメリカ大陸への到達は、すでに11世紀に北欧のバイキングによってなされていたと思われるが、それはヨーロッパ社会にもまたアメリカ社会にもなんら衝撃を与えなかったし、継続的な植民を引き起こすだけの歴史的条件を伴っていなかった。その後、ヨーロッパが拡大する条件を備えたときに、アメリカ大陸に到達してそこへの継続的な植民の糸口を開いたのはコロンブスである。
アジアに達するつもりで大西洋を西に向かって航行したコロンブスは、1492年10月12日、今日の西インド諸島のサン・サルバドル島を「発見」した。すでに人類の居住していたアメリカ大陸への彼の到達を「発見」とよぶことについては、近年、歴史学者の多くが異議を唱え、「二つの文化の出会い」と表現するようになってきている。コロンブスは死ぬまで彼の「発見」した土地をインディアス(それは今日のインド亜大陸だけでなく、日本や中国を含めたアジアの南東部、東部全体の意味に使われていた)の一部と考え、そこの先住民をインディオと名づけた。彼の「発見」した土地が実はヨーロッパ人にとっては未知の新大陸であったことは、1503年イタリア人航海者アメリゴ・ベスプッチによって明らかにされ、その名をとって新大陸はアメリカとよばれることになった。コロンブスによる「発見」後、主としてイスパニョーラ島(ハイチ島)にあって植民地経営にあたっていたスペイン人は、ここを本拠にして1510年前後からカリブ海のほかの島々、メキシコ、南アメリカ大陸の探検と征服に乗り出し、そこに新しい都市を築いた。スペイン人たちは当時のロマンチックで空想的な騎士道物語によって黄金郷の存在を疑わず、彼らの空想と信仰が、その超人的ともみえる勇気とエネルギーの根源になっていた。スペイン人、ポルトガル人が新大陸に植民を開始しだした1500年前後から、スペイン、ポルトガルの新大陸支配が崩壊する19世紀初めまでの約300年間は、一般に植民地時代または副王領時代とよばれる。
[中川文雄]
アステカ王国とインカ帝国の征服
1518年からスペイン人はメキシコ湾岸の探検を行っていたが、1519年から1521年にかけて、キューバを起点としたエルナン・コルテスがアステカ王国を征服した。1524年からインカ帝国の探索を始めたフランシスコ・ピサロは、1531年から1533年にかけてインカ帝国を征服した。16世紀初めの新大陸の先住民人口は、少なくとも1300万と考えられ、その半数以上がこれらの国に集中していた。近年では、16世紀初頭、アステカ王国は2500万、インカ帝国は1150万の人口を擁したとの説が有力であり、そうした先住民人口はその後の1世紀間で、ヨーロッパとアフリカからもたらされた疫病と破壊、酷使のために数分の1に激減した。
数百人のスペイン人が、彼らに何万倍する人口の両国を短期間で征服しえたのは、先住民側に白人を神聖視する伝説が存在し、内紛と対立があったからである。さらに旧大陸では当然のことであった戦術やウマの使用に未知であったため、それが大きな心理的衝撃となったこと、また、両国の中枢ともいうべき皇帝がスペイン人の策略によって捕虜にされ、両国の戦士階級の反抗が著しく弱められたことなどによる。スペイン人は両国の戦士階級の抵抗を短期間で壊滅させ、その後は従来の支配組織を利用して従順な農民たちを支配していった。
アステカ王国、インカ帝国を征服したスペイン人は、さらにグアテマラ高地のマヤ人の王国(1523)、現コロンビアのチブチャ王国(1538)などの、ほかの高文化農耕先住民を征服した。しかし、狩猟、採集、原始的農業の段階の先住民が住む、そのほかの広大な地域のスペイン人による征服と植民は、はるかに時間を要した。
[中川文雄]
スペイン植民地の支配機構
スペイン人は先住民の都市を略奪し、先住民文化を破壊し、インディオを大農園や鉱山に送り込んで非人道的に酷使した。そうしたスペイン植民者からインディオを保護しようとする努力がドミニコ会の修道士バルトロメ・デ・ラス・カサスによってなされ、スペインの王権は、植民者がインディオに及ぼす権利を制限する法律を制定した。しかし、その後もインディオに対する収奪は過酷であった。破壊と搾取を行う反面、スペイン人は都市を建設し、宗教的組織をつくりあげ、スペインの宗教と文化を移植する努力を行った。
スペインの新大陸植民地の支配機構としてまず案出され、長く影響を残したのがエンコミエンダ制であった。これは、スペイン人植民者のなかの選ばれた者に、その地域を防衛し先住民を教化する義務の代償として、一定数の先住民を割り当て、彼らを労役に徴発する権利を与える制度であった。王室官憲の組織ができあがらない植民地時代初期においては、エンコミエンダの権利を与えられた植民者が、王室の代行として先住民から貢租を徴収した。このようにして、植民者は当初は絶大な権力を先住民に及ぼしたが、その権力は16世紀後半以後、王権によってしだいに制限される方向に向かった。王権が精密な植民地行政組織をつくりあげ、植民者に代行させていた権限を自らの手に収めていったからである。
植民地には幾段階もの行政機構があり、それがお互いをチェックしあっていたが、それに加わりうる人間は主としてスペイン本国生まれの人間(ペニンスラール)であり、植民地生まれの白人(クリオーリョ)はもっとも下位の行政機構であるカビルドとよばれる市参議会においてのみ有力であった。行政機構の最高位に位するのが副王であり、これは国王の分身として植民地を治める上流貴族出身の高官で、官吏、僧侶(そうりょ)の任免権をもち、国王から発せられた法令の施行に関して、強力な権限と自由裁量権をもっていた。副王はメキシコ(1535)とペルー(1542)に置かれ、新大陸を二分して広い領域を直接統治したが、18世紀にはヌエバ・グラナダ(1717)とラ・プラタ(1776)の副王領が増設された。
[中川文雄]
スペイン植民地の教会組織
カトリック教会は王権と結び付いて、多くの地域で植民とスペイン化に重要な役割を占めた。植民地時代の初期には、教会のなかに、先住民の間に真のキリスト教的世界をつくろうとする動きが強くあった。先住民のことばで説教し、インディオを司祭にしようという努力も16世紀なかばまでは続けられた。しかし16世紀後半になると、そうした努力は捨てられ、王権の下で先住民をスペイン化することに伝道の重点が置かれ、教会組織は王権支配と一体化した。1501年と1508年の教皇令でローマ教皇庁はスペインの王室に、新大陸での教会の建設と維持、先住民の改宗を行う義務と引き換えに、十分の一税の徴収の代行と僧職の任命権という大幅な権限を与えたが、これはその後、植民地時代を通じて、歴代の教皇とスペイン国王の間で守られた。教会の伝道僧の地道な努力は征服者の力よりも、さらに大きく先住民社会の変容とスペイン化を促した。伝道僧は農工などの物質文化の面においても先住民の生活に大きな変化を与えた。他方、王権の庇護(ひご)下に教会への富の集中は植民地時代末期までに莫大(ばくだい)なものとなった。
[中川文雄]
スペイン植民地の経済生活
スペイン植民地の経済は、16世紀には鉱山の開発と新たな農畜産物の導入によって急速に拡大したが、17世紀には先住民人口の減少、鉱山の衰退によって停滞、縮小し、18世紀にふたたび回復拡大をみせた。16世紀なかばに南アメリカ(現在のボリビア)のポトシ、メキシコのサカテカス、グアナフアトなどの銀山が発見され、それらが1557年に完成した水銀アマルガム法の採用によって製錬が容易になり、銀産は急激に上昇し、世界の銀産の大半を占め、それはヨーロッパに運ばれて価格革命を引き起こした。同時に新大陸においては多くの鉱山都市、商業都市が生まれ、なかでも新大陸最大の都市ポトシの繁栄は世界に知れわたった。それらの都市を中心にして、また、本国が求めた貴金属生産を中心にして、植民地経済が展開し、それに刺激されて農牧業、製造業も発展した。17世紀に入ると鉱山の衰退と先住民人口の減少のために経済は停滞し、縮小に向かい、それが回復するのは18世紀になってからであった。
スペイン人は旧大陸から新たな家畜(ウシ、ウマ、ヒツジ、ブタ)や新たな作物(コムギ、米、サトウキビ)をもたらし、また、征服前は新大陸の一部でしか栽培されていなかった作物を新大陸全体に広めた。彼らは、さらに役畜の利用、鉄器の使用、井戸掘りの技術などをもたらし、それによって農牧に利用される地域は拡大した。
スペインの重商主義は、植民地の生産を規制して本国の産業の興隆を図るというよりは、通商をスペイン人商人の手に収めておくことに重点が置かれ、植民地が必要とする工業製品は、繊維、ガラス、金属、火薬などに至るまで、高級なものを除いては多くは植民地で製造された。新大陸植民地とヨーロッパとの交易は、王権の厳しい統制下に置かれ、植民地はスペイン本国とのみ交易を行い、ほかのヨーロッパ諸国との交易は許されず、貿易ルートや貿易独占港が指定され、また、特許状を得た特定商人のみが貿易に参加することができた。
[中川文雄]
大土地所有制の成立と農民の抵抗
17世紀になって鉱業が衰退するにつれて、植民者の関心は農牧業に移り、土地所有の欲望が大きく促された。王室は植民者に比較的小面積の土地譲渡しか許さず、先住民の土地所有権をむしろ保護しようとしたが、植民者はそうした方策を無視して、先住民の土地を徐々に自己の支配下に収めていき、大土地所有が生まれた。植民者が先住民村落の共有地を徐々に自己の所有下に収めていく一方では、村落にいた多数のインディオが高い租税や鉱山労働への徴発を恐れて、そうしたものから免除される私有地へ逃げ込んだ。こうして土地と人間を吸い込んで拡大したのが私有大農地ラティフンディオであった。ラティフンディオは単なる経済活動の単位ではなく、農民の全生活を支配する自己完結的な小世界であった。大土地所有者にとって土地は権威のシンボルであり、技術革新や資本の投下によって生産性を高めることをせず、もっぱら労働収奪に頼る形態が保持された。非生産的で浪費の性向が強く、労働を軽蔑(けいべつ)し貴族的趣味を有する地主階級が生まれ、彼らの考え方や心情がその後のスペイン植民地とそこから独立した国々の支配階級の価値観を構成した。
大農地や鉱山で激しい収奪を受け、あるいは先住民村落においても王室の下級官吏からの収奪に苦しんだインディオや混血の農民、黒人奴隷は、植民地時代を通じて数多くの反乱を起こした。それは白人支配者に脅威を与え、支配者側を悩ませたが、いずれも鎮圧された。インディオや黒人が行使しうるいまひとつの抵抗の方法は、イベリア文化の受容を拒否し、彼らの本来の神々を復活させる宗教儀礼や宗教運動を通じて、その内的な世界を守ることであった。
[中川文雄]
スペイン植民地の文化
スペインの文化が新大陸に移植されたが、それはイベリア文化の引き写しではなかった。旧大陸では実現していなかったものをまず新大陸において実現しようとする理想主義がそこにあった。いくつかの広場を結ぶ直交する街路の整然とした計画都市が、スペイン本国に先だって新大陸植民地に建設されたのはその一例である。物質文化、儀礼、生活習俗・言語の面で南スペインの影響が圧倒的に強かった。文学、美術などでは、エルシーリャ・イ・スーニガの叙事詩『ラ・アラウカーナ』や修道女フワナ・イネス・デ・ラ・クルスの形而上(けいじじょう)学的な詩や戯曲のような個性的なものも生まれたが、概してスペイン文化の亜流であったといえる。教育は教会の手に握られ、その対象は白人ないしはインディオ貴族の子弟に限られていた。1551年のメキシコ大学、リマのサン・マルコス大学に始まって、大学や高等教育機関は新大陸スペイン植民地で25を数え、神学、法学、医学の教育や研究がなされた。
[中川文雄]
ブラジルの植民地時代
ブラジルへのポルトガル人の植民は、スペイン人の新大陸征服に比べると、きわめて遅々としか進行しなかった。1500年ペドロ・アルバレス・カブラルによってブラジルは発見されたが、その後は染料の原料パウ・ブラジル(赤い木の意。ブラジルの名はこれに由来する)を産する程度で、東洋貿易がもたらす富にひかれたポルトガル人はブラジルを比較的無視した。しかし、ポルトガル王はブラジルがフランスから侵略されつつあることを知り、1530年にはフランスの勢力を追い払わせ、いくつかの植民地を建設させた。当時のブラジルは、スペインとポルトガルが1494年に結んだトルデシリャス条約によってほぼ西経50度以東の範囲であったが、ポルトガル国王はこれを功績ある貴族に分割して、土地の使用権、統治権を幾多の特典をつけて世襲的に与えた。スペインの軍事征服と対照的にポルトガルのブラジル植民は商業的意図を有した農業移民であった。
16世紀後半になると、ヨーロッパでの砂糖の需要が拡大し、ブラジル北東部の海岸地帯に砂糖農園が多く生まれた。砂糖農園では内陸のインディオが奴隷として使役されたが、それは農業労働に質量ともに不十分で、労働力を補うため多数の黒人奴隷がアフリカから移入された。この砂糖農園では、白人農園主を頭に黒人や混血の奴隷がそれに従う家父長的な雰囲気のなかで、白人と黒人の混血が進行し、人種偏見の比較的少ない社会が生まれた。地縁で結び付いた村落共同体よりも、家族や拡大家族のつながりを重視する人間関係の伝統が生まれ、それは、その後のブラジル全体での社会のあり方に大きな影響を与えた。
一方、ブラジル南部のサン・パウロでは、これという富源もなく、住民は金、銀の探索から、やがて奥地の先住民を奴隷として狩り集めることを生業とするようになった。バンデイラとよばれるこれらの奴隷狩りの冒険者は、隊伍(たいご)を組んで奥地を駆け回り、その足跡は遠くアマゾン地方に及んだ。彼らの探検によって、スペイン人植民者が17世紀以後顧みなかった南アメリカ中央部の森林・サバナ地帯が、事実上ポルトガルの勢力範囲に入り、ポルトガル領土はトルデシリャス条約で定められたよりもはるか西方に押し広げられた。1750年のマドリード条約、1777年のサン・イルデフォンソ条約によって、今日のブラジルの領土の大きさがほぼ決定された。
文化面では、植民地時代のブラジルはスペイン植民地に比べて未発達で、植民地に大学はつくられず、印刷所もなく、高等教育はポルトガル本国で行われた。
[中川文雄]
18世紀改革・19世紀独立革命・混乱期
18世紀の国際環境と軍人の台頭
1700年スペインのハプスブルク家が断絶し、フランス王家と血縁関係のブルボン王朝が始まった。これによってスペインとフランスの関係は平和的になったが、反面、当時最大の海洋国として勃興(ぼっこう)しつつあったイギリスと敵対関係に入り、植民地においてイギリス海軍の侵略を盛んに受けることになった。植民地防衛のために軍制改革の必要性が主張され、各地に民兵の制度が設けられた。植民地における軍人の地位と権威が高められ、軍人は特殊法廷などの特権を得るようになり、この特権にひかれて植民地生まれの白人の子弟は民兵軍の士官に進んで加わった。これは、武力によって植民地が解放される軍事的基盤を養うことになったが、同時にそれは、独立後の共和国が軍人首領(カウディーリョ)に支配される運命へとつながった。
[中川文雄]
経済繁栄と自由貿易への動き
18世紀も1730年代のペスト流行が過ぎると、植民地の人口は着実に増加し、銀産は回復し、商用作物の生産が拡大し、工業面でも繊維、冶金(やきん)、陶芸などが発展した。こうした経済繁栄とイギリスからの市場拡大の要求の前に、啓蒙(けいもう)的な君主カルロス3世は1765年、従来の特許商人の独占による特定ルートの貿易を廃し、スペイン人の一般商人による植民地と本国との自由な貿易と植民地間の貿易を許すことにした。この結果、植民地の都市の経済活動はさらに活発となり、商人と市民階級、そして少数だが中産階級的自由職業人が台頭した。彼らはのちにいっそうの貿易の自由を求めて独立を支持するようになった。カルロス3世による貿易の自由化は主としてスペイン帝国内における自由化であり、外国、とくに産業革命に入ろうとしていたイギリスの商人や産業資本家は、この程度の改革には満足しなかった。彼らはスペイン植民地が自由な市場として開放されることを望み、1810年代に独立運動が勃発すると、それを支援する立場をとった。
[中川文雄]
18世紀文化と独立思想
ブルボン王朝の啓蒙的な君主は、植民地の行政を中央集権化し、科学的研究を奨励し、人口状態や経済状態の調査を行わしめた。啓蒙君主による上からの改革と並行して、フランスの啓蒙思想は18世紀後半から植民地の知識人の間に浸透し、権威と伝統に対する批判の目を養い、絶対君主の権力に抗して市民的社会をつくる主張を植民地のなかに生んだ。さらにフランス革命は、フランス植民地のイスパニョーラ島西半分のサン・ドマングで黒人奴隷の反乱を誘発し、優れた軍事指導者トゥーサン・ルーベルチュールに率いられた奴隷軍は、フランス軍やイギリス軍の干渉を退けて、1804年独立を達成しハイチ共和国が誕生した。アメリカ独立革命、フランス革命という二つの大きな市民革命の衝撃を受けても、なお、スペイン植民地では、市民社会をつくろうとする主張が独立ということばに結び付くことはまれであった。ラテンアメリカの独立は、ナポレオンのフランス軍によるイベリア半島の占領によって、ようやく実現の契機を与えられた。
[中川文雄]
独立の過程とその性格
1808年、スペイン国王がナポレオンによってとらわれの身とされ、植民地の各地で権力の真空状態が生まれた。従来、植民地行政にほとんど参与の機会を与えられていなかったクリオーリョ(植民地生まれの白人)は、この機に乗じて、国王フェルナンド7世への忠誠を誓いつつも、現地の副王の権威を否定し、自治の表明を行った。1809年から1811年にかけて、一部のクリオーリョはさらに進んで独立宣言を行った。1814年ナポレオン戦争が終わってフェルナンド7世が復位したが、植民地人の期待に反して、彼は本国優位の絶対主義体制を復活させようとした。そのため植民地人の自治宣言はスペインからの独立運動へと転換し、武力抗争に発展した。1824年末までに、スペインの支配がきわめて強固であったキューバとプエルト・リコを除いた全新大陸スペイン植民地で独立派が勝利を収めたが、南アメリカの解放と中央アメリカ、メキシコの独立とは、同じ独立とはいってもかなり異なった性格のものであった。
南アメリカの解放は、ベネズエラとブエノス・アイレスを拠点とし、シモン・ボリーバルとホセ・デ・サン・マルティンJosé de San Martín(1778―1850)を指導者とする貴族的エリートの自由主義者がイギリスの軍事的・経済的援助のもとにスペイン王党軍と戦い、これを打ち破ることによって達成された。一方、メキシコと中央アメリカにおいては、クリオーリョの間に、既成秩序の下で各種の特権を享受していた保守派が強力であった。メキシコでは、独立を希望し、しかも民衆的な基盤にたって社会改革を進めようとする運動が武力抗争に発展したが、クリオーリョの多くはスペイン官憲と協力してこの抗争を鎮圧した。1820年、スペイン本国で自由主義的な憲法が採択されると、それが植民地に波及することを恐れて、保守派が独立に踏み切るという過程がメキシコと中央アメリカではみられた。ここでは、独立とは植民地支配下での特権をめぐるスペイン官憲と植民地生まれの白人の争いという性格を如実に示していた。独立戦争のなかからムラート(白人と黒人の混血)やメスティソ(白人とインディオの混血)が将校として台頭し、そのなかからのちに大統領となる者も幾人かを数えた。しかし、南アメリカでも、中央アメリカ、メキシコでも、インディオ、黒人、混血の大多数は独立戦争の兵士として徴発されたが、独立によって新しい身分を得ることはまれであった。
スペイン植民地が多大の流血と破壊を経て独立を達成したのと対照的に、ブラジルは平和裏に独立を達成した。1807年、ナポレオン軍の侵入を逃れてポルトガル王室はブラジルに移り、以後、ブラジルは繁栄し、文化的にも興隆し、もはやポルトガルの支配を受けたくないとの感情がブラジル住民の間に生まれた。1822年、ポルトガル本国の議会が、在ブラジルの摂政(せっしょう)である王子ドン・ペドロDom Pedro Ⅰ(1798―1834)を本国に召喚しようとしたことを契機に、王子自らが指導権をとりブラジル帝国として独立が達成された。
[中川文雄]
反動と無政府の時代(1825~1850)
王権がスペイン植民地から追放されると、そのあとに待っていたのは政治的混乱とカウディーリョとよばれる軍人首領による支配であった。非妥協的で強力な自己主張を行うスペイン系アメリカ諸国の支配階級は、彼らの間で文民政治のルールを打ち立てることができず、また旧植民地は1825年から1830年までの間に数多くの国に分割された。軍人首領たちの経済思想は保護主義的であり、教会の特権を保持しようとするのが一般的であった。一方、自由主義的知識人はスペイン的伝統を否定し、イギリス、アメリカ、フランスに範を求めた近代国家の建設を求めて論陣を張り、政治活動に加わったが、この時代にその努力が実現をみることは少なかった。
独立後も帝政の下にあったブラジルが、国土を分裂させることもなく、また、比較的安定した政権の下に秩序を保ったのは、スペイン系諸国と対照的であった。
[中川文雄]
独立後の国際関係
1823年、スペインのフェルナンド7世が旧秩序の復興のため、フランス、ロシアなどの神聖同盟諸国に、独立したばかりの旧植民地に武力干渉するよう要求した。しかし、当時の最大の海軍国イギリスは独立によって市場が開放されることを望み、この再征服の意図の前に立ちふさがり、ラテンアメリカの独立の実質的な守護者となった。一方、アメリカ合衆国はその南にある新生の諸国に道義的支援を与えた。1823年12月にモンロー宣言を行い、アメリカ大陸がこれ以上ヨーロッパ諸国の植民地化の対象になりえないという原則を世界に向かって公表した。実際には、1860年代に至るまでアメリカにはヨーロッパ列強のラテンアメリカへの干渉を阻止する力はなく、イギリスは1830年代に新たな領有を広げ、フランス、スペインも短期間であったが幾度か干渉を行った。アメリカは、モンロー宣言以前から新大陸に残存するスペイン植民地に対して領土的拡大を意図していたが、それは、やがて新生の隣国に向けられるに至った。メキシコに対して1836年にテキサスを独立させ、のちにそれを併合し、1848年にはメキシコ戦争に勝利して、当時のメキシコ国土の半分を割譲させ、大西洋から太平洋にまで広がる文字どおりの大陸国家となった。また、両洋の結節地点である中央アメリカ地峡への進出が、1848年以後アメリカの政府と民間人によって計画されるようになった。
アメリカのこうした進出に対して、ラテンアメリカ諸国では一部の親ヨーロッパ的・保守的知識人の間で強い批判と警戒心が生まれた。しかし、当時のラテンアメリカ諸国では相互の連帯感が弱く、しかも独立を脅かす主たる敵はアメリカよりもヨーロッパ諸国とみなされた。さらに自由主義者はアメリカを自らが学ぶべきモデルとして崇拝の念を抱いていたこともあって、反米感情は一般に弱く、それが強まるのは20世紀に入ってからであった。
若いラテンアメリカの諸国がその独立を保持するため、結束して外部の勢力にあたることは、南アメリカ北部の解放者ボリーバルによって提唱されていた。彼は1826年、パナマ市にスペイン系諸国の代表者会議を開き、共同防衛同盟を結成しようとしたが、南アメリカ南部諸国の参加を得られず、その構想は実現しなかった。その後、19世紀中葉に同様の会議が三度にわたって開かれたが、連帯感の弱さと相互の利害対立から失敗に終わった。
[中川文雄]
物質的進歩と西欧化の時代
外資と近代技術の導入
独立戦争による疲弊、それに続く独立後の政治的混乱によって、ラテンアメリカ諸国の経済活動は19世紀なかば過ぎまで停滞した。19世紀後半になってヨーロッパでの産業革命の進行と消費生活の変化に伴って、ラテンアメリカはその新たな食糧や原料供給地となることが期待された。1870年以後、ヨーロッパ諸国、とくにイギリスはラテンアメリカの鉄道、港湾の開発に投融資し、新しい鉱山や農場を開拓した。19世紀末になるとアメリカがまずカリブ海地域に対し、ついで第一次世界大戦後は南アメリカに対して経済権益を求めた。
ラテンアメリカは欧米のための一次産品の生産に特化したが、それは第一次世界大戦終了時までは、ときおりくる小さな不景気を除いてはラテンアメリカ経済を困難に陥れることはなかった。海外市場でのこれら産品への需要の伸びが概して上昇の一途をたどったからである。繁栄がもたらされ、同時に、欧米の資本、近代技術、文化によって、ラテンアメリカの経済、社会、文化が欧米への従属と模倣という方向に向かって大きな変化を遂げた。
[中川文雄]
移民の到来
新しい技術の導入と国際市場の拡大によって、それまで無視され、あるいは不可能であった資源の開発が、ラテンアメリカのいくつかの地域で急速に進行した。そうした地域に住民の労働力を動員する新しい形式が生み出されたが、質的にも量的にもとくに高い労働力を必要とした地域には、おりから商品経済の浸透によって農民が追い立てられていた南欧、中東欧からの多数の移民が入った。そのため、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部などには従来のイベリア的、閉鎖的な階層社会とは違った開放的、競争的な社会が生まれた。
[中川文雄]
政治の安定化と秩序と進歩の哲学
19世紀後半の最初の30年間、ラテンアメリカ諸国の政治はまだ不安定であったが、1850年以前の無秩序の状態から、法と秩序をより尊重する型の軍人や文民の支配へと移行した。自由主義者の主張が保守主義者を抑え、植民地時代から引き継がれた教会や軍部の特権が廃止され、教育を教会から公権力の手に移し、教会資産を解体することがいくつかの国で行われた。1880年以後になると都市で商工業者階級が台頭し、彼らはイギリス・フランス資本のもとにある大地主階級とともに西欧的な文化を積極的に摂取し、秩序と進歩の哲学を信奉し、政治的には比較的安定した時期が、19世紀末から1920年代までのラテンアメリカの多くの国で実現した。
[中川文雄]
アメリカの進出とナショナリズム
19世紀末、キューバへのアメリカの経済権益は巨大なものとなり、1898年キューバで独立運動が内戦化するや、アメリカはこれに干渉してスペインに宣戦して勝利を収め、キューバ、プエルト・リコをそれぞれ独立国、属領として勢力圏に加えた。さらに1903年にはパナマをコロンビアから独立させ、ついで1910年代に入るとカリブ海、中央アメリカの小国やメキシコの内政に干渉した。このもっとも典型的なヤンキー帝国主義は1930年代には善隣外交によって改められるが、その記憶はラテンアメリカ諸国の脳裏に深く刻まれ、強い反米感情を植え付けるに至った。
[中川文雄]
第一次世界大戦とラテンアメリカ
アメリカへの不信を反映して、ラテンアメリカ諸国は第一次世界大戦に際し、わずか8か国が対独宣戦布告を行い、残る12か国のうち、5か国が対独断交を行っただけで、アルゼンチン、チリ、メキシコなど7か国は中立を維持した。第一次大戦の結果としてのヨーロッパの没落とアメリカのいっそうの隆盛は、ヨーロッパを精神的故郷とみなしていたラテンアメリカの知識人に大きな衝撃を与え、そのなかから新たな国民文化を志向した文化的ナショナリズムが生まれた。
[中川文雄]
現代
現代の起点
メキシコのように、1910年代に早くも社会革命の糸口が切られ、その革命のもたらした変化が今日の制度の母胎になっている国もあるが、一般的には1920年代末までのラテンアメリカ諸国は、19世紀後半以来の近代技術、制度の導入と自由主義哲学に導かれて、外国資本と外国移民による資源の開発と西欧的な文化を志向していた。こうした動向は1930年代になって急に消え去ったわけではない。しかし、1930年代以後のラテンアメリカには、こうした動向と対立するいま一つの動向、つまり、国民的統合と自立を目ざすとともに、民衆的基盤での福利の増大を実現しようとするナショナリズムを掲げる広義の革命勢力が台頭した。そのきっかけを与えたのは世界大恐慌であった。世界大恐慌によって多くのラテンアメリカ諸国が輸出産業部門、国家財政の面で痛烈な衝撃を受け、外国依存のモノカルチュア経済およびそれを無批判に受け入れてきた過去の考え方に批判の目が向けられた。従来は少数の文人の所有物でしかなかったナショナリズム――ラテン民族の精神的優越を誇る形の汎(はん)ラテン的ナショナリズムないしはユートピア的なインディオ至上主義にかわって、あるいはそれを踏み台として、物質的基盤に根ざした国家を単位とするナショナリズムが生まれ、それはより広い国民層に受け入れられた。
1930年代までに多くの国で都市、鉱山などに無視できない数の労働者階級と中産階級が生まれ、それは従来の外国資本と直結した寡頭政治に満足しえない政治勢力を形づくった。こうした支持層を背後にしてナショナリズムを旗印にたてたのが、ブラジルのバルガス政権、メキシコのカルデナス政権、すこし遅れて1940年代アルゼンチンのペロン政権などの、民衆政治家による強力で国家主義的な政権であった。こうしたナショナリズムの系列は、1930年代のメキシコ、ボリビアでの石油国有化、1940年代のアルゼンチンの鉄道国有化など、外資支配の産業の国有化を促し、一方、工業化の促進による経済的自立を求めた。
[中川文雄]
第二次世界大戦と戦後の秩序
1930年代のアメリカの善隣政策により、ラテンアメリカとアメリカの関係は改善され、第二次世界大戦では最終的にはラテンアメリカのすべての国が枢軸国に対して宣戦を布告した。ラテンアメリカ諸国は民主主義諸国の資源庫として、その産物を低価格で連合国側に供給することを余儀なくされたが、それにしても、戦争の膨大な需要と供給の途絶はラテンアメリカ諸国の経済発展、とくに工業化を刺激した。
第二次世界大戦後、1950年代末までのラテンアメリカは、伝統的なクーデターが政治の安定を乱したが、既存秩序をまっこうから否定するような革命や運動はなく、アメリカの圧倒的な支配下に置かれた。グアテマラ、ボリビア、ベネズエラで革命政権が生まれたが、アメリカはそれらを自分の好む方向へと誘導し、あるいは力でそれを殲滅(せんめつ)した。しかし、一次産品価格の低落と人口増加率の急激な高まりから、生活水準が停滞し、それに伴う不満が鬱積(うっせき)した。
[中川文雄]
革命と軍部台頭の1960年代、1970年代
武力抗争の末、1959年に政権奪取したキューバ革命は、こうした鬱積した問題への解決の一つであるとともに、アメリカによる西半球支配へのまっこうからの挑戦となり、その結果は、ラテンアメリカ諸国の内外での政治抗争を激化させた。多くの国で、キューバ革命の進行に鼓舞され、また、キューバからの支援を受けた左翼革命勢力が農村と都市でのゲリラ戦を試みたが、それらはアメリカの軍事援助で強化された各国の軍に鎮圧され、また、米ソ間の勢力圏の暗黙の了解のもと、武力革命路線は後退した。ただし、中米地域においては、少数の家族による寡頭支配体制を打破すべく、革命勢力による武力抗争が繰り広げられ、エルサルバドルは内戦に入り、一方、ニカラグアでは、1979年、ソモサ独裁政権の打倒に成功したサンディニスタ政権の誕生となるが、ここでは、アメリカに支援された反革命勢力コントラとの抗争が内戦と化し、これらの内戦の解決は、ラテンアメリカ全域で民主化志向が強まり、また、冷戦の終結により代理戦争の意味がなくなる1990年代初頭にまで引き延ばされた。
1960年代、1970年代、左翼革命勢力の台頭によって危機意識を強めた軍部は、自らの政治的使命を自覚し、政治への介入を強めた。70年代なかばまでに、メキシコ、コスタリカ、カリブ海旧イギリス領諸国らを除いて、ラテンアメリカのほとんどの国が軍事政権支配下に置かれた。そのなかには、ブラジル、ペルー、チリでのように、軍部が長期的、組織的な支配を行い、テクノクラートがそれに協力し、経済、社会の構造に大きな変化が生ずることも起きた。
[中川文雄]
経済危機と民主化の1980年代
1970年代の世界を揺るがした二度の石油危機では、資源豊かなラテンアメリカ諸国は相対的に有利な立場にあった。その豊かな資源を担保とし、また、抑圧的な政治の下での安定した秩序を売りものにして、ラテンアメリカ諸国は、大規模な経済開発のための資金を先進国の金融機関から借り入れた。しかし、1980年代に入って世界的な高金利時代が始まり、かつ、一次産品価格の低迷から、債務返済が不可能となった。1982年、メキシコが対外債務の利子支払い不能に陥ると、ラテンアメリカ諸国から資金が急激に海外に流出し、各国が金融危機に直面した。企業倒産、失業、ストライキが顕著となり、経済はマイナス成長に落ち込み、それでいながらハイパー・インフレーション(超インフレ)が進行し、国民生活は困窮した。1980年代はラテンアメリカ諸国にとって、経済が著しい後退を示した10年間として、「失われた十年」とよばれた。
経済運営に失敗した軍事政権は政治運営にも自信をなくし、政権を文民に移譲することが多くの国で起きた。一方、1980年代後半になると、世界的な民主化の動きに促されて、文民支配ではあっても、それまで権威主義的な一党による支配、あるいは少数の家族による独裁を続けてきた国々で、複数政党化と選挙結果の尊重が顕著となった。その意味で1980年代はラテンアメリカにとって民主化の10年間でもあり、その流れは1990年代に入って、さらに強まった。
[中川文雄]
ネオ・リベラリズム下の1990年代と残された課題
1980年代に進行した経済破綻(はたん)に対応するため、その後に各国で新たに誕生した政権は、アメリカと国際金融機関との協調による解決を図るべく、従来の保護主義的で国家の介入度の大きい経済方式から、ネオ・リベラリズム(新自由主義)に沿った経済方式に転換した。それは、価格や貿易の自由化、国営企業の民営化、補助金の打ち切り、余剰人員の大幅な整理、などを伴う、経済の安定化と市場化に向けての大きな転換であった。
そうした転換の結果、ハイパー・インフレーションは抑えられ、経済危機からの脱却にある種の見通しが立つようになった。チリやブラジルのように物価の安定と経済成長の双方に成功した例もみられ、1990年代末でのラテンアメリカ経済の将来への見通しは、1980年代に比べて相当に明るくなった。
マクロ経済面での安定は得られたものの、各国に存在する大きな所得格差の是正はなされず、市場原理の強化の下で、富裕者への富の集中と膨大な貧困層との対比は、むしろ強められた。一方、ラテンアメリカ諸国では、1960年代以来の40年間で、広範な領域で大きな社会変化が起きた。都市化、工業化、運輸・通信網の発達、モータリゼーション、テレビの普及、それらに伴った女性の社会参加の高まり、宗教戒律の軽視、性モラルの自由化、既成政党の権威失墜、暴力犯罪の多発などが進行した。それは、一面では居住環境の悪化、生活の質の低下と不安の増大を強めたが、他方では、従来よりも、もっと平等主義的で、住民の権利が主張しうる社会への志向が強まったといえる。
[中川文雄]
民族・文化・社会
民族
一般に民族は、「生活様式やわれわれ意識を共有する集団」と定義される。この定義に従えば、現代ラテンアメリカは、いくつかの大きな民族単位に分類できる。また無数の民族単位にも分かれる。このような錯綜(さくそう)がみられるのは、イベリア=キリスト教文化という文化的大伝統のもとに各地域で各集団が独自の小伝統を発達させてきたラテンアメリカでは、人々がレベルの異なるいくつかの民族集団に同時に所属し、時と場所により、いずれかを選択することがありうるからである。そこに観察される多民族性・多重民族意識は、人種混交、文化状況、歴史過程、地域性のすべてを反映している。それだけに、ラテンアメリカには通常の民族概念を当てはめにくい。
15世紀に始まる新興民族国家スペインの自民族中心主義は、征服したインディオindio(先住民)社会とその文化に対するスペイン人の優越意識を植民地体制のなかに制度化した。これは、その後のスペイン人と非スペイン人の関係を大きく規定し、ひいては今日のスペイン系ラテンアメリカ諸国の精神風土を方向づけることにもなった。たとえば、スペイン人とインディオとの混血の度合いによるカースト的な身分階層制をはじめ、スペイン系やメスティソmestizo(混血)系の支配する植民地主義体制に対しインディオが各時代に各地で表明した不満にはすべて「反逆(レベリオン)」という全面的否定のレッテルが貼(は)られた。また、インディオ社会の進歩とはスペイン系文化への同化にほかならないと広く考えられてきた。これらは、今日のスペイン系ラテンアメリカ社会を特徴づける権威主義的な精神風土の根源が、15世紀末以後、アメリカ大陸に移植されたスペイン民族中心主義にあったことを示している。
そのようななかで、インディオは近代国家の一員として、ますます外部社会に関与せざるをえなくなっており、スペイン語を習得し、西欧的生活習慣を身につけ、農業を離れて教師、仲買小売業者、政府機関職員などの職を得、エリート化する者も増えている。国によって事情は異なるが、そのような場合、彼らがアイデンティティの問題を十分に解決しているとはいえない。スペイン民族主義および近代主義が強い文化風土のなかで、自己の民族所属を操作し、国民社会での社会的地位の獲得に努力するインディオの場合もある。
ブラジル地方征服当時、すでに黄金時代を過ぎていたポルトガルは、アメリカ大陸の植民地経営にスペインほどの民族主義を持ち込まなかった。そのために、ブラジルでは血統や文化的背景による権威主義や階層制度は、スペイン領植民地に比べ弱かったといわれる。
先住民統合化政策などの実行上、為政者の側が多民族主義を打ち出し、民族所属意識の再編成を図ることもある。また、ラテンアメリカという概念は、アングロ・アメリカという概念との対比において政治的に出現することも多い。実際、ラテンアメリカをてこに共同意識が形成されるのは、本来はアングロ・アメリカとかならずしも一致しないのだが、アメリカ合衆国に対抗し、あるいは先進国一般に対して団結をみせる場合であることが少なくない。
このような場合に形成される「ラテンアメリカ民族意識」はかなり人工的、二次的、戦略的なものである。文学、芸術などの分野でもラテンアメリカは一様であるかのような錯覚に陥るが、実際には国境の壁は厚い。また、一国内をみても、アルゼンチン文化、メキシコ文化、ブラジル文化などと一括してとらえることはできないほどの多様性を含んでいる。
そのようなラテンアメリカに暮らす人々にとり、「民族と文化」とは、民族間、文化間の関係として意識化されることが多い。ラテンアメリカの国々では、独立以後、多民族国家を統合するイデオロギーとしての国民文化づくりが唱えられ、その一方でわれわれラテンアメリカ人とはだれなのかという自問も繰り返されてきた。その背景には、諸文化と諸民族が混在するラテンアメリカ人の大多数が、ヨーロッパ人でもインディオでもない新しいアイデンティティの確立を模索しているという状況がある。
[落合一泰]
文化
ラテンアメリカを文化的な広がりとしてみた場合、その文化は、地理学的に定義される領域を越え、アメリカ合衆国南西部のテキサス州、ニュー・メキシコ州、アリゾナ州などでも色濃くみられる。また、カリフォルニア州やフロリダ州にもメキシコ系やキューバ系住民が増加している。ニューヨーク市にはプエルト・リコ系住民が多い。アメリカ合衆国では、ヒスパニック系と総称されるこのようなラテンアメリカ系文化とその担い手たちが社会的、文化的に一大勢力に育ちつつある。また、イギリスのロンドンには、主として旧植民地のジャマイカなどからの移民も少なくない。
イベリア=キリスト教文化という文化的大伝統が存在するラテンアメリカだが、それを基層文化で分類すれば、その構成人間集団は、(1)インディオ、(2)メスティソ、(3)アフロ・アメリカ系、(4)ヨーロッパ系、(5)移民の5集団に大きく分けられる。これらの相違は、渡来した文化の違いのみならず、各地、各時代で受け入れ側のアメリカ大陸の文化社会環境に差があったことも反映している。基層文化を構成する集団の地域的分布や特徴は以下のとおりである。
(1)インディオ メキシコ中部・南部、グアテマラ、エクアドル、ペルー、ボリビアなどのおもに高地に閉鎖的な共同体を形成する農民、およびブラジルとコロンビアのアマゾン川流域、ベネズエラのオリノコ川流域、中央アメリカのカリブ海沿岸部などに居住するインディオ諸集団である。
ここで明らかにしておくべきことは、インディオという名称は、非インディオが南北アメリカ大陸の全先住民を包括する語として用いる集団名称だが、そうよばれる人々自身には、そのような実体がないという点である。たとえば現代メキシコのインディオ社会では、インディオというスペイン語はだれでも知っているが、このことばは上記の意味では具体的に了解されていない。インディオにとり「われわれ」とは、一般に村単位のメンバー意識である。同じ土着言語を用いても、村々の間には民族集団としての共同意識が存在しないことが多い。
(2)メスティソ 本来メスティソとは、生物学的混血を意味したが、現在では、社会的・文化的混血も含意する。メスティソたちは、今日のラテンアメリカ文化・社会の中核を形成している。
(3)アフロ・アメリカ系 ブラジル北東部、フランス領ギアナ、スリナム、ガイアナ、カリブ海諸国および中央アメリカのカリブ海沿岸部などに居住する。植民地時代にサトウキビ、ワタ、タバコなどのプランテーションに導入されたアフリカ人奴隷の子孫で、アフリカ文化を色濃く保持している。ヨルバ系アフリカ人の渡来したカリブ海地方とバントゥー系アフリカ人が導入されたブラジルでは、文化的な相違が少なくない。
(4)ヨーロッパ系 住民はおもにチリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部に居住する。征服直後に入植したスペイン人やポルトガル人と異なり、19世紀にヨーロッパから渡来した移民の子孫が主で、イタリア、スペイン、ドイツ、イギリス、旧ユーゴスラビアの出身者が多く、ユダヤ系も少なくない。ラテンアメリカに同化する一方、出身国単位の組織を維持発展させ、父祖の地への帰属意識を保持している場合もある。ヨーロッパ系住民が社会経済的に上層階級を占める場合が多い。
(5)移民 少数の難民、クェーカー教徒のような宗教団体、労働者として渡来し定着した中国人、農業移民として入植し、現在は各方面で活躍するようになった日本人、商人として活躍するアラブ系移民などで、集団としての民族文化を保持する場合も少なくない。
以上の5タイプのうち、人口のうえで大多数を占めるメスティソ社会には、思考・行動様式において、西欧文化と土着文化との融合がみられる。たとえば、メスティソ文化の一つの精神的基盤として、フォーク・カトリシズムとよばれる、ローマ・カトリック教に土着的・民俗的要素が融合した宗教原理と行動があげられる。その最大の特徴は、聖人信仰の卓越だが、とくにグアダルーペの聖母に代表されるマリア信仰の卓越は、ヨーロッパ、アメリカ大陸の古い地母神信仰に基づくものと考えられる。
[落合一泰]
社会
メスティソ社会では、とくに一対一の人間関係が重視される。制度を介しての間接的関係より、直接的、個人的な人間関係が重視される。これは、ラテンアメリカの人間関係を特徴づける縁故主義の背景をなしている。これはまた、間接民主制への不信の源泉でもあり、ラテンアメリカの政体が一般に不安定にならざるをえない遠因ともなっている。ラテンアメリカには、そのような人間関係を統合する存在として、カリスマ性をもつ独裁者が出現しやすい。
ラテンアメリカに特徴的な男女関係として、マチスモmachismoとよばれる男性優越主義がしばしば指摘される。雄としての男性の力の誇示と名誉の保持がその中心概念である。これは、スペインの名誉観に起源をもつものと考えられる。女性にとっては純潔の美徳を守ることが最大の名誉であり、一方、男性にとっては、人生において、獲得していく名誉、とくに女性に対する優越が名誉の基盤である。この両性の名誉は根本的に矛盾するものであり、マチスモは、その矛盾の心理的・社会的出現形態だといえる。また、マチスモは、すべてのラテンアメリカ人男性の心理と行動を規制しているというより、彼らの生き方の一つのオプションであるとみなす立場もある。
ラテンアメリカでは、数のうえでは人口の3分の2を占めるインディオやメスティソの農民が主流だが、白人を中心とした少数の上流階級が都会に存在し、19世紀にスペイン植民地体制から脱却してのちも国内植民地主義体制が維持されている場合が多い。近年は、都市部を中心に中産階級の進出も顕著である。一方、大都市へインディオ、メスティソ農民が大量に流入し、重大な都市問題に発展している。メキシコ市やリマ市などでは、それぞれベシンダーvecindad、バリアーダbarriadaとよばれるスラムの形成がみられる。
このようなスラム社会では、アメリカの人類学者ルイスO. Lewisが「貧困の文化」とよんだ次のような特徴をもつ文化がみられることが多い。それは、(1)有効な社会参加の不足、(2)拡大家族以上の社会組織の欠如、(3)不安定な幼児期・思春期・青年期、(4)男性による女性の性的支配、(5)男性・父親の責任行動の不足と女性・母親中心主義、(6)兄弟・姉妹間の緊張関係、(7)運命主義などである。
[落合一泰]
『田中耕太郎著『ラテン・アメリカ史概説』上下(1949・岩波書店)』▽『ラテン・アメリカ協会編『ラテン・アメリカの歴史』(1964・中央公論社)』▽『中川文雄他著『ラテンアメリカ現代史Ⅰ Ⅱ』(1978、1984・山川出版社)』▽『増田義郎著『世界の歴史7 インディオ文明の興亡』(1977・講談社)』▽『加茂雄三著『世界の歴史23 ラテンアメリカの独立』(1978・講談社)』▽『国本伊代著『概説ラテンアメリカ史』(1992・新評論)』▽『国本伊代・中川文雄編『ラテンアメリカ研究への招待』(1997・新評論)』
百科事典マイペディア 「ラテンアメリカ」の意味・わかりやすい解説
ラテン・アメリカ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「ラテンアメリカ」の解説
ラテンアメリカ
Latin America[英],América Latina[スペイン]
アメリカ大陸で,スペイン系,ポルトガル系の言語,文化が卓越したメキシコ以南の地方の総称。アングロアメリカに対する。スペインでは好んでイスパノアメリカと呼ばれる。最近では,非ラテン的文化色の強いカリブ地域(西インド諸島)を別に扱って,「ラテンアメリカとカリブ」という表現も普及しつつある。わが国でいう中南米にあたる。ラテンアメリカの歴史は三つの段階に分けられる。第一は,外部からの影響なしに,アメリカ大陸固有の住民がメソアメリカ文明,アンデス文明などを達成した時代。第二は,1492年のコロンブスの航海以後,19世紀初めまでのスペイン,ポルトガル植民地時代。第三は独立後の近現代である。植民地時代には,各地域とも王室の政治的・経済的統制のもとに置かれて,銀山の開発や砂糖の生産などを行った。労働力不足を補うために多数のアフリカ人が奴隷として導入された。18世紀以後各地で産業が興り,クリオーリョたちの間に自由貿易を望む声が起こったとき,世界市場の開拓に積極的だったイギリスの圧力のもとに,メキシコ,中米の独立および南アメリカの独立が達成された。1889年まで帝政を守ったブラジルを除いて各国は共和制をとったが,大土地所有制やカウディリョの闘争がはびこって政治は安定しなかった。経済的にはイギリス資本が中南米を支配した。19世紀末からアメリカ合衆国の力が強まり,アメリカ‐スペイン戦争によって最後のスペイン植民地として残っていたキューバが独立し,プエルトリコはアメリカ領となった。第一次世界大戦後イギリスの力が失墜してアメリカ合衆国の支配力が決定的となった。各国で,大衆社会の出現とともに社会運動も激化し,メキシコ革命,ボリビア革命,グアテマラ革命,キューバ革命などの激動があいついだ。ポピュリズムの政治が30年代から盛んになったが,安定した民主主義や経済社会の発展はまだ未来の問題である。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ラテンアメリカ」の意味・わかりやすい解説
ラテンアメリカ
Latin America
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のラテンアメリカの言及
【アメリカ】より
…一般にグアテマラからパナマまでを中央アメリカCentral America,中央アメリカとメキシコとカリブ海諸島とを中部アメリカMiddle Americaと呼ぶこともある。また,文化史的観点から,アングロ・サクソン民族の文化的伝統が強いアメリカ合衆国以北のアングロ・アメリカと,スペイン,ポルトガルのそれが強いメキシコ以南のラテン・アメリカとに区分することもある。
【地形】
パナマ地峡で結ばれた北アメリカ・南アメリカ大陸は,太平洋側に新期造山帯のコルディレラ山系,大西洋側に古い地塊,中央部に構造平野的な低地が配列しており,地形の概要は南北ほぼ類似している。…
※「ラテンアメリカ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...