翻訳|solar system
精選版 日本国語大辞典 「太陽系」の意味・読み・例文・類語
たいよう‐けいタイヤウ‥【太陽系】
- 〘 名詞 〙 銀河系に属し、太陽を中心に運行する天体の集団。水・金・地球・火・木・土・天王・海王の八惑星と冥王星など五つの準惑星、多数の衛星、非常に多数の小惑星のほかに彗星、流星、微粒子などを含み、大部分は太陽を焦点として、ほぼ同一平面上を公転する。太陽界。
- [初出の実例]「此星は〈略〉又我大陽系に連合するものなり」(出典:改正増補物理階梯(1876)〈片山淳吉〉下)
改訂新版 世界大百科事典 「太陽系」の意味・わかりやすい解説
太陽系 (たいようけい)
solar system
一つの恒星,太陽を中心とする多数の小天体の集団を太陽系という。太陽系を構成する小天体は,大きさと運動の違いによって惑星,衛星,小惑星,すい星などの種類に分けられる。太陽系の諸天体は万有引力によって相互に結びつき,整然とした力学系を構成している。
太陽系の主要な構成員は(太陽以外では)惑星と呼ばれる天体で,太陽に近いほうから水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星の9個があって太陽を公転している(図1)。地球より内側にある水星と金星とを内惑星と呼び,地球の外側の火星,木星,……,冥王星を外惑星と呼ぶ。また水星から火星までを地球型惑星,木星から海王星までを木星型惑星と呼ぶ。冥王星はどちらにも属さない。地球型惑星と木星型惑星とを比べると,前者は小さいが平均密度が大きく,後者は大きいが平均密度は小さい。冥王星は大きさでは地球型に属するが平均密度では木星型に属する。
水星と金星を例外として惑星は1個あるいは複数個の小天体を伴っている。これらの小天体はそれぞれの惑星の衛星と呼ばれ,母惑星を公転している。衛星はその母惑星に比べると小さいが,木星や土星の衛星の中には水星とほとんど同じかもっと大きな衛星が3個もある。地球の唯一の衛星,月(太陰)も衛星としては大きいほうである。1984年までに約40個の衛星が発見されているが,木星や土星には軌道の未確定な微小衛星がなおいくつも存在している。
微小衛星といえば,きわめて微小な衛星が母惑星のすぐ近くに無数に群がって環状に整然とした運動をしている。土星の環は昔からよく知られていて,どうして土星だけが環をもつのかが不思議であったが,1977年に天王星に環が発見され,次いで,79年にボエジャー1号,2号が木星にも環を発見,確認したので事情は一変した。もっとも環を上記のように考えれば多数の衛星をもつ木星,土星,天王星に環があるのは当然ともいえる。しかし土星の環だけがきわだって大規模であるゆえんはいまだ明らかでない。
火星と木星の軌道間には多数の小天体が太陽を公転している。これらは小惑星と呼ばれ,軌道の確定したものは約3000個に達し,しかも年々増加している。最大の小惑星は直径1000kmであり,直径500km以上の小惑星は3個ある。大部分の小惑星は直径が100km以下であり,小さな小惑星ほど数は多い。すい星も太陽を公転する小天体であるが,太陽に近づくとその放射熱を受けて揮発性物質を放出し長い尾をもつのが特徴である。また運動のようすも惑星や小惑星とは非常に異なる。約700個のすい星の軌道が求められているが,そのうち太陽に周期的に近づくすい星は約300個である。以上のほかに天体と呼ぶには小さすぎるような微粒子がほとんど無数に太陽を公転していて,たまたま地球の大気圏に突入すると大気との摩擦で燃えて流星となる。
このように太陽系の構成員は太陽,惑星と衛星,小惑星とすい星,流星(となる宇宙塵)があげられるが,その質量の配分は個数の少ない構成員ほど多い。すなわち,ただ1個しかない太陽は太陽系全質量の99.866%を占有しているし,残る0.134%の大部分99.99994%は9個の惑星と約40個の衛星が占めている。個数にすれば断然多い小惑星とすい星の質量は太陽系全体の0.00000008%にすぎない。ほとんど無数の宇宙塵の質量は上記の精度では0である。
(2006年8月,国際天文学連合(IAU)は総会で惑星の新しい定義案を採択し,これによって冥王星は準惑星(dwart planet)に分類されたが,本稿での記述は従来のままとする--編集部)
太陽系の広がり
太陽系の形と大きさを惑星の空間的分布で表すのは,その質量配分から妥当である。すると太陽系は円盤状に広がっていてその直径は約100億kmということができる。太陽にもっとも近い恒星ケンタウルス座α星までの距離は約40兆kmであるから,太陽系の直径はその1/4000にすぎない。つまり恒星界のスケールに比べると,太陽系の広がりはほとんど点と変わらない。この事実は力学的に見れば太陽系が外界の影響を受けない孤立した系であることを示す。
太陽系の円盤は黄道面で代表される。黄道面は地球の軌道面であるが,他の惑星の軌道面も黄道面とあまり変わらない。黄道面は地球の中心を含んで全空間を二分するが,そのうち北極のある側を黄道面の北側という。太陽系の俯瞰図(ふかんず)は通常黄道面の北側からの図である。また太陽や惑星の南北両半球を区別するときは,黄道面の北側から見えるほうを北半球とする。
太陽系の中心はもちろん太陽と考えてよいが,太陽系の重心は太陽(の中心)から最大で160万kmの範囲を移動する。しかし慣性空間に対して不動なのは重心のほうである。その重心を通り黄道面と1°35′の傾きをなす平面は慣性空間に対して不動であって太陽系の不変面と呼ばれる。この不変面は木星の軌道面とほとんど一致する。
太陽系概念の成立
太陽系を構成する諸天体のうち,太陽と月と水星,金星,火星,木星,土星の5個の惑星は太古より知られていた。ギリシア時代になって,プトレマイオスは宇宙の中心に地球が静止し,そのまわりを日月5惑星がめぐるという天動説を完成した。16世紀になると,コペルニクスは地動説を唱え,宇宙の中心には太陽が静止し,地球は月を伴って自転しながら5惑星ともども太陽を公転すると現代風に改められた。しかし地動説が論じたのは宇宙そのものであって太陽系ではない。宇宙の中の太陽系という考えが成立するためには,天動説のみならず地動説にも現れる“恒星天”の実体が明らかになることが不可欠であった。やがて16世紀末には恒星ミラ(くじら座ο星)の変光が発見され,17世紀初めにG.ガリレイが望遠鏡による天体観測を始め,17世紀の後半にはI.ニュートンの万有引力論が惑星運動を解明して,しだいに太陽と惑星の集りとしての太陽系の概念が形成されていった。
英語の太陽系を意味するsolar systemが初めて文献に現れたのは18世紀初頭であるから,だいたいそのころから太陽系の概念も固まってきたものと思われる。19世紀の初めにはF.W.ハーシェルが太陽系の空間運動を発見しているので,このころには太陽系の概念も成立していたわけである。同じころに連星が発見されるや,連星の間に働く引力が太陽系の中で成立する万有引力と同じものか否かが論じられて肯定的な結論が得られたのである。
太陽系天体の組成
惑星が地球型と木星型とに区別されることはすでに述べた。前者の平均密度は3.9~5.5g/cm3と高く,後者では0.7~1.6g/cm3と低い。なお太陽の平均密度は1.4g/cm3である。このような平均密度の相違は天体の組成の違いを示している。すなわちまず太陽と木星型惑星は軽い元素からなり,地球型惑星は重い元素からなるということができる。次に,宇宙にもっとも多く存在してもっとも軽い元素は水素(H)で,ヘリウム(He)がこれに次ぐから,太陽と木星型惑星の主成分は水素とヘリウムと考えたい。実際太陽と木星と土星ではそうなっている(天王星と海王星は後述)。ただし平均密度が1g/cm3にもなるのは,太陽や大惑星の巨大な質量の自己重力によって天体の内部で超高圧が実現し,このために木星と土星では水素やヘリウムの原子核の全体が電子の全体を共有して高い密度になっているからである。このような状態は通常の金属に見られるので水素やヘリウムの金属状態といわれる。木星は土星より質量が大きくて内部の圧力が高く,金属状態は土星より広い範囲にわたるので平均密度も高いと理解される。ここで太陽は質量がけた違いに大きいのに平均密度が木星とほとんど変わらないのは温度の違いによるものである。すなわち木星や土星に比べると太陽の内部は超高温で,これがけた違いな質量の自己重力によるけた違いな圧縮力と拮抗しこれを緩和しているからである。その代り太陽におけるその高温度は太陽の中心部で核融合反応を誘起することになって恒星の仲間に入ることになる。
天王星と海王星が木星の約1/20の質量しかないのに木星と同程度の平均密度をもつのは,水素やヘリウムより重い元素が主成分となっているからと考えられる。宇宙で水素とヘリウムに次いで量の多い元素は酸素(O),炭素(C),ネオン(Ne),窒素(N),鉄(Fe),ケイ素(Si),マグネシウム(Mg),硫黄(S),……の順となっている。この順序は元素の原子数の多少の順に並べるとO,C,N,Ne,Mg,Si,Fe,S,……のように順序が少し変わる。そして天王星,海王星の組成は実際O,C,Nを主成分としていて,メタン(CH4),アンモニア(NH3),水(H2O)という化合物になって氷の形態で存在している。そしてこれらの化合物はどれも水素というもっとも豊富な元素と結びついている。なお,化合物をつくらない不活性元素のNeは主成分となっていない。実は上述のO,C,Nに続く元素Fe,Si,Mgは金属鉄あるいはOも含めた酸化物の岩石の形態で木星型惑星の小さな中心核の主成分となっている。木星の場合,中心核の質量は5%にみたない。
密度が1g/cm3程度の天体には他に小さな衛星やすい星の核がある。核は小さすぎて望遠鏡でも点としか見えないが,核表面のアルベドを適当に仮定して明るさから求めた大きさは大すい星でも直径10km程度である。このような核や小衛星では自己重力はまったく問題とならないので,密度が1g/cm3の物質H2O(氷)を主成分として他には天王星と海王星にも登場した元素C,Nの化合物からなるものと考えられる。
地球型惑星は木星型惑星より小質量なのに平均密度は5g/cm3程度なので明らかに重い元素から構成されている。木星型惑星の中心核がむき出しになったと考えればよい。つまり全体が岩石質でさらに金属質の中心核をもつ。前述の宇宙の元素の存在度は硫黄(S)より後は量の順にカルシウム(Ca),ニッケル(Ni),アルミニウム(Al),ナトリウム(Na),クロム(Cr),……と続き,原子数の順ではAl,Ca,Na,Ni,Cr,……となる。そして地球型惑星の金属質中心核はFeとNiでつくられているが,たしかにNiはFeに次いで多い金属である。また上記の非金属元素はどれも主要な岩石を構成する元素となっている。地球型惑星の平均密度の相違(3.9~5.5g/cm3)は金属中心核の大きさの相違と考えられる。質量の大きいほど中心核も大きいと考えたいが,そう単純ではない。最大質量の地球の平均密度5.52g/cm3はたしかに最大であるが,最小質量の水星の平均密度5.43g/cm3が地球に次いでいる。
前に水星とほとんど同じかもっと大きな衛星が3個あると述べたが,質量を比べると水星に及ばない(約4割)。それにしても準惑星級の天体であるが,その平均密度は2~4g/cm3となっている。したがって,水星は例外として,質量が減ずるにつれて重い中心核の占有率も減じ平均密度も減じていく傾向がある。実際もっと小質量の衛星や小惑星の密度が1~3g/cm3となっているが,これらは氷や岩石質の密度である。以上に見るように,太陽系天体の組成は平均密度と元素存在度によって推察されるとおりにほぼなっている。
内惑星と外惑星
内惑星と外惑星の区別は地球型と木星型のように惑星の実質的区別ではないが,地球から行われる惑星の観望には本質的である。地球から観測して惑星が太陽と同じ方向にくるときを合,反対方向にくるときを衝という。内惑星の場合には太陽のこちら側の合と向こう側の合がともに起こり,それぞれを内合,外合という。内合のとき惑星は地球にもっとも近づくが新月の状態で暗い。外合では満月の状態となるが距離はもっとも離れる。このように内惑星は月のように満ち欠けしてその見かけの大きさも著しく変える。そして光度が最大となるのは水星では内合の前後約15日目,金星では前後約36日目である。金星の極大光度は-4等以上なので日中でも肉眼で見えることがある。内惑星の視運動(天球上の運動)は太陽の前後を行きつ戻りつするだけなので真夜中に見えるようなことはない。つまり衝は起こらない。そして太陽からもっとも離れる角度は水星で約28°,金星で約49°でこれらを最大離角という。また内惑星が太陽の東側(西側)で最大離角になるときを東方(西方)最大離角という。そして水星では内合の約22日前(後),金星では内合の約71日前(後)に起こる。内惑星に特有なまれな現象に太陽面通過がある。内合のときに惑星がその軌道上の交点の近傍にあるときに起こる。水星の太陽面通過は今世紀で13回起こるくらいの頻度だが,金星の場合は前回が1882年12月で次回は2004年6月まで起こらない。もっともその次は8年後(2012年6月)に起こる。
外惑星は満ち欠けはほとんどせず光度が最大となるのは衝のときである。衝は惑星が地球にもっとも近づくときでもあり,そのうえ真夜中に南中するので観測の好機である。内惑星の視運動は太陽を前後するだけでわかりやすいが,外惑星では複雑である。惑星の惑は〈まどい歩く〉を意味している。複雑な視運動は順行,留,逆行,留,順行,……の繰返しとなる(内惑星でも同じ)。ここに順行というのは太陽の年周運動の向きで,日本を含めて北半球では,南の空で西から東である。天文学では,この向きを一律に〈西から東〉の向きと決めている。太陽と惑星の黄経はこの向きに増加する。太陽を中心に考えても同じであって,地球を含めて惑星の黄経が増加する向きが順行である。後述の公転と自転の順行とはもちろん一致する。留は順行と逆行とが入れかわるときで惑星の東西方向の動きは止まる。火星の場合には相次ぐ衝の間(≒会合周期=780日)で順行は約91%(706日),逆行は約9%(74日)の割合である。
太陽系天体の運動
太陽系の諸天体は,太陽を公転する惑星などの運動も,あるいは惑星を公転する衛星の運動もすべてケプラー運動で近似的に表される。近似の精度は高いので通常はケプラー運動として扱って十分である。実際の運動のケプラー運動からのずれは摂動といわれ,たとえば太陽系の安定性を論ずる場合には摂動の性質が重要となる。それからすい星の軌道は諸惑星の軌道を横切って長く伸びており,したがって惑星,とくに木星や土星などの大惑星に接近する場合には摂動を無視できなくなる。
惑星,小惑星そしてすい星のケプラー運動は黄道面を基準面として記述される。つまりケプラー要素の軌道傾斜(i)は黄道面を基準とした値である。すでに述べたように惑星の軌道傾斜は小さい。楕円軌道の形はケプラー要素の離心率(e)で表されるが,惑星の離心率は小さくて軌道は円に近い。もっとも冥王星の場合はi=17°,e=0.25のように小さいとはいえないがこれは例外である。冥王星を例外として惑星はほぼ黄道面上をほぼ円運動している。運動は黄道面の北側から見て反時計回りであり,このような運動を順行という。冥王星の運動も順行である。なお軌道の知られている約3000個の小惑星も,一つの例外もなく順行している。軌道の大きさはケプラー要素の半長径(a)で表される。半長径は平均距離とも呼ばれ,円運動では円の半径となる。惑星の平均距離を天文単位(AU)で表すと,距離はボーデの法則に従い隣り合う軌道は適当な間隔を隔てている。ただし海王星と冥王星の軌道の関係は例外であって両軌道はほとんど交差するほどである。小惑星の代表をケレスにとると,ケレスの平均距離はボーデの法則に従っている。すい星の運動は惑星や小惑星とたいへん異なっていて,一般に軌道傾斜も離心率も大きく,運動の向きが逆行の場合もある。逆行は黄道面の北側から見て時計回りに運動する場合でハリーすい星はその一例である。楕円軌道をもつ約300個のすい星のうち約170個は平均距離が海王星より大きく,太陽近傍に回帰するまでに200年以上を要する。
惑星を公転する衛星の運動では基準面として黄道面の代りに母惑星の赤道面(近接衛星の場合)や母惑星の軌道面が使われる。約40個の衛星の中で逆行運動をする衛星が6個ある。近接衛星は軌道傾斜も離心率もほとんど0である。つまり母惑星の赤道面内を円運動している。木星や土星のように多数の衛星をもつ衛星系では母惑星からの平均距離を表すボーデの法則に類似の数式がいろいろくふうされている。
すべての天体は公転と同時に自転もしている。すい星の中心核とて例外ではない。しかし自転の状況がよく知られているのは太陽と惑星といくつかの衛星や小惑星である。自転の向きも公転と同じ決め方で順行と逆行を区別する。太陽を公転する天体でも惑星を公転する天体でも自転は順行が大部分を占める。実際逆行は金星と冥王星だけである。ただし天王星の自転は自転軸が軌道面に横転していると考えて逆行に入れなかった。さらに小惑星の自転は変光を手がかりとするので順行,逆行は判別しにくいのだが,天王星のように自転軸が横倒しに近いものがある。ハリーすい星の中心核の自転も類似の状況にあるらしい。次に自転周期を見ると,太陽(27日),水星(59日),金星(243日)は長く,冥王星(6日)はやや長いが,他の惑星および小惑星は短い(1日~数時間)。木星型惑星は平均密度(ρ)が低いうえに自転が速いので形状の扁平さが目だちとくに木星と土星で著しい。実際扁平の程度は惑星の赤道における(遠心力)÷(表面重力)を目安として推量できる。そしてこの比そのものはρP2(Pは自転周期)に反比例する。実際,扁平の程度を扁率(f)で表すと,地球から海王星までの6惑星では地球,火星,海王星,天王星,木星,土星の順に扁率は増加するが,同じ順にρP2は減少している(表1)。
木星と土星はそれぞれ十数個の衛星を従え,衛星の距離を表す表式も存在して太陽系のミニチュアといわれている。しかし大きな違いもある。それは木星,土星の自転が速いことと,さらに太陽の自転が遅いことに関係する。木星とその衛星の系で木星の質量は全体の99.98%を占めるが角運動量も木星(の自転)が99.34%を占めている。土星とその衛星系でもほぼ同じだが,太陽系では質量が99.87%もある太陽の角運動量は2%に達しない。
自転と公転の尽数関係
月は満ち欠けをするが,月面の模様がつねに同じであることは太古より知られていた。これは月の自転周期が公転周期と一致し,月の公転が順行なので月の自転も同じく順行であることを示している。このような場合に月の自転周期と公転周期が1:1の尽数関係にあるという(尽数は有理数を意味する)。長い間このような関係は太陽に近い水星にも成立するものと考えられ,それを支持する望遠鏡の観測もあったわけだが,1965年に行われた地球からのレーダー観測で自転周期が59日に決まり,公転周期88日と一致しないことが明らかになった。その代りマリナー9号の火星探査(1971-72)では火星の2個の衛星がどちらも1:1の尽数関係の自転をしていることがわかり,さらにボエジャーの木星,土星探査(1979-80)によって木星や土星の多数の近接衛星が同様な自転を行っていることが発見あるいは確認された。
水星の場合に戻ると公転周期と自転周期は一致しないが,その比は88:59=1.491……で3:2に近い。これを偶然と考えればそれまでであるが,力学的に有意と考えると比は正確に3:2であるはずで,これを3:2の尽数関係という。木星や土星の近接衛星では1:1の尽数関係がいくつか見られることを述べたが,3:2尽数関係は報告されていない。それでは月や近接衛星で1:1であるものがどうして水星で3:2となるのであろうか。結論をいえばそれは太陽のまわりの水星のケプラー運動の離心率が0.2と大きいからである。一般に離心率がeのケプラー運動では,ケプラーの第2法則により近日点通過時の惑星の角速度はn(1+e)1/2÷(1-e)3/2となる。nは惑星の平均運動で360°÷(公転周期)つまり平均の角速度である。水星の場合e=0.206で角速度は1.55nとなる。そこで1.5nという角速度を考えると,1.55nより少し小さいので近日点を含む90°の範囲の平均角速度になっている。ゆえに水星の自転の角速度が1.5nであるならば,水星は近日点通過の前後の約15日間太陽にほぼ同じ面を向けることができる。そして重要なことは1公転後にちょうど裏の面を向けて近日点を通り2公転後には完全に初めの状態に戻ることである。水星を楕円体(ラグビーボールの形状)とするとき,力学的に意味があるのは水星の最長軸が太陽の引力の最大になる近日点の前後で太陽に向かうことにあるので,上述のように表と裏が交代しても差し支えない。とにかく重要なのは自転角速度が正確に1.5nであることで,これが公転周期と自転周期の3:2の尽数関係になる。そして,表2を見ると,もし水星の離心率が0.32であったなら2:1の尽数関係が成立すべく水星の自転周期は44日となることだろう。月の場合はe=0.055で近地点での角速度は1.12n(nは月の平均運動)となるが,それなら自転角速度はnであってよく1:1尽数関係が成立している。この場合は月の楕円体の最長軸はつねにほとんど地球を向き,したがって裏面が向くことはない。
公転の尽数関係
二つの周期の間の尽数関係は同一天体の自転・公転周期のほかに隣り合う天体の公転周期の間にも存在する。著名な例に土星の衛星チタンとそのすぐ外側のヒペリオンがある。チタンとヒペリオンの公転周期をそれぞれPTとPHで表すと,
PT:PH=15.9454日:21.2766日=3:4.003……
のように3:4にきわめて近く,この場合を3:4の尽数関係という。しかし自転と公転の尽数関係の場合と違って比が正確に3:4とならないことが意味をもっている。それを見るためにまず両衛星の軌道面を同じとして土星,チタン,ヒペリオンがこの順に一直線になった瞬間(両衛星の合)を考える。つまりこのときにチタンとヒペリオンとはもっとも近づく。チタンは土星の最大の衛星でありヒペリオンはこのときチタンの大きな摂動を受けるわけである。次の合は両衛星の1会合周期後に起こるのであるが,もしチタンとヒペリオンの公転周期の比が正確に3:4であれば会合周期はPTの4倍ともPHの3倍とも表せる。4PT=63.7816日であるからこの間にチタンとヒペリオンはそれぞれ軌道を4公転,3公転して初めの位置に戻って合になるわけだ。ところが実際には会合周期は1/(1/15.9454日-1/21.2766日)=63.6374日となって先の日数より0.1442日短い。ということはそのぶん360°×0.1442日/15.9454日=3.°256だけ手前で合になる(チタンもヒペリオンも順行しているので合の方向は逆行する)。会合周期ごとに合の方向が3.°256逆行すれば1年で18.°7逆行することになる。
ヒペリオンは1848年に発見されたが,その後まもなく近土点(遠土点といっても同じ)が1年に18.°5という猛スピードで逆行することが観測された。摂動論の常識ではチタンの質量から期待できる近土点の後退速度は1年に1.°5であったので,ヒペリオンの後退速度は意外であった。チタンの軌道は円と考えてよいが,ヒペリオンの軌道は離心率0.1の楕円であるために,両衛星の軌道間の距離は41万km(ヒペリオンの遠土点で)~10万km(近土点で)と4倍も変わる。ゆえに合が近土点で起これば遠土点の場合の16倍の摂動力をヒペリオンは受けることになる。ヒペリオンはチタンと1会合周期ごとに接近することは避けることができないが,接近時の距離をなるべく大きく保ちたいならば遠土点の近くで合になるしかない。あるとき遠土点で合になったとすれば,次の合は約3°手前で起こるが,遠土点もそれだけ逆行するので合は再び遠土点で起こるというしくみになっているのである。つまり3:4.003の端数の0.003はヒペリオンの遠土点の異常な逆行に結びつけて理解される。以上の事柄は,公転周期の代りに平均運動で表せばnT,nH,ωHをそれぞれチタン,ヒペリオン,ヒペリオンの近土点の平均運動として3nT-4nH+ωH=0と表せる。木星のガリレオ衛星のイオ,ユーロパ,ガニメデの平均運動nI,nE,nGの間にはnI-3nE+2nG=0の関係が成立してラプラスの関係といわれる。天王星の衛星アリエル,ウンブリエル,チタニア,オベロンの平均運動をnA,nU,nT,nOとするとnA-nU-2nT+nO=0も成立する。これらはすべて公転周期の尽数関係と呼ばれ,ほかにも多数の例が見られる。そしていずれの場合も関与する天体が相互の大接近を避けて現状を維持しようとする傾向が読み取れる。逆に見ればそういう関係であるからこそ現在にも存続しているのである。
木星と土星の公転周期をPJ,PSとすると,PJ:PS=11.862年:29.457年=2:4.9666となって2:5に近いので2:5の尽数関係といわれるが,この場合の4.9666は自転,公転の場合のように5とみなすべきでもないし,ヒペリオンの場合のような格別の意味があるわけでもない。しかし近似的な2:5尽数関係によって,木星と土星の平均黄経には880年の周期で振幅がそれぞれ20′,48′の長周期摂動が現れる。これらの摂動は対応する摂動力に比べて異常に大きく木星で約5000倍,土星で約1000倍に倍増されている。このように近似的尽数関係によって摂動力の効果が倍増される現象は〈小分母の問題〉といわれる。
木星と小惑星との運動にも幾多の尽数関係がみられる。(小惑星の公転周期):(木星の公転周期)が2:3の小惑星が31個発見されていてヒルダ群小惑星と呼ばれ,1:1の小惑星も35個あってトロヤ群小惑星と呼ばれている。また小惑星チューレは3:4である。将来チューレのほかにも発見されればチューレ群小惑星と呼ばれることになる。トロヤ群小惑星は木星と同じ軌道上にあって同じ公転周期で木星の前後60°の離角で太陽を公転している。公転周期の比が1:1から外れると木星との大接近は避けられない。しかしチューレやヒルダ群の場合はこのような意味合いはない。それどころか同じ尽数関係でありながら1:2,3:7,2:5,1:3の場合にはちょうどそこにだけ小惑星が存在しないのでカークウッドの空隙と呼ばれる。すなわち尽数関係の比の値が2/3~1なら群,1/3~1/2なら空隙となっている。
→小惑星
太陽系の安定性
太陽系の主要な構成員である惑星が,だいたいにおいて同じ平面内を円に近い楕円運動をしていることはすでに述べた。また隣り合う軌道は適当に離れていて惑星どうしはあまり近づかない。実は冥王星の軌道は例外をなすのでひとまず除外しておく。
惑星どうしがあまり接近しなければ惑星間の引力も太陽の引力に比べて小さいままにとどまり,それを無視すれば惑星の運動はケプラー運動で表せて,したがって太陽系の現状は維持される。それでは惑星間の引力を考慮したらどうなるかというのが太陽系の安定性の問題である。惑星に番号をつけて水星,金星,……,海王星を1,2,……,8番と呼ぶことにし,mj,aj,ej,ij(j=1,2,……,8)で各惑星の質量,半長径,離心率,軌道傾斜を表す。惑星がケプラー運動をするならこれらはすべて定数である。摂動論によれば惑星の相互作用によってaj,ej,ijは時間(t)とともに変動し,変動分(摂動)をそれぞれδaj,δej,δijとすれば, と表せる。そして摂動は時間変動のようすによって短周期摂動,長周期摂動,永年摂動の3種に分類される。短周期摂動は摂動の量が摂動力に比例してきわめて小さいので安定性の問題には関与しない。するとまずδajには短周期摂動しか含まれないというラプラス=ポアソンの定理がある。よって安定性の問題では,
と表せる。そして摂動は時間変動のようすによって短周期摂動,長周期摂動,永年摂動の3種に分類される。短周期摂動は摂動の量が摂動力に比例してきわめて小さいので安定性の問題には関与しない。するとまずδajには短周期摂動しか含まれないというラプラス=ポアソンの定理がある。よって安定性の問題では,
δaj=0 (j=1,2,……,8)
とするのに等しい。次にラプラスの定理, が成立する。C,C′は定数で,その値はej(t),ij(t)に現在値ej(0),ij(0)を代入して得られる。ej(0),ij(0)が小さいのでC,C′もそれに応じて小さい。m3=1,a3=1の単位でiは1850年の黄道を基準として度で表すと,
が成立する。C,C′は定数で,その値はej(t),ij(t)に現在値ej(0),ij(0)を代入して得られる。ej(0),ij(0)が小さいのでC,C′もそれに応じて小さい。m3=1,a3=1の単位でiは1850年の黄道を基準として度で表すと,
0.03e12+0.69e22+e32+0.13e42+725e52+294e62+63.8e72+94.5e82=2.740
0.03i12+0.69i22+i32+0.13i42+725i52+294i62+63.8i72+94.5i82=3411
となる。これらの関係から木星~海王星のe,iに上限があることは明らかである。たとえば,木星の離心率は(2.740/725)1/2=0.0614……以上にはなれないし,軌道傾斜は(3411/725)1/2=2.°1……でおさえられる(現在値はe5=0.048,i5=1.°3)。ゆえに,これらには永年摂動が含まれないことがわかる。また0.048が0.0614になったとすると変動は30%に近く,摂動力m6/m0=1/3500(m0は太陽の質量)より格段に大きいので長周期摂動である。軌道傾斜についても同様である。もっとも上記の上限値は実際に達せられる値というわけではない。永年摂動論の複雑な計算によれば0.0608≧e5≧0.0255であり,そのかなりの範囲0.059~0.027を振動する周期は6万9000年である。
小質量の水星~火星の離心率,軌道傾斜についてはラプラスの定理から情報は得られない。しかし質量配分から見れば太陽と木星型惑星だけで太陽系と称してもよいのだから,ラプラスの定理は太陽系の安定を示しているのである。永年摂動論によれば地球型惑星についても長周期摂動のみ存在して,地球の場合では0.0677≧e3≧0,4.°7≧i3≧0である(現在値はe3=0.0167,i3=0°)。i3の変動の4.°7の中の3.°5の変動は9万8000年の周期で繰り返される。地球の自転軸は黄道面に直立しないで23.°5傾いているのが現状であるが,この傾きは黄道面が現在と比べて4.°7傾くと28.°2~18.°8と変動する。この変動の約95%が約10万年の周期で繰り返されるのである。類似の現象は火星でも起こり,今度は7.°5≧i4≧0で(現在はi4=1.°85)自転軸は直立から25°傾いているから32.°5~17.°5ともっと大きく変動する。このような地球や火星の軌道面に対する自転軸の傾きの大きな変動はこれらの惑星の過去の気象に大きく影響したことであろう。
最後に,冥王星は質量が小さいので冥王星を議論に加えても上述の結論は変わらない。また冥王星自身の運動は,海王星との公転周期の比が2:3の尽数関係にあるために両惑星の合は冥王星の遠日点の近くでしか起こらず,前述の軌道の関係にもかかわらず冥王星は海王星との大接近を免れて運動の現状が維持されている。
太陽系の起源
これまで述べてきたような数々の特徴を有するのが太陽系であり,星間雲のガスと塵(固体微粒子)から約50億年かかって現在の太陽系がいかに形成されたかを論ずるのが太陽系起源論である。太陽系の起源が太陽そのものの起源と進化に深く関連することはいうまでもないが,とくに太陽系の惑星形成期における太陽の進化過程は1960年代に明らかにされた。また時期を同じくして人工飛翔(ひしよう)体が太陽系空間探査に活躍する時代に入り,太陽系の現状に対する幾多の新知見が得られた。まず何よりもアポロ月有人探査で持ち帰った月の石の標本はそれまで地球の岩石が調べられた程度とは比べようもないほど綿密に調査された。太陽系起源論の着実な歩みはこのときに始まったとさえ感じられる。さらに月の石を徹底的に調査した新技術は当然のことながら隕石の調査にも適用されて大きな成果をあげている。実際,隕石が原始太陽系の姿をとどめる化石としてその重要性が一般に認識され始めたのはこのころである。さらに人工飛翔体で得られた情報を列挙すると,水星と火星そして火星~土星の多くの衛星に見られる月面さながらのクレーター群は予想をはるかに超えたもので人々を驚かせた。さらには,これらの衛星の特徴的な自転(公転と同期),火星の生命探査,木星の衛星イオの火山活動,木星の大赤斑を取りまく大気の渦巻,木星の環,土星の環の超微細構造等々となる。なかでも金星の大気が100atmもあり炭酸ガスが主成分で硫酸の雨が降っている,などの情報は,得られてみるまでは予想もできなかったし,また得られた後は比較惑星学の誕生を促す要因となった。つまり金星と地球は質量も大きさも太陽からの距離もそんなに違いがないのに,どうして大気圧や組成が現状のように違うのかという発想に基づくものである。そしてこの比較惑星学は太陽系起源論に多くの示唆を与えている。今後も人工飛翔体や新技術を駆使した大望遠鏡による太陽系の探査,観測が進められれば,さらに予想外の新知見が得られるやもしれず,そうなると太陽系に関する現在の知識が太陽系起源論の必要とする十分な情報を与えているかという懸念も生ずる。
ここでは太陽系の特徴の中で本質的と考えられる次の諸点をとり上げよう。いわば太陽系起源論が成立するための必要条件である。(1)太陽系の大部分の質量は太陽が担い,大部分の角運動量は惑星(木星型)が担う。(2)惑星の軌道面はほぼ同一平面上にあり軌道は円に近い。(3)これらの軌道の半径はほぼボーデの法則に従って分布する。(4)多くの惑星は衛星と環を伴っている。(5)小惑星が存在する。(6)公転も自転(太陽も含めて)もほとんど向きが同一である。(7)公転,自転の周期に多くの尽数関係が存在する。(8)惑星には地球型と木星型の区別が存在する(冥王星は例外)などがあげられる。ただしこれらの特徴に比べて,たとえば,逆行衛星の存在や天王星の自転軸の横転,そしてすい星の存在を偶発的とするかしないかは実は問題である。
恒星は星間物質(ガスと塵)が凝縮して生まれるのだが,その初期の段階を原始星という。原始星から恒星へと進化するとき原始星のすべての物質が恒星になれば惑星系を伴わない単独の恒星となる。しかし,大部分の物質が恒星になる場合は,取り残されたわずかの物質から惑星系が生まれるのである。両者の違いの要因として原始星の角運動量が考えられる。極端に考えて原始星の角運動量が0なら単独星に進化する。逆に角運動量が非常に大きい場合にかりに単独星になったとすれば,角運動量は保存されるので原始星の角運動量がそのまま恒星の自転の角運動量にもち込まれることになり,恒星は自転が速すぎて分裂してしまう。実際には単独星になってから分裂するのではなく,単独星にはならないで惑星系を伴うという結果になる。これが原始太陽の場合であると考えたい。とすると現状はどうであろうか。
現在の太陽系では太陽の自転角運動量は自転周期25日の剛体回転として計算すれば2.1×1048gcm2/sであり,また,惑星の公転角運動量の総計は314×1048gcm2/sとなる(表3)。ゆえに惑星の角運動量をすべて太陽が担ったとすると太陽の角運動量は150倍となり,したがって自転周期は現在の1/150の4時間となる。そして太陽が4時間で高速自転をすれば赤道上の遠心力は表面重力の1/2の程度となり,太陽は分裂するかしないかのせとぎわの状態におかれる。これならば上述の分類で原始星の角運動量が大きくて惑星系を伴う場合に入れてもよい。しかし太陽の自転には赤道加速という現象が見られ,太陽が剛体回転していないのは明らかである。内部の回転が表面(自転周期25日)より速ければ太陽の角運動量は上記の値より大きくなる。これを5×1048gcm2/sとすれば,上述の4時間の自転周期は10時間に伸び,遠心力と表面重力の比は約1/10となる。これなら上述の論旨からすると原始太陽は単独星に進化してもよいわけで,つまり事態はそう単純ではないということである。したがってここでは2×1033gの質量(太陽の質量で,以下M.と記す)をもつ原始太陽系が,300×1048gcm2/sくらいの角運動量をもつと惑星系を伴う恒星に進化するものと考えよう。
原始太陽系の質量配分は現状とは少々異なっていて中心の原始太陽は全質量の95%くらいをもっていたとされている。つまり原始惑星系の質量は5%であって現状の0.13%に比べると何十倍も大きかったと考えるのである。その理由としてわかりやすいのは地球型惑星の組成である。前述のように地球型惑星は現在HやHeをほとんどもっていないが,原始惑星のころには宇宙の元素存在比の割合でこれらのガスを保有していたと推定される。そうすると惑星の中心核を構成するFeやNiなど金属質の量は昔も今も変わらないので,それに見合う大量のH,Heが加わることになるのである。1M.の質量をもつ原始太陽のまわりを総計0.05M.の質量の8個の原始惑星が,ほぼ現状のように太陽を公転する状態は実は太陽系形成期のかなり後の段階である(なお,この時点での冥王星の運動状態は明らかでない)。ところで原始惑星系の多量のガスが失われたのは,そのころに主系列に入る直前の太陽(Tタウリ星段階といわれる)が不安定で激しく活動したので,その強い放射や太陽風によるものと思われる。またその際に惑星間空間に充満していたガスも吹き払われてしまったので,以後の諸天体の運動は現在のような真空の空間で行われ,ラプラス=ポアソンの定理やラプラスの積分が成立するようになった。冥王星の現在の運動はこのころに確立されたものであろう。
太陽系形成のこの後期の段階はガス散逸期といわれる。この時期に原始惑星が微惑星の衝突合体による成長を完遂していたかいなかったか学説の分かれるところであって,地球型惑星の原始大気の問題にも関連してくる(惑星)。ところで上述の微惑星というのは直径10kmくらいの金属質あるいは岩石質の微小天体(質量は1018gくらい)であって,これらの大集団が太陽をとりまく円盤を形成した状態から微惑星の衝突合体によって上記の原始惑星系がつくられたものと考えられており,この期間は衝突期といわれる。ここで微惑星の大きさが上記の値よりかなり小さいと衝突過程で惑星大にまで成長できず,したがって小惑星ばかりの太陽系になるし,反対に微惑星の質量が大きすぎると惑星ばかりで小惑星のない太陽系になるという数値実験も報告されている。そして微惑星の大きさの違いはその原材料となる固体微粒子の個数の多少によるというのである。ではその微惑星はどのようにしてつくられたのであろうか。
太陽系の起源のそもそもの発端が星間雲の凝縮であることはすでに述べた。低温で約10Kのおもに水素からなる星間雲が密度のゆらぎで10⁻20g/cm3程度の高密度になると,その部分の1M.くらいの質量は重力的に不安定になって周囲から分離し自己重力で収縮を始める。分離した星間雲は初めは現在の太陽系の100倍以上の大きさの巨大な球と考えてよい。このガス球は収縮につれて中心部に急速に物質が集中し,一方で少なからぬ角運動量をもっていたので回転速度を増して形はしだいに扁平になる。そしてついに95%の質量の原始太陽をとりまく5%の質量の円盤状の原始惑星雲が形成された。この時点で角運動量の大部分が円盤部に存在するということは可能であろうか。たとえば原始太陽と原始惑星雲円盤の全体が剛体のように回転しているならそれは可能である。実際原始太陽の半径をr,円盤の半径をrDとすれば,両者の角運動量の比は大ざっぱに考えて2/5r2×0.95:1/2rD2×0.05であり,r/rDが1/20で角運動量比は1%以下になる。円盤の密度が外側ほど低いとするとr/rDはもっと小さくてすむ。しかし元の星間雲がたとえ一様に回転していたとしても,剛体回転を保ったまま収縮して原始太陽と円盤とに進化できるかというとそれはできないのである。いろいろ考察してみても質量の大部分を担った原始太陽が角運動量の大部分を担うということになる。そこで原始太陽は急速に自転していたに違いない。ただしその平均密度をd(g/cm3)とすると自転周期は よりは短くなれない。原始太陽が太陽に進化する過程での角運動量の円盤への輸達は電磁気的効果も含めて検討されつつある。さてこの原始惑星雲は収縮の効果によって温度が上がり2000Kほどになったものと考えられる。収縮の急激だった原始太陽の中心部はずっと高温で数百万Kにも達していたであろう。原始惑星雲円盤の温度はその後は放射冷却によりゆっくりと失われていくが,その過程で融点の高い順序に物質(ミクロン程度の固体微粒子)が析出する。そして析出した微粒子は衝突してくっつきながら成長して惑星雲円盤の赤道面に沈殿していく。こうしてガスの円盤の赤道面にはmm~cm程度の微粒子がぎっしりと敷きつめられた状態となる。そしてその密度がある閾値を超えると再び重力不安定が起こって今度は質量が1018gくらいの微小天体の大群(~1014個)に分裂する。この微小天体が前述の微惑星である。微惑星には組成の違い(たとえば金属質,岩石質,氷質)があったろうが,平均してその密度を2g/cm3とすると大きさは直径が約10kmとなる。最後に微惑星どうしが衝突し,合体したり破壊したりという複雑な衝突過程を繰り返しながらしだいに原始水星から原始海王星までが後者ほどゆっくりと形成されていった。もっとも質量が1024g(直径1000km)以上になれば,あとはその重力で他の微惑星を捕獲しながら成長できる。
よりは短くなれない。原始太陽が太陽に進化する過程での角運動量の円盤への輸達は電磁気的効果も含めて検討されつつある。さてこの原始惑星雲は収縮の効果によって温度が上がり2000Kほどになったものと考えられる。収縮の急激だった原始太陽の中心部はずっと高温で数百万Kにも達していたであろう。原始惑星雲円盤の温度はその後は放射冷却によりゆっくりと失われていくが,その過程で融点の高い順序に物質(ミクロン程度の固体微粒子)が析出する。そして析出した微粒子は衝突してくっつきながら成長して惑星雲円盤の赤道面に沈殿していく。こうしてガスの円盤の赤道面にはmm~cm程度の微粒子がぎっしりと敷きつめられた状態となる。そしてその密度がある閾値を超えると再び重力不安定が起こって今度は質量が1018gくらいの微小天体の大群(~1014個)に分裂する。この微小天体が前述の微惑星である。微惑星には組成の違い(たとえば金属質,岩石質,氷質)があったろうが,平均してその密度を2g/cm3とすると大きさは直径が約10kmとなる。最後に微惑星どうしが衝突し,合体したり破壊したりという複雑な衝突過程を繰り返しながらしだいに原始水星から原始海王星までが後者ほどゆっくりと形成されていった。もっとも質量が1024g(直径1000km)以上になれば,あとはその重力で他の微惑星を捕獲しながら成長できる。
先に原始惑星雲円盤の中でガスから析出したミクロン程度の微粒子が衝突合体しながらmm~cm程度に成長することを述べたが,さらに10km程度の微惑星から1000km程度の原始原始惑星までの成長も衝突過程によるわけで,太陽系起源論における衝突現象の重要な役割が認識できる。ところで上述の微惑星の捕獲による原始惑星への成長は衛星系の形成とも無縁ではないし,原始惑星の自転にも関連する過程である。それは後に述べることとして,冥王星を除く諸惑星がほぼ同一平面上をほぼ円軌道で同じ向き(順行)に太陽を公転するという太陽系の特徴は上記の原始惑星の形成過程から理解できるだろう。また原始惑星がほぼ現在の惑星の位置(太陽からの現在の距離)で形成されたと考えるならば,ボーデの法則あるいは類似の惑星距離の規則性はこの段階で成立していたはずである。しかしこれらの法則は惑星の公転周期の間の尽数関係とは無縁であるので,最終的な距離は原始惑星相互の力学的調整で決められたものと考えられる。
前に戻って原始原始惑星がつくられた段階でその自転が順行か逆行かは原始惑星の自転の順行,逆行とは無関係としてよい。そこで簡単に考えて自転していなかったとしよう。原始原始惑星が原始惑星に成長する過程は微惑星の捕獲であることはすでに述べた。太陽のまわりを円運動する原始原始惑星(質量1024g)の重力圏内に微惑星(質量1018g)が飛び込んできて原始原始惑星のまわりに公転を始めたと考えよう。1018:1024=1:106=10⁻6を0とみなすとこれは制限三体問題で扱われる問題となる。そして公転が無限に続かないことが証明されている。しかしこの証明は現実には無視してよいことになる。なぜなら微惑星は何千何万回と公転できるからである。そこで原始原始惑星のまわりにたとえばその1/10の質量に相当する10万個の微惑星が群がって公転する状態も考えられる。するとこれらの微惑星は公転中に何回も衝突してエネルギーを失い原始原始惑星に落下しては元の公転の向きに自転を促すこととなる。ガスが存在すればこの過程はさらに確実で速やかになる。衝突しても落下するまでにエネルギーを失わなかった微惑星は衛星として残る。この考察が正しければ衛星の公転の向きと原始惑星の自転の向きとは一致するはずであるが,この事実は実際に太陽系の特徴の一つとみなされている。問題は惑星の自転が(例外もあるが)順行であること,つまり捕獲された微惑星の公転が順行ということに帰着する。この点に関しては数値的シミュレーションでは確かにそうなるといえるくらいなのが現状である。
太陽系の概念が成立したのが18世紀初めであることは前に述べたが,18世紀半ばには早くもI.カントが太陽系起源説を提唱した(1755)。この起源説は,これに刺激されて後にP.S.deラプラスが力学的不備を補った類似の説を唱えた(1796)のでカント=ラプラスの起源説といわれる。ただしラプラスの説も半ば通俗的な概論に終始したものである。カント=ラプラスの説の特徴の一つは星雲から太陽と惑星とが同時に生まれたとする主張で,カント=ラプラス星雲説と呼ばれる。その後この星雲説に相対する遭遇説,捕獲説がいくつも現れたが,これらのすべてに共通の特徴は太陽が先に生まれその後で惑星がつくられたという主張である。遭遇説の代表的なものには微惑星説,潮汐説,連星説がある。カント=ラプラスの説から順を追って紹介しよう。捕獲説については簡単に触れるにとどめる。
星雲説ではまずゆっくりと回転する高温のガス雲から出発する。ガス雲は冷えるにつれて収縮し,収縮につれて自転速度を速め,赤道部分の遠心力が増加して重力より大きくなると本体から分離してガスの環が残される。本体はさらに収縮を続けるにつれて次々と環を分離し,これらの環が後にそれぞれ惑星に凝縮したというのである。もちろん最後の環を分離した星雲本体は太陽になる。こうして惑星の運動の特徴は説明される。また環が惑星に凝縮してしまわないうちにミニ星雲に収縮して衛星系が生まれるとされる。しかしガスの環がそれ自身で収縮して1個の惑星になることは不可能なのであって,J.C.マクスウェルが1859年にそれを証明した。もう一つの困難は,最初の星雲から収縮に収縮を続けた星雲本体,つまり太陽の自転は,その質量に似合う程度に現在よりずっと高速でなければならないという点である。この角運動量の重要性は61年にバビネJ.Babinetが指摘し,太陽系における角運動量分布の特殊性は,84年フーシェM.Fouchéにより,1900年モールトンF.R.Moultonによって強調されて以来有名になり,以下の遭遇説が世に出るきっかけとなった。
遭遇説の中の微惑星説はチェンバレンT.C.Chamberlinとモールトンが1900年に提唱し,潮汐説はJ.H.ジーンズとジェフリーズH.Jeffreysが17年に提唱したものであるが,両者はよく似ている。すなわちその昔に太陽の近くを恒星が通過してその潮汐力で太陽の表面から物質(ガス)が噴出する。この噴出物質から惑星が形成されるのであるが,惑星の角運動量は通過星のもっているきわめて大量の角運動量のほんの一部をさいて得られると考えるのである。噴出した物質は遭遇が終わった後に通過星の軌道面と同じ平面上を通過星と同じ方向に運動するであろう。そして物質は急速に冷え始め揮発性物質のガスを残して不揮発性物質は液化する。ここまでは両説とも共通である。そして微惑星説ではまず液化してできたのは無数の微小液滴であり,これらは速やかに固体化し微惑星になって太陽のまわりを共通の方向に回転し平たい円盤状の集団となったと主張する。次にこれらの微惑星の中で質量が大きかったいくつか(惑星の核)が付近の微惑星を集めて成長して惑星になったと考える。惑星核の軌道は初め大きな離心率をもっていても,これに降りそそぐ微惑星は惑星核がもっとも速く運動しているときにはその速度を弱め,もっともゆっくり運動しているときには早めるので軌道はしだいに円に近づくのである。一方の潮汐説によると,太陽から分離する物質の量は通過星が近づき最接近し遠のくにつれて少多少の紡錘状になろうという点に着目して,そのまま惑星になるような大きな液体球を考える。紡錘形の中ほどの大きくふくらんだ部分が大質量の木星や土星になるわけである。しかしこの両説を通じての困難が1935年にラッセルH.N.Russelによって指摘された。困難はいぜんとして角運動量に関係している。太陽からr0の距離で円運動をする単位質量の粒子を考えるとその角運動量は (Gは万有引力定数)で与えられる。この粒子が元は太陽にもっと近いrの距離から運ばれてきたとする。その速度をv,vの横方向の成分をv⊥とすれば,角運動量はrv⊥で与えられる。角運動量の保存から
(Gは万有引力定数)で与えられる。この粒子が元は太陽にもっと近いrの距離から運ばれてきたとする。その速度をv,vの横方向の成分をv⊥とすれば,角運動量はrv⊥で与えられる。角運動量の保存から の関係が得られる。一方,太陽からrの距離における脱出速度をveとすると,
の関係が得られる。一方,太陽からrの距離における脱出速度をveとすると, である。つまりv⊥があまり大きいとv≧v⊥だからv>veとなって粒子は太陽から永久に逃げてしまう。そうならないための最小限のrはr=r0/2で与えられることがわかる。この結果によれば太陽物質に海王星の運動を与えるためには,まず物質をひきちぎって少なくとも土星の距離までもってきてそれから適当な速度を与えるということになる。こんなことを通過星が行うには通過星自身が太陽からこの程度の距離を保たねばならない。しかしそれでは潮汐力があまりにも弱すぎて太陽物質を引き出せないのである。そこでラッセルが35年に発表して翌年リトルトンR.A.Littletonが改良した連星説の提唱となった。これによれば太陽はかつて連星であり,その伴星に通過星が接近して潮汐作用で物質をひき出し,そのごく一部が惑星になったとするのである。これなら確かに惑星の角運動量は問題とならない。しかしこのラッセル=リトルトンの遭遇説は,微惑星説,潮汐説ともども,恒星から噴出した高温ガス粒子は微惑星や惑星に固まるどころかまたたくまに雲散霧消してしまうというスピッツァーL.Spitzerの指摘(1939)によって短命に終わったのである。
である。つまりv⊥があまり大きいとv≧v⊥だからv>veとなって粒子は太陽から永久に逃げてしまう。そうならないための最小限のrはr=r0/2で与えられることがわかる。この結果によれば太陽物質に海王星の運動を与えるためには,まず物質をひきちぎって少なくとも土星の距離までもってきてそれから適当な速度を与えるということになる。こんなことを通過星が行うには通過星自身が太陽からこの程度の距離を保たねばならない。しかしそれでは潮汐力があまりにも弱すぎて太陽物質を引き出せないのである。そこでラッセルが35年に発表して翌年リトルトンR.A.Littletonが改良した連星説の提唱となった。これによれば太陽はかつて連星であり,その伴星に通過星が接近して潮汐作用で物質をひき出し,そのごく一部が惑星になったとするのである。これなら確かに惑星の角運動量は問題とならない。しかしこのラッセル=リトルトンの遭遇説は,微惑星説,潮汐説ともども,恒星から噴出した高温ガス粒子は微惑星や惑星に固まるどころかまたたくまに雲散霧消してしまうというスピッツァーL.Spitzerの指摘(1939)によって短命に終わったのである。
以上はいわば歴史的な太陽系起源説であるが,もっと新しい説にはスウェーデンのH.アルベーンの電磁捕獲説(1942),ドイツのC.F.ワイツツェッカーの渦動星雲説(1944),ソ連のシミットShmidtの隕石捕獲説(1944),イギリスのホイルF.Hoyleの連星説(1944),アメリカのホイップルF.L.Whippleの光圧星雲説(1947)などがある。また,現代ではソ連のサフロノフV.S.Safronovの星雲説(1969),アメリカのキャメロンA.G.W.Cameronの星雲説(1978),そして日本では京都モデル,非均質モデルがあり,いずれも星雲説である。現代の起源論がすべて星雲説であるのは,太陽と惑星が同時に誕生したという1970年代の新知見に基づいているからである。
第2の太陽系
太陽系の起源として遭遇説が世に認められた20世紀の前半には,第2の太陽系を考える余地はなかった。J.H.ジーンズの計算によると,太陽近傍の恒星間の平均距離を6光年とすると1個の星が他と衝突あるいは大接近するのは6×1017年の間に1回の割合である。宇宙の年齢は約2×1010年にすぎない。したがって太陽が他星と大接近して太陽系が形成されたのはまったくの偶然事ということになって,第2の太陽系は存在しないわけではないが稀有(けう)な存在となる。それなら現実はどうであろうか。といっても第2の太陽系を望遠鏡で確認することは困難である。たとえばわれわれの太陽系をもっとも近い恒星ケンタウルス座α星(距離4.3光年)から観測すると,口径5mの望遠鏡をもってしても,木星はほとんど望遠鏡の限界等級に近い暗さでしかも1等星の太陽からほんの4″しか離れていないので見分けるのはむずかしい。それよりむしろ形成前の原始太陽系星雲ならそれが放射する赤外線によって見ることができる。これは最近の赤外線観測技術のもたらした大きな成果である。実際すでにそういう天体が太陽からあまり遠くない場所に5個も発見されている。その中の2個,こと座α星(ベガ)とがか座β星は太陽から50光年以内の距離にある。しかもがか座β星のまわりに広がる円盤はごく最近光学望遠鏡による写真撮影まで行われた。以上の事実は太陽系の形成が稀有なできごとではなく,1984年現在の太陽系起源論が正しいことを観測的に支持するものである。
執筆者:堀 源一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「太陽系」の意味・わかりやすい解説
太陽系
たいようけい
solar system
太陽系の構成天体
私たちの太陽系は太陽を中心とし、その重力場内で運動する惑星、衛星、小惑星、彗星(すいせい)、隕石(いんせき)、さらには固体微粒子などの階層の異なる天体(粒子)集団からなっている。太陽系全質量の99.87%は太陽が担い、残りの0.13%のほとんどは惑星が占めている。次に質量の多いのが彗星で、全体の約30万分の1と推定されている。衛星と小惑星の質量はすべてをあわせても全体の300万分の1以下にすぎない。一方、太陽系の角運動量のほとんどは木星や土星など巨大惑星が担い、太陽の自転角運動量は全体の約0.5%にすぎない。
太陽系の骨格をなすのは、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8個の惑星である。太陽に近い6個の惑星は明るく、古来より知られていたが、1778年にF・W・ハーシェルによって新惑星が発見され、のちに天王星と名づけられた。また、海王星は1846年J・G・ガレによって発見された。なお、1930年C・W・トンボーによって発見された冥王星(めいおうせい)は、発見以来惑星の仲間として認められていたが、2006年8月に開催された国際天文学連合(IAU)総会において、質量がきわめて小さく(地球の約430分の1程度)、また、海王星軌道以遠に多数の小天体が存在することから、冥王星は惑星とせず、惑星より小さな準惑星に分類されることとなった。
惑星はその組成や内部構造から二つのグループに分けられている。太陽に近い水星、金星、地球、火星の四つはいずれも質量が地球質量以下で、また、平均密度は約4グラム/立方センチメートルより大きく、地球型惑星とよばれている。これらの惑星では、中心に鉄を主成分とする核があり、その周りを石質(マントル)物質が取り巻いた構造となっている。
他方、木星、土星、天王星、海王星の四つは木星型惑星とよばれ、質量は地球の318倍~15倍と大きいが、平均密度は約2グラム/立方センチメートル以下である。木星型惑星では、金属、石質物質、氷質物質からなる中心核の周りを大量のガス成分(水素、ヘリウム)が取り巻いている。これが木星型惑星の巨大化と小さな平均密度の原因となっている。木星型惑星は太陽からの距離が遠くなるほどガス成分が少なくなっているが、中心核の大きさはいずれも同程度と推定されている。また、木星、土星の内部は超高圧状態にあるため、深部では水素が金属状態にあると考えられている。
地球以遠の惑星には衛星が付随している。2006年末現在、正式に認知された衛星は太陽系全体で121個に上る。この他、木星、土星、海王星には、惑星探査機、天体観測で発見され、軌道要素の追認をうけていない微小衛星がかなりあり、これらを含めると総数は160個を超える。衛星の多くは母惑星の自転方向と同じ方向に公転している。これを順行衛星とよぶ。一部の衛星は母惑星の自転方向とは逆に公転しており、逆行衛星とよばれている。衛星の大きさはさまざまで、木星のガリレオ衛星(4大衛星)や海王星のトリトン、地球における月などは最大級の衛星であり、水星の大きさに匹敵している。また、火星の二つの衛星や木星、土星にみられるいくつかの衛星はたいへん小さく、直径数キロメートルにすぎない。逆行衛星の多くはこのような小さな衛星である。月や火星の衛星は石質、金属質の物質からつくられているが、木星以遠の衛星の主成分は水やアンモニア、メタンなどの氷と推測されている。
木星型惑星はいずれも環(わ)をもっている。土星の環は1655年C・ホイヘンスにより発見され、環といえば土星固有のものと考えられていたが、1977年には天王星の環が、また、1979年には惑星探査機ボイジャー1、2号によって木星の環が確認された。さらに、1983年には海王星に環らしきものが地上から観測され、1989年にはボイジャー2号によってその存在が確認された。1998年現在、木星には1環、土星には7環、天王星には11環、海王星には4環が知られている。いずれの環も母惑星の赤道面内にあり、その主要部分はロッシュ限界内にある。環は厚さ2~3キロメートル以下と非常に薄く、構成物質は数センチメートル以下の無数の氷塊と推定されている。
太陽の周りを公転する直径1000キロメートル以下の小天体群を小惑星という。その多くは火星軌道と木星軌道の間にあり、とくに2.1~3.3天文単位の帯状領域(小惑星帯)に集中している。その数は、軌道要素が確定し、登録番号が与えられているものが約13万個(2006年6月現在)、総数は100万個とも推定されている。大きさは、最大の大きさを誇るケレスでも直径約1000キロメートルにすぎない。小惑星は軌道運動の特徴からいくつかの族に分けられている。最近は、表面反射能の特性によっても4~5のグループに分けられており、反射特性がある種の隕石と類似していることが知られている。小惑星帯から著しく外れたところにも少数ながら小惑星が存在する。これらを特異小惑星とよぶ。隕石の供給源の一つと考えられ、地球にたいへん接近するアポロ群小惑星や、木星と土星の間にある小天体キロンなどはこれに分類されている。
1992年に冥王星の外を公転する小天体が初めて発見されて以来、2007年4月現在までに約4万1200個の海王星以遠の小天体が知られており、カイパーベルト天体(あるいはエッジワース‐カイパーベルト天体)とよばれている。その多くは、35~60天文単位の軌道長半径をもつが、100天文単位を超える軌道長半径をもつ天体もみつかっている。理論的な解析から、これら小天体の軌道(軌道長半径、離心率、軌道面傾斜角)は海王星の引力に強く影響されていることも知られている。カイパーベルト天体の大きさはさまざまで、半径10キロメートル程度の小天体から、冥王星に匹敵する1000キロメートル規模の天体も知られている。
華麗な尾を引き、ときおり太陽近辺に現れる彗星の本体は核とよばれ、直径約数キロメートルの、石質や金属質の微粒子の混じった氷塊と考えられている。木星軌道よりも内側に入ると太陽光に熱せられ、核から揮発性成分が蒸発・電離して明るく輝きだすとともに、蒸発物質が太陽風に吹き流されて巨大な尾(「イオンの尾」とよばれる)を形成する。同時に、氷塊に混じっていた微粒子も揮発性成分の蒸発に伴って飛び出し、「微粒子の尾」を形成する。このような彗星の描像は理論的に予測されていたものであったが、1986年ハリー彗星に向けて送られた各国の彗星探査機の詳細な観測によって、この予測が裏づけられた。彗星は一般に大きい離心率と軌道面傾斜角を有し、太陽に対し球状に分布している。このことは、おおむね黄道面に集中した惑星と好対照をなしている。
隕石は月の石とともにわれわれが手にすることのできる数少ない地球外物質である。隕石はその化学組成や変成の程度によっていくつかのグループに分類されている。そのうち、炭素質コンドライトとよばれる隕石は水などの揮発性成分に富み、水素、ヘリウムや希ガスなど、一部のとくに揮発性の高い元素を除いて、太陽大気の元素組成とよく一致している。それゆえ、太陽大気とともに太陽系内の元素組成推定の基礎にされている。
黄道面近くにはセンチメートル~マイクロメートルの大きさをもつ小さな粒子が無数に存在している。それらが太陽光を反射し、黄道光として観測される。また、とくに粒子密度の高い領域に地球が入ると、地球大気に飛び込んだ粒子が流星、あるいは流星雨として観測される。そのほか、太陽系空間には、太陽コロナから吹き出した太陽風プラズマおよびそれに引きずられた太陽磁場が存在する。
[中澤 清]
惑星の運動
すべての惑星は太陽の周りを楕円(だえん)軌道に沿って回っている(ケプラーの第一法則)。1公転に要する時間は軌道長半径の二分の三乗に比例するという、いわゆるケプラーの第三法則が成り立つ。水星は88日で太陽の周りを1公転するが、地球は1年、木星は約12年、海王星は実に165年で太陽の周りを一周する。軌道の離心率と軌道面傾斜角は水星を除いていずれも小さい。すなわち、どの惑星も太陽の周りを円に近い軌道に沿ってほぼ同一平面上を太陽の自転と同じ方向に公転している。惑星が太陽引力によってのみ運動しているものならば、軌道要素は一定不変に保たれる。しかし、惑星は微弱ながら互いに引力を及ぼし合っており、そのため、離心率や軌道面傾斜角は変動する。ただ、変動幅は小さく、このことが「惑星どうしの衝突や大規模散乱(惑星が他の惑星によって跳ね飛ばされること)はない」という、いわゆる太陽系の安定性を保証している(アーノルドの定理)。天王星より内側の惑星では、太陽からの軌道平均距離がティティウス‐ボーデの法則によって近似され、惑星はほぼ等比級数的に並んでいることになる。
惑星の多くは公転方向と同じ方向に自転しており、自転軸は公転面に対しほぼ垂直である。ただ、金星では自転周期が長く、回転方向は反対(逆行)である。また、天王星では自転軸が約90度傾いており、横倒しの形で自転している。
なお、惑星運動においてケプラーの法則が成立するのは、太陽引力が太陽からの距離の二乗に反比例するというニュートンの万有引力の法則のためである。歴史的にいえば、ケプラーの法則から万有引力の法則が導かれ、近代科学の基礎が築かれた。また、天王星の観測位置とニュートン力学から計算された位置の差から海王星の存在が予言され、ほぼ予言どおりに発見された。このことによりニュートン力学は揺るぎないものとなったわけで、惑星の運動こそが近代科学をつくりだしたといえる。
[中澤 清]
惑星の科学探査
太陽系内の諸天体の観測は、1960年代までは望遠鏡観測など、もっぱら天文学的な手法で行われていた。1970年代以降は、探査機による「その場観測」が行われるようになり、惑星や衛星に関する知見は飛躍的に増大、精密化した。
木星型惑星は大量のガス成分をもっているが、その主要な成分は水素とヘリウムである。ヘリウムの質量比(大気1グラム中に含まれるヘリウムの質量)は木星、天王星、海王星ではおおむね0.27で、太陽大気の値とほぼ等しい。ただ、土星ではこの比が0.06と小さい。これは、土星内部の物理環境下では水素とヘリウムの不混和がおこり、原子量の大きなヘリウムが深部に沈殿してしまった結果と考えられている。
金星と火星の大気主成分は炭酸ガスである。原始地球の大気主成分も炭酸ガスであったと推定されており、地球型惑星の初期大気はいずれも炭酸ガスであったと考えられている。しかし、各惑星の質量や太陽からの距離が違うため、惑星それぞれに独自の大気進化がおこり、現在の大気量およびその主成分は惑星ごとに異なるものとなった、と理解されている。
木星に強い磁場があることは、1950年代に発見された木星電波の研究からわかっていたが、地球、木星以外の惑星磁場は惑星探査によってはじめて明らかにされた。自転速度がきわめて遅い水星や金星にも微弱ながら磁場がある。また、土星の磁場は木星に次いで強く、天王星、海王星にも地球程度の強さをもつ磁場の存在が確認されている。火星では局所的な磁場はあるものの、大域的な磁場は観測されていない。多くの惑星では、自転軸と磁極軸がおおむね一致しているが、天王星では55度もずれている。惑星磁場の原因は良電導性流体のダイナモ作用と考えられているが、地球型惑星では鉄を主成分とする金属流体核、木星や土星では高圧下の金属水素がダイナモ作用を担っていると推測されている。
惑星探査によって地球型惑星の表面地形も詳細にわかってきた。大気をもたない水星は、月と同じような大小さまざまなクレーターで覆われており、また、月と同じく表地形と裏地形が大きく異なる「地形の2極性」を示す。金星には火山状の高地や溶岩流を思わせる細い縞(しま)状地形など、火山性の多様な地形がみられるものの、地球のようなプレート境界(表層の大規模な割れ目)は存在しない。火星には火山性の地形のほかに、河川や大洪水の跡など、かつて水が存在したことを示す種々の地形がみつかっている。
[中澤 清]
太陽系の年齢
もっとも確からしい太陽系の年齢は隕石の同位体比分析から得られる。ウランやカリウム、ルビジウムなど放射壊変する同位元素は、それらが置かれている物理・化学的環境とは無関係に一定の割合で壊変する。このことを利用して放射性同位元素やその生成同位元素の分析によって、隕石がつくられた時期を割り出すことができる。少数の隕石に若い年齢のものもあるが、多くは約45億6000万年という年齢を示す。これよりも古いものがみつからないことから、隕石はこの時期に形成されたと考えられている。他方、地球や月の岩石の多くはかなり若く、もっとも古いものでも38~40億年である。しかし、月の「土」は隕石と同じ45億6000万年前後の年齢を示す。月や地球の岩石が若い年齢を示すのは火成活動のためであり、太陽系の年齢としては45億6000万年と考えるのが妥当であろう。
他方、恒星進化の理論的研究から、太陽自身の年齢を45億6000万年とすれば、現在の太陽半径、太陽光度と矛盾しないことが知られており、太陽を含め太陽系のすべての諸天体が45億6000万年前につくられたことになる。
[中澤 清]
太陽系外太陽系
バーナード星に惑星が付随していることは1950年代から知られていたが、近年の天文観測技術の格段の進歩により、1990年代なかばから恒星の周りの高精度の惑星系探査が盛んに行われるようになった。その結果、2006年末までに、約200個の系外惑星が発見されている。これら系外惑星の多くは木星級の大きさ(木星質量の10~1倍)であり、軌道長半径も小さい(0.05~1天文単位)。これは、質量が大きく、公転周期の短い惑星が発見されやすいという観測上の選択効果の反映にほかならない。最近では、少数ながら、地球質量の数倍程度の惑星も発見されている。
系外惑星の軌道運動はさまざまで、惑星軌道半径が異常に小さな(0.05天文単位)もの、軌道離心率が異常に大きいもの(0.4~0.6)など、われわれの太陽系とはかなり異なった系外太陽系もみつかっている。また、二重星の一方の恒星周りを回る惑星もみつかっており、太陽系の多様な姿が明らかになりつつある。
[中澤 清]
太陽系起源論の歴史
太陽系の起源に関してこれまでに多くの説が唱えられてきた。それらは二つの考え方に大別される。第一は、太陽と他の天体との遭遇あるいは衝突といった偶然的なできごとに成因を求めるもので、微惑星説、潮汐(ちょうせき)説、連星説などがこれに属する。第二は、太陽の誕生と進化の過程において形成されたとするもので、カント‐ラプラスの星雲説や電磁説、乱流説などがある。また、後述する現代的な形成論もこれに属する。
惑星の形成が初めて書物で取り上げられたのは1745年ビュフォンによる『惑星の起源』であった。その10年後にはI・カントによって星雲説が発表される。カントの星雲説はのちにラプラスにより修正、補強され、今日、カント‐ラプラスの星雲説として有名である。1844年にはフーシェにより「角運動量の困難」が提示された。「太陽系のもつ角運動量の98%は質量がわずか0.13%に満たない惑星によって担われている。この事実を説明することがすなわち惑星形成を説明することである」という議論である。星雲説ではこの問題に明解な解答を与えることができず、1900年ごろより、遭遇説にとってかわられた。
遭遇説にはいくつかの変形がある。T・C・チェンバリンやF・モールトンの微惑星説では、たまたま太陽の近くを他の恒星がよぎり、その潮汐力によって太陽表面から飛び出した物質が微粒子として固化し集積したものが惑星となったと考える。また、J・ジーンズやH・ジェフェリーズが展開した潮汐説は、同様にして飛び出した物質が紐(ひも)状となりそこから惑星が生まれた、とする考えである。H・N・ラッセルやR・A・リットルトンの連星説では、太陽はもともと連星であったが、他の恒星の通過によって伴星が飛び去り、その際、潮汐説と同じような現象がおこったとする。これらの説は一時有力視されたが、1939年L・スピッツァーにより「高温の太陽表面から引き出された物質は固まることはできず雲散霧消する」との決定的な反論が出され、その後、あまり顧みられなくなった。
こののち、C・ワイゼッカーによる乱流説や、H・アルベーンの電磁説が提唱される。乱流説では、原始太陽の周りを回る気体の中に乱流渦が生じ、渦と渦の間に固体微粒子が集められ惑星に成長すると考える。また、電磁説では、原始太陽の周りのプラズマと太陽磁場の相互作用が惑星形成に重要な役割を果たしたとする考えである。しかし今日では、これらの説はいずれも歴史的意味しかもっていない。
現代的な太陽系起源の研究は、原始星の観測や恒星の形成の理論、隕石、月、惑星などの観測を基礎にして、より厳密に物理法則を適用しながら、太陽系のもつ特徴を統一的に説明すべく、1970年代からV・S・サフロノフや林忠四郎らによって始められた。いくつかの問題点を残しているものの、太陽系起源の大筋はしだいにはっきりしてきた。
[中澤 清]
惑星系の形成
太陽および太陽系内天体のもととなるのは、銀河系に漂っていた星間雲である。「雲」とはいってもたいへん希薄低温で、典型的な温度は20K、密度は1立方センチメートルについて10-19グラム程度である。その主成分は水素とヘリウムガスで、のちに惑星や衛星となる固体成分は固体微粒子(星間塵(じん))として星間雲内に浮かんでいる。
この星間雲が自らの引力によって収縮を開始する。収縮を始めてから約100万年たったころ、中心には原始太陽がつくられ、その周りには希薄な円盤状の太陽系星雲が形成される。安定な状態に落ち着いたときの太陽系星雲の温度、密度は300~100K、10-9~10-11グラム/立方センチメートル程度であり、温度、密度ともに太陽から離れるほど低くなっている。また、太陽系星雲の質量は太陽質量の数%程度と考えられている。固体成分は太陽系星雲内に固体微粒子として含まれているが、重要なことは太陽系星雲の温度と微粒子の組成との関係である。小惑星領域より内側では星雲の温度が150Kよりも高く、外側では低い。太陽系星雲程度の圧力の下では、150Kよりも低温では水やアンモニアは固体の状態であり、それより高温ではガスの状態である。すなわち、木星領域以遠では惑星材料物質が金属、石質物質および氷質物質からなり、星雲ガスのうち約1.7%(重量比)が固体微粒子の形で存在している。他方、地球など太陽に近い領域では金属、石質物質のみが惑星材料物質であり、星雲ガスのうち、わずか0.34%(重量比)にすぎない。のちに知るように、このことが木星型惑星と地球型惑星の差を生み出し、また、小惑星形成とも深く関係しているのである。
太陽系星雲内に浮かんだ固体微粒子は星雲ガスとともに太陽の周りを回っているが、しだいに星雲赤道面に沈降し始める。そして、1000~1万年でほとんどの固体微粒子は星雲赤道面近くのきわめて薄い層に集中してしまう。この層のことを固体層とよんでいる。固体層は比重の大きい微粒子が集まっており、それだけ密度も高い。そして、固体粒子群のつくりだす引力が太陽の引力を上回るようになり、重力的に不安定となる。その結果、1枚の薄い円盤であった固体層がばらばらに分裂してしまうのである。分裂破片の大きさは直径約10キロメートルで、火星の衛星や彗星の大きさに匹敵している。この分裂破片はもはやれっきとした天体であり、微惑星とよんでいる。組成は、固体微粒子の組成を反映し、小惑星軌道以内ではミリメートル~センチメートルサイズの岩石質、金属質の固体粒子からなり、また、低温の遠方領域では、氷質の粒子が大部分を占める。
太陽系全体でつくられる微惑星は10兆個にも及ぶ。これらは太陽系星雲ガス中にあって、太陽の周りを回りながら互いに衝突を繰り返す。微惑星は星雲ガスからつねにガス抵抗力を受け、そのため、衝突速度は小さく抑えられている。微惑星どうしの衝突がおこったとき、高速度であれば微惑星は破砕されてしまうだろう。しかし、低速度衝突の場合、衝突すれば互いに合体し、大きな微惑星へと成長していく。月程度の大きさにまで成長した天体を原始惑星とよんでいる。原始惑星はさらに微惑星を集積して成長を続ける。地球の場合、現在の大きさにまでなるのに数百万年から1000万年かかると推定されている。また、木星領域では、木星の中心核(地球質量の10~15倍)にまで成長するのに1000万~2000万年とされている。惑星の成長時間は一般に太陽からの距離が遠いほど長い時間を要することが知られている。おおむね太陽に近い惑星から成長が完了していったのである。
原始太陽は形成されてから約2000万年までTタウリ段階とよばれる進化段階にある。このころの太陽は表面活動がたいへん激しく、強い紫外線や太陽風を吹き出している。Tタウリ型星の観測によれば、紫外線の強度は現在の太陽の1万~10万倍も強いことが知られている。この強い紫外線や太陽風によって太陽系星雲はしだいに散逸し、惑星間空間は今日みられるような希薄な状態となったと考えられている。
微惑星から原始惑星への成長は太陽系星雲のガスの中で進行する。それゆえ、原始惑星は円運動している星雲ガスからつねに抵抗を受け、太陽赤道面内の円軌道からあまりずれることはできなかった。惑星がほぼ同一面内を円に近い軌道に沿って運動しているのはこのようなガス抵抗作用の結果と理解される。太陽系星雲ガスの影響はこれにとどまらない。月のサイズよりも大きく成長した原始惑星では自らの引力も強くなる。この引力によって周りの星雲ガスを原始惑星重力圏内に引き付け、濃い大気を形成する。この大気は水素とヘリウムが主成分であり、現在の大気と区別して原始大気とよんでいる。原始惑星の質量が大きくなればなるほど引き付けられる大気量は増える。地球サイズにまで成長した原始惑星では、大気総質量が1026グラムにもなる。原始大気は地球型惑星の形成にも、また木星型惑星の形成にもたいへん重要な役割を果たすことになる。
木星領域では星雲ガスが散逸する前にすでに木星の中心核は地球質量の5~10倍に成長している。その周りには膨大な量の原始大気が引き付けられ、大気質量は原始惑星の質量に匹敵するほどである。このような状況になると大気は力学的安定さを失ってしまう。それまで原始惑星の重力圏に広がっていた原始大気は原始惑星表面に集中し、大気の主成分である水素やヘリウムが惑星に取り込まれてしまうのである。希薄になった惑星重力圏にはさらに星雲ガスが流れ込み、このガスもまた惑星に取り込まれてしまう。このようにして、木星は大量のガスを取り込んだ結果、巨大な、しかし平均密度の小さな惑星になったのである。
土星以遠の惑星でも同じ過程が介在したはずである。しかし、太陽から離れるほど原始惑星の成長に長時間を要し、十分成長する前に星雲ガスが散逸してしまう。そのため、取り込める星雲ガスの量は少なかったのである。これが遠方の木星型惑星ほどガス成分の量が少ない理由である。
原始大気の存在は地球型惑星の形成、進化にも重大な影響をもつ。地球型惑星の場合、成長が完了するまで星雲ガスは存在している。すなわち、原始惑星はつねに原始大気をまとって成長してきたのである。現在の地球大気と同様に原始大気も保温効果をもつ。原始大気では大気量が多いためその効果はたいへん強い。原始惑星が現地球質量の6分の1以上の大きさになると、保温効果のため原始惑星の表面温度は融点を超える。地球の大きさにまでなったときには、実に1800Kを超える高温となる。このように、地球型惑星は灼熱(しゃくねつ)の状態で成長したのである。
原始地球表面の温度が惑星物質の融点を超えると、集積してきた微惑星は短時間のうちに溶け、金属と岩石物質が分離する。そして重い金属は沈殿し、原始地球は三重構造になる。すなわち、中心に低温で金属、石質物質の混じった原始中心核があり、その周りに金属層、最上部に溶融した石質層が取り巻いている。比重の大きい金属層が中間に挟まった構造は不安定で、そのうち原始中心核と中間金属層が逆転し、今日みる金属中心核・マントル構造に至ったと考えられている。
[中澤 清]
太陽系内小天体の起源
小惑星、衛星、彗星、隕石など太陽系内小天体の起源については多くの説が提唱されているが、いまだ確定的なものはない。しかしこれら小天体の起源も以下のように惑星形成過程の自然な延長として理解できる。
太陽系の形成が始まって約1000万年のころ、小惑星領域では惑星成長がまだ十分進んでおらず、月サイズ以下の原始惑星、微惑星が多数存在していた。同じころ、地球や火星はほぼ現在の大きさにまで成長している。太陽に近いほど成長が速いからである。他方、木星領域でも原始木星はほぼ成長を完了している。この領域では氷成分が惑星材料物質に加わっており、小惑星領域より遠方にあるにもかかわらず材料物質が多いため惑星成長が速いのである。形成開始後1000万~2000万年のころ、太陽系星雲ガスはしだいに散逸し、惑星間空間は希薄になる。ちょうどこのころ成長を終え巨大な惑星となった木星は小惑星領域まで摂動(せつどう)を及ぼす。木星に振り回されたうえに、衝突速度を抑制していた星雲ガスがなくなったわけで、小惑星領域の原始惑星や微惑星の速度はしだいに増大する。そして相互の衝突は激しいものとなって、成長とは逆に小砕片に砕かれてしまう。これが火星と木星の間に多数の小天体が存在する結果を招いたのである。
当初、小惑星帯には、現在知られている小惑星の数の約1000倍ほどの天体が存在したと推測されている。それらは木星から長年月にわたる摂動を受け、軌道がしだいにずれ、大部分は木星に、一部は火星や地球に衝突して、今日ではそのほとんどが失われてしまった、と考えられている。現在でも、小惑星帯やアポロ・アモール型小惑星群から小さな破片が飛来し、地球表面に落下する。これが隕石である。隕石には高速衝突の痕跡(こんせき)が残っており、他方、小惑星の反射特性と隕石の反射特性の類似性も知られている。小惑星が隕石の母天体であったとするのは自然な考え方であろう。
惑星の成長がほぼ完了し太陽系星雲が散逸したあとも、惑星に取り込まれなかった微惑星や原始惑星などの小天体が残っている。とくに惑星成長の遅い木星型惑星の領域ではかなりの数の小天体が存在したはずである。取り残された小天体が星雲散逸時あるいはその後惑星に遭遇し、ときおり惑星重力圏に入ることもおこっただろう。このような小天体に待ち受けている運命は次の三つのうちのいずれかである。一つは惑星と衝突することである。この場合、惑星の成長に寄与するだけで特別なことはおこらない。第二の可能性は、惑星から大きな摂動を受け、跳ね飛ばされてしまうことである。惑星重力圏からふたたび脱出し、これまでとはまったく違った離心率や軌道面傾斜角の大きい軌道に入る。何度も惑星と接近するうちに、太陽赤道面内に集中していた微惑星もしだいにいろいろな軌道面傾斜角をもち、太陽の周りに球状に分布するようになる。また、離心率も極端に大きくなり、長楕円(ちょうだえん)軌道を描くようになる。これらが彗星にほかならない。上述のような軌道運動の特性に加えて、木星型惑星領域の微惑星が直径10キロメートルほどの、砂や金属粒子を含んだ氷塊であることも彗星の特徴に符合している。
第三の可能性は、惑星重力圏に入った小天体が潮汐力の作用などで、重力圏内に捕獲され、惑星の周りを回り続けることである。これが衛星である。木星型惑星の領域では多くの小天体が惑星に取り込まれず残っていた。そのためそれらが惑星重力圏に突入する確率も増える。こんなわけで木星型惑星には多くの衛星が付随しているのだろう。重力圏に多くの小天体が入ると、小天体どうしが衝突することもおこる。そして多数の小さな破片に砕かれ、そのうちの一部分は衛星としてとどまる。たいへん小さな衛星はこのようにしてつくられたと推測されている。
衛星には惑星から潮汐力が働いている。この力のために、たとえば、月はしだいに地球から遠ざかっている。順行衛星の場合、潮汐力は衛星の軌道半径を大きくする方向に働くが、逆行衛星の場合には逆に軌道半径を小さくするよう作用する。その結果、逆行衛星はしだいに軌道半径が小さくなり、ついには母惑星のロッシュ限界内まで突入する。ロッシュ限界内では衛星が安定には存在できず、粉々に砕かれてしまう。このような砕片が惑星の周りに同心円状に広がり、惑星の環を形成したと考えられている。
海王星以遠では、惑星の成長はきわめて遅く、いまだに惑星の成長が続いている、ともいえる。理論的な見積りによると、この領域では、太陽系の年齢(45億6000万年)をかけてやっと50~100キロメートルサイズの天体になる。この領域に100キロメートルサイズの多くの小天体(カイパーベルト天体)が観測されているが、これらは成長途上の原始惑星とも考えられる。
[中澤 清]
『中澤清編『太陽系の構造と起源』(1979・恒星社厚生閣)』▽『松井孝典他著『岩波講座 地球惑星科学1 地球惑星科学入門』(1996・岩波書店)』▽『松井孝典他著『岩波講座 地球惑星科学12 比較惑星学』(1997・岩波書店)』

太陽系惑星の軌道

太陽と惑星の大きさ比較

地球と木星の内部構造模式図

カント‐ラプラスの星雲説

ワイゼッカーの乱流説

ジーンズ‐ジェフェリーズの潮汐説

原始太陽と太陽系星雲、固体層の形成

原始地球の内部構造

太陽

水星
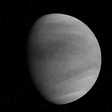
金星

地球

火星

木星

土星

天王星
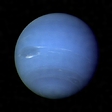
海王星

冥王星

月
知恵蔵 「太陽系」の解説
太陽系
(土佐誠 東北大学教授 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太陽系」の意味・わかりやすい解説
太陽系
たいようけい
solar system
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「太陽系」の意味・わかりやすい解説
太陽系【たいようけい】
→関連項目地球
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...






