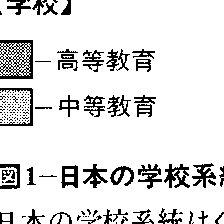精選版 日本国語大辞典 「学校」の意味・読み・例文・類語
がっ‐こうガクカウ【学校】
- 〘 名詞 〙 一定の設備と方法によって、教師が児童、生徒、学生に継続的に教育を施す所。日本では近江朝に始まり、大宝令で制度化された。その後、時代により変遷し、現在は、教育基本法、学校教育法などで設立、運営されている。学校教育法では小・中・高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校、幼稚園をいい、料理学校などの各種学校はこれに含めないが、通称としては各種学校も含めて広く用いられている。学院。学黌(がっこう)。
- [初出の実例]「人皆忩忙、代不レ好レ学、由レ此学校凌遅、生徒流散」(出典:家伝(760頃)下)
- 「さて王公の高位の子弟も庶人の賤きも一つ学校にごたまぜに入ると云ことにてはなし」(出典:大学垂加先生講義(1679))
- [その他の文献]〔詩経‐鄭風・子衿・序〕
学校の語誌
大宝令で、中央に大学、地方に国学が置かれ、官吏を養成した。平安初期には、藤原氏の勧学院、和気氏の弘文院、空海の綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)などの私学が生まれ、平安中期以後は、官吏の世襲により学校は衰えたが、中世に北条実時の金沢文庫、上杉憲実の足利学校が開かれた。禅宗寺院の塾は寺子屋の源流になり、江戸幕府は昌平黌をはじめ、専門学校を設立した。
改訂新版 世界大百科事典 「学校」の意味・わかりやすい解説
学校 (がっこう)
学校とは何か
学校とは,少なくとも,次の3条件を備えた教育施設を指す。(1)そこに学ぶ者の心身の発達や学力の水準に即し系統だてて配列された教育内容が用意されていること,(2)教師と複数の生徒による教科の授業(集団的な教授=学習の過程)と,学校行事,クラブ活動など教科以外の諸活動とが行われていること,(3)校舎や運動場など教育用の特別の施設を備えていること。しかし,すべての学校がこの3条件を備えているのではなく,例外も多い。(1)については発達の段階を考慮せず,おとなの読む古典を,意味が理解できなくともそのまま暗記させたり,易から難へと系統だてた教材配列をとっていないことがあり,(2)については,一対一の授業もあれば,複数の教師による指導もある。また(3)では,独自の施設ではなく寺院や一般民家などを利用する例もあった。したがって学校をひと言で定義するのは難しいが,日常生活や労働の現場で学ぶのではなく,そこを離れて,生産に必要な技術や,その社会の伝統である倫理的・宗教的価値や禁忌について,一定の時間まとまった学習を行う場であることは共通である。
では,このような教育を行う学校はいつ成立したのか。学校が万人のために存在することは,20世紀後半の日本では当然とされている。しかし人類の歴史のなかで,学校が今日ほど普及したのは古いことではない。見方にもよるが,学校の急激な普及は欧米や日本でも19世紀後半からであり,第三世界ではその普及は遅れ,20世紀最後の四半世紀にいたっても,なお文盲率が50%を超える国がある。ただし一部の階層のための学校となると,歴史は古い。しかしその古さも,人類の教育の歴史のなかでは新しいものといえる。
学校の起源
〈学校〉の語は,古代中国の《孟子》にある〈設為庠序学校,以教之〉に由来しており,この国の学校の起源は古く,周の時代にさかのぼることができる。庠,序ともに学校の意をふくんでいる。ヨーロッパの場合,ギリシア語では閑暇scholeを意味し,ローマでも学校ludusは同じ意味をもっていた。これらは,学校が奴隷制なしには成立しなかった自由人のための教育機関であったことを示している。さらにさかのぼると古代エジプトやバビロニアにも学校があった。ナイル川の洪水記録を保存し,領地の境界の測量を行ったりするため,読み書きのできる書記が為政者にとって必要となったころ,エジプトの一高官は息子に〈おまえの母を愛するように文字を愛しなさい〉と助言し,文字による知識を獲得することによって,〈おまえはいかなる種類の肉体労働からも解放され,高名な行政長官になることができる〉という,励ましの手紙を書き送っていた。興味深いことに,このような内容の手紙が《学問をたたえる歌》という標題の教訓集として編集され,学校の教材として使われていたのである。生活に必要な知識や技術を次の世代に伝えるための教育はどんな時代にもあったが,学校の成立に必要不可欠な条件は,生産力の向上と文字の発明であった。生産力の向上によって余暇のできた支配者層が,文字による知識を習得し,社会を支配するために学校を設けるようになったのである。
学校ができれば,そこでどのような教育方法をとるべきか,が問題となる。古代ギリシアのアカデメイアを例にとると,まずプラトンは講義形式による教育はほとんど行わず,一問一答により学習に助言を与え,研究を組織する方式をとった。彼は,教える者と学ぶ者とがともに生活し,対話を重ねるなかで魂に点火し,それをみずから育てることが大事だと考えていた。これに対してアリストテレスは講義を行ったものと思われる。今日残されているその著作は,彼の講義のための覚書であり,講義に先立って彼は,学ぶ者の学習過程を想定し,それにそって周到な準備を重ねたものと推定されている。ここには対照的な教育方法がみられ,学校教師による教育方法の工夫・改善はその後も続けられ,今日にいたっている。
学校の歴史--宗教と学校
近代以前の学校は,宗教と密接な関係があるので,以下主要なものをとりあげておく。
儒教の場合
儒教(儒学)は,孔子が古先聖の道を集大成し,仁によって一貫した人道を実行することを徳とした教えであり,〈儒〉には〈武〉の力に対し〈文〉の理の意がふくまれている。大学の道,つまり君子の学の目的については〈明徳を明らかにするにあり,民を親(あら)たにするにあり,至善に止まるにあり〉(《大学》)とされ,徳性が重視された。学校については〈礼儀相先んずるの地にして,月々に之れをして相争わしむるは,殊に教養の道に非ず〉(《小学》)というように礼儀を重視し,毎月成績を争わせるのは学校の本来の目的ではないとしていた。しかし実際は科挙という試験の通過が士大夫への道であり,まさに月々の成績は統治官僚を志す者として軽視できぬものとなっていた。学校制度は唐の時代に中央教育行政官庁である国子監の下で整備され,貴族の子弟を入学させる国子学をはじめ,階層に応じ大学,四門学,律学,書学,算学が設けられた。儒教は漢代に中国の国教となり,以後清朝にいたるまでその地位を占め,1919年の五・四運動において初めて徹底的に批判された。儒教は6世紀の初め日本に入り,やはり統治の手段としての役割をもたされ,とくに徳川幕藩体制の下では,武士道と結びついて厳格に解釈され,それにもとづく人間像が手本として人民教化のために利用された。
イスラムの場合
7世紀に創始され,今日6億の信者をもつといわれるイスラムの社会では,多くの父母は子どもが宗教心をもつ人間に育ってほしいと期待し,早くからコーランにもとづく厳しいしつけをしてきた。近代学校制度成立以前には,子どもはクッターブkuttāb(〈学校〉を意味するアラビア語)という初等教育機関に通った。この学校はイスラムの歴史とともに古く,各地の町や村にあり,ごく基礎的な読み書き算の教育のほかはコーランの暗誦であった。修業年限,施設などに決まりはなかったが,5,6歳から12歳前後までの子どもが通っていた。クッターブに続くのは,地方の中心都市に設けられていたマドラサmadrasa(〈教育施設〉を意味するアラビア語)であり,これはウラマー`ulamā'(学者・宗教指導者層)育成を目的とする高等教育機関である。教育内容の中心は法学で,コーラン諸学,ムハンマド(マホメット)の伝承,神学,言語学などのほか,数学,天文学,医学など,イスラムにとって外来の学問文化がふくまれることもあった。授業はイスラム教徒の礼拝堂であるモスクで行われることが多かったが,マドラサ専用の施設もあり,大規模なところでは数十名の教師,数百名ときには1000名を超える学生をかかえ,奨学金や宿舎が提供されたりした。さらにアズハル(10世紀,カイロに設立),ニザーミーヤ学院(11世紀,バグダードに設立,その後主要都市に設立)など最高学府も整えられた。大学が法令によりモスクから分離するのは1936年のことである。
キリスト教の場合
世界の近代文化・思想,したがってその形成に寄与する学校に最大の影響を与えたのはキリスト教である。キリスト教系の学校は,初期にはユダヤ教のシナゴーグの方式をとり入れていたりしたが,2世紀にはキリスト教洗礼志願者向けの学校としてカテキューメンの学校がアレクサンドリアなど小アジア各地につくられた。政治的・思想的迫害にもかかわらずキリスト教へ改宗しようとする者のために,修業年限2~4年でキリスト教の基礎知識を習得させることを目的としていたが,幼い子どもに洗礼を受けさせる風習が広がり,この学校は5世紀には衰退した。同じく2~3世紀にかけて,やはりアレクサンドリアなど東方都市に,神学のほか,キリスト教の立場からギリシア・ローマの文化をも教える問答学校ができた。教授法として問答法を採用し,異教徒をも入学させ,キリスト教文化史上大きな役割を果たしたが,4世紀以降,教会生活の変化とともに,本山学校,僧院学校に変わった。変化をもたらした最大のものは,313年のコンスタンティヌス1世(大帝)による信教の自由を定めたミラノ勅令の公布であり,これによりキリスト教は国家の保護の下に置かれることになり,人々の生活に強い影響を与えるようになった。そして6世紀末のグレゴリウス1世の教皇就任から16世紀のルターによる宗教改革までのほぼ1000年の間,ヨーロッパの学校はキリスト教の支配下に置かれることになった。16世紀,ルターによる宗教改革がキリスト教学校に与えた影響のうち重要なのは初等教育の重視であり,ここで段階に分けた教育課程編成が始まり,学年制の端緒となった。
近代学校の出発
学校の世俗化
このころから,長い期間教会の支配下にあった学校への批判が強まり,モンテーニュは,圧制的な学校のあり方や単なる博学を批判し,17世紀には,F.ベーコンの〈知は力なり〉という知識観を受け継ぎ,チェコスロバキアのJ.A.コメニウスが,反封建・反教会の立場から,平和主義と普遍人類的な知識体系の確立を目ざし,教授学の確立に尽力し,近代教育への道を切り開いた。彼は,神は神の前では個人の身分は問わぬのだから,ある種の人々だけの知能を開発するのでは不公平であるとし,すべての人にすべてのことを教える技術の創造の必要を説き,学習全体を精密に学年に区分し,先の学習が後に続く学習への道を平らにし,それを照らすたいまつにすることを提案していた。イギリスのJ.ロックも,当時の学校におけるスコラ的な古典知識のつめ込みに強く反対し,伝統的な修辞学や論理学より数学の教育を重視していた。
ロックや,それに続くルソーにみられるのは,家庭教育の重視である。人間にとって自由・平等が重要であると自覚した近代市民革命では,精神の自由を獲得するうえで教育は権利として重視され,その自由にとって学校という集団で行う教育はなじまないと考えられた。しかし,ルソーの《エミール》に書かれている家庭教師による一対一の教育はあまりに特権的であり,現実的でないことは明白であった。そこで公費による平等の学校教育が構想されるようになる。その成果は,まず新興のアメリカにあらわれた。独立宣言に先立つバージニア権利章典(1776)以来,すべての人は生来ひとしく自由かつ独立であることが強調され,公立・無償の学校への道が開かれた。ついでフランス革命期には,ジロンド派憲法草案(1793)で〈初等教育は,すべての者の需要であり,社会は,すべての構成員に対し,平等にこれを引き受けるものである〉とされ,同年のモンタニャール派(山岳派)憲法でも,教育はすべての者の需要であるとしたうえで,〈社会は,その全力をあげて一般の理性の進歩を助長し,教育をすべての者の手の届くところに置かなければならない〉とされていた。ジロンド派に属し革命後の教育計画をたてようとしたコンドルセは,教育の自律性確保のため,教育を宗教的権威から独立させると同時に行政的権力からも独立させようと試み,教育行政権を学者・知識人の互選による国立学術院にゆだねるとの構想をたてた。学校は小学校,中学校,アンスティテュinstitut(社会の指導層の養成機関),リセlycée(大学),国立学術院(学術研究のほか,公教育の監督・指導を担当)から成るとし,無償とするほか,貧困家庭の子どもの優れた者のために奨学制度を構想した。これらの構想は,革命政府の下では実現されなかったが,教育を権利としてとらえ,学校教育の世俗性や無償を目ざすことは,その後,近代教育の原則として認められるようになった。
産業革命と学校
一方,中世末期以来,手工業の発展とともに,同業組合学校や徒弟学校,さらに実科学校などが設置されるようになっていたが,学校が特定の上層階級の人のものでなく,広く一般民衆にとっても必要不可欠の存在とみられるようになるのは,産業革命に続く19世紀中葉のナショナリズムの高揚をまたなければならなかった。フレーベルは,人間は少年時代になると〈学校の人Schüler〉になるといった(日本では中国渡来の〈学童〉の語を,明治以来小学生にあてた)。彼によれば,学校は〈人間が自己の外にある事物やその本質を,それらに内在している特殊な法則や普遍的な法則に従って認識するように導かれるところであり,またその認識に到達するところ〉である。外的なもの,個別的なものが学ぶ者に提示され,これを通じて内的・普遍的なものに到達するよう導かれるところが学校であるとされたのである。このような考えは教育学の発展を促し,それが教師の力になっていくが,しかし当時の産業革命は教育理論よりも当面の必要を満たすことを求めており,熟練労働者の育成のため,一定の学力を習得させる場としての学校教育の普及が緊急の課題となった。大量の教育の普及には,生徒を有効に編成し,教育の効果をあげなければならなかった。イギリスのベルAndrew Bell(1753-1832)とランカスターJoseph Lancaster(1778-1838)は,数百人の生徒を集めた学校で,祈禱・朗唱などは一人の教師が指導し,進度に応ずる必要のある科目の場合はいくつかのグループに分け,学力の高い年長者を助教monitorとして指導にあたらせる方式をとり,これがベル=ランカスター方式(またはモニトリアル・システム)と呼ばれ,産業革命以後に採用された。しかし義務教育の普及とともに組織だった教員養成がすすみ,数十人の学級編成がとられるようになったが,一斉指導の方式は引き継がれた。日本でも,個別に手習いを指導していた寺子屋から近代学校への転換のさい,一斉指導に切り替えられた。
複線型学校と統一学校運動
ヨーロッパでは義務教育制度が成立した19世紀後半にいたっても,なお独自の初等教育段階の学校をともなう伝統的な中等学校が存続した。イギリスのパブリック・スクールpublic school,フランスのリセ,コレージュcollège,ドイツのギムナジウムGymnasiumがその代表的なものである。そこでは男女別学で,古典語教育が重視され,社会の指導者層の養成を目的に教育が行われてきた。これに対し,中等教育機関を,民衆のための初等学校primary schoolに接続する中等学校secondary schoolとして,階梯制ladder systemに位置づけようとする改革の動きが出てきたのは,19世紀末から20世紀にかけてである。さらに前述の伝統的な中等学校をもこれと一元化しようとの動きがヨーロッパ各国で始まり,これは統一学校(ドイツ語Einheitsschule,フランス語école unique)運動と呼ばれている。ドイツでは1907年,社会民主党が,学校の階級的性格を排除した統一学校制度を提唱し,第1次大戦後ワイマール共和国は憲法(1919)で,万人に共通の基礎学校Grundschuleの上に中等・高等学校が構築されること,その学校は職業の多様性に応じてつくられること,またそこへの入学のさい家庭の経済的・社会的地位や宗派が基準とされてはならないことなどが定められた。フランスでは,第1次大戦中から統一学校を提唱していた民間団体の一員であるE.エリオを党首とする急進社会党が,24年政権を握るや,統一学校委員会を設置して学校制度改革案を練り,中等学校無償法を成立させた。ついで37年,社会党内閣の下で初等・中等学校改革案が国会に提出されたが,実施にいたらなかった。この改革案はイギリスに影響を与え,1944年教育法(バトラー法)によって統一中等学校制度へ向かうことになった。それは,5歳で入学する6年制初等学校(プライマリー・スクールprimary school)を統一基礎学校とし,その上に中等学校を接続させるという方式だが,中等学校は文法学校(グラマー・スクールgrammar school),技術学校(テクニカル・スクールtechnical school)および高等小学校を昇格させた近代学校(モダン・スクールmodern school)の3本立てであり,これを単一の総合中等学校(コンプリヘンシブ・スクールcomprehensive school)に統合する試みは,第2次大戦後,とくに労働党政権の誕生をまたなければならなかった。
ソビエト連邦では社会主義革命後の一時期,学校死滅論があらわれた。それは,大衆が建設・闘争・実践のなかで学ぶことが多くなり,学校は死滅するというもので,学校でクラブ活動が行われ,学校が地域や家庭における子どもの作業を組織したり,児童読物を提供したりする等々,学校の意義・役割が無制限に大きくなるとともに,学校が学校としての存在を停止し,子どもは学校外の野原や工場でいよいよ活動するようになるという説であった。一見新しいこの考えは,左翼日和見主義的傾向と批判された。労働・生活のなかで子どもが学ぶということは確かにあるが,系統的な教授の放棄によって,社会発展を抑えることになるとされた。こうしてソ連でも学校の拡充が重要な政策の一つとなった。1918年,統一労働学校令により9年制統一学校制度が出されたが,34年これを廃し,初等学校のみの4年制,初等4年と中等3年の7年制,これに2年の中等後期を加えた9年制という3種類の学校制度が定められた。これは地域の実情を考慮した制度であり,順次9年制への移行がすすめられた。
早くから複線型の学校制度を脱却したのはアメリカであり,H.マン(1796-1859)は自然法的権利としての教育を受ける権利を強調し,この考えから公教育費の増額,学校数を増加させる運動がすすんだ。さらにこれを受けて,1860年代には統一基礎学校としての初等学校(コモン・スクールcommon school)がつくられ始め,19世紀末には,これに中等学校(ハイ・スクールhigh school)を接続させる方式がとられるようになった。その多くは8・4制であり,20世紀に入って初等学校最終の2学年と中等学校の第1学年とをあわせて下級中学校(ジュニア・ハイ・スクールjunior high school)を設け,6・3・3制がほぼ半分の州で実現した。以上のように,欧米諸国では第1次大戦後,教育を受ける機会の均等実現の主張は強くなり,〈中等教育をすべての者にsecondary education for all〉のスローガンをかかげて中等学校の拡充がすすめられた。しかし,統一学校運動が推進され,また政府も改革案作成に努力したにもかかわらず,イギリス,フランスなどではエリート養成のための伝統的中等学校,さらには初等学校さえ,第2次大戦後まで温存され続けたのである。
日本の学校
近世以前の学校
日本で初めて〈学校〉の名を冠した教育機関は,栃木の足利学校だが,その起源は中世とされているものの明確ではない。15世紀,永享年間(1429-41)に校規が整備されて学校として再興され,16世紀にはF.ザビエルやL.フロイスら宣教師により総合大学としてヨーロッパにも紹介されるほど盛んとなった。しかし,〈学校〉の名をつけていないとしても,日本には足利学校より古い時期に学校が設けられていた。学校制度の確立を促したのは唐の文化であり,天智天皇の時代に大津に儒教の学校がつくられたといわれるが,今日伝わる最古の教育法令は701年(大宝1)の〈大宝律令〉にふくまれている。そこでは,首都に大学(または大学寮)のほか,職業専門教育機関として陰陽寮,典薬寮,雅楽寮を設け,地方に国学を設けるという方針が示されていた。大学,国学の重要な教材は《孝経》《論語》など中国の古典であった。しかし平安中期以降,各地に戦乱が起こって国学は廃止され,大学も12世紀,治承年間(1177-81)に焼失し再建されなかった。唐の制度を模したこれらの学校は官吏登用のための官学であり,一方,有力氏族が一門の子弟のために私学を創設する例も多く,藤原氏の勧学院,橘氏の学館院,和気氏の弘文院などがその代表的なものであった。以上にあげた学校が上流社会の子弟のみに門戸を開いていたのに対し,庶民のための学校として例外的に設けられたのが,空海による綜芸(しゆげい)種智院で,設立は828年(天長5)あるいはその数年前と推定されている。綜芸は仏・儒・道の三教を指すのかどうか明白でないが,種智は菩提心を育てることであり,彼の著作《三教指帰》からも明らかなように,仏教の教育に力を入れようとして設立されたのである。この学校は庶民の子弟のための最初の学校として注目されることが多いが,835年(承和2)の空海の死去以後は衰退する。衰退の最大の原因は,空海の予想に反し,当時なお入学を希望する庶民の少年が少なかったところにあるといわれる。
その後,鎌倉,室町と戦乱の続く時代に学校は衰退し,わずかに前掲の足利学校や神奈川の金沢(かねさわ)文庫が隆盛を迎えたほかは,キリシタン学校が注目に値する。F.ザビエルが鹿児島に到着したのが1549年(天文18)であり,77年(天正5)には豊後領内の府内(現在の大分市)に最初の学林(コレジヨ)設立計画をたて,その3年後に実現し,肥前の島原半島では新管長A.バリニャーノによって79年,学林と修業所(セミナリヨ)が設立されている。さらにこれら九州地方だけでなく,翌80年には近江の安土城下にセミナリヨが建てられ,本能寺の変までのわずか1年余りであったが,多くの人材を養成した。87年の秀吉によるキリシタン禁令により,九州の有馬,天草に移り,91年から6,7年間,天正末期から慶長初期にかけ学林は活発な活動を行い,さらに長崎に移っても盛大であった。京都でも秀吉没後17世紀初頭に復活したが,鎖国(1639)により活動は完全に抑えられた。キリシタン学校では神学のほか,哲学,論理学,さらに天文学,数学,医学などの初歩も教えられていたと推測されており,半世紀余りの期間ではあったが,日本の文化に大きな影響を与えた。
幕藩体制下の学校
天下統一を果たした徳川家康は学問を重視し,藤原惺窩(せいか)門下の林羅山を登用した。彼は朱子学の立場から儒学の基本である修身・斉家に始まる治国・平天下を説いて幕藩体制の理論的基礎を提供し,1630年(寛永7)には,幕府から与えられた江戸上野の忍岡の土地に塾を開き,幕府の最高学府となる昌平黌(昌平坂学問所)の基礎をつくった。これは,市井の学者による批判を受けながらも,幕末の国学,蘭学の高揚を迎えるまで権威を保ち続けた。江戸時代の学校としては,このほか,藩校(藩黌,藩学),郷学,私塾,寺子(小)屋などがあり,戦乱のない社会で,それぞれ発展した。藩校は各藩が藩体制強化のため武士の子弟に儒学と武道を教授することを目的として設置された。寛永年間(1624-44)に始まり,急速に増加するのは18世紀中葉,延享年間(1744-48)以降である。19世紀中葉,文久・慶応(1861-68)のころからは庶民の子弟を入学させたり,蘭学や,さらにすすんで広く洋学をとり入れる藩校も増えた。藩という国の強化を目的とする藩校の基本的性格や漢学中心の教育内容は,明治の〈学制〉以降,国家有為の人材を養成しようとする中等学校に受け継がれた。
藩校が武士のためのものであったのに対し,庶民の教育機関として自主的につくられたのが,寺子屋である。室町中期に始まり,江戸中期以降,商業の発展とともに急増する。寺子屋の教育内容といえば読み書き算(そろばん)が浮かんでくるが,読み書き,とくに手習いが中心であり,算は幕末になって増加する。徳川吉宗が手習い師匠に《六諭衍義大意(りくゆえんぎたいい)》を配布し,寺子屋を教化の機関にしようとしたこともあったが,寺子屋は何といっても町人,農民の生活の必要から出てきた要求にこたえる初等教育機関であった。〈学制〉以降,小学校が急速に普及するのは,寺子屋が基盤としてあったからにほかならない。
藩または民間有志によって設立され,藩校と寺子屋の中間にあったのが,郷学である。そのうち,一つは城下から遠い地に藩士の教育のために建てられたもので,これは藩校に近い。第2は一般領民のための教化機関で,19世紀中葉以降,藩の設立が多くなる。教育内容は読み書きそろばんで,読み書きの内容が寺子屋より高度であった。郷学がもっとも増えるのは明治維新直後であり,この時期には藩の直営や民間人設立ではなく村立が激増し,〈公立〉という考えの基礎を形成し,実際に大部分の郷学は学制以降,公立小学校に転身した。江戸時代のもう一つの重要な学校は私塾である。幕府や藩の学校に対し市井の学者が自宅などを教場として開いたものである。中江藤樹,伊藤仁斎,荻生徂徠さらに広瀬淡窓らがそれぞれの学問的立場を明確にしながら弟子を養成し,幕末には緒方洪庵らのように洋学塾を開く者が増え,一方,吉田松陰の松下村塾に代表される,下級武士を対象とし社会革新を目ざす武士の養成を行う塾もあらわれた。官立の学校がともすると固定した学問に停滞しがちな傾向をもつのに対し,私塾は,これを批判し,さらに積極的に新しい学問にとり組み時代を切り開く役割を果たすことがあった。
江戸時代には学校制度は整えられていなかったし,階層によって違う学校が用意されていた。しかし当時のどこの学校でも,ほぼ共通の教材とされていたのは《論語》で,その冒頭は学問する喜びを述べた文であり,また寺子屋で広く使われた《実語教》の冒頭でも人間にとって智が大切だと説かれており,これらは人々の学習意欲を高め,学問尊重の気風を広げ,後の学校普及の土台となった。しかし幕末,開国を迫られ,欧米による植民地化の危機に迫られたとき,旧来の教養では対抗不可能であり,急速に欧米近代科学技術の導入が必要となり,そのための人材育成に向けて学校制度を整備することが為政者にとって緊急不可欠の課題となったのである。
近代学校への移行
日本の近代学校は1872年(明治5)の〈学制〉公布に始まる。この〈学制〉公布にあたって出された〈被仰出書(おおせいだされしよ)〉(太政官布告)では,学校が設けられて久しいが,その方向を誤っていたとして,今後は華・士族に限らず,農工商および婦女子も学問をすべきであるとした。とくに重要なのは高度の学問は当人の才能に任せるが,〈幼童の子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものは其父兄の越度たるべき事〉というように,小学校教育を重視していたことである。しかも,従来の誤りは学問をするのは国家のためであるとされていたところにあるとし,今後は,各人が身を立てるために学問をすべきであるとした。学校は大学,中学,小学の3段階にわけ,全国にそれを配置し,そのほかに師範学校を設置するという壮大な計画がたてられ,旧来の藩校や寺子屋を利用するほか,新しい学校を創設する努力が続いた。学校では能力主義による人材登用が重視され,厳格な試験による進級の方式がとられ,その試験を突破した人間像は森鷗外の《舞姫》などに描かれ,また試験の苦しさは夢に見るほどであると正岡子規が《墨汁一滴》に記している。
民衆には読み書き能力を習得したいという要求があったものの,その要求とくい違う教育内容や学校建設にあたっての過重な経済的負担への不満から学校焼打事件が各地で起こった。79年には,自由教育令といわれる教育令が出され,強制的・画一的性格を改め,町村の小学校経営上の困難や親の負担を軽減する措置がとられ,また学校設置の資力の乏しい地方では教員巡回による教育という方式をとってもよいとされた。この教育令では学校の種類は小学校,中学校,大学校,師範学校,専門学校のほか,〈各種ノ学校〉とされた。この自由教育令により就学率の低下や校舎建築中止などが起こり,文部卿河野敏鎌は〈苟モ文明ヲ以テ称セラルル国ニシテ普通教育ノ干渉ヲ以テ政府ノ務メトセサルハナシ〉とし,早くも翌80年3月には教育令改正に着手,12月には改正教育令を公布した。そこでは,学校事務管理のための学務委員を,教育令では町村住民による選挙で選出するとされていたのを府知事・県令の任命制に改めたのをはじめ,学校の設置・管理に対する地方長官による統制を強め,小学校の教科では,初めて修身を先頭に置いて道徳教育を重視する方針をとった。修身重視は,1879年の〈教学聖旨〉に示された,仁義忠孝を中心とした徳育こそ日本古来の教育の中心である,という考えにもとづくものであった。ついで81年には,小学校教則綱領が出され,各教科の目標・内容が示され,これにのっとって教科書がつくられることになり,同年,小学校教員心得も出され,両者を通じて〈尊王愛国ノ志気〉の養成が重視されるようになった。これらが自由民権運動を抑圧するためであることは明らかであり,学校は民衆教化の役割を負わされることになったのである。
ついで伊藤博文内閣の初代文相森有礼の下で,86年小学校令,中学校令,師範学校令,帝国大学令という四つの勅令が出され(学校令),小学校を義務制にするなど教育普及に向けて学校制度が整備されたが,同時に国家による統制は一段と強化された。東京大学(1877創立)を改編した帝国大学についても〈国家の須要に応ずる〉学術を研究・教授するというように目的が示された。これは,学問研究を国家目的に従属させる方針の明示であり,小・中学校の教科書は文部大臣を検定権者とする検定制がとられるにいたった。
教育勅語体制の確立
このような制度上の整備にとどまらず,1889年制定の大日本帝国憲法と密接に結びつくものとして翌90年に教育勅語が発布された。この勅語は,日本教育の根本方針は〈皇祖皇宗ノ遺訓〉にあるとし,そこから徳目を引き出し,国民はこの徳目を実践し,国家有事のさいには一身を国にささげ,天皇の治世がいつまでも盛んに続くよう助けるべきだ,と説いていた。教育勅語発布とともに,学校では,この精神にもとづく教科の授業とともに,儀式,修学旅行,運動会などの学校行事により日本精神を体得させることが重視されるようになった。修学旅行という外国には例のない日本の学校独自の行事は,20世紀に入り,伊勢神宮参拝を中心とした敬神崇祖の念を強める教育活動の一つとして,また紅白にわかれて得点を争う運動会は,日清戦争のころから戦意高揚のための行事として重視された。学校でこれらの行事より重要な位置を与えられていたのは,祝日・大祭日の儀式である。教育勅語発布の翌91年6月には〈小学校祝日大祭日儀式規程〉が定められ,紀元節,天長節,元始祭,神嘗祭および新嘗祭には,教員・生徒一同式場に参集して行う儀式の内容が示された。それは,御真影(天皇,皇后の写真)への最敬礼・万歳奉祝,教育勅語奉読,校長の訓話による忠君愛国の士気の涵養,祝祭日に相応する唱歌の合唱という内容であり,儀式は独特の宗教的雰囲気の下ですすめられ,参列した子どもたちに強い印象を与えた。
森有礼文相は各地の講演などで繰り返し〈学問と教育は別である〉と語っていた。これは学問の研究成果を初等・中等教育の内容とすることを妨げるという方針であり,科学的認識の能力の発達を抑え,神話を史実にするという官製の歴史を子どもに教えることによって日本の国体の尊厳を信じ込ませようとしたのである。祝祭日の学校儀式はこれを補強する有力な手段であった。〈久米邦武事件〉といわれる当時の一事件に問題点が典型的に示されている。帝国大学教授久米邦武の論文〈神道は祭天の古俗〉が91年に学術誌である《史学雑誌》に掲載されたときには,なんら社会的に問題とならなかった。ところが,伊勢神宮の起源についても科学的解明をめざすこの論文が,翌92年,一般向けの歴史雑誌《史海》に転載されるや,神道家たちがその取消しを迫り,久米は大学の職を追われたのである。専門家向けと一般向けとの区別は,大学と初等教育との区別,学問と教育との区別につながるものであり,以後,同様の事件は科学と芸術の諸分野で起こる。日本の学校では,欧米のキリスト教国家と違い,宗教的権威が教育内容に圧力を加えることはなく,したがって,たとえば欧米では20世紀後半に入ってもなお,ときに教えてはならぬとされてきた進化論が,日本では早くも1880年代には,なんの障害もなく学校で教えられるようになった。しかし,日本では同時に,政治的権力が自己の支配体制をおびやかすおそれがあるとみた教育内容は,学校から徹底的に排除され,画一的な教育内容が強いられることになったのである。
新教育運動と学校
20世紀初頭には,社会民主党がその宣言(1901)で,平等の教育のため国家が教育の全費用を負担すべきことをかかげ,また教育の内容についてはその画一的なあり方への反対の声をあげる者があらわれ始めた。代用教員石川啄木もその一人であり,画一的・形式的教育に強く反発し,詩人が教師となることの意味を力説し,個性的な実践にとり組んだ。啄木にみられる自由で創造的な教育は1910年代中葉,大正中期から新教育運動として開花する。とくに成城小学校,自由学園,玉川学園,児童の村小学校など個性的な私立学校がつぎつぎに設立され,いずれも個性尊重の自由主義教育を展開した。また女子の専門教育については政府は教員養成のための女子師範学校,高等女子師範学校を設立しただけで,中等教育機関を高等女学校とし(1895年,高等女学校規定制定),これを女子にとっては〈高等〉の学校であると規定していた。しかもこの学校の教育内容水準は男子中等学校よりも低かった。そのような状態のなかで20世紀に入り,津田梅子,吉岡弥生,成瀬仁蔵ら民間人の努力によって専門教育機関がつぎつぎにつくられ,第2次大戦後の大学の女子への門戸開放を準備したのである(女子教育)。
戦時体制下の学校
20世紀に入ってからの資本主義の発展を背景に,経済界などの高等教育機関増設の要望にこたえ,1918年帝国大学令を廃して大学令を公布,慶応,早稲田,明治など,私立の専門学校がようやく大学として認可された。しかし大学令では,大学の目的に国家思想の涵養が加えられ,国家による大学統制が強められた。大正期新教育運動がすすむ一方,同じ時期に小・中学校から大学まで,学校に対する国家統制強化の準備がすすめられていたのである。30年代に入ると,学校教育の自主的改革を志向する民間教育運動は抑えられ,36年の教学刷新評議会答申で,日本では古来,祭祀と政治と教学とは根本において不可分であるとの考えにもとづき,学校を〈国体ニ基ク修練ノ施設〉とする方針がたてられ,敬神崇祖の美風を盛んにするための施設(奉安殿など)の設置が定められた。そして41年小学校は名称も国民学校に改められ,そこでの教育を全般にわたって皇国の道に帰一せしめることとされた。一方,高度国防国家建設のために学制改革や義務教育年限延長が各方面から提案されていたが,戦争の急迫はその実現を妨げた。そのなかで,1935年発足の青年学校を39年には男子の場合19歳まで義務制として軍隊教育の代行をさせることにした。すでに1925年,男子中学校以上の学校には陸軍現役将校を配属して教練を必修として課していたが,この配属将校が戦時下,学校内でもっとも権力をもった存在となっていった。敗色が濃くなると学校から教育が姿を消し,45年3月,閣議決定の〈決戦教育措置要綱〉では,緊迫した事態の下,学生・生徒は食糧増産,軍需生産,防空防衛,重要研究など緊要な業務に総動員されること,国民学校初等科を除き,他の学校は上記の目的達成のため,4月1日から1年間,原則として授業を停止することが規定された。さらに5月には〈戦時教育令〉(勅令)が出され,学校では,戦時に緊切な要務に従事するとともに,戦時に緊要な教育訓練を行うため学校ごとに教職員と学生・生徒により学徒隊を組織することが決定された。政府はあらゆる者を戦争に向けて動員しようとしたのであり,それは,日露戦争中,明治天皇が教育関係者に向け〈軍国多事ノ際ト雖モ,教育ノ事ハ忽ニスヘカラス。其局ニ当ル者,克ク精勤セヨ〉(〈露国と交戦中東京帝国大学に於いて文部大臣久保田譲に賜はりたる御沙汰〉,1904年7月11日)という御沙汰を下したのと大きな違いであった。〈軍事教育令〉が出されたことで学徒出陣,勤労動員,さらに例外とされた国民学校初等科の場合も集団疎開や勤労奉仕により,事実上学校では,その本来の任務である教育が行われなくなっていたのである。この時期,沖縄ではすでに戦闘が終了していた地域があり,住民の収容所のなかで,特別の施設や教材もない混乱状態にもかかわらず,子どもに読み書きを教えようとの試みがあり,これは戦後教育であったが稀有の例であり,日本中の学校は教育活動をほとんど停止した状態で8月15日を迎えた。
戦後の教育改革
ポツダム宣言には,〈日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ〉とあった。ここでいう障礙のなかで強力なものの一つは学校であったから,必要なのは戦前の教育への反省であった。しかし文相はポツダム宣言受諾にあたり,学校関係者に対し,未曾有の国難を招来した原因は〈皇国教学ノ神髄〉を十分発揮できなかったところにあるとし,今後は教職員,学生・生徒とも〈国体護持〉に努めるべきだとの訓示を出した。これは学校教育の敗戦責任を問うものであり,戦争責任は不問に付されたままであった。しかし,いつまでも国体護持のみを学校の使命としていることはできず,1945年9月15日に文部省の出した〈新日本建設ノ教育方針〉では,なお国体の護持をかかげながらも,世界平和と人類の福祉に貢献する新日本建設のための教育方針が示された。ここには社会教育もとりあげられていたが,やはり中心課題は学校教育の改革であり,学校から軍国的思想や軍事教育を一掃し,科学的思考力や平和愛好の精神を育てることであった。一方,連合国軍最高司令部は10月22日に〈日本教育制度ニ対スル管理政策〉を出し,学校の教育内容から軍国主義,超国家主義を廃し,代りに基本的人権の思想に合致する諸概念の教授および実践の確立を奨励し,続いて〈教育関係者ノ調査,除外,認可ニ関スル件〉(10月30日),〈国家神道,神社神道ニ対スル政府ノ保証,支援,保全,監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件〉(12月15日),〈修身,日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件〉(12月31日)という指令が出された。これは教育に関する占領軍の〈四大指令〉といわれている。いずれも学校教育のあり方に強い反省を迫るものであった。
46年3月には,第1次アメリカ教育使節団が来日,報告書は,高度に中央集権化された教育制度は,かりにそれが極端な国家主義と軍国主義の網のなかにとらえられていないにしても,強固な官僚政治にともなう害悪を受けるおそれがあり,教師は画一化されることなく,その職務を自由に発展させるには地方分権化が必要であるとし,学校は,非文明主義,封建主義,軍国主義に対する一大抗争に加わるだろうと期待していた。報告書は教育の目的・内容・方法から制度や教員養成など,学校教育に直接関係のある問題のほか,国語改革,成人教育などにも言及していた。この報告書が戦後教育改革の方向を示唆したことは確かだが,すべてこのとおりに実行されたのではないし,また日本側にも教育改革のための努力があった。同年6月,文部省の出した〈新教育指針〉には,平和的文化国家の建設と教育者の使命が熱っぽく説かれており,同年8月設置された教育刷新委員会(総理大臣所轄,委員長安倍能成,1947年11月以降,南原繁。49年6月,教育刷新審議会と改称)は,教育の諸問題について精力的に審議を行い,改革のための建議を行った。同年12月27日に出された第1回の建議は,日本国憲法の理想の実現は根本において教育の力にまつべきであるとの考えに立って教育基本法を制定する必要を説いたものである。翌47年3月に公布された同法では,第6条で学校とその教員について〈法律に定める学校は,公の性質をもつものであって,国又は地方公共団体の外,法律に定める法人のみが,これを設置することができる。法律に定める学校の教員は,全体の奉仕者であって,自己の使命を自覚し,その職責の遂行に努めなければならない。このためには,教員の身分は,尊重され,その待遇の適正が,期せられなければならない〉と規定された。
この教育基本法にもとづいて日本の学校は新たな出発をすることになる。この法でいう〈法律〉とは,同日に公布された学校教育法であり,この法は,教育の機会均等,普通教育の向上と男女差別撤廃,学制の単純化,学術文化の進展という見地から,学校制度を改革し,6・3・3・4制を発足させるために作成され,この公布により,国民学校令,中等学校令,大学令などは廃止された。そして4月から新学制による小学校(国民学校初等科を改称)と中学校が発足し,翌48年高等学校,ついで49年大学(キリスト教系・女子系の12の公私立大学はひと足先に48年),さらにこの年に大学に入学した者が卒業する53年に大学院がそれぞれ発足したのである。普通教育の新教科として1947年9月から社会科が設けられ,教科書は学校教育法で国定制を廃止,49年4月から検定教科書が使用されるようになった。国定教科書廃止の後,文部省は,教師が自主的に教育計画をたてるさいの手引きとして1947年3月以降《学習指導要領(試案)》を刊行し,今後の学校教育について〈下の方からみんなの力で,いろいろと,作りあげて行く〉(《学習指導要領一般編(試案)》,1947年3月20日刊)という方針を示した。この方針に従い,各地で教師自身による調査を基礎にして地域教育計画がたてられ,あるいは教科書にこだわらず,自主的選択教材による授業が展開されるなど,学校には,かつてない自由で活気ある雰囲気がみられた。
教育政策の転換と学校
しかしこのような学校は長続きしなかった。米ソ冷戦,朝鮮戦争勃発を背景に,1951年9月,サンフランシスコで単独講和条約と日米安全保障条約が調印され,その直後の11月に,占領下の改革を検討し直すため同年5月内閣に設けられた政令改正諮問委員会が,〈教育制度改革に関する答申〉を行った。答申は,戦後の改革が民主的教育制度確立に資するところが少なくなかったとしながら,国情を異にする外国の諸制度に範をとったので,日本の実情に即しないところがあるという,その後たびたび繰り返される理由をあげ,教育委員会制度や教科書制度とともに学校制度についても再改革の案を示した。そこでは,6・3・3・4の学校体系は原則的に維持するとしながら,画一的な制度を改め実際社会の要求に応ずる弾力的な制度にすること,普通教育偏重を改め,職業教育を重視することがあげられていた。これらは,すぐには実現しなかったが,学校の再改革は50年代の終りから高校多様化を中心にすすめられた。これは指導層と中堅技術者と現場労働者という各層の養成に適した学校を制度として整えさせようとの要求であり,以後,経団連,日経連など経済団体は80年代中葉まで百数十回に及ぶ教育関係の要望書を公表,関係機関に提出し,学校教育のあり方の変更を迫っている。
とくに1960年代の高度経済成長政策下,学校はその政策実現に必要な人材開発の手段とされた。経済界からの要望をいくつかあげると,60年7月,経済同友会〈産学協同〉,12月日経連〈専科大学創設〉,61年8月日経連・経団連〈技術教育の画期的振興策の確立〉,63年11月経済同友会〈工業化に伴う経済教育〉(高校社会科内容の刷新),65年5月日経連〈後期中等教育〉,68年11月経済同友会〈大学教育の基本問題〉,69年2月日経連〈当面する大学問題〉等々である。1960年代末の大学紛争にあたって大学問題についての見解が出されるが,焦点は後期中等教育であり,61年に5年制の高等専門学校が創設され,6・3・3・4制という単線型の一角が崩された。ついで63年1月の経済審議会答申〈経済発展における人的能力開発の課題と対策〉では,諸条件の変化が新しい基準による人の評価・活用のシステムを要請しているとし,教育における〈能力主義の徹底〉を提唱した。66年10月の中央教育審議会答申〈後期中等教育の拡充整備について〉では,各人の個性・能力・進路・環境に適合する教育(多様化)が提案された。これの別記として愛国心育成を強調した〈期待される人間像〉がそえられたところにも,以後の教育で後期中等教育の改革が重要視されていたことがあらわれている。
以上の要望や答申の総まとめとして出されたのが71年6月の中教審答申〈今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について〉であり,幼児教育から大学院にいたるまでの全学校教育についての改革案が示され,これにもとづく学校改革は〈学制〉公布,敗戦後の改革につぐ〈第三の教育改革〉であるとされた。5歳児全員の幼稚園就園,4,5歳から小学校低学年までの同一教育機関での一貫教育,中等教育のいっそうの多様化,大学における高度化した研究と大衆化した教育との分離などが提案された。しかし幼稚園については保育所などの反対があり,多様化は70年代中葉にいたって破綻が明らかとなり,大学については研究と教育の結合という原則の重要性が改めて大学人によって確認されるなど,この答申はそのままでは実現されなかった。しかし70年代以降,学校制度には,中学・高校の接続や義務教育年限など問題が多いことは多くの人の認めるところとなり,日教組も教育制度検討委員会を70年代と80年代の2度にわたって設置し,制度改革構想の検討を委嘱したほどである。
一方,小・中・高校の教育内容は1950年代以降,学習指導要領がほぼ10年ごとに改訂されてきた。50年代後半からはその性格が改められ,教科書への拘束力が強化され,このため教科書は画一化と寡占化の傾向を強めた。また50年代以降の国際的な科学・技術の発展への対応にあたり,教育内容を十分に整理しないまま新しい内容を付け加えた(たとえば小学校算数に〈集合〉を追加)ため,内容が難しく,しかも量が増えたので,70年代からは〈落ちこぼれ〉が流行語になるほど,授業についていけない子どもが増えた。これとほぼ並行して高校で,80年代に入っては中学校で校内暴力,登校拒否,非行が急増し,教師は学園の秩序の回復に向け懸命に努力しなければならなくなった。
現代学校の問題
しかし学校の問題で悩んでいるのは日本だけではない。問題が集中しているのは,学校が普及している先進国では中等教育であり,アメリカでは1950年代末から暴力教室が問題となり,60年代にはハイ・スクールの落伍者・中退者の激増,学校の荒廃が憂慮されており,西欧では複線型の中等教育を単線型・総合制に改革する案が繰り返し出されながら,万人の納得できる学校制度は確立されていない。またソ連をはじめ社会主義諸国では生産労働と教育の結合という原則を実地に移すための方法が何度か提案されたものの,その実践はなかなか持続しなかった。中国では66年以降,文化大革命によって,特権階層の子弟が多数上級学校へ入学していることへの反対運動や,知識人,学生の農村,工場などへの下放運動が起こされたが,その革命期をすぎて近代化が提唱されるや,文化大革命以前よりもはるかに徹底した能力主義がとられ,各階層の重点学校に学力の高い生徒を集め,早急に科学・技術の飛躍的前進をはかろうとしている。この方式が民衆に広く支持されているとはいえず,学校のあり方の検討が続いている。
こうして学校のあり方は,さまざまな角度から検討することが国際的な課題となっている。学校の制度や教育内容には問題が山積しているのだが,生活に余裕のあるかぎり,その学校教育を少しでも長く受けようとし,しかも進学率や,安定した職業への就職率の高い学校への進学を希望する者は,20世紀後半,各国で増加してきた。ときには本人よりも親の希望によるところが大きく,学歴社会と称してこれも国際的な問題として広がり始めている。日本でも学歴社会の問題がたびたび指摘されてきたが,事態がより深刻なのは発展途上国であり,それだけに学校の未来には解決を要する課題が山積していることになる。そのなかで学校とは何かが改めて問われる。
かつてJ.デューイやG.S.カウンツらアメリカの教育学者は社会改造との関係で学校を問題にしてきた。また日本では,宮原誠一の〈教育は社会の基本的な諸機能の再分肢〉であるとの考えを受け継ぎ,勝田守一が,学校はその諸機能を意図的・組織的に遂行するところであり,学校の機能には,社会的統制,職業的訓練,文化価値の内在化(教養)の三つがあるとした。これらはだれもが認める学校の機能であるが,具体的にどのような学校にするかが問題である。1950年代から数学教育改造運動にとり組んできた遠山啓は,70年代に入って,学校は自動車学校型の学校と劇場風の学校のどちらかにするのがよいと提案した。前者は,将来就く仕事に必要な知識・技術は順序だてて確実に習得させる学校であり,後者は,みずから選択して入場し,自分の興味に合致しなければ退場自由という学校である。また学校のあり方を根本から問うI.イリイチの〈脱学校の社会deschooling society〉の提言も70年代末以降,世界各国で注目されるようになった。そこで学校に代わる学習機会として示された網状組織opportunity webは,(1)教育的事物などのための参考業務,(2)技能交換,(3)仲間選び,(4)広い意味での教育者のための参考業務,の四つである。すべての人に教育を行うことは,すべての人による教育を意味するとの提言は大事であり,中国でも古くから〈教学相長ず〉といわれてきた。しかしこの網状組織はおとなたちの学習にとっては有効でも,子どもの発達を保障することを任務とする教育組織としては貧困である。学校は,それぞれの国によって異なった歴史や社会的位置をもっており,また学校を支える財政的基盤にも違いがある。したがって全世界的に一挙に同じ方向・方針・方法で問題を解決することは不可能であり,21世紀を展望しながら,着実な解決をはかることが,いたるところで求められているのである。そのさい重要なのは,学校を固定したものとするのではなく,義務づけられた教育課程のなかでも,自主的に教育課程を編成し直そうとする努力をふくむものとして定義づけなければならないということである。
→教育 →教師 →大学
執筆者:山住 正己
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「学校」の意味・わかりやすい解説
学校
がっこう
一定の教育目的を達成するために、継続的、計画的に教育活動の営まれる組織であり、教育をする者、教育を受ける者、および教育活動に必要な施設設備を中心に構成される。教育は、もともと人間のあらゆる生活活動のなかにいつも存在するものであり、人間が社会生活を始めて以来、今日に至るまで連綿と継続してきたものである。そのような教育は、社会生活の変遷を通じて、直接に間接になんらかの方向に無意図的に人間形成が行われてきた段階から、しだいに一定の目的と形式のもとに営まれる意図的な形成作用を含むような段階にまで到達するようになった。なんらかの教育目的を達成するためには、一定の期間に、継続的にまとまった教育の行われる場を必要とする。その場は、教育目的がより能率的合理的に実現できるように、整った教授組織や学習計画をもち、それに見合った施設や設備が用意される。そのなかには、わが国の江戸時代にみられた寺子屋のように、お師匠さん1人で簡単な読み書きを教えるものもあれば、今日の学校のように多数の教員と児童・生徒等を擁する大規模な組織のもとに、長期にわたって計画的な教育を行うものもある。施設においても、小さなバラックの一隅を借りたものから、広大な校舎と優れた設備を完備するものまである。
教育という事業が社会的に広く有用であると認められるようになれば、それが営まれることはしだいに社会的な慣行となって定着する。さらに社会の発展に伴い、より組織的体系的な教育が要求されるようになると、国家はそれに必要な法律を制定して、教育機関の設置や運営を図ろうとする。そのような教育の場が、現在われわれの周辺に存在する学校である。学校の発達する過程において、一つの学校だけでは社会の多様な教育要求を満たすことができなくなると、さまざまな教育目的をもつ学校が、さまざまな系統や段階に組み合わされて一つの学校体系を構成する。
[真野宮雄]
学校の起源と成立
学校は、人間の社会生活の変遷に伴う、さまざまな必要から成立してきた。
[真野宮雄]
集団生活と教育組織
原始社会の人間は、食物を獲得したり、住居をつくったり、動植物を飼育栽培したりすることや、そのために必要な身体を強健にすべきことなどを自ら覚えたり、家族や社会集団を通して、その知識や技術を代々伝達するようになった。このような伝達は、家庭生活や社会生活のなかで、日常的に無意図的に行われていたものである。ところが、集団生活の発達とともに、彼らにとっては集団の安定を図ることが自分たちの生活の安定につながるようになるので、それぞれのメンバーは、自分たちの集団生活を守るために尽くさなければならなくなる。そのため、社会集団では、内では集団における秩序の維持を、外に向かっては他の集団からの攻撃に対する防衛のために、集団のメンバー同士が互いに一定の資質や能力をもつことを要求しあう。そこで、とくに集団内の子供たちが大人になるときに、その集団における正式の一員となるための訓練および承認を受ける場として、入社式とよばれる一つの教育的習俗を生ずるのである。
この習俗は、長老たちの手によってその集団の若者たちに施されるもので、その目的は、(1)集団の成員として十分に奉仕できるような強健な身体を備えること、(2)集団の伝承的な知識を習得し、集団の宗教的儀式に参加すること、(3)集団の組織内における自己の位置を自覚し、集団に対する絶対的な忠誠心を養うこと、(4)外敵に対して集団を防衛できる十分な戦闘能力を身につけること、などとされていたという。これは、人間の集団生活を維持するための必要から生まれた計画的な集団教育の組織として、もっとも古くからみられた慣行といわれる。もともと入社式は、集団のメンバーすべてに施されるものであったが、社会集団において支配したり支配されたりする階層が発達するのに伴って、特定の階層だけのための教育組織に移行する。その典型は、古代ギリシアのスパルタや初期のアテネなどの都市国家に認められる。
集団生活の必要から生まれた教育組織はわが国にもみられる。江戸時代に、村の若者たちによって構成された若者組(あるいは若者衆、若衆連など)はその代表例である。若者組は、村の若者が一定年齢に達するとかならず加入すべき義務があり、村の祭礼行事や娯楽的催しの主役を務めたり、村内の警備や共同労働に従事するなどの社会的機能をもっていた。それとともに、若者たちは、若者組における団体生活を通じておのずから村落生活に対する認識を深め、村落の集団生活に必要な生産技術なども習得して、村落の成員にふさわしい人格の形成や能力の発展を図った。
その後の近代国家における国民教育のための学校にも、大規模な集団教育の組織として、これらと共通な意図や内容が認められるのである。
[真野宮雄]
信仰生活と学校
人間が自らの信仰を深めることは、その精神生活において重要な意味をもつ。ヨーロッパにおいて、キリスト教による教化事業は、すでに古代末期より行われていたが、中世にはヨーロッパ各地における教会制度の発達に伴って、組織的に拡大されていった。そのために、各寺院や修道院ではまず僧侶(そうりょ)養成を目的とする学校を設け、さらに信者教育を目ざす教会付属学校などの設置も図るようになる。宗教改革以後には、さらに新しい宗派の信仰生活を広く民衆一般に普及するために、学校を通してすべての民衆子弟に対する宗教教育を強化することがますます求められるようになった。しかし、宗教教育のための学校の組織化には、その背景に強大な推進機構を必要とする。その結果、教会と世俗権力との結合をもたらし、やがて国家の確立とともに、宗教教育は国家のためのイデオロギー教育として、あるいは救貧政策の一環として、国家に利用されるという傾向に陥るのである。
[真野宮雄]
教養生活と学校
社会階層の分化とともに、支配者あるいは貴族階級は、奴隷の労働や農民たちの労働のうえに安住するようになり、もっぱら毎日の貴族生活を送るための教養、あるいはその社会的地位を飾るのにふさわしい教養を身につけることを求めた。古代ギリシアのアテネ後期における貴族たちは、奴隷の労働によって生み出された閑暇(skholēギリシア語の閑暇という意味から、閑暇を利用して教養を身につける時間、さらに教養を身につける場所と転じ、学校schoolの語源となる)を利用して、アテネ各地に設けられた学塾に通い、自分たちの貴族的教養を豊かにすることにふけっていたという。貴族たちの教養のための教育は、中世以後になると教会付属学校や宮廷学校などに受け継がれ、さらにルネサンス期には、古代ラテン語やギリシア語による人文主義教育を行う古典語学校がヨーロッパ各地に生まれ、全人的、調和的な教育を目ざそうとした。その内容は、しだいに文法、修辞学、論理学(弁証法)、および算術、幾何、天文学、音楽などのいわゆる自由七科seven liveral artsとしてまとめられ、それに宗教教育や身体教育などを加えることもあった。しかし、16世紀以後には古典語教育の形式的な側面だけが、上流階級の地位を飾るための教養として伝えられていったのである。
[真野宮雄]
経済生活と学校
農業中心の時代から、しだいに商工業活動などが盛んになるにつれて、一般民衆の社会生活にもさまざまな変化が生じてくる。とくに中小商人や手工業者にとっては、まず日常語の読み書きや計算の能力が生活上欠くことのできない道具となる。近世以後のヨーロッパの商業都市には、スリー・アールズ3R's(読みreading、書きwriting、算術arithmeticのこと。わが国では、読み、書き、そろばん、といわれた)を教えるための公設公営の学校や私塾が生まれるようになった。わが国の江戸時代における寺子屋も、同様の背景によるものである。一方、商工業などに関する職業訓練は、初めのうちはほとんど徒弟制度に依存していたが、その後の資本主義経済の発展とともに消滅し、職業学校における組織的な職業教育に変わっていくのである。このように、スリー・アールズの教育あるいは職業訓練のための組織の発生は、民衆の経済生活の発展による日常生活の変化に負うところが大きい。しかし彼らには、上流階級のように、自分たちに必要な教育を自分たちの力で広く組織化することはほとんどできなかった。そのため、近代国家の成立以後、国家の力によって、その国民教育の組織のなかに組み入れられていくのである。
[真野宮雄]
近代的教育組織への発達
社会生活の発展に伴って、教育の目的、対象、内容、水準などをそれぞれ明確にする学校が発達し、やがてヨーロッパなどでは、それらが二つの学校教育の系統に組み合わされた学校体系を構成するようになる。
[真野宮雄]
下構型学校系統
ヨーロッパでは12、13世紀ごろになると、裁判官、弁護士、医師、聖職者などの新しい専門職業への需要が高まってきた。そこで、当時の西ヨーロッパ各地からは、新たな職業を目ざした多数の青年たちが、法学、医学、神学などの高等の専門学術の習得を求めて著名な学者の塾に集まり、やがてそれらを中心に学校町(まち)(ラテン語でstudium)が形成されるようになった。彼らは、自分たちの身分や利益を擁護するために、当時の商人や職人のギルドに倣った学徒組合(ラテン語でuniversitas)を結成し、その特権を手に入れるために法王や国王からの特許状による公認を得ようとした。これがヨーロッパにおける中世の大学の起源とされ、なかでもボローニャ、サレルノ、パリ、オックスフォードなどが最古のものといわれている。このような中世大学の成立は、後世の大学自治の原型を示し、その多くが今日なお各国において伝統的な大学として存続している。しかし、大学の創設当初にみられた自由な特質は、やがて教会や国家の保護・干渉によって制約されたり、あるいはゆがめられ、また古典語中心の学問研究は保守的貴族的な性格をますます強め、しだいに形式的な貴族的教養だけに役だてられるようになったのである。
一方、ルネサンスの影響によって、古典を中心とする教養教育のための学校が、教会付属学校から独立したり、あるいは新しく設立され始めた。これらの古典語学校は、今日のヨーロッパにおける主要な伝統的中等学校の基礎を形成するものであり、イギリスのグラマー・スクールgrammar schoolやパブリック・スクールpublic school、あるいはドイツのギムナジウムGymnasium(ドイツ語)などに代表されている。しかし、その後の大学の保守化、貴族化とともに、大学がその入学資格をこれら古典語学校の卒業生とするようになったことなどから、古典語学校はしだいに大学の下位に接続する中等学校となり、本来の独立した地位を失って、もっぱら大学の予備校としての役割を果たすに至った。ここに、貴族階級の子弟を対象に、主として教養教育を与えようとする教育組織が、「大学→中等学校」という一つの学校系統を成立させる。しかも、中等学校は、大学への入学準備の必要から、しだいに学年を下級段階へ延長していった。したがって、この学校系統は、その発達の仕方からみると、大学を最高教育機関として、「上から下へ」順次に構築されるという特徴をもつので、下構型学校系統といわれる。また、この学校系統は、もともとの成立目的から教養的学校系統、その教育の対象から貴族学校系統、さらに中等学校が基礎になっていることから中等学校系統ともいわれるのである。
このように、中等学校から大学に至る教養教育のための特権的な学校系統は、その後、教育内容において近代的教科を加えたり、また教育対象を新興階級にも拡大して、彼らの上流階級へ接近しようとする要求にも応ずるようになっていった。しかし、相変わらず社会的なエリート層を育成しようとする役割を続けていくのである。
[真野宮雄]
上構型学校系統
一般庶民の日常生活のための学校は、長い間、不完全かつ貧弱なままに放置されていた。結局、彼らの学校の整備や組織化は、ほとんど教会や国家などの力によって進められる社会政策ないし教育政策の拡大に依存しなければならなかった。ヨーロッパでは、彼らの学校が各国家の政策対象とされる以前には、しばらく宗教団体や民間団体による教育普及運動にゆだねられていたことも多い。19世紀に入ると近代国家では、国民教育の拡充のために、ようやく初等教育の組織をつくるための国家関与を強めたり、さらには法律によって義務教育なども定めるようになってきた。このようにして成立した各国の初等教育制度は、学年制の発達とともに上級段階へ延長され、教育内容も初歩的な読み書きから、やがて職業補習教育や職業教育までも含むようになる。とくに19世紀末以後の資本主義諸国間に生じた産業競争の影響は、それぞれの国の産業教育の振興政策となって現れ、多数の下級技術者を養成するための職業学校の拡大を生じてきたのである。
近代国家では、このような民衆子弟を対象とした国民教育の強化と職業教育の振興を目ざす教育政策によって、「小学校→補習学校または職業学校」のように「下から上へ」向かって順次に構築される学校系統がしだいに形成されてきた。そこで、この学校系統は、その発達の仕方から上構型学校系統とよばれ、また、もともと民衆の日常生活、とくに経済生活に有用な知識や職業技術を授けるために発達した経過から職業的学校系統ということもできる。さらにその教育対象から庶民学校系統、基礎となる学校の種類から小学校系統ともいわれる。この学校系統は、すでに成立していた下構型学校系統に対して、しばらくの間まったく並列的に発達するのである。
[真野宮雄]
学校体系の複線型と単線型
下構型学校系統と上構型学校系統の成立によって、二つの学校教育がそれぞれ分かれて行われるようになったのは、とくに19世紀後半から20世紀にかけてのヨーロッパ諸国においてである。これは、ヨーロッパ諸国における貴族と庶民という二つの階級の長い歴史を背景としていたからである。ところが、階級分化がヨーロッパほど明確ではなく、またその歴史も浅いアメリカでは、二つの学校教育もそれほど明確に現れることはなく、ほとんど単一の学校系統のなかにさまざまな学校が含まれていた。したがってアメリカの学校は、ヨーロッパのように学校系統の違いによって教育目的や内容を異にするよりも、むしろ初等、中等、高等という教育水準に基づいて、それぞれの学校段階に分けられ、それぞれの段階に応じた教育を行うようになった。
ヨーロッパにおいて発達した学校体系は、複数の学校系統が並列し、ほとんど交差することがない。すなわち、社会的な地位や身分によって初めから入学すべき学校系統およびその後の進路が別々に定められ、本人の能力や希望とは無関係に、その学校系統に属する学校だけで教育を受けることとなり、別の学校系統の学校へはほとんど進学できないという仕組みになっていた。それに対してアメリカの場合は、単一の学校系統であるため、上級段階の学校への進学や卒業後の進路において、社会的な地位や身分などによる制約があまり認められないという。このように、ヨーロッパとアメリカとではまったく正反対の学校体系となっており、前者を複線型学校体系、後者を単線型学校体系と称する。また、この二つの学校体系を両極として、その中間には分岐型学校体系が存在する。
[真野宮雄]
教育の機会均等と学校制度の改革
個人の自由・平等についての権利思想は、フランスの市民革命やアメリカの独立革命などをきっかけとして芽生えてくる。それは、やがて教育のうえでは、教育の機会均等の要求となり、そのための学校制度改革が進められるようになるが、その歴史的な背景としては、19世紀における近代公教育の発展があげられる。
[真野宮雄]
近代公教育の発展
近代国家では、新しい市民社会を確立するために、個人の自由・平等とともに、市民としての教育を受ける責任も求められるようになる。教育を受けることが、個人の利益としてだけではなく、一市民の責任として、公共的な性格をもつものと考えられるようになってきたのである。市民に広く教育を普及させるために、公立学校を設けようとする動きは、19世紀のアメリカなどを中心にみられる。しかし他方では、工場制工業の発展によって多数の年少労働者の発生など、多くの社会問題も現れてくる。各国では、このような教育の受けられない状態から子供たちを保護して、学校教育を受けさせようとする立場からも、しだいに義務教育を定めるようになった。また、教育を受ける個人の経済的な負担を少なくするために、無償教育も採用され、授業料やさらに教科書の無償なども取り上げられるようになった。さらに、学校で受ける教育の内容が、学習者自身にとって、その将来の幸福や利益にも役だつように、宗教的、政治的な立場からの強制を排除すべきだという考えも広まり、教育の宗教的・政治的中立性を定める国家も増加し始めたのである。このようにして、近代公教育を実現するための学校は、すでに19世紀後半に成立し始めていたが、教育の機会を不均等にする学校制度を改革しなければ、根本的な解決とはならなかったのである。
[真野宮雄]
教育機会の均等化
ヨーロッパでは、教育を受ける機会を均等化するために、複線型学校体系を改革し、すべての者に初等教育以上の中等教育、さらには高等教育を受けられるようにする必要があった。その具体化は、19世紀末からのドイツや第一次世界大戦中のフランスで展開された統一学校(ドイツ語でEinheitsschule、フランス語でécole unique)の運動、あるいは第一次世界大戦後のイギリスにおける中等学校の開放運動などにみられる。これらの運動は、すべての国民に対して同一の学校で同一の初等教育を与え、それ以後の学校教育についても、それぞれの能力と希望に応じて教育を受けることのできる機会を開放しようとするものであった。そのためには、複線型学校体系における最初の4~6年間の教育を一つの初等学校に統一する分岐型学校体系の樹立が、当面の改革目標とされたのである。その結果ドイツでは第一次世界大戦後のワイマール共和国憲法(1919)において、フランスでは第二次世界大戦後のベルトワン改革(フランス語でRéforme Berthoin)において、またイギリスでは1944年教育法において、それぞれようやく中等学校への道が広く開放されるようになった。
一方アメリカでは、すでに19世紀後半に八・四制を中心とする単線型学校体系がほぼ成立していた。しかし実際には、8年間の初等教育の期間中に中途退学者が増加したり、4年間の中等教育ではカレッジ進学者の学力水準が低下するという問題などが生じた。そこで、一連の中等教育改造運動がおこり、まずカレッジ進学者の学力水準を高めるために、中等教育の拡充を目ざした六・六制への改造計画が主張され始めた。しかし、20世紀に入ると、新たに初等教育から中等教育への進学者の拡大を図ろうとする気運が強くなり、3年制のジュニア・ハイスクール設置の動きもみられるようになった。さらに全米教育協会(NEA)内に設けられた中等教育改造委員会の報告書(1918)は、中等教育の充実と拡大、および将来の進路選択と決定を行うのに有利な制度として六・三・三制案を唱え、その採用を各州に勧告したのである。
このように、単線型学校体系のアメリカでは、ヨーロッパ諸国のような学校系統の統合という方法よりも、学校段階の区分を変更することによって、中等教育以上の教育を受ける機会を開放しようとしたといえる。各国における教育機会の均等化への動きは、このようにして、それぞれの歴史的・社会的諸条件を背景としながら、さまざまな学校制度改革を展開してきたが、これらはさらに第二次世界大戦後から現代にも継承されているのである。
[真野宮雄]
わが国の学校の現状と課題
第二次世界大戦後の日本では、教育の機会均等の実現を目ざして、六・三・三・四制の単線型学校体系を根幹とする学校制度が構築されるようになった。しかし、現代社会の要請にこたえるためには、なお多くの課題が残されている。
[真野宮雄]
わが国の学校
学校を広義にとらえると、次のように分類することができる。
〔1〕法制上の学校
(a)学校教育法による学校
(イ)第1条校 教育基本法における「法律の定める学校」に該当するもので、これには小学校(初等普通教育)、中学校(中等普通教育)、高等学校(高等普通教育および専門教育)、中等教育学校(中等普通教育ならびに高等普通教育および専門教育)、大学(広い知識の教授、専門の学芸の教授・研究、知的・道徳的および応用的能力の展開)、高等専門学校(専門の学芸の教授と職業に必要な能力の育成)、盲学校・聾(ろう)学校・養護学校(幼稚園・小学校・中学校または高等学校に準ずる教育、障害を補うために必要な知識・技能の教授)、幼稚園(幼児の保育)の10種がある。なお、放送大学は第1条に掲げる大学に属する。
(ロ)その他の学校 第1条に掲げるもの以外の教育施設には、専修学校(職業もしくは実際生活に必要な能力の育成、または教養の向上を図る)、および各種学校(学校教育に類する教育を行う)がある。
(b)他の法律による学校 各省庁等の管轄あるいは独立行政法人に属するもので、職業訓練校、保育所・児童自立支援施設、防衛大学校、水産大学校、海技大学校・航海訓練所・海員学校、および航空大学校などがある。このほかに、社会教育法の対象となる教育活動のなかには、その組織が整備化されて学校あるいはそれに類似した名称を用いるものもある。
〔2〕法制外の学校 企業あるいは各種団体等の設けるさまざまな教育組織、さらには未公認の各種学習塾まで含まれる。
[真野宮雄]
学校の課題
第二次世界大戦後の各国における教育改革は、義務教育年限の延長、および中等・高等教育制度の開放と改革、さらには就学前教育や初等教育制度の整備・拡充などをもたらし、教育の機会均等の実現と個人の能力・適性の助長発展のためにも重要な役割を果たそうとしてきた。しかし、今日のような社会・産業変革の時代に対応するためには、学校教育の具体的な内容とともに、その限界についても改めて問題にされようとしている。現代の教育では、人間ひとりひとりの発達過程に応ずることがますます求められ、しかも学校には、子供が将来の社会生活のなかで、あらゆる社会変化に対応しながら、いっそう発展の可能性をもたらすことが期待されている。
しかも、現代社会では、科学技術の急速な発達や人間の平均寿命の伸長などによって、教育は人間の生涯にわたる社会生活に対してますます重大な影響を生ずるようになった。そのため、人間には職業生活上でも教養生活上でも、生涯にわたって絶えず成長発達すべきことが求められる。そこで、従来のような一定期間内の学校教育だけではおのずから不十分となり、すでに1960年代中ごろよりユネスコ(国連教育科学文化機関)を中心に生涯教育の問題が取り上げられ、その具体化も進められている。
1970年代以後も各国における教育動向として、人間の一生のために人間性豊かな教育を求める「教育の人間化」という流れとともに、未来の学校のあり方についてのさまざまな提案がみられる。わが国においても、「21世紀を展望した教育」の実現を目ざして、臨時教育審議会(1984~87)や文部科学省中央教育審議会等の答申に基づき、多方面に及ぶ教育改革が進行中である。とくに、「ゆとり」のなかで、子供たちに「生きる力」をはぐくむという教育理念を基本に、学校教育内容の厳選と家庭や地域社会における教育の充実を目ざしている。2002年(平成14)4月から公立学校の学校週5日制を実施し、今日の国際的・社会的諸情勢に対応した学校教育の改善・充実を図ろうとしている。さらに、大学・高等学校における入学者選抜の改善、中高一貫教育の導入、大学入学年齢の特例等の教育上の例外措置など、制度上の改革にも及んでいる。このような教育改革を具体化するためには、学校の組織構造自身の弾力化とともに、学校段階間の連続性を図り、さらに家庭や地域社会との密接な連携が必要となる。
[真野宮雄]
『伊藤秀夫・真野宮雄編著『教育制度の課題』(1975・第一法規出版)』▽『河野重男編著『現代教育講座3 現代の学校』(1975・第一法規出版)』▽『吉本二郎編著『教育学研究全集7 学校組織論』(1976・第一法規出版)』▽『真野宮雄編著『現代教育制度』(1977・第一法規出版)』▽『沖原豊・真野宮雄・藤原英夫編著『講座 教育行政2 教育制度と教育行政学』(1978・協同出版)』▽『辻功・木下繁弥編『教育学講座20 教育機会の拡充』(1979・学習研究社)』▽『真野宮雄・桑原敏明編著『教育権と教育制度』(1988・第一法規出版)』▽『吉本二郎・朴聖雨編『学校(講座 学校学1)』(1988・第一法規出版)』▽『真野宮雄編著『生涯学習体系論』(1991・東京書籍)』▽『教育制度研究会編『要説 教育制度』(1991・学術図書出版社)』▽『文部省編『学制百二十年史』(1992・ぎょうせい)』▽『牧野篤著『多文化コミュニティの学校教育――カナダの小学校より』(1999・学術図書出版社)』▽『下村哲夫・染田屋謙相編著『学校教育改革の実現をめぐる問題事例』(2000・学陽書房)』
百科事典マイペディア 「学校」の意味・わかりやすい解説
学校【がっこう】
→関連項目教育|教員|初等教育|脱学校論
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「学校」の意味・わかりやすい解説
学校
がっこう
school
学校「スクール」school(ドイツ語ではSchuleなど)の語源とされるラテン語の「スコラ」schola,ギリシア語の「スコレー」scholēは,本来「閑暇」を意味するものとされ,生活に余裕のある貴族階級によって生み出されたものである。学校の発生は,文字の発生,文字による文化の進歩,蓄積と深い関係をもっている。生活のなかでの教育のみでは十分に文化を次代に伝達することができなくなったとき,これを組織的,計画的に授けるために学校が発生する。
日本で初めて学校が設けられたのは近江令時代であるとされているが,そののち公家の教育機関として大学寮などが発達した。これは,アジア大陸との交通が盛んになるとともに大陸文化が導入され,組織的な教育機関が必要となったためである。中世には主として寺院において学問文化が伝承され,近世になると武家の学校として藩校,庶民の学校として寺子屋などが発達した。明治維新以後は,欧米文化の導入とともに近代的学校が発達し,欧米の制度を模範として,全国民を対象とする近代学校制度が整備された。近代の学校は国家の管理のもとに公教育機関として発達し,義務教育の制度が設けられるようになった。産業の発達や社会の変容とともに,学校の制度も教育内容もその面から大きな影響を受けて今日にいたっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「学校」の読み・字形・画数・意味
【学校】がくこう(かう)
 文公上〕庠序學
文公上〕庠序學 を設爲して、以て之れに
を設爲して、以て之れに ふ。~學は則ち三代之れを共にす。皆人倫を
ふ。~學は則ち三代之れを共にす。皆人倫を らかにする
らかにする 以なり。
以なり。字通「学」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
デジタル大辞泉プラス 「学校」の解説
学校
世界大百科事典(旧版)内の学校の言及
【アカデミー】より
…アレクサンドリアの学術文化を隆盛に導いたプトレマイオス1世,古典文化摂取のため宮廷に学者や詩人を集めたフランク王カール大帝,オックスフォード大学の母体となる学園を創設したイギリスのアルフレッド大王たちは,この言葉の中に教育施設の意味合いを強くこめていたものと思われる。学校そのものをアカデミーという習慣は,その後さまざまな形で西欧世界に定着した。17~18世紀のスイスやイギリスなどの新教徒国にその傾向が著しく,さらに現在でも中学以上の私立学校に対してこの呼称を用いるところは多い。…
【学校建築】より
…近代以前の学校は,大学を除けば,多くは他施設(教会や修道院,王宮,兵営など)に付随し,独立した場合でも,他用途の建物を転用するかその形式や手法を借用して造られたものが多かった。
【ヨーロッパにおける変遷】
古代の建築で学校として用いられたものには,ギリシアやローマなどでパラエストラpalaestraあるいはギュムナシウムgymnasium(ともにラテン語)と呼ばれたものがある。…
【教育】より
…その教育には公的機関の関与のもとに,公費によって組織された公教育と,家庭ないしは私塾による私教育の形態がある。しかし,教育の公教育化は,近代以降一般的であり,今日では私立学校も,公教育の一環として位置づけられる場合が多い。
【教育の根拠】
人間は教育によってその精神的,身体的可能性を開花させ,同時に社会の成員として必要な労働能力,社会的能力を身につける。…
【子ども(子供)】より
…まず,おとなになるための見習い期間とでもいうべき家事使用人となり,さらにそれぞれの身分や家柄に応じた徒弟修業へと入っていく。結果として彼らは,特別の場所や学校に隔離されることもなく,あらゆる点で,きわめて早い時期から全体としての共同生活に組み込まれていった。子どもを説明するための特別の用語は,14世紀以前には見いだされないし,子ども用の服装,玩具,本,また子どもだけの遊びなどが16世紀以前に見られないのは,このことを証している。…
※「学校」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...