共同通信ニュース用語解説 「宇宙開発」の解説
宇宙開発
冷戦が続く1960年代、米国とソ連(当時)が有人飛行や月面着陸の実現を競い合った。その後、巨費を要する月探査は中断し、地上と国際宇宙ステーションなどの基地をスペースシャトルやソユーズといった宇宙船で往復することが主流に。政府機関が主導し、軍事利用色も濃かったが、今世紀に入ってスペースシャトルが退役すると、民間が開発した宇宙船が担う役割が大きくなった。米国などの企業は宇宙旅行にも熱心で「官から民」への動きが加速している。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「宇宙開発」の意味・読み・例文・類語
うちゅう‐かいはつウチウ‥【宇宙開発】
- 〘 名詞 〙 ロケットや人工衛星による天体の観測・探索や、宇宙空間からの地球の地理的測量や気象観測などによって、人類の活動範囲を宇宙空間に拡大する作業。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「宇宙開発」の意味・わかりやすい解説
宇宙開発
うちゅうかいはつ
space exploration
space activities
space development
大気圏外の、いわゆる宇宙空間に光学カメラやレーダーなどの観測機器や人間を送り出し、それを基礎にして新たに知識を増やしたり、あるいは直接に人間の生活に役だたせようという一連の活動。アメリカなどでは宇宙探査space explorationが用いられているが、日本では英語でspace developmentと表現することが多く、space activities(宇宙活動)も好んで用いられている。大気圏外での観測は、それまでの地上からだけのものからは想像もされなかった新しい知識を提供したし、宇宙空間での飛行は、画期的でさまざまな宇宙空間利用の道を開いたのである。
第二次世界大戦後のミサイルギャップ(ミサイル技術の格差)のなかで繰り広げられた米ソ二大国による国威発揚を目的とした宇宙開発競争は、アメリカのアポロ計画による有人月面探査終了後、アメリカの経済・社会的な問題などもあって、徐々に減退し始めた。1980年代後半に入ると世界的な地球環境保護意識の高まりから、人工衛星によって地球を監視し、災害防止などにも役だたせる手段としての利用が脚光を浴びる形となった。さらに東西冷戦の緩和、終結という状況のなか、各国の宇宙開発は自国の技術を確保しつつ、財政上からも国際協力プロジェクトのかたちが始まり多様化し、そして商業衛星打上げから始まった宇宙ビジネスの時代に入っている。
[新羅一郎・久保園晃]
宇宙開発の歴史
宇宙開発の先史
宇宙開発という活動が始まるためには、まず宇宙へ目を向けることが先決であった。その歴史は意外に古く、すでに古代ギリシア時代に、ルキアノスによって月への旅行の空想物語が書かれている。東洋でも8世紀には、唐の玄宗皇帝(在位712~756)が仙術で月の宮殿に遊んだという伝説が生まれた。日本にも9世紀末の『竹取物語』がある。17世紀になると、ガリレイが望遠鏡で、月には山や平野があることを確認し、それによりルキアノスの古い本が見直され、版を重ねたという。そのころケプラーも、妖精(ようせい)が人間を月世界に連れて行くという小説を、惑星の運動に対する有名な三法則を発表したのちに書いている。当時はこうした空想旅行小説が大流行で、イギリスのゴドウィンFrancis Godwin(1562―1633)の『月世界の人』(1638)やフランスのシラノ・ド・ベルジュラックの『月への旅行』(1649)などが出版された。ゴドウィンはハクチョウに引かれて行くことを考え、ベルジュラックは一種のパチンコ風のもので飛んで行くことにした。
[新羅一郎・久保園晃]
科学的な発達史
19世紀もなかばになると、科学知識がしだいに進み、一般的になった。フランスの小説家ベルヌが、砲身300メートルの巨砲で、容器に入れた人間を発射する『地球から月へ』を出版した。また、アメリカの天文学者ヘールは『煉瓦(れんが)の月』を書いて、のちの人工衛星の考えを発表した。19世紀末にはドイツのガンスウィントHermann Ganswindt(1856―1934)がロケット宇宙船の着想を世に問うたが、ロケットの理論を初めて本格的に展開したのはロシアのツィオルコフスキーである。彼はロケットの質量比とか噴射速度の重要性を明確にし、1903年に論文「ロケットによる宇宙空間の探究」を発表した。やがてアメリカのゴダードは1919年に「きわめて高い高度に到達する方法」という論文で、多段ロケットにより月へ到着することを述べた。彼はまた1926年には最初の液体燃料ロケットの飛翔(ひしょう)実験に成功した。多段ロケットの使用法をさらに深めたのはドイツのオーベルトで、1923年に『惑星間空間用ロケット』を書き、宇宙飛行にはロケットが必須(ひっす)であることを明確に述べた。そして1942年、それまでのものより画期的に大きく、しかも誘導装置を備えたV2号ロケットが出現する。V2号そのものはドイツの新兵器の一つであったが、その開発者フォン・ブラウンの胸中には宇宙飛行のことが去来していたに違いない。
[新羅一郎・久保園晃]
宇宙開発の科学技術的基礎
地球の引力に逆らって宇宙空間に乗り出すうえでまず必要なことは、引力に打ち勝つことであり、それにはロケット技術の発展が第一の条件であった。ロケットは、推進剤を多量に短時間で消費することによって強大な推進力を発生させる。しかもこの力は真空中でも発揮される。なお、ロケット本体は、できるだけ軽量であると同時に、十分な強度を保っていることが重要である。発射されたロケットなどの飛行体に対しては、その軌道や姿勢が適切に誘導・制御されることが不可欠であり、電波誘導をはじめ慣性誘導の技術が発達した。搭載機器についても、所定の期間完全に作動し、かつ観測結果がはるかかなたから地上に伝達されるためには電波技術が確立していなければならない。ロケット全体としては非常に部品が多く、しかもそれらの信頼性が高いことが要求される。この信頼性および安全性を調和よく高めて効果をあげるために、全体のシステムをいかに組み立てるべきかという問題が生まれ、ここからシステム・エンジニアリング・マネジメントの分野が生まれた。これらの技術開発は先端的なものばかりであり、同時に多くの関連分野をそこに集中させることが必要である。単に一つの研究所や会社では手に余る事業であるため、国家予算でまかなわれる巨大科学技術(ビッグ・サイエンス)とよばれるものを生むことになり、宇宙開発という大事業が国家の威信の象徴ともみられるようになった。同様のことが、第二次世界大戦にその端を発した原子力開発にもみられる。
[新羅一郎・久保園晃]
宇宙開発の目的
宇宙開発が取り上げられたのは、第二次世界大戦後の、いわゆる冷戦の時期であった。大陸間弾道弾と人工衛星打上げ用のロケットとでは基本的にはほとんど差がないという事情もあって、宇宙開発の第一の目的は軍事利用にあった。長距離の偵察用飛行機にかわって、偵察用人工衛星の価値が高く評価されたのである。第二に国の力の誇示、すなわち国家の威信が重視された。たとえば、スプートニク1号やウォストーク(ボストーク)1号の打上げが成功したときソ連は、「これは社会主義体制の勝利だ」と誇った。第三が純粋に科学的な基礎研究の手段としての重要性であって、これによって新しく宇宙科学という学問の分野が生まれた。第四に、人工衛星を人間生活に直接役だたせようという意図であって、そのための人工衛星を実用衛星という。実用衛星の最初は1960年の気象衛星タイロス1号で、それ以来、通信、気象観測、航行、測地、地球資源探査、地球環境保全、宇宙環境利用など各種の衛星が打ち上げられ、大きな成果をあげている。
なお宇宙開発がもたらしたものとして、宇宙技術の波及効果(スピンオフ)がある。先端技術を駆使するものであり、その技術は各方面に利用されていった。たとえば、ロケット機体用の軽量・高張力鋼開発、ロケット弾頭とか再突入時のためのセラミック開発技術、人工衛星用の電源の応用、遠距離通信技術の発展、無重量状態での材料科学、生命科学などさまざまな活用である。
また、宇宙開発による国際協力の推進も見逃せない。宇宙平和利用条約が生まれ、観測結果を利用しあったり、宇宙計画を国際協力で遂行しようという動きが盛んになってきた。
[新羅一郎・久保園晃]
太陽系の無人宇宙探査計画
宇宙探査の手始めは観測ロケットによる大気圏の物理特性の解明であった。ドイツの兵器として登場したV2号は、1946年秋、アメリカで打ち上げられ、地上からでは観測されない短紫外線が太陽から放射されていることを明らかにした。それ以来、今日まで、多くの観測ロケットが打ち上げられたが、観測時間を拡大し、また局地的な観測を全地球的なものに広げるために人工衛星が誕生した。
世界で初めての人工衛星はソ連のスプートニク1号で、1957年10月4日に打ち上げられた。直径58センチメートル、重さは約84キログラムの球形で、超高空の大気密度を測定した。アメリカ初の人工衛星エクスプローラ1号(1958年2月1日打上げ)は、地球をドーナツ状に取り巻く放射能帯(バン・アレン帯)を発見した。このように科学研究を目的とした人工衛星を科学衛星という。主として無人のものをさすことが多いが、有人の宇宙船でももちろん、その主たる目的は科学研究にある。人工衛星の軌道が地球のまわりから伸びるにつれ、太陽から放出される太陽風とか、地球を立体的に取り巻く磁気圏の状態なども判明してきた。
一方、地球の引力を脱出して太陽の周囲を回る人工惑星が出現するとともに、月、金星、火星、水星、木星、土星などを探究する各種の宇宙探査機が活躍するようになった。その最初の成功は、1962年8月27日に打ち上げられたアメリカのマリナー2号で、109日の飛行ののちに、金星から3万4000キロメートルのところを通過し、金星の表面温度やその大気の構成などを測定し報告してきた。1964年11月28日打上げのマリナー4号は火星から約9800キロメートルまで接近し、表面の写真22枚を電送してきたが、期待された運河はなかった。
月への軟着陸に初めて成功したのはソ連のルナ9号(1966年1月31日打上げ)で、月面のパノラマ写真を送ってきた。惑星への軟着陸の最初はソ連の金星4号(1967年6月12日打上げ)で、その大気や気象を測定した。火星への初めての軟着陸はソ連の火星3号(1971年5月28日打上げ)で、同年12月に成功した。
水星探査機の始まりはアメリカのマリナー10号で、1973年11月3日に打ち上げられ、翌年3月に水星から640キロメートルまで接近し、水星表面が月面そっくりであることを確認した。
アメリカは1972年3月3日パイオニア10号を打ち上げ、それは翌年12月に木星に接近し、表面の模様や、木星の衛星ガニメデの奇怪な姿を電送してきた。パイオニア11号(1973年4月6日打上げ)も1974年12月に木星、1979年9月に土星に最接近して、それぞれ観測に成功した。パイオニア10号および11号は、1983年6月と1990年2月にそれぞれ太陽系を脱出した。一方、1977年9月5日アメリカからボイジャー1号が打ち上げられ、まず1979年3月に木星に接近したのち、1980年11月には土星に接近し、土星の環(わ)の微細構造や、土星の衛星タイタンを観測した。ボイジャー1号より少し前の1977年8月20日にはボイジャー2号が打ち上げられ、1981年8月に土星に最接近し、土星の環のより微細な構造を明らかにして、天王星に向かった。
[新羅一郎・久保園晃]
有人宇宙飛行計画
ソ連のスプートニク2号(1957年11月3日打上げ)にはイヌが乗せられ、宇宙で1週間を過ごしたが、それは、やがて人間が乗った宇宙船の出現を予想させるものであった。これに対抗してアメリカはマーキュリ計画を発足させ、有人衛星を実現しようとした。マーキュリ・カプセルは総重量1.3トンで1人乗りである。7人の宇宙飛行士が選抜され、彼らの訓練も始まった。ところがソ連でも1人乗りの宇宙船の計画が進んでおり、それは重さ4.7トンであった。ソ連は1960年8月には、イヌを2匹乗せたスプートニク5号を無事に回収し、有人飛行の間近いことを思わせた。そして、1961年4月12日、ついに有人飛行が実現した。宇宙船の名前はウォストーク(ボストーク)1号、搭乗者はガガーリン、1時間48分で地球を1周し、無事にソ連領内に着陸した。宇宙空間から地球をみたガガーリンは「地球は青かった……」という名言を残した。人間が宇宙に乗り出した最初の記録であり、ここに本格的な有人宇宙飛行時代が始まった。
ウォストークに遅れをとったマーキュリ計画は、翌1962年の2月20日に、グレンJohn H. Glenn(1921―2016)を乗せたフレンドシップ7号の地球3周に成功した。1人乗りの次には2人ないし3人乗りの宇宙船が登場する。1964年10月12日打上げのソ連のウォスホート(ボスホート)1号は3人乗りで地球を16周し、1965年3月18日打上げのウォスホート2号は2人乗りだったが、その1人レオノーフ(レオーノフ)А.А.Леонов/A. A. Leonov(1934―2019)は宇宙船から出て、世界初の船外活動を20分間行った。アメリカの2人乗り宇宙船は1965年3月のジェミニ3号から始まる。アポロ計画で必要とされたランデブーならびにドッキングの技術を習得するためである。最初のランデブーは、ジェミニ6号(1965年12月15日打上げ)とジェミニ7号(1965年12月4日打上げ)との間で1965年12月15日に成功した。続いてジェミニ8号は1966年3月16日、標的用の無人宇宙機アジェナと史上初めてのドッキングを行った。ソ連でもソユーズ4号(1人搭乗、1969年1月14日打上げ)とソユーズ5号(3人搭乗、1969年1月15日打上げ)との間でドッキングに成功し、5号の乗員2人が4号に移乗した。
1969年7月16日打上げのアポロ11号は7月20日に人類初の月着陸に成功した。月面に降り立ったのはアームストロングとオルドリンEdwin Eugene Aldrin Jr.(1930― )で、アームストロングはその際、「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である」との名言を残した。月までの往復の飛行時間は195時間19分であった。
ソ連のソユーズ11号(1971年6月6日打上げ)は、まえもって軌道に打ち上げられていたサリュート1号とドッキングし、搭乗者3人がサリュートに移乗して、各種の実験を行った。6月30日にソユーズは地球に帰還したが、搭乗者3人は死体で発見された。飛行時間は約570時間に及び、宇宙ステーションのはしりとなった。
ポストアポロ計画として1973年には、アポロ宇宙船打上げに使われたサターンⅤ型ロケットの第3段の内部を改造して宇宙ステーションとするスカイラブ計画が実施された。1973年5月14日、サターンⅤ型が打ち上げられ、無人の実験室(スカイラブ1号)が軌道に乗った。5月25日、月着陸部を除いたアポロ宇宙船(スカイラブ2号)がサターンⅠB型により打ち上げられ、スカイラブ1号とドッキングして3人が移乗した。そしてスカイラブ1号内で種々の科学技術実験を行い、滞宇宙日数28日で帰還した。次のスカイラブ3号の打上げは同1973年7月28日で、59日間宇宙に滞在した。最後のスカイラブ4号の打上げは同年11月16日で、滞宇宙の記録は84日間と延び、スカイラブ計画は成功裡(り)に終了した。無人のスカイラブ1号は1979年7月12日オーストラリア南西部一帯に分裂落下した。打上げ当初のその高度は440キロメートルであった。ソ連のサリュートはT7号まで打ち上げられ、ソユーズとはT7号までがドッキングを行った。このT7号は1982年8月19日打上げで12月10日に帰還した。同船には宇宙に行った2人目の女性宇宙飛行士サビツカヤSvetlana Savitskaya(1948― )が同乗した。
アメリカはスカイラブの次にはスペースシャトルの飛行を始めた。これは、機体を数十回にわたり使用・回収をし、費用の節約を図ろうというもので、科学技術の実験のほかに、次期計画の宇宙ステーションの組立てや、そこからの人工衛星の打上げなどを目的としている。
[新羅一郎・久保園晃]
世界および日本の動向
スプートニク1号以来世界で打ち上げられた人工衛星の数は、2007年12月末までに5942個に達する。そのうち、消滅したり回収されたりしたものも多い。これらの97%近くが人工衛星であり、正確な数は不明であるがその多くを軍事衛星が占めると推測される(アメリカは軍事衛星は打上げ後に軍事衛星として発表するが、ロシアはソ連時代から軍事衛星、科学衛星の区別なく、一括して「コスモス」と呼称し、その実体は軍事目的が多い)。
宇宙開発において、ソ連、アメリカが他の国々を大きく引き離してきたのは明らかであるが、それに続くのはフランス、中国およびインドといえよう。フランスでは中距離弾道弾の開発に力を入れ、それに手を加えて、1965年11月26日に国産のロケット「ディアマン」で自国製の人工衛星A1(42キログラム)を軌道に乗せた。日本は1970年(昭和45)2月11日に初めて「おおすみ」(24キログラム)を打ち上げた。続いて同年4月24日には中国が「東方紅」(173キログラム)を打ち上げたが、その重さは「おおすみ」の7倍を超えていた。中距離弾道弾から大陸間弾道弾へと開発を進めていたイギリスの進展は意外に遅く、自力で人工衛星を軌道に乗せたのは1971年10月28日である。「プロスペロ」(66キログラム)と命名され、「ブラックアロー」ロケットで、オーストラリアのウーメラ基地から打ち上げられたが、その後、ロケットの不具合が続きウーメラからの打上げは中止された。
[新羅一郎・久保園晃]
国際協力の形
自国産のロケットで自国製の人工衛星を軌道に乗せるほかに、自国製の観測計器を外国の人工衛星に積み込んで打ち上げたり、衛星そのものは自国産だが、打上げは外国に依頼する方法も珍しくない。
宇宙開発は、ロケットによる各種衛星の打上げから軌道への投入、運用、データ受信、処理や解析、さらには大気圏への再突入、落下、回収という一連のサイクルをもつ活動であり、元来、国境を越えた活動範囲をもつ。したがって経費もかさみ、1国、1機関ではまかないきれなくなっているのが現状である。科学的探査や地球観測の分野では、1個の衛星に多くの国の観測機器を搭載して共同研究とするケースが増えており、成果もあがったのである。
たとえば、1962年4月26日には、イギリス製の電離層観測器具を積んだエリール1号という衛星がアメリカから打ち上げられたし、同1962年9月29日には、カナダ製の衛星アルエット1号(145キログラム)がアメリカのロケットにより打ち上げられた。1964年12月15日にはイタリア製の衛星サンマルコ1号が、アメリカの射場からアメリカのロケットによりイタリア人チームの手で打ち上げられた。日本の気象、通信、放送の三静止衛星もアメリカNASAのデルタロケットにより1977年、1978年にそれぞれ打ち上げられた。
さらにはアメリカの木星探査機ガリレオやハッブル宇宙望遠鏡(NASAとESAの共同)、ヨーロッパの太陽極軌道観測機ユリシーズ(NASAとESAの共同)や、地球磁気圏の尾を観測する日本のジオテイル(NASAと宇宙科学研究所の共同)などの国際共同プロジェクトをあげることができる。
実用衛星分野でも、たとえば各国内用通信衛星をはじめ国際移動通信衛星機構(IMSO)、国際電気通信衛星機構(ITSO)、ヨーロッパ通信衛星機構(ユーテルサット)などの衛星は、国際宇宙ビジネスとして各国のメーカーに発注、製作されたうえ、それをさらに他国のロケットやアメリカのスペースシャトルで打ち上げ、各機関が運用するという形態が多くなっている。衛星打上げビジネスとして、ロシアや中国も、西側諸国より安価な信頼の高い打上げサービスを提供しようとしており、各衛星ユーザーとしても、利用する打上げロケットの選択には一大決心が求められている。
スペースシャトルが実用段階に入って、観測機器とか人工衛星そのものをスペースシャトルによって打ち上げるのが一般的になり、アメリカ国籍でない人が同乗することになった。すでに、1978年3月2日に打ち上げられたソ連のソユーズ28号にはチェコスロバキア人の宇宙飛行士が乗り込み、1977年9月29日から飛行を続けていたサリュート6号無人宇宙機とドッキングした。この方式の国際宇宙船は、その後、ポーランドや東ドイツとの間でも打ち上げられた。また1975年7月15日にはソユーズ19号とアポロ宇宙船とが同日に打ち上げられ、ドッキングののちに双方の宇宙飛行士が移乗して交歓した(アポロ/ソユーズドッキング計画)。そのときの最大の困難は英語とロシア語との会話の問題であったといわれる。宇宙開発において、国際協力はいろいろな形で進められている。2001年4月28日、民間人として初めてアメリカの実業家デニス・チトーが推定約2000万ドルでロシアのソユーズに乗り込み、国際宇宙ステーション(ISS:International Space Station)に移乗して6日間滞在し、商業宇宙旅行への始まりとなった。続いて2002年4月26日には、南アフリカの富豪マーク・シャトルが約2000万ドルを支払ってソユーズに乗り込み、ISSに約1週間滞在した。
ソ連で開発され1986年2月19日に打ち上げられた第3世代宇宙ステーション「ミール」への搭乗者も東欧圏に限らず、西側各国宇宙飛行士による利用も宇宙ビジネスとして行われた。ミールはその後、当初の基幹モジュール、クリスタル、クバント(2基)、スペクトルおよびプロリーダモジュールと増結されて、1996年4月には全重量約123トンの大型宇宙ステーションとなった。さらに冷戦緩和後は、ロシアも国際宇宙ステーション(ISS)計画に参加し、1995年6月から1998年6月にかけてISS計画の第1段階におけるスペースシャトル/ミール結合ミッションが計9回、米ロ宇宙飛行士の活躍の場となった。一方ミールは老朽化が進み、唯一の宇宙ステーションとしての任務は、第2段階の1998年11月20日(ISSの最初の構成要素「ザーリャ」打上げ)からISS建設に移行された。ロシアではミールの存続を求める声も高かったが、2000年12月ロシア政府は資金難のためミールの廃棄を決定、ミールは翌2001年3月23日に大気圏突入後、南太平洋に分裂落下して約15年の活動を終了した。
1984年アメリカ大統領レーガンの日本・ヨーロッパ・カナダへの参加要請で始まった新しいISS計画は、その後たび重なる設計変更があったが、1993年ロシアの参加という米ロ間の政治的決定を受け、世界15か国による最大規模の国際宇宙協力プロジェクトとなった。
一方、着々と有人活動の準備をしてきた中国は、4回の無人宇宙船「神舟」を打ち上げ(1999年11月21日、2001年1月10日、2002年3月25日、同年12月30日)、2003年10月15日には、初の有人宇宙船「神舟5号」の打ち上げに成功し、世界で三番目の有人宇宙船打ち上げ国となった。
[新羅一郎・久保園晃]
各国の宇宙開発体制とそのおもな機関
日本では、宇宙開発・利用政策を受け持つ政府機関として従来の宇宙開発委員会があり、宇宙開発に関する重要な政策を企画・審議して内閣総理大臣に意見を述べていたが、2001年(平成13)1月の中央省庁再編により同委員会は文部科学省下に所属し、宇宙開発事業団(NASDA(ナスダ))の活動のみに関与するという過渡的存在となった。
その後、抜本的な宇宙基本法の決定(2008年5月21日)および国としての宇宙開発戦略本部が発足し、宇宙基本法が策定されている。
研究機関としては航空宇宙技術研究所(NAL(ナル)。2001年4月より独立行政法人)、宇宙科学研究所(ISAS(アイサス)。文部科学省)などがあった。後者の付属施設として鹿児島県肝付(きもつき)町内之浦(うちのうら)に鹿児島宇宙空間観測所(打上射場)などがあった。このほかに、文部科学省、総務省および国土交通省の共管特殊法人である宇宙開発事業団、その付属施設として種子島(たねがしま)宇宙センター(打上射場)や筑波(つくば)宇宙センターなどがあった。これら、文部科学省下であった宇宙3機関(宇宙開発事業団、航空宇宙技術研究所、宇宙科学研究所)は、2003年10月、統合され新たな独立行政法人、宇宙航空研究開発機構(JAXA(ジャクサ))となった。これに伴い、鹿児島宇宙空間観測所は、内之浦宇宙空間観測所に改称された。
アメリカの航空宇宙局(NASA(ナサ))も政府の一機関であり、アメリカ全土にまたがる施設(14か所)をもち、航空・宇宙関係の研究と開発を行っている。付属機関として、エームス研究センター、ジョンソン宇宙センター、マーシャル宇宙飛行センター、ケネディ宇宙センター、ゴダード宇宙飛行センター、ジェット推進研究所、ラングレー研究センター、グレン研究センター、ステニス宇宙センターなどのほか、全世界に点在する人工衛星追跡施設やデータ取得施設をもつ。
ヨーロッパでは、ヨーロッパ宇宙研究機構(ESRO)とヨーロッパロケット開発機構(ELDO)とが別々にあったが、1975年5月にヨーロッパ宇宙機関(ESA)に統合された。加盟国はオーストリア、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、オランダ、スイス、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、スペイン、アイルランド、ノルウェー、フィンランド、ポルトガルの15か国(カナダは協力国)で、本部はパリにある。フランスはESAの重要メンバーであるが、それとは別に国立宇宙研究センター(CNES)を有する。ドイツもESAの主要メンバーであるが、宇宙研究開発の実施機関として国立航空宇宙研究所(DLR)をもっている。
一方、東西冷戦緩和後、ロシアもロシア宇宙庁(RSA)を新しく発足させ(その後ロシア航空宇宙機関=RASAと改称)、大国として自国および国際協力での宇宙開発や商業衛星打上げに積極的である。
[新羅一郎・久保園晃]
宇宙開発の将来
生命が地球に誕生して以来、人類は海から陸へ、陸から空へとその活動領域を拡大してきた。生命の進化の延長線上にあるわれわれ人類は、いまや科学技術を駆使し、その活動領域を宇宙へと拡大しつつある。
人類は古来、宇宙、太陽系の存在、地球およびそこに住む生命体の誕生といった根源的な疑問への答えを探求し続けてきている。この疑問にこたえる宇宙の科学的探求活動は、人類の知的フロンティアの拡大を目ざすものとして、ますます重要なものとなってきている。これらによって得られるさまざまな知見や知識は、新しい宇宙観・地球観・生命観を生み出し、新たな思想や文化の創造、知的で成熟した社会の実現に貢献するものと考えられる。
衛星通信・放送、全地球測位システム(GPS)による航空・船舶・自動車等のナビゲーション、気象衛星を用いた天気予報は、すでに人々の生活に不可欠なものとなっている。このような衛星システムの利用は今後ますます高度化し、将来の高度情報通信社会を支える重要なシステムとして、質の高い豊かな生活に貢献するものである。また、無重量などの宇宙空間の特徴を利用した新しい材料・医薬品等の開発についても進展が期待される。
一方、人工衛星の利用により、気象・海洋・地表の変化、地球の温暖化、緑の減少と砂漠化の進行、オゾン層の状況、災害の発生状況等を定期的かつ高精度で観測することが可能と考えられ、宇宙開発は地球科学の推進や地球環境の保全等に大きく貢献する可能性をもつといえよう。
また、厳しい環境への対応や高い信頼性が要求される宇宙技術は、幅広い分野の科学技術を結集することが要求される先端的な総合技術である。宇宙技術を開発し、高度化していくたゆまぬ努力は、材料、コンピュータ、ロボット、エレクトロニクス、通信、情報処理等のさまざまな分野の新技術の創出に貢献するとともに、これらの技術を利用した付加価値をもつ新しい産業を創出することに貢献する可能性を秘めている。これらと併行して一般人の宇宙旅行ビジネスも徐々に本格化されよう。
さらに、未知なる宇宙は次世代の青少年にとって最大の挑戦の対象の一つであり、宇宙開発を通じてこの宇宙への夢とチャレンジ精神を青少年に引き継いでいくことは、科学技術のみならず幅広い分野にわたって将来の人材の養成を促し、人類の経済社会の活力の維持に貢献すると考えられる。
日本においては、このような宇宙開発のもつ意義を十分に認識し、1955年(昭和30)、東京大学生産技術研究所でのペンシル・ロケット研究の開始以降、関係者の営々たる努力が積み重ねられてきた。その結果、宇宙科学については、多くの分野で国際的にも高い評価を得る成果をあげている。また、通信、放送、気象、地球観測、宇宙環境利用等の実利用分野の宇宙開発についても、順次自主開発努力を拡大し、H-ⅡAロケットおよびH-ⅡBロケットの打上げや各種人工衛星の開発等により、分野によっては国際的な水準の技術や能力を得るに至った。しかし、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、中国が力を入れはじめた宇宙商業ビジネス、とくに衛星打上げサービス分野への参入には打上げロケットのコスト低減、信頼性の向上など克服すべき問題が多い。
目を海外に転ずれば、アメリカおよびロシアの宇宙開発においては、国威発揚や軍事的な意味合いの強いプロジェクトの推進から、経済性と効率性を重視して、宇宙技術の軍民転換を図り、将来へ向けた先端技術を開発することに重点を移しつつある。これに、世界の打上げ市場をリードしているヨーロッパ、独自の立場で自主技術開発を推進してきた中国が加わって、世界の宇宙開発においては商業利用を重視する動きが一段と強まっている。また、従来、日本、カナダ、ヨーロッパ、アメリカの4極で進められていた国際宇宙ステーション計画に、ロシアが新たにパートナーとして参加するなど、大きな宇宙開発のプロジェクトについては、国際協力を重視するという流れがこれからの世界の宇宙開発の主流になりつつある。このように、世界の宇宙開発は商業利用と国際協力の重視が今後の重要な課題となるものと考えられる。
以上のような内外の大きな情勢の変化のなかで、日本の宇宙開発はさらに新たな展開をしていくべき段階にある。日本としては、宇宙開発のもつ意義を改めて確認するとともに、世界における宇宙開発の商業利用および国際協力重視の流れを十分認識し、これまでに培った宇宙開発の技術や能力を高めつつ、グローバルな視点にたった無人・有人の宇宙の本格利用を目ざして、宇宙ビジネスや世界の宇宙開発に積極的な役割を果たすことが、国民から強く望まれている。
[新羅一郎・久保園晃]
『山中龍夫・的川泰宣著『宇宙開発のおはなし』(1991・日本規格協会)』▽『キャロル・ストット著、的川泰宣監修(日本語版)、スティーヴ・ゴートン写真『ビジュアル博物館71 宇宙探検』(1998・同朋舎)』▽『中村浩美著『最新 宇宙開発がよくわかる本』(1999・中経出版)』▽『田中一郎編『21世紀の宇宙開発』(2001・科学技術振興協会)』▽『的川泰宣著『ロシアの宇宙開発の歴史――栄光と変貌』(2002・東洋書店)』▽『武部俊一著『宇宙開発の50年――スプートニクからはやぶさまで』(2007・朝日新聞社)』▽『笹本祐一著『宇宙へのパスポート3 宇宙開発現場取材日記』(2008・朝日新聞社)』▽『『歴史群像シリーズ 日本の宇宙開発――果てなき空間への果てしなき夢』(2009・学研マーケティング)』▽『日本航空協会編、刊『航空宇宙年鑑』各年版』▽『日本宇宙少年団編、的川泰宣・毛利衛監修『スペース・ガイド』各年版(丸善)』▽『中野不二男著『日本の宇宙開発』(文春新書)』▽『的川泰宣著『月をめざした二人の科学者――アポロとスプートニクの軌跡』(中公新書)』▽『中冨信夫著『NASA宇宙探査の驚異――「宇宙の姿」はここまでわかった』(講談社+α文庫)』

スプートニク1号

惑星探査機「マリナー」(イメージ図)
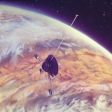
惑星探査機「パイオニア」(イメージ図)

惑星探査機「ボイジャー」(イメージ図)

アポロ11号による人類初の月面着陸と月…

宇宙実験室「スカイラブ」

人工衛星「おおすみ」

スペースシャトルの打上げ

木星探査機「ガリレオ」

ハッブル宇宙望遠鏡

国際宇宙ステーション(ISS)

実験棟「きぼう」

軌道科学宇宙ステーション「ミール」

種子島宇宙センター

ケネディ宇宙センター

ESA本部

H-ⅡAロケット

H-ⅡBロケット
改訂新版 世界大百科事典 「宇宙開発」の意味・わかりやすい解説
宇宙開発 (うちゅうかいはつ)
宇宙開発は,日本でとくによく用いられる用語である。海洋と宇宙という新しい場を利用する技術の必要性が認識されるようになって,未開地の開発,あるいは開拓と同じような意味合いで海洋開発が取り上げられ,そして未開の新しい環境下における先端技術としての共通性から宇宙開発という言葉が生まれた。
しかし,英語では宇宙開発の英訳であるspace developmentが使用されることはきわめて少なく,space exploitation(宇宙利用)というのがふつうである。
宇宙開発は,本来の意味からすると人間の宇宙空間および天体の利用であるが,これまでの経過をふりかえると,そのための技術の開発,すなわち人工衛星とロケットの開発と解釈される傾向があり,一般にはとくに両者を区別することなく,人間の宇宙への進出の活動全体を宇宙開発と解釈しているようである。
→宇宙飛行 →人工衛星 →ロケット
宇宙への進出
宇宙開発が大きな課題として認識されるようになったのは,1957年に始まった国際地球観測年を契機としてであり,ここにおいて全世界的な事業として宇宙空間の観測を主とするこの分野の研究が取り上げられた。そして具体的に人類の宇宙への進出の第一歩となったのは,この期間の57年10月4日にソ連(現ロシア)が打ち上げた人類初の人工衛星スプートニク1号であり,初めて人工衛星による地球の周辺の空間の観測が行われた。続いてアメリカが打ち上げたエクスプローラー1号は,スプートニクより高い高度を飛ぶ人工衛星となり,これによる観測で地球を取り巻く放射線帯(バン・アレン帯)が発見された。
このように人工衛星は宇宙空間の観測に新しい道を開いたが,これと並行して,人間と生物を人工衛星で打ち上げて,宇宙での生活を研究することも直ちに開始されている。すなわち,ソ連は57年11月3日にライカ犬をのせたスプートニク2号を打ち上げて無重量状態下において哺乳動物が生存できることを証明した。これに対抗してアメリカはマーキュリー計画という有人飛行計画を立て一連の飛行を開始し,61年1月31日にはチンパンジーを弾道飛行させた。人間が宇宙空間に進出したのは,初の人工衛星打上げからわずか3年半後であり,61年4月12日ソ連はYu.ガガーリンを人工衛星ボストーク1号にのせ,地球の周回飛行を行った。
1960年代の半ばまでは,宇宙開発は米ソ二大国の独占であったが,60年代後半になると両国に続く国が現れてきた。なかでも65年にA1衛星を打ち上げたフランス,70年に〈おおすみ〉を打ち上げた日本,同じく70年に〈東天紅〉を打ち上げた中国の3国は自国で開発したロケットを用い,独力でも宇宙開発を進める意志を示したものであった。さらに71年にイギリスは自力でオーストラリアからプロスペロ衛星を打ち上げ,インドも80年にロヒニ衛星を打ち上げて,自力による人工衛星打上げの7番目の国となった。
科学観測
宇宙開発の初期の段階では,将来の宇宙空間利用に必要なさまざまなデータの収集や純粋な科学研究を主目的として,地球周辺の宇宙空間の観測がアメリカ,ソ連を中心に活発に行われた。アメリカはエクスプローラー・シリーズによって,地球周辺のみならず地球を脱出して太陽系の空間観測も行った。さらに1960年代からはより大型の科学衛星として,OAO(orbital astronomical observatoryの略),OGO(オゴ)(orbital geophysical observatoryの略),OSO(オソ)(orbital solar observatoryの略)のシリーズを打ち上げて,天文学,地理学,太陽観測などを行った。60年前後からはタイロス,エッサのような地球を観測する科学衛星の登場とともに,人工衛星を地球上の2点間の通信のために用いる初期の通信衛星の実験も行われ,宇宙空間における科学研究を主体としながらも,同時にそのために必要な技術の生活への応用が早くも開始されていた。
→科学衛星
月を目ざして
科学観測の方法は地球を周回する人工衛星によるもののほか,月や惑星に直接探査機を送り込む方式へと発展した。すでに1959年にソ連のルナ3号は月の裏側の写真を地球に送ってきており,66年にはルナ9号が月面上に軟着陸して初の月の表面の写真を送ってきた。アメリカはアポロ計画の予備観測として,レンジャー,サーベイヤー,ルナオービターの月観測計画を実行した。1961年から始まったレンジャー計画は,探査機が月に衝突するまでの写真をとることを主目的として合計9機が月に送られたが成功率は低く,9号機でようやく衝突までの完全な写真がとれた。66年からのサーベイヤー計画は,無人の探査機を月面に軟着陸させて,月面上で月の岩石や土の性質を調べ,アポロの有人月着陸船の着陸点を探査するのが目的であった。サーベイヤーは月面に5機着陸して,写真撮影と土の分析をする任務を遂行した。ルナオービター計画は精密な月面地図を作成するために66年に始められたもので,月のまわりを回る月の人工衛星にカメラをのせて詳細な月面図を作成し,これをアポロの着陸地点の選定に用いた。これによって月に関する科学的知識は飛躍的に増大した。
アポロ計画は,〈1970年代にアメリカは人間を月に着陸させ無事に帰還させる〉というケネディ大統領の公約を実現する計画であったが,69年7月16日にN.アームストロングとE.オルドリンが月面に無事着陸したことは,人類の歴史上画期的なできごとであった。アポロ計画で月面に足跡を残した人間は12名であり,彼らは月面で多くの科学研究の仕事をし,また毎回持ち帰った月の石は研究用として今なお十分なストックを蔵している。
ソ連は人間を月に送ることは計画していなかったが,無人探査機による研究の面では,70年のルナ17号でルノホートという月面車を走らせたり,72年にはルナ20号で月の岩石を自動装置によって地球に持ち帰るなど,高級な技術を試みて成功している。
→月
惑星探査
1970年代には惑星探査の分野においてアメリカとソ連が大きな成果をあげた。とくに76年アメリカの火星バイキング探査機が着陸して,火星の光景を写真で送ってきたり,土を分析して生物の存在を確かめようとしたことは特筆される。地球にもっとも近い金星には,ソ連が1965年金星表面にペナントを送り込んで以来,82年までに14機のベネラVenera(金星の意)探査機を送り,金星の表面の探査においてはいつも先駆的役割を果たしてきた。一方,アメリカはマリナー10号(1973-74)によって金星の上空の大気を測定し,パイオニア金星(1978)によって地表データを得ている。
火星より遠い,木星以遠の星と金星より太陽に近い水星とは,そこにいくためにいずれもロケットの能力が格段に大きいものが要求されるので〈深宇宙〉ということがある。この空間の惑星の探査に関しては,アメリカの独壇場である。すなわち,木星,土星,天王星,海王星などの太陽系の外惑星の探査にはこれまでパイオニア10号と11号が先鞭をつけ,続いてより本格的なボエジャー1,2号が送られた。ボエジャーは,木星と土星の写真撮影と観測を行うとともに,フライバイすることによって加速し,より大きな速度を得てさらに天王星と海王星を目ざし,最終的に太陽系を脱出することになっている。1,2号それぞれの探査機は,この間,約10年間作動し続けるために,文字どおり長い寿命を保つように設計されていた。そして,ボエジャー2号は打上げ後12年の1989年,海王星に最接近し任務を終えた。
→惑星
宇宙空間の利用と人間の滞在
宇宙がまだ観測や研究の対象であったころ,宇宙空間はせいぜい国家威信や軍事能力の誇示のための目的しかないと考えられていた時代がしばらく続いた。しかし,人工衛星や有人飛行技術がある程度確立されるや否や,これらの技術を地上の生活に役だてうることがすぐに明らかになってきた。そしてそれが可能になったものは順次,地上の一般の人々の社会活動の一部として,あるいは軍事力の一部として不可欠なものとなってきた。
通信
最初に宇宙技術の応用が実用化されるようになったのは通信の分野である。人工衛星を中継局として用いるアイデアは,作家のA.クラークが静止衛星軌道の利用として早くから予言していた。しかしこれはロケットや衛星技術が進歩するまでは実現せず,最初の通信衛星には,約1500kmの高度の軌道で,地上から送った電波を反射して別の地点で受信をする原理のエコー衛星が試みられた。これにややおくれて,通信を中継する機能をもった衛星が作られ,地上からの電波を人工衛星が受信して,これを増幅して地上の受信局に送信するものが出てきた。リレーとかテルスターと呼ばれるもので,低高度の人工衛星軌道で試験的に用いられた。さらに改善された通信衛星はこれを静止衛星軌道にのせて,つねに地上との位置関係を同じに保ち,あたかも地球上の上空に固定した中継局のように利用するものである。NASA(ナサ)のシンコム3号(1964)がこの種の衛星の先駆けとなり,現在ではインテルサットという国際組織による同名の通信衛星の運用が行われ,国際通信の一端を担っている。このほか,ロシアは高緯度の領土に適した楕円軌道のモルニア型衛星を用いて国内通信に供している。
通信衛星には地上の2点を結ぶもののほかに,人工衛星と人工衛星,人工衛星と地上の間の通信を行うものも登場しつつある。また一方向的通信というべきものに放送衛星があり,これも静止衛星が利用できるようになって登場したものであって実用衛星の中では新しい歴史をもつ。
→宇宙通信 →衛星通信 →衛星放送
気象観測
気象衛星は人工衛星から雲の画像をカメラでとって地上に送ってくるもので,アメリカはタイロス,ニンバスの各試験研究用,そしてエッサによる実用にはいずれも低高度衛星を用いた。ソ連のメテオールも同様な気象衛星である。世界気象監視計画では,各国が分担して合計5個の静止気象衛星を打ち上げている。
資源探査
資源衛星は人工衛星から光の波長ごとにいろいろな写真画像をとり,それを物質の出す光の波長の分布(スペクトル)の特性と比較することによって地表の状態を知ることができる原理を利用している。資源衛星は他の実用衛星に比べるとややおくれて,アメリカでは1972年にアーツを,続いて75年2号をランドサットという名称で打ち上げ,得られた画像のデータは各国に設けられた地上局で受信して,その地元での利用に供されている。農業の作柄,森林の状態などの監視,地質学・水理学・海洋学のデータ収集,地図の作成など幅広い重要な分野にわたって利用されているが,他国の上空から情報を得ることの合法性といった点で問題を残しており,放送衛星の放送対象とともに宇宙法の争点の一つとなっている。
測地,航行援助
地上で位置を求めるために,天体の代りに用いられるものが測地衛星である。測地衛星の試みは実用衛星の中では通信衛星とともに古く,1962年にはすでに登場している。初期のものはフラッシュランプを点滅させ,地上でこれを写真撮影してこれをバックの星空と比較したり,2点で同時観測したりして地上の位置を出した。その後用いられたものはレーザー光線を反射する鏡式のものがふつうである。航行衛星は同じことを電波を使って行い,船や航空機の航行を援助するためのものである。人工衛星も数個同時に用いて精度を上げており,NAVSTAR(ナブスター)と呼ばれる航行衛星システムは,すでに商業化されて船舶でごくふつうに用いられている。
軍事利用
これまでにあげた各種の機能,あるいはこれらを組み合わせた機能をもった衛星を,軍事目的のために用いるものを軍事衛星と称している。例えば通信衛星により軍用機,艦船,基地間の通信を行うためのシステムがある。また測位に用いるものは,とくに今日のように航空機や艦船がミサイルの発射点となっているときには重要である。いわゆる偵察衛星は地上画像による情報収集を目的としたものであるが,さらに核爆発やミサイル発射検出機能をもつものも利用されている。このように,これまでの軍事衛星は主として支援と偵察の任務をもち,戦略・戦術システム,中枢部との関連づけがその有効さを左右している。なお,衛星攻撃用人工衛星の実験を別とすれば,軍事衛星そのものを攻撃的な兵器とした例は,これまでのところはないと信じられている。
有人飛行
宇宙空間の利用を目ざすとき,そこでは人間が一定の期間滞在することが課題となり,またその基地としての宇宙ステーションの建設,宇宙ステーションと地球との往復などの問題を解決しなければならない。アメリカがアポロ計画の月飛行を行っている間に,ソ連は71年4月19日に大型の宇宙ステーション,サリュート1号を打ち上げて,ソユーズとの連係飛行による長期間の宇宙飛行を開始した。これはアメリカが月への人間一番乗りを目ざしたのに対して,ソ連は地道ではあるが宇宙への長期の進出を第1の目標としたことを意味している。サリュートは82年までに1号から7号が打ち上げられ,この間,宇宙飛行士による各種の観測と実験を行うとともに長期宇宙滞在の人体に及ぼす影響を研究しつつある。宇宙船内での人間の滞在時間は次第に延びているが,4ヵ月以内ならばとくに無重量状態の効果である骨の成分の喪失などは地上に帰還後数週間のうちに回復することが明らかにされているが,6ヵ月以上になると問題が残るといわれている。
一方,アメリカはこの分野でのおくれを取り返すために,アポロ計画半ばからアポロの器材を用いたスカイラブ計画を開始した。スカイラブはアポロ計画で用いた長さ100mのサターンロケットの4段目を改造して宇宙ステーションとしたものである。1973年に打ち上げられ,科学実験を数多く遂行した後,79年にオーストラリア南西部に落下した。
1975年にはアメリカのアポロ宇宙船とソ連のソユーズ宇宙船によるアポロ・ソユーズ共同飛行が行われたが,この時点を境として,アメリカはそれまでの使い捨てのロケットから再使用可能なスペースシャトルの利用への転換を目ざし,打上げロケットを全面的にこれにおきかえるとともに,宇宙空間における活動もスペースシャトルを積極的に利用するという方向づけを行った。すなわち,スペースシャトルはこれまでのロケットのように人工衛星を直接打ち上げるだけでなく,宇宙ステーション建設のための資材の運搬,宇宙ステーションと地球との連絡,宇宙環境における科学実験などを行うスペースラブの搭載およびこれとの組合せによる運用など幅広い利用を目ざしたものである。スペースラブでは,その乗員は特別に訓練を受けなくてもよく,また搭載機器もなるべく地上の規格品をのせることができるようにするなど,これまでより幅広い分野の人々に宇宙をより身近にするということを前提として構想されたものである。
有人飛行においては,宇宙環境の人体に及ぼす危険性とともに,宇宙飛行そのものの安全性が問題となる。ソ連のソユーズ1号は飛行の帰還時にパラシュートが開かず宇宙飛行士が死亡しているが,これが宇宙飛行中に起こった初めての事故であった(1967)。2番目の事故は1971年6月30日,ソユーズ11号の帰還時に発生した。このときは正常に帰還したかのように見えたが,のっていた3人の宇宙飛行士は,空気の抜けた気密室の中で死亡していた。アメリカの場合宇宙飛行中に死亡事故を起こしたことはないが,1970年4月11日に打ち上げられたアポロ13号は燃料電池の酸素タンクの破損のために緊急帰還している(その後86年1月28日,アメリカのスペースシャトル・チャレンジャー号が打上げ72秒後に爆発し,乗組員7人死亡の事故がおきた)。
このように危険性が高いにもかかわらず,米ソ以外の国々も有人宇宙飛行への参加の動きが高まっていた。スペースラブでは,開発を通じて有人宇宙飛行の技術に習熟するとともに,これを用いた飛行にESA(イーザ)の加盟国から選抜した科学者が参加したし,ソ連のサリュート計画には東欧諸国などの宇宙飛行士が参加し,ソ連の宇宙飛行士とペアを組んでソユーズ宇宙船にのり込みサリュートに短期滞在をしている。このほか,フランスと中国は独力で有人宇宙船を打ち上げるための計画を明らかにしており(中国は2003年に成功),国際的な宇宙活動に有人飛行の占める比重が大きくなることが予想される。
→スペースシャトル
宇宙をめぐる利権
前述のように国際協力に基づく宇宙の国際化が進められている一方では,宇宙を巡る権益争いも目だつようになってきた。宇宙を巡る国際問題では,〈宇宙はだれのものか〉というのが基本テーマであり,これは海洋開発が抱えているのと同じ性格のものである。もっとも問題点,あるいは資源的価値が今一つはっきりしないという点で海洋ほど鮮明な利害論争はまだ出ていない。目先のことをいえば,利用価値の高い静止衛星軌道の使用権,領空の概念がどこまで適用されるかという資源衛星や軍事衛星の飛行権,電波の侵入を認めるかといった放送衛星の問題などがあげられよう。
→宇宙法
宇宙開発のコラム・用語解説
【世界の代表的な宇宙開発機関】
[アメリカ]
- NASA
- National Aeronautics and Space Administrationの略。アメリカ航空宇宙局と訳される。アメリカ政府機関の一つで非軍事宇宙計画のすべてを担当する。1958年にNACA(National Advisory Committee for Aeronauticsの略)を母体として設立された。大規模の実施機関として,ジョンソン,マーシャル,ケネディなどの有人飛行センターをはじめ,計11の宇宙飛行センターや研究所を有する。アポロ計画,スペースシャトルのように未知の分野にかかわる大きな計画を立案し実行する能力がとくに優れている。
[ソ連]
[日本]
- 宇宙開発事業団
- 1969年に日本の宇宙開発の中で科学分野以外の分野を一元的に実行する機関として設立された。このため,さくら(通信),ゆり(放送),ひまわり(気象)など実用目的の静止衛星シリーズを開発する一方,これを打ち上げるためにNⅠ,NⅡ,HⅠなどのロケットを開発してきた。発射場は種子島宇宙センターにあり,また筑波宇宙センターにおいて衛星追跡管制を行う。このほか,ロケットの試験場やNASAの地球観測データを受信するセンターを有している。
- 宇宙科学研究所
- 81年4月に東京大学の宇宙航空研究所が独立してできた全国大学利用研究所。日本の宇宙科学研究を行う中枢的な研究所である。その起源は1955年に始まったペンシルロケット研究にさかのぼることができる。70年に打ち上げた〈おおすみ〉により日本は世界で4番目の衛星打上げ国となった。現在はMロケットによる科学衛星計画を担当しているが,大学機関がロケットの開発まで行いつつ科学衛星を打ち上げている例は世界でもほかに例がない。
[ヨーロッパ諸国共同]
- ESA
- European Space Agencyの略。欧州宇宙局と訳される。フランス,西ドイツ,イギリス,イタリアを中心として,西欧諸国が共同して設立した宇宙開発の機関。1975年に従来ヨーロッパの宇宙科学研究を進めてきた機関であるESRO(エスロ)(European Space Research Organizationの略)と,宇宙ロケットの開発を担当してきた機関であるELDO(エルド)(European Launcher Development Organizationの略)が合併してできた組織。科学と応用のための人工衛星の開発および打上げ用アリアンロケットの開発と,これによる人工衛星の打上げ,さらにはアメリカとの共同計画によるスペースラブの開発など科学・応用有人の宇宙活動を手がけている。本部はパリ,研究センターがオランダとイタリアに,またオペレーションセンターが西ドイツにある。
[西ドイツ]
- DFVLR
- Deutsche Forschung und Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrtの略。ドイツ航空宇宙研究所と訳される。ドイツ研究技術省の下におかれ,宇宙開発に関する研究と開発を行う総合的機関である。本部はボンの近くにあるが研究センターはドイツ全土に散在している。ミュンヘンは人工衛星技術,シュトゥットガルトは推進,ボンは気体力学,宇宙医学,ゲッティンゲンとブラウンシュワイクは空気力学など,古くから有名な研究所が勢ぞろいしている。
[中国]
- 中国空間技術研究院
- 中国は日本の省に相当する宇宙航空工業部という政府組織の下に空間技術研究院がおかれ,これにロケット,人工衛星の開発のための研究所,工場,試験センター,ロケット発射場などの実施機関が所属している。さらに宇宙空間の科学研究を行うために科学院の下に空間技術センターがおかれ,日本の宇宙科学研究所で行っている宇宙観測の研究と同様の分野の研究を行っている。
[インド]
- ISRO(イスロ)
- Indian Space Research Organizationの略。インド宇宙研究機関と訳される。原子力委員会の中にあった宇宙研究部門が1972年独立してできた組織。現在はインド宇宙省に属する。本部および四つのセンター(研究・開発センター,発射場,衛星追跡センターなど)からなる。なかでも,創始者の原子力委員長の名をとったビクラム・サラバイ宇宙センターは,国産の人工衛星とその打上げロケットの開発から打上げまでを行っている最大のセンターである。
宇宙開発の将来
宇宙利用としてはまだ小規模なものであるが,目ざされているものの一つに太陽発電衛星がある。これは,静止衛星軌道上の人工衛星で太陽熱を利用して100万~1000万kWの電力を発電し,それを地上へマイクロ波などによって送電しようというものである。人工衛星といっても大きさが5kmないし20kmの大きな建造物である。このような大型の構造物の建造のためには,地球の資源よりも月の資源を開発したほうが運搬が容易であり,各種公害も出さなくてすみ,将来は月の資源開発は真空中で太陽エネルギーによって精錬するという新しい技術が登場すると思われる。また,これを発展させると月だけでなく小惑星を鉱物源として利用することができ,このようなところで大量に資材が加工できるようになると宇宙空間に大都市を作ることも可能になる。アメリカのG.K.オニールの提案したスペースコロニーはその代表的なものであり,これらが行われるようになって,初めて宇宙開発はほんとうに開発という意味をもつことになる。
日本の宇宙開発
日本の宇宙を目ざしたロケット研究は,1955年東京大学生産技術研究所の糸川英夫のグループによるペンシルロケットの打上げに始まる。このロケットは直径1.8cm,長さ23cmの固体ロケットで,都下国分寺で水平発射実験を繰り返して,ロケットの基本的な特性を明らかにしていった。その後これはベビーロケット,カッパロケットへと発展する。57年に始まった国際地球観測年の事業としてカッパロケットによる高層大気観測が承認され,これを機会にカッパロケットが日本の観測ロケットとして用いられることとなった。これは東大生産技術研究所を中心とする文部省および大学関係を中心に組織され,国際地球観測年の後も事業は継続され,ロケットはラムダ,ミューと大型化した。そして64年宇宙科学研究のための全国大学共同利用研究所として宇宙航空研究所が誕生,科学衛星計画を担当することになり,この結果,これまでの観測ロケットはすべてこの研究所が引き継ぎ,新たにミューロケットの開発が始まった。70年2月日本初の人工衛星〈おおすみ〉がラムダ4S型5号機によって打ち上げられ,翌年にはミュー4S型ロケットにより科学衛星の1号〈しんせい〉が打ち上げられて,科学衛星による観測が本格的に始められた。
一方,人工衛星の実利用面では,1969年10月に宇宙開発事業団が発足し,実利用分野の人工衛星計画とこれを打ち上げるロケットの開発を担当することになった。電離層観測衛星はその第1の目標で,このためのロケットとして,アメリカのソーロケット技術をベースにしたNIロケットが開発され,技術試験衛星〈きく〉,電離層観測衛星〈うめ〉などが打ち上げられた。
執筆者:長友 信人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「宇宙開発」の解説
宇宙開発(うちゅうかいはつ)
宇宙飛行可能な観測・探査ロケット開発の動因は,第3回地球観測年(1957~58年)ではなく,冷戦期(45~89年)の大陸間弾道弾(ICBM)搭載可能な大型ロケットの開発競争であった。旧ソ連が人類初の人工衛星スプートニク1号打ち上げに成功した(57年)ことは,アメリカへ甚大な衝撃「スプートニク・ショック」を与え,1960年代以降の宇宙開発を含む自然科学研究・教育へのめざましい整備,投資拡大をもたらした。有人宇宙飛行も旧ソ連に先んじられたアメリカは,ケネディ大統領提唱のアポロ計画(11号月面着陸,69年)の成功で面目を一新した。大気圏外の宇宙と地上を往復,再利用するスペースシャトルは70年代から開発され,81年就航の「コロンビア」が1番機である。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
百科事典マイペディア 「宇宙開発」の意味・わかりやすい解説
宇宙開発【うちゅうかいはつ】
→関連項目ロケット(工学)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の宇宙開発の言及
【航空宇宙工業】より
…このロケット技術をさらに進めることで,ナチス・ドイツでは第2次大戦後に米ソで実用化された各種ミサイルのプロトタイプのほとんどすべての実験が行われていた。ソ連のスプートニク1号打上げ成功の後,アメリカは遅れをとり戻すため58年にNASA(アメリカ航空宇宙局)を設立し,61年にはケネディ大統領によりアポロ計画が発表され,69年アポロ11号により人間を月面に着陸させることに成功し,宇宙開発の第1期段階は終了した。その後,72年にニクソン大統領がスペースシャトル計画を承認したことにより,新しい宇宙開発時代(宇宙空間の宇宙での実用化時代)の道が開かれた。…
【人工衛星】より
…1950年代に入ると,米ソは競って人工衛星打上げを目ざしたが,57年10月4日,ソ連(現ロシア)が世界初の人工衛星スプートニク1を軌道に乗せることに成功した。宇宙開発の歴史は,国際地球観測年の歴史でもあり,スプートニク成功の直前の57年7月以来今日に至るまで,これに基づいた宇宙科学観測が継続されており,日本の宇宙開発の第一歩もこれによっている。 60年代に入ると直ちに人工衛星の実用的利用も模索され始めた。…
※「宇宙開発」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...

