目次 本の材料と形態の歴史 前史 中国,日本 インド メソポタミア エジプト ギリシア ローマ 小アジア 中世 ルネサンス以後 世界の出版史 西洋 ローマから中世へ イスラム文化圏 大学出版,書物市場の拡大 印刷・出版業の成立 著作権,出版者 中国 写本から木版本へ 宋版 中国の活字本 元・明・清 近・現代 日本 古代・中世 活字版の時代 書店出版の時代 明治以後 現代 現代における本の役割 課題と将来 本は書物,図書とも呼ばれ,最も歴史が長い情報伝達の媒体である。形態的には,自然のままの(たとえば木の葉や竹),または加工した物質的材料(たとえば羊の皮,紙)を選び,その上へ文字や図を筆写または印刷したものを有機的に配列し,保存・運搬に適するよう,その材料の性質が要求する方法でひとまとめにしたものをいう。内容的には,思想または感情の伝達を目的とするもののすべてが含まれる。ユネスコが1964年,加盟国に対し行った〈本及び定期刊行物統計の統一化に関する勧告〉によれば,〈本とは表紙を除き,少なくとも49ページの不定期刊行物であって,その国で出版されかつ一般的に入手できるもの。但し(1)主として広告の目的で刊行されるもの,(2)一時的な性格を有するもの(時刻表,電話帳など),(3)文章記述が最重要部分を占めない楽譜,地図類は除外する〉とされている。
この項目では本とその出版史などについて解説するが,関連の項目として〈印刷 〉〈出版 〉〈雑誌 〉〈製本 〉〈装丁 〉〈愛書趣味 〉も参照されたい。また,〈新聞 〉〈マス・コミュニケーション 〉などの項目においても関連する事項が解説されている。さらに〈百科事典 〉〈図書館 〉の項目も付随的な解説を含んでいるので,参照されたい。清水 英夫
本の材料と形態の歴史 本はその特質から内容の面と物としての面の2面をもつが,ここではまず後者の面から本の歴史をみることにする。
前史 本は思想または感情の伝達が目的である以上,穴居時代の人間が壁に描いた絵画,むかし中国やペルーで行われた結縄 (けつじよう),北アメリカ原住のインディアン が用いた貝殻文字,いまも未開人の間で行われるという藁算(わらざん)などは,書物の原始的な形とみてよいであろう。しかしこれらは,有効で正確な伝達手段ではない。歴史家ヘロドトスが,ペルシアのダレイオス王についてしるしている物語は暗示的である。ダレイオスがスキタイ人の国に攻め入ったとき,1人のスキタイ人伝令が国王の信書をもたらした。信書は1羽の鳥,1匹のカエル,1匹のモグラ,3本の矢の絵であった。ダレイオスはカエルが水を,モグラが土をあらわすとみ,ペルシア人の兵力(3本の矢)に恐れ,スキタイ人たちはその水陸の国土を捨て,鳥のように逃げてゆくと判読し,おおいに安心したのに,その夜スキタイの王は猛烈な攻撃を加えてきた。ペルシア人たちが鳥のように逃げ去るか,モグラのように土にもぐるか,カエルのように水にくぐるかしなければ,スキタイ人の激しい攻撃をのがれられないであろうというのがその絵手紙の真意だったのである。どのようにでも解釈される絵文字の意味を一定のものとするために,象形文字が生まれ,さらに進化して表音文字となる。十全な意味での書物は,文字の形成を必要な先行条件とした。
中国,日本 秦がまだ天下を統一しない時代には,書物の材料は竹と木であった。竹はおおむね25~75cmの長さの簡(竹のふだ)で,これに8~30字くらいを1行に書く。30~100字くらいまでを書く必要のあるときは,ふつう90cm2 の牘(とく)(木のふだ)を用いる。しかし100字以上を必要とする場合には,簡を何本でもなめし革で編みつらねたもの,すなわち〈冊(さく)〉をつくる。冊という字は簡をなめし革でつらねた象形文字であり,ここに中国の最も古い書物の形態が求められる。しかし周の威烈王から秦の始皇帝に至る戦国時代(前403-前221),中国では帛(はく)(絹布)もまた書写の材料となった。帛を書物とする場合は巻子本 (かんすぼん)(軸をつけて巻いたもの)の形態をとったと想像されるが,帛は価高く,実用には供せられなかった。中国ばかりでなく,やがて世界中の書物に革命をうながしたのは,後漢の和帝時代(88-105)の末に完成した紙の発明である。紙がもっぱら書物の材料となってからは,巻子本,折本 (おりほん)(巻子本を縦に細長く折りたたんだもの。経巻や法帖(ほうじよう)類に多い),旋風葉 (せんぷうよう)(折本の背の部分をのりづけしたもの。表紙を軽くつまんで広げると,風にひるがえるように紙がひらひらするところからの呼称),粘葉装 (でつちようそう)(料紙を二つ折りにして重ねあわせ,折目の部分にのりづけしたもの)を経て綫縫(せんぼう)(糸とじにしたもの)に至る。これらの形態は,中国文化の圏内にあった朝鮮や日本にも伝わったが,日本では,ほかに,列帖装(れつちようそう)(何枚かの料紙を重ねて中央から折ったものを1単位とし,これを幾つか重ねて表紙を添え,糸でかがったもの),大和綴(やまととじ)(室町以降に発達した袋綴(ふくろとじ)と同じように料紙を重ね,こよりなどで下とじを行い,前後に表紙を添え,右端を2ヵ所結びとじにしたもの)など,独自の方法を案出した。また日本における西洋風のとじ方は,天正の末年(16世紀末)キリシタン版が行われてからのことである。
インド ヤシ科に属するターラ樹(パルミラヤシ )が,古くから書物の材料に用いられた。長さは2mにも及ぶその扇状の葉をよくかわかし,横45~60cm,幅7cmほどに切り,両面に文字を書き入れる。数十葉を重ね,一定の場所に穴をあけて糸を通し,同じ大きさの木製の板の間に収めて散乱を防ぐ。インド,ビルマ(現ミャンマー),セイロンなどの仏教国では,仏典がこの貝多羅葉(ばいたらよう)によって保存・伝達されたため,金属や紙を材料とする場合にも,同じ形態がまねられた。
メソポタミア ティグリス,ユーフラテス両大河の間にはさまれたこの地方では,年中絶えず河水によって泥が運ばれたために,粘土の供給が豊かであり,粘土板が書物となった。適当な大きさと厚さをもつ粘土板が作られ,その柔らかな両面に,アシ(葦)や木片をとがらせた筆を直角に軽くつきこみ,直線から成る楔形(くさびがた)文字 を書きつづっていく。これを太陽の熱でかわかし,かまどに入れて焼きしめると,ほとんど石と変わらないほどの強さを得る。火に燃えず,水におかされず,またパピルスや羊皮や紙と違い,動物からの害も受けず,土中に埋めておけば戦禍にも耐え,たとえ破壊されても,破片を集めれば,ある程度にもとの形が得られる。この地方では数千年にわたってこれが書物であり,文化を栄えさせた。イギリスのアッシリア学者G.スミス(1840-76)が,H.ラッサム(1826-1910)その他の協力者とともに,数回に及ぶ探検によって,往古のアッシリア図書館の遺跡をしらべた結果,おびただしい数にのぼる粘土板文書 が推定され,有名なアッシュールバニパル王のものだけでも,2万部に達するという。現在の書物のページづけに相当する番号が,粘土板の各面にしるされ,共通の見出しがどの陶面にもつけられていた。たとえば大英博物館所蔵の世界創造についての粘土板文書は,どの面も〈むかし天上にあったものは空と呼ばれた〉との文言で始まる。保存の点では理想的な粘土板文書も,重いため運搬が不便であり,またこの材料のために発生した楔形文字も,アラム文字に屈し,ついに粘土板文書は書物の世界から消え去った。そのころ,もっと便利な書物の形態がエジプトで用いられていた。
エジプト およそ5世紀に至るまでの約5000年間,地中海域の文化国家で書物の材料となったパピルス は,小アジアやナイル川沿岸の湿地に往時繁茂した植物で,カヤツリグサ科 に属し,高さは2mに及び,根の太さは人間の腕ほどあり,切断面は三角形をなし,牛の尾に似た先のほうに花が咲き,竹のような節がある。東洋諸国のヤシや竹と同じように用途が広く,食料や衣料のほか,花は婦人の頭髪の飾りにも用いられた。旧約聖書の《出エジプト記》の第2章には,生後3ヵ月のモーセが,パピルスで編んでアスファルト と樹脂とを塗った籠に入れられ,ナイル川の岸のアシの中に捨てられる記事がある。このパピルスから書物の材料をつくる方法は,プリニウスの《博物誌》第13巻にくわしくのっている。すなわちパピルスの茎を割れば,長さ30cmほどの節と節との間に,木髄質が見いだされる。これを抜き出して鋭いナイフか何かで縦に細く裂き,すきまなく1列に並べ,さらにその上へ同じものの1列を直角に置き,のりの力をもつナイル川の濁水を注いで密着させ,重しをかけて日に干し,槌(つち),象牙,貝殻,または軽石などでみがくと,かなり良質の紙に似たものができる。木髄の中心部が最上で,高級な書写の材料となり,外皮に近い部分は劣等品を作った。その供給は政府の専売であったらしく,下請業者の実在を示す2世紀の文書が残っている。こうしてできたパピルスの1枚の幅は,38cmに達するものもあるが,ふつう25cmくらいのものが最上とされた。紙を意味する英語のペーパー,ドイツ語のパピール,フランス語のパピエ,ロシア語のパプカなど,みなパピルスから出ているので,パピルスを紙の始まりであるかのように考え,プリニウスの記述中に見える〈テクスントゥルtexuntur〉(織る,置く,作る)を〈漉(す)く〉と訳した例もあるが,漉くという操作を経ずに,水に浸してプレスしただけのパピルスは本質的に紙とはいわれない。粗質多孔の植物繊維であるため,これに文字をしるすには特別のインキが必要とされる。インキはすす(煤)と水とを混ぜて作られたが,インキを適度にペンへひきとめておくためにアラビアゴム が加えられた。インキの質は中世のものほど良くはなく,エジプト人が消しゴムの代りに使った海綿で容易に消された。アシ製のペンの先をとがらして二つに割るくふうは,パピルスに文字を書く必要から考え出されたものである。文字は象形文字であるが,パピルスにならば金石に彫る場合と比べ,ひじょうに速く書けるので,しだいに線がくずれ,原形を失っていった。しかし神官たちはパピルスに書く場合にも,つとめて正確な原形を保とうとしたから,古代のエジプトでは,神聖文字(ヒエログリフ ),神官文字(ヒエラティック ),民衆文字(デモティック )の3種類の文字が並び行われた(エジプト文字 )。書写の材料が文字にまで変化をもたらす一例である。1枚のパピルスにはいくらも文字が書けず,また上下の2層を直角に交差させるため,表と裏とでは繊維の向きが異なり,ふつう片面だけにしか書かれなかったので,何十枚かをのりでつぎあわせ,中国の巻子本に似た巻物をつくる。いままでに知られている最も長い巻物は,ラメセス2世 の治世をほめたたえた大英博物館所蔵のハリス・パピルスで,33mにも達するが,一般に長尺のパピルス巻物は,富んだ人が死んだとき墓に埋めるための儀式用〈死者の書〉であり,実際に読むための文学的なテキストは短い巻物に書かれるのが普通であった。パピルス本が現れてから,エジプトの書物文化はめざましい発展をとげ,プトレマイオス朝 の首府であったアレクサンドリア には,紀元前すでに大きな図書館(アレクサンドリア図書館 )が建ち,盛時には一説に70万巻以上の蔵書を誇ったといわれる。
ギリシア クレタ島では,ギリシアの先住民族であるミノア人によって,ギリシア文学 の興るはるか以前の時代,少なくとも前2000年のころ,文字の行われていたことが今日十分に証明されている。伝承によれば,ギリシア文字は,前14世紀のころ,カドモスがフェニキアからアルファベット を移入したときに始まるという。したがって,ホメロス時代に文字がなく,ただ記憶によってだけ文学を伝えたとする旧説は今日ほとんど信じられず,少なくとも職業的な吟唱者たちは,なにかの形の書物をもっていたものと推定されるが,当初それがどのようなものであったかを確実に知る手がかりはない。ヘロドトスによれば,皮が小アジアで古い時代から書物として用いられたらしい。パピルスもおそらく早い時代にエジプトから輸入されたであろう。《イーリアス》が24巻に分けられたのは,すでにパピルス巻物がギリシアにおいても用いられるようになってから後のことである。《オデュッセイア》は《イーリアス》より少ない巻数におさめられるにもかかわらず,やはり24巻に分けられたのは,《イーリアス》と釣り合うためであろう。そういう場合には,大きな文字で書かれるのがつねであった。しかし一般にギリシアの巻物は,エジプトのそれに比べてはるかに短く,ふつう10mを長さの限度とする。
パピルス巻物は,文字を書く前に仕立てられ,これに左方から欄を作っていく。詩を書く場合には,1欄の幅は詩行の長さによってきまる。オックスフォード 大学図書館蔵の《イーリアス》第2巻のパピルス巻物は,類のないほど大きな文字で書かれているので,欄の幅は約19cm,余白を入れると約25cmもある。写字生が自由に行の長さを選びうる散文の場合だと,欄の幅はずっと短くなり,5~8cmが普通であった。余白の大きさは,その本の外観の美しさを顧慮して割り当てられ,書物がすでに工芸美の対象であったことが知られる。巻物の初めには,ほぼ1欄と同じ幅の空白をみるが,これは読むときに巻物を持つための,また思いがけない損傷から内容を守るための便宜であろう。この空白の部分にわれわれは作品の題名や著者名を予期するが,初期の活字印刷本でもそうであったように,題扉(だいひ)(とびら)にあたる部分は初めになく,あるとすれば巻末であった。
ローマ 古くは麻に書いた書物もあったらしいが,ラテン文学盛時のローマでは,もちろんパピルス巻物が書物の普通の形態であり,カトゥルス,マルティアリス ,ティブルスらの作家に,しばしばその言及をみる。美装を誇る場合には,パピルスの端に軸がとりつけられ,軸からは取っ手がつき出て飾りともなった。読まないときの保護のために,美しく染色された皮が巻物を包む。現今の書物の背文字の役目は,パピルスまたは包皮の端からたれている張紙がする。パピルス巻物は,本棚に反物のように横たえられるか,円筒形の容器に数巻ずつ入れられるかした。1世紀にはローマにおいてもすでに羊皮紙本のかなりの普及をみているが,その用途は下書きや備忘のためであったらしく,パピルスが最も権威ある書物の材料だと考えられた。ほかに注意すべきものにローマ人の発明した蠟板の書物がある。これは18世紀の終りころまで,ヨーロッパではかなり広範囲に用いられた。ブナその他,強い木で作った書物型の小板が何枚かとじあわせられている。それらの小板は,裏も表も中央部が長方形にえぐられており,そのえぐられた部分に黄色または黒色の蠟が一面に塗られる。ただ最初と最後の蠟板の外に面したくりぬきだけが,文字のすり消えるのを恐れて蠟引きされていない。この蠟板に,スティルスstilusと呼ぶ先のとがった鉄筆で字を書く。〈文体〉を意味する英語のスタイル,フランス語のスティル,ドイツ語のシュティルは,この鉄筆からきた言葉である。ローマ人はこの蠟板を書信の往復にもよく使った。
小アジア プリニウスはパピルスについて記した《博物誌》の同じ場所で,皮紙がペルガモンで発明され,その後この材料の使用が一般に広がり,これによって人類の不滅性が確立したと述べている。ヘレニズム時代に文化の一大中心地となった小アジアのミュシアの首都ペルガモンの王エウメネス2世 (在位,前197-前159)は,父アッタロス1世の雄図をついで学芸の振興に力を注ぎ,アレクサンドリアのそれにも匹敵するほどの図書館を建てようと思い立ち,当時エジプトのプトレマイオス 5世エピファネス王(在位,前205-前180)のもとでアレクサンドリア図書館長をしていた文献学者,文法学者ビザンティンのアリストファネス (前257ころ-前180ころ)を,ペルガモンの自分の宮廷に招こうとした。プトレマイオスは怒ってアリストファネスを獄に投じ,ペルガモンへのパピルス輸出を厳禁した。エウメネスはパピルスに代わるものとして,当時小アジアが羊,ヤギ,牛などの多産地であるのに目をつけ,古くから行われていたのとは別の方法で,これらの動物の,とくに子の皮を書写の材料とするのに成功した。皮は注意深く洗われ,毛を除き,軽石でみがかれ,チョークで仕上げられる。その結果,パピルスのように折り目から裂ける恐れはなく,強く,色はほとんど白に近い良質のものが得られた。ただし,近年ユーフラテス上流のローマ陣地遺跡を発掘したとき,皮紙文書が出土し,その年代がほぼエウメネス2世の治世の初めに相当することがわかったので,皮紙(羊皮紙 )はエウメネス2世以前すでにアジアで用いられており,彼のなしとげたところは,他の目的のために存在していた材料を文学的な目的のために発達させたのにすぎないと説く学者もある。それはともあれ,皮紙を意味する英語の〈パーチメント 〉は,〈ペルガモンの(紙)〉を意味するギリシア語の〈ペルガメネ〉からきている。当初は出版行為において,ただちに皮紙がパピルスの競争相手となりはしなかった。ローマの作家たちが書物に関して述べている言葉は,少なくとも1世紀末まではパピルスについてである。折ることも切ることも自由にでき,両面に書写が可能である皮紙の機能が十分に利用されて,現今の書物の体裁が確定したのは5世紀以後である。
中世 この〈巻く本〉から〈とじる本〉への進化は,暗黒時代とも呼ばれた中世,修道院の中に閉じこもって信仰と文明との明りを護持したキリスト教の修道士たちによって行われた。1926年までに出土したオクシュリュンコス全写本を調べると,3世紀以前にはコデックス (冊子本)はまったく現れていないのに,4世紀になると,異教文学のパピルス巻物はずっと減り,キリスト教の著書が大多数を占め,その総数36のうち2点を除いて他はみな冊子本である。このように,異教に対するキリスト教の勝利は,書物の世界においては,パピルスと皮紙とを問わず,巻物形式に対する冊子本形式の勝利となり,やがて皮紙が書物の主要な材料となってからは,ルネサンスに至るまでのおよそ1000年間,書物工芸の黄金時代をもたらした。
冊子本作製の順序を略述すると,まず十分にみがかれた1枚の皮紙を写字机の傾斜面に置き,定規をあてて鉛でうすく線を引き,頭文字の部分を残し,他の本文を入念に書きすすめる。エジプト人の使ったのと同じアシのペンもみられるが,鵞(が)ペンも新しく用いられた。皮にしみこむためには,パピルス用のインキは不適当なので,没食子(もつしよくし)の汁,緑礬(りよくばん),樹脂などを混じた良質のものがくふうされた。頭文字は絵の巧みな修道僧の手でとくに美しく金,銀,赤,青などの絵具をもって描きあげられ,その周囲を花,鳥,小動物などいろいろの図様で彩飾する。このようにして必要な枚数が何ヵ月か何ヵ年かのちに完成すると,丁合せをして小口と反対の端に2ヵ所ないし3ヵ所縦にみぞを作り,そこへ皮の帯を通してとじあわせ,金属か木の板のパネルを前後にあてがい,そのパネルをさらになめし革で包み,パネルとなめし革の間へ皮帯を逃がし,突き出たその端に,とめ金や錠前をつける。現今の書物の形態はこのときすでにできあがったといってよい。表紙にはなめし革の代りにビロードその他の材料が用いられることもあり,それに刺繡を施し,または金,銀,宝石をちりばめ,豪華の限りをつくすものもまれでなかった。その結果早くも10世紀以後華麗になりすぎて本来の用途から離れ,表紙の浮彫はますます高くなり,象嵌はいよいよ大きくなり,正しい工芸的見地からは堕落の方向をたどった。皮表紙の場合でも,鋭利な道具で文字や図案を切り刻むのと,鈍い道具で型押しするのと二つの方法があり,中世では主として前者が用いられ,9世紀に作られた〈フルダの福音書〉などはその代表的作例であるが,これも時代がくだるにつれ工芸的には堕落している。
ルネサンス以後 中国で発明された紙は,玄宗の天宝10年(751)唐がアッバース王家のアブー・ムスリム に敗れたのを契機として,サマルカンド やバグダードに伝わり,13世紀ついにイタリアやスペインにはいった。これが書物の形態を規定し,活字印刷術の発明が中世冊子本の普及を可能にした。活字が彩飾本における最もすぐれた書体の忠実な模倣であったように,紙もまた皮紙を理想としてその書物の材料としての機能を見いだしていった。しかし紙の性質によって,書物の形態にも,中国・朝鮮・日本で発達した袋綴型と,ヨーロッパで発達した両面印刷型と,二つの系統が立てられる。かりに前者を東洋型,後者を西洋型と名づけることができよう。西洋の紙は手すきのも機械すきのも,繊維の処理がこまかなため細密で両面印刷がきくのに対し,東洋の手すき紙は繊維が長く粗放で,かつ板張りが多いため裏表の不同を生じ,かなりの厚紙でも片面しか印刷ができない。それぞれ長所と欠点とをもつこの二つの型の美点を,どう調和させるかに今後の書物工芸の一つの問題があろう。
世界の出版史 1冊の本は人類の叡知の反映であるとともに,それは出版という営為により,初めて公のものとなる。現代では出版物は商業出版によるものが大半を占めるが,出版が社会的な営みとして成りたつようになるためにはだれでも本を手にできるように社会そのものが発達するまで待たねばならなかった。ここでは以上にみてきたような材料と形態の変遷に加えて,出版を通じて形成されてきた本の世界の歴史をみることとする。
西洋 古代のエジプトには〈死者の書 〉というものがあり,死後の世界への通行券として遺体とともに墓に葬られ,また会葬者も故人をしのぶ記念としてこれを買い求めたと伝えられる。地中海域における最も古い出版行為であろう。アレクサンドロス大王 (在位,前336-前323)の時代になると,出版も盛んであったらしいが,それは著者の名声を広めるためであって,金銭的な利益は伴わなかった。アレクサンドリアが文化の中心であった時代には,そこに有名な図書館があり,ギリシア,ローマ,エジプト,インドの書物を多く蔵していた事実から推して,出版もまた盛んであったことが想像される。
ローマから中世へ しかし出版の実況が初めて具体的にとらえられるのは,ローマが文化の中心となってからであり,およそ紀元50年ころのことである。パピルスに文字を書いて巻物に仕立てる当時の書物製作過程はきわめて簡単であり,しかも多くの奴隷がその製作に従事したから,今日では想像も及ばぬほど,早くまた安く書物は生産された。1世紀のローマの風刺詩人マルティアリスは,《銘句集》第2巻の初めに,その1巻を1人の奴隷が1時間で写し,しかも彼はその時間内にほかの仕事もしたと書いている。キケロが親友アッティクスに送った手紙その他によると,書物は生産過剰となり,一掃売出しさえ行われたらしい。出版物はローマの皇帝が検閲した。暴君ドミティアヌスなどは,自分の意に反する書物が出版されると,その著者のみならず筆写した奴隷まで殺したと伝えられる。法治思想の発達したローマではあったが,版権に関する規約はなかった。著者が出版者から稿料をもらったかどうかについては,肯定と否定の両論があるが,詩人ホラティウスは,〈私の作品は海のかなたにまで伝わって名声四方にとどろいているけれども,いっこうに黄金は私のふところにはいってこない〉と嘆き,マルティアリスも,〈私の詩は蛮人の住むブリトンの国でまで歌われていながら,名声は財布と無関係である〉といっていることから推察すると,どんなによく売れても,著者は利益のわけまえにあずからない場合のほうが多かったらしい。ただし同じ書物をだれが出版してもよいことになっていたから,1人の出版者だけが利益を独占することもできなかった。2世紀の初めに,ローマのおもな出版者たちが相談して,歴史に残る最初の出版組合を作ったのは,出版者相互の利益を確保するためであったろうといわれている。
ローマ文明が衰えると,ローマの出版業も衰え,330年,コンスタンティヌス大帝が都をビュザンティウム に移してから,出版は著者自身が出版者を兼ねるという原始的な方法にかえった。パピルスに代わって羊皮紙が書物の主要な材料となり,書物の形も巻物から現在のようなとじ本に移った。中世における出版の歴史に忘れることのできない名は,ヌルシアの聖ベネディクトゥスである。彼はそれまでの観想的な修道生活を西欧的な対社会的・活動的生活に変えた人として記憶されるが,労働の一つとしての書物の出版が修道士のおもな仕事となり,修道院における写字彩飾室は,実質的にみて当時の出版所にほかならず,出版とは,書写彩飾された1冊の書物を長上の恩顧者に献納する宗教的な行為を意味した。14世紀の愛書家ボッカッチョやベリーRichard de Bury(1287-1345)などは,当時の修道士に書物を愛する念慮の薄いことを嘆いているが,それは必ずしも一般に出版が衰えたことを意味するのではなく,むしろ修道院における出版行為は広くヨーロッパ全土にゆきわたり,そのまま活字印刷による書物へ移っていったとみるのが正しいであろう。初期の活字本は,体裁や字体がまったく彩飾書写本の模倣であった。
イスラム文化圏 中世のヨーロッパに大きな影響を与えたアラビア文明は,出版の歴史にも重要な役割を果たしている。ギリシア文化の継承者であったが,ネストリウス派 に属していたため,ビザンティン皇帝ゼノンやユスティニアヌス1世に迫害されたシリアの学者たちはペルシアにのがれ,最後のペルシア王朝でギリシア語の書物をペルシア語に翻訳する仕事に従い,やがてアラビア人の主権が確立すると,さらにこれをアラビア語に翻訳した。すでに中国の製紙法が伝来していた8世紀から9世紀にかけて,アッバース朝 の第5代のカリフとなり,学芸を熱愛したハールーン・アッラシード の治世にはバグダードに100以上の書店が数えられ,そのなかには書写本工場をもつ出版所も少なからず含まれていた。ハールーン・アッラシードの子で,アッバース朝第7代のカリフとなったマームーンは,もともとイラン文化の心酔者であったが,父王の志をついで芸文の興隆に意を注ぎ,多数の翻訳官や写字生を宮廷に集め,とくにギリシア文献の出版を奨励し,アッバース朝文運の全盛期を将来した。出版の中心地はもちろんバグダードであったが,カイロも有名であり,コルドバがこれに続いた。アラビア人とならんでユダヤ人が中世の出版事業に貢献した事実もいちじるしい。イスラム文化の中心地には,アラビア人とともに必ずユダヤ人の活動がみられる。10世紀のカイロでは,多くの写字生や製本師を使っていたヤブク・ベン・ユスフ・ベン・キルリスと呼ぶユダヤ人出版者の名が記録されているし,12世紀のカイロで出版事業を営んでいたユダヤ人の出版目録も残っている。アラビア人による出版は,主として哲学や天文学や文学に中心を置いていたが,ユダヤ人は医学や法学をとくに重んじた。
大学出版,書物市場の拡大 修道院以外に,中世ヨーロッパの書物出版を推進した他の一つの原動力は,13世紀からルネサンス時代にかけて,ボローニャ,パドバ,フィレンツェ,パリ,オックスフォードなどに創立された大学である。たとえば,14世紀のパリは西欧での書物出版の中心地であったが,最初出版者の仕事は,委託された一つの稿本から多くの副本を作り,それを学生に貸すことであった。のちに書店自身の出版物を売るようになっても,出版物の性質,代価などについては,大学側の厳重な検閲を受けねばならなかった。ほかの大学でも事情は同様であり,オックスフォードとケンブリッジ の両大学が,1409年にウィクリフ一派の出版物を禁止したなど,その著名な一例である。大学の統制下にある出版者は,〈定在出版人stationarii〉と呼ばれたが,その事実は,常在的に一定の場所を占拠しない書物販売制度,すなわち当時すでに書物市が開かれたり,書物行商人の活動があったりしたことを物語る。書物市(ブック・フェア )が中世の終りころから書物の普及のために演じた役割は大きく,ドイツのフランクフルト に始まった書物市の隆盛は,のちライプチヒに移り,同市がドイツにおける出版の中心地となり,やがて出版業組合の結成をうながすにいたる。書物行商人が出版の歴史に活躍した足跡もまた大きい。彼らが各地を遍歴して売り歩いたのは,暦,1枚刷りの俗謡,平易な宗教書など,安価で持ち運びやすいものばかりであったが,民衆を書物に親しませる素地を作った。イギリスでは,17世紀には彼らの手によって清教徒派,王党派,カトリック派の小冊子が民衆に頒布され,19世紀には聖書その他の宗教書がおびただしく販売された。
書物の広範な市場は,文字を読む興味と経済力とをもつ読者の増加を前提とする。13~14世紀がその条件をみたした。たびたびの十字軍の遠征や,陸路および海路による貿易業者たちの旅行に伴い,民衆の知識欲は高まり,商業は活発となった。そしてすでに宗教は教会から個人へその意義を移そうとしていた。公的と私的とを問わず,文書活動は盛んにならずにはいなかった。読むことでなく書くことでさえ,14世紀の終りになると僧職階級の特権ではなくなった。羊毛やニシンや香料の取引によって巨額の利益を得る商人が現れ,通商に便利な都会には,それらの商人や親方工匠が集まり,従来の地主階級の想像もしなかった快適な生活を営むようになった。地主もやがて都会に広大な邸宅をかまえ,村落と都市との間の物産の交換がはげしくなり,荘園収入に関する訴訟事件がふえていった。透明ガラスが発明され,暗い北欧の建築に画期的な変化がおこり,冬季でも外光をとり入れることができるようになり,やがて光学レンズによる眼鏡がくふうされて,暇の処理に苦しむ金持ちの老人たちを読書人に変えていった。水車による動力の利用が盛んとなり,イスラム圏をこえて12世紀にスペインやイタリアの製紙工場でつくられた紙は,14世紀にはヨーロッパ全土に広がり,パピルスや羊皮紙に代わって書写の主材料となる。一方,長い大洋航路を乗りこえて,東洋の香料を地中海域や北海沿岸へ運ぶために,航海便覧を必要とする水先案内人の数が増加する。これらはいずれも,書写による中世の出版技術だけではまかないきれない書物の生産を必要とする社会的・政治的・経済的要因であった。ちょうどそういう時代に,活字印刷術が発明完成され,今日に及ぶ近代の書物出版が始まったのである。現代における欧米でのベストセラー は,2万5000部以上の初版を常識とするが,活字印刷術が始まって間のない15世紀では,1版の部数は平均300部内外であった。18世紀の半ばになっても,1版が600部を超す場合はまれであった。これにはもちろん例外があり,エラスムスの《格言集》などは16世紀の最初の数十年間に,各版1000部を刷って34版を重ね,同じ著者の《対話集》は,存生中に2万4000部を印刷している。ルターの《ドイツ国民のキリスト教貴族に与う》は,発行後5日間に4000部を売りつくした。これらの数字は,1900-30年までの30年間に,イギリス聖書協会が聖書2億3700万部を発行したのに比べるとものの数ではないが,活字印刷術が創始されてまだ100年にもなっていない事実を考え,さらにその前のながい手写本時代を顧みると,驚異的な記録といわなければならない。ヨーロッパ全土を通じて15世紀中に出版された書物,いわゆる揺籃(ようらん)期本(インクナブラ )の表題はおそらく3万を上まわり,しかもそのなかには300版以上を重ねたものもあるから,実際の出版部数はおびただしい。それらのうち,今日なお愛読されているのは《イミタティオ・クリスティ》だけで,土地の所有権を論じたリトルトンの著述などは当時のベストセラーであったにもかかわらず,完全に忘れ去られた。
印刷・出版業の成立 出版の側から見て,初期の活字印刷者中最も注目されるのはイタリアのA.マヌティウス である。彼は1495年ころにベネチアで印刷事業を始め,コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)から亡命してきた多くのギリシア学者たちに指導されて,ギリシア古典の正確な版本を刊行した。彼の創始した〈イタリック体〉の小型版本は,古典をたやすく民衆の手に与えるための企画であり,出版の歴史に名を残す最初の普及廉価版ともいえよう。15~16世紀にかけては,ベネチアがヨーロッパにおける最も活発な印刷出版の中心であったが,やがてパリがこれに追いついた。ベネチアではおもにギリシアやラテンの古典文学が翻刻されたのに対し,パリは自国語による伝記小説の類を盛んに出版した。イギリスはもっぱらパリから文化を吸収していたので,出版にあらわれたイタリアのルネサンス運動に直接触れる機会が少なく,そのためにイギリスのルネサンスがおくれたことは出版と文化との関係を考える場合注目に値する。書物に題扉をつける習慣は写本時代にはほとんど行われず,初代の活字印刷者たちもその慣行に従ったが,15世紀末にパリで出版された書物の多くは,題扉に書名と大型の店標と出版者名とをしるし,印刷者の名を多くは末尾の刊記にしるしている。これは出版事業が盛んとなった結果,出版者と印刷者とが分離した事実を物語るものである。近代的な産業組織が最も早く発達したリヨンでは,1539年,印刷職工の同盟罷業をみたが,これは出版業がすでに近代資本主義の様相を帯びていた証拠であろう(印刷工 )。罷業は4ヵ月続いたが解決せず,数年後にやっと妥協が成立した。印刷業者と印刷工との間に賃金の取り決めが協約された最も古い例は,1785年のロンドンにみられる。
著作権,出版者 著作物について著者ならびにその相続者に与えられる版権,および複製権の原則が確立したのは,フランス国民公会が1793年の7月に定めた法律によってである。フランスでは1838年に,ユゴー,デュマその他の作家たちが,文学者の利益を守るために文芸家協会を作り,その会の発起で,78年,国際文学会議が組織され,やがてそれが86年の会議で〈文学,科学および美術著作物の保護に関するベルヌ条約〉(いわゆるベルヌ条約)に結実し,著作権 の国際的保護が規定された。96年には第1回の出版者国際会議がパリで開かれ,出版における国際間の協力が討議された。その目的を最も誠実に実現しようとしたのは,イギリスの出版者アンウィンSir Stanley Unwin(1884-1968)であろう。第1次世界大戦後の出版事情を視察するために,1926年,イギリスの〈書物人協会Publishers Association〉(小さな民間の協会であるが,書物の職能に関しては最も権威のある構成)が出版者や書物販売業者の代表をドイツとオランダに送ったとき,アンウィンは派遣団の団長となり,きわめてすぐれた報告書を書き,その結果,イギリスでは出版者と書物販売業者とを緊密に結ぶ協同委員会ができた。アンウィンはまた1924年ロンドンに国民書物会議を設けたが,その発展したものが現今の国民書物連合National Book Leagueであり,出版者,書物販売人,読者を結ぶ有力な機関となった。第2次世界大戦は第1次世界大戦のときと比較されないほどの惨禍をまねき,イギリスのこうむった打撃もはなはだしかったのにかかわらず,イギリスの出版事業が第1次世界大戦のときほどの痛手を受けずにすんだのは,上記のようなアンウィンの処置がよかったためである。
グーテンベルク以来の活字印刷による書物を出版の対象とする時代は,おそらく近い将来に終りを告げるか,あるいははなはだしい変化をとげるだろうといわれている。ファクシミリ,ワードプロセッサー,ビデオテックスなどのニューメディアが活字印刷術の優位を脅かそうとしているからである。しかし,書物の形態がいかに変わろうとも,文化を伝承するための出版行為は,人類の存続するかぎり不変であろう。寿岳 文章
中国 印刷術はおそらく唐代の初めに中国で始まったとみられ,したがってその出版の歴史はきわめて古い。版本に限らずとも,すでに殷(いん)代(前16~前11世紀)には,占いの道具として使った獣骨や亀甲に占いの趣旨や結果を書きとめた(甲骨文 )ほか,青銅器や石にも刻字して(金石文 )人々や後代に伝えることも行われていた。春秋時代から前漢時代にかけては,竹簡,木簡,帛が書写材料となった。孔子の〈韋編三絶〉した易や春秋の諸経は竹簡,木簡であって,すなわち秦の始皇帝が焚書により焼き捨てさせたのもこれであった。
写本から木版本へ 後漢時代の105年,蔡倫(さいりん)が製紙法を発明し,良質で本格的な紙の量産が可能となった。唐代は写本の時代から板木 (ばんぎ)を用いた刊本(木版本)の時代への転換期であったといえる。《旧唐書(くとうじよ)》巻十七には835年(太和9)に唐の高官の馮宿(ふうしゆく)が,暦を私人がみだりに印刷するのを禁じたという記録があるが,中国の現存最古の刊本は,1907年にスタインが敦煌莫高窟(とんこうばつこうくつ)で発見した《金剛般若波羅蜜多経》である。868年の刊年が入った巻子本で,字体のみごとさなどから,この時期にはすでに木版印刷技術はかなり高度に達していたと思われる。また〈洛陽の紙価〉の故事は,西晋時代に書写用の紙が売れたことを伝えているが,すでに唐代中期には洛陽に写本の書肆(しよし)があったことは確かであり,洛陽は唐代は文化の中心地であるとともに,出版の中心地であった。刊本の書肆が興ったのは唐末だったとみられる。唐末から五代時代にかけては出版の中心地は唐末の都であった四川省(蜀(しよく))の成都に移り,多くの書肆があった。
932年(長興3)五代十国の一つ後唐の宰相馮道(ふうどう)が皇帝の明宗に上奏をして勅許を得,《九経》(易経,詩経,礼記などの儒家の経典)全277巻の大出版事業を行った。馮道は後唐以後も11人の皇帝に仕えながら,21年後の953年に完成した。印刷・出版は国子監 (国立大学)で行い,ここで彼は,ほかにもいくつかの大出版を行った。
宋版 宋代は商工業,貿易の発展を背景として,文化がおおいに興った時代である。唐代以来の木版印刷術の発達も宋代で完成され,印刷・出版事業は国を挙げて盛んになった。そして紙,墨,書体なども大幅に改良されて,美本の名をほしいままにする〈宋版〉が生み出されたのである。
中央官府の手になる官版の出版の中心は国子監であり,その監修になる〈崇文院本〉〈秘書監本〉〈徳寿殿本〉〈左廊子本〉の4種は造本,刻書,印刷の精緻な点で,最も有名である。また本格的に出版が企業化したのもこの時代であり,四川,杭州,福建などは民間出版のメッカであった。そのうち建安(福建省)の余,臨安(杭州)の陳の2書肆は,大出版社として著名であったことが葉徳輝《書林清話》などから知られる。
宋代の官版は,歴史,儒学,禅宗などの典籍の出版が多かったが,とくに大出版として有名なのは,2代皇帝太宗の勅版《大蔵経 》5048巻(971-983)である。使用した版木の数13万枚と伝えられる。そののち南宋末までに数回にわたり官版,私版の《大蔵経》出版がなされ,いくつかは日本にも渡来して現存している。
現代では宋版は中国史上最も美しい本として貴重品扱いであるが,日本では,静嘉堂文庫 にまとまったコレクションがあり,世界的にも著名で多くの稀覯(きこう)本を含んでいる。
中国の活字本 中国は活字本の出版についてもおそらく最初である。まず11世紀の半ば,宋の慶暦年間(1041-48)に畢昇(ひつしよう)が膠泥(こうでい)を加工して,いわゆる陶活字を発明し印刷を行ったことが沈括《夢渓筆談》などから知られる。さらに元代には王禎 が《農書》を出版(1314)するために木活字約6万本を彫刻させ,試刷りとして《大徳旌徳県史》100部を1298年(大徳2)に印刷した。
なお遅くとも1241年(高宗28)以前に,つまりグーテンベルクより200年以上も前に,高麗では銅を主とした金属活字による本が出版されていた(発明者は不明)。高麗朝の後の李氏朝鮮でも鋳字,出版にはことのほか熱心で,3代太宗以下,歴代の王が王立鋳字所(1395設立)で大規模な活字鋳造と本づくりを行った(朝鮮本 )。
元・明・清 元も書物文化については南宋の後を継ぎ,みごとな本づくりを行った。庶民向けの文学の出版も元末から盛んになった。次の明代にも官民ともに出版活動がいっそう盛んになり,例えば2万2877巻,1万1095冊にも及ぶ《永楽大典 》(1403勅命)などが編纂された。木活字が流行したり(銅活字も使われるようになった),また多色刷りが発達し彩色版画集が多く出版されたのもこの時代であった。
清の康煕帝(在位1661-1722)はみずから古典を校閲して,《康煕字典 》や《古今図書集成 》などの欽定書を多数刊行した。彼の衣鉢をついだのが乾隆帝(在位1735-95)で,古代から清代までの重要著作物をすべて収めた中国最大の双書《四庫全書 》などを編纂させ,宮廷内の武英殿で書籍刊行事業を行ったりした。ここで刊行された本は武英殿本(または殿本)と呼ばれて珍重されている。
近・現代 中国にグーテンベルク式活字印刷術が入ったのは1588年(万暦16)で,バリニャーノ が日本へ向かう途中に2年ほどマカオにとどまって2冊の本を印刷している。しかし本格的に導入されたのは清末であった。清末・民国期の出版の中心地は上海であり,なかでも商務印書館 は民国期を通じて最大の出版社で,《四部叢刊 》のほかこの時期の大出版をほとんど手がけている。
中華人民共和国となってからは,一部が台湾に移ったほかは,すべてが国営となり,近年では二百数十社の出版社がそれぞれの出版領域を特定の分野ごとに分けて活動している。鈴木 敏夫
日本 古代・中世 製作年代が明らかな最古の印刷物で,その現物も残っているのは,孝謙天皇が770年(宝亀1)に印刷した《百万塔陀羅尼》であり(〈百万塔 〉の項参照),10万基ずつ全国の十大寺に納められた。また,正倉院記録に740年(天平12)に将来された仏教版画〈印仏 〉1巻を納めたと記されているが,この願経は来日していた鑑真の教えと推定されている。平安末以後,印仏は日本でも制作され,鎌倉以後は盛んになる。一方,経文印刷は1009年(寛弘6)藤原道長が中宮安産の祈願に〈法華経〉1000部を印刷したこと(《御堂関白記》)に始まる。薄紙に薄墨刷りした摺経(すりきよう)である。僧侶は研学のため経文を必須としており,興福寺では財を募り《成唯識論(じようゆいしきろん)》10巻を1088年(寛治2)に印刷したが,これは良紙,能書,濃墨で優秀である。この〈春日(かすが)版 〉が始まると,西大寺,東大寺,唐招提寺,法隆寺などでも出版され,研学用から俗人に読誦させるようになったが,これらは寺院版 と総称される。鎌倉時代中ごろ高野山に,後期には京都や鎌倉にも及んだ。〈高野版 〉は能筆に版下を書かせ,厚様に濃墨を用いて優れたものが多い。高野山では経師大和屋善七など数名を招き,印刷・販売させた。
鎌倉末期から京都,鎌倉の両五山を中心に禅宗の高僧の語録を彫刻し元版と同様の印刷が行われるようになるが,これらは五山版 と呼ばれ,南北朝時代の戦乱の中に語録,漢詩集,儒書まで広く出版された。この時代の刻版は宋版の影響が多く,また元の刻工兪良甫,陳孟栄なども来日して刻法を伝えている。仏書だけでなく漢籍の出版も行われ,《寒山詩》(1378),《論語集解》(1364,堺の道祐居士刊)その他韻鏡類や医書も多く刊行された。医書は堺の阿佐井野家で多く刊行され,阿佐井野版と呼ばれる。堺は当時貿易港として繁栄し需要も多かったのであろう。室町時代末期には地方に知識人が分散して封建諸侯などの保護者を得て印刷を行うようになり,大内版 ,薩摩版,周防版などが現れた。
活字版の時代 九州三侯による天正遣欧使節を率いて法皇その他に謁見したイエズス会のバリニャーノは印刷機,活字,印刷工を率いて再び来日し,1591年(天正19)にローマ字で日本語訳《サントス(聖徒)の御作業のうち抜書》を印刷し,1611年(慶長16)の《ひですの経》まで約30点を印刷した。その中には国文の活字を作って印刷した《落葉集》なども含まれている。惜しむべきはこれらキリシタン版 は国内で禁書として滅ぼされ,わずかに在外のものが残っている。一方,文禄・慶長の役(1592-98)の際もたらされた朝鮮系活字によるものでは,後陽成天皇勅版で《古文孝経》(1594),《日本書紀神代巻》(1599)など数点,徳川家康の命で伏見版 も1599年から《孔子家語(けご)》《六韜(りくとう)三略》など10余点が,また駿河版 では銅活字で《大蔵(だいぞう)一覧集》(1615)などが印刷された。民間でも本圀寺の《天台四教儀集解》(1596)をはじめ,寺院で盛んに印刷された。私人では1596年小瀬甫庵の《標題徐状元補註蒙求》,その他医書が続いて出版された。また国文の出版では,鳥養(車屋)宗晰(そうせき)が1601年に《謡曲》を印刷した(謡本 (うたいぼん))。08年には本阿弥光悦の考案で《伊勢物語》,続いて《観世流謡曲百番》が印刷され,光悦版下とみられるものは31種に及び美術史上も注目されるが,その他《源氏物語》など角倉素庵本とみられるものもある(嵯峨本 )。このように古活字版 は慶長から寛永(1624-44)前半までの35年間に300点以上も出版されたといわれるが,その背景には戦国争乱を経て勃然としてわき起こった書籍の需要があった。
書店出版の時代 活字版は一版ごとに組み直し,校正の労がはなはだしいので,増大する需要のもとでしだいに旧の整板(一枚彫)になっていった。同時に多くの書店が参入したが,その主力は刀を捨てた浪人であった。著者に三河武士の鈴木正三(しようさん)がいれば,豪邸を寺に直して村上勘兵衛はみずから書店を開いたが,これは平楽寺の屋号で現在も営業している。当時の著者は私塾を開くか,諸侯の儒官であって,進んで書くものはまれであった。藤堂高虎の儒官如竹にその師の《南浦文集》3巻を出させた中野市右衛門も,初版は刊行者名なしの活字版として刊行したが,1649年(慶安2)の再版でようやく店名を入れた。夏の陣,冬の陣を描いた《大坂物語》が1615年(元和1)に出て以来,新作が仮名草子 で発行されるようになったが,ほとんど店名も刊年も入れていない。この中に絵を入れ朱,黄,緑,紫を単純に手彩色したものを丹緑本(たんりよくぼん)といった。作者で有名な人物に浅井了意(《御伽婢子(おとぎぼうこ)》1666)や鈴木正三(《二人比丘尼(びくに)》1664)らがおり,寛永年間に早くから出版を始めた有名な書店としては敦賀屋九兵衛,風月庄左衛門,村上勘兵衛,山本九兵衛,永田調兵衛など名家がある。
江戸は新開地で気風も荒く,上方とは様相が異なっていた。京都では史書,軍書,医書,儒書などは〈物の本〉と呼び,その版元を〈物の本〉屋というのに対し,江戸では版元を,板木屋と公称した(〈本屋 〉の項を参照)。江戸では出版物も十数枚綴じの古浄瑠璃本や絵入本が主であったが(現存のうち《にしきど合戦》(1665)が古いほうである),これより以前の正保年間(1644-48)の〈武鑑〉あたりから出版が始まったといえよう。《長明物語》(1648),《武者物語》(1656)はともに松会(しようかい)市郎兵衛の出版である。《にしきど合戦》の版元ははんぎや又右衛門で,別に又左衛門が《うぢのひめきり》(1658)などを出版しており,この2人は1674年(延宝2)まで出版活動をしている。鱗形屋 (うろこがたや)は1657年(明暦3)に《花鳥山桜西明寺百首》を出版し,又右衛門らの古浄瑠璃本を引き継いで幕末まで活動した。江戸で最も流行したのは坂田金時の子公平(きんぴら)を主人公とした金平浄瑠璃で,これは鳥居派の絵入本で流布し金平本と呼ばれた。やや遅れて京都で子ども用の赤表紙行成本があり,江戸では小本のお伽噺絵入りの赤本 が延宝ころ(1670年代)出版され,享保ころ(1710年代)には年長向きになり黒本といい,やがて青本となり(黒本・青本 ),安永ころには黄表紙となった(以下,合巻に至る江戸後期の小説出版については〈草双紙〉の項の図を参照)。黄表紙 は1775年恋川春町が《金々先生栄華夢》を自作自画で出したのが初めで,当時の理想生活を洒落と滑稽の軽妙な筆致で描き,大当りをとり,朋誠堂喜三二(きさんじ),市場通笑,唐来三和(とうらいさんな),山東京伝など名手が続出した。関西では仮名草子の形式で井原西鶴が1682年(天和2)に《好色一代男》8冊を大坂の荒砥屋孫兵衛から出版し,名文をもって全国的評判をとった。これらを好色本 という。八文字屋2代自笑は,元禄から盛んに好色本を出版し八文字屋本 といわれる。
幕府は出版取締りにあたったが効がなく,1722年(享保7)にようやく本屋仲間(三都の本屋が形成した仲間組織。江戸では書物仲間といった)を公認し,行事を設けて町奉行所に連絡させ,一方で本屋仲間は政道や風俗に有害な出版を自粛し取締りに乗り出した。こうして町奉行大岡越前守によって出版の規制が確立した。当時京都160店,江戸125店,大坂69店のほかに新店などが300店と推定され,取締りも容易ではなかったが,8代将軍吉宗の質実政策(享保改革)の実施によって重圧が加えられた。株仲間は重板類板の権利を守るのに協力し,取締りもつごうよくすべり出したものの,華美と風俗の乱れはとどめがたく,松平定信の寛政改革による弾圧を経て水野忠邦の天保改革による強硬政策の断行をもってしても,幕末の紛乱を避けることはできなかった。
一方,仏書,漢籍は京都に版株を押さえられていたため,塙保己一編《群書類従》でさえも,書店を通じて売りこめないほどの状態であった。江戸は新文学で生きるほかに道はなく,大坂は京都や江戸の板木を買いこんで出版するほかに方法がなかった。通人相手の洒落本 は遊女の遊び方に通(つう)をきかし,手練手管やかけひきに粋客を喜ばす小説趣向であり,黄表紙は仮名が主で,粋(いき)や通を気取って読ませるものである。初期の洒落本は1728年《両巴巵言(りようはしげん)》のように清の艶書体を模しているが,延享・宝暦(1744-64)ごろにはややくだけたものになる。それが江戸の吉原,深川などを舞台にとるようになると,真価を発揮して通を誇り野暮(やぼ)をくさす文学に一変した。その最盛期に当時最高の作者山東京伝と新進大出版家蔦屋(つたや)重三郎 が禁圧の対象となった。1791年(寛政3)京伝は蔦重(つたじゆう)から金1両余の前借りで洒落本《仕懸(しかけ)文庫》《娼妓絹篩(きぬぶるい)》《錦之裏》を出すが,松平定信の禁令にかかり,作者,書店ともに立ち直れないほどの厳罰を被った。これ以後洒落本に手を染める者はなく,黄表紙も仇討などにテーマを一変した。また,1冊では書ききれず5冊を合わせたものが出現し,これを合巻 (ごうかん)と称した。一方,関西では明・清稗史(はいし)の翻案が興り怪談奇談を作り,これを読本(よみほん)といったが,都賀庭鐘(つがていしよう)や上田秋成が作者として登場した。秋成は《雨月物語》を1768年(明和5)に出版したが,やがて江戸でも山東京伝や曲亭馬琴が力を入れ,馬琴は《南総里見八犬伝》(1841完成)の大作をはじめ,多数の合巻や読本を作った。合巻物はいよいよ華麗になり,柳亭種彦の《偐紫(にせむらさき)田舎源氏》(鶴屋喜右衛版)は1842年(天保13)に完成し,国貞の挿絵のけんらんの美に庶民から大奥まで酔わされてベストセラーとなるが,作者は老中水野忠邦から圧迫され,怪死するに至った。そのころ為永春水は合巻物を一歩進めて人情本 を流行させるが,その傑作は《春色梅児誉美(しゆんしよくうめごよみ)》(1832-34)であった。彼は以後〈春色〉を冠した人情本20点を門弟にも書かせ,人情本は大流行となるが,水野の諸事倹約令の網にかかり,1842年に摘発され,春水は翌年悶死した。種彦,春水にとどまらず,《江戸繁昌記》の寺門静軒や役者の市川団十郎まで江戸払いとなり,同年株仲間も解散させられた。翌43年水野の失脚により出版界も息を吹き返し,人情本や錦絵も復興したが,勢いはなく作者,画工のレベルも一段と低下した。本屋仲間は1852年(嘉永5)に復興して新入者300余人に達した。なお,以上のような出版の隆盛,本の普及には貸本屋 も寄与している。
風刺や諧謔の好きな江戸っ子には咄本の流れがあって,滑稽本 はそれを受けたものである。平賀源内《風流志道軒伝》《根南志具佐(ねなしぐさ)》(1763)などを先駆とし,次代には十返舎一九《東海道中膝栗毛》(1802-22)が大当りし,式亭三馬《浮世風呂》《浮世床》などの傑作が出る。また,江戸時代には俳書がよく出版されるが,元禄(1688-1704)ごろからは京都の井筒屋庄兵衛がこれを独占し,同様に謡本では山本長兵衛,浄瑠璃本では山本九兵衛などが独占した。江戸では須原屋茂兵衛の〈武鑑〉〈地図〉,大坂で炭屋五郎兵衛の後藤(芝山)点〈四書〉〈五経〉のような独占を生じた。
蘭学書ははじめ禁制であったが,のち禁を緩め,1774年(安永3)杉田玄白訳《解体新書》(5冊)に始まり,天文学,科学,暦法に及び,幕末には兵書が多くなる。大鳥圭介訳《築城典型》は自作の活字版である。《厚生新編》はフランスのショメルによる《百科全書》のオランダ語版を邦訳したもので,版にならなかったが,蘭学を発展させた。辞典ではハルマ蘭仏語辞典を稲村三伯らが苦心して《ハルマ和解(わげ)》27巻に翻訳し,わずか30部印刷した(1796)。また,オランダ商館長ズーフが吉雄権之助ら11人に完訳(1812-33)させた《ズーフ・ハルマ》は写本で伝わったが,桂川甫周によって《和蘭字彙》28冊(1855-59)として刊行された。オランダ語に次いで,英語ではヘボン《和英語林集成》(1877)が出版された。弥吉 光長
明治以後 明治初期に著作家として活躍したのは,福沢諭吉ら洋学者が多かったが,本づくりについては,西南戦争ころまでは江戸期の和本とあまり変わらなかった。しかしその後しだいに,手漉和紙は洋紙に,印刷は活版印刷に,製本も洋式製本に変わっていった。明治初期の代表的書物としては,福沢の《西洋事情》(1866),中村正直の《西国立志編》(1870-71),内田正雄の《輿地誌略(よちしりやく)》(1870)が,〈明治の三書〉とされ,この3書によって近代化のスタートがきられたといわれる。明治10年代には,自由民権もの,実録もの,毒婦物語などが混在した形でもてはやされた。明治20年代には,近代文学の出現を含んだ出版の多彩化が生じ,日清戦争以後は,学校教育の普及に伴って生じた大量の新しい読者層を対象にした出版が行われるようになった。明治30年代以後になると,幸徳秋水の《社会主義神髄》などの社会主義の書物が多く出されるようになったのが特徴的であったが,とくにこれらは出版法や新聞紙法によって強い規制を受けた。
大正期には,デモクラシー,労働問題,普選問題などの社会問題を扱った書物が非常に多くなった。いわゆる大正デモクラシーの波の中で出版活動はますます盛んになった(その時期に創業した出版社の中には現在もなお存続しているものも多い)。中でも講談社は,大衆的通俗出版を軸とする出版で,講談社文化といわれ,それに類する大衆出版はこの時期かなり盛んであった。それと対照的に岩波書店は,学問的な本を出して成功し,岩波文化(岩波アカデミズム)といわれ,出版の二大潮流を形成した。また中央公論社や改造社なども,大正デモクラシーの波に乗って成功した。
1926年に改造社が1冊1円の《現代日本文学全集》を出して大成功したことから,各社もこれにならい,27-30年ころは円本 ブームとなった。他方,1927年には〈岩波文庫〉も創刊され,この時期はいわば廉価版時代であった。しかし31年に起こった満州事変のころからは出版への統制がきびしくなり,とくに37年の日中戦争勃発から第2次大戦終了までは,出版の自由は壊滅状態であった。
戦後は,極度の物資不足のため,粗悪な泉貨紙を使うなど,悪条件の中ではあったが,内容的には以前の統制法規は撤廃され,長い間抑圧されていたさまざまな出版が行われるようになった。ただし一般に無統制と思われていたが,GHQによるきびしい検閲が行われていた。鈴木 敏夫
現代 第2次大戦後の〈本の飢餓〉状況の中で,出せば何でも売れるというつかのまの出版ブームの時代があった。《日米会話手帳》や《旋風二十年》《愛情はふる星のごとく》などのベストセラーが,当時を象徴している。しかし,日本の出版界が本格的な立直りを示したのは昭和30年代に入ってからである。いわゆる大衆化現象のシンボルはテレビと週刊誌であるが,〈カッパブックス〉などのベストセラーや百科事典,文学全集などのブームを成り立たせた〈大衆〉は,もはや戦前的意味の,すなわち知的エリートとは無縁の庶民ではなく,いわば国民そのものだったのである。しかし,このような〈本の革命〉は日本だけの現象ではなく,先進国に共通してみられるところであった。ただ,欧米のそれがペーパーバックの爆発的普及を伴ったのに対し,日本ではハードカバーを含めて全般的に激しい〈出版爆発〉がみられた。
その理由としては,戦後における民主化の諸条件である両性の平等,労働条件の向上,所得の平準化などが新しい読者層の造出をうながしたが,なかんずく本にとって決定的だったのは,普通高等教育および大学教育の一般化であった。彼らは,従来の,狭いが固い読書階級に代わって,広範囲で流動的な読者層を形成するに至った。そして,戦前はせいぜい婦人雑誌に限定されていた女性が,膨大で熱心な一般読者群として登場してきたのである。
戦後におけるベストセラーの推移は,新しい大衆読者の誕生とその推移を示している。また,テレビはこれらの大衆読者に新たな刺激を与え,とりわけ1980年以降にその強い影響がみられる。しかし,若者に現れているメディア離れの新現象により,読書の傾向には流動的要素が強くなりつつある。
現代における本の役割 少なくとも伝統的な本は,文字を中心とするが,読む行為は,最も本質的な理解を可能とする。その意味で,〈読むこと〉は〈考えること〉である。これに反し,テレビなど視聴覚メディアは理性よりも情緒に訴える力が大きい。表現の方法や内容を豊かにすることには秀でていても,しばしば正確性や論理性を犠牲にせざるをえない。また,視聴覚メディアは,その受容にあたって,ほとんど受け手の能動性を必要としない。本など活字メディアに比べて本質的なこの受動性が,視聴者の思想や趣向の画一化を強く促進することになる。他方,本は視聴覚メディアに比べてダイナミズムに欠けるため,著しく流動的な現代的状況にマッチしがたいという弱点がある。しかし,この弱点は同時に,人々の観点や趣向が表面的,刹那(せつな)的に傾くことを防止する役割を果たすことにもなっている。このことは,健全で冷静な世論形成のうえで欠かすことのできない特性といえよう。
コミュニケーションの道具という点では,視聴覚メディアのほうがはるかに機能的である。しかし,視聴者はテレビの内容を動かすことはできないし,心を通わせることもできない。本というメディアの特色は,読書というコミュニケーションが,特有の体験,固有の心的冒険である点にある。読むという行為は絶対的に同一化できない性質のものである。しかし,本が最も人間的なメディアであるのは,その無限ともいうべき選択可能性にあるといえよう。本は古今東西にわたる知識の宝庫であり,なお年間数十万点にのぼる新刊書が加わっている。その中から,人がその主体性において本を選びうるという条件にこそ読書の特質がある。読む前に存在するこの無限の選択可能性は,他のメディアにないものであるが,出版の自由,読む自由の保障は,この意味での選択の自由の保障であるということができる。
課題と将来 本を脅かすものとして,いわゆるニューメディア の問題がある。ニュー・メディアが,オールド・メディアの代表である本とその出版に大きな影響を及ぼすことは十分に予想される。しかし,これまでの経験が教えるところによれば,新しい伝達メディアが出現するたびに,もう本は終りだという予測が行われた。19世紀の初頭に,フランスの政治家,評論家のジャン・ルイ・ブランは〈本の時代は終わり,新聞の時代が始まった〉と述べた。たしかに,世論形成やニュース報道のメディアとして,新聞は大きな威力を発揮した。しかし,本は滅ぶどころか,本格的な出版活動はむしろそれから始まったのである。映画やラジオ,さらにはテレビが出現したときも,本はもはや過去のものだといわれた。けれども,本や雑誌は生きつづけたばかりか,未曾有(みぞう)の発展を遂げたのは,テレビ出現後しばらくたってからのことだったのである。
そのありさまは,あたかもフェニックス(不死鳥)を思わせるのであるが,本の生命力は,文字伝達がコミュニケーションの原点だというところにある,といわなければならない。新しいメディアは,本の生命力をますます強いものにしてきたということができる。しばらく前から活字離れ現象が指摘され,本の危機がまた人々の口にのぼるようになった。たしかに,これからの時代はマルチ・メディア化の方向に進むであろう。だが,人間の精神形成,人格形成にとって,ニュー・メディアが役だつとすれば,やはり補助的役割なのであって,本が基本であるという状況に根本的な変化は起こりえないと思われる。しかし,このことは,本の形態,製作過程はもちろん,その内容も旧態のままであることを意味しない。古典は文字どおり古典として生きつづけるであろうが,これからの本が将来に向けて古典でありうるための条件は,大きく変化していくにちがいない。清水 英夫
 [名]
[名] [接尾](本)助数詞。
[接尾](本)助数詞。 1)糸口・端緒・緒・端・はじめ・始まり・起こり・
1)糸口・端緒・緒・端・はじめ・始まり・起こり・ 2)根本・
2)根本・ 4)原因・たね・近因・遠因・せい・根本・はじめ・起こり・きっかけ・
4)原因・たね・近因・遠因・せい・根本・はじめ・起こり・きっかけ・ 〈ホン〉
〈ホン〉 〈もと〉「大本・旗本」
〈もと〉「大本・旗本」 [名]
[名] [接頭]名詞に付く。
[接頭]名詞に付く。 [接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。
[接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。 1)書物・書籍・図書・書冊・冊子・書巻・典籍・
1)書物・書籍・図書・書冊・冊子・書巻・典籍・
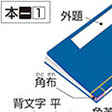






 立〕本 ムカシ・キハマル・タメシ 〔字鏡集〕本 モトヰ・タメシ・フルシ・モト・ムカシ・ハジメ
立〕本 ムカシ・キハマル・タメシ 〔字鏡集〕本 モトヰ・タメシ・フルシ・モト・ムカシ・ハジメ に作り、
に作り、 (はつ)声。ともに本の声義と関係はない。
(はつ)声。ともに本の声義と関係はない。 本・真本・正本・製本・石本・善本・素本・草本・蔵本・足本・俗本・大本・台本・拓本・治本・張本・定本・底本・点本・伝本・殿本・唐本・搨本・謄本・徳本・読本・抜本・反本・板本・版本・秘本・碑本・標本・副本・複本・粉本・報本・豊本・坊本・墨本・務本・模本・訳本・様本・藍本・臨本・暦本・和本
本・真本・正本・製本・石本・善本・素本・草本・蔵本・足本・俗本・大本・台本・拓本・治本・張本・定本・底本・点本・伝本・殿本・唐本・搨本・謄本・徳本・読本・抜本・反本・板本・版本・秘本・碑本・標本・副本・複本・粉本・報本・豊本・坊本・墨本・務本・模本・訳本・様本・藍本・臨本・暦本・和本