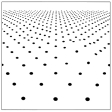精選版 日本国語大辞典 「知覚」の意味・読み・例文・類語
ち‐かく【知覚・智覚】
- 〘 名詞 〙
- ① 知りさとること。知り感じとること。
- [初出の実例]「此生あて知覚あり、知覚は此生恃む」(出典:清原国賢書写本荘子抄(1530)八)
- [その他の文献]〔後漢書‐杜詩伝〕
- ② 思慮分別をもって知ること。心で外界の事物を認識するはたらき。
- [初出の実例]「心と云は念慮知覚なりと思ひ、心は草木なりと云へば信ぜず」(出典:明和本正法眼蔵随聞記(1235‐38)四)
- ③ 感覚器官を通して外部の物事を判別し、意識すること。また、そのはたらき。
- [初出の実例]「知覚ある薄き表皮の上なれば」(出典:遁花秘訣(1820)牛痘の種法を拒み誹謗するの弁)
- 「娘は次第次第に知覚を恢復して来た」(出典:刺青(1910)〈谷崎潤一郎〉)
知覚の語誌
( 1 )日本では多く仏書で②の意に用いられた。
( 2 )「蘭語訳撰」(一八一〇)では gevoel の訳語に用い、③の挙例「遁花秘訣」も感覚器官の働きを指しているから、「感覚」の意を派生したのは近世のことと思われる。
最新 心理学事典 「知覚」の解説
ちかく
知覚
perception(英・仏),Wahrnehmung(独)
【知覚と感覚】 かつて感覚sensationと知覚とを厳密に区別して,感覚を知覚の要素と考える立場もあったが,現代ではその区別は明確でなく,単純な条件下の単一の刺激により生じる感性体験を感覚とよび,より複雑な条件下で刺激パターンから生じるそれを知覚とよぶ場合が多い。知覚は対象性と意味をもち,空間的・時間的な広がりをもつことが多いが,感覚にはそれらがない。たとえば,バラの香りを嗅ぐのは感覚であるが,それによりバラの花の存在を感じることは知覚といえる。色が赤いと見えること自体は感覚であるが,信号機の赤信号は空間的に定位され意味をもって知覚される対象である。純音を聴くのは感覚であるが,ピアノが発する音楽や人の話を聞くのは知覚といえる。
【知覚と知覚対象のずれ】 われわれが知覚している世界は,客観的・物理的世界を忠実に写したものではなく,かなりのずれがある。これは単なる間違いでなく,注意深く見ても,聞いても,大きさや長さや傾きや位置や音や重さが,客観的・物理的なものと違って知覚される。これを錯覚illusionという。視覚における錯覚を錯視optical illusionという。錯覚は19世紀末から研究され,種々の錯視図形が考案され,それぞれの研究者の名前をつけてよばれてきた。これらの錯視は,錯視図形に限られた特殊な問題でなく,錯視の量に大小の差はあっても,日常のわれわれの知覚でつねに起こっている知覚の歪みを示しているものである。錯覚は視覚に限らず,たとえば物理的にまったく同じ重量のものでも,大きいものは軽く,小さいものは重く感じる重量感の錯覚(シャルパンティエの錯覚Charpentier's illusion)などがある。錯覚は程度の違いはあっても,多くの人びとに共通に生じるもので,その点で幻覚hallucinationとは異なる。
また,知覚は感覚器官に対する刺激の強度やパターンを忠実に反映していない。日陰に置かれた白紙から網膜に到達する光の強度は,日向に置かれた灰色紙から到達する光の強度より低くても,白紙は明るく,灰色紙は暗く知覚される。明るさの恒常性brightness constancy(あるいは明度の恒常性lightness constancy)とよばれる現象である。物理的に同じ大きさの対象の網膜像の大きさは観察距離に反比例して減少するが,遠方の対象は網膜像が小さくても実際に近い大きさに知覚される。大きさの恒常性size constancyの現象である。視線に対して傾いた面の形は網膜上では歪んでいるが,正対した場合の形に近く知覚される。形の恒常性shape constancyの現象である。遠方の対象が発する音から到達する音波は弱いが,知覚上は近くの同種の対象の発する音の大きさとさほど違って感じない。音の大きさの恒常性loudness constancyの現象である。これらの恒常現象constancy phenomenon,すなわち知覚の恒常性perceptual constancyは,一般に完全には成立しないが,われわれの知覚世界を物理的環境に近いより安定したものとしている。
【感情・情動・認知】 赤い色は情熱を表わし,青は平静を感じさせる。尖った形は危険を,丸い形は穏やかさを感じさせる。高い音は快活な印象を,低い音は陰鬱の感情を誘う。また明るい声,鋭い音,涼しい色合い,軽快な形,愉快な旋律,重い動きなど,五感を通して感じるものは,単にそれぞれの感覚だけでなく,さまざまな共感覚的傾向synesthetic tendencyを生み,さらに感覚を超えた感情affect,情動emotionも生じさせている。これらを総合して感性Kanseiとよぶこともある。絵画や音楽などの芸術やデザインの基礎ともなっている。
また,認知cognitionという語が知覚よりさらに広い意味に使われる。人が外界からの情報を処理する過程を指し,知覚者のもつ知識や要求や注意attentionが関係する。同じ情報が感覚器に到達しても,知覚者の経験や関心の違いによって,認知するものは大きく異なる。新聞を開くと非常に多くの文字が目に映るが,自分の関心がある文字しか認知されない。政治に関心がある人には政治関連の記事が,スポーツに関心が強い人には,スポーツ記事が目に付く。また,自分と同姓の人物の記事は自然に目に留まる。知らない漢字は読むことはできない。
人を,見るもの聞くもの触れるものに変化がない単純な状況下に長時間おくと,精神的に不安定になり,幻覚を生じたりする。このような状況を感覚遮断sensory deprivationとよぶが,ある程度の感覚は残されているので,むしろ知覚遮断の状況である。人はなんらかの知覚とその変化をつねに求めている。人が窓から外を眺めたり,テレビを見たり,本を読んだり,音楽を聞きたがるのは,知覚への要求の現われといえる。
人がなんらかの知覚能力の障害をもつと,知的能力や運動能力の障害と同様に,生活に大きなハンディキャップが生じる。自分が生活し行動する環境について,十分な情報が得られないからである。知覚の重要性を示している。
【知覚研究の歴史】 すでにギリシア時代に,知覚に関する考察が始まっている。プラトンPlatonは,感覚を通して知る経験的世界のすべてが純粋なイデアideaの不完全な現われにすぎないと考えた。彼によると,不滅な霊魂が人間の肉体に入る前にイデアはすでに存在して,感覚を手がかりとしてそれが想起されるという。後世の認知心理学のスキーマschemaの概念と通じるものがある。プラトンが感覚を軽視したのに対して,アリストテレスAristotelesは,感覚は視・聴・嗅・味・触より成るとし,外界の知識はこの五感five sensesを通じて与えられると考えた。ただ,個々の感覚を通じて得られた経験は個別的な知識を与えるにすぎず,それらの感覚を統合した知識が対象を認識する手がかりを与えるとした。彼は複数の感覚を統合する働きを共通感覚とし,運動,静止,形,大きさ,数をその例とした。今日の感覚と知覚と認知の区別に似ている。
近世に至り,物理学者ニュートンNewton,I.がプリズムを用いて太陽光を7色に分け,それらの光をレンズで集光すると白色に戻ることを確かめるとともに,一部の色光のみをレンズで集光することによって,光の混合により生じる混色color mixtureの現象を観察している。彼はその著『光学Opticks』(1704)の中で,色の物理的性質とともに,色覚についても論述している。彼は,「光線には色がついていないThe Rays are not coloured」と述べ,色をあくまで感覚としてとらえている。彼は,赤い光などとよぶことは不適切で,「赤を作り出す光線Red-making Ray」などとよぶべきだと述べている。これは彼が色を感覚としてとらえ,物理的存在としての光線と明確に区別したことをよく示している。生得観念を否定したイギリス経験論哲学者ロックLocke,J.(1706)は,友人であるモリヌークスMolyneux,W.が提起した疑問,「生まれながらの盲人が成人して,触覚で球と立方体が区別できるようになってから,開眼した場合,視覚によって球と立方体が区別できるか」に対して否定的に論じている。その後,バークリーBarkley,G.は『視覚新論A essay towards new theory of vision』(1709)において,距離は,遠くても近くても眼底に,ただ1点をしか投影しない。かなり遠くに離れている諸対象の距離は,むしろ経験に基づく判断の働きであると論じている(経験説empiricism)。前述のモリヌークスの疑問についても,開眼者は触覚と視覚の習慣的な連合を獲得していないので,眼で見ただけでは球と立方体の区別はできないと述べている。
19世紀初頭にヤングYoung,T.は,色覚の三色説の原型を発表している。彼は,光は波動であるとし,網膜上の神経の末端が網膜に到達した光と共振することによって色覚が生じると考え,赤,緑,菫の3種の神経を想定した。これらの三原色以外の光には,その光の共振数に比較的近い共振数に感じる2種の神経が同時に共振することで対応していると考えた。たとえば,黄の光には赤と緑の神経が同時に共振することとなる。この状態が大脳に黄の光の到来を知らせる信号になると想定された。この説は半世紀後,ヘルムホルツHelmholtz,H.L.F.von(1860)によって整備された形で再提案された(ヤング-ヘルムホルツの三色説Young-Helmholtz trichromatic theory)。この間に,感覚神経が感覚の種類に応じて分化していることを明確に述べたのが生理学者ミュラーMüller,J.P.(1838)の特殊神経エネルギー説die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien,theory of the specific energies of sensesである。この説は,まず感覚は外界の物理的性質を直接に反映するものではなく,外界の刺激が生じさせた神経興奮の結果として間接的に生まれるものであることを明らかにし,次にそのような神経は,視・聴・味・嗅・触の五感によって異なっていることを説いている(現代の特徴抽出器feature detectorの説もこの延長線上にあるといえる)。他方,ドイツ観念論哲学者のカントKant,I.(1781)は,空間と時間は先天的直観であると説いた。ミュラーは,神経線維の空間的配列がそのまま知覚に反映されるとして,空間知覚の生得説nativismを提唱している。この考えは,ウェーバーWeber,E.H.(1852)の感覚圏sensory circle(触覚の2点閾によって考えられた皮膚上の領域)の仮説,ロッツェLotze,H.R.(1852)の局所徴験Lokalzeichen,local signの説(視覚や触覚には,刺激される局所に固有の性質があるという考え),へリングHering.E.(1864)の両眼視による空間視の生得説に至っていると考えられる。ヘルムホルツは,感覚の研究ではミュラーの特殊神経エネルギー説に忠実であり,色覚の三色説や聴覚の共鳴説に見られるように生得説的である。他方,知覚の研究に対しては,イギリス経験論哲学の影響を受けて経験説的である。それを最もよく表わしているのは,無意識的推論unbewusster Schluss,unconscious inferenceの説である。この無意識的推論は,過去経験における連合の反復によって形成されたものであり,抵抗しがたく,意識的にこれを排除することはできないとされた。彼は種々の知覚現象をこの無意識的推論の説によって説明している。彼のこの説は,その後の知覚研究に大きな影響を与えている。たとえば,現代の代表的知覚心理学者グレゴリーGregory,R.L.(1998)は強くこれを支持している。心理学を独立の学問として確立したブントWundt,W.(1896)は,人の意識Bewusstsein,consciousnessを心理学の対象とし,後述の内観法によって,心的要素に分析することを心理学の使命と考えた。彼によると,心的要素には純粋感覚reine Empfindung,pure sensationと単純感情einfaches Gefühl,simple feelingがあり,それらが結合して種々の心的複合体psychisches Gebilde,psychical elementを形成しているが,知覚的表象は心的複合体の一種であるとされた。その際,心的複合体はそれを構成する心的要素にない新しい性質をもつことがあるが,それは創造的総合の原理Prinzip der schöpferischen Synthese,principle of creative synthesisによるとした。彼の伝統を受け継いだティチナーTitchener,E.B.(1910)は,知覚は具体的な意味をもつ複雑な経験であり,それを分析すれば感覚と心像imageとなるが,その結合の仕方の文脈によって意味が生じるとした(意味の文脈説context theory of meaning)。
20世紀初頭に生まれたゲシュタルト心理学Gestalt psychologyは,単なる要素の集合以上の全体過程をゲシュタルトGestaltとよび,その立場から,感覚の集合には分解できない全体過程として知覚を論じた。ウェルトハイマーWertheimer,M.が1912年に行なった最初のゲシュタルト心理学の立場からの研究は,運動視の研究であった。彼は,2点の継時的刺激によりその2点間に運動印象が生じる仮現運動Scheinbewegung,apparent motionの現象を,2光点の感覚に分析できない全体過程の例とした。彼は,網膜上の2ヵ所の継時的刺激により生起した興奮は,中枢において一つの生理過程において横の移行を生じさせていると考えた。さらにケーラーKöhler,W.(1920)は,ゲシュタルトの諸原理が物理現象でも成り立っていることを強調するとともに,大脳生理過程も物理現象であり,ゲシュタルトの諸原理の支配下にあって,心理現象がゲシュタルト性を示すのは,それを支えている生理過程にゲシュタルト性があるからであると主張した(心理物理同型説psychophysical isomorphism theory)。彼はこの立場からその後に図形残効figural aftereffectの研究などを行なっている。これに対して,ほぼ同時代にワトソンWatson,J.B.(1913)が主張した行動主義behaviorismにおいては,意識を心理学の研究対象とせず,刺激と反応の関係の解明が主目的とされ,感覚や知覚の問題も刺激の弁別行動として扱われた。たとえば,色の知覚は波長の弁別の問題とされた。しかし,その後のトールマンTolman,E.C.(1932)らの新行動主義neo-behaviorismの立場では,知覚は刺激と反応の間に想定される媒介変数の一つとして取り扱うことが可能となった。
20世紀半ばになると,ブルーナーBruner,J.S.(1951),ナイサーNeisser,U.(1967)などにより,知覚を,知覚者がすでにもっている期待expectation,仮説hypothesis,ないしスキーマschemaを外部からの刺激によって確認する過程として見る認知心理学cognitive psychologyの立場からのアプローチが盛んになってくる。そして,その期待がいかにして形成されるか,過去経験や欲求や注意がどのように知覚に影響するかが,研究されるようになった。認知心理学的アプローチでは,知覚は,知覚者が行なう情報処理過程の一環とみなされ,感覚器に入力された情報の特徴を抽出して記憶・思考などのより高次の情報処理過程に送る中間過程とみなされる。他方,ギブソンGibson,J.J.(1979)は知覚への生態学的アプローチecological approachを主張し,知覚者を環境中の能動的行為者としてとらえ,外界から与えられる感覚情報中で,環境の変化や知覚者の移動に際しても不変性を保つ環境情報の不変項invariantと,環境的事物の知覚者にとっての生態学的役割を意味するアフォーダンスaffordanceの概念の重要性を唱えた。
このように知覚研究の歴史は,知覚機能が生得的なものか,過去経験に基づくものかという生得説と経験説の対立,知覚が感覚的要素の結合か,要素に分解できない全体かという要素論elementismと全体論wholismの対立,知覚が外部からの情報に基づく受動的なボトム・アップ処理bottom-up processingか,知覚者がすでにもっているイデア,期待,スキーマなどによる能動的なトップ・ダウン処理top-down processingかの対立の間を揺れ動きながら,発展してきた感がある。
【知覚の研究法】 心理学が独立する以前の知覚に関する考察は,哲学者による日常体験に関する思弁的考察か,自然科学者による光や音などの物理的実験に随伴する考察であった。
19世紀後半に心理学を独立の学問として確立させたブントは,心理学の研究対象を直接経験すなわち意識であると定義した。ブントは心理学者を訓練して,各自の意識を自分自身で観察し,分析して,心理学の基本データとしようとした。内観法Selbstbeobachtung,introspectionである。意識の一部である知覚も内観法によって研究された。しかし,この方法では,訓練を受けた心理学者自身の意識しか研究の対象にできない。幼児や,精神障害者の意識を内観によって求めることはできない。内観法の限界は明らかであった。実際にはブント自身も,フェヒナーFechner,G.T.(1860)の考案した精神物理学的測定法psychophysical methodやドンデルスDonders,F.C.(1869)らに始まる反応時間測定法reaction time methodを広く用いていたし,幼児や動物の心理状態にも考察を広げている。また感覚・知覚研究には,刺激条件を厳密に統制するため,実験室で種々の実験装置を用いて,刺激を統制し反応を測定している。今日の心理学でも,研究対象とする人びと(被験者subject,観察者observer,実験参加者・実験協力者participantなどとよばれる)に各自の体験した事柄をそのまま報告してもらうことがある。一種の内観報告である。しかし,報告はあくまで言語行動の一部であり,報告内容がそのままその人の意識内容を表わしているとは解していない。ある内観報告がなされたということは客観的事実であっても,その内容は客観的事実とは言えない。
ブントの内観法のように,分析的態度を取らずに知覚現象をありのままにとらえてその特徴を知覚者自身が記述し,その成立条件を探る方法を実験現象学experimental phenomenologyとよぶ。ゲーテGoethe,J.W.vonの色彩研究にすでにその萌芽が認められるが,カッツKatz,D.(1911)が同じ青でも,空の青のように定位の不明確な現われ方を面色Flächenfarbe,film color,色紙の青のように定位の明確な表面色Oberflächenfarbe,surface color,水の青のように空間を満たす空間色Raumfarbe,volume color,などと名づけて分類した色の現われ方Erscheinungsweise der Farbe,mode of appearance of colorの研究,ルビンRubin,E.J.(1921)の図と地Figur und Grund,figure and groundの研究などがその典型例である。ゲシュタルト心理学者もこの方法を駆使しており,とくに新しい知覚現象の発見に有力な方法である。
自分の知覚・感覚はたしかに自分で観察できるが,他の人の知覚・感覚はまったくうかがい知れない。ことばや行動や表情から推測するだけである。それに対して,行動はだれにでも観察できる。たとえば石原式色覚検査表では,色の斑点から構成された数字を読むことが求められる。数字を構成する斑点の色と,地となる部分の斑点の色が色覚障害者には似て見えるために,数字が読みにくいのである。ここで重要なことは,この検査では決して色名を答えさせないことである。色覚検査表の場合,地と数字の色の違いが区別(弁別discrimination)できるかをテストしているのである。弁別行動を用いれば,動物の色覚も研究できる。フリッシュFrisch,K.von(1927)は,ミツバチの色覚を色紙や単色光の弁別行動を通して研究した。現在も広く感覚・知覚研究に用いられている精神物理学的測定法は,基本的には刺激と反応の関係に基づく非常に客観的な方法で,行動主義的方法論に適合することがグレアムGraham,C.H.(1950)によって指摘されている。刺激を組織的に変化させて「はい」「いいえ」,「大」「小」などの単純な回答の出現率が一定(50%など)となるための刺激の物理的値を閾値thresholdや主観的等価点point of subjective equalityとしているからである。さらに,近年は精神物理学的測定法を動物や乳児に適用して,動物や乳児の感覚・知覚を研究する動物の精神物理学(心理物理学)animal psychophysicsや乳児の精神物理学(心理物理学)infant psychophysicsも発展して,動物や乳児の感覚・知覚研究に適用されている。
知覚の実験的研究には,知覚を生じさせる刺激の厳密な統制と反応の測定が必要である。そのため,ブントの時代から種々の実験機器が開発され使用されてきた。その一部は物理学,生理学,医学へも流用されたが,心理学独自のものも多い。たとえば混色器,瞬間露出器,実体鏡(ステレオスコープ),可変音響発生機,嗅覚計,時間測定器(クロノスコープ),カイモグラフなどである。その後,技術の進歩に従い,改良を重ね,今日では刺激の統制・呈示と反応の測定にコンピュータが広く用いられている。また,外部からの影響を遮断するための実験室として暗室,防響室,無臭室などが利用される。
知覚研究は,それぞれの時代の生理学と緊密な関係を保って進められてきた。初期には生理学者が知覚研究を行なってきたが,その後心理学者が生理学的手法を利用するようになった。初期には感覚器官である網膜や蝸牛殻などの生理学との関連が研究されたが,しだいに脳の各感覚野の生理学との関連が論じられ,今日ではさらに高次の脳領域との関連が研究され,機能的磁気共鳴画像functional Magnetic Resonance Imaging(fMRI)などの測定なども,知覚研究に利用されている。 →運動の知覚 →感覚 →感性 →ゲシュタルト心理学 →恒常現象 →錯覚 →実験心理学 →図形残効 →精神物理学 →精神物理学的測定法 →認知
〔大山 正〕
出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「知覚」の意味・わかりやすい解説
知覚
ちかく
perception
人間をはじめとする生活体が視覚、聴覚、触覚などの感覚受容器を通して環境の事物やその変化を知ることを意味する。感覚は、受容器が興奮し、求心性神経によって伝達されたインパルスimpulseが感覚中枢を刺激することによってもたらされる直接的経験であるが、知覚はいくつかの受容器の相互作用に基づいた総体的な経験である。過去の記憶内容との照合、注意、思考、言語といった心理的過程や、運動系との相互作用を重視して考えた場合、さらに広義に認知cognitionといわれる。最近では知覚や記憶、思考などを連続した不可分の情報処理過程とみて、主体的要因を含む階層構造を想定する、いわゆる認知的アプローチが試みられている。
[西本武彦]
知覚の構造
光とか音のように直接感覚受容器に与えられる刺激は近刺激proximal stimulus、元になっている刺激は遠刺激distal stimulusとよばれる。同じ遠刺激でも受け取る条件によっては異なって知覚される。その逆もいえる。テレビのブラウン管上の人物は電気的に合成された擬似人間であるが、近刺激としては実在する人物と等価である。知覚された事物は一つの構造をもっている。すなわち、刺激布置にまとまりができて(分凝segregation)、部分的に図と地が分節figure-ground articulationしている。この分節を規定する要因としてゲシュタルト心理学では閉合の要因、シンメトリーの要因などいくつかの要因をあげる。図と地の問題に最初に注目したのはルビンである。この反転現象は、物理的刺激としては同一のものでも知覚する主体にとっては図が地になり、地が図になるというように対応関係が変わることを示している。図は無秩序に存在するのではなく、互いにまとまりをもつ。これを知覚対象の群化という。近さの要因、類同性の要因、共通運命の要因などいくつかの要因があげられていて、分節の要因とあわせてゲシュタルトの法則とよばれる。群化の法則は「よい」形態を成立させる法則であり、プレグナンツ(簡潔性)の原理principle of Prägnanzが働く。
実際の生活空間では、知覚対象は時空間的に時々刻々変化し、明るさ、大きさ、角度、距離などが変わるが、相互の割合が変わらなければ対象の知覚は変わらない(知覚の恒常性perceptual constancy)。逆に、同じ対象でも周囲の刺激布置や枠組みによって異なって知覚されるのが幾何学的錯視である。
知覚は複雑な心理的過程の総体であり、そこには生活体の学習経験や社会的・文化的背景が反映する。性格検査の一つとして有名なロールシャッハ・テストは多義的で、あいまいな図形を用いるが、基本的には見る人のパーソナリティーがそうした図形の知覚内容に反映するとする力学的知覚の立場にたっている。力学的知覚、社会的知覚といわれるのは主体の欲求や期待を重視する立場であり、ニュールック心理学new look psychologyとよばれる。
[西本武彦]
知覚研究の歴史
(1)構成主義的知覚理論 19世紀後半、ドイツ人ブントによって出発した科学的な心理学は、構成主義的心理学であり、心理現象を単純な基本要素の結合によって説明しようとした。この立場の知覚研究は知覚表象を純粋感覚に分析し、その結合法則を考察することであり、ティチナーによってさらに強く主張された。(2)ゲシュタルト理論 構成主義的心理学では知覚を要素過程に分析しようとした結果、素朴な知覚経験の現実性が失われた。これに対してカッツやルビンは心理現象をあるがままにとらえることを主張して、日常空間での色の見え方や図・地の反転現象を詳細に記述した。この立場は実験現象学experimental phenomenologyとよばれ、ゲシュタルト心理学に組み入れられた。ゲシュタルト心理学は構成主義、連合主義をモザイク説として退け、知覚を含む心理現象は体制化された全体構造によって規定されるという全体論的立場を主張した。たとえば、メロディーは個々の音の総和以上の全体的特徴をもつし、構成要素である個々の音を一定音階だけ変化させても同じメロディーとしての特徴は保たれる。すなわち移調transposition可能である。心理現象はもっとも単純で安定した体制に落ち着くように自動的に変化する、というプレグナンツの原理が、ゲシュタルト心理学の基本原理である。ゲシュタルト心理学は、ウェルトハイマーの仮現運動apparent movementを起点とし、ケーラーの心理物理同型論psychophysical isomorphism、コフカらの図形残効figural aftereffect研究、レビンの心理学的場理論に発展していった。(3)現代の知覚研究 ゲシュタルト心理学においてはその研究の多くが図形を暗室で提示するというように、実生活空間から離れた環境で行われた。この点を批判してギブソンは、自然環境のなかでの通常の観察による知覚を重視した。視空間は「面」「線」「距離」の諸特性をもつが、彼はこれらを網膜像における勾配(こうばい)に関係づけたので勾配説gradient theoryといわれる。近接刺激のなかに、知覚の成立に必要な情報が含まれるとする考えである。ブルンスウィクE. Brunswik(1903―55)は、知覚を環境に対する適応の手掛りとしてとらえ、その生態的妥当性ecological validityを問題にして、遠刺激、近刺激、知覚の三者関係をレンズ・モデルlens modelで示した。またエームズA. Ames Jr.に代表されるトランスアクション説transaction theoryにおいては生活体と環境との力動的相互関係が重視され、過去経験によって生まれた仮説が知覚を導くと考える。
このほか、ゲシュタルト心理学ではあまり取り上げられなかった欲求、期待、性格といった生活主体の要因を重視したのが、ニュールック心理学である。ブルーナーらの貨幣の見かけの大きさと貧富の差との関係を調べた実験などがある。
以上のような機能主義的傾向とは別に、ヘッブの細胞集成体説は知覚過程に対応した神経生理学的過程の成立メカニズムを想定する。しかしモデルの実証性はまだ十分ではない。現代の知覚研究にあって生理心理学的研究は目覚ましく進展している。ヒューベルD. H. Hubelによって発見された、図形特徴を選択的に検出する神経細胞feature detector、マッハ現象Mach phenomenaを説明する側抑制(そくよくせい)lateral inhibitionのメカニズムは知覚研究に大きな影響を与えている。
さらに精神物理学がフェヒナーによって創設されて以来、彼の考案した測定法は改良を加えられながら今日、調整法method of adjustment、極限法method of limits、恒常法constant methodとして心理量の評価のうえで重要な役割を果たしている。スティーブンスによって定義された四つの尺度やべき関数、通信工学で生まれた信号検出理論の精神物理学への適用など、心理量の測定法には飛躍的な発展がみられる。
[西本武彦]
哲学における知覚
哲学においては、事物についての直接的な認識という性格を示す経験的意識が「知覚」である。もし「感覚」と「知覚」を区別するならば、まとまった体制を備え、事物の直知である「知覚」は、与えられた感覚素材を総合‐統握し、解釈し、あるいは記憶や期待によって補ったりしながら、事物を事物として現出させる経験的意識であると解される。これに対して単に素材的印象としてのデータ(所与)は「感覚」とよばれる。ただし、知覚から区別される単に印象的なセンス・データ(感覚与件)なるものが、実際の経験において与えられることがあるかどうかは疑わしく、「感覚」と称されるものも、単に体制が比較的単純な知覚であるかもしれない。
ヘーゲルは『精神現象学』(1807)において、知覚を感覚とともに(自己意識とは区別される)対象意識の項目に入れ、しかも知覚が感覚よりも高次なのは、感覚(的確信)がまったく直接、無媒介の「いま」と「ここ」にとらわれているのに対して、知覚は単なる感覚印象的なものを媒介し、たとえば「白く」も「固く」も「丸く」も……ある一つの「物」(たとえば灰皿)をとらえる、つまり事の真実をとらえる(wahr-nehmen)からだとしている。だが、この見方も前記の「知覚」という語の今日における一般的な用法を逸脱するものではない(西洋では近代の初めごろまでは、知覚perceptioは前述したよりも広く、心的な把握の働き一般をさすのに用いられた)。
知覚はまた、事物の認知であるという点では、想像、身体感覚、夢などに対比させられ、直接的な知という点では、推論のような働きに対比させられることもある。
サルトルの『想像的なもの(想像力の問題)』(1940)によれば、想像的な意識はその対象を無として、つまり非存在として措定するが、そのことは逆にいえば、想像には知覚にみられる対象の「観察」が伴わないこと、想像が一種の「擬似観察」であることを示す。知覚には、対象の射映面的な現出に伴う際限のない観察ということがあり、無限にくみ尽くしがたい豊饒(ほうじょう)性があるのに対して、想像物の擬似観察は、観察とはいっても、想像する主観が初めそこに措定したもの以上には出ない観察である。知覚の主題的対象がそれを取り巻くもろもろの地平に守られながら、前後左右、遠近さまざまの現出様式(射映面)を通して物として現前してくるところに、知覚物が想像物や単なる観念とは違って、「生きた」知覚物であるしるしが認められるのである。
[山崎庸佑]
『藤永保他編『新版 心理学事典』(1981・平凡社)』▽『R・L・グレゴリー著、金子隆芳訳『インテリジェント・アイ』(1972・みすず書房)』▽『J・E・ホッホバーグ著、上村保子訳『知覚』(1981・岩波書店)』▽『和田陽平他編『感覚・知覚心理学ハンドブック』(1969・誠信書房)』▽『ヘーゲル著、金子武蔵訳『精神の現象学』上下(1971、79・岩波書店)』▽『メルロ・ポンティ著、竹内芳郎他訳『知覚の現象学』全二巻(1967、74・みすず書房)』
改訂新版 世界大百科事典 「知覚」の意味・わかりやすい解説
知覚 (ちかく)
〈知覚〉は,日本では古来,〈知り,さとる〉という意味の語であったが,西周が,アメリカ人ヘーブンJoseph Havenの著《Mental Philosophy》(1857,第2版1869)の邦訳《心理学》上・下巻(1875-79)の中で,perceptionの訳語として使用して以来,哲学や心理学などで英語,フランス語のperceptionやドイツ語のWahrnehmungの訳語として定着するに至った。perceptionという語は,〈完全に〉〈すっかり〉などの意を示す接頭辞perと,〈つかむ〉を意味するラテン語capereとからなる語であり(ドイツのWahrnehmungは,〈注意〉の意を有するwahr-英語のawareなどに残っている-と,〈取る,解する〉を意味するnehmenとからなっている),たいていは五感によって〈気づく〉〈わかる〉ことを意味する。哲学や心理学でも,感覚を介する外的対象の把握が普通に〈知覚〉と呼ばれている。したがって,それは,純粋に知的な思考や推理とは区別されるが,また単なる感覚とも区別されるのが普通である。しかし,その場合問題になるのは,実はそうしたことのもつ認識論的価値であるから,その点をめぐって知覚についての議論もさまざまに分かれてくることになる。
まず,知覚が刺激の単なる変容としての感覚から区別されるのは,知覚が対象についての認知を含むと考えられているからである。一方,知覚が感覚を媒介にした把握に限られるのは,知覚に対象との直接的接触が期待されているからである。その意味では,知覚は,対象との直接的接触による直観知への要求を反映した概念ともいえる。事実,われわれ自身の内的状態や意識そのものの把握が,いわゆる五感によるものではないにもかかわらず,ときに〈内部知覚〉などと呼ばれるのは,知覚のそうした理解にもとづいているわけである。そして知覚がそのような対象の直接知と解されるならば,それが知識の最も基礎的な源泉と考えられるようになるのも当然である。フッサールやメルロー・ポンティなどがその好例であって,フッサールによれば,知覚こそは対象自体を与えてくれる〈本源的〉知なのである。もっとも,知覚を対象の直接的把握とすることには反論もある。例えば,机の知覚において,われわれが直接に見ているのは机の前面だけであり,その裏側はいわば想像されているにすぎないからである。われわれの錯覚も,多くはそのようなところから生じているわけである。そして,そのことがまた,〈現象〉と〈実在〉ないし〈物自体〉とを区別する存在論的二元論や,あるいは知覚を純粋な感覚(例えば〈感覚所与〉)となんらかの知的作用との合成物と見る主知主義的解釈の根拠ともなる。フッサールが,〈外部知覚〉の明証性と〈内部知覚〉の明証性とを,前者を〈不十全〉とし後者を〈十全〉として区別したのも,外的知覚の一面性を配慮してのことであった。
しかし,これらの議論は,それほど説得的なものではない。確かに,われわれは知覚において思い違いをすることがある。しかし,その誤りは,対象に近づくなり視点を変えるなりして修正することができる。したがって,あるときの知覚の誤りから,われわれの知覚のすべてを一挙に非実在的な〈現象〉の把握とするのは,形而上学的飛躍といわなければならない。しかも,われわれが〈現象〉と異なる本物の〈実在〉を仮定するということ自体,実はわれわれが日常,誤認と正しい認知との違いを体験していることにもとづくのであって,その違いこそは知覚が教えてくれたものなのである。また,知覚の主知主義的解釈も,〈感覚所与〉といった概念がすでに経験的に確認しえないものであるところに,重大な難点をもっている。そのうえ,知覚は動物にもあると考えられるから,その構成要素として知的作用を仮定する必要はないし,そもそも知覚は,まだ判断ではないのである。それは,例えば〈ルビーンの杯〉などで,図形の反転が判断や解釈によって起こるのではないことからも知られる(反転図形)。なお,〈外部知覚〉と〈内部知覚〉の明証性の違いに関しても,例えば容易に自己反省をなしえない幼児のような存在もある以上,われわれはここでむしろ,内部知覚が何によって可能になるかをこそ問題にしなければならないであろう。
このように見るならば,知覚のもつ認識論的価値を過小に評価すべき理由はあまりないといわなければならない。もちろん,知覚の可謬性は否定できないことであり,したがってそのつどの知覚はさまざまの科学的手段によって修正される必要があるにしても,そもそも外的対象があり,世界が存在することは,知覚による以外に知りようがないからである。メルロー・ポンティが知覚を,いっさいの説明に前提されている〈地〉と呼んだのは,その意味においてである(《知覚の現象学》序)。知覚を刺激や神経の興奮などから因果的に説明しようとする〈知覚の因果説〉の不備も,根本はその点にかかわるのである。
執筆者:滝浦 静雄
知覚と感覚の生理学
知覚は具体的な意味のある意識的経験で,なんらかの対象に関係しているということで,受容器の刺激の直接的な結果として起こる感覚と区別される。例えば形の知覚とかメロディの知覚というように,知覚は複雑な刺激パターンによってひき起こされる場合が多い。しかし色彩知覚や運動知覚のように対象とは独立に起こる知覚もあり,感覚との区別はあいまいである。
W.ブントやE.B.ティチナーなど構成心理学の人々は,要素的な純粋感覚を仮定し,その総和と,それと連合した心像(以前に経験した感覚の痕跡)を加えたものが知覚であると考えた。しかしM.ウェルトハイマーやW.ケーラーなどゲシュタルト心理学の人々は,知覚を要素的な感覚に分けることは不可能で,むしろ直接的に意識にのぼるのはつねに,あるまとまった知覚であると考えた。例えばウェルトハイマーが1912年に発見した仮現運動の場合は,少し離れた2個の光点が順番に提示されると,静止した別々の光点には見えず一つの光点が動いているという運動印象だけが得られる。ケーラーは,あらゆる知覚現象には必ずそれに対応する脳の生理的過程があるという心理物理同型論psychophysical isomorphismの立場から,仮現運動が実際の運動と等しい生理過程を大脳皮質にひき起こすのであろうと考えた。最近の神経生理学的研究によると,実際にネコやサルの視覚野とその周辺で記録される運動感受性細胞は,連続的な運動だけでなく仮現運動にもよく反応する。したがって今日では,知覚は受容器でとらえた感覚信号の空間的・時間的パターンから,中枢神経系で何段階かの情報処理を経て読み取られた,あるまとまった意味のある情報であると理解されている。
知覚の恒常性
知覚はもともと感覚の種類によって大きく分かれているが,さらに同じ感覚の中でもいくつかのカテゴリーに分かれる。特に視覚は,明るさ,色彩,形態,大きさ,運動,奥行き,空間などさまざまなカテゴリーの知覚に分かれる。これらのカテゴリーの多くに共通の現象として,知覚の恒常性がある。例えば明るさ(白さ)の恒常性は,照明の強さと無関係に黒い物は黒く,白い物は白く見える現象をいう。これは知覚系が明暗の対比をもとにして表面の反射率を識別しているからである。色の恒常性は照明光のスペクトルが大幅に変わっても,その物に固有の色が見える現象をいう。ランドE.Landによると,これは知覚系が,赤,緑,青の色光の相対的な反射率を識別しているためで,これもおそらく色の対比がもとになっていると思われる。大きさの恒常性は,対象の距離を変えてもその大きさが同じに見える現象をいい,形の恒常性は,見る角度を変えても形が同じに見える現象をいう。これらは知覚系が網膜像の大きさや形のほかに,距離や面の傾きを計算に入れていることを示している。このように知覚の恒常性は,対象を見る条件がいろいろに変わっても,同じ物はつねに同じに見えるようにする知覚の働きを示す現象で,外界の認識のために重要な意味をもっている。しかし一方では,恒常性を保つメカニズムがさまざまな錯視の原因にもなっている。
知覚の神経生理学的研究
この方面の研究は,ヒューベルD.H.HubelとウィーゼルT.N.Wieselが1963年にネコの視覚野で,細長いスリットや黒い線およびエッジに反応する細胞を発見してから急速に発展してきた。視覚野にはこのほか,両眼視差や網膜像の動きや色の対比を検出する細胞があり,これらが立体視や運動視や色彩知覚のための情報処理を行っている。しかし意識にのぼる知覚に対応する神経系は,より高次の感覚周辺野や連合野にある。最近,ゼキS.Zekiは第4視覚野で色彩知覚に直接対応する色覚細胞を発見した(1980)。また第5視覚野(またはMT野)には奥行きを含むさまざまな方向の運動に反応する細胞が集まっている。視覚周辺野のその他の領域も,それぞれ別のカテゴリーの知覚に関係していると思われる。そして側頭連合野(下側頭回)は形態視に関係し,頭頂連合野は空間視に関係した情報処理を行っていることが明らかになりつつある。そのほか,体性感覚野とその周辺には,皮膚表面の動きやエッジに反応する細胞や,いくつかの関節の組合せや関節と皮膚の組合せ刺激に反応する細胞があって,触覚による形態知覚や触空間や身体図式(姿勢)の知覚に関係する情報処理を行っている。聴覚野とその周辺には,複合音や雑音や周波数変化(FM音)に反応する細胞があって音声の知覚に関係する情報処理をしているほかに,音源定位に関係する細胞群も記録されている。このように,知覚は大脳皮質における複雑な感覚情報処理の結果である。
→感覚
執筆者:酒田 英夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「知覚」の読み・字形・画数・意味
【知覚】ちかく

 ほ
ほ なり。但だ璽書(じしよ)のみを以て兵を發し、未だ虎符(こふ)の信
なり。但だ璽書(じしよ)のみを以て兵を發し、未だ虎符(こふ)の信 らず。詩、上
らず。詩、上 して曰く、~如(も)し姦人の詐僞する
して曰く、~如(も)し姦人の詐僞する るも、由(よ)りて知覺する無(なか)らんと。
るも、由(よ)りて知覺する無(なか)らんと。字通「知」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「知覚」の意味・わかりやすい解説
知覚
ちかく
perception
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「知覚」の意味・わかりやすい解説
知覚【ちかく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の知覚の言及
【感覚】より
…
【哲学における感覚】
仏教用語としては古くから眼識,耳識,鼻識,舌識,身識(これらを生じさせる五つの器官を五根と称する)などの語が用いられたが,それらを総称する感覚という言葉はsensationの訳語として《慶応再版英和対訳辞書》に初めて見える。日常語としては坪内逍遥《当世書生気質》などに定着した用法が見られ,また西田幾多郎《善の研究》では知覚と並んで哲学用語としての位置を与えられている。 哲学史上では,エンペドクレスが感覚は外物から流出した微粒子が感覚器官の小孔から入って生ずるとしたのが知られる。…
※「知覚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...