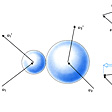翻訳|collision
精選版 日本国語大辞典 「衝突」の意味・読み・例文・類語
しょう‐とつ【衝突】
- 〘 名詞 〙
- ① 攻撃すること。突入すること。
- [初出の実例]「敵四面萃レ之。高重左右衝突。所レ向皆披」(出典:日本外史(1827)四)
- [その他の文献]〔南史‐蕭摩訶伝〕
- ② 二つ以上の物がぶつかり合って短い時間内に大きな力を及ぼし合うこと。また、その現象。つきあたること。ぶつかること。〔新令字解(1868)〕
- [初出の実例]「船舶が双方の船員の過失に因りて衝突したる場合に於て」(出典:商法(明治三二年)(1899)六五〇条)
- ③ 立場、意見などの相反するものどうしが、言論や腕力・武力で争い合うこと。また、その争い。
- [初出の実例]「唯是桓譚無レ信レ讖、寧知衝突断二肝心一」(出典:周南先生文集(1760)三・丁未秋従物先生泛舟墨水)
- 「曲り角で中学校と師範学校が衝突したんだと云ふ。中学と師範とはどこの県下でも犬と猿の様に仲がわるいさうだ」(出典:坊っちゃん(1906)〈夏目漱石〉一〇)
改訂新版 世界大百科事典 「衝突」の意味・わかりやすい解説
衝突 (しょうとつ)
collision
一般に物がぶつかることであるが,物理学,化学,工学では非常に重要な概念の一つである。物理学,化学での衝突はわれわれが日常体験する衝突現象とはだいぶ趣を異にするものを含んでいる。日常われわれの経験する衝突現象とは,球の衝突とか自動車の衝突とかで,衝突する物体どうしの間には接触するまでは相互作用が働かないとみなせる。すなわち,剛体どうしの衝突である。しかし,星と星との衝突とか,電子とイオンの衝突では距離の2乗に反比例する引力が働き,このために軌道は双曲線を描いて,直接に触れ合うという日常的な意味で衝突することはむしろまれである。ここでは日常的な意味での衝突を剛体系の衝突,そうでない場合を遠達性ポテンシャルによる衝突と分けて論ずることにする。分子,原子,イオン,電子,原子核,陽子,中性子,その他の素粒子の間での衝突現象は,古典力学ではなく量子力学で扱わなければならない。量子力学での粒子の運動は,物質の波動性によって波としての性質ももっている。このために散乱ということばが使われることがある。また衝突する粒子の内部構造が変化する場合,反応ということばが用いられるが,広くは衝突に含まれる。
剛体系の衝突
例として,質量m1,m2の2個の回転していない球が正面衝突する場合を考える。2物体は速さv1,v2で球の中心を結ぶ線上に向いて進んでいるとする。一方の速さの向きを正にとり,反対方向の速さを負にとる。衝突後の速さをv1′,v2′とする。v1′とv2′はやはり2球の中心を結ぶ直線上にある。これらの量の間には,
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
の関係がある。すなわち,2物体を構成する系の重心の運動量は衝突の前後で保存されている。しかし,この式だけでは衝突後の速さv1′とv2′は決まらない。球と球がぶつかったときに,どんな勢いではね返されるかが問題となる。相対速度v1-v2でお互いにぶつかった球が同じ大きさの相対速度(v2′-v1′=v1-v2)ではね返される場合と,これより小さい相対速度ではね返される場合がある。前者は完全弾性衝突であり,後者は非弾性衝突である。一般には,これら前後の相対速度の比 をもって反発の度合を表す(負号をつけるのはv1-v2の方向とv1′-v2′の方向が反対方向のため)。eを反発係数coefficient of restitutionといい,e=1が完全弾性衝突,0<e<1が非弾性衝突であり,e=0は完全塑性衝突,または完全非弾性衝突と呼ばれる。e<1の場合は相対運動のエネルギーは衝突後球の内部エネルギー(熱エネルギー)に変換される。日常的な例をとると,車どうしが衝突した場合,堅牢につくってあると弾性衝突に近い衝突となり,大きな速さではねとばされかえって被害が大きいので,なるべく車体の内部エネルギーとして吸収されるような構造にすることが望ましい。このために車の前部は適度につぶれやすい構造になっている。
をもって反発の度合を表す(負号をつけるのはv1-v2の方向とv1′-v2′の方向が反対方向のため)。eを反発係数coefficient of restitutionといい,e=1が完全弾性衝突,0<e<1が非弾性衝突であり,e=0は完全塑性衝突,または完全非弾性衝突と呼ばれる。e<1の場合は相対運動のエネルギーは衝突後球の内部エネルギー(熱エネルギー)に変換される。日常的な例をとると,車どうしが衝突した場合,堅牢につくってあると弾性衝突に近い衝突となり,大きな速さではねとばされかえって被害が大きいので,なるべく車体の内部エネルギーとして吸収されるような構造にすることが望ましい。このために車の前部は適度につぶれやすい構造になっている。
さて気体を構成している分子は,ヘリウム,アルゴンなどの希ガスのように1原子で1分子のものもあれば,水分子のように3原子で1分子というものもある。衝突によって内部へエネルギーが移る可能性のない希ガスの場合とか,可能性はあっても実際に移りにくい場合には,分子は完全弾性衝突に近い衝突を繰り返す。したがって気体運動の基本的な性質は剛体の完全弾性衝突を仮定して導かれる。
遠達性ポテンシャルによる衝突
この場合には遠くから力が働くために,物体が実際に触れ合うことなく相互作用し,軌道が曲げられる。例えば星の運動は万有引力によって軌道が曲げられる。この場合,さらに物体の内部に影響が及ぶことがある。天体どうしが近くを通過すると,引力によって月による海の潮の干満と類似の現象が起こる。また電子や陽子と原子核とは電気的クーロン力によってその軌道が曲げられ,ある場合には原子核を励起することもある。このように実際に剛体系の場合の衝突が起こらなくても,原子核の内部状態に変化を与えることができる。原子や分子,あるいは原子核とこれらの構成粒子である電子,陽子,中性子,その他の素粒子などとの衝突過程は,これらの粒子が波動性をもっているので一般には散乱過程とも呼ばれており,量子力学によって定式化されている。ここでは系の衝突粒子を便宜上入射粒子と標的とに分けて論ずることにする。標的の状態が基底状態から励起状態になるときには,入射粒子の運動エネルギーは標的のエネルギー差の分だけ減少する。このような衝突を非弾性衝突と呼び,衝突前後で粒子の運動エネルギーの変化しない衝突を弾性衝突と呼んでいる。また,初めに標的が励起状態にあって衝突後に基底状態に戻るときには,入射粒子は衝突後運動エネルギーが増加する。これも非弾性衝突であるが,一般には超弾性衝突とか脱励起衝突と呼んでいる。
このように剛体系の衝突は,物体が離れているときには相互作用が起こらず,接触した瞬間だけ起こるものであり,一方,遠達性ポテンシャルによる衝突は,物体が離れているときに相互作用が起こるものであるが,一般の衝突ではこの両者を含んでいる。すなわち,遠達性ポテンシャルによる衝突でも,正面衝突に非常に近づけば,星と星が衝突する場合を考えてもわかるように,剛体系の衝突現象が加わる。反対に剛体系の衝突でも万有引力が働いているが,非常に弱い。一般に物理学や化学では,衝突する粒子(または物体)の間の相互作用ポテンシャルを粒子(物体)間距離の関数として描くことによって統一的に論じている。
執筆者:渡部 力
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「衝突」の意味・わかりやすい解説
衝突
しょうとつ
二つの物体が、その大きさよりずっと大きい距離からしだいに近づき、短い時間だけ相互作用を及ぼし合う現象。ふたたび離れていくことが多いが、2物体が合体してしまう場合もある。衝突の直前と直後で、重力のような外力の位置エネルギーの変化は小さいのが普通なので、相互作用を別にすると、力学的エネルギーとしては、各物体の重心運動のエネルギー(1/2)mv2(mは物体の全質量、vは重心の速さ)と、重心に対する相対運動(回転や振動など)を考えることが多い。2物体が衝突直前にもっていた運動量をp1=m1v1, p2=m2v2、衝突直後のそれらをp1'=m1v1', p2'=m2v2'とすると、ベクトル量としての運動量保存則
p1+p2=p1'+p2' (1)
はかならず成り立つ。また2物体の角運動量の和も保存される。しかし、重心運動の運動エネルギーの保存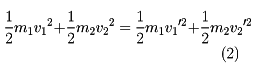
は成り立つとは限らない。物体の全運動量は重心の運動量に等しいが、エネルギーはそうではなく、重心に対する相対的な運動(回転や振動などの内部運動)の運動エネルギーや変形などによる弾性エネルギーの変化なども考えて、それらの相互転換を考慮しなければいけないからである。内部運動には、巨視的に運動とみえる振動や回転のほかに、微視的な原子・分子の熱運動も含まれる。重心運動以外のエネルギーに変化がなければ(2)式が成り立ち、この場合の衝突は弾性衝突とよばれる。そうでない衝突を非弾性衝突という。巨視的な2球の衝突の場合には、相対速度v2'-v1'とv2-v1の、接触点における法線成分の大きさの比をとって、反発係数またははねかえり係数とよぶ。これは、球の材質で決まる0と1の間の値をとることが経験的に知られている。衝突で両球がくっついてしまうのは反発係数が0の場合であり、弾性衝突では反発係数は1である。微視的な粒子は量子力学で扱わねばならないので、波動力学が適用され、衝突現象は波の散乱という形式で処理される。このために衝突のことを散乱ということが多い。個々の微粒子の行動の追跡はできず、多数の粒子の流れを扱うので、それと標的粒子との衝突の仕方はさまざまで、衝突して出てくる粒子は散らばる。この場合、どの方向へ出てくる粒子はどのくらいの割合かを示す衝突断面積(散乱断面積)という量が研究の対象となる。なお、衝突前後で粒子の種類や数が変わる場合には反応とよぶ。
[小出昭一郎]
百科事典マイペディア 「衝突」の意味・わかりやすい解説
衝突(物理)【しょうとつ】
→関連項目運動量保存の法則|粒子線
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「衝突」の読み・字形・画数・意味
【衝突】しようとつ
 、乃ち
、乃ち 士數百人を
士數百人を
 し、風に因りて火を縱(はな)ち、直ちに之れを衝
し、風に因りて火を縱(はな)ち、直ちに之れを衝 す。
す。 、
、 に大いに敗る。
に大いに敗る。字通「衝」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
化学辞典 第2版 「衝突」の解説
衝突
ショウトツ
collision
普通,二つの物体が近接して,2物体間に相互作用(ポテンシャルないし力で記述される場合が多い)がはたらく現象をいうが(二体衝突),ときには三つ以上の物体が同時に相互作用する多体衝突もある.衝突の前後で,物体の内部エネルギーの変化がなく,運動エネルギーが保存される場合を弾性衝突,そうでない場合を非弾性衝突という.量子力学では,粒子の衝突は,散乱ないし反応とよばれ,前者は衝突の前後で粒子の種類や数が変化しない場合,後者は変化する場合である.衝突に際しては,系の全エネルギー,運動量,角運動量,電荷などは変化しない保存量であり,衝突の起こる確率は量子力学では衝突断面積で表される.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衝突」の意味・わかりやすい解説
衝突
しょうとつ
collision
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...