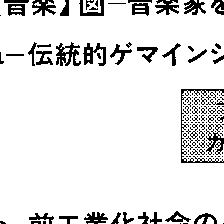精選版 日本国語大辞典 「音楽」の意味・読み・例文・類語
おん‐がく【音楽】
- 〘 名詞 〙
- ① 音による芸術。音の強弱、長短、高低、音色、和音などを一定の方法によって取捨選択して組み合わせ、人の理性や感情にうったえるもの。人声による声楽、楽器による器楽とに大別される。日本では、古くは天上の楽や、それを模した法会の楽をいった。
- [初出の実例]「雅楽寮及諸寺種々音楽並咸来集」(出典:続日本紀‐天平勝宝四年(752)四月乙酉)
- 「只今、更に音楽有る事无し。此れは何に置ふ事ぞ、と。師の云く、我れ、心神変わず、正しく音楽の音有り」(出典:今昔物語集(1120頃か)一五)
- [その他の文献]〔呂氏春秋‐大楽〕
- ② 雅楽の器楽合奏。
- [初出の実例]「停東遊、以音楽可奉、自余如常」(出典:御堂関白記‐寛仁二年(1018)四月六日)
- ③ 芝居の囃子(はやし)の一種。笛、篳篥(ひちりき)、太鼓入りで人物の登場、退場に用いるもの。
- [初出の実例]「舞台よき所迄押出し、留ると、鈴(れい)のいったる音楽になり」(出典:歌舞伎・暫(1714))
音楽の語誌
( 1 )「音」は歌声、「楽」は楽器の発する音。古代では「音楽」は「楽」よりさらに狭義で、仏教の聖衆が謡い奏でる天上の楽、あるいは天上の楽を地上に模して荘厳しようとする法会の舞楽の意で用いられ、「音声楽(おんじょうがく)」が和文脈にみえるのに対して主に漢文脈にみえる。
( 2 )「今昔物語集」などの説話では天上の楽や法会の楽をいう「音楽」に対して世俗のそれを「管絃」といって区別している。
( 3 )明治初期でも宮内庁は雅楽の意に限定しており、「音楽」があらゆる音楽活動や形態の総称となったのは文部省の訓令によって音楽取調掛が創設された明治一〇年代以降である。
改訂新版 世界大百科事典 「音楽」の意味・わかりやすい解説
音楽 (おんがく)
音楽とは何か
音楽は絵画や彫刻とともに人類の始源までさかのぼりうる創造的な営みの一部であるが,絵画や彫刻が視覚的に訴えかける空間的な形象性を特徴とするのに対して,音楽は聴覚を媒介として,時間的に展開され把持される意味を形づくる。音の強弱,高低,色彩,リズム的な継起,一定のパターンによる反復や変形などがその意味形成の手段となり,同時にその意味を認める心的な働きがあって,音楽は成立する。その意味で,音楽は語られる言語と多くの共通面をもっている。事実,外国人の語る言葉は,その言葉がわからない人にとって,ある場合〈音楽的〉に聞こえるものである。その場合聞き手にとっては,個々の言葉が具体的になにものかを指し示す概念的な指示作用は理解の外に置かれ,音の強弱,高低,色彩,長短などのかもし出すニュアンスにもっぱら意識が集中してゆく。その結果,いわば抽出された純粋な〈音〉による形成作用が,快または不快の対象として受けとめられているのである。音楽は,このような聞き方の方向づけの上に成り立ち,さまざまなジャンルを包含しつつ独自の領域を形成する。
現代は,音楽の聞き方が柔軟な広がりを見せつつある時代といえよう。とくに日本では,洋楽・邦楽の各ジャンル,歌謡曲,民謡,ジャズ,ポピュラー音楽など,あらゆる種類の音楽が並立し,さらにCMソングやバックグラウンド・ミュージックまで数えれば,音楽は膨大な広がりをもっている。この状況は,とくに第2次世界大戦以後のマス・コミュニケーションの発展によるあらゆる種類の音楽への接近可能性と,音響機器の発達による録音再生および複製の広範な可能性によって開かれたものであり,新しい状況は音楽の概念そのものの変質と拡大を促したのである。しかし,過去の状況は別であった。明治以前の日本では,たとえば雅楽は寺社と公卿階級に属し,能楽は武家階級のもの,長唄や浄瑠璃は町民のものというように,音楽の各ジャンルは,社会的階層の中に個別的,閉鎖的に所属するという傾向が強かった。
吉川英士によれば,〈音楽〉という用語は,古く中国からもたらされたが,奈良朝ころまでは,表記するためにその文字を借りても,〈おんがく〉とは訓(よ)まず,〈うたまひ〉〈もののね〉などといった。次いで,平安初期ころから,〈おんがく〉という語が用いられたが,主として唐楽・高麗楽系統の器楽合奏曲を指した。江戸時代以降になると,日本の民族的伝統音楽も,ときに〈おんがく〉という名称で呼ばれるようになったが,なお一般化せず,明治以降は西洋音楽とその様式によって作曲された音楽が,主として〈おんがく〉と呼ばれた。そのようにして,〈音楽〉を外来のもの,高尚なもの,雅と俗に関していえば雅なるものとする限られたとらえ方が,日本では近代に至るまで支配的であった。
日本以外の諸国ではどうであろうか。諸民族の文化に対する視野の広がりに伴って,今日われわれは無文字社会にもそれぞれの音楽文化が存在することに気づいている。しかし,社会的な行動の脈絡の中で,豊かな〈音づくり〉があったとしても,それを〈音楽〉として意識しない民族も少なくない。たとえば,イスラム文化圏で接するコーランの朗誦は,ときに胸を打たれるほど美しい。しかし,当人たちは,音楽に携わるという意識をもってはいない。現実に音楽的な営みはあっても,それを〈音楽〉として受容する態度は見られず,もっぱらメッセージ的な性格が重視され,音楽的行為の純音楽的側面は無意識の層に溶けこんでいる場合が少なくないのである。音楽を〈音楽〉として意識するのは,とりわけ抽象的・美的な精神の働きである。
このような抽象的・美的な意識の頂点に位置するのは,おそらく〈絶対音楽〉の概念によって代表される西欧近代の音楽意識であろう。しかし,西欧の〈音楽〉に関する概念にもそれなりの変遷があった。英語のミュージックmusic,ドイツ語のムジークMusik,フランス語のミュジックmusique,イタリア語のムージカmusicaなどの語の共通の語源とされるのは,ギリシア語の〈ムシケmousikē〉であるが,それはそもそも〈ムーサMousa〉(英語でミューズMuse)として知られる女神たちのつかさどる技芸を意味し,その中には狭義の音芸術のほか,朗誦されるものとしての詩の芸術,舞踊など,リズムによって統合される各種の時間芸術が包含されていた。このように包括的な〈音楽〉の概念は,ヨーロッパ中世においては崩壊し,それに代わって思弁的な学として〈自由七科septem artes liberales〉の中に位置づけられる〈音楽〉と演奏行為を前提として実際に鳴り響く実践的な〈音楽〉の概念が生まれたが,後者は中世からルネサンスにかけてのポリフォニー音楽の発展につれて,しだいにリズム理論,音程理論などを内部に含む精緻な音の構築物へと進化した。これらの実践的な音楽とその理論がギリシア古代から一貫して受け継いだのは,音楽的な構築の基礎を合理的に整除できる関係(ラティオratio)と数的比例(プロポルティオproportio)に求める考え方である。合理的に割り切れることと数的比例を重んじるこの精神は,古代中国の音律理論にも見られるところであるが,これをリズム理論,音程とハーモニーの理論,楽節・楽段の構造その他,部分と全体の照応するほとんどすべての関係に及ぼして,精緻な音の構築物を作ろうとするところに西欧的な〈作曲composition〉の特色があった。バロックから古典派にかけての音楽の発展は,それぞれの時代の表現の要求を反映しながら,全体としてより大規模で自律的な音の構築物に向かう歩みであったといえよう。
いわゆる〈絶対音楽〉の概念は,この線上に現れるものである。その絶対性の中には,音楽創造が絵画や彫刻のように模写すべき対象をもたないという意味での〈絶対性〉,作品構成の原理の中に音楽そのものの自律的法則性以外,いっさいの外来的な価値の規範や形成法則が持ち込まれないという意味での〈絶対性〉,創作者の立場が社会的に拘束されない純粋な創造者の自由を享受するという意味での〈絶対性〉,作品が完全な彫琢をへて決定的な姿でそこに存在するという意味での〈絶対性〉など,種々の意味の位相が重なり合っている。しかし,これらの個々の意味での〈絶対性〉が果たして厳密な意味で存在しうるか否かは,重大な疑問であると言わなければならない。むしろ〈絶対音楽〉の概念は,19世紀西欧の思想的産物であり,その時代の音楽の価値規範を観念の世界に投影したものと言うべきであろう。20世紀の音楽は,こうした意味での反省に基づく西欧世界の一部音楽家による音楽の実用性と社会的性格の重視や,非西欧的な音楽文化への関心を特色とすると同時に,その一方で各地域の伝統音楽に重大な影響を及ぼしつつある西欧音楽語法の世界的規模での進出を大きな特色としている。
音楽は,つねに演奏されることによって,その生命を維持する。即興を本旨とする音楽も,口承による音楽も,記譜された作品も,その点に関して言えば同一である。楽譜は,作品を固定する手段であると同時に,実際の演奏に対する覚書,指示書としての役割をもっている。しかし,その指示は,すべてを数量的に規定した電子音楽の作品のような場合は別として,演奏に携わる者の本来的な創造的自由を前提としたものである。たとえ同じ作品を同じ人が演奏しても,その音響像は今日と明日では異なるのが,音楽の本来的な姿である。民謡は歌う人ごとに微妙な差異を見せつつ,歴史的に変貌し推移する。即興を旨とする音楽は,決して同一の形態にとどまることがない。にもかかわらず,演奏に携わる人,聴く人が,そこにある種の客体的な同一性を感じとるのも事実である。そのようにして音楽は,人間性の創造的自由によって支えられ,つねに変容しつつ,その客体的存在と同一性を保つのである。
音楽はまた,音素材による形成作用である。音素材は,一部の具象音楽の場合を除いて自然的な所与として存在するものではなく,人為的に琢磨され(声楽,発声),機械的手段を用いて作り出され(器楽,楽器),選択され(音律,音階),結合される(楽式)。その様相は,歴史的にも地理的にもさまざまな変異を見せ,それを通じて今日の地上の諸民族がもつ,豊かな音楽言語が形成された。
諸芸術の中における音楽は,具象的な表現の対象をもたず,しかも直接に情緒的・知的な反応を呼びさますことに大きな特色がある。この特色は,音楽を諸芸術の中で,とりわけ精神的な芸術として高く位置づける論拠になると同時に,表現の明瞭性を欠くものとして低く位置づける論拠にもなった。哲学者ライプニッツの〈音楽は魂の意識しない数学的計算〉であるという言葉や,古代ギリシアのエートス,中国の礼楽の思想などは,音楽の存在の多面的な性格を,それぞれに反映するものである。また音楽は,すでに述べた日本古代の〈うたまひ〉の概念や,古代ギリシアの〈ムシケ〉の概念に見られるように,〈演ずる〉という行為を通じて,詩,演劇,舞踊などと本来的に結びつき,芸術的な表現のひとつの総合領域を形成することが多い。儀式や祭典における音楽も,同様な性格をもっている。と同時に音楽は,映画音楽や付随音楽,ムード音楽,医療音楽,シグナルとしての音楽など,多様な応用領域をもっている。芸術的な観点からすれば,すべてを通じて問われるのは,精神的な営みとしての創造性の高さと密度であるが,これらの応用領域も無視しがたい存在として広く社会生活の中に浸透しているのが,今日における音楽の状況である。
執筆者:服部 幸三
西洋の音楽
西洋音楽史の特質
ドイツの音楽学者ウィオラWalter Wiora(1906- )は従来の西洋中心の音楽史に反対して世界音楽史を提唱し,人類の音楽を,(1)先史時代,(2)古代と東洋の高度文化,(3)西洋音楽,(4)技術と産業文化の時代,の四つに分けた(《世界音楽史--四つの時代》1961,邦訳1970)。彼によれば,西洋音楽はその中で,中世初期から20世紀初頭にいたる1000年間,それ自身で一つの時代を形成するユニークな存在であり,他の諸地域の音楽と並存する地理的現象ではなく1個の歴史的現象であって,地球上の他のいかなる音楽にも類を見ない独自の性格を備えていると述べている。
西洋音楽の歴史を振り返ると,およそ300年ごとに大きな変化が見られ,同時代の人びともその〈新しさ〉を意識して〈新〉という語をもってその変化を呼んだ。すなわち,1300年ごろの〈アルス・ノバars nove〉,1600年ごろの〈ヌオーベ・ムジケnuove musiche〉,1900年ごろの〈ノイエ・ムジークNeue Musik〉である。1000年ごろに起こった譜表記譜法の発明をこれに加えるならば,300年の周期性はいっそう明らかとなる。しかもこの300年期の中間には,およそ150年の間隔でさらに時代を画する現象を指摘することができる。少なくとも記録のある限り850年ごろといえるポリフォニーの始まり,初期ポリフォニーの最初の成果を示す1150年ごろの聖マルシアル楽派,1450年ごろに起こりルネサンス時代の開始を告げるフランドル楽派,J.S.バッハが没しバロック時代の終りを記す1750年。美術史から借用され音楽史でも一般化している様式概念を以上の時代区分に当てはめるならば,西洋音楽の歴史は,《ハーバード音楽辞典Harvard Dictionary of Music》(1944)にならって,およそ次のように図式化できよう。
850年 ポリフォニ 初期中世
ーの始まり
1000年 譜表記譜法 ロマネスク
の発明
1150年 聖マルシア 初期ゴシック
ル楽派
1300年 〈アルス・ノ 後期ゴシック
バ〉
1450年 フランドル ルネサンス
楽派の台頭
1600年 〈ヌオーベ・ バロック
ムジケ〉
1750年 バッハの死 古典・ロマン派
1900年 〈ノイエ・ム 現代音楽
ジーク〉
西洋音楽史の第1の特質は,以上のような技術や様式の変化を通じて見られる歴史の継続性と発展性であり,単なる過去の伝承にとどまらないその力動的な歴史は西洋音楽に固有な性格を与えている。第2に,西洋音楽は社会の基層文化から養分を吸収しながらも,しだいに自律的な芸術へと発展し,教会その他の社会制度に対する奉仕者の地位から徐々に独立し,個々の作品が作者の個性や独創性を反映しつつ1個の自律的で完結した精神世界を形成する方向へと進んだ。第3の特徴は,音楽のさまざまな側面で行われた合理化の追求である。音楽の理論化は西洋に限らず他の高度文化にも認められるが,西洋音楽では理論と実践が常に補完的関係にあって,教会旋法や調性といった音組織,定量記譜法や拍節リズムといった時間組織,対位法や和声法といった作曲法において,理論的にも実践的にも精緻かつ整合的な体系を作りあげた。音楽という,ある意味では最も非合理的な芸術が,むしろその非合理的な性格ゆえに,他の諸芸術には見られないほどの合理化を推し進めたのである。楽器においては,鍵盤楽器の発達が他の音楽文化に例を見ない西洋文化固有の特徴だが,これも一つには音組織の合理化という要求の産物であり,また一つには,対位法や和声法といういわばテクスチャー(音の織地)の立体化に対応し,また社会的には,これまた西洋文化に固有な芸術音楽の大衆化と相補的な関係にあった。西洋音楽史の第4の,そしておそらく最も基本的な特徴は,合理的な記譜法体系を発達させたところにある。最初は口承の補助として,旋律の動きを大まかに示すにとどまったネウマから出発したが,やがて譜表の導入によって相対的音高を明確に表示し,ポリフォニーの発達に伴って音の持続関係(音価)を示す精細なリズム記譜法を完成し,近代にいたってテンポや強弱など,他の要素まで記譜されるようになった。楽譜の存在はもちろん西洋に限らない。しかし,西洋の楽譜は旋律の上行・下行や諸声部の上下関係などを視覚的に抽象化し,細部のニュアンスはともかく,未知の作品も楽譜から演奏可能なものとするだけの精度を備えている。西洋音楽特有の大規模かつ構成的な諸形式(フーガ,ソナタなど)は,このような記譜法の存在を不可欠の前提として成立したのであり,楽譜によってまた西洋文化は音楽を客観化し,その歴史はすぐれて〈作品の歴史〉となったのである。西洋音楽のグローバルな普及は,単に植民地政策の結果ではない。西洋音楽は他の音楽諸文化ではなく,その力動的な歴史過程の中で,他の文化には見られない固有音楽的(音楽内的)な普遍性を獲得したのである。
古代
音楽を意味する英語musicが,音楽と詩と舞踊の包括的概念であるギリシア語mousikēに由来しているように,古代ギリシアの音楽は西洋の音楽の源であった。叙事詩が作家自身の楽器の伴奏で吟じられた。前8世紀ころのホメロスの作品も朗唱叙事詩であった。前7世紀にはスパルタが音楽の中心となり,アポロンやディオニュソスの祭典にはアウロスやキタラを助奏とした独唱曲が発達し,前6世紀に入るとアテナイでコロスが盛んになった。ギリシア音楽はピュタゴラスの音楽理論やプラトンの音楽美学の面でも以後の西洋音楽に多大の影響を与えた。
→ギリシア音楽
中世
中世の西洋音楽は古代地中海世界の分裂と西ヨーヨッパ世界の成立に深くかかわりあいながら誕生し,キリスト教聖歌,特にローマ・カトリック教会の典礼聖歌であるグレゴリオ聖歌の成立と,元来その聖歌の敷衍・拡張として始まったポリフォニー(多声音楽)の発達を最大の特色としている。初期キリスト教教会は,ユダヤ教の聖歌を母体として各地に独自の聖歌を生んだが,ローマ・カトリック教会の成立とともにそれらが整理統合されていった。しかし,この聖歌の現存するレパートリーはその大部分が8世紀以後にアルプスの北,ガリア,ゲルマン地方で作られたと考えられている。グレゴリオ聖歌はやがてトロプスtropus(進句)やセクエンティアsequentia(続唱)という曲種によっていわば水平的次元での拡張として,ないしはグレゴリオ聖歌の一種の注釈として,同じくアルプスの北でポリフォニーが誕生する。西洋におけるポリフォニーの最古の記録は9世紀の理論書に見られるが,それが最初に開花するのは12世紀のことで,狭義の西欧世界の成立と特に修道院文化の隆盛と密接な関係にあった。中部フランスのリモージュ近郊にある聖マルシアル修道院は,1150年ころ,なかでも特に重要な中心であった(聖マルシアル楽派)。そのポリフォニーはオルガヌムorganumと呼ばれ,下声に長く引き伸ばされたグレゴリオ聖歌を置き,その上に自由なリズムで細かく動く上声を配した2声の楽曲であった。12世紀末からポリフォニーの中心地は北に移動し,13世紀末までパリのノートル・ダム大聖堂が特に重要な位置を占めた(ノートル・ダム楽派,パリ楽派)。ここでは楽長レオナンLéoninとペロタンPérotinを中心に2~4声のオルガヌムやモテットが発達した。それらはグレゴリオ聖歌という土台の上に築かれた壮大な音の構築物で,ゴシック様式の大聖堂にも似た趣を備えている。このようなポリフォニーの発展は合理的な記譜法の存在と不可分の関係にあり,11世紀初頭に譜線を用いた譜表記譜法によって相対的な音高が正確に表示されるようになったのち,六つのリズム・パターンを組み合わせるノートル・ダム楽派のモード記譜法を経て,13世紀後半には個々の音の長短を明示する定量記譜法も体系化された。教皇権と皇帝権という二つの中心をもっていた西欧社会は,14世紀に入ると教皇権の失墜によって大きく変化し,世俗権力の増大や商業都市の繁栄を背景として音楽にも明らかな世俗化の傾向が現れてくる。特に12~13世紀にフランスを中心に栄えた騎士道的な吟遊詩人トルバドゥール,トルベールの単旋律歌曲を母体として,愛や自然を歌った世俗的な多声歌曲バラードballade,ロンドーrondeau,ビルレーvirelaiなどが開花,宗教音楽のモテットにも世俗的要素の侵入が著しかった。スコラ的な神学の影響で13世紀までは3拍子が三位一体の象徴として〈完全な拍子〉と呼ばれたが,14世紀には〈不完全な〉2拍子も自由に用いられるようになった。フランスのG.deマショーやイタリアのF.ランディーニに代表される14世紀の音楽は,13世紀の〈アルス・アンティクアars antiqua(古い芸術)〉に対して〈アルス・ノバars nova(新しい芸術)〉と呼ばれた。14世紀に芽生えたルネサンス的ないぶきは15世紀前半になってさらに強まる。ブルゴーニュ公国の宮廷やその広大な領土内で活躍した一群の作曲家をブルゴーニュ楽派というが,その代表者G.デュファイとG.バンショアは,J.ダンスタブルを中心とするイギリス音楽から大きな刺激を受け,ミサ曲やフランス語のシャンソンの分野で豊かな成果を生んだ。特に,古くからイギリス人が好んだ3度や6度の音程を採り入れ,その後西洋音楽の基礎となる3度和声を確立したことが重要である。音楽史における15世紀前半は〈中世の秋〉(J.ホイジンガの言葉)であると同時に,ルネサンス時代の夜明けでもあった。
ルネサンス時代
古典古代文化の復活という意味に限るなら,音楽の歴史にルネサンス時代は存在しない。しかし諸声部間の均衡に基づく耳に快い同質的な響き,部分と全体との完全な調和という美の理想,作曲家の個性の発現,近代的・合理的思考は,15~16世紀の音楽をその前後の時代から明確に区別しているといえよう。前述のとおり,15世紀前半のブルゴーニュ楽派は中世的要素と近世的要素を併せもつ過渡期であるが,3度和声の新しい響きに注目して,これを初期ルネサンスに分類することも多い。15世紀後半に入ると,ブルゴーニュ公国の属領であったフランドル地方の音楽がヨーロッパ各地の宮廷や教会で重要な地位を占め,16世紀後半にいたるまで,一般にフランドル楽派と呼ばれる全ヨーロッパ的な様式を確立する(ドイツでは,ブルゴーニュ楽派とフランドル楽派を合わせてネーデルラント楽派と呼ぶことが多い)。初期のJ.オケヘム(オケゲム)とJ.オブレヒトから,最盛期の代表者ジョスカン・デ・プレをへて後期のO.deラッスス(ラッソ)にいたるこの楽派の多彩な展開の中で,おもにミサ曲やモテットなどの宗教音楽を通じて,その後西洋和声の中心となる4声書法,やがてバッハのフーガに結晶する通模倣様式,すなわち同一の楽想をすべての声部で順次模倣する対位法様式(対位法)が確立され,高度な技法によって形式の完璧な調和が達成されると同時に,特にジョスカン・デ・プレやラッススの音楽には形式の均整美に加えて豊かな人間感情の表現が認められる。この時代はまた各地で国民国家の成立が見られ,音楽においても16世紀中ごろから,フランドル楽派の影響を受けつつ,いくつかの国民様式が現れ始める。世俗音楽の分野ではフランスでパリを中心にシャンソンが栄え,イタリアではマドリガーレ(マドリガル)が人気の中心になる。16世紀末のL.マレンツィオやC.ジェズアルドのマドリガーレは特に大胆な半音階和声を駆使して強烈な感情表現を行い,世紀末的頽廃の香りさえただよわせ始める。16世紀後半のイタリアではまた,ローマのG.P.パレストリーナが教皇庁礼拝堂を中心に清澄な響きのうちでカトリック教会音楽の理想像を実現する一方,ベネチアのサン・マルコ大聖堂では,アンドレアとジョバンニの両ガブリエリを中心に二重合唱の技法や声と楽器の協奏様式が発達して,来たるべきバロック時代を準備する。16世紀の音楽に著しい多様化の傾向は,宗教改革によっても助長された。イギリスでは1534年の英国国教会成立に伴い,ヘンリー8世からエリザベス1世の時代にかけて,サービスserviceやアンセムanthemといったイギリス固有の教会音楽が生まれ,ドイツでもルターの宗教改革(1517)以来,プロテスタント教会固有の賛美歌としてコラールが作られ,やがて18世紀のJ.S.バッハにいたるまで,ドイツ教会音楽にゆるぎない土台を提供することになる。カトリック圏では,前記のイタリアと並んでスペインが,ローマ楽派の影響を強く受けながらも独自の表現を確立する。16世紀は器楽の台頭によっても特徴づけられる。器楽はおもに声楽曲の編曲から出発したが,リュートや鍵盤楽器,またビオルの合奏などにおいてしだいに器楽特有の技法を発展させた。16世紀は〈踊る世紀〉といわれるほど舞踊が盛んで,この分野からも器楽特有の舞曲が発達した。この時代に顕著な様式の多様化と相互浸透,そして音楽の社会的普及にとっては,1501年に始まる楽譜印刷の果たした役割も忘れることができない。
バロック時代
1600年前後は西洋音楽史の中で最も大きな転換期であった。中世音楽とルネサンス音楽は社会の変化やそれを背景とする思考方法の変化に伴って,それぞれ異なった様相を呈しているが,純音楽的にはポリフォニーの発展という一つの連続する糸によってたどることができる。それに対してバロック音楽は,ルネサンス時代に完成したポリフォニーの形態と理念を意図的に放棄することから始まった。ルネサンスのポリフォニーが諸声部の対等性に基づいて1個の均質な音響空間を形成したのに対して,バロック音楽では音響空間が上声と下声(通奏低音)に分裂し,緊張をはらんだこの双極構造の中で内声部は一般に副次的な位置を占めるにすぎない。16世紀末,フィレンツェのカメラータ(文学者,音楽家のグループ)によって創始されたモノディは通奏低音に支えられた独唱のスタイルで,歌詞の抑揚や情緒を,あたかも語りのように表現しようとした。初期バロックの天才C.モンテベルディが語ったように,今や〈言葉が音楽の主人〉となり,言葉の内容に即した表現を実現するためには,マドリガーレのようなポリフォニー音楽においても,ルネサンス・ポリフォニーの規則に縛られない破格な進行や和声が許されるようになった。モノディの原理はオペラを生み,オラトリオやカンタータの中でも適用された。オペラはモンテベルディから18世紀のナポリ楽派までイタリアを中心に発達,宮廷芸術から市民芸術へと変貌する中で類型化されたが,フランスもリュリからラモーまで,バレエや古典劇の伝統を踏まえた独自のオペラを発達させた。バロック音楽の第2の原理は協奏原理である。これは異質なものの対比を強調するもので,16世紀末のベネチア楽派から芽生え,イタリアだけでなく,シュッツをはじめとするドイツの教会音楽でも用いられた。コレリやビバルディの手で完成された器楽の協奏曲は,この原理を明快な形式へ結晶させたもので,バロック時代の最も重要な器楽形式になった。声楽においても器楽においても,バロック時代にはそれぞれの表現媒体に固有な語法(イディオム)が確立し,それに伴って演奏技巧の飛躍的な進歩が見られたが,18世紀前半のバロック後期になると,媒体間でイディオムの交換が行われ,各ジャンルの表現力が一段と豊かになった。演奏技巧の発達はバロック音楽の即興性とも深く関係している。作曲家が書く楽譜は作品の骨格にとどまることが多く,不動の土台となる通奏低音を除いて,他の声部の奏法に関しては演奏家に大幅な自由が許されていた。バロック時代には声楽でオペラ,オラトリオ,カンタータ,器楽で協奏曲,ソナタなどの多くの新しいジャンルが生まれると同時に,イタリア,フランス,ドイツを中心にして明確な国民様式が形成され,さまざまな技法と様式は18世紀前半にJ.S.バッハの中で融合する。ルネサンスからバロックにかけて一見伝統の断絶があるかに見えるが,ポリフォニーの伝統はモノディ様式や協奏様式と並んで特にドイツで生きつづけ,バッハのフーガに代表されるような和声を前提とする新しい対位法様式を生んだ。
古典・ロマン派
響きの同質性と均整美を追求したルネサンス音楽と,異質な響きの対比や破格な表現に新たな可能性を求めたバロック音楽は,鋭く対立している。そして18世紀中ごろから,歴史の振子は再び古典的均整と調和の方に振り戻される。音楽的には通奏低音の廃止と最上声を重視して他声部がそれを和声的に伴奏するホモフォニー様式の成立,交響曲,弦楽四重奏曲,ソナタなどその様式を基盤とする近代的な諸形式の誕生,そして社会的には絶対主義体制や教会的秩序の解体と,近代市民社会の成立に伴う音楽生活の変質,またそれと深くかかわりあう個性的表現の重視などを,古典派音楽の特徴と見ることができよう。音楽史における古典派という概念はハイドン,モーツァルト,ベートーベンによって代表されるウィーン古典派とほとんど同義に用いられるが,この古典派は突如出現したわけではなく,すでに18世紀前半から徐々に芽生えつつ,イタリア,フランス,ドイツで,前古典派と総称される一群の作曲家たちによって準備されたのである。特に重要なのはG.B.サンマルティーニを中心とするミラノ,エマヌエル・バッハに代表されるベルリン,J.シュターミツをはじめとするマンハイム,ハイドン以前のウィーンの各楽派である。このような前提の上に成立したウィーン古典派は,バロック時代に確立した長・短調の調性を受け継いでそれを形式の構成原理へと高め,交響曲,協奏曲,室内楽,ソナタなどのおもに第1楽章において,主題の指示・展開・再現という図式のソナタ形式を完成した。特に,主題を動機に解体して,それを有機的に発展させる主題労作の手法は,ハイドンによって創出されたのちベートーベンにおいて頂点に達し,楽曲構成の最も重要な手法の一つになった。古典派の音楽は形式の均整を通じて普遍的な表現を追求したが,ベートーベンの後期になると個性的な表現が内部から形式の均整を突き破り,ロマン派音楽への移行を示すようになる。いわゆるロマン派は,個人的感情の表現を重視し,F.シューベルト以来のドイツ歌曲,シューベルト,R.シューマン,ショパンなどに見られる抒情的オペラやR.ワーグナーの楽劇など,確かに多くの新しい音楽を生み,ロシアや東欧・北欧などに国民楽派を育て,新しい表現のために調性や和声を拡大し,音楽の色彩的な効果を発展させた。しかし,そのような新たな発展にもかかわらず,古典派とロマン派のあいだには,バロックと古典派のあいだに見られるような作曲原理の本質的な変化は存在しない。ドイツの音楽史家ブルーメFriedrich Blume(1893-1975)も主張するように,18世紀中ごろから19世紀末までの150年間は,西洋音楽史全体から見れば〈古典・ロマン派〉と呼ぶべき一つのまとまった時代を形成しているのである。
現代の音楽
しかし早くも19世紀の末から,この古典・ロマン派の伝統を解体させる傾向が芽生えつつあった。最も象徴的なのはバロック時代以来西洋音楽の基盤であった調性が崩壊し始めたことであろう。それはR.ワーグナーの楽劇における半音階の多用によって,また一方ではドイツ・ロマン派の過度な感情表出に反対して外界の印象を直観的に音で形象化しようとしたドビュッシーが,教会旋法や全音音階を導入し,和音の機能的関連を否定して個々の和音の独立的な色彩価値を重要視したことによって生じた。20世紀にはA.シェーンベルクが調性を全面的に否定して無調音楽を書き,それを組織化して12音の音列技法を創始した。弟子のA.ウェーベルンがそれをさらに徹底させたのち,第2次世界大戦後は音高以外の要素もセリー化するセリー音楽が生まれた。一方,ストラビンスキーは原始的なリズムによって激しい衝撃を与え,バルトークなど民俗音楽の要素を採り入れて新しい表現を求めた作曲家もある。また,現実音をモンタージュするミュジック・コンクレートや電子音楽,またJ.ケージをはじめとする〈偶然性の音楽〉も登場して,楽譜として構成された西洋音楽の伝統的な作品概念は否定され,〈作品の歴史〉としての西洋音楽史は一つの終局を迎えるのである。
→楽譜 →現代音楽 →古典派音楽 →中世音楽 →バロック音楽 →ルネサンス音楽 →ロマン派音楽
執筆者:角倉 一朗
東洋の音楽
ここではアジア大陸を中心に継起した音楽文化の潮流のおもなものを通時的に概観する。〈東洋音楽〉という概念は本来ないのであって,これは〈西洋音楽〉に対比させて漠然と指すときにのみ生ずる。
しかし東洋の諸民族の音楽を西洋のそれと比べてみたとき,西洋ではまったく異質であっても東洋ではおおむね共通して見られる要素をいくつか挙げることができる。(1)単旋律的であること。(2)さまざまな微分音程が旋律中に現れること(西アジアの旋法,東南アジアの音階など)。(3)声楽が多くのジャンルの中心となっており,〈歌い物〉や〈語り物〉の様式が細かく分化・発達している(中国の説唱,日本の浄瑠璃など)。(4)小ぶしなど装飾的な節回しが多用される。(5)個性的な発声法・音色の尊重。喉を使ったいろいろな発声技巧や独特の声柄の多用。(6)リズム上の細かい技法。無拍のリズム。(7)舞踊や演劇など身体演技を伴うジャンルや,人形芝居,影絵芝居と結びついた音楽が多い。(8)さらに宗教儀式との結びつきが全般的に濃厚で,音楽が重要な社会的機能を果たしている場合が少なくない。
東洋の音楽を概観するとき,これを大きく五つの音楽文化圏に分けて見ることができる。(1)東アジア,(2)西アジア,(3)南アジア,(4)東南アジア,(5)オセアニアであるが,この五つの音楽文化の流れは相互に孤立していたわけではなく,歴史上のある時点で直接・間接の交流をもっていたことはいうまでもない。ここでは個々の民族の音楽の歴史や音楽構造の詳細はそれぞれの独立項目に譲り,音楽文化の歴史的な流れの接点,相互の影響などに焦点を置いて大観するにとどめる。
東アジア
中国とその直接の影響下にあって独自の音楽文化を開花させた朝鮮半島と日本列島がその代表的なもの。またモンゴルやチベット,そしてベトナムやミャンマーなど中国音楽の影響圏に入った周辺地域の音楽をも含む。
→チベット[音楽] →中央アジア[音楽] →モンゴル音楽
この地域の音楽を特徴づける〈中国的〉なものの筆頭は,五声と十二律の概念に代表される古代中国の音楽理論と,その背景にある五行説に基づく世界観,および八音に代表される儒教の祭祀音楽のための楽器とその合奏である雅楽である。漢民族は古く殷代(前17~前10世紀ころ)に郊祀のための歌舞を中心とする独特の音楽をもっていた。周・漢代(前10~後3世紀)に礼楽思想が確立し,鐘,磬,塤(けん),鼓,琴,柷(しゆく),笙,篪(ち)など八音の合奏が天地の和を象徴するものと考えられた(楽者天地之和也)。また孔子が理想とした楽は舞を伴う(楽則韶舞)。そこで文武八佾(はちいつ)の舞を奉納し郊祀廟祭の礼楽とした。この雅楽の伝統は今日韓国,台湾,ベトナムにわずかながら伝承されている。しかし日本にはこの種の雅楽は伝来しなかった。
前2世紀ころから中国に西域楽とその楽器(胡笳,胡笛,琵琶,箜篌など)や百戯などが伝来しはじめ,それまでに形成された漢民族固有の楽舞に外来文化の要素が付加される。後2世紀ころには天竺楽や亀茲楽が導入され,以後,南北朝,隋,唐と時代が下るにつれて北狄,扶南,林邑,高麗,百済,新羅などの楽舞が輸入された。こうして6~8世紀の中国の宮廷では実に国際的な音楽が享受された。そこでは胡楽と俗楽から代表的なものが選ばれて七部伎が制定され,公式の宴饗楽として用いられた。これが後に九部伎に,そして十部伎に拡大されるが,その一部が奈良・平安期の日本へ伝来し,日本の雅楽となった。なお朝鮮半島にも宴饗楽が輸入され,〈タンアク〉(唐楽)の名で今日も行われている。
→雅楽
宋代になると民間の散楽や説唱などを母体として雑劇が生まれた。中国独特の戯曲音楽の成立で,これが俗楽の中心的な存在となり,後の元代の雑劇(元曲),明代の崑曲,そして清代の京劇へと展開した。これは前の時代の外来音楽の盛んな摂取・消化と対照的な動きであり,ここで中国の音楽は新たな民族様式形成の時代に入る。日本でも2~3世紀遅れて並行現象が見られ,雅楽や声明など大陸音楽の輸入と消化の時期を経て,日本独自の平曲や能楽そして歌舞伎など新しい民族様式を生み出す時代が後続した。朝鮮半島でも高麗朝の末期に山台戯(仮面劇)が発達し,李朝になると民間音楽の活動がますます高まり,李朝後期にはパンソリが興り,後にそこから唱劇と呼ばれる一種の歌劇が生まれている。
→中国演劇 →中国音楽 →朝鮮演劇 →朝鮮音楽 →日本音楽
新しい楽器に焦点を当ててみると,元代に胡琴と三弦が出現した。モンゴル経由で中国に伝来した中央アジアの楽器であるが,後世の民間楽器の代表的なものになった。三弦は14世紀末に琉球に伝来し,さらに16世紀中葉に日本本土に伝えられ,近世日本音楽の最も重要な楽器となった。
西アジア
古代オリエント文明の発祥地メソポタミアとエジプトを含むこの地域の音楽の歴史はきわめて古い。イスラム教徒のそして遊牧民の音楽文化が全域を覆っている。今日伝承される音楽のおもな潮流はイラン(ペルシア),アラブ世界,トルコの三つに大別できるが,アラブ世界はさらに東方アラブ世界(西アジアのアラブ諸国とエジプト)と,西方アラブ世界(マグレブ)の音楽に細分される。ほかに非イスラム教徒の音楽文化として,ユダヤ教徒(イスラエル),キリスト教徒(シリア,ギリシア,アルメニア,コプトなどの東方教会)やゾロアスター教徒の音楽も忘れることはできない。
→エジプト音楽 →コプト音楽 →ユダヤ音楽
イランは西アジア音楽文化圏の中では最も古い歴史を誇る。特にササン朝(3~7世紀)の宮廷では音楽が重用され,楽器の種類の豊富さと旋法理論の精緻さでは群を抜いていた。7世紀中葉アラブに征服されイスラム化して,アラブ文化の強い影響下に入ったが,こと音楽に関しては征服者にその後も影響を与えつづけた。アラビア語の楽語や楽器名にはペルシア語に由来するものが多い。
→イラン音楽
アラブの音楽はアッバース朝(750-1258)の都バグダードで開花する。初期のイスラムの学者の中には歌舞音曲に対して否定的な立場を採る者もいたが,音楽を数学の一分科として科学的研究の対象として扱うことは許され,キンディー,ファーラービー,イブン・シーナーのごとき哲学者は音楽に関する理論的な著述を残した。この伝統は9世紀以後のもので,本来ギリシア学の摂取消化の結果である。西アジアの音楽史上最も重要な著述を残した理論家はサフィー・アッディーンで,彼が提唱した17不等分律音階は,後世のイラン,アラブ,トルコの音楽理論の基礎となった。さまざまな中立音程の理論的な位置づけである。
マグレブのアラブ音楽は9世紀前半にコルドバで活躍した音楽家ジルヤーブを開祖とする。彼はバグダードで学びアッバース朝カリフのハールーン・アッラシードの宮廷に仕えた優れた音楽家であった。したがって今日北アフリカで伝承されている古典音楽(アンダルス音楽)の萌芽は9世紀初めのバグダードの宮廷音楽にさかのぼる。アラブの楽器はヨーロッパへも流入した。
→アラブ音楽
11世紀にアナトリアに進出したセルジューク・トルコの宮廷では初めアラブ・ペルシア様式の音楽が採用された。13世紀に創立されたイスラム神秘主義のメウレウィー教団はその典礼にこの様式の音楽と旋回(舞踊)を採用した。ここで発展した音楽が後にトルコの古典音楽となり,以後,オスマン帝国を通じて洗練され今日に伝えられている。16~19世紀にオスマン帝国の音楽家はマカームとウスールの体系を極限にまで発展させた。18世紀のヨーロッパで流行した〈トルコ行進曲〉はオスマンの軍楽隊の響きを模したものにほかならない。
→トルコ音楽
南アジア
インド亜大陸とヒマラヤ南縁地方およびスリランカ(セイロン島)を包含するこの地域は複雑な民族構成と言語をもち,したがって多彩な民俗音楽をもつが,この地域の音楽を特徴づけているのはヒンドゥー文化の色彩である。ただし一歩近づいて耳を傾けると,南と北とでは響きが異なる。これは13世紀以後イスラム文化の影響を強く受けた北インドと,その影響が少なく,古来の〈インド的〉な特徴を比較的純粋に保持した南インドの相違である。
最古のインド音楽は前15世紀ころのバラモン教聖典ベーダにさかのぼる。《サーマ・ベーダ》の朗唱(サーマン)は今日まで連綿と口頭伝承されているが,インド音楽の源泉の一つである。前数世紀ころから徐々に形づくられた《ラーマーヤナ》と《マハーバーラタ》の二大叙事詩には当時の音楽に関する記述が含まれ,音楽用語や楽器名も記録されているので,二千数百年前のインドで既に高度に発達した音楽が享受されていたことを知る。そしてこの二大叙事詩の口誦は舞踊や演技をも伴って,単に南アジアのみならず,東南アジアへも伝播した。釈迦に始まる仏教はアショーカ王の時代(前3世紀)にほぼ全インドに広まり,仏教文化は以後数世紀の間栄えたが,音楽が重要な役割をもっていたことは仏教遺跡に残された図像やパーリ語聖典に記録されている数多くの楽器名から想像に難くない。その一部である声明は中国を経由して日本に伝えられ,今日まで伝承されている。
インドの音楽理論は独特なもので,最古の楽劇論書《ナーティヤ・シャーストラ》には7声,22律の理論を含む詳細な楽理の体系が展開されている。13世紀初頭に著された楽書《サンギータ・ラトナーカラ》はそれ以前のインド音楽の大要を記した貴重な文献である。なぜなら,ちょうど同じ頃デリーにイスラム王朝が成立し,以後北インドの音楽は西アジアの影響を受けて一変するからである。インド音楽のイスラム化に特に力があり,ヒンドゥスターニー音楽の基礎を築いたのは有名なペルシア詩人で音楽家のアミール・ホスローとされている。彼は西アジアのマカームを導入し新しいラーガを編み出し,今日の北インドの古典音楽の代表的な様式キヤールを創り出し,またイスラム賛歌カッワーリーを創始したと伝えられる。
14世紀の中葉に既に南北の音楽様式の違いが指摘されているが,今日の南インドのカルナータカ音楽の基礎は15~16世紀のビジャヤナガル王国で確立され,17世紀後半以後その中心地はタンジョールに移った。この宮廷音楽の伝統はマドラス(現,チェンナイ)を中心に伝承されている。
北インドでは16世紀中葉ムガル帝国のアクバル帝の宮廷音楽家ターン・センがヒンドゥーとイスラムの両文化の伝統を融合してヒンドゥスターニー音楽を大成した。彼の流儀はセーニャ・グラーナの名で今日も伝承される。
→インド音楽 →仏教音楽
東南アジア
この地域の音楽の特徴として第1に青銅のゴングの響き,とりわけ独特の音階に調律された大小のゴングを含む旋律打楽器を主体とした野外の合奏が挙げられる。インドネシアのジャワやバリのガムランをはじめ,フィリピン(ミンダナオ島)やマレーシア(北ボルネオ)のクリンタン,タイのピーパート合奏,カンボジアのピン・パート合奏,ミャンマーのサイン・ワイン合奏などはこのゴング・チャイムの音楽文化圏の代表的なものである。インドシナ半島やジャワ島には前3~前2世紀ころから銅鼓が広く分布しており,祭器として用いられていた。東南アジアのゴング・チャイム音楽もその起源を古代の祭祀にもち,今日もなお儀礼と密接に結びついている。古代日本の銅鐸や祇園囃子の鉦も広義のゴング・チャイム文化圏に含めることが可能である。
東南アジアは歴史的にインドと中国の両文化から影響を受けてきた。唐楽にその名をとどめる扶南や林邑(林邑楽)は後1~3世紀ころそれぞれクメール族とチャム族によって今のカンボジアとベトナム中部に建てられた国だが,いずれもインド文化を採り入れており,ジャワのボロブドゥール遺跡(8~9世紀)やカンボジアのアンコール・ワット(12世紀)寺院にこれを物語る浮彫が残されている。今日伝承されている東南アジアの舞踊劇や影絵芝居にも《ラーマーヤナ》を扱ったものは非常に多い。タイやカンボジアのラコーン,ミャンマーのザト・チー,ジャワやバリのワヤンやワヤン・オラン,マレーシアのワヤン・シャムはその数例にすぎない。東南アジアの音楽文化では,隣接する民族が互いの文化を採り入れて影響し合っている点も注目される。14世紀タイのアユタヤ朝の音楽は12~13世紀のアンコールのそれを取り込んだものである。逆に18世紀末以後のカンボジアの音楽はタイの音楽に負っている。ミャンマーの音楽も古代においてはインドと中国の影響を強く受けたが,19世紀にはタイの楽器を採り入れた。
→インドネシア[音楽]
イスラムが東南アジアの音楽文化に与えた影響も少なくない。14世紀後半にマラッカが,15世紀後半にはジャワがそれぞれイスラム化された。イスラム教徒の典型的な音楽様式にマレーシアのノーバト合奏,ローダト(預言者ムハンマドの賛歌),ジクル,そしてジャワのララス・マディヨが数えられるが,いずれも現地化したものである。
→イスラム音楽
キリスト教は16世紀前半に東南アジアに到来し,宣教師らがヨーロッパ音楽をもたらしたが,フィリピンを除いては20世紀に至るまで洋楽はここで根を下ろさなかった。300余年にわたるスペイン支配の結果(そして人口の8割以上がカトリック教徒),フィリピンでは洋楽が古典から民謡(特にスペイン系の)そしてジャズやポピュラーに至るまで浸透している。しかしこのことは古来の土俗的な要素を保った民謡や民俗楽器,周縁の少数民族の歌舞の不在を意味しない。
→フィリピン[音楽]
オセアニア
この地域は17~19世紀にヨーロッパ先進諸国の植民地となり,キリスト教と西洋音楽の洗礼を受けるにいたった。したがって今日のオセアニアの音楽は少なからず変容を示し,伝統的な歌舞のみならず,キリスト教の賛美歌,西洋風コーラスとハワイアン・ミュージック,そしてロック・バンドから日本の歌謡曲まで含む。だが16世紀にヨーロッパ人に発見されるまではほとんど新石器時代の文化に属し,無文字社会であった。今日なお未踏に近い地域も少なくなく,音楽が社会生活のさまざまな側面で機能的に用いられている。歌(叙事詩)が文字に代わって部族の歴史や家系の記録の手段として歌われるのはその一例である。ニュージーランドのマオリの歌パテレは正確に記憶され演唱されることが何よりも重視され,音楽家の訓練と美意識とはもっぱらこの記録の正確性に奉仕する。
→オセアニア[音楽]
音楽と諸民族
言語と同じく,音楽をもたぬ人は存在しない。音楽することは地球上のすべての民族に共通して見られる行動であるが,その形態や内容は実にさまざまである。そしてある民謡の一節を聞いて直ちにそれがどの民族の音楽に属するか判断できるほどに,音楽はその作り手(担い手)の個性ないし民族性をその響きの中にもっているのである。また同じ民族が時代や地域ないし社会を異にすることによって,いくつかの響きの異なる音楽様式を創り出すことも少なくない。それぞれの音楽様式はそれを生み出した人間集団の生活様式や美的価値体系を端的に反映しており,またそれらに束縛されているので,その文化的背景や音の意味を理解することなしに異文化の音楽のメッセージを正しく受け止めて楽しむことは難しい。したがって,一つの様式の音楽が簡単に〈世界の共通語〉にはなり得ないのである。
また一方,ある音楽様式の表現技術やそれを感じとる美意識は,後天的に身につけるものである。日本人がヨーロッパの音楽様式を学び取り,その語法を使い演奏や作曲をするのと同様に,欧米人が邦楽や東南アジアの音楽を演奏することも不可能ではない。
地球上のさまざまな音楽ないし,音が主要な要素を成す芸能は,いくつもの角度から光を当てることによって,その本質の普遍的な側面とそれぞれの民族性の表れ方の違いを見ることができる。例えば,音楽の概念ないし定義,音楽のしくみ,演奏形態,楽器の種類や扱い方,社会における音楽の用途と機能,音楽家(専門家と素人),伝承のしかた,音楽以外の芸能との関連などである。
→民族音楽 →民俗芸能
音の高低,長短を組み合わせて旋律やリズムを作り,音型の反復によって形式をさまざまにくふうすることは,どの民族にも共通しており,これは人類に普遍的な音楽行動の一側面であるといえる。だが,何をもって一つの独立した歌ないし楽曲と認識するか,というようなことは民族によって,また音楽のジャンルによって千差万別である。当該の文化の中では厳然と区別されているいくつかの歌が,文化を異にするものの耳にはまったく同様に響くという例は多い。また人々が一堂に会していっしょに歌う場合を例に挙げてみると,民族によっては,皆が常に声を合わせて,同じ節,同じ歌詞を同時に歌うとは限らない。原則としてユニゾンで一糸乱れずに歌うのが理想とされているのは,日本人や北米のインディアンなどだが,南米のインディオやスリランカのベッダ族は一人一人がわれわれには互いに無関係に聞こえる旋律を同時に歌う。また意図的に異なる旋律を同時に歌う方法も民族によってさまざまであり,二つの声部が平行4度で歌ったり(ヨーロッパ中世),一つの声部が低音を持続させてドローンを響かせたり(南アジア),二つ以上の声部が種々の和声を響かせることを意図した歌い方(ヨーロッパ,アフロ・アメリカ)などがあり,さらに,いくつかの声部がぶつかりくいちがうような音型を継続的に歌うことによって,全体として独特な音響とリズム型が現れるホケトゥスhoketus(ある旋律を歌詞に関係なく休符をはさんで短い断片にする)風な多声性(アフリカのピグミー,グルジア,インドネシアのバリ島)などが挙げられる。
さらに演奏の形態を別の角度から観察すると,1人ないし一団の音楽家がステージの上で演奏し,聴衆がこれを受動的に静粛に聴くという形(近代ヨーロッパ,日本)と,逆に音作りの場にいる人々がすべて積極的に演奏に参加し,弾き手と聴き手とが厳然と区別されない形(アフリカなど)とがある。また合奏(合唱)の場合を例にとると,1人の指揮者によってグループ全体が統率される形(オーケストラ)と,強力なリーダーをもたず,全員が没個性的に共同作業をしながら,バランスのとれた響きを作り上げていく形(インドネシアのガムラン)とが存在し,この両者の中間がさまざまなレベルで見られる。このように音楽の行動,音響のしくみと社会行動の規範,文化の類型とは深くかかわり合っているのである。
また各民族の音楽文化は環境とも深い関係をもつ。とりわけ,楽器の種類や素材はそれぞれのおかれた自然環境における物質文化をよく反映している。例えば,遊牧文化における羊皮(太鼓,バッグパイプ),羊腸弦(弦楽器の発音源,フレット),角(撥,管楽器の歌口),馬の尾毛(弓)や,竹の群生地における笛,竹琴,竹の共鳴胴,体鳴楽器(四つ竹,竹鼓,鳴子)など,そして絹文化における絹弦など,枚挙にいとまがない。このように人は身近な自然環境から楽器の材料を得て,その音色を素材に音楽を作り,また逆にその音のイメージにふさわしい楽器を作り出したり新たな材料をくふうしたりしてきた。ある種の発声法や音色に対する好みもこれと無関係ではない。インドから東南アジアにかけて特徴的な鼻にかかった声柄の偏好,地中海沿岸地方から西アジア一帯に見られる喉をつめた発声の傾向,ヨーロッパとアフリカの一部で見られるヨーデルの多用はその一例である。また楽器の音色や音質に関しても,〈さわり〉や共鳴弦のくふう(または近年の電気的なエコーをかける)をして,より豊かな音への欲求,高音域に対する偏好(東アジア),低音域に対する偏好(チベットや南米のインディオ),大きな音量に対する偏好(アフリカ,アフロ・アメリカ,南ヨーロッパ),ソフトな音に対する偏好(オセアニア,南米のインディオ)が指摘され,これらの特徴的な音楽様式の地理的な分布は,過去の民族移動のおもだった道筋と,文化伝播の歴史とをある程度まで後づけている。と同時に,音楽は固定・不変のものではなくそれぞれの民族の社会構造を反映して作り変えられ,また他民族の音楽を借用して採り入れ,これを時間をかけて固有の様式に変容させる,動的なものであることも忘れることができない。
執筆者:柘植 元一
音楽と社会
音楽は,それ自体で完結する秩序ある形成体の側面をもつと同時に,社会の中で生産・享受され,社会の中で一定の明確な機能を果たしている。古代から現代までの各民族の音楽の歴史が明らかに示しているように,音楽は,呪術,労働,宗教,舞踊,儀式……などのために生産・享受されてきた。西洋の19世紀の〈絶対音楽〉の理念は,たしかに社会的機能からの自由を求め,音楽作品の自律性と完結性を強調したが,しかしその理念の成立根拠は,〈音楽とは何か〉の章で論じられているように,きわめて脆弱なものであった。音楽学者のエッゲブレヒトH.H.Eggebrecht(1919- )は,その著《音楽的思考Musikalisches Denken》(1977)で,〈自律音楽〉と〈機能音楽〉という区分法を提唱し,〈絶対音楽〉に見られるような作品中心の芸術音楽を〈自律音楽〉,世俗音楽,舞踏音楽,労働歌,娯楽音楽,ポピュラー音楽などを〈機能音楽〉に分類している。エッゲブレヒトの論考で詳述されているように,明確な機能をもたない〈自律音楽〉の考え方は,時代的にも地域的にもひじょうに限定されており,世界の民族の音楽のあり方を考えれば,〈機能音楽〉の方がむしろ一般的といってもよいだろう。
音楽と社会は密接な関連があるが,音楽文化と社会構造の関連は,複雑に入り組んでいて,その相互の関連を解き明かすことはかなり困難な作業であり,その解明のためには,文化と社会のあり方自体を考察しなければならない。社会学者のルイスG.H.Lewisは,雑誌《Sociology of Popular Culture》(1978)の中で,社会構造と支配的な文化パターンを図の左のように分類しているが,この図式を音楽にあてはめて考えれば(図の右),次のようなことが指摘できる。伝統的なゲマインシャフトにおいては,一つのフォーク・カルチャーが支配的であり,そこでは,作曲家と演奏家と聴衆が一体となって一つの音楽を共有している。しかし前工業化社会においては,共有の基層の文化が分裂しはじめ,エリート・カルチャーが出現し,作曲家と演奏家と聴衆の形成する幸福な共同体は崩壊する。工業化社会においては,大衆の出現とともに明確な三角形の社会階層が形成され,それとともに,音楽文化においても,社会の基層の人々の支える大衆音楽からエリートのための高度な芸術音楽までのヒエラルヒーが形成される。音楽作品という理念,体系化された記譜法,演奏会制度などによって,作曲家,演奏家,聴衆の区分はいっそう明確なものになり,芸術音楽の作曲家と一般的な聴衆の間の距離はしだいに大きくなっていく。20世紀前半の西洋の芸術音楽のおかれた状況は,図のcの工業化社会のパターンにおける音楽のあり方を示している。ドビュッシーは,自分の唯一の音楽評論集に《反愛好家クロシュ(8分音符)氏Monsieur Croche antidilettante》というタイトルをつけて,音楽的なディレッタントではなくエリートのために創作することを明示した。またシェーンベルクは,弟子のベルクとウェーベルンとともに〈私的演奏会〉という一連の演奏会を開いたが,そのコンサートから一般のディレッタントをいっさい締め出してしまった。脱工業化社会においては,作曲家,演奏家,聴衆はおのおの孤立して,社会的・文化的なヒエラルヒーは崩壊し,社会的階層と文化的な趣味の間の一致は見られなくなりつつある。レコード,テープレコーダー,放送などの科学技術の発展は,かつてなかったような膨大な数の音楽ファンを生み出したが,それらの音楽愛好家は,さまざまなメディアを通して,古今東西のあらゆる種類の音楽に接することになった。
今日の日本の音楽文化は,この脱工業化社会のパターンの典型になりつつある。今日の日本の音楽愛好家は,西洋のバロック音楽から現代音楽,日本の民謡や演歌,タンゴやモダン・ジャズなど,あらゆる時代のあらゆる音楽に接している。1981年にNHK放送世論調査所が行ったアンケート調査によれば,今日の日本人の好む音楽は,歌謡曲(66%),演歌(51%),日本民謡(40%),映画音楽(33%)という順で,西洋の芸術音楽(クラシック)の中の交響曲,管弦楽曲,協奏曲は第11位(15%)にランクされ,日本の伝統音楽の文楽・義太夫は,最下位の60位(0.1%)に入っている。今日の日本の音楽文化は,歌謡曲と演歌という二つの大衆音楽を基底として,図のcの三角形を形成しているようにも見える。しかし現実には,さまざまな時代とさまざまな地域の〈複数の音楽(musics)〉が,相互に関連なく,いわば無重力の状態で浮遊している。音楽における価値体系が崩壊した今日においては,社会の上層にいるエリートが,モーツァルトの交響曲を聴いた翌日,カラオケによって演歌を楽しむということも,しばしば見られる現象になっているのである。
今日の音楽文化もまた,マス・コミュニケーションと資本の二つの強大な力によって支配されている。大衆社会の出現とマス・コミュニケーションの発達は,19世紀までは想像もできなかったような膨大な数の聴衆を作り出したが,こうした多数の音楽ファンは,従来には見られなかったような態度で音楽に接するようになった。音楽社会学者でもあるT.W.アドルノは,1933年の論文《音楽の社会的位置について》で,音楽聴取の態度の変化に注目し,音楽に接する人々を次の六つの類型に分類した。音楽の構造を聴き取る能力をもった〈エキスパート〉,全体のまとまりを自発的に理解する〈よき理解者〉,レコードを次々に購入して聴く〈教養消費者〉,音楽を聴いて解放されることを望む〈情緒的聴取者〉,陳腐なコンサート音楽に飽きて古楽に聴きいる〈復讐型聴取者〉,ジャズだけを聴く〈ジャズファン〉である。これらのさまざまなタイプのなかで最多数を占めるのは,音楽を娯楽としてとらえる〈娯楽型聴取者〉(〈エキスパート〉以外の聴取者はみなこのタイプになり得る)であり,これらの人々は,マス・コミと資本の管理のもとに音楽を商品として扱い,モーツァルトから演歌までを次々に消費していく。アドルノはさらに38年の論文《音楽における物神的性格と聴衆の退化》で,娯楽として音楽を楽しむ人々が,一種の〈物神崇拝〉(たとえばストラディバリウスの音色に対する憧憬)にとりつかれて〈退化〉し,資本によって管理された商品としての音楽を消費している構造を明らかにしている。
マス・コミュニケーションと資本主義は,単に大衆音楽においてだけではなく,芸術音楽の分野でも,独特なスターダムの体制を生み出した。今日の芸術音楽家は,なによりもまず音楽コンクールに入賞することをねらい,世界各地で開催されているコンクールに無事入賞した人は,放送局とレコード会社とジャーナリズムを通してスターへの道を目ざすようになった。18,19世紀においてもオペラ座の支配人は大きな力をもっていたが,今日のマネージメントに携わる人々(特に膨大な資本と人的関係をもつユダヤ系マネージャー)は,音楽家に対して絶対的な支配力をもつようになった。強大な支配力をもつマネージャーに見いだされた音楽家は,レコードや新聞を通して宣伝され,ロンドン,パリ,ベルリン,東京,ニューヨークなどの演奏会場を飛行機で往復することになる。
20世紀に入ってからのテクノロジーの発展は,音楽の世界にも多大な影響を与え,音楽生活のあり方を根底から揺り動かした。テープレコーダーや電子音響機器の発明は,電子音楽やミュジック・コンクレートなど演奏家を必要としない新しい音楽を生み出し,LPレコード,カセット,ウォークマン,コンパクト・ディスクなどの普及は,従来のコンサート中心の音楽享受を一変させた。かつて音楽会場に足を運んで隣席の人の動きを感じながらステージ上での音楽的できごとに参加していた聴衆は,電車のなかで一人でモーツァルトを聴いたり,深夜一人で自分の書斎でモーツァルトを聴いたりするようになった。テープやレコードの高度な録音技術の発達は,演奏のスタイルも変質させ,演奏家たちの主要な関心は,音楽作品の全体よりもむしろ細部に向けられるようになり,精緻で正確なスタイルが好まれるようになった。ピアニストのG.グールドは,コンサートでは不正確な演奏しか可能でないと明言し,コンサートの形式を拒否して,何度も録音を取り直しながら完璧な演奏を目ざしてレコーディングに専念した。大衆社会の登場とともに出現したレコードは,〈今,ここで〉という音楽行為の一回性を否定し,W.ベンヤミン流に言えば〈アウラaura〉の消滅した新しい複製芸術のあり方を示している。
レコードやカセットの普及は,バックグラウンド・ミュージック(BGM,環境音楽)を生み出す直接的な契機となった。バックグラウンド・ミュージックは,労働の能率を向上させたり,精神を安定させたりするために使用される柔らかなムードをもった音楽である。環境音楽という考え方は,工場や病院から始まり,以後デパート,駅,喫茶店,レストランにひろがっていった。環境音楽の最初の主張は,人間と環境の間に一定の安定した音空間を作ることであったが,しかしその普及とともに,聴きたくない音楽を強制的に聴かされるという逆説的な結果を引き起こすことになり,現代の〈機能音楽〉の代表的な〈BGM〉は今日大きな問題をかかえこんでいる。カナダの音楽家シェファーR.M.Schafer(1933- )は,こうした〈BGM〉の弊害を批判し,〈サウンド・スケープsound-scape(音の風景)〉という思想をかかげて,人間と外界の世界の調和を目ざした環境音楽のあり方を模索している。なお音楽学の研究分野のなかで,音楽と社会の関連について研究する音楽社会学は,音楽史や音楽美学などよりも文献の数も少なく立ち遅れていたが,1960年代以降,その重要性が認識され,急速に注目を集めるようになった。
執筆者:船山 隆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「音楽」の意味・わかりやすい解説
音楽
おんがく
音楽とは、音響現象のさまざまな特性を秩序だてながら使い分けて、一定の時空間のなかに繰り広げる人間の芸術的活動の所産である。身体や物体を利用して構築されるこの音響世界は、社会的存在として人間が送る生活のなかに有機的に組み込まれて文化的な意味や価値が与えられ、状況に応じて社会的機能を果たすのである。そして音楽は、時代の変遷とともに伝承ないし変形されたり、地域を越えて伝播(でんぱ)し変容したりして、人類文化の縦と横の広がりのなかで重要な役割を演じてきた。
[山口 修]
概念としての音楽
語義と音楽概念
音楽ということばは、中国および周辺の国々で、英語のmusicなど(フランス語でmusique、ドイツ語でMusik、イタリア語でmusica、アラブ諸国でmūsīqī, mūsīqā)に対応する近代的な用語である。音楽という用語の文献上の初出は、中国では秦(しん)代の成立とされる『呂氏(りょし)春秋』(前3世紀)、日本では『続日本紀(しょくにほんぎ)』(797)であり、それ以後も用例は散見されはするが、意味内容は今日のものとは一致せず、特定の種目や楽曲をさすことが多かったらしい。「音楽」に相当する中国の用語は「楽」であり、これは「声」(物に感じて動くもの)、「音」(それが変化して形を表す場合)、「楽」(その音を重ねて楽しむとき)という三分法の一つの概念である。象形文字としての「楽(樂)」は、「木」に「糸(幺)」を張った弦楽器を「白(爪(つめ))」で奏するという意味であるとする説がある。別の解釈としては、「木」の台の上に「幺(騎鼓)」が二つ置かれ、それを「うつ(白)」ともされる。いずれにせよ楽器を奏することが原義であり、さらに上流階級の人々の音楽をさすことがニュアンスとして含まれている。日本でも「音楽」の意味で「楽」の字をあてる習慣があり、やはり雅楽などを示唆することが多かった。楽の字の訓読みとしては「あそび・あそぶ」が妥当と考えられる。ただし「あそび」は、音楽だけでなく、狩猟その他の日常生活からやや離れた特殊な活動をさす多義的な大和(やまと)ことばである。ちなみに、今日でも奄美(あまみ)諸島や沖縄では音楽演奏の類義語として「あそび」「うたあそび」といったことばが使われている。日本語ではほかにも「もののね」「うた」「音曲」などの総称的用語があるが、それぞれ含蓄範囲が限られており、明治以後「音楽」が一般的に使われるようになった。
インドでは古代以来サンスクリット語のサンギータsa gītaが総称語として用いられているが、これはギータgīta(歌)、バーディャvādya(楽器)、ヌルッタn
gītaが総称語として用いられているが、これはギータgīta(歌)、バーディャvādya(楽器)、ヌルッタn tta(舞踊)を包括するものであった。西アジアでは「歌」を意味するアーバーズāvāz(ペルシア)、ギナーghinā'(アラビア)とは別に、ムーシーカーmūsīqā(アラビア)が使われることもある。ヨーロッパでも諸語本来のものとしては「歌」ないし「旋律」を意味する用語だけであった。たとえば、イギリスのソングsong、チューンtune、フランスのシャンソンchanson、メロディーmélodie、ドイツのゲザングGesang、リートLiedである。状況は他の民族でも類似していることが多い。東南アジアではラグlagu(マレー)、アフリカではニンボnyimbo(タンザニア)、ミクロネシアではエリタクルelitakl(ベラウ)などがその例である。
tta(舞踊)を包括するものであった。西アジアでは「歌」を意味するアーバーズāvāz(ペルシア)、ギナーghinā'(アラビア)とは別に、ムーシーカーmūsīqā(アラビア)が使われることもある。ヨーロッパでも諸語本来のものとしては「歌」ないし「旋律」を意味する用語だけであった。たとえば、イギリスのソングsong、チューンtune、フランスのシャンソンchanson、メロディーmélodie、ドイツのゲザングGesang、リートLiedである。状況は他の民族でも類似していることが多い。東南アジアではラグlagu(マレー)、アフリカではニンボnyimbo(タンザニア)、ミクロネシアではエリタクルelitakl(ベラウ)などがその例である。
こうした背景があったために、「ミュージック」系統の用語が世界的にかなり広く使われているのが現状である。それは、ヨーロッパにおいてムーシケーmousikē(ギリシア語)、ムシカmusica(ラテン語)に基づいて諸民族が借用語を確立したのに始まる。ギリシア語のムーシケーは、ムーサイmousai(単数形はムーサ)に関連するという意味の形容詞であったのが名詞化したものである。ムーサイはギリシア神話の主神ゼウスが記憶の女神ムネモシネに生ませた9人の女神で、それぞれ叙事詩、叙情詩、悲劇、喜劇、音楽、舞踊、歴史、天文などを受け持っていた。したがってムーシケーの含蓄するところは、言語、詩歌、音楽、舞踊といった、ことば、運動、時間にかかわる技芸や、それらに従事するときの人間行動にまで及ぶ。そこにすでに備わっていた理論的学問的性格はさらに強化されて、ヨーロッパ中世のムシカとして概念が明確になる。すなわち、自然や宇宙を支配する数とその比例原理に着目したハルモニアharmonia論であり、3種のムシカが区別される。ムシカ・インストルメンターリスm. instrumentalisまたはムシカ・ソノーラm. sonoraは器官(声)や器具(楽器)によって産出される現実の音楽、それの基礎となっているとされるムシカ・ムンダーナm. mundanaは宇宙の音楽、そしてムシカ・フマーナm. humanaは人間の魂の音楽である。この論を基盤にしてムシカは、教育機関スコラにおいて、修辞学、算数などと並んで自由七科のなかに含まれるようになった。
中世以後のヨーロッパ音楽史が華やかな展開を遂げるにつれ、「ミュージック」系統の用語は各国で着実に根を下ろしていった。そして18~20世紀の植民地政策の落し子として、ヨーロッパ以外の地にも普及していった。しかし20世紀後半になると、異なる文化価値を是認する文化的相対主義の考え方が顕著になり、それに応じて世界の多様な音楽様式をそれぞれ尊重する傾向が現れてきた。それを反映しているのが、英語でいえばmusicsのように複数形の使用を奨励し、異なる音楽文化を十把ひとからげに扱わないという態度である。
[山口 修]
周辺領域との関連
人間行動の一つとしての音楽は、本来それ自体で独立できるものではなく、さまざまな周辺領域とのかかわりにおいて成立している。高度の自律性をかちえたとされる西洋音楽ですら、現実に鳴り響くことを前提にしている以上、一定の社会的、文化的脈絡のなかに置かれるのであるから、音楽外的な効果から自由ではありえない。
音楽がもっとも深い関係をもつ周辺領域は言語であろう。それは第一に、発音を基礎にした音声言語(発話)が、音楽と同様に聞き手に向けられる伝達形態であるという事実である。第二には、音楽の主要な形式の一つである声楽がまさにことば(歌詞)をそのなかに取り込んでいるという直接的な交差関係がある。そして第三に、音楽概念の本質的な部分の一部がさまざまなレベルにおいて音楽用語として言語化されたり、「音楽について語る」という行為が日常生活においても特殊な方法(音楽批評、音楽学など)でも実行されるという関係がある。そのなかでも第一のものは、音を駆使するときに分節的か、それとも韻律的かの方法、またはその組合せの方法をとるという点で、音楽と言語の構造上の連関に直結した問題である。より具体的には、西アフリカのいわゆるトーキング・ドラムが、ことばを模倣して言語的意味内容を担いながら王朝の系譜を物語ったり、挨拶(あいさつ)や裁判にも使われたりすることがある。さらにヨーロッパの鐘、オセアニアの割れ目太鼓(スリット・ドラム)、仏教の音具(法器)などが1日の一定の時間に一定のパターンに即して発音させられるときに、一定の雰囲気を醸し出すだけでなく、さらに伝達内容を含んでいたりすることがある。
身体運動もまた音楽と切り離せない関係をもっている。発音行為それ自体が、声帯・楽器いずれを使うにしても、身体運動によっていたり、手拍子や足踏みといった行為、カイロノミー(手示法)としての西洋音楽の指揮者や、アフリカ、オセアニアのグループ・リーダーの身体動作は、とりもなおさず当該音楽様式の構造を視覚的に表現していると解釈できる。さらに、身体運動は舞踊というもう一つの芸術形式となり、音楽との相補的な関係が築き上げられる。アフリカやアメリカ(インディアンおよびラテン系混血メスティソ)の場合のように、身体の激しい動きにつれて首や脚(あし)につけた音具がリズミカルに発音するといった音楽と舞踊の直接的同調の関係もあれば、沖縄の組踊やジャワの古典舞踊タリtariの場合のように、音楽と舞踊が重要なポイントでしか同調しない関係もある。身体運動はさらに、演劇や宗教儀礼のなかでも音楽との関係を複雑に示している。
音楽はまた、文化のなかのその他の視覚的あるいは触覚的実体とも関連しながら成立する。演奏が行われる場は、一定の様式に基づく建築空間やある程度選択加工の手を施した自然空間であることが多く、特定の音響効果がそれぞれ意図されているものである。さらにその空間には美術的な装飾が付加されることも普通であるし、演奏者や聴き手(聴衆)すらも、特定の衣装や化粧によって演奏空間の様式的統一に貢献するものである。
このように音楽は周辺領域との密接な関係のなかで意味作用を発露するのであり、このことは、諸民族の音楽概念が複合的に形成されていることからも裏づけられる。その例として、前述のインドの「サンギータ」をはじめ、日本の「芸能」、インドネシア語の「カラウィタン」karawitan、オーストラリア先住民の「インマ」inma、英語の「パフォーミング・アーツ」performing arts、ワーグナーの主張する「総合芸術」Gesamtkunswerkといった一連の用語があり、いずれも音楽、舞踊、文芸などが有機的に一体になっていることを概念化している。類似のことは「歌」という用語にもいえる。すなわち、歌は文芸としての詩と音楽としての旋律を契機としてもっており、切り離すのは本来不自然である。この例は、ハワイのメレmele、ヨルバ(アフリカ)のオリンorin、ラオスのルムlum、ペルシアのアーバーズなど、他の民族にも多数みられる。
[山口 修]
音楽の分類
諸民族が展開してきた音楽文化に対して、あるいはそのなかに存在する多くの種目に対して、恣意(しい)的な分類を行いレッテルをはることは、便利であると同時に誤解を招く危険がある。たとえば「東洋音楽」と「西洋音楽」を対置させるとき、少なくとも日本人からみれば世界の二つの地理様式に大別された形でわかりやすいが、その背後には西アジア、アフリカ、オセアニアといった地域に対する配慮が欠けていることを知らねばならない。また最近の傾向として「民族音楽」ということばが安易に使われているが、これも西洋音楽のみを「音楽」とよぶか、あるいは「クラシック音楽」「ポピュラー音楽」「邦楽」に対して同時代の他の音楽を「民族音楽」とよぶという意味合いが強く、適切ではない。中立的な呼称としては「ヨーロッパ音楽」「アフリカ音楽」「アジア音楽」、あるいは「日本音楽」「ドイツ音楽」「インド音楽」といったように地域名や国名を冠する方法があるし、これは実際ある程度行われている。しかし、地域や国境を越えて「クラシック」「ジャズ」「ポピュラー」「ロック」などが普及する例も多いので、こうしたジャンル名を併用するのが現実的であろう。同じく注意を要する呼称として「芸術音楽」と「民俗音楽」を対置させることがあるが、ある特定の地域(ヨーロッパやインド)のなかではある程度通用するとしても、全体には当てはまらない。
[山口 修]
事象としての音楽
構造と形式
音楽に構造を与え、ひいては形式感や様式の確立に至らしめているのは、各民族のもつ音に対する感性である。時代様式や民族様式が築かれるときの音楽的な契機としては、音に備わった諸特性、すなわち音高、持続、音色、音強のうちどれに重点を置くかという、集団による意志作用が働いていると考えられる。たとえば、通俗的に「クラシック音楽」とよばれている西洋近代の芸術音楽においては、音高の絶対的に厳密な区別がもっとも強く働き、その現れとして24の調性が体系的に整理されている。そして、それぞれの調性には旋律と和声の進行についての原則がかなり細かく定められていて、これだけでも音楽理論という一分野をなすほどになっている。さらに、これらの調整された音高群を、その水平的連続を重視するポリフォニーないし垂直的連続を重視するホモフォニーというテクスチュア(音楽構成原理)のもとで組み立てるところに、この様式の特徴がある。これに対してアジア諸民族の音楽の多くは、テクスチュアとしてはヘテロフォニーの原理に基づく。ヘテロフォニーとは、基本的には同形の旋律が同時進行するときに、時間的ずれや装飾などによって結果的に多声となっているものをさす。したがってこの場合、各パートの音色上の微妙な差異に重きが置かれる。アフリカの場合は、音の強弱と持続の複雑な組合せと絡み合いのなかでリズムの多様性をもっとも前面に打ち出し、ときにはポリリズム(同時に複数のリズムが使用されること)の形をとったりする。テクスチュアのもう一つの原理はモノフォニーで、独唱ないし独奏による単旋律のこの種の音楽は、すべての時代すべての民族がもつものといっても過言ではあるまい。
音高の操作についてもうすこし詳しく述べると、まず第一に連続的な音高変化(滑音ないしグリッサンド)とその逆の段階的な変化(音階)の2種類が区別されなければならない。アナログ的な音高変化は、声や擦弦楽器さらにリード系の管楽器の表現において、ほとんどすべての民族の音楽で頻繁に聴かれるが、多くは音階音の移行に際してすり上げたり、すり下げたりする形をとる。しかしアジアやオセアニアにおいては、滑音表現が表現目的の中心となっている例もある。デジタルな音高変化はそれぞれの民族で音階としてパターン化しており、さらに音階音ごとに序列がつけられて、主音ないし終止音、あるいは3度、4度、5度、オクターブといった枠をつくる核音を中心にして音組織をつくりあげ、その特質が様式のアイデンティティ確立に寄与するほどである。
音の長短や強弱が音楽的に利用されるのは拍子およびリズムにおいてである。拍子は、規則的な拍感がない場合と、明確に感じられる場合とがあり、それぞれ自由リズム、固定リズムとよばれる。さらに固定リズムでは、一定の時間単位を分割することを基本にした分割リズム、そして拍をグルーピングして加法的に延長していく付加リズムとが区別される。しかし現実の音楽では、この2種類が混在している場合がみられる。たとえばインドの古典音楽において 4+2+2
4+2+2 という付加リズムが前面に出ていても、とくにテンポが遅いときには1拍のなかが分割されるのである。
という付加リズムが前面に出ていても、とくにテンポが遅いときには1拍のなかが分割されるのである。
このようにして音の特性を人為的に操作する技法は、さらに形式感をつくりあげようとする方向に向かっていく。それは、時間芸術としての音楽が絶対時間の進行の真っただ中で人工的な音楽時間を形成することであり、それが達成されると、時間的広がりを超えて空間的なまとまりすら感じさせるものである。形式形成に向かう出発点は単音発音であり、次に動機(モチーフ)ないし音変化最小単位がつくられる。言語でいえば、単語に相当する動機は、異なる単語をつなげたフレーズ(楽句)の形成に貢献し、さらに文章(楽節)をつくりあげる。楽句や楽節のくぎりを明確にするのは、パターン化した旋律輪郭や和声進行によって半終止や完全終止の働きが遂行されたり、休止符や特定楽器の音が挿入されることによってなされ、この句読法にも似た分節法はコロトミーcolotomyとよばれる。動機、楽句、楽節は反復、変形(変奏)、対比の原理に従って時間的シークェンスのなかに配列され、音楽時間の秩序が築き上げられる。
[山口 修]
意味と記号
時代や民族によって形式化し様式化した音楽という音の連なりないし流れは、それ自体で特殊な音楽時空間(ミクロコスモス)を形成しているという点で、すでに一つの意味を担わされている。それは音楽に内在する秩序という意味であり、それが正しく表現されるとき、もう一つの意味、すなわち音楽外的な文化的意味をもつことになる。換言すれば、特定のパターンや楽曲は文化によって規定された記号として、文化の担い手に伝達されるのである。その記号のあり方は文化ごとに多かれ少なかれ差異があるが、おもなものをいくつかあげておこう。
第一に、描写音楽などにおいて自然を模倣する場合、模倣の客体と主体の間にアイコンicon的な一致ないし類似が達成されることによって、鳥の鳴き声、水の流れ、雷鳴などが追体験される。第二に、慣れ親しんだ聴き手でないと理解が不可能な、文化によって恣意的に約束事として取り決められた性格づけが楽句、楽節、楽曲などに施されている場合がある。具体例としてはワーグナーの楽劇において登場人物に付与される指導動機、日本の三味線音楽において名称のつけられた合方(あいかた)というパターン(雪の合方、佃(つくだ)の合方、虫の合方など)があげられる。これらは部分的な、いわば小レベルのものであるが、儀礼音楽の特定レパートリーとして楽曲全体が冠婚葬祭などの場で演奏される大レベルのものもあり、結婚行進曲、ベートーベンの『第九交響曲』の「歓喜に寄す」、長唄(ながうた)『松の緑』、レクイエム、葬送行進曲、地歌『残月』などがその例である。第三に、国歌、応援歌、食卓音楽、BGM(バックグラウンド・ミュージック)などがそれぞれ人心を鼓舞したり特定の雰囲気を醸し出したりするような社会的機能を帯びるという意味が音楽に与えられる例がある。これは、さらに広げて解釈すると、オペラ・ハウスやコンサート・ホール、ロックの演奏現場、サロン音楽や家庭音楽、儀礼音楽など、いずれをとってみてもそれぞれ独自の雰囲気があり、そこに居合わせた人々に独自の効果を及ぼすという意味があって、極言すれば、すべての音楽にこの種の音楽外的・神話的意味が与えられているといってもよいだろう。
[山口 修]
文化としての音楽
起源と伝承
音楽の起源については、民族によっては神話伝説のたぐいのなかに語られていることがあるが、それらは本当の起源についての証言というよりも、むしろそれぞれの民族がもっている音楽観、世界観をくみ取る素材といったほうがよい。音楽の起源についての学説は18世紀以来いくつか出されてはいるが、しょせん類推の域を出ない。推察の根拠として「現存する未開民族」の音楽のあり方が利用されることがあるが、その考え方の立脚点はダーウィン的な進化論であって、今日では排除すべきものと主張する傾向が強い。ともかく、従来提出されてきた音楽起源説のおもなものをあげておこう。
(1)性衝動説 ダーウィンは、鳥を観察することによって、異性を呼ぶ発声が音楽の起源であるとした。
(2)言語抑揚説 J・J・ルソー、ヘルダー、スペンサーらは、音声言語の抑揚と音楽の関係が直接的であるとみなした。
(3)感情表出説 感情が高じたときの発声が音楽的であるとする考え方で、スペンサーやブントが唱えた。
(4)集団労働説 バラシェクやビュヒナーは、集団労働における掛け声の特色に着目した。
音楽がどのような起源をもつにしろ、現に各民族において伝統が伝承されていることは注目に値する。ただし厳密な伝承もあれば、変化を加えながら伝承する民族もある。現在まで行われてきた伝承形態を2大別するなら、一つには口承(口伝(くでん))ないし身体伝承があり、もう一つは文字や楽譜による「書伝」とよぶことのできる形態である。もちろん量的には前者が人類の歴史と現在を通じて圧倒的に多い。伝承の内容としては、楽曲演奏の技術だけでなく、創作(作曲)、記憶、受容まで及んでいると考えられる。そして口伝にしろ書伝にしろ、伝承活動を支える重要なものは言語であるといえよう。
口伝は、話しことばによって知識が師匠から弟子へと伝えられることを基本とするが、音楽の場合、話しことばなしに模倣をするということも大きな働きを果たしている。模倣は、子供のときから大人の行動を目撃するというごく自然な状況もあれば、一定の手続と経済的・肉体的負担を伴う徒弟制度ないしスクーリングという形式的な状況もある。そして演奏能力習得や記憶を助ける手段となるのが口唱歌(くちしょうが)やソルミゼーションといったシステムの導入である。これはパターンに名称を与えること、音階音に名称をつけて旋律をある程度理論的に把握すること、楽器の旋律やリズムの特徴を描写的に声でうたうこと(口三味線など)といった技法を含んでいて、それなりに楽譜的な機能を帯びている。口伝は多くの場合、師匠を正確にまねることから出発し、文化によっては、習得したあとで自分の個性を織り込むことが許されたり助長されたりすることもある。いずれにせよ、口承の結果はかなり厳密な伝承が達成される。
これに対し、伝えるべき内容を文学や他の記号を駆使して「書かれたもの」として残す方法は、当然文字社会でみられる伝承形態である。作曲技法、唱法(奏法)、鑑賞法をことばで表し、さらに文字化することにより、ある程度の音楽の客体化、概念の抽象化が図られることになる。書伝の方法のなかでこれがもっとも端的に実行されるのは楽譜であろう。そこには、声楽であればまず歌詞が書き留められ、それ以外に音楽の重要な側面が記号として書き換えられることになる。そこに書き留められた(二次元的に視覚化された)音楽の一断面は、音楽の実体のごく一部ではあっても、重要な側面はすべて書き留められているはずであり、その意味ではイーミックemicな(文化の担い手にとって意味をなす)側面がそこに集約されていると考えられる。ここで留意しなければならないことは、たとえ楽譜の介入が伝承過程のなかに及ぼされてきても、実際の伝承は楽譜だけを通して行われるのではなく、口承が併用されることである。書伝が伝承の中心であったのは、中世以来のヨーロッパ音楽や仏教音楽、雅楽など、例は限られている。
[山口 修]
伝播と変化
音楽は他の文化項目と同じように、共同体、民族、国家、地域を超えて伝播(でんぱ)していく。短い行動半径のなかでしか生活しえなかった古代・中世においてすら、楽器が西アジアから東アジア方面やヨーロッパ方面に移動していった形跡がたどれるし、当然それとともに音楽理論や楽曲も伝えられていったと考えられる。ただし、導入された音楽文化をそのまま受け入れるか、自国風に大幅に変化させてしまうかは、民族によって程度がまちまちである。ごく大まかにいえば、西ヨーロッパや中国は外からの文化をすばやく変容させながら吸収していく傾向が強く、それに加えて内的な欲求から革新的であったため、時代ごとに様式が大きく異なる結果となっている。これに対して、西アジア、南アジア、アフリカ、アメリカ(インディアン)、オセアニアの諸民族は、ごく近隣どうしの相互影響はあるにしても、遠い異文化からの音楽を容易には受けつけず、伝統に固守しながら、時代に応じてすこしずつ変化させる傾向が強かった。これら両極の中間に置かれるのが東南アジア諸民族と朝鮮、日本などである。日本の例でいえば、大陸から雅楽や仏教音楽を、そしてヨーロッパから近代音楽を受け入れたとき、積極的に異文化を忠実に見習おうとする姿勢がまず貫かれ、ある程度根を下ろしてからやっと自国風に消化して変化させるという傾向が感じられる。
20世紀は交通、通信技術の目覚ましい発達を通じて、諸民族の音楽文化交流を促進してきた。なかでも顕著な傾向は、大衆音楽が世界的レベルで画一化されるかにみえることである。しかし、民族のアイデンティティは簡単には消えず、大衆音楽の分野でもヨーロッパ、アメリカ(黒人・白人)、西アジア、南アジア、東南アジア、東アジア、オセアニア、アフリカのそれぞれが、独自の様式を確立しつつあるのが現状である。これに対して芸術音楽では、ヨーロッパ由来のレパートリーが多くの国々で受け入れられ、いまでは非ヨーロッパ系の優れた演奏家や作曲家が輩出するようになってきた。この傾向と並行してインドやインドネシア(ジャワとバリのガムラン)の古典音楽を代表として、いわゆる「民族音楽」ブームが台頭してくる。このような音楽様式の多様性が現代の人類の音楽性の特徴となっている。
[山口 修]
『ブラッキング著、徳丸吉彦訳『人間の音楽性』(1978・岩波現代選書)』▽『ザックス著、皆川達夫・柿木吾郎訳『音楽の起源』(1969・音楽之友社)』▽『ヴィオラ著、柿木吾郎訳『世界音楽史 四つの時代』(1970・音楽之友社)』▽『マルム著、松前紀男・村井範子訳『東洋民族の音楽』(1971・東海大学出版会)』▽『小泉文夫著『音楽の根源にあるもの』(1977・青土社)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「音楽」の意味・わかりやすい解説
音楽
おんがく
music
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「音楽」の意味・わかりやすい解説
音楽【おんがく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「音楽」の読み・字形・画数・意味
【音楽】おんがく
 樂の由來する
樂の由來する の
の
 し。度量に生じ、太一に本づく。太一は兩儀に出で、兩儀は陰陽に出づ。
し。度量に生じ、太一に本づく。太一は兩儀に出で、兩儀は陰陽に出づ。字通「音」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「音楽」の解説
音楽
おんがく
- 初演
- 延宝5.10(江戸・大和守邸)
出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報
関連語をあわせて調べる
1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...