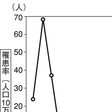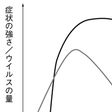共同通信ニュース用語解説 「インフルエンザ」の解説
インフルエンザ
インフルエンザウイルスが原因の感染症。A型、B型などの種類がある。例年冬から春ごろにかけて流行する。潜伏期間を経て、高熱、頭痛、全身の
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「インフルエンザ」の意味・読み・例文・類語
インフルエンザ
- 〘 名詞 〙 ( [英語] influenza 元来はイタリア語で「影響」の意 ) 伝染性の強い熱病。感冒の一種。ウイルスによって多く冬期に起こり、A・A1・A2・B・Cの五型がある。一九一八~二三年にかけてのスペインかぜや一九五七年のアジアかぜなど、世界的な大流行をみることがある。気道粘膜にカタル性炎症を生じ、高熱を発し、筋肉痛、全身倦怠などを伴い、急性肺炎を起こしやすい。流行性感冒。流感。
- [初出の実例]「女子(をんな)は十九が厄年といふが、お前は、去年劇(ひど)く流行性感冒(インフリュウエンザ)をやったから」(出典:二人女房(1891‐92)〈尾崎紅葉〉上)
EBM 正しい治療がわかる本 「インフルエンザ」の解説
インフルエンザ
●おもな症状と経過
インフルエンザウイルスの感染によっておこる病気で、ふつうのかぜ症候群に比べ、急激に強い症状が現れるものです。多くは寒気で始まり、高熱がでて、のどの痛み、せき、鼻水、くしゃみ、頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、下痢(げり)などがおもな症状となります。症状は3、4日間続き、熱が下がり始めると、徐々に全身症状もおさまってきます。
通常は経過は良好なのですが、肺や気管支を中心にほかの臓器で細菌感染が発生し、炎症がおきる二次感染には注意が必要です。とくに、お年寄りや乳幼児、心臓病や糖尿病のある人では深刻な合併症であるインフルエンザ脳症、心筋炎(しんきんえん)、心外膜炎(しんがいまくえん)、筋炎などがおこって、死亡に至る場合や重い後遺症が残る患者さんもいます。
ワクチンの接種は有効な予防法ですが、インフルエンザウイルスのタイプは毎年変異するので、ワクチンはその年ごとに接種する必要があります。
以前はかぜ症候群との判別が確実ではありませんでしたが、現在ではすぐに判別できるキットが普及し、正確な診断が可能になりました。
●病気の原因や症状がおこってくるしくみ
インフルエンザの原因となるウイルスはA型、B型、C型に大別されますが、深刻で大きな流行を引きおこすのはA型で、その年によって流行するウイルスは違います。インフルエンザウイルスは、急性期の患者さんのせきやくしゃみによって、空気中に浮遊するエアロゾル(直径10ミクロン未満)を介してほかの人の呼吸器系の細胞に感染します。感染後24時間潜伏し、増殖していきます。鼻やのどの円柱上皮細胞(えんちゅうじょうひさいぼう)、肺内の肺胞(はいほう)細胞、粘液腺(ねんえきせん)細胞やマクロファージなどのなかで、ウイルスが複製・放出され、周囲の細胞に感染します。全身症状は、感染細胞に対して体を防御する目的でつくられる腫瘍壊死因子(しゅようえしいんし)や、インターフェロン6などのサイトカインによっておこると考えられています。
●病気の特徴
世界中で流行がみられ、集団発生するのが大きな特徴であり、わが国での流行は一般的に冬から春先にかけておこっています。
よく行われている治療とケアをEBMでチェック
[治療とケア]発病後2日以内であれば、抗ウイルス薬を用いる
[評価]☆☆☆☆☆
[評価のポイント] A型あるいはB型のインフルエンザに対して、ザナミビル水和物もしくはオセルタミビルリン酸塩を発病後早期(2日以内)に用いれば、インフルエンザの症状を約1~3日短縮する効果があることが非常に信頼性の高い臨床研究によって確認されています。しかし、合併症を抑えるかどうかは不確かです。(1)~(27)
以前、A型のインフルエンザに使用されていたアマンタジン塩酸塩もしくはリマンタジン(日本では未発売)は現在、耐性株の出現により特別な場合を除いては推奨されなくなりました。(2)
[治療とケア]ワクチンによって予防する
[評価]☆☆☆☆☆
[評価のポイント] 60歳以上のお年寄りに対するワクチンの効果は、非常に信頼性の高い臨床研究によって確認されています。(28)~(30)
[治療とケア]薬によって各種の症状を抑える
[評価]☆☆
[評価のポイント] 各種の症状を緩和(かんわ)するために薬が用いられます。頭痛、筋肉痛、発熱に対しては、非ステロイド抗炎症薬でなく、アセトアミノフェンの使用を勧めています。とくに子どものインフルエンザに対して、非ステロイド抗炎症薬のメフェナム酸、ジクロフェナクナトリウムおよびサリチル酸系の薬(アスピリンなど)は、解熱目的での使用を原則としてしないことになっています。
[治療とケア]二次感染が確認されたら、抗菌薬を用いる
[評価]☆☆
[評価のポイント] インフルエンザウイルス感染による合併症としておこる細菌性肺炎、急性中耳炎、急性副鼻腔炎(きゅうせいふくびくうえん)など、細菌による感染症が明らかな場合には、抗菌薬の使用が理にかなっています。
[治療とケア]消化のよい食べ物で栄養をとる
[評価]☆☆
[治療とケア]水分を十分にとる
[評価]☆☆
[治療とケア]空気が乾燥している場合は加湿する
[評価]☆☆
[治療とケア]外から帰ったらうがい、手洗いをする
[評価]☆☆
[評価のポイント] 病気のおこってくるしくみや、専門家の意見や経験から支持されています。
[治療とケア]人混みへの外出を避ける
[評価]☆☆
[評価のポイント] 病気のおこってくるしくみや、専門家の意見や経験から支持されています。また、マスクをすることで予防が可能になる可能性があると考えられます。
[治療とケア]熱のある場合、入浴は控える
[評価]☆☆
[治療とケア]熱がある場合は、布団を薄めにして、熱を逃がすようにする
[評価]☆☆
[評価のポイント] 病気のおこってくるしくみや、専門家の意見や経験から支持されています。
よく使われている薬をEBMでチェック
抗インフルエンザウイルス薬
[薬用途]A、B型ともに有効
[薬名]リレンザ(ザナミビル水和物)(1)~(27)
[評価]☆☆☆☆☆
[薬名]タミフル(オセルタミビルリン酸塩)(1)~(27)
[評価]☆☆☆☆☆
[評価のポイント] ザナミビル水和物もしくはオセルタミビルリン酸塩は、A型およびB型のインフルエンザに対して、発病後早期に用いると、症状を約1~3日短縮する効果が非常に信頼性の高い臨床研究によって確認されています。合併症を抑えるかどうかは不確かです。
以前A型インフルエンザに使用されていたアマンタジン塩酸塩もしくはリマンタジン(日本では未発売)は現在、耐性株の出現により特別な場合を除いては推奨されなくなりました。(2)
熱がある場合
[薬名]アセトアミノフェン(アセトアミノフェン)(31)(32)
[評価]☆☆☆☆☆
[評価のポイント] 非ステロイド抗炎症薬、アスピリン、アセトアミノフェンをかぜもしくはインフルエンザ症状の患者さんに使用したとき、アスピリンの副作用が大きいという非常に信頼性の高い臨床研究があります。非ステロイド抗炎症薬を使うと消化性潰瘍(かいよう)や腎障害(じんしょうがい)の副作用が心配されるので、より安全なアセトアミノフェンの使用が勧められます。
くしゃみ、鼻水、鼻づまりが強いとき
[薬用途]非ピリン系感冒薬
[薬名]PL顆粒
[評価]☆☆
[薬用途]抗ヒスタミン薬
[薬名]レスタミンコーワ(ジフェンヒドラミン塩酸塩)
[評価]☆☆
[薬名]タベジール(クレマスチンフマル酸塩)
[評価]☆☆
[評価のポイント] いずれの薬も専門家の意見や経験から支持されています。
せきが激しいとき(鎮咳薬(ちんがいやく)、抗炎症薬)
[薬名]メジコン(デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物)
[評価]☆☆
[薬名]リン酸コデイン(コデインリン酸塩水和物)
[評価]☆☆
[薬名]ブルフェン(イブプロフェン)
[評価]☆☆
[薬名]ノイチーム/レフトーゼ(リゾチーム塩酸塩)
[評価]☆☆
[評価のポイント] いずれの薬も専門家の意見や経験から支持されています。
ねっとりした痰(たん)がでるとき(抗炎症薬、去痰薬、抗菌薬)
[薬名]ムコソルバン(アンブロキソール塩酸塩)
[評価]☆☆
[薬名]クラリス/クラリシッド(クラリスロマイシン)
[評価]☆☆
[評価のポイント] いずれの薬も専門家の意見や経験から支持されています。
総合的に見て現在もっとも確かな治療法
急激な症状をやわらげる
インフルエンザウイルスの感染によっておこる病気で、いわゆるふつうのかぜに比べて急激に強い症状が現れるという特徴があります。現在効果が確かめられている治療は、こうした強い症状に悩まされる期間を短くする抗インフルエンザウイルス薬を使ったものです。
発病後早期に薬による治療を受ければ、症状の続く期間が1日短縮
リレンザ(ザナミビル水和物)およびタミフル(オセルタミビルリン酸塩)は、A型およびB型のインフルエンザに対して、発病後早期に用いれば、インフルエンザのつらい症状が続く期間を約1~3日短縮する効果が確認されています。したがって、発病後早期のインフルエンザと考えられる患者さんでは、特別な理由がなければ、いずれかの薬が使われます。とくに65歳以上の高齢者、妊娠中の女性や出産後2週間までの女性、基礎疾患があって重症化しやすい場合などは積極的に薬を使用することが勧められています。
以前A型インフルエンザに使用されていたアマンタジン塩酸塩もしくはリマンタジン(日本では未発売)は現在、耐性株の出現により特別な場合を除いては推奨されなくなりました。(2)
高熱、筋肉痛には対症療法
つらい症状である高熱や筋肉痛などへの対症療法、とくに解熱鎮痛薬の使用も副作用に留意するなら十分理にかなっていて、有効性は誰もが認めるところと思われます。
ただし、子どもの場合、解熱鎮痛薬の使用は慎重に考えられています。アセトアミノフェン(アセトアミノフェン)は安全性の高い薬と考えられていて、子どものインフルエンザに対して、解熱鎮痛目的で使用されています。しかし、非ステロイド抗炎症薬のポンタール(メフェナム酸)、ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム)およびサリチル酸系の薬(アスピリンなど)は、解熱目的での使用を原則としてしないことになっています。これはこれらの薬を使うことによって、インフルエンザ脳症になる場合があるからです。
インフルエンザでは、安易に解熱薬を使うとかえって自然治癒力を妨げて治るのに時間がかかるのではないかという説もあるようですが、臨床研究ではそのような証拠は認められていません。
(1)Glezen WP. Clinical practice. Prevention and treatment of seasonal influenza. N Engl J Med 2008; 359:2579.
(2)Fiore AE, Fry A, Shay D, et al. Antiviral agents for the treatment and chemoprophylaxis of influenza --- recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2011; 60:1.
(3)Fiore AE, Shay DK, Broder K, et al. Prevention and control of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008. MMWR Recomm Rep 2008; 57:1.
(4)Cooper NJ, Sutton AJ, Abrams KR, et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in treatment and prevention of influenza A and B: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ 2003; 326:1235.
(5)Nicholson KG, Aoki FY, Osterhaus AD, et al. Efficacy and safety of oseltamivir in treatment of acute influenza: a randomised controlled trial. Neuraminidase Inhibitor Flu Treatment Investigator Group. Lancet 2000; 355:1845.
(6)Hayden FG, Osterhaus AD, Treanor JJ, et al. Efficacy and safety of the neuraminidase inhibitor zanamivir in the treatment of influenzavirus infections. GG167 Influenza Study Group. N Engl J Med 1997; 337:874.
(7)Randomised trial of efficacy and safety of inhaled zanamivir in treatment of influenza A and B virus infections. The MIST (Management of Influenza in the Southern Hemisphere Trialists) Study Group. Lancet 1998; 352:1877.
(8)Jefferson T, Jones M, Doshi P, et al. Oseltamivir for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory comments. BMJ 2014; 348:g2545.
(9)Heneghan CJ, Onakpoya I, Thompson M, et al. Zanamivir for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory comments. BMJ 2014; 348:g2547.
(10)Ison MG. Optimum timing of oseltamivir: lessons from Bangladesh. Lancet Infect Dis 2014; 14:88.
(11)Fry AM, Goswami D, Nahar K, et al. Efficacy of oseltamivir treatment started within 5 days of symptom onset to reduce influenza illness duration and virus shedding in an urban setting in Bangladesh: a randomised placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis 2014; 14:109.
(12)Gaglia MA Jr, Cook RL, Kraemer KL, Rothberg MB. Patient knowledge and attitudes about antiviral medication and vaccination for influenza in an internal medicine clinic. Clin Infect Dis 2007; 45:1182.
(13)Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D, et al. Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review. Lancet 2006; 367:303.
(14)Treanor JJ, Hayden FG, Vrooman PS, et al. Efficacy and safety of the oral neuraminidase inhibitor oseltamivir in treating acute influenza: a randomized controlled trial. US Oral Neuraminidase Study Group. JAMA 2000; 283:1016.
(15)Kaiser L, Wat C, Mills T, et al. Impact of oseltamivir treatment on influenza-related lower respiratory tract complications and hospitalizations. Arch Intern Med 2003; 163:1667.
(16)Hernán MA, Lipsitch M. Oseltamivir and risk of lower respiratory tract complications in patients with flu symptoms: a meta-analysis of eleven randomized clinical trials. Clin Infect Dis 2011; 53:277.
(17)Lee N, Chan PK, Choi KW, et al. Factors associated with early hospital discharge of adult influenza patients. Antivir Ther 2007; 12:501.
(18)McGeer A, Green KA, Plevneshi A, et al. Antiviral therapy and outcomes of influenza requiring hospitalization in Ontario, Canada. Clin Infect Dis 2007; 45:1568.
(19)Bowles SK, Lee W, Simor AE, et al. Use of oseltamivir during influenza outbreaks in Ontario nursing homes, 1999-2000. J Am Geriatr Soc 2002; 50:608.
(20)Aoki FY, Boivin G. Influenza virus shedding: excretion patterns and effects of antiviral treatment. J Clin Virol 2009; 44:255.
(21)Kawai N, Ikematsu H, Iwaki N, et al. A comparison of the effectiveness of oseltamivir for the treatment of influenza A and influenza B: a Japanese multicenter study of the 2003-2004 and 2004-2005 influenza seasons. Clin Infect Dis 2006; 43:439.
(22)Aoki FY, Macleod MD, Paggiaro P, et al. Early administration of oral oseltamivir increases the benefits of influenza treatment. J Antimicrob Chemother 2003; 51:123.
(23)Kawai N, Ikematsu H, Iwaki N, et al. Factors influencing the effectiveness of oseltamivir and amantadine for the treatment of influenza: a multicenter study from Japan of the 2002-2003 influenza season. Clin Infect Dis 2005; 40:1309.
(24)Hayden FG, Treanor JJ, Fritz RS, et al. Use of the oral neuraminidase inhibitor oseltamivir in experimental human influenza: randomized controlled trials for prevention and treatment. JAMA 1999; 282:1240.
(25)Burch J, Corbett M, Stock C, et al. Prescription of anti-influenza drugs for healthy adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2009; 9:537.
(26)Jefferson T, Jones MA, Doshi P, et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1:CD008965.
(27)Hsu J, Santesso N, Mustafa R, et al. Antivirals for treatment of influenza: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Ann Intern Med 2012; 156:512.
(28)Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary LA, et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD004876.
(29)Wong K, Campitelli MA, Stukel TA, Kwong JC. Estimating influenza vaccine effectiveness in community-dwelling elderly patients using the instrumental variable analysis method. Arch Intern Med 2012; 172:484.
(30)Fry AM, Kim IK, Reed C, et al. Modeling the effect of different vaccine effectiveness estimates on the number of vaccine-prevented influenza-associated hospitalizations in older adults. Clin Infect Dis 2014; 59:406.
(31)Hurwitz ES, Nelson DB, Davis C, et al. National surveillance for Reye syndrome: a five-year review. Pediatrics 1982; 70:895.
(32)Pugliese A, Beltramo T, Torre D. Reye's and Reye's-like syndromes. Cell BiochemFunct 2008; 26:741.
出典 法研「EBM 正しい治療がわかる本」EBM 正しい治療がわかる本について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「インフルエンザ」の意味・わかりやすい解説
インフルエンザ
いんふるえんざ
influenza
インフルエンザウイルスによっておこる急性の呼吸器感染症。かぜ(またはかぜ症候群)に属する一疾患であり、かつては流行性感冒(英語でgrippe、ドイツ語でGrippe、フランス語でgrippe)ともよばれた。
[加地正郎]
歴史
インフルエンザは詳細な流行の記録が17世紀ころから残されているが、その歴史は遠く紀元前にまでさかのぼることができるとされている。近年の世界的な大流行としては1889~1890年の流行と、1918~1919年のスペインインフルエンザがある。とくにスペインインフルエンザは、全世界での患者6億、死亡者3000万に達し、日本でも患者2300万、死亡者38万余という惨禍を残し、インフルエンザの歴史のみならず、感染症の流行史においても特筆すべき大流行であった。
1933年にインフルエンザの病原ウイルスが発見されたが、それ以後では1957年のアジアインフルエンザ、1968~1969年の香港(ホンコン)インフルエンザ、1977~1978年のソ連インフルエンザなどが有名である。
[加地正郎]
流行
インフルエンザウイルスには、A、B、Cの3型があり、このうちA型およびB型は強烈な伝播(でんぱ)力をもち、広範な流行をおこす。患者のくしゃみ、咳(せき)によって飛び散った気道分泌物の小粒子に含まれたウイルスが直接に(飛沫感染)、あるいは空気中に浮遊しているさらに小さな気道分泌物由来の粒子中のウイルスが(飛沫核感染あるいは空気感染)周囲の人の呼吸器に侵入して感染をおこす。集団生活の場では、飛沫核感染によって同室内の人が同時に多数罹患(りかん)する。日本では、秋の終わりから翌年の初春までの寒い時期に発生する。流行は、まず家庭内といった小範囲での発生に始まり、ついで学校などの集団発生となって、そこで感染した学童、生徒が各家庭で感染を拡げる結果、その地域での流行として拡大していく。
流行後は集団としてそのウイルスに対する免疫ができるが、ウイルスの抗原変異によって抗原構造のずれた型のウイルスが出現すると(連続変異)、その集団免疫ではその流行を阻止できず、ふたたび流行する。さらにA型では、こうした流行のくり返しである年月の間には集団免疫が高くなるので、その集団免疫を乗りこえるため、それまで流行していた型とまったく違った抗原構造をもつ型が出現する(不連続変異)。出現当初の冬にはそれに対する免疫がない状態なので、世界的な大流行となり、その後規模がそれほど大きくない流行をくり返す。こうした連続変異と不連続変異によってA型流行の歴史が綴られていく。
A型ウイルス粒子の表面に存在する2種のスパイク(突起)すなわち赤血球凝集素hemagglutinin(HA)とノイラミニダーゼneuraminidase(NA)の抗原性によって、HAは1~16まで、NAは1~9までの違った型が知られており、このHAとNAの組合せによって理論的には16×9=144の亜型(subtype)の存在が考えられ、鳥類をはじめ多くの動物の間に分布している。人の間で流行をおこした、あるいは現在も流行している亜型はH1N1(ソ連型)、H2N2(アジア型)およびH3N2(香港型)であり、最近H1N2という亜型の流行も報告されている。
なお、HAの分類について現在のH1は赤血球凝集抑制試験によってHsw1(swはswine、豚型の意)、H0、H1、H2、H3という亜型に分類されていたが、1980年から二重免疫拡散法によるデータからHsw1、H0、H1の3つはH1としてまとめられることになった。
ここには流行の歴史を一般に用いられている名称でそれぞれの亜型による流行期間をのべると、豚型(Hsw1N1)流行1917~1928年、古典的A型(H0N1)流行1930~1946年、Aプライムまたはソ連型(H1N1)流行1947~1956年および1977年から現在、アジア型(H2N2)流行1957~1967年、香港型(H3N2)流行1968年から現在で、香港型とソ連型の二つが、流行を繰り返しているところであるが、そろそろ新しい亜型の登場と、それによる大流行が警戒されているところに、2003年暮から家禽の間で流行し始めたH5N1型が世界的な広がりをみせ、人への感染例への報告が相次ぐに及んで、このH5N1型による大流行が危惧されている。
[加地正郎]
ウイルスの感染と進展
呼吸器粘膜には、上皮細胞の線毛(繊毛)の動きと粘液の作用で、侵入してきたウイルスを排除するという働きをはじめとする、感染防御のメカニズムが備わっているが、呼吸とともに鼻やのどから侵入してきたウイルスがこの防御機構に打ち勝って呼吸器粘膜細胞に感染をおこすと、その細胞内でウイルスは増殖し始め、増殖したウイルスは細胞を破壊して細胞外に出て周囲の細胞へと感染を拡大していく。
大局的にみると、ウイルスの感染は鼻やのどの上気道から気管や気管支の下気道へ、つまり呼吸器の奥のほうへと進んでいき、それに応じて鼻やのどや気管支に炎症がおこる。したがって、急性鼻炎や急性気管支炎の症状が現れるわけであり、炎症が広範かつ高度におこるため、熱などの全身反応も強くなる。
[加地正郎]
症状
潜伏期は1~3日とたいへん短い。急激に発病するが、熱、頭痛、腰痛、全身のだるい感じなどの全身症状で始まり、続いてのどの痛み、咳などの呼吸器症状が現れる。熱は急速に上昇し、1~3日後には38~39℃にも達する。同時に頭痛、腰痛、筋肉痛、関節痛などの痛み、全身のだるい感じが強くなる。呼吸器からの症状としては、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰(たん)などが現れるが、声がれ、鼻出血などもときにみられる。そのほか、嘔吐(おうと)、腹痛、下痢などの消化器症状も出現することがある。この消化器症状は、小児では成人よりもおこりやすい。
熱は3、4日後には解熱するか、解熱しないまでも徐々に下降し始め、5~7日以内には解熱する。熱の経過に応じて頭痛などの全身症状や呼吸器症状も軽くなっていき、普通はおよそ1週間で治癒するが、咳だけが残ったり、全身のだるい感じがなかなかとれないこともある。
このような症状はA型もB型も同様であるが、一般的にはB型がやや軽い。しかし、新型インフルエンザとして人での流行が懸念されているH5N1ウイルスによるインフルエンザは、これまでの報告によるときわめて重症で、ウイルス自体によって肺病変が強くおこり、呼吸不全から多臓器不全をきたし、高い致死率を示している。この点はこれまでのインフルエンザとは、その様相を異にしている。
[加地正郎]
合併症
従来のインフルエンザでもっとも警戒すべき合併症は肺炎である。病原のウイルス単独でも肺炎をおこしうるが、ウイルス感染によって気管支粘膜の上皮細胞が破壊され、その部の感染防御の働きが低下したのに乗じて細菌が二次的に感染するため肺炎合併症がおこるのが普通である。二次感染をおこす細菌としては、ブドウ球菌、インフルエンザ菌、肺炎球菌、連鎖球菌などが主であるが、緑膿菌(りょくのうきん)や肺炎桿菌(かんきん)なども注目されている。
この肺炎を合併しやすい素因としては、慢性呼吸器疾患(慢性気管支炎、気管支拡張症、気管支喘息(ぜんそく)など)や心疾患、ことに僧帽弁膜症、糖尿病などの存在、高齢、妊娠などがあげられている。また、肺炎を合併する頻度は一般には数%以下、普通は1%前後である。このように合併頻度は低いが、流行に際してのインフルエンザ患者数はきわめて多数に上るので、肺炎を合併してくる患者の実数もまた多数となる。
肺炎のほかにも、小児では急性脳症やライReye症候群などの重篤な神経系の合併症には警戒を要する。このほか心筋炎や心外膜炎などの心合併症がみられることもあるが、これらの合併症はそれほど多いものではない。
[加地正郎]
予後
インフルエンザは合併症をおこさない限り約1週間で治癒する疾患で、予後は一般に良好である。肺炎を合併すると予後はかならずしも良好でなく、二次感染菌に対する強力な抗菌療法にもかかわらず重篤な経過をたどることがあるので注意する必要がある。また、種々の慢性の病気をもつ患者がインフルエンザに罹患すると、それをきっかけにして、以前からの病気が悪化することがある。
[加地正郎]
治療
インフルエンザウイルスに直接に作用する抗ウイルス剤としてアマンタジンが用いられ、ある程度の治療効果が認められている。しかし、ウイルスが耐性を獲得しやすい難点があり、現在ではノイラミニダーゼ阻害薬のリン酸オセルタミビル(「タミフル」)およびザナミビル(「リレンザ」)が広く用いられているが、これらの薬に対しても耐性ウイルスが報告されるようになった。そのほか治療としては高熱に対する解熱薬、激しい頭痛や腰痛などの痛みを和らげる鎮痛薬、ひどい咳には鎮咳(ちんがい)剤(咳止め)を用いるというように、苦痛となる症状を抑える対症療法が中心となる。このほか、一般的な療法として安静と水分補給があげられるが、安静はとくに重要で、治癒を促し、肺炎合併症を予防するのに役だつ。肺炎合併症には、二次感染をおこしている細菌に対する化学療法が必要となる。
なお、細菌の二次感染による肺炎の合併を予防する目的でインフルエンザの発病当初から抗菌薬の投与を行うことについては議論のあるところである。前述のような肺炎を合併しやすい素因のある例では必要なこともあるが、一般にはこの予防的抗菌療法は行わないのが普通である。抗菌薬はインフルエンザウイルス自体には無効である。
[加地正郎]
予防
インフルエンザワクチンの接種が行われる。現行のものはホルマリン不活化HAワクチンである。HAワクチンとは、ウイルス粒子の成分のうち、感染を防ぐのにもっとも重要な抗体をつくらせる赤血球凝集素(HA)という成分を集めてつくったワクチンの意味である。ワクチンとしては不必要なウイルス成分の脂肪が除かれているので、副作用がそれだけ軽減される。1972年(昭和47)以来、それまでの不活化したウイルス粒子(全粒子)を用いたワクチンからこのHAワクチンに切り替えられている。
現在のワクチンにはA型(香港型、ソ連型)およびB型が含まれており、いずれの型が流行しても対応できる。さらにウイルスの連続変異に対応するため、毎年製造のワクチン株の選択にも考慮が払われている。一般にワクチンの予防効果は70~80%程度とされている。13歳未満では1~4週間の間隔で2回、成人では通常1回、皮下に注射するが、注射後1~2週間から3~6か月間くらい予防効果が期待できる。したがって、流行期より以前の10~11月ころに注射するが、効果の持続期間が短いことと、年々流行してくるウイルスの型がすこしずつ変わる傾向があり、ワクチンもそれに対応してつくられるので、毎年予防注射を受けることが必要となる。
肺炎を合併しやすい素因をもつ人には、とくにワクチン接種が勧められるが、その場合には既存の病気その他に対する慎重な配慮が必要である。また、ワクチンはウイルスを孵化(ふか)鶏卵で培養してつくるため、鶏卵アレルギーの人は注射を避ける。ワクチンの副作用としては、注射部位が赤く腫(は)れたり痛みがあるほか、熱や全身のだるい感じなどがみられることがあるが、その出現頻度は低く、また一般に軽度で、特別の処置を要することはほとんどない。
また、ワクチンのほかに、流行が発生した場合、休校や学級閉鎖などの措置をとって流行の拡大を食い止めるように努める。休校の期間は2、3日では不十分なことが多く、5日程度が望ましいとされる。
[加地正郎]
インフルエンザウイルス
オルトミクソウイルスOrthomyxovirusに属するウイルス。1本鎖RNA(リボ核酸)ウイルスで、A型、B型、C型がある。
インフルエンザウイルス粒子は球状で80~120ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)、カプシド(ウイルス核酸と結合タンパク質を取り巻くタンパク質殻)は螺旋(らせん)対称形エンベロープ(外被)を形成する。ゲノム1本鎖RNAは線状で、A型は8分節、C型は7分節、各遺伝子ごとに分節している。第7分節、第8分節RNAから転写されるmRNA(メッセンジャーRNA)には長いRNAと短いRNAがあり、それぞれから異なったタンパク質が翻訳される。全分子量は4~5×106ダルトン(1ダルトンは1.661×10-27キログラム)、全塩基総数13~15×103塩基。各型の原形ウイルスについては全塩基配列も決定されている。ウイルスRNAは核タンパク質が螺旋対称状に配列し、それに3種類のRNAポリメラーゼ(RNA鋳型からのRNA形成を触媒する酵素。PA、PB1、PB2)が結合してヌクレオカプシド(カプシドに直接取り込まれているウイルスの核酸)を形成する。8本のヌクレオカプシドはエンベロープに包まれる。直径80~120ナノメートル、球状、ときには多形態性を示す。エンベロープは細胞膜脂質二重層を基本単位とする。赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼneuraminidase(NA)がスパイク状に外面に突出している。膜タンパク質membrane protein(M1)といわれる粒子は脂質二重層を裏打ちするように粒子が配列し、膜タンパク質(M2)は4本が束のような形となり、二重層を貫通したように、内側から外側に突き出したようになっている。イオンチャンネルとしての役割をもつ。
インフルエンザウイルスが宿主(しゅくしゅ)(ウイルスの寄生対象となる生物)細胞に感染するとHAタンパク質が分解酵素によってHA1とHA2に開裂する。H1は細胞表面のシアル酸レセプター(受容体)に吸着し、細胞内に取り込まれる。エンドソーム内へは酸性条件下でHA2が働きウイルスエンベロープ脂質二重層とエンドソーム膜脂質二重層と融合がおこり、ヌクレオカプシドが細胞内に放出される。次にヌクレオカプシドに付着しているRNAポリメラーゼ(PA、PB1、PB2)がウイルスゲノムRNAを転写して、プラス鎖mRNAを合成する。
このmRNAと宿主のつくる新しいmRNAとウイルスの塩基配列が初動的役割を果たし、PB2、PB1、PAの順番で誘導、転写が進行する。感染初期にはRNAポリメラーゼ、核タンパク質、非構造タンパク質の合成が先行し、ゲノムRNAの複製とヌクレオカプシドの形成が進む。感染後期になって膜タンパク質、赤血球凝集素、ノイラミニダーゼの合成促進と細胞膜への輸送によってエンベロープ構造ができあがる。次に8種類のヌクレオカプシド1組がエンベロープを周囲にもちながら出芽する。出芽直後のウイルス粒子は、ノイラミニダーゼが周囲のシアル酸基を切断することにより、細胞表面から遊離する。
インフルエンザウイルスは核タンパク質や膜タンパク質の抗原性によりA型、B型、C型の3タイプに分類する。
(1)インフルエンザA型ウイルス 赤血球凝集素(HA)の血清型は16種(H1~H16)、ノイラミニダーゼ(NA)の血清型は9種(N1~N9)、このHA血清型とNA血清型を組み合わせると、理論上は144亜種が存在することになる。カモ、アヒル、シチメンチョウなどの鳥類からはHA、NAの血清型のすべてが発見されている。現在まで70余の亜種株が分離固定されている。ヒトから分離されたインフルエンザA型ウイルスはH1N1、H2N2、H2N2の3亜種である。ウマやブタも自然宿主となる。ウマやブタなどの動物のインフルエンザウイルスはヒトに感染伝播することはないと考えられる。
(2)インフルエンザB型ウイルス HA、NAの血清型が各1種類だけで、亜種はない。自然宿主もヒトだけである。
(3)インフルエンザC型ウイルス A型、B型とは異なり、独特なものである。A型のノイラミニダーゼに当たるRNA分節が欠落しているからで、ヘマグルチニン‐エステラーゼhemagglutinin-esterase(HE)によって分類される。亜種はなく、自然宿主もヒトだけである。
[曽根田正己]
『永武毅編『インフルエンザQ&A』(2000・医薬ジャーナル社)』▽『泉孝英・長井苑子編『医療者のためのインフルエンザの知識』(2005・医学書院)』▽『加地正郎著『かぜへの挑戦』(講談社・ブルーバックス)』▽『加地正郎著『インフルエンザの世紀――「スペインかぜ」から「鳥インフルエンザ」まで』(平凡社新書)』▽『W・I・B・ビヴァリッジ著、林雄次郎訳『インフルエンザ』(岩波新書)』▽『中島捷久・中島節子・沢井仁著『インフルエンザ――新型ウイルスはいかに出現するか』(PHP新書)』
六訂版 家庭医学大全科 「インフルエンザ」の解説
インフルエンザ
Influenza
(呼吸器の病気)
どんな病気か
インフルエンザウイルスの感染による炎症です。ヒトからヒトへ感染しやすく、数年に一度大流行が起こります。また、気管支炎や肺炎だけでなく、心不全や脳症などを併発し、死亡率の高い病気です。高齢になるほど、および年齢が低いほど死亡率が高く(図4)、大流行の時には日本でも数万人、あるいはそれ以上が死亡しています。
インフルエンザウイルスはヒトの体内で爆発的に増えます。ウイルスは約8時間で100倍に増えるので、1個のウイルスは24時間後には100万個になります。数千万個にまで増えると症状が現れるので最初に数十個のウイルスに感染すると約1日後には症状が出始めます。潜伏期(感染してから症状が出始めるまでの時間)が極めて短いわけですが、これがインフルエンザの大きな特徴であり、爆発的に広がる原因のひとつです。
インフルエンザウイルスはいつまで体内で増加し続けるのでしょう。実は感染後2~3日でウイルスの数は最大になり、その後は免疫抗体ができるため、増えた時と同じような速度で減り始めます(図5)。感染して5~6日後には体内からインフルエンザウイルスはほとんどいなくなりますが、多くの場合はまだ発熱が続いています。ウイルスを退治するために役立つ物質(炎症性サイトカイン)が過剰につくられるため、症状を持続させるからだといわれています。
原因は何か
ヒトに感染するインフルエンザウイルスにはA型、B型、C型の3つがあります。A型とB型は重症になりやすく、とくにA型ではウイルスの表面にあるスパイク(感染の際に役立つとげや爪のようなもの)が時々姿を大きく変えるためにワクチンが効かなくなります。これを
最も有名なのは1910年代後半のスペインかぜです。青壮年から高齢者まで世界中で4000万人が、日本でも38万人以上が死亡しました。当時の日本の人口は現在の半分ですから、現在同じことが起こったら80万人近くが亡くなる計算になります。しかし、2009年春から出現した豚由来の新型インフルエンザでは、診断や治療法の向上もあってそのような大きな被害は出ていないようです。
患者さんの
吸い込まれたインフルエンザウイルスは、自分の体の表面のヘムアグルチニンというスパイクで気道の粘膜に吸着し、細胞に侵入します。侵入したウイルスは細胞の仕組みを利用して自分の遺伝子を増殖させ、自分と同じ姿の子どもをたくさんつくります。生まれた子どもは細胞の外へ出て、まだ感染していない細胞へ感染し、同じように自分の子どもを多数複製します。
ウイルスが細胞の外へ出る時に役立つもうひとつのスパイクをノイラミニダーゼといいますが、後で述べるインフルエンザウイルスに直接効く薬は、このノイラミニダーゼのはたらきを抑えてしまうのです。それ以外にもインフルエンザウイルスが感染する仕組みを抑えてしまう薬が多数、開発されつつあります。
症状の現れ方
インフルエンザは、潜伏期が極めて短いのが特徴です。感染して1~2日後に体のだるい感じや寒気、のどや鼻の乾いた感じ(
発症の3~5日後ころに急に解熱して起き上がれるようになりますが、体力の回復には1~2週間が必要です。気力の回復にも意外と時間がかかります。ところが、高齢者や普段から治療を要する慢性の病気をもっている人、妊婦や年少者などではこれだけにとどまらないことが多いのです。発病の早期から気管支炎や肺炎、さらには脱水症状や心不全、呼吸不全を合併しやすく、不幸な結果になる人も出てきます。そうした状況に陥るまでの時間が極めて短いのがインフルエンザの特徴で、早めの対応が求められます。
検査と診断
流行の初期にはインフルエンザの診断は意外に難しいものです。医師はまず病歴を詳しく聞き出しますが、自分の周囲の流行状況を含めて前項の「
これは、鼻の奥やのどなどを綿棒でこすり、そのなかにインフルエンザウイルスだけがもっている特有な部品(
インフルエンザは感冒より重症なので、血液検査やX線検査の回数が増えます。インフルエンザの場合にも他の似た病気が隠れていることがあります。区別すべき最大の病気は他の感冒、肺炎などで、それらとの区別は極めて重要です。
治療の方法
インフルエンザの治療も大きく2つに分けられます。対症療法がそのひとつですが、症状が感冒より強い分、しっかりと行う必要があります。
一部の解熱薬が乳幼児の脳炎や脳症の発症に関連しているのではないかといわれていますが、まだ明確ではありません。ただ、否定できるわけではないので、疑わしい薬剤については気をつけるべきです。それらのなかで安全性が高い解熱薬はアセトアミノフェンです。
原因療法では、数年前からインフルエンザウイルスに直接効く薬が使われています。インフルエンザウイルスがヒトの細胞に感染する最初の過程を抑えるアマンタジン(シンメトレル)、複製された子どものウイルスが細胞から出て行く過程を抑えるザナミビル(リレンザ)とオセルタミビル(タミフル)です。
後二者については、有効成分をまったく含まない薬(プラセボ)と効果を比較した試験で、はるかによく効くことが確かめられました。肺炎などの重症の合併症を併発する率もはるかに低いことが確かめられましたが、直接ウイルスに効く薬のため、ウイルスが体内で減り始める3日目以降には効き目が極端に落ちてしまいます。インフルエンザの治療に関しても早期治療が重要です。
病気に気づいたらどうする
インフルエンザでは早期受診、早期診断、早期治療開始が重要であることを力説してきました。合併症を併発しやすい人や重症化しやすい人ではとくに重要です。「感冒(かぜ)」の項でインフルエンザワクチンを打つべき人としてあげた人たちは、ワクチンを打って予防するだけでなく、発症したらすぐに医師の診察を受けることが大切です。
予防の方法
予防の基本はワクチンの接種です。ワクチンはかかるのを防ぐのではなく、重症化を抑えるものであることもあって、いまだにインフルエンザワクチンは効かないと思っている人もいますが、ワクチンの効果は内外ですでに実証されています。
海外では20万人以上を対象に、ワクチンを打った人と打たなかった人とに分けて調査した成績が複数あります。いずれもワクチン接種によって、インフルエンザや肺炎による入院患者数が30~60%減り、死亡者数が50~70%減っただけでなく、脳血管疾患(脳出血や
米国では、肺炎の原因菌として最も多い肺炎球菌に対するワクチンも普及していますが、2つのワクチンを打つとさらに効果のあることが実証されています。肺炎球菌ワクチンを打つべきとしてすすめられているのは、インフルエンザワクチン接種をすすめられている人とほとんど重なります。日本でも普及し始めているので、医師に相談してください。
渡辺 彰
インフルエンザ
Influenza
(感染症)
どんな感染症か
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって起こるウイルス性呼吸器感染症です。世界中で、全年齢にみられる普遍的で最も頻度の高い重要な病気で、小児と高齢者で重症化しやすいとされています。流行の規模は一定ではありませんが、毎年冬季に流行がみられ、学級閉鎖の原因や、高齢者施設における施設内流行の原因にもなります。
A・B・C型のインフルエンザウイルスがありますが、臨床的に問題になるのは、A型の2亜型(Aソ連型とA香港型)とB型です。2009年春には豚由来の新型インフルエンザウイルスA型が出現しました。このウイルスはその後世界中に広まり、WHO(世界保健機関)は6月にパンデミック(世界的大流行)の宣言をしました。日本においても同年の秋から冬にかけて、小児を中心に非常にたくさんの方が感染しました。インフルエンザはヒトの鼻咽頭で増殖したウイルスが、飛沫感染でほかのヒトの鼻咽頭の細胞に感染して発症します。
症状の現れ方
いずれの型のインフルエンザも1~3日の潜伏期をへて、悪寒を伴う高熱、全身
症状の程度・持続期間は、流行ウイルスの種類、年齢、過去の罹患状況などによってさまざまですが、合併症がない場合、1週間~10日以内に軽快します。発症した場合の重症度は、ウイルス側の要因(前回の流行からの期間やウイルスの変異の度合い)と、個体側の要因(感染歴や免疫状態)などによって決まります。
乳幼児は初感染であることが多く、成人に比べて重症化しやすく、また高熱による熱性けいれんを起こすことがあります。細菌性の肺炎や中耳炎の合併があると高熱が続きます。
検査と診断
咽頭ぬぐい液や鼻汁材料を用いた、インフルエンザの抗原検出キットで10~15分の短時間に判定することができ、A・B型の判別も可能です。
血清反応による診断では、発症時と2~4週後のペア血清でCF(インフルエンザ共通抗原)、HI(型特異的抗原)抗体価の有意な上昇でわかります。臨床ウイルス学的にはウイルスの分離を行い、流行株の抗原的性状を解析します。
治療の方法
対症療法が主体になります。高熱に対しては冷却とともに、アセトアミノフェン(カロナール)などの解熱薬を使います。呼吸器症状に対しては
特異的な治療法として、抗ウイルス薬があります。A型に対してはアマンタジン(シンメトレル)がありましたが、近年、耐性ウイルスが出現したため使用されなくなりました。A・B型両方に効果があるものとして、ノイラミニダーゼ阻害薬(タミフル、リレンザ)が用いられていますが、近年タミフル耐性のAソ連型ウイルスが出現し、世界中に広まりました。一方、前述の豚由来新型インフルエンザウイルスA型に対してはタミフル、リレンザとも効果があります。いずれも発症2日以内の使用開始が効果的です。
予防の方法
現在、不活化インフルエンザワクチンの皮下接種が、主にリスクの高い人に対して、重い合併症を予防する目的で行われています。65歳以上の高齢者と、60歳以上の心肺疾患をもつ人が対象で、法律による接種が可能になっています。
乳幼児に対するワクチンの予防効果や軽症化については、現在研究中です。
病気に気づいたらどうする
飛沫によって他人に感染するので、一般的に発熱などの主要症状がなくなるまで登校や出社は停止します。家庭でも感染予防のため、患者さんの気道分泌物の付着した物の扱いに注意し、手洗いとうがいを励行します。
堤 裕幸
インフルエンザ
Influenza
(お年寄りの病気)
高齢者での特殊事情
インフルエンザは、一般にもよく知られるウイルス感染症です。ヒトのインフルエンザウイルスは1933年に分離され、ワクチンが実用化され改良が続けられていますが、今なお、世界中で流行がみられ、毎年問題となる重要な流行性感冒です。小児ではインフルエンザ脳炎(のうえん)・
インフルエンザウイルスは自然状態では細長い形をしており、大きさが約100nmの多形性のウイルスです。ウイルス周囲にヘマグルチニン(Hemagglutinin:赤血球凝集素)、ノイラミニダーゼ(Neuraminidase)などの突起をもっています。インフルエンザウイルスの感染や抗体による防御は、このヘマグルチニン、ノイラミニダーゼのはたらきが重要で、ウイルスの型を示す時に用いられるH、Nはそれぞれの頭文字からきています。
2009年5月より世界的に流行したウイルスはH1N1というタイプでした。swine(猪豚)に由来し、豚インフルエンザと訳されて風評被害が広がったため、新型インフルエンザと呼ばれました。このウイルスは、若年者を中心に猛威をふるいましたが、高齢者の感染は少なく、重症化もわずかでした。そこで、昔流行したウイルスと類似し、高齢者が免疫をもっていた可能性が考えられます。対策として、ワクチンの接種を受けるとともに、日々の体調管理が重要になります。手洗い、外出時のマスクや眼鏡(ゴーグル)の装着、人込みを避けるなどの基本的な注意を行うべきです。
一方、鳥インフルエンザとして流行が危惧されるH5N1は、感染力は低いが、ひとたび感染が起こると強毒性で死亡率が高いものです。高齢者、とくに糖尿病、
治療とケアのポイント
インフルエンザ予防の基本は、ワクチン療法です。流行状況の把握と予測技術の発達によって、ワクチンの有効性も高まっていますが、ウイルスは、年単位で抗原性が変化する連続抗原変異(小変異)と、数年から数10年単位で突然、別の亜型に代わる不連続抗原変異(大変異)を生ずるため、完全な予防は不可能です。
新型ウイルスの鳥インフルエンザウイルスについても、世界中でワクチン開発が行われており、実用化は近いが、ワクチン自体の安全性とともに、国民すべてにいきわたるかなど、供給面の問題も残っています。
また近年、ノイラミニダーゼ阻害薬というインフルエンザ専用の薬(タミフルやリレンザ)が開発されました。この薬はノイラミニダーゼを選択的に阻害することにより、ウイルス粒子の宿主細胞からの遊離・放出を阻止し、ウイルスの増殖を抑制します。発症早期に服薬を開始するほど効果が高くなります。
ノイラミニダーゼ阻害薬はインフルエンザ予防にも有効です。まだ感染していない高齢者が内服すると、発症しにくくなります。ただし、費用が高く、現時点で予防投与は認められていません。また、鳥インフルエンザでは、ノイラミニダーゼ阻害薬耐性ウイルスが見つかっており、今後、ノイラミニダーゼ阻害薬が効果を発揮しないウイルスの流行が心配されています。
インフルエンザウイルスは、飛沫感染であるため、人込みに出るのは、危険です。流行期は外出を避け、食料を備蓄して、人との接触を避けることです。外出時には、粘膜(眼球結膜)からの感染があり得るので、マスクをするとともにゴーグルも使用することが予防策として重要になります。また手洗いは、すべての感冒予防策として重要ですが、飛沫感染を主とするインフルエンザ感染については、必ずしも重要性は高くありません。
寺本 信嗣
インフルエンザ
Influenza
(子どもの病気)
どんな病気か
流行するインフルエンザの原因ウイルスにはA型とB型があります。ともに、変異といって少しずつ形を変える性質があるため、私たちは十分な抗体を作ることができず、何度でも感染してしまうのです。
症状の現れ方
例年12~3月下旬が流行期です。潜伏期は1~3日で、突然の高熱(39℃以上)で、ぐったりする症状(全身
成人や年長者では関節痛や筋肉痛があり特徴的ですが、乳幼児はその症状のはっきりしないことが多い傾向があります。
合併症として気管支炎、肺炎、
検査と診断
高熱にもかかわらず、のどの発赤が軽い傾向があり、以前は症状で判断していましたが、近年、鼻の粘膜を綿棒でこすって抗原を調べる検査ができるようになり、軽症のインフルエンザ患者さんが診断されるようになりました。もちろん、この検査も万能ではありません。
発熱してすぐの場合や逆に数日たったあとでは、インフルエンザであっても検査で陰性となる可能性もあります。
治療の方法
安静と十分な睡眠、水分・栄養補給が大切です。以前は特効薬はありませんでしたが、近年、オセルタミビル(タミフル)、ザナミビル(リレンザ)というインフルエンザウイルスを殺す薬(抗ウイルス薬)が使えるようになりました。
インフルエンザにかかった10代の患者さんが精神症状を呈し、インフルエンザ治療薬(タミフル)との関連が疑われていますが、インフルエンザだけでも精神症状が出ることも指摘されており、薬剤の是非についての結論は出ていません。
一方、解熱薬の使用と脳症の発症に因果関係があることは、ある程度明らかになっています。アセトアミノフェン(アンヒバ、カロナールなど)以外の解熱薬の使用は、脳症時の死亡率を上げます。熱が高いからといって解熱薬を乱用するのではなく、安静と水分補給に努めるべきです。
予防法
流行期には外出をひかえ、帰宅時には手や顔を洗い、うがいをすることが大切です。また、前述のように、脳症の発症は発熱してすぐのことが多く、病院受診前にけいれんや意識障害を起こすこともあります。したがって、発病してから治療するよりも、予防が大切です。
予防するための唯一の方法は予防接種です。予防接種してもインフルエンザにかかることはありますが、重症化を抑える期待はできます。
新型インフルエンザと季節性との違い
世界で2009年10月末現在で500名弱が感染し、約半数が死亡している鳥インフルエンザA型(H5N1)の流行が危惧されていましたが、2009年に、豚由来のインフルエンザA型(パンデミックH1N1 2009)の流行が始まりました。
パンデミックH1N1 2009の特徴は、感染力が強いこと(患者1人が感染させる人数は2.0~2.3人、季節性は1.3人)、肺でウイルスが増殖するため、喘息をはじめとする呼吸器の慢性疾患を抱えている人や、免疫が弱まっている妊婦さん、糖尿病、各種の難病治療中の患者さんが重症化しやすいことにあります。また、季節性では乳幼児に多い脳症が、小学校低学年をピークに発症している傾向があります。ただし、これは抗体をもたない私たちにとって初めての流行のためかもしれず、今後の推移を注意深く検討する必要があります。
是松 聖悟
出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「インフルエンザ」の意味・わかりやすい解説
インフルエンザ
influenza
流行性感冒,略して流感ともいわれ,インフルエンザウイルスによって起こる感染症の一つ。突然の発熱,頭痛,悪寒,だるさ,咳,筋肉痛などがあり,上気道,鼻腔,結膜などに炎症が起こる。冬季に多い。インフルエンザウイルスはRNAウイルスで,A,B,Cの諸型に分けられ,A,B型はさらにいくつかの亜型に分けられる。流行するインフルエンザウイルスの型は年によって異なる。通常いろいろの地域に散発的に流行するが,しばしば世界的な大流行がみられる。感染は上気道からの飛沫感染とされ,潜伏期は1~4日。発熱はふつう3~5日継続する。インフルエンザウイルス以外による感染症でも,同じような上気道の炎症で始まることが多く,とくに感冒症候群(風邪)と呼ばれているものとは区別しにくい。感冒症候群は明確な流行の形をとらない場合が多いが,確実な診断は血清学的検査によってインフルエンザウイルスに対する抗体価を測定する以外に方法はない。インフルエンザウイルスに感染したあと,二次的に他の細菌などに感染することも多い。気道粘膜はインフルエンザウイルスに侵されて壊死に陥るが,これが二次的に他の病原体の感染の温床となり,急性の副鼻腔炎,中耳炎,化膿性気管支炎,気管支枝炎,肺炎,気管支拡張症などを引き起こし,ときには心囊炎,心筋炎を合併することもある。このように悪質な合併症があるので,インフルエンザを軽視してはならない。
インフルエンザウイルス自体に有効な治療薬は現在まだ発見されていないので,人体のもつ抵抗力によって自然に治るのを待つわけであるが,それを助ける意味で,まず安静,それに鎮咳(ちんがい)剤,解熱剤などを用い,合併症を引き起こさないようにすることが第一である。合併症を起こすと,慢性化しやすいので恐れられたが,近年は合併症の治療に抗生物質が用いられ,そのおかげで重症で致命的な合併症はみられなくなった。インフルエンザの症状が激しいときには最初から抗生物質を用いたほうが安全な場合もある。
予防にはワクチン注射があり,1~2週間の間隔で2回行う。この有効性は数ヵ月から1年間は持続するといわれる。流行するウイルスの型とワクチンのウイルスの型が違うと効果は少ないので,ワクチンは最近流行した二,三の型のウイルスを用いて作られる。
執筆者:高谷 治
インフルエンザウイルスMyxovirus influenzae
ミクソウイルス属のRNAウイルスで,長さ80~120mμ,球形のものが多いが,線形のものもある。大きくA,B,Cの3型に分けられ,A型はさらにA0,A1,A2などの亜型に,B型もB1,B1a,B1b,B2などの亜型に分けられるが,変異の度合はA型のほうが大きい。またA型ウイルスは抗原構造が少しずつ変化し,ときに急激に変化するという特徴をもっている。この急激な変化を不連続変化という。インフルエンザウイルスに感染すると,その型のウイルスに対する免疫を獲得するが,不連続変化によって新型のウイルスが生じると,大流行を起こすことになる。B型ウイルスにも抗原構造の変異はあるが,A型の場合よりは小さく,流行の度合もA型のほうが強い。病原ウイルスの同定は,患者のうがい水から孵化(ふか)鶏卵培養法によって,ウイルスを分離するか,適当なウイルスの抗原を用い,血清学的に補体結合反応あるいは血球凝集抑制反応によって判断する。
執筆者:川口 啓明
インフルエンザワクチン
インフルエンザの流行型は毎年のように変わるが,ワクチンの生産開始は,流行の半年から1年も前なので,流行株の予想は立てても,当然,当り外れがある。かりに予想が的中しても効果は80%程度である。また,少数ではあるが重い副作用もある。このため,集団接種に反対する医師もいる。なお,児童に集団接種しているのは日本だけである。
→ワクチン
執筆者:矢田 透
疾病史
近代医学の発達により,ペスト,コレラ,痘瘡(とうそう)などの疫病がほとんど征服された今日でも,インフルエンザだけは世界的流行をくりかえし,人類最後の疫病といわれている。この疫病はギリシア時代から知られていたが,近代までは記録が欠けているため,正確な年代記はたどれない。18~19世紀には文明世界では16回の世界的流行があったことが知られ,とくに1847年の流行ではロンドンで25万の死者を数え,89年には〈旧アジア風邪〉といわれる大流行があった。インフルエンザは周期的に流行することがその特徴であり,ほぼ10年ほどの間隔で大小の流行をくりかえしている。
インフルエンザ流行史でとび抜けて大きな災厄をもたらしたのは,〈スペイン風邪〉として知られる1918-19年の世界的大流行で,かつてのペスト(黒死病)の惨禍を想起させる疫病史上の一大事件となった。その原発地について,最も可能性の高いのはアメリカと中国であった。1918年早春,アメリカの兵営でインフルエンザの発生があり,ときあたかも第1次大戦のさなか,4月にはフランス戦線に感染し,4月末にはスペインに広がり,6月イギリスにこれが移り,〈スペイン風邪〉と呼ばれるにいたった。これとほぼ同時に,中国本土と日本の海軍でインフルエンザ発生が報告され,5月に中国全土にまんえんした。大戦終結の年にあたる18年はヨーロッパに世界各地から兵士と労働者が集まり,インフルエンザ流行の絶好の状況のなかで,第2波がヨーロッパを席巻し,数週間のうちに世界中の兵士と市民を襲い,地球上の住民の約半数が罹患したという。第3波は翌年の冬に起こり,これまで免れていた地域を襲い,多くの人命を奪った。その伝染力はすさまじく,潜伏期もきわめて短く,ある日たった1人の患者しかいなかった軍隊で,翌日は数百人の患者が発生するというほどであった。とくに20~40歳の働きざかりの人々に重症者が多く,肺炎の合併症が死亡のおもな原因であった。このインフルエンザによる死者は,アメリカで40万人以上,イギリスで20万人,インドでは500万人といわれる。世界中でこのインフルエンザにより,約2500万人の死者を算したと推定され,細菌学的医学の勝利に冷水をあびせ,大戦の死者をはるかにしのぐ伝染病の猛威のまえに,〈疫病の時代はまだ去っていない〉と疫学者をして嘆じさせた。日本でも罹患者2500万,死者38万余という,これまでにない惨禍をもたらした。
続いて57-58年の〈アジア風邪〉の世界的流行が記憶に新しい。中国に原発したそれは地球上の全域を侵し,日本でも人口の半数が罹患したといわれるが,幸いにも多数の人命を奪うということはなかった。しかしこのアジア風邪の伝播速度は,スペイン風邪のそれよりはるかに速かった。アジア風邪ウイルスは,1957年2月から11月までの10ヵ月で世界を一周した。それはいうまでもなく現代人の移動の頻繁さと迅速さに起因している。密集した集団生活,満員の交通機関,迅速な航空輸送など,現代の社会環境が世界中の人々をほとんど同時に侵襲するインフルエンザの爆発的な性格をつくったのである。
日本では,とくに江戸時代後期,つまり18世紀後半から19世紀前半にかけて,古書で風邪(ふうじや)・風疫・感冒などと呼ばれたインフルエンザの大流行をたびたび記録している。それらの流行は,世事にちなんで〈お駒風〉〈谷風〉〈お七風〉〈アメリカ風〉などの呼名がつけられ,いずれも全国的に猛威をふるい,多数の死者を数え,社会生活に大きな影響を及ぼした。そして,その大半は18世紀末から19世紀初頭のいわゆる異常厳冬期に集中・発生している。近世日本のインフルエンザの発生・伝播の経路をみると,ほとんどの流行がまず長崎に発生し,続いて中国地方から上方(かみがた)を経て関東に到達,さらに奥羽へと東進している。このことは,長崎が当時唯一の外国に開かれた門戸であったからであり,またインフルエンザが舶来の伝染病であったことを裏書きするものである。
→風邪(かぜ)
執筆者:立川 昭二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
家庭医学館 「インフルエンザ」の解説
いんふるえんざ【インフルエンザ Influenza】
[どんな病気か]
インフルエンザウイルスが感染することによっておこり、全身症状が激しく、大流行をくり返すのがインフルエンザの特徴です。
肺炎(はいえん)などの重い合併症をひきおこしやすく、もともとあった慢性の病気を急に悪くしたりします。
●どのように感染するのか
インフルエンザは、患者さんのウイルスを含む分泌物(ぶんぴつぶつ)が、せきなどで小さなしぶきとして空中にただよい、それを吸い込むことで感染することが多く、マスクやうがいをしても、ほとんど感染が防げません。手洗いでも十分には侵入を防げません(図「かぜ・インフルエンザウイルスの感染経路」)。
●インフルエンザウイルスの種類と型
A型、B型、C型があります。
感染の流行が問題になるのは、A型とB型です。A型は何十年かに1回、免疫(「免疫のしくみとはたらき」)のしくみがウイルスをとらえるときの特徴である血清型(けっせいがた)を変えて変身するため、世界的な大流行(パンデミー)をおこします。
[症状]
鼻水、せきなどの呼吸器の症状よりも、全身の症状が先に現われるのが特徴です。
全身の症状というのは、突然に現われる高熱(38℃以上になることも多い)、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感(けんたいかん)(だるさ)で、重症感(「重い病気だ!」という感じ)が強いことも特徴の1つです。
事実、肺炎のような重い病気に進むこともあり、慢性の病気を急に悪くすることが知られています。
発熱は3日ほど続き、少し遅れて鼻かぜ、のどかぜの症状が現われてきます。それも3~4日目がピークで、しだいにやわらいできます。
合併症がなければ7日ほどで自然に治ります。ただし、せきなどが長引くことがあります。
症状はA型のほうが重く、新しい血清型(けっせいがた)のウイルスが流行(パンデミー)するときは、人類に抵抗力ができていないので、より重症になります。
●合併症について
よくひきおこされ重症化しやすいのは、ウイルス肺炎(「非細菌性市中肺炎」のウイルス肺炎)や二次感染(ウイルスの感染につづいての感染なので二次という)による細菌性肺炎です。3日以上解熱(げねつ)しない、一度下がった熱がまた上がった、膿(うみ)のようなたんが出る、呼吸が困難、胸痛などの症状が出てきたら、すぐ医師の診察を受けましょう。
喫煙者や高齢者、慢性の病気(表「インフルエンザによる重症化や合併症の可能性の高い人」)がある人の場合は重症になったり、ほかの病気をともなったりしやすいので注意が必要です。心筋炎(しんきんえん)、心外膜炎(しんがいまくえん)、脳炎(のうえん)、髄膜炎(ずいまくえん)などをともなうこともあります。
合併症で、もう1つ重要なのは、もともとある慢性の病気が急に悪くなる場合です。
ぜんそく、肺気腫(はいきしゅ)など慢性の呼吸器の病気、心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう)、慢性うっ血性心不全(けつせいしんふぜん)のある人は、とくに注意する必要があります。
◎重症化しやすいので注意を
[治療]
かぜと同様で、対症療法と一般療法がおもですが、重症になりやすいので注意が必要です。
子どものインフルエンザにアスピリンを使うと、ライ症候群(けいれん、意識障害、肝臓障害をおこす死亡率の高い病気(コラム「ライ症候群」))をおこす可能性があるといわれているため、どうしても熱を下げなければならないときは、ほかの解熱薬が勧められています。
[予防]
現在、日本では、インフルエンザの感染と重症化の予防が期待できるのは、インフルエンザワクチンの接種ですが、日本でもアマンタジン内服による予防が、特別な場合のみ認められました。もちろん医師による処方が必要です。
また、抵抗力が弱っている人をインフルエンザに感染している可能性のある人と接触させないように、引き離すこともあります。
百科事典マイペディア 「インフルエンザ」の意味・わかりやすい解説
インフルエンザ
→関連項目ウイルス病|風邪|学校伝染病|咳|伝染病|届出伝染病|飛沫感染|ライ症候群|流行性感冒
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
知恵蔵 「インフルエンザ」の解説
インフルエンザ
(今西二郎 京都府立医科大学大学院教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「インフルエンザ」の意味・わかりやすい解説
インフルエンザ
influenza
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「インフルエンザ」の解説
インフルエンザ
世界大百科事典(旧版)内のインフルエンザの言及
【杆菌】より
…長さの短いものは短杆菌,長いものは長杆菌と呼ばれる。短杆菌は,インフルエンザ杆菌のように,長さが短いために球菌と区別しがたいものがある(インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされるが,インフルエンザ杆菌は二次的な合併症を引き起こす病原菌の一つである)。杆菌には,細菌が連鎖状に連なった連鎖杆菌や,コリネ型菌のように,複数の細菌がくっついてV・Y・L字形や平行状の配列をとるものがいる。…
【気管支炎】より
…原因は種々のウイルスや細菌の感染によるものが多いが,塩素ガスなど化学性刺激ガスの吸入でも起こる。前者の代表的なものは,インフルエンザ(流行性感冒,流感)によるものである。治療は,鎮咳(ちんがい)剤や去痰剤を服用するが,膿のような痰が出て細菌感染が疑われるときは抗生物質が使われる。…
※「インフルエンザ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...