翻訳|grammar
精選版 日本国語大辞典 「文法」の意味・読み・例文・類語
ぶん‐ぽう‥パフ【文法】
- 〘 名詞 〙
- ① 法令の成文。法規の条文。
- [初出の実例]「国司乖二文法一以廻二方略一、違二正道一以施二権議一」(出典:菅家文草(900頃)九・請令議者反覆撿税使可否状)
- [その他の文献]〔史記‐汲黯伝〕
- ② 文章を構成するきまりや文章の規範。また、文章の作法。
- [初出の実例]「史記が文法になるぞ。題目も何代史も此史記を本にするぞ」(出典:史記抄(1477)三)
- ③ 語句・文章に修飾や誇張をほどこすこと。文章のあや。文飾。
- [初出の実例]「牛若丸の武功を称美せんとて、かく百余人と沙汰するやと申に、全く是文法(ブンホウ)にあらず」(出典:浮世草子・風流誮平家(1715)四)
- ④ 言語学の対象の一つ。小さい言語単位が連接して大きい単位を形づくるときの法則性、また、その規範。普通、単語・文節・文の範囲で説かれるが、語構成や文連接、文章構成の問題を含んでいうこともある。
- [初出の実例]「其学科は新古語を探索し文法を学び歴史を読み」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉初)
改訂新版 世界大百科事典 「文法」の意味・わかりやすい解説
文法 (ぶんぽう)
grammar
概説
文法とは
一般に文法と呼ばれているものは,当該の言語における,(1)単語が連結して文をなす場合のきまり(仕組み)や,(2)語形変化・語構成[派生語や複合語のでき方]などのきまり(仕組み),あるいはまた(3)機能語[助動詞・助詞・前置詞・接辞・代名詞等]の用い方のきまり(仕組み),とほぼいえるであろう。
たとえば, 〈ねこがねずみを食べた。〉は日本語のまっとうな文であり,これを〈ねずみをねこが食べた。〉と言いかえてもやはりまっとうな文であるが,一方,これを〈ねこが食べたねずみを。〉のような語順で言いかえたり,〈ねこねずみ食べた。〉と言ったりすれば,まっとうな文にはならない((1)の例)。また,
〈ねこがねずみを食べた。〉は日本語のまっとうな文であり,これを〈ねずみをねこが食べた。〉と言いかえてもやはりまっとうな文であるが,一方,これを〈ねこが食べたねずみを。〉のような語順で言いかえたり,〈ねこねずみ食べた。〉と言ったりすれば,まっとうな文にはならない((1)の例)。また, 〈美しい〉と〈きれい(綺麗)〉とは,前者が〈美しかった〉〈美しくない〉などと変化(活用)し,〈美しさ〉という派生名詞を有するのに対し,後者に同じ要領(〈い〉を〈かった〉〈くない〉〈さ〉に変える)をあてはめて〈きれかった〉〈きれくない〉〈きれさ〉と言うことはできず,〈きれいだった〉〈きれいでない〉〈きれいさ〉と言う((2)の例。もっとも,〈きれいさ〉という名詞形には抵抗を感じる向きもあるかも知れないが)。これら
〈美しい〉と〈きれい(綺麗)〉とは,前者が〈美しかった〉〈美しくない〉などと変化(活用)し,〈美しさ〉という派生名詞を有するのに対し,後者に同じ要領(〈い〉を〈かった〉〈くない〉〈さ〉に変える)をあてはめて〈きれかった〉〈きれくない〉〈きれさ〉と言うことはできず,〈きれいだった〉〈きれいでない〉〈きれいさ〉と言う((2)の例。もっとも,〈きれいさ〉という名詞形には抵抗を感じる向きもあるかも知れないが)。これら
 は,いずれも,日本語の文法(に基づく事実)の一例である。日本語を自由に使いこなせる日本人にとっては,これらは,あらためて取り上げるまでもなくわかりきったことであるが,それは幼児期にこうした知識を労せずして習得したからなのであって,これから日本語を学ぼうとする外国人にとっては意識的に習得せねばならないことなのである。なお,上記(3)で述べた〈機能語〉とは,動詞・名詞・形容詞などのように実質的な意味をもつ語(実質語・実辞などということがある)ではなく,いわばそれらの語を補足するような語というほどの意である(形式語・虚辞などと呼ぶこともある)が,この(3)についてはのちに少々補うところがある。
は,いずれも,日本語の文法(に基づく事実)の一例である。日本語を自由に使いこなせる日本人にとっては,これらは,あらためて取り上げるまでもなくわかりきったことであるが,それは幼児期にこうした知識を労せずして習得したからなのであって,これから日本語を学ぼうとする外国人にとっては意識的に習得せねばならないことなのである。なお,上記(3)で述べた〈機能語〉とは,動詞・名詞・形容詞などのように実質的な意味をもつ語(実質語・実辞などということがある)ではなく,いわばそれらの語を補足するような語というほどの意である(形式語・虚辞などと呼ぶこともある)が,この(3)についてはのちに少々補うところがある。
ところで,いま で〈ねこがねずみを食べた。〉を例に見たことは,この文に限らず,およそ〈名詞+が+名詞+を+動詞(+助動詞)。〉という型のあらゆる文についていえることであり,さらにいえば,〈が〉〈を〉の代りに,たとえば〈に〉〈で〉〈から〉などを含む文についても同様のことがいえる。また,
で〈ねこがねずみを食べた。〉を例に見たことは,この文に限らず,およそ〈名詞+が+名詞+を+動詞(+助動詞)。〉という型のあらゆる文についていえることであり,さらにいえば,〈が〉〈を〉の代りに,たとえば〈に〉〈で〉〈から〉などを含む文についても同様のことがいえる。また, の〈美しい〉の活用も,この語に限ったことではなく,他に〈強い〉〈かわいい〉〈厳しい〉など実に多数の語が同じように活用し(これらを形容詞と呼んでいる),一方,〈きれい〉と同じようにふるまう語も〈丈夫〉〈可憐〉〈穏やか〉など,数多い(いわゆる形容動詞)。文法というものは,どの言語でも,このように,普通,特定少数の文や語句だけについてのきまりではなく,〈一定の条件を備えた任意の文〉について,あるいは〈一定の範囲の多数の語句〉について同じように成り立つ一般性の高いきまり,すなわち規則性としてとらえられる事がらなのであり--だからこそわれわれは比較的容易に言語を習得できるわけである--,さらに,そうした種々の規則性の背後に,実はいっそう抽象度の高い原理が見いだされることもしばしばなのである(これに対し,特定の文や語句だけについてのきまりは,特に〈語法〉と呼んで区別することがある)。このように,(1)~(3)に関する一般性の高い諸々の原理や規則性と,多少の個別的なきまりとがいわば束になって当該の言語を成り立たせているわけで,それらの一つ一つのことをではなく,特にそれらを総体としてとらえた概念のことを文法(文法体系)と呼ぶ場合もある。なお一部に,文法とは,たとえば〈起きれる〉〈寝れる〉は誤りで,〈起きられる〉〈寝られる〉が正しい,というような類のこと,すなわち規範意識に基づくきまりのことだととらえている向きもあるようだが,規範意識など持ち込む以前に,すでに言語自体に上述のような多数のきまり・規則性・原理が,現実の仕組みとして存するのであり(冒頭に〈仕組み〉と書き添えたゆえんである),文法のうち,人為的に規範を持ち込める余地はさほど多くはないのである。規範意識を含む文法を特に〈規範文法〉ということがあり,各言語のいわゆる〈正しい標準語〉の文法がこれであるが,規範にかなっているか否かはともかく,上に述べてきた(1)~(3)に関するきまり・規則性・原理(の体系)という意味での文法ならば,どの言語のどの方言にも--標準語とはかけ離れた方言にも--存するわけである。
の〈美しい〉の活用も,この語に限ったことではなく,他に〈強い〉〈かわいい〉〈厳しい〉など実に多数の語が同じように活用し(これらを形容詞と呼んでいる),一方,〈きれい〉と同じようにふるまう語も〈丈夫〉〈可憐〉〈穏やか〉など,数多い(いわゆる形容動詞)。文法というものは,どの言語でも,このように,普通,特定少数の文や語句だけについてのきまりではなく,〈一定の条件を備えた任意の文〉について,あるいは〈一定の範囲の多数の語句〉について同じように成り立つ一般性の高いきまり,すなわち規則性としてとらえられる事がらなのであり--だからこそわれわれは比較的容易に言語を習得できるわけである--,さらに,そうした種々の規則性の背後に,実はいっそう抽象度の高い原理が見いだされることもしばしばなのである(これに対し,特定の文や語句だけについてのきまりは,特に〈語法〉と呼んで区別することがある)。このように,(1)~(3)に関する一般性の高い諸々の原理や規則性と,多少の個別的なきまりとがいわば束になって当該の言語を成り立たせているわけで,それらの一つ一つのことをではなく,特にそれらを総体としてとらえた概念のことを文法(文法体系)と呼ぶ場合もある。なお一部に,文法とは,たとえば〈起きれる〉〈寝れる〉は誤りで,〈起きられる〉〈寝られる〉が正しい,というような類のこと,すなわち規範意識に基づくきまりのことだととらえている向きもあるようだが,規範意識など持ち込む以前に,すでに言語自体に上述のような多数のきまり・規則性・原理が,現実の仕組みとして存するのであり(冒頭に〈仕組み〉と書き添えたゆえんである),文法のうち,人為的に規範を持ち込める余地はさほど多くはないのである。規範意識を含む文法を特に〈規範文法〉ということがあり,各言語のいわゆる〈正しい標準語〉の文法がこれであるが,規範にかなっているか否かはともかく,上に述べてきた(1)~(3)に関するきまり・規則性・原理(の体系)という意味での文法ならば,どの言語のどの方言にも--標準語とはかけ離れた方言にも--存するわけである。
なお,(1)~(3)を併せた趣で,文法とは〈その言語における,音(おん)(音声)と意味との結びつき方に関する一般的なきまり(の総体)〉などと定義されることもある。たとえば,(イ)〈ねこがねずみを食べた。〉,(ロ)〈ねずみをねこが食べた。〉,および(ハ)〈ねこをねずみが食べた。〉では,使われている単語はまったく同じでその順序が異なるだけであるが,(イ)や(ロ)のように並べた音連続には同じ意味を対応させ,(ハ)のように並べた音連続にはこれらと違う意味を対応させるのは,まさに文法のしからしめるところである,というような例(あるいはもっと単純に,〈美しい〉は現在形,〈美しかった〉は過去形,というような音と意味との対応の例)で考えれば,この定義もうなずけるであろう。
さて,以上に述べてきた意味での文法に関する学問,すなわち,(1)~(3)のきまり・規則性・原理としてどのようなものが存するかを体系的に明らかにしようとする学問(およびその成果,理論)のことをもまた,文法という(〈文法学(文法論)〉という場合もある)。学問としての文法は,後述のように長い歴史を有するが,今日では一般に,意味論や音韻論と並ぶ言語学の一部門として位置づけられている。文の適否にかかわることがすべて文法の問題であるわけではなく,たとえば,〈ねこがチーズを食べた。〉はまっとうな文だが,〈チーズがねこを食べた。〉はまっとうでない,というようなことは意味(論)の問題だと見るのが普通である。つまり,第2の文も文法上は妥当だとみなすわけで,実際,フィクションの世界を描いた文としてなら可能である。ただし,文法と意味(論)の境界が見きわめ難い場合も,実は少なくない。ちなみに,冒頭の(3)の機能語の用法についても,厳密にはすべてが文法の問題なのではなく,そのある面は意味(論)の問題だと見ることができる。そして,残りの面は実は上記の(1)あるいは(2)としてとらえ直せるかと思われ,こう考えれば,上記(3)という項目はあらためて立てるには及ばないことになる。が,文法と意味(論)の境界の画定が難しい上,一般に機能語の用法は(すべて)文法の問題だという把握が根強いようなので,これに従って,(3)も掲げた次第である。
文法の下位区分
学問としての文法は,しばしば〈シンタクスsyntax〉(統語論,構文論とも)と,〈形態論morphology〉(語形論,語論とも)とに下位区分される。
シンタクスは,単語が連結して文をなす上でのきまり・規則性・原理の研究,すなわち冒頭の(1)(および(3)のうち(1)にかかわること)についての研究である。窮極的にはこれらを体系的に明らかにしようとするわけだが,それには各種の構文の〈文の構造〉を分析し,かつ,互いに関連があると認められる複数の構文(たとえば能動文と受動文)の間の関係に見られる規則性などにも目を向ける必要がある。具体的には,単語以上で文以下の単位として〈句〉や〈節〉を立て(日本語の場合には〈文節〉〈連文節〉に拠る立場もある),また〈主語・述語〉〈目的語〉〈補語〉〈修飾語〉などの概念を適宜用いながら,こうした研究を行うことが多い。なお,(1)のきまりそのもののことをもシンタクスという。
一方,形態論は単語あるいはこれと同程度の言語単位の内部構造を分析し,これに関係するきまり・規則性・原理を体系的に把握しようとする研究で,典型的には冒頭に述べた(2)(および(3)のうち(2)に匹敵するような面)が研究テーマとなる。欧米の言語学では,一般に〈形態素〉という単位(〈意味を有する最小の単位〉などと定義され,ある場合には単語と一致し,ある場合には単語の一部をなすような単位)を設定し,これに基づいて形態論の研究を行ってきた。日本語については,形態素という単位を設定しない研究者も多いが,単語や文節の内部構造の検討,活用の分析など,形態論に相当するような研究は種々行われてきた。
以上のように,おおまかには,単語より大きいレベルを扱う分野がシンタクス,単語程度よりも小さいレベルを扱う分野が形態論だといってもよい。同じような性質をもつ単語を同じ〈品詞〉としてまとめる,いわゆる〈品詞分類〉は,どちらの分野にも関係する。なお,このほか,文が連結して一貫性のある文章をなす上でも相応のきまりがあるはずだとして,それらを明らかにしようとする〈文章論〉を,シンタクス・形態論とともに文法の一分野として唱える向きもあるが,この場合のきまりは,先の(1)~(3)とはかなり異質の,いわば傾向的なきまりにとどまるものであり,重要な研究課題ではあるものの,やはり文法とは呼び難い。
広義の文法
以上に見てきた普通の意味での文法のほかに,意味(論)・音韻(論)の問題(あるいはそのうち一方)まで,またときには表記法の問題などまで含めた広い範囲のものを文法と呼ぶ立場や場合もあるので,注意を要する。ヨーロッパでは,歴史的には,修辞法的な要素まで含めて文法ということもあったようである。また,コンピューターや論理学などにおける人工的な言語(記号体系)についても,単語(記号)を連結して文(式)をなす上でのきまりなどを文法とかシンタクスとか呼ぶことがある。
→形態論 →シンタクス →品詞
科学としての文法
趣旨・方法など
一般の人が学校教育等で外国語や古典語あるいは当代の自国の標準語などの文法を学ぶ場合,それは当該の言語に関する能力(読む,書く,聞く,話す能力。あるいはそのうちいくつか)を身につけたり高めたりするための手段として,という趣旨をもつ場合が多い。一方,文法学者が文法を研究するのは,そのような〈手段としての文法〉の学習への貢献を図るという趣旨もないことはないが,一般には,むしろ文法それ自体への興味に基づく,まさに〈科学としての文法〉である。学校の文法をつまらないと感じる人は日本に限らず少なくないようで,そうした人からすれば,文法が興味深いなどという文法学者は奇異に映るかも知れないが,実は,学校の文法と文法学者の研究とでは,かなり隔たりがあり,むしろ後者のほうが一般の人の関心をそそる面を多少は備えているのではないかと思われる。以下,文法学者による〈科学としての文法〉について,今少し解説を加えよう。
文法という語が,第1には,実際に存する(1)~(3)のきまり・規則性・原理(の体系)という意で,第2には,それに関する学問の意で,すなわち二義的に用いられることはすでに見たが,まず,第1の意味での文法について,その〈存し方〉がいかなるものかを補足しておこう。人は,十分に習得した言語(特に幼時以来自然に習得したいわゆる母国語)を用いる場合には,いちいちその文法を意識する必要はない。たいていの日本人は,もし学校等で文法教育を受けなければ,〈美しい〉はしかじかの活用をする,というようなことを自覚的な知識として明確には持たぬまま一生を過ごすであろうし,文法教育を受けたところで,平生そうした知識をいちいち意識して言語を用いているわけでは決してない。それでも,人は自由に言語をあやつる。つまり,自覚や意識はしていなくとも,当該の言語の文法(文法体系)を脳中に一種の知識として承知していて,おのずからそれに従ってその言語を用いているわけである。そして,同じ言語を用いる人々の脳中には,多少の個人差はあるにしても,基本的に共通の文法が備えられていると考えられる。第1の意味での文法とは,このように,主としていわば無自覚的な知識として脳中に存するものなのだが,これを自覚的な形で取り出し,体系として明示しようとする,その学問がまさに第2の意味での文法であり,これが文法学者の仕事である。この意味で,文法理論を立てるということは,人間の脳のありよう(の一部)についての仮説を立てることにほかならない,といえる。具体的には,おおむね次の(i)(ii)(iii)のような要領で仕事を行う。
(i)文法(第1の意味での)の帰結である諸々の言語事実を細かく観察する。
およそわれわれの用いる文は原則的にすべて文法の帰結なので,みな観察の対象となるわけだが,なかでも特に興味深い諸事実に着目していく。外国語や古典語の文法を研究する場合は,本国人や文献に十分に当たって,この(i)の段階の仕事に力を注がねばならないのはもちろんだが,母国語の場合でも,冒頭の
 のようなわかりきった事実のほかに,実は細かく注意を向けるべきことは数多い。たとえば,いわゆる主語に助詞〈は〉を用いるのと〈が〉を用いるのとでは(〈僕は行く。〉と〈僕が行く。〉とでは)どこか違いがあることは,誰しも漠然と感じていようが,ではどう違うのか。これを探るうちに,実は,両助詞が単なるニュアンスの違いという程度にとどまらぬ大きな違いを生じる次のような場合があることに気づく。すなわち,
のようなわかりきった事実のほかに,実は細かく注意を向けるべきことは数多い。たとえば,いわゆる主語に助詞〈は〉を用いるのと〈が〉を用いるのとでは(〈僕は行く。〉と〈僕が行く。〉とでは)どこか違いがあることは,誰しも漠然と感じていようが,ではどう違うのか。これを探るうちに,実は,両助詞が単なるニュアンスの違いという程度にとどまらぬ大きな違いを生じる次のような場合があることに気づく。すなわち,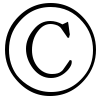 (イ)〈山田は戦いに敗れると,東京を去って行った。〉,(ロ)〈山田が戦いに敗れると,東京を去って行った。〉の両文で,〈東京を去って行った〉は誰の行為か(意味上の主語は誰か)--(イ)では〈山田〉自身であると解される(そうとしか解せない)のに対し,(ロ)では,〈山田〉自身とも解せなくはないものの,むしろ,前の文脈から誰か他の人物(たとえば〈山田〉の妻とか支援者とか)が了解されていて,その人物が〈東京を去って行った〉と解すのが自然であろう。つまり,〈は〉と〈が〉の1字の違いで,顕在しない主語の解釈が異なってくるわけである。ちなみに,英語では,いわばこの代りに,次のような事実が興味深い。すなわち,
(イ)〈山田は戦いに敗れると,東京を去って行った。〉,(ロ)〈山田が戦いに敗れると,東京を去って行った。〉の両文で,〈東京を去って行った〉は誰の行為か(意味上の主語は誰か)--(イ)では〈山田〉自身であると解される(そうとしか解せない)のに対し,(ロ)では,〈山田〉自身とも解せなくはないものの,むしろ,前の文脈から誰か他の人物(たとえば〈山田〉の妻とか支援者とか)が了解されていて,その人物が〈東京を去って行った〉と解すのが自然であろう。つまり,〈は〉と〈が〉の1字の違いで,顕在しない主語の解釈が異なってくるわけである。ちなみに,英語では,いわばこの代りに,次のような事実が興味深い。すなわち, (イ)〈After Yamada lost the battle,he left Tokyo.〉,(ロ)〈After he lost the battle,Yamada left Tokyo.〉,(ハ)〈Yamada left Tokyo after he lost the battle.〉,(ニ)〈He left Tokyo after Yamada lost the battle.〉の4文は,互いに,名詞と代名詞の位置,あるいは主節と従属節の順序を入れかえた点が違うだけであるが,このうち,(イ)(ロ)(ハ)ではheをYamadaと解し得るのに対し,(ニ)ではそれが不可能で,heを別人と解さねばならない。これら
(イ)〈After Yamada lost the battle,he left Tokyo.〉,(ロ)〈After he lost the battle,Yamada left Tokyo.〉,(ハ)〈Yamada left Tokyo after he lost the battle.〉,(ニ)〈He left Tokyo after Yamada lost the battle.〉の4文は,互いに,名詞と代名詞の位置,あるいは主節と従属節の順序を入れかえた点が違うだけであるが,このうち,(イ)(ロ)(ハ)ではheをYamadaと解し得るのに対し,(ニ)ではそれが不可能で,heを別人と解さねばならない。これら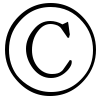
 のように,平生はつい見過ごしがちだがはなはだ興味深い細やかな文法上の事実というものは,どの言語でも実はいくらでも存するのであり,文法学者はその発見に努めるのである。また,たとえば,
のように,平生はつい見過ごしがちだがはなはだ興味深い細やかな文法上の事実というものは,どの言語でも実はいくらでも存するのであり,文法学者はその発見に努めるのである。また,たとえば, 〈太郎が子犬を捨てた。〉/〈子犬が太郎に捨てられた。〉のように,受動(受身)文は,ふつう能動文における〈を〉を伴う名詞を主語にして作られるので,この要領を〈太郎が次郎に子犬を捨てさせた。〉にもあてはめるならば,その受動文は〈子犬が太郎に次郎に捨てさせられた。〉となってもよさそうなものだが,実際にはこうは言わず,〈次郎が太郎に子犬を捨てさせられた。〉と言う,--というように,(言えてもよさそうなのに)言えない文(〈非文〉という)にも適宜注意を向ける必要がある。
〈太郎が子犬を捨てた。〉/〈子犬が太郎に捨てられた。〉のように,受動(受身)文は,ふつう能動文における〈を〉を伴う名詞を主語にして作られるので,この要領を〈太郎が次郎に子犬を捨てさせた。〉にもあてはめるならば,その受動文は〈子犬が太郎に次郎に捨てさせられた。〉となってもよさそうなものだが,実際にはこうは言わず,〈次郎が太郎に子犬を捨てさせられた。〉と言う,--というように,(言えてもよさそうなのに)言えない文(〈非文〉という)にも適宜注意を向ける必要がある。
(ii)観察した諸事実を整理・分析して,その背後にある(それら諸事実に対して合理的な説明を与えるような)きまり・規則性・原理を求める。
その際,だいたいこのような感じの規則的なものが見てとれる,といった程度の漠然とした把握にとどめず,科学的に明確な形で規則化することが肝要なのだが,これがなかなか難しいことが多い。冒頭の のような事実から,形容詞の活用はしかじかであるという規則性を取り出すことなどは,容易な部類なのだが,たとえば
のような事実から,形容詞の活用はしかじかであるという規則性を取り出すことなどは,容易な部類なのだが,たとえば で見た〈ねこがねずみを食べた。〉を〈ねずみをねこが食べた。〉と言いかえうるというような規則性を一般的な形で明示するのでさえ,存外に難しい。一見,〈名詞1+助詞1+名詞2+助詞2+動詞(+助動詞)。〉という文は,〈名詞2+助詞2+名詞1+助詞1+動詞(+助動詞)。〉と言いかえられる,とでも規則化できそうに見えるが,実はそうはいかない。たとえば〈実験室のねずみを食べた。〉は,〈ねずみを実験室の食べた。〉と言いかえられないからである。そしてそれは,この文では,
で見た〈ねこがねずみを食べた。〉を〈ねずみをねこが食べた。〉と言いかえうるというような規則性を一般的な形で明示するのでさえ,存外に難しい。一見,〈名詞1+助詞1+名詞2+助詞2+動詞(+助動詞)。〉という文は,〈名詞2+助詞2+名詞1+助詞1+動詞(+助動詞)。〉と言いかえられる,とでも規則化できそうに見えるが,実はそうはいかない。たとえば〈実験室のねずみを食べた。〉は,〈ねずみを実験室の食べた。〉と言いかえられないからである。そしてそれは,この文では,
〈[実験室のねずみ]を食べた。〉
のように[ ]の部分が一つのまとまりをなしていて,これをくずせないためである。詳細には立ち入らないが,このように文法(特にシンタクス)上のきまり・規則性・原理を見いだすには,多くの場合,単語の表面的な並び方ばかりでなく,そのまとまりのなし方にも--すなわち前述の〈文の構造〉に--目を向ける必要がある(これは のみならず,
のみならず,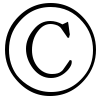 や
や の,またおそらく
の,またおそらく の背後にある規則性を探る場合にも,そうである)。ただし,その〈文の構造〉の把握も,重要で興味深い課題ではあるが,必ずしも容易ではないこともしばしばなのである。
の背後にある規則性を探る場合にも,そうである)。ただし,その〈文の構造〉の把握も,重要で興味深い課題ではあるが,必ずしも容易ではないこともしばしばなのである。
(iii)見いだした諸々のきまり・規則性・原理を,その相互関係等も十分に明らかにしつつ,窮極的には一つの体系として構築・明示する。
このような理論体系のことをも文法体系あるいは文法という(それは,前述の,われわれの脳中に存すると考えられる文法体系についての仮説と解しうるものである)。その構築は,文法学者にとって魅力的な課題であり,これまで,一つの言語に対して,何人もの学者が各自の文法体系の提示を競い合い,あるいは先人の体系の細部をさらに充実させようと努めてきた。ただし,もとより容易な課題ではなく,体系のおおまかな骨組みについてさえ,学者によってとらえ方がかなり異なることも珍しくない。ちなみに,異なった体系に拠って考えれば,特定の言語事実の分析(単純な例としては,ある単語がaという品詞かbという品詞か,など)も異なりうるわけで,文法書によって説くところが違うということも起こる次第である。
なお,以上(i)~(iii)の研究は,各言語(方言)の各時代の文法ごとにそれぞれ十分に行うべきものであるが,同じ言語の各時代の文法がある程度明らかになったところで,その歴史的な変遷の過程(〈文法史〉あるいは〈歴史文法〉)に目を向ける研究も起こるし,いくつかの言語の文法を対照吟味したり(〈対照文法〉という),さらには諸言語の文法の普遍性を探ったりする研究も起こることになる。
生成文法
ところで,従来は,前記(iii)の文法体系の構築を図る場合,それによって何を達成しようとするのかという目標が明瞭ではなかった。したがってまた,〈よりよい体系〉とは何かという基準もはっきりせぬまま,各学者がいわばそれぞれの嗜好に応じて各人各様の文法体系を主張してきたわけである。しかし,近年に及んで(1950年代半ば),アメリカの学者N.チョムスキーは,〈その言語の文をすべて生成する(つくり出す),かつ,それだけを生成する(つまり非文は生成しない)〉ことを目標に据え,これを達成するような文法体系の構築を図るべきだとする〈生成文法〉の考え方を提唱,自らその具体的な理論を素描して見せた。数式のようなフォーマルな規則を駆使し〈数学的言語学〉とも呼ばれるその理論には,心情的に抵抗を示す向きもあるものの,今日ではすでに各国の多数の文法学者が依拠するにいたっている。上掲の目標だけでも,その達成は実はなかなか困難なもののようであるが,チョムスキーはさらに,言語一般の性質(各言語の文法をフォーマルに記述し,抽象度の高い観点をとった場合に浮かび上がってくる普遍性)の追究なども標榜,このように高い諸目標を設定することで,(そのもとでの)〈よりよい体系〉の構築を目ざして多数の学者が協力・競争する態勢が整ってきた。それとともに,各言語および言語一般について,従来は見落としていたさまざまの興味深い--人間の脳のありようをかいま見させてくれるような--事実や規則性・原理が相次いで見いだされつつある。こうして,いわば前記の(i)(ii)(iii)が互いに互いの進展を促し合うような理想的な展開で,文法研究の質を従来に比べて飛躍的に向上させながら,〈生成文法〉理論の研究は今日ますます盛んに行われている。なお,この理論では,その後,狭義の文法のほか音韻(論)・意味(論)までも含めた範囲のものを〈文法〉と呼び,その〈文法〉を,あらまし,〈当該の言語(その音,意味,およびその結びつき方)に関する知識の総体〉およびそれについての理論,と定義している(ここにいう知識には,もちろん上述の無自覚的な知識も含む。そもそも,上述の,文法を脳中の知識としてとらえる考え方自体,チョムスキーが明確に打ち出したことなのである)。
文法研究の歴史と動向
文法研究の歴史は古く,インドではすでに前5~前4世紀ごろ,パーニニがサンスクリットの精緻な文法書を残している。ギリシアでは,gramma(〈文字〉)の学すなわち読み書きの学というほどのものが早くから行われていたが(これが現代英語grammarなどの語源),やがてプラトンやアリストテレスらによる文法的な考察の萌芽--今日いう文法・論理学・哲学が十分に分化せぬままではあったが--を経て,前100年ごろ,トラキアのディオニュシオスが8品詞を立てての整然としたギリシア語文法書を著すにいたった。前1世紀のローマ人ウァロや,6世紀の東ローマ帝国のプリスキアヌスらは,ギリシア語文法にならって,シンタクスも加えたラテン語文法に関する体系的な大著を残し,特に後者はラテン語の〈規範文法〉をほぼ確立したとされる。近代に及ぶまでヨーロッパでは,ラテン語が学術語・宗教語・共通語としての地位を占めてきたため,文法といえばラテン語の文法を意味し,その学問・教育は,(読み書きのための〈手段としての文法〉という趣旨が強かったが)連綿と行われてきた(〈ラテン語教育〉の項も参照)。さらに,そうした伝統的なラテン語文法にならって,やがて当代のヨーロッパ諸言語の文法の研究も徐々に行われるようになり,これらを〈伝統文法〉と呼んでいる。たとえば英語では,19世紀末にH.スウィートが,また20世紀前半にO.イェスペルセンが,いずれも〈伝統文法〉の集大成ともいうべき業績を残している。一方,18世紀末にヨーロッパ諸言語とサンスクリットなどの類似が指摘されると,19世紀には,それら諸言語--一般的な言い方をすれば,歴史的に共通の祖にさかのぼると考えられる諸言語--を相互に比較してその歴史的な関係を究明しようとする〈比較文法〉が興った(〈比較文法〉という語は前掲の〈対照文法〉とは異なり,このように限定的な意味で用いる)。この分野はその後科学的な精緻な方法論を加え,今日も盛んであるが,狭義の文法よりもむしろ音韻についての比較に力を注ぐ面も大きく,〈比較言語学〉と呼ぶことも多い。1言語を対象とする普通の意味での文法とは趣の異なるものである。さて,20世紀に入って〈構造言語学〉が興ると,これに基づいて文法研究も趣向を変えた。すなわち〈伝統文法〉が概して前述の〈規範文法〉としての色彩を有したのに対し,当該の言語で行われている文法の現状をありのままに記述する方針をとるようになり(これを〈記述文法〉という),研究対象もヨーロッパ以外の諸々の言語(アメリカ・インディアン諸言語など)に広げて,〈科学としての文法〉の面を強めた。方法的にも厳密さを高めたが,シンタクスの面では〈伝統文法〉よりかえって後退したうらみもあり,いわばそうした行詰りを打開すべく生まれたのが前述の〈生成文法〉の理論だといえる。この理論こそ,文法研究を真に科学と呼べる水準に高めたものと評してよい。これに基づく研究が今日活発に行われていることは上述の通りだが,最近では,これと同様の目標をもちつつも,チョムスキーとは異なる方法による--たとえば,チョムスキーの理論が〈変形〉という規則を用いる(〈変形文法〉とも呼ばれる)のに対し,その〈変形〉を用いないような--体系もいくつか提唱され,それぞれ関心を集めつつある。なお,近年では,ある言語の文を他の言語の文に〈自動翻訳〉する機械を作るという実用的な目的に基づく,主として工学者による文法研究--まったく新しい意味での〈手段としての文法〉といえよう--も各国で盛んに行われている。
日本では,中世に歌学者らが作歌のための手段として助詞・助動詞などの用法の研究を行ったのが,文法研究の始まりとされる。近世の国学者らはこれにいっそう科学的な姿勢を加えて,いわゆる係り結びや活用の研究,初歩的な品詞分類にも及んだ。本居宣長(もとおりのりなが),富士谷成章(ふじたになりあきら),本居春庭(はるにわ),鈴木朖(あきら)らにすぐれた業績がある。幕末から明治にかけてオランダ語や英語の文法書に接すると,一時期,これにならった日本語の文法書も次々に現れたが,その後は,いわば旧来の国学者らの文法研究と,欧米における文法や心理学・論理学等の諸研究との双方から,成果を適切に摂取しつつ,日本語の文法研究が進められてきたといってよい。大槻文彦(おおつきふみひこ),山田孝雄(やまだよしお),松下大三郎,橋本進吉,時枝誠記(ときえだもとき),三上章(みかみあきら)(1903-71)らがそれぞれ特色ある体系的な研究を残している。現代では,これら先学の研究の継承発展を目ざす努力が続けられる一方,前述の〈生成文法〉に基づく日本語文法の研究も活発になってきている。なお最近は,外国人による日本語の文法研究や,日本人による外国語の文法研究もともに盛んになり,それぞれ,本国人によるすぐれた研究に十分比肩するものも少なくない。
→生成文法
文法教育とその問題点
学校で,自国の標準語について基礎的な読み書きに加えて文法の知識も教授したり,あるいは外国語や古典語(ヨーロッパでは主としてラテン語)の文法を教授したりというように,なんらかの文法教育を行っている国は少なくない模様である。そうした〈学校文法〉は,おおむね,当該の言語の能力の養成を図る前述の〈手段としての文法〉であり,また,(特に書いたり話したりする能力の養成も図る場合には,)ふつう,〈規範文法〉である。ほぼどの言語でも,〈規範文法〉一般の性質として,言葉づかいにゆれがあるような場合については,より古い形や用法を規範とする傾向があるようで,それはごく自然なことと思われるが,行き過ぎると,ときに,大多数の人々の意識からかけ離れたものを規範とするおそれもなしとしない。一般論として,文法教育の企画者(教科書の執筆者等)は,言語は絶えず変化して行くものだという柔軟な観点ももちながら,しかもその時代の妥当な規範を打ち出すよう意を払わねばならない。
現代日本の学校における主たる文法教育としては,中学・高校の段階のいわゆる〈英文法〉と〈国文法〉があげられ,後者にはさらに〈口語文法〉と〈文語(古典)文法〉とがある。〈英文法〉は英語のいわゆる〈伝統文法〉に,〈国文法〉は橋本進吉の体系に,ほぼ拠っている。〈英文法〉と〈文語文法〉とは,それぞれ,英語の能力および日本の古典語(おもに平安時代語)の読解能力を養成する〈手段としての文法〉であり,少なくともそうした能力を養おうとする意欲の高い生徒については,確かに相応の教育効果をあげていると思われる。が,たとえば前者における〈書き換え問題〉(ほぼ同義の異種の構文に書き換える練習。空所を補充する形で行うことも多い)や,後者における〈品詞分解〉(文を単語に分けて逐一その品詞等を答える練習)など,ある程度までは有益であるにしても,行き過ぎると〈文法のための文法〉や些末主義に陥りやすい面も有している。また,〈口語文法〉には,標準語の〈規範文法〉を示して習得させる,〈文語文法〉への導入をたすける,言語の規則性・体系性等に目を向けさせる(すなわち〈科学としての文法〉の面ももつ),などいくつかの趣旨があると思われるが,いずれの趣旨もいま一つ十分に達成されていない感を免れない(たとえば,〈規範文法〉として不十分な一例をあげるならば,今日社会的にも習得の需要が高い敬語の使い方の規範を十分明瞭に示していない,など)。それに,〈英文法〉〈国文法〉とも,総じて,わかりやすさと魅力に欠けるうらみがあり,〈文法嫌い〉の生徒も少なくないと聞く。さらにいえば,〈英文法〉と〈国文法〉とが互いにまったく独立に教授され,そのため,ときに,同様の概念を違う術語で呼んだり,逆に,同じ術語の意味が微妙に異なったりするのも,ある程度やむをえないにせよ,好ましいことではなく,生徒の理解を妨げる一因となりうるようである。
このように,〈英文法〉〈国文法〉ともに,課題はなお多い。まず,文法教育の企画者としては,最近の文法研究の成果も適宜取り入れつつ,教科書・参考書等にさらにくふうを加えてゆく必要があろう。一方,教室での教授者に豊富な技量があれば,以上のような問題点の多くを克服して魅力ある文法の授業が行えることも,また事実のようである。そうしたすぐれた教授者も決して少なくはない反面,逆に,教授者自身の〈文法嫌い〉が生徒の〈文法嫌い〉を生んでいるような場合さえ珍しくないのは,残念な実状である。その背景には,多くの大学が,英米文学や日本文学専攻の学生に,文法その他言語学方面の講義をほとんどあるいはまったく行うことなく,英語や国語の教員免許を与えている現状があり,この点も問い直されてよかろう。多くの中学・高校生に文法への興味をもたせるとまではいかなくとも,せめて,〈文法嫌い〉がもとで〈英語嫌い〉や〈国語嫌い〉にまでなる生徒をつくらないようにすることは,日本の英語教育・国語教育全体の中でも重要な点の一つであり,この点を十分認識しながら,わかりやすく魅力ある文法教育を目ざして,その企画者,中学・高校の教授者,ひいてはその養成にあずかる大学教育の各方面いずれも,今後いっそう真摯に努力すべき面があると思われる。
なお,日本語の習得を望む外国人を対象とした文法書も,しだいによいものが著されてきているが,こちらもさらに充実させて行く余地がある。
執筆者:菊地 康人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「文法」の意味・わかりやすい解説
文法
ぶんぽう
grammar
言語の音声と意味を結び付ける体系をさすが、学者の意図や方法論などにより、いくつかの意味に使い分けられている。一つの言語の正しい使い方という規範的目的をもって書かれた文法、つまり規範文法に対し、言語学者が通常用いる意味は、規範文法のような価値判断の伴わない、客観的または科学的な見地からの記述、つまり記述文法をさす。記述文法という用語はまた、一時点での言語の状態を対象とした、いわゆる共時的な記述をさすが、この用法では、言語の歴史的発展を対象とした通時的記述である歴史文法と対比される。方法論的な観点からの用法としては、歴史言語学における言語間の比較という点を取り入れた比較文法という名称や、近年のチョムスキーの提唱による文法理論をさす変形文法(生成文法)というものがある。また、文法学者により体系化された文法理論の場合には、とくに日本では、文法学者の姓を冠したもの、たとえば「山田文法」(山田孝雄(よしお))、「時枝(ときえだ)文法」(時枝誠記(もとき))というような使われ方もする。
音声と意味を結び付ける体系としての文法は、通常いくつかの部門に区分されて研究されるが、これらは下図のような構成で関連づけられている。
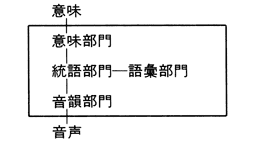
これらの部門は、文法研究の下位分野として成立しており、次の諸分野がそれぞれの部門と関係している。まず、言語の中心的な単位の一つは単語であるが、語の形成について研究する分野は語彙(ごい)論とよばれ、文法の辞書である語彙部門を対象としている。文を構成する場合には、辞書に収められている単語を選び出して組み合わせるわけであるが、どのような言語においても、いかなる組合せも可能であるわけでなく、一定の法則に従って組み立てられている。文の組立てに関する法則性を研究する分野が統語論である。文の意味は、それに使われる単語によって決定されるように考えられがちであるが、けっしてそうではなく、文としての形式が整って初めて文の意味は決定されるのである。このことは「太郎が犬を追いかけた」と「犬が太郎を追いかけた」を比較すれば明らかであるが、このように単語が一定の統語的法則に従って文の形に整えられたものに対して、その文の意味が決定される。意味論は、このような文の意味を研究対象とするばかりでなく、個々の単語の意味も研究範囲としている。したがって、意味論は、意味部門と語彙部門の両方にまたがる分野であるといえる。最後に、文の意味と対比して、文がいかに発音されるかということ、つまり音韻部門の研究を対象とした音韻論がある。音声に関する研究には、この音韻論のほかに音声学がある。音声学が、言語音の生理的および物理的側面を研究するのに対し、音韻論は、個々の音がどのような体系をなして語形成に参加しているか、そして個々の単語が文をなして連結されたときに、どのように発音されるかという点を研究対象としている。
以上の各分野の研究が、個々の言語に対して適用されるのが通常の文法研究であるが、個々の言語を超越したレベルでの研究も進められていて、人類言語全体を通した、統語的特徴、音韻的特徴といったものの追求が近年とくに盛んになっている。このような人類言語の全体的な記述を目ざした文法を普遍文法とよび、個別文法と区別している。
[柴谷方良]
日本語の文法
単語は次のように分類できる。(1)事物の名称を表す――名詞、(2)事物の作用・存在・状態を表す――動詞・形容詞・形容動詞、(3)前記2類の語にさまざまな意味を添える――副詞(接続詞・感動詞・連体詞も含めて)、(4)つねに他の語に伴って使い、さまざまな意味を添える――助動詞・助詞。
前記の品詞のうち、活用のある語は動詞、形容詞、形容動詞、助動詞の4語である。活用は、動詞型、形容詞型、形容動詞型、特殊型(助動詞の場合。無変化活用も含む)の4種がある。活用は、現代語では、語の断(そこで文が切れる)・続(あとに他の語が続く)に際して生じる、体系的な語形変化であって、動詞型の命令形を除いて、活用に際してその語形変化に伴う意味の変化はない。その点、現在、過去等と、語形変化に伴って意味が変化する英語等の西欧語とは異なっていることになる。ただし、平安時代までの日本語では、動詞型活用の語には時間に伴って事態の変化する意味が含まれていた。平安時代末から動詞には時間に伴う意味がなくなり、時間にかかわる意味のない命令形だけがその語形独自の意味を残すということになる。平安時代まで時代をさかのぼってみたとき、活用のある語で、動詞、形容詞、形容動詞ではその活用の意味に異なりがある。動詞は動作・作用・存在等を表すが、活用は、時間に対応した形での意味の変化を表している。まだ現実化していない事態(未然形)、すでに現実化している事態(連用形)、基本となる事態、その基本ということから時間的には現在の事態(終止形)、目前の事態、ただし下に体言がくるという変化(連体形)、現実化した事態を前提にして、下に続ける(已然(いぜん)形)、相手への命令(命令形)という変化である。この語形変化は、動詞の表す事態が時間の推移とともに進展・変化することを、古く日本人が認識したことを示している。形容詞は「(し)く(連用形)」「し(終止形)」「(し)き(連体形)」の三つの活用形(他の活用形は、どれも動詞「あり」の熟合したもので、形容詞本来の活用形ではない)があるが、これには、その語の表す事態が、その置かれた場面でどのような様相を示すかという変化があり、時間にかかわる意味の変化は認められない。形容詞の表す状態の意味を時間とのかかわりで認識しなかったということになる。動作・作用・存在は時々刻々に変化するが、状態は、そのような変化は認めがたいということがあり、活用に、動詞と形容詞とで意味の差が出るのも当然ということになる。存在を「あり」という動詞でとらえ、不在を「なし」という形容詞でとらえたのも、存在は時間の推移につれて変化するが、不在は変化するはずもないから、とすると納得しやすい。形容動詞は語尾に動詞「あり」がついてできた語であり、その源から動詞の性格を有している。
名詞、副詞は活用しない。動詞のように、時間の推移に伴って、その語の表す事態が変化するということもなく、形容詞のように、その場面によって様相の変わることもないことからいって当然といえる。名詞は、ある事物を他の事物から区別するためにつくられた語である。副詞は、名詞の表す事物、動詞・形容詞・形容動詞の表す動作・作用・状態等が、その場面のなかで他と、とくに異なる点のあるとき、それを述べるために使われる語である。その意味で、副詞は、これらの語に対して補助的な働きをする語ということになる。なお、現在は、ここでいう副詞はさらに細分化され、おもに用言を修飾する語(副詞)、体言を修飾する語(連体詞)、文と文、語句と語句をつなぐ働きをする語(接続詞)、感動・呼びかけ・応答を表す語(感動詞)と4類に分けられるのが一般である。これらの語が組み合わされて文ができあがる。
文は、まとまった思想を表すために表現されたひと続きの、いくつかの語よりなるものをいう。一語だけでなる一語文もある。この場合、文と語が同じ形になるが、その場面に応じた表現者のなんらかの意図に基づいたものが文であり、語と対応する事柄を表すだけであって、実際に、ある場面で使用されたのではないのが語であるということに違いがある。西欧語では、文は大文字で始まるということで外形上も一つの単位とする意識がはっきり現れているが、日本語ではそれがはっきりしていない。本来は一つの文という意識は不明確であったと思える。
日本語の文は、述語は不可欠であり、かつ文末という確固とした位置を占め、そこを動くことがない。他の語は、それを意味のうえで補って、表現をわかりやすいものとするという構造をもつ。述語のみが基本成分であり、他は補いの成分ということになる。「主語――述語――(他の成分)」という基本構造をもつ英語などの西欧語とは異なっている。この述語の位置にくることのできるのは、名詞、動詞、形容詞、形容動詞と、ある場合の副詞である。その意味で、名詞、動詞、形容詞、形容動詞の4類の語は、表現上も基本成分となりうるものである。ただ、名詞はそれだけでは文中の成分となりえず、助詞、助動詞などの語の補助を必要とする点で、前述の3類の語とは異なっている。述語にかかっていく他の成分は、助詞の補助を受ける。助詞という関係を表す語があるために、述語以外の成分は、文中のどこに置かれてもよい。文中の位置によって、いかなる成分かが決定される西欧語とは異なっている。ただし、日本語も古い時代にさかのぼると、名詞なども「が」「を」といった語を伴わず文の成分となっていた。述語という基本の成分に対して、意味の補いをつけるという形で表現がなされるため、ただ事柄を述べるだけでよいという意識に基づき、そのような表現が成り立っていたのである。しかし、現代語に近づくにしたがい、文を成り立たせる語と語との関係を意識する傾向が強まり、助詞をつける形式が確立してきている。
[山口明穂]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「文法」の意味・わかりやすい解説
文法
ぶんぽう
grammar
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「文法」の意味・わかりやすい解説
文法【ぶんぽう】
→関連項目比較言語学
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の文法の言及
【言語学】より
…しかし,どの言語も人間の言語である限り一定の共通性を有しているはずであり,したがって,個々の言語の研究が人間言語一般の本質解明に寄与するわけであり,また,他の言語の研究成果,とりわけ他の言語の研究で有効であることがわかった方法論が別の言語の研究においてもプラスになるわけである。 個別言語の構造の研究は,言語そのものの有する三つの側面に応じて,〈音韻論〉〈文法論〉〈意味論〉に分けてよい。
[音韻論]
音韻論的研究は,その言語がどのような音をどのように用いてその音的側面を構成しているかを研究する。…
【生成文法】より
…1950年代中ごろにアメリカの言語学者N.チョムスキーが提唱し,以後,各国の多くの研究者の支持を集めている,文法の考え方。文法とは,〈その言語の文(文法的に正しい文)をすべて,かつそれだけをつくり出す(しかも,各文の有する文法的な性質を示す構造を添えてつくり出す)ような仕組み[=規則の体系]〉であるとし,その構築を目標とする。…
【品詞】より
…文法用語の一つ。それぞれの言語における発話の規準となる単位,すなわち,文は,文法のレベルでは最終的に単語に分析しうる(逆にいえば,単語の列が文を形成する)。…
【ラテン語教育】より
…ラテン語が独自の理論的分析をうけるのは,4,5世紀,つまりいわゆる〈俗ラテン語〉の時代以降のことである。4世紀のドナトゥス,5~6世紀のプリスキアヌスをもって代表者とするが,ことに後者の《文法教程(文法提要)Institutiones grammaticae》全18巻は,文法理論の標準的な教則本として,後世に長く使用された。
[ヨーロッパ中世におけるラテン語の地位]
ヨーロッパ中世では,ラテン語は唯一の公用普遍語であった。…
※「文法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

