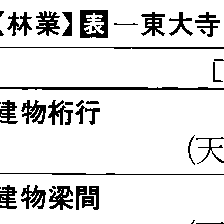林業(読み)リンギョウ(その他表記)forestry
精選版 日本国語大辞典 「林業」の意味・読み・例文・類語
りん‐ぎょう‥ゲフ【林業】
- 〘 名詞 〙 天然、または植栽した樹木を育成・保護し、材木に加工などして利益を得る生産業。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「林業」の意味・わかりやすい解説
林業
りんぎょう
forestry 英語
Forstwirtschaft ドイツ語
économie forestière フランス語
日本の農林統計調査などでは、林業の定義を広義と狭義の両面で行っている。広義には、林業は森林を造成し、その主産物および副産物を生産・販売する経済行為としている。狭義には、森林の維持造成から木材の生産・販売を行う経済行為を林業と定義し、副産物のキノコや山菜の採取・販売行為を特用林産として区分する(「農林水産統計調査用語集」)。学会関係では、狭義の定義をおもに採用し、林業をさらに二つの形態に区分する。自然の更新で生育した天然林を対象に行われる林業を採取林業(天然林林業)とし、樹木の植栽で造成された人工林を対象に行う林業を育成林業(人工林林業)として区分する。1990年代からは、地球の温暖化対策などの国際的な取組みの進展とも相まって、森林のもつ公益的機能(国土保全・水資源保持等)の造成を推進する治山事業や木質バイオマス事業なども林業として取り扱われる方向にある。
[山岸清隆]
林業の特質
産業としての林業は、農業などの他産業に比べて次のような特質をもっている。(1)原材料の樹木は、自然条件に対する要求度が農作物などに比して相対的に低く、気候寒冷地や農耕不適地でも生育できる。農業の困難な厳冬地のロシア・シベリアには針葉樹林が広大な規模で生育し、林業がシベリアの基幹産業となっている。(2)樹木の生育期間は著しく長く、半世紀を超える投下資本の固定や長期の維持管理を必要とする。そのため、林業は私的経営にはなじみにくく、経済効率を追求しすぎると森林資源の荒廃を招く危険性がある。(3)林業の展開形態は、木造建築物の歴史に規定される。日本では、採取林業(天然林林業)から育成林業(人工林林業)への展開をたどっているが、これは1000年にも及ぶ木造建造物文化を背景に生み出されたものである。世界的には、非木質系の建造物文化の歴史を有する国が多く、木材の多面的な消費文化(内装材、紙・パルプ用材、燃料用材等)に対応した採取林業(天然林林業)が主要な形態となっている。(4)林業の産業的な展開には、木材生産という経済行為と同時に、森林資源の荒廃を防ぐための植伐規制や伐採跡地の再生を義務化する保安林制度を必要とする。世界の文明発祥地の森林荒廃は、保安林制度の必要性を示しているが、保安林制度を設けている国が少なく、保安林制度を設けていても運用の規制されているケースが多い。
[山岸清隆]
世界の林業
世界の林業は、日本を除いては天然林を対象とした採取林業の段階にある。国連食糧農業機関(FAO)の『世界森林資源評価』(2010)によると、2010年時点の世界の森林面積は40億3300万ヘクタール、そのうち樹木植栽で造成された人工林は7%にしかすぎず、森林の再生を自然の更新にたよる天然林が93%を占めている。地域別では、アジアは森林に対する人工林の比率(人工林率)が21%と群を抜いて高く、その他の地域はいずれも10%以下(ヨーロッパ7%、北米5%、アフリカ、南アメリカ、オセアニア各2%)となっている。国別では、日本の人工林率は41%ときわめて高く、日本への主要な木材輸出国のアメリカは8%、ロシアは2%、ラワン材の主要輸出国のマレーシアは9%、集成材の輸出国の北欧・ノルウェーは15%などとなっている。FAOの統計データベース「FAOSTAT」(2012)によって世界の木材生産の用途別の動向をみると、2010年時点の世界の木材生産量は34億0500万立方メートル、内訳は製材、合板、パルプ等の産業用材の生産が15億3700万立方メートル、45%、燃料用の薪炭材生産が18億6800万立方メートル、55%と、世界レベルでは薪炭材の生産が過半を占めている。薪炭材生産比率の高い地域は、アフリカ(89%)、アジア(74%)、中南米(58%)などである。これに対し、産業用材の生産比率の高い地域は、北米(91%)、オセアニア(84%)、ヨーロッパ(77%)などである。産業用材の国別生産状況は、2010年時点ではアメリカがもっとも多く、年間の生産量が3億0000万立方メートル、世界の総生産量の20%を占めている。ついでブラジルが1億3300万立方メートル(世界シェア9%)、ロシアが1億3000万立方メートル(同8%)、カナダが1億2800万立方メートル(同8%)、中国が1億0200万立方メートル(同7%)などとなっている。同時点の日本の産業用材の生産量は1800万立方メートル、世界シェアが1%程度となっている。日本は、林業最盛時の1967年(昭和42)には生産量が5300万立方メートルにも及び、2010年(平成22)時点の3倍もの木材生産を行っていた。
[山岸清隆]
世界の木材貿易
世界の木材貿易は3000年にも及ぶ歴史を有することもあって、重量・容積のかさむ商品にもかかわらず貿易が早くからグローバル化していた。紀元前1200年ごろには、地中海貿易を独占していたレバノン周辺のフェニキア人がレバノンスギを主要な交易品としていた。7世紀から8世紀にかけて地中海貿易で栄華をきわめたイタリア・ベネチアの商人は、レバノンスギを交易品として取り扱い、自国の交易拠点の「海上都市」づくりにもレバノンスギを大量に使用している。この木材貿易の歴史は現在にも受け継がれ、木材交易のスケールが五大陸のすべてに及んでいる。たとえば、日本の木材貿易の相手国をみても、北半球では、8000キロメートルかなたのカナダ、アメリカをはじめ、高緯度の北欧諸国、亜寒帯のロシア・シベリア、熱帯の東南アジア諸国などから木材を輸入している。南半球では、南米大陸南端のチリ、アルゼンチン、日本の裏側のブラジルをはじめ、オセアニア大陸のオーストラリア、ニュージーランド、さらには森林消滅の激しいアフリカ諸国などからも木材を輸入している。その貿易相手国数は、100か国以上にも及んでいる。FAOの『世界森林資源評価』(2010)によると、2010年時点の世界の木材貿易(産業用材、薪炭用材)は、輸出量が1億2100立方メートル(輸入量1億1600万立方メートル)となっている。世界の木材生産量に占める輸出量の割合は4%と少なく、わずかな気象変動でも木材不足問題が発現しやすい状況にある。しかし、木材は農産物とは異なって日々に生活に与える影響が相対的に軽微であることもあって、木材不足問題が世界の社会問題となることはあまりない。木材貿易の主軸をなす産業用材の輸出入では、アジアを除いてはいずれも輸出が輸入を上回る木材輸出地域となっており、アジアだけは輸入が輸出の8倍にも及ぶ木材輸入の地域となっている。国別では、ロシアは世界の輸出量全体の19%を占めてトップに位置し、ついでアメリカ10%、ニュージーランド9%などとなっている。木材輸入については、中国が世界の輸入量全体の32%を占めて最大の木材輸入国となっており、ついでオーストリア7%、ドイツ6%、スウェーデン6%などとなっている。産業用材の製品種類別の輸出入動向では、(1)製材品は北米のカナダ、ロシア、スウェーデンなどのヨーロッパが主要な輸出地域となっており、アメリカ、中国、日本が主要な輸入国となっている。アメリカと中国は、世界の1位、2位を競う製材品の生産国であるが、同時に世界の主要な輸入国ともなっている。(2)合板は、中国、マレーシア、タイなどのアジアが主要な輸出国となっており、アメリカ、日本、ドイツが主要な輸入国となっている。とくに中国は、世界の合板生産量の3分の1を生産し、その多くが日本などへの輸出に振り向けられている。他方、アメリカも中国と並ぶ合板の生産国であるが、中国とは異なって世界トップの合板輸入国ともなっている。(3)木質パルプは、北米ならびに南米のブラジル、チリが主要な輸出地域となっており、中国、アメリカ、ドイツ、イタリアなど主要な輸入国となっている。なかでも中国の輸入量は群を抜いて多く、世界の輸入量の4分の1を占めている。日本と韓国も木質パルプの主要な輸入国となっており、極東アジアに世界の木質パルプの輸出が集中する形態となっている。
[山岸清隆]
日本の林業
日本は、歴史上早くから「木の文明」を生み出し、木造建造物文化を発展させてきた。6500年前の貝塚と推定される福井県の鳥浜貝塚からは、スギの丸木船やトチの盆、カヤの小弓、ヤブツバキの櫛(くし)などが出土している。青森県の縄文遺跡の三内丸山(さんないまるやま)遺跡からは、木造の住居群落とともにクリ材を使用した巨大構造物が出現している。8世紀の奈良時代に建立された東大寺大仏殿は世界有数の巨大木造建造物である。12世紀の初めと16世紀の中ごろに焼失したものの、太径木を列島の各地から集め再建を行ってきた。最初の建立と12世紀の再建では、ヒノキなどの巨木は近江(おうみ)(滋賀)、山城(やましろ)(京都)、播磨(はりま)(兵庫)などの近畿一円から調達された。18世紀の再建ではヒノキの巨木は岡山と山口から、アカマツの巨木は宮崎などから調達された。こうした巨大木造建造物の建立は、森林の荒廃や太径木の消滅を伴ったが、洗練された日本特有の木造建築文化を発展させ、人工林林業を早くから行わせるものとなった。酒樽(さかだる)生産の奈良・吉野林業は、700年前の室町時代から人工造林を始めている。小丸太材生産の青梅(おうめ)林業(東京)、貫(ぬき)材生産の天竜林業(静岡)、料亭や茶室などの高級建築用の磨(みがき)丸太生産の北山林業(京都)などは、いずれも300年以上前の江戸時代から人工造林を本格化させた木材産地である。明治期には、私有林の創設とも相まって人工造林の一定の広がりがみられた。しかし、明治政府の私有林に対する地券交付は近畿、東海などの地域に偏って行われたため、人工造林の広がりも地域的に限定されたものであった。人工造林が全国スケールに展開するのは、木材需要が急増する1950年代の復興期からである。とくに、1955年(昭和30)以降の高度経済成長期では、住宅着工が5年単位で倍々ゲーム(1955年26万戸、1960年42万戸、1965年84万戸、1970年148万戸)で増加し、木材需要も高度経済成長時代の15年間に4000万立方メートル台から1000万ヘクタール増の5000万立方メートル台にまで増大した。それを背景に人工造林も全国規模に波及し、1950年代後半から1960年代にかけて600万ヘクタールもの造林が行われた。2007年(平成19)時点の人工林面積1035万ヘクタールの6割にも及ぶ人工林の造成が、この高度経済成長期に行われたのである。この高度経済成長期に展開された人工造林には、次のような特質があった。(1)農地改革による農民解放の成果が表れ、地主層に偏奇していた造林が農民層でも活発に行われたことである。民有林の造林は、戦前期は年間10万ヘクタール前後であったが、それが農地改革の終了する1952年からは3倍増の30万ヘクタールに急増し、それ以降20年近くにわたってこの造林が継続された。(2)第二次世界大戦後の人工造林は、造林費の軽減を図るために密植方式(伐採時本数の3倍~4倍植栽)の造林が行われたことである。植栽から始まる造林作業でもっとも費用のかかる作業は、雑草から植栽木を保護するための下刈作業である。通常、下刈作業は、植栽後、造林地が密閉するまでに7回前後行われるが、密植造林は植栽木の間隔が狭く密閉が早まるため、下刈回数を減らすことができる。この密植造林のもつ下刈回数の減少機能が注視され、高度経済成長期の人工林造成に採用された。(3)この密植方式によって造成された人工林は、間伐などによる樹木本数の適正管理を必要とした。成林させるまでに5回前後の間伐を必要としていたが、この間伐を行わないと樹木間の生存競争が激化し、人工林の生育が阻害され、降雨災害や風害、雪害などに見舞われやすくなる。(4)しかし、戦後に造成された人工林は、1960年代に本格化する外材輸入によって間伐材の販路が失われ、間伐費の確保ができないままに放置され、間伐が手遅れとなった人工林が各地に発生している。集中豪雨時の人工林地の崩壊や、雪害や風害による人工林の大規模な倒木は、間伐が行われずに放置された密植方式の人工林の問題を提示している。(5)こうした問題を抱えながらも、戦後に造成された人工林は資源的な成熟化が進み、伐期50年の循環型の林業を展開しても、毎年の建築用の製材需要を十分にまかなえるだけの潜在的木材供給能力をもつまでになっている。
[山岸清隆]
森林の所有形態
日本の森林は、三つの事業体によって所有されている。『森林・林業統計要覧2011』によると、2007年(平成19)時点の日本の森林面積は2510万ヘクタール、事業体別の所有構成は国有林が769万ヘクタール、31%、公有林(都道府県有林、市町村有林・財産区有林)が283万ヘクタール、11%、私有林(個人、会社、社寺、各種団体・組合など)が1455万ヘクタール、58%となっている。世界的には、国有林、公有林などの公的所有の比率の高い国が多いが、日本は公的所有林の比率が4割程度にとどまっている。この森林の所有形態には、地域的な差異がみられる。「日本の統計」(2010)によると、国有林は、北海道、東北、北関東それに南九州に広く分布し、北海道、東北には国有林全体の68%が集中している。都道府県有林は、面積が130万ヘクタールで47都道府県のすべてに所在している。都道府県別では、北海道(62万ヘクタール)、山梨県(17万ヘクタール)、岩手県(7万ヘクタール)の3道県の所有規模が大きく、この3道県だけで都道府県有林全体の71%を占めている。市町村有林は、面積が都道府県有林に近似し、132万ヘクタールとなっている。都道府県別では、北海道(31万ヘクタール)、長野県(11万ヘクタール)、新潟県(6万ヘクタール)、鹿児島県(6万ヘクタール)、岩手県(5万ヘクタール)、岐阜県(5万ヘクタール)、山口県(5万ヘクタール)などの市町村の集中し、これら1道7県で市町村有林全体の52%を占めている。私有林は、国有林とは対極的な分布形態になっている。東海(72%)、近畿(79%)、中国(77%)、四国(76%)、それに北部九州(5県、79%)などでは、私有林比率が7割以上にも及んでおり、これらの地域は私有林地帯とよばれている。
[山岸清隆]
所有形態形成の歴史
森林の所有形態の地域的な差異は、明治初期の土地改革として行われた地租改正・官民有区分(公有林の官・民区分)によって原型がつくられたものである。この明治初期に行われた土地改革は、欧米諸国の外圧のもとで急速な富国強兵を図る必要から、幕藩体制下の封建貢租の全額確保を指針に農地や山林の地券交付が行われた。地券交付においては、地域的に異なる方式がとられた。(1)明治政府は地租の物納から金納への転換を図るために、地租を金納しうる商品経済の発達した地方には優遇措置を設け、農地地租の軽減や山林の地主層への地券交付が優先して行われた。たとえば、近畿、東海地方では、幕藩体制下においても綿花などの商品作物の栽培が行われ、木材の商品化も大きく進展し、物納地租から金納地租に対応しうる状況にあった。明治政府は、これらの地域に対しては旧来の封建貢租に比して地租の軽減措置を設けるとともに、地租負担能力のある地主層に藩有林も含めた山林の地権交付を優先して行った。近畿、東海などの私有林地帯は、こうして生み出されたものである。(2)他方、農林産物の商品化が遅れ、金納地租への転化のむずかしい地方に対しては、封建貢租をそのまま金納地租額に転化させるともに、金納地租の不足を山林の官林化でまかなう方式をとった。東北地方などは、江戸、大阪の大消費市場から遠隔地にあって木材の商品化が遅れていたが、こうした地域の藩有林の多くは官林化される一方、草肥採取や薪炭生産に集落ごとに利用していた入会林(いりあいりん)の多くを官林化し、農民に対する山林の地券交付も厳しく制限した。東北地方の「軒先(のきさき)国有林」は、こうして生まれたのである。(3)明治政府は山林の官林化に対する農民騒擾(そうじょう)の慰撫(いぶ)策として県などに官林の払下げを行うが、公有林はこうしたケースで生み出されたものである。また、官民有区分で残存された入会林(部落有林)の多くも明治末期に公有林へ移管され、そうした山林を市町村に払下げる方式がとられた。(4)明治期に生み出された森林の所有形態は、1940年代後半に行われた農地改革でも改革の対象外とされ、明治期の原型を継承した状態で21世紀の今日に継承されている。
[山岸清隆]
木材自給率と環境問題
木材自給率(国産材/木材需要)は、国産材の需給状況を表示する指標である。林野庁が1999年(平成11)に作成した先進10か国の木材自給率の一覧表によると、先進10か国のうち、日本の自給率(20%)よりも低い国は、イタリア(15%)、韓国(9%)の2か国のみである。日本よりも森林率のはるかに低いアメリカは86%、フランス86%、ドイツ71%、産業革命の時点で森林の大半を喪失したイギリスでも日本の自給率を8ポイントも上回る28%となっている。日本は、木材の自由化の行われる直前の1960年(昭和35)には木材自給率が87%にも及んでいたが、それ以降外材輸入の増加とオーバラップして木材自給率が低下したものである。イギリスは、戦時経済下の木材危機を経験し、その対策として木材自給率の向上に取り組んだものである。ドイツは世界各地から木材を輸入しているが、地球規模の環境保全を図るという趣旨で熱帯雨林からの木材輸入を規制している。他方、木材自給率は、環境指標の面において、国産材のもつ地球温暖化物質の炭素の固定状況(二酸化炭素の炭素換算)を表示する機能をもっている。『森林・林業白書』(2009年版)によると、40坪(120平方メートル、平均木材使用量23立方メートル)の木造住宅1棟は6トンの炭素を固定するとされる。炭素固定量を木材の使用量で換算すると、木材4立方メートルで1トンの炭素を固定する計算となる。これを原単位として日本における国産材の炭素固定量を試算すると、次のようになる。『森林・林業白書』(2012年版)によると、2010年時点の木材需要量は7025万立方メートルとなっており、この木材需要の炭素固定量は1756万トンとなる。炭素固定量1756万トンは、1997年の「京都議定書」において日本政府が国際公約した1約束期間(2008~2012)に達成するとした年間の炭素固定量1300万トンを超える量である。しかし、日本の木材自給率は26%と低く、国産材による炭素固定量は456万トン、木材需要のもつ炭素固定量のわずか26%にしかすぎない。木材需要の擁する炭素固定量の74%もが、外国の炭素を固定する状況となっている。日本が21世紀の国際的な地球温暖化対策に寄与するためには、国際的にきわめて低い木材自給率を高める取組みを必要としている。日本は、建築用の製材需要をまかなえるだけの潜在的木材供給力をもつ規模の人工林を造成しているだけに、木材自給率の向上もそれほどむずかしいものではない。
[山岸清隆]
『林業発達史調査会編『日本林業発達史 上』(1960・林野庁)』▽『林業構造研究会編『日本経済と林業・山村問題』(1978・東京大学出版会)』▽『全国森林組合連合会編・刊『森林組合制度史』全4巻(1983)』▽『有永明人・笠原義人編著『戦後日本林業の展開過程』(1988・筑波書房)』▽『黒木三郎編著『新国有林論』(1993・大月書店)』▽『山岸清隆著『森林環境の経済学』(2001・新日本出版社)』
改訂新版 世界大百科事典 「林業」の意味・わかりやすい解説
林業 (りんぎょう)
森林のもつすべての機能を十分に発揮できるよう管理し取り扱う人間の営為をいう。森林は木材の生産をはじめ食料,衣料,住居資材の供給源として人々の生活を豊かにしているが,現代ではさらに環境保全の働きが重要となっている。
森林の役割
森林は山腹を流下する水の破壊力を緩和し,谷川が一時にあふれて下流に洪水を起こすことを防ぎ,土砂崩れ,土砂流出を阻止して下流の安全を守る。海岸地方にある海岸林は暴風や季節風の風力を殺して細砂の移動飛散を抑制し,背後にある農地,家屋,生産施設,道路等を保護するほか,〈白砂青松〉に代表されるような美しい緑に包まれた自然を提供する。さらに都市においても公園,緑地としての都市林を適切に配置することにより,都市の機能が円滑に発揮されるのに役立っている。都市の拡大とともに急速に需要が増加するのは水である。生活用水,産業用水として従来とは比べようもないほどに水の使用量は増え,今後もいっそうの増大が見込まれている。この結果,水を保持し,流量を調節する水源林の整備,充実の重要性がますます高まっている。
このように現代は木材生産だけでなく環境保全に果たす森林の役割が急速に大きくなっている。さらに地域開発が進むなかで森林の役割の重要性が高くなっている。都道府県あるいは市町村の開発計画は全国ほぼ共通して急激な都市化,工業化,モータリゼーションによる生活環境の悪化を防ぎ,快適で安全な道路,機能的な都市施設の整備発展を,美しい緑と豊かな自然の中で配置することを計画している。機能的な公園都市,健康的な生活安全都市,中枢管理機能の高い都市,住民自治の進んだ都市などを将来の都市像として掲げる多くの都市開発計画の中で,森林を都市機能の中でどのように生かすかが大切な課題となっている。
都市だけの問題ではなく山村においても,そこで描かれる未来像では,経済的に豊かな村,知的水準の高い村,健康水準の高い村などが目標とされ,若者が定着し,人々が生活を楽しむ社会を築くことがめざされている。そのために,土地利用の合理化,集落の整備,道路や水道,医療施設などの生活環境の整備が計画されている。森林を山村経済振興の基礎におき,森林資源の造成と充実,整備を課題とするものも多い。とくに下流都市部への水の供給地としての役割をもつ山村では,その供給力を高めるため,流域を範囲とした広域の森林整備が緊急の課題とされている。このように森林の機能として,水源地帯山村,都市,海岸地帯を問わず,環境を保全するための意義が大きくなっているのが現代である。
また木材生産をはじめ,木の実,山菜,キノコ類,その他数多くの生産物を森林は産出する。木材の用途はきわめて多様で,社会のすみずみにまで木材を原料とする製品が行き渡っている。すでに日本では使用量がきわめて少ないけれども世界的には依然として重要な用途である木炭やまきのような製品もある。とくに木炭の水質浄化機能や土壌改良機能は,環境を良くする視点から見直されている。森林の生産機能は木材だけではない。現在多くなっているのはシイタケなどキノコ類である。シイタケは,かつては香港をはじめ各国に輸出されるほどであったが,現在ではほとんど国内で消費される。中山間地帯の主要な産業である,竹材は竹炭,フローリングなどの用途が開けている。そのほか,ワラビ・ゼンマイなどの山菜類,キハダ・オウレンなどの薬用植物,コウゾ・ミツマタなどの和紙用植物,漆などの生産物がある(〈木材〉〈林産物〉の項参照)。
保全林業と生産林業
林業は,環境保全の機能を果たすために森林を取り扱う保全林業と経済生産の機能を上げるために森林を取り扱う生産林業とに分けられるが,両者が別々にあるのではなく,つねに結合して存在するところに林業の特質がある。かつてはスギ,ヒノキなどの針葉樹を植え,それを伐ることを主目的とする用材生産林業が〈林業〉で,環境保全の機能は用材生産林業が副次的に発揮する効用としてとらえられていた。経済生産を十分に行うことによって付随的に保全機能=公益性を満足させることができるとした。経済性を上げるための生産活動が林業で,環境保全の機能を高めるための森林の取扱いはむしろ〈非林業〉とされていた。それほどに林業とは用材生産を目的とした森林の取扱い(植林,保育,伐採,保護)と考えられていた。しかし森林の環境財としての価値が大きくなるにつれて,環境保全の機能を果たすための森林の取扱いの意義が大きくなり,かつてのように〈付随的位置〉ではなく,経済生産機能と両立する意義を有するようになった。〈伐る〉ことのみに森林の営為の目的があるのではなく,〈伐らない〉ことにも森林の営為の目的があることが明らかとなるにつれて,いままで支配的であった生産林業としての林業のとらえ方から,生産林業と保全林業の二つが両立した林業という考え方に変わってきた。
生産・保全管理体系=コンサベーション
林業は生産林業と保全林業の両者を含み,両者は不可分に結合しているが,その結合の体系として〈生産・保全管理体系〉がある。生産・保全管理体系とは林業生産における植伐のバランスを維持し,林地の土地生産力に適応した生産を行い,自然物である森林の,自然性を尊重した取扱い(植林,保育,伐採,保護,修復などの管理,施業)をすることである。植伐のバランスを図ることにより林産物の供給量は減少しても,その代りに,森林の活気ある自然性を維持し,森林のもつ環境保全価値(水源の涵養(かんよう),土砂の崩壊防止,土砂の流出防止,緑の賦存,清浄な大気の維持,美しい自然景観の保存,野生鳥獣に生息地を与えるなど)がよりよく発揮されれば,それのほうがよいということである。この生産と保全を両立させる管理体系を確立させるところに林業政策の目標もおかれる。
林業の計画化
森林の取扱いについての目的,方法は地域により人により著しい差異がある。したがって林業計画をたてるに際しては画一的な価値規準ではなく,地域ごとに,その地域の自然をつくり育てる計画として,また地域の社会,経済の発展の基礎となる計画としてたてられることが肝要となる。そしてそれは単に行政区画による単位でなく,同一自然環境をもち社会的・経済的環境に近似性が強い地域を単位としてたてられる地域計画を基礎として林業を行う必要性が大きくなる。つまり,林業は〈伐る〉ことと同時に〈伐らない〉ことを達成しなければならず,そのためには営林行為は一定の規制(社会的合意に基づく管理行為)のもとにおかれることとなる。
林業技術
林業技術には生産技術と保全技術の両者がある。生産技術には植栽技術,保育技術,伐採技術,搬出技術などの広い分野が含まれ,保全技術は治山技術,保護技術,治水技術,風致計画技術,緑化技術などの広範な範囲を含んでいる。それぞれの技術が同一の場で結合するのは,技術適用の目的を同じくするからである。共通の目的とは〈地力を維持し,荒廃を防ぎながら生産する〉という林業における基本的技術目的である。具体的には乱伐,暴採などの地力を破壊する生産を行わないこと,いいかえれば自然の理法にかなったやり方で〈伐る〉ことも〈伐らない〉ことも行うことである。合理的な林業生産を行うことにより合理的な森林保全も行われる。したがって,地力維持技術が林業技術の本質となる。
林業政策の方向
地力維持を図るという技術上の目的を,木材増産という経済的要求のなかでどのようにして貫くかという,技術と経済の両立を求めたのが日本の林業政策の歴史であった。具体的には森林法の推移に示される。1897年の森林法は営林監督制度と保安林制度の二つの制度を柱にしていた。前者は地力の維持を図るために営林行為に対して加える,国権による〈応分の強制〉であり,後者は地力の破壊を防ぐための国権による〈応分の保護〉としてとらえられていた。1907年に改正された森林法では営林監督制度,保安林制度に加えて森林組合制度を設け,3本柱の構造にした。森林組合は森林所有者の団体であり,所有者たちの〈衆多の力〉によって,合理的な林業の生産・保全を行おうとした。所有者たちの自主的な管理により植伐のバランスを図り,地力の荒廃を防ごうとしたのである。この方向をより徹底させたのが1939年に改正された森林法であった。森林組合の設立範囲と林業計画(施業案と称した)の樹立範囲とを市町村の行政範囲と一致させ,生産技術,保全技術の総合化,組織化を図った。林業生産力(地力維持を図りながら最大の生産を上げる能力)の発現組織としてほぼ完璧なまでに整備されたのが,この制度であった。しかし戦時の木材需要はこの生産・保全管理組織を守る余裕を与えなかった。伐採生産は自然のサイクルを崩してまで進み,技術と経済との相克が生まれた。
1951年に改正された森林法では,一転して自然的生産循環を根幹とする技術主義的考え方で組み立てられた。森林を保続生産原則によって経営し,過伐をしないこと,森林の生産性向上を意味するよりよい施業を導入することが基本となり,伐採制限を根幹とする森林計画がたてられた。その後数回の改正があったが,現在では環境保全に対する要求と合理的林業生産に対する要求との二つを盛りこんだ森林計画がたてられている。
林業労働者
第2次大戦前まで日本の林業は農山村に多く存在した過剰人口によって支えられていた。戦後,とくに高度成長期に至り農山村からの若年労働力の第2次および第3次産業への流出が続き,林業労働力の減少と高齢化は深刻なものとなった。国勢調査によれば,1960年に44万人(うち50歳以上は24%)を数えた林業就業者は70年21万人(同29%),80年18万人(同48%),90年11万人(同68%)と減少してきた。林業労働は季節的な繁閑の差が大きいため,大半が農業との兼業による短期就労によっており,賃金,社会保障・保険の適用,労働災害の多発などの点で他産業に比べて不利なため,若年労働力が流出する原因ともなっている。なお〈林業労働〉の項目を参照されたい。
世界の林業
生産(開発)と保全の両立を図る林業は世界の課題となっている。1982年5月,ナイロビで開かれた国連人間環境会議では,〈開発と保全の総合〉の必要性が各国から提言された。森林開発(生産)の必要性は,薪炭材の需要の面からも大きい。発展途上国を中心とする薪炭材の不足現象が進めば,地球上の森林減少は著しくなり,土壌保全や環境保全に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。また地球の砂漠化を止めることも大きな課題として提起されている。古くから人工林を育てた国もあれば,天然林を伐採している国もある。砂漠化に悩む国,薪炭林の減少の著しい国もある。また,木材を伐採することにより外貨を稼ぐ国もある。これらの国々が合意する共通的な〈世界林業政策〉の樹立が求められてきている。21世紀の林業の課題がここにある。
→森林
執筆者:筒井 迪夫
近代以前の日本林業
林業の歴史は,住宅の建築用材をはじめ光熱用の薪炭材その他所要の林産物採取に不自由をきたすようになった時代から始まる。したがって生活に必要な林産物を手近な林野において自由に採出できた古墳時代以前にまでさかのぼることはできない。歴史時代になると,構造用材としての木材を主体とする林産物の需給関係は一変する。
古代の木材需要
まず飛鳥・奈良時代の建築用材は,その90~95%は木材であったことに留意しなくてはならない。この時代の都市民や農家の住宅用材を数量的に明らかにすることはできないが,761年(天平宝字5)に売却された右大臣藤原豊成の別宅(建坪36坪)の総材積は313石(1石=10立方尺=0.278m3)と計算される。1坪当りの用材積は9石弱で,現在の木造住宅の4倍を超える木材使用量に当たる。これと同期に石山寺へ運漕された中古住宅で,大きさ3丈四方,高さ9尺7寸の1棟は当時の中級官人の舎屋に比定できる粗末な構造であるが,しかもなお7寸角(径7寸平方の材)の梁(はり)・桁(けた)としてい木・木舞(こまい)を使用しているのは,原木が豊富であったことを示している。なお,この建物の規模を半減程度に縮小した家屋が一般庶民の住宅であったと想定される。
奈良時代以前の木材需要面で注意されるのは,多量の良材を必要とした都城と大寺の造営である。歴代遷都が原則であるかのように都が移動する原因の一つは,伊勢神宮や鹿島,香取神宮の建築更新期が20年と定められたように,掘立て式建築物の耐久力の限度にあったと考えられるが,別な理由としては,宮殿造に必要なヒノキの良材を至近の山に求めることが困難になってきた事情によるものである。大和国内の豊富な良材資源は,平城京の造営までにおおかた荒廃に帰したといえるが,それまでの用材供給量は知るべくもない。
奈良時代の建築用材で比較的実数に近い使用量の知られる建造物に東大寺大仏殿(金堂)がある。大仏殿の大柱(84本)は口径3尺8寸,長さ100尺内外の長大材であったから,柱1本の材積は85.5石(24.62m3)となり,この柱を含めての大仏殿用材は補修材を合わせて5万3800石(原木石はこの2倍)と推定される。院堂を含む建造物に充てられた用材に,小屋掛け,足場材の類をも加算すると,東大寺全構の完成までには少なくとも製材石で10万石(2万7800m3)以上の木材を必要としたものとみられる。東大寺,興福寺を含めた南都七大寺の造営に投入された用材は,平城京全体の建設に供給された木材の総量を材質の面でも上回ったであろうと想像される。また,国分寺の造立が契機となって中小寺院の建立は諸国にも伝播するようになるが,これらの造寺にあてられた良大材以下の用材は推測に余るほどおびただしいものであったに違いない。
天武天皇時代に20年に一度,伊勢神宮の造替遷宮が行われるようになってからの〈御造営御木目録〉によれば,1回の内・外宮更新に要するヒノキ材は末口物(皮はぎ丸太)2377本のほか,平物・余慶木(予備材)113本,その総材積は1万6663石にのぼる(1材の平均は6.7石)。寺院用材とは違いすべてヒノキの上質材であることが注目される。
平安遷都以後も,京都や鎌倉は幾多の戦禍に見舞われ,また自然災害にも弱い木造家屋の集中都市であったため,建設・復旧等に少なからぬ木材が消費されたことは見過ごせない。
用材の供給
大寺を含む都城の経営に必要な木材は,当時の未熟な採運技術によって搬出可能な奈良周辺の山林にこれを求め,林材資源の払底するにつれて奥地の未開発林へと伐り進んだであろうが,搬出不便な山からの採材はヒノキ以下の大径木に限られたとみられるところから,都を平安京へ遷すに至った理由の一つは,大和国内の用材資源が多年の乱伐によって枯渇状態に陥ったためであったと考えられる。京都の外郭の丹波,山城,近江等には,のちに山国杣(やまぐにのそま)や北山杉で知られるように,未開発の良材林が多く,しかも水運によって大材の搬出も容易な地利に恵まれていた。これより早く694年(持統8)遷都の藤原宮造営の際には,近江栗田郡の田上山(田上杣(たなかみのそま))に主要のヒノキ材を求め,琵琶湖から瀬田川を下っていかだ(筏)に組み木津川の木津で陸上輸送に移さなくてはならなかった。また東大寺の主用材も田上山や野洲川上流の甲賀山に採っている。《正倉院文書》によって用材採運手順をみると,用材を採取すべき杣の選定が終わるとともに山作所が設けられ,長上工が木工(杣工(そまだくみ))らを率いて入山し,撰木,造材が終わると,役夫が人力で車庭に運び,ここから水辺まで車で搬出する。なお超大材を引きおろすには修羅(しゆら)を使用したと思われる。1186年(文治2)に始まる東大寺再建の際には,周防国が東大寺に寄進され,佐波川の奥地から用材が採出された。鎌倉の町造りには伊豆狩野山の奥などから用材が伐り出されており,鎌倉にも材木座が成立するようになる。
林産物には木材のほか,炭,薪などがあるが,734年(天平6)の〈造物所作物帳〉には,買檜久礼(榑木(くれき)),買薪,買炭などがみえ,奈良時代から商品化が進んでいたことを示している。
山林の保護については676年(天武5)から樹木の伐採禁止や禁野の記事がみられるが,古代,中世を通じて略奪的採取林業に終始し,林材資源保続のための積極的な造林などはほとんどみられなかった。
近世の林業
豊臣秀吉の統一政権が確立すると,長期内戦によって荒廃に傾いた都鄙の再建事業が展開する。そのような建設機運の端緒ともなったのは,大坂城や方広寺大仏殿に代表される秀吉の造営事業であるが,そのころは畿内近国の目ぼしい山林はおおかた衰退していたため,秀吉の造営用材採出は,それまで未開発状態にあって,しかも良材の蓄積豊富な飛驒山,木曾山をはじめ,遠く秋田地方の山林にまで及んだ。その採材圏を一挙に拡大するのは,徳川家康の時代になってからである。それは,江戸をはじめとする城下町の造営が全国的な規模で,しかもいっせいに行われる空前の大建設時代が展開されるからで,建設に必要な木材はどれほどあっても足りないという事情によるものである。家康はこのような用材事情を見越して関ヶ原の戦直後,ヒノキ材の宝庫木曾山林を秀吉同様に蔵入地として確保し,運材ルート木曾川の改修工事に着手するかたわら,隣接する伊那郡の美林地帯を直領とした。そして両地の代官,奉行を督励しながら美濃,信濃諸大名の役夫を動員し,さらには商人資本をも導入して狂乱的な用材生産を強行する。こうして木場や材木問屋(〈木材〉の項参照)など流通組織の発達も促された。採材地と規模において差こそあれ,配下諸大名においてもこれにならって推進されたので,各地城下町の造営がほぼ一段落する17世紀半ばころには,熊沢蕃山をして〈天下の山林十に八尽く〉と慨嘆せしめるほどの荒林状態を招いた。こうした深刻な事態への対応を余儀なくされた幕府諸藩は,林材の濫採と消費規制に乗り出す一方,民利を無視して領主占有林(御林(おはやし),留山(とめやま))と伐採禁止木の制定を急ぎ,他方において植樹造林の実施・勧奨に積極性を示すようになった結果,江戸時代末期には総体的にみて初期のころの山林蓄積をほぼ回復するほどの成果を収めるに至った。これは,古代以来一方的な収奪に終始した〈採取林業〉から,農業的な〈育成林業〉への転換がもたらした成果と評価することもできるであろう。なお御林に対して農民が占有する山を百姓林,農民が立入りを許された山を百姓稼山といった。
→燃料
執筆者:所 三男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「林業」の意味・わかりやすい解説
林業
りんぎょう
forestry
世界的にみる林業は水源地や荒れ地も含めた森林地帯の管理をさし,材木源の確保だけでなく,森林の保護改善も目的とされている。世界の陸地の表面積の約1/3は分類上森林地帯であり,毎年立木の約1パーセントが伐採される。その約半分が燃料となり,残りは木製品,紙用パルプ,充填材などになる。木材として利用する樹木は,針葉樹,広葉樹,単子葉植物に大別される。針葉樹は,軟材樹または裸子植物ともいわれ,ほとんどが常緑樹にはいる。代表的なものに,マツ,トウヒ,ダグラスモミ,セイヨウスギ,イトスギ,レッドウッド,ツガがある。針のような尖った葉が特徴で,厳しい気候や比較的貧しい土壌でもよく育つ。針葉樹林の大半は北半球にあり,とくに大森林化しているのは北のタイガ地帯一帯で,北アメリカ,ヨーロッパ,スカンジナビア,ロシア北部,中国および日本の北部に広く帯状に密生している。北半球南部と南半球にも若干の針葉樹林がみられる。商業的な利用価値が高く,おもに紙,家具,建築材に使われる。広葉樹は堅木ともいわれ,温暖地帯のほか亜熱帯や熱帯の森林でも育つ。温暖地帯に育つ種には,オーク,ニレ,カバ,セイヨウトネリコ,カエデ,クリがあり,亜熱帯,熱帯の常緑樹にはユーカリ,チーク,マホガニー,バルサがある。温暖地帯の広葉樹は落葉性で,秋に落葉し葉のないまま越冬する。家具,化粧板,羽目板,床材など多目的に利用されている。単子葉植物にはヤシ,タケなどがある。主に熱帯,亜熱帯地帯にみられ,針葉樹や広葉樹に比べると商用価値は低い。ヤシ類はココナツ,ナツメヤシなどの果実や葉を利用した製品の方が,材木としてより経済価値が高い。タケは比較的に利用範囲が広く,紙用パルプから建築や家具造りにまで利用されている。
森林の計画的管理はヨーロッパでは中世初期に始まった。広大な森林地帯は君主や貴族の所有となり,各々の必要に応じ,また貿易の商品として利用された。材木の切出しや狩猟地としての利用に関する法は,各領主が定めた。やがて燃料や木製品の価値が上がり市場が拡大すると,領主は伐採と並行した計画的造林を考えるようになり,これが今日の林業の基礎になった。林業の科学面からの研究は,原則として土地の複合利用管理が中心で,現段階での活動はもっぱら木材の収穫と造林である。主要目的は産出高の維持,すなわち伐採と造林を綿密な計画のもとに行い,常時木材が供給できるように管理することにある。政府は法と政策をもって伐採量を定め,ときには伐採禁止地区を設ける。森林管理官は,例えば常に伐採地区と造林地区があるように,伐採を厳しく管理している。伐採地の再生手段を造林法という。技術的には自然再生法 (日本でいうところの採取林業) と人工再生法 (日本でいうところの育成林業) の2つの方法があり,それぞれに利点欠点をもつ。自然再生法は伐採方法がポイントで,間隔をあけ縞目状に木を残すことにより,残った木から自然に種子が供給され再生する。耕作,栽培などの手間がほとんどかからない利点があるが,再生種は原生種に限られる。人工再生法は種子または枝を採取し,森林地の苗床で育てる方法で,ある程度育った苗は再生用地に移植される。この方法は再生地に別種の樹木を植林できるため,より科学的管理が容易なのが利点で,一般に再生も早い。ただし,多額の資金を要し,かつ比較的その回収に時間がかかることが大きな欠点といえる。本来の複合利用管理の概念はこれにとどまらず,管理官は土地管理の延長上にある野生生物の保護,および雑草,害虫,菌類による病気や腐食,火事などから森林を守る対策の実施にも責任がある。森林地帯は,景色をめで自然に学ぶため,さらに狩猟や釣り,キャンプ,ハイキングなどの行楽までを含む保養娯楽のためにも,保存維持されねばならないと考えられる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「林業」の意味・わかりやすい解説
林業【りんぎょう】
→関連項目国有林
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の林業の言及
【森林】より
…木材の商品としての価値が高まるにつれ,積極的に造林が行われ始めた。たとえば,吉野地方および尾鷲地方では元禄(1688‐1704)のころから人工造林がすすめられ,ほぼそのころより,北山林業,飫肥(おび)林業,山武林業など各地の林業が起こり,それぞれ独特の林業技術が確立するに至った。とくにスギの挿木造林の進展は多くのスギの地方品種を生み出している。…
※「林業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
今日のキーワード
デジタル貿易
国境を越えて、データや情報の移転を伴う商取引の総称。ECサイトやコンテンツ配信サービスの利用、国外にある宿泊施設の予約など、インターネットを基盤とし、電子的または物理的に提供される製品・サービス全般を...