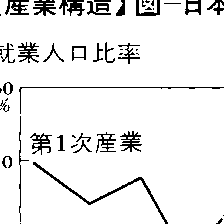精選版 日本国語大辞典 「産業構造」の意味・読み・例文・類語
さんぎょう‐こうぞうサンゲフコウザウ【産業構造】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「産業構造」の意味・わかりやすい解説
産業構造
さんぎょうこうぞう
industrial structure
一国の産業全体のなかでの産業間の関係をさす。その際に、対比される産業をどのようにとらえるか、また何を基準として関係を考えるかは、それを問題にする視角によって異なってくる。一国の産業全体のなかの産業間の関係については、経済学の研究が進みだした当初から、優れた経済学者の頭脳のなかでは明確に意識されていた。古くは重農主義者のF・ケネーが『経済表』(1758)において、地主階級、生産階級(農業)、不生産階級(商工業)の三者を区別し、その間の経済循環を論じている。また、K・マルクスが『資本論』第2巻(1885)のなかで再生産を論じている際の第一部門(生産手段の生産部門)と第二部門(消費手段の生産部門)という2部門分割も、産業間の分析を含んだものである。ドイツの歴史学派に属する多くの論者も、その経済発展段階説は、一種の産業構造の議論を展開しているともいえる。しかし、20世紀に入ってから、とくに1930年代以降、今日の産業社会を産業構造的な視点でとらえるようになってから、本格的にこの分野の研究は発展してきた。
[富山和夫]
研究の広がり
その際に、もっとも基礎的な分析と考えられているのは、C・クラークの分析である。彼の主著である『経済進歩の諸条件』(1940)は、産業を第一次産業、第二次産業、第三次産業の三つに分類したフィッシャーAllan George Barnard Fisher(1895―1976)に倣って、世界各国の長期にわたる資料を分析し、次のような結論を引き出したものであった。すなわち、それぞれの産業の就業者数は、経済進歩の進まない段階では第一次産業が圧倒的に高い比率を占めているが、経済の進歩とともに変化を遂げ、まず第二次産業の就業者の比率が増加し、やがて第二次産業と第三次産業の就業者の比率が増大して第一次産業の就業者の比率は低下する。さらに経済が進歩すると、第二次産業よりもむしろ第三次産業の就業者の比率がより大きくなり、就業者では最大の部門となっていくというものである。彼はその際に、農業、製造業、商業という順に収益が高まるというW・ペティの法則を採用している。
なお、今日の産業の三大部門の分類とC・クラークのそれとは同一ではなく、公益事業などの扱いが異なっている。一般に産業の分類は、それを使う目的によって最適なものが決まるので、分析目的によって産業の組み替えなどが行われる。一般にはそれらの最大公約数として標準産業分類がつくられている。
C・クラークの分析は、比較的資料の入手が容易な就業者数を使っていることから、多数の国について、長期間の分析ができることが利点となっている。しかしながら、就業者数の比率は、産業別の所得水準が異なることから、厳密に産業の相対的な大きさを反映するとは限らない。また、経済進歩の結果として最大の部門となる第三次産業については、そのなかに家事労働に従事する者を含むことなどから、後進的な部分が進歩的な部分と同一の取扱いとなっているとの批判もある。さらに、産業を三大部門に分割することによって、産業の大きな変化は把握できても、第二次産業部門内部あるいは第三次産業部門内部での変化をより細かく観察するという視点に欠けるという弱点がある。
第二次産業の内容が、経済の進歩に伴ってどう変わっていくかについての考察は、1931年にホフマンWalther Gustav Hoffmann(1903―1971)が『工業化の段階と類型』という著作のなかで初めて体系的に論じている。ホフマンは、「工業化」とは迂回(うかい)生産が進むことであると主張した。迂回生産というのは、直接に最終目的の製品をつくるのではなく、そのための製造設備などの資本財をつくり、それらの資本財を利用するという回り道(迂回)をすることによって、生産性を高めるという考え方である。したがって、ホフマンによれば、工業化は、年々に生産される製造業製品の用途の変化を生み、消費財に対して資本財の比率が高まっていくはずである。このことから、彼は、消費財産業と資本財産業との比をとることで、工業化の度合いがわかると考えた。現実に彼が消費財産業と資本財産業とを分類するうえで採用した方法は、彼の本来の意図とは異なり、各産業の製品の用途がどの程度まで消費に向かい、あるいは資本として使用されたかという基準をもとにしている。彼の方法は、産業連関分析が発達した現在の時点からみると、財の用途と産業の財の産出とを近似して行っていることから難点が多いとされている。彼が事実上分析しているのは、消費財と資本財の両産業の比ではなく、一種の重化学工業化率である。
製造業の内部の重化学工業化は、従来の軽工業(食品、繊維などの諸工業)に対して、重化学工業(鉄鋼、非鉄金属、機械、化学などの諸工業)のウェイトが高まることを意味している。しかし、重化学工業化比率の高さだけで工業発展の水準を判断することは適当ではない。1960年代の日本の重化学工業化率は、すでに、アメリカ、イギリス、フランスなどのいわゆる欧米先進工業国と同一の水準となっていた。しかし、その時点でも、日本とアメリカとは、工業の生産性において大きな隔たりがあった。ここから、重化学工業化率とは別の、工業水準を判断する基準が求められるようになってきた。製造業の部門を素材産業と加工・組立て産業とに分割し、その比をみようという試みである。
篠原三代平(しのはらみよへい)(1919―2012)は、その論文「加工度からみた産業構造の一視点」(『経済研究』18巻2号所収・1967)のなかで、アメリカと日本の繊維関連産業の分析を行い、そこにアメリカと日本との工業製品の加工度の差異をみいだし、新しい産業構造をみる視点を指摘している。日本の産業は素材産業の大きさに比べて、素材を加工し、組み立てる産業が十分に発展してvいない。それが、ほぼ同一の重化学工業化率にもかかわらず、工業の生産性では大きな遅れとなっている。したがって加工、組立ての産業のウェイトを高めていくこと(高加工度化)が、これからの日本の産業構造の変化の方向であると彼は主張している。日本の産業は、資源を大量に消費する鉄鋼、化学などの産業が相対的に過大であるとの感じをもっていた者が多く、資源多消費型の産業構造といわれていたが、これを加工度の低さとして明確にした点が大きな功績である。その後、産業構造を考える際には高加工度化という分析視点が不可欠なものとなった。
1970年代になると、それまでの高度成長を第一とする考えが反省される時期に入り、産業を判断する基準がしだいに変わっていった。所得水準の上昇、環境問題の深刻化などがそれを促した。そこで生まれてきたのが、産業構造の知識集約化という発想である。これは、これまでの重化学工業化あるいは高加工度化という議論とは発想の異なるもので、これからの産業は、知識集約型の産業がしだいにウェイトを増していかなければならない、というものである。具体的には、研究開発集約型産業(航空機、電子計算機、ファイン・ケミカルなど)、高度組立て産業(数値制御工作機械、工場生産住宅など)、ファッション産業(高級家具、高級雑貨など)、知識産業(エンジニアリング、コンサルティングなど)の諸産業をより振興していくことを内容としている。これは、産業の判断基準の変化に伴って、これまでは軽工業の分野であるがゆえに軽視されがちであった家具、衣料品、雑貨などのなかにも、所得水準の上昇を背景にして、高級な、ファッション性のある製品が十分に存在意義をもつことを指摘している(軽工業製品の一部を再評価)。また、一般的な高加工度化の傾向にもかかわらず、素材でもファイン・ケミカル(医薬品、高級接着剤など)に象徴されるように、研究開発の成果を集約したような製品はこれからも機会が豊かであることを示している(素材産業の一部の再評価)。さらに、たとえ組立て製品であっても、国際競争などとの関連では高度なものへと発展を遂げていくべきであると強調している(組立て製品の限定)。知識産業では、従来の「物」をつくるということから、そうした過程で体得してきたエンジニアリングなどの無形の知識を売ることの重要性を指摘している(一種の「物離れ」現象)。知識集約化の議論は、さらに、新技術、新産業などへの産業の傾斜を強める方向に向かっている。
製造業にかかわる産業構造論のもう一つのテーマとして、日本では二重構造をめぐる議論がある。これは1957年(昭和32)の『経済白書』などが問題を提起したもので(「二重構造」ということばの最初の使用者は有沢広巳(ひろみ)である)、日本の経済は近代部門と前近代部門の2部門に分かれているとして、この2部門の競争と共存の機構の解明が課題とされてきた。中村秀一郎(ひでいちろう)(1923―2007)の唱えた「中堅企業論」は、高度成長の過程で変貌(へんぼう)してきた中小企業の一つの典型を指摘したもので、その後の日本の二重構造論を考えるうえでのもっとも重要な成果となっている。
産業全体の変化についての研究も、その後いくつかの点で発展を遂げた。先に述べたC・クラークの分析が、全産業を対象としつつも、就業者数の比率の分析にとどまったのに対して、S・クズネッツは、多くの著作のなかで、就業者ではなく所得による三大部門間の関係の分析を行っている。その結論は相対所得平準化傾向ということであるが、この結論には疑問も多く、それをめぐる研究が盛んになっている。
[富山和夫]
産業構造と国際関係
産業構造は、国際関係によっても大きな影響を受ける。輸出入の状況によって産業構造は変わってくるからである。輸入品の多い国内産業は相対的に小さくなり、反対に輸出品の多い産業は相対的に肥大する。その典型的なものは、C・クラークの分析に登場するイギリスの第一次産業就業者の比率が19世紀の初頭から低水準にあり、それに対比される第二次産業就業者の比率が高水準であったことである。こうした研究は、すでに1930年代からのものであるが、戦後に発達した産業連関分析を利用し、輸出と輸入が産業構造と経済成長の相互作用にどうかかわるかという研究も進んでいる。
最近では、日本でも資本輸出(企業の対外進出)が活発になってきた。これは、商品の輸出が相手国の産業や労働市場の保護などの視点から限界になってきたことから生じたものである。商品の輸出は、それを生産する産業が国内で相対的に高いウェイトを占める方向に作用する。これに対して、資本輸出は、企業にとっては事業機会の拡大を意味するものの、国内の産業の拡大に対しては抑制的に働き、表面上では産業構造を変化させない作用をもっている。つまり、資本輸出という現象がなければ、国際競争力の優れた産業は相対的に大きなウェイトを占め、国際競争力の低い産業は逆の立場になるのであるが、資本輸出によって、産業構造と国際競争力との相関関係が不明確になってくる。ここから、産業構造をこれまでのように国内のなんらかの資源配分の問題に限定して論ずることには一定の限界のあることが明確になってきた。産業活動の国際化、企業活動の多国籍化を反映するような、国際的な視野にたつ新しい分析の登場が期待されている。
産業構造の研究はこのように産業構造変動の方向を探り、さらにそれに対して長期的な資源配分政策を提示するという性格のものである。したがって産業とその存立基盤の変動によって産業構造として問題にするものも変化していく。
[富山和夫]
『篠原三代平著『産業構造論』第2版(1976・筑摩書房)』▽『稲毛満春著『産業構造論』(1971・東洋経済新報社)』▽『富山和夫著『現代産業論の構造』(1973・新評論)』▽『池田勝彦著『産業構造論』(1973・中央経済社)』
改訂新版 世界大百科事典 「産業構造」の意味・わかりやすい解説
産業構造 (さんぎょうこうぞう)
industrial structure
産業構造とは,国民経済を構成する各種産業の比重や仕組み,関係をあらわすものである。これに対して,一つの特定産業内における企業の行動や企業間の構造を示すのが産業組織(〈産業組織論〉の項参照)である。したがって産業活動の見方としては,産業内の問題を産業組織という表現を使い,産業間の問題を産業構造という言葉であらわす。産業構造を考えるということは,各種産業の国民経済における組合せ状態をとらえることであり,経済活動のなかで,各産業がどういう比重で構成されているかを問題とする。こうした構成を考える理由は,それによって一国経済の生産の型と特徴をとらえること,また,その構成変化の様相を追跡することであり,これによって,国民経済の特性と,歴史的発展過程およびその将来の判断の基礎を得ようとするからである。
産業構造を分析する場合に,どの段階の産業分類が適当かという問題がある。たとえば自動車産業の一部である乗用車産業か,自動車産業か,造船・航空機等も含む輸送機械産業か,さらに総体の製造業か,産業の区切り方は産業構造を分析する目的に対応して決まる。また産業の比重を示す指標として,フローの概念である生産・出荷額,従業者数,給与総額などを使うか,ストックの概念として有形固定資産額などを使うか。これも,産業構造を分析する目的に応じて選択されるわけである。したがって産業構造のあらわし方は,いろいろな産業分類や,産業指標によるのであり,一義的なものはない。
1940年イギリスの経済学者C.G.クラークは産業を第1次産業,第2次産業,第3次産業の三つに分類し,一国の経済の発展につれて労働人口,所得の比重が第1次産業から第2次産業へ,さらに第3次産業へ移動する(ペティの法則)という歴史的な傾向を実証した。日本についても図のように同じことがいえる。これが産業構造の変化を大ざっぱな3分類法によって分析した最初のものである。その後S.S.クズネッツらによっても,同様な分析がなされている。
産業構造の分析を工業部門に絞って行ったものとして有名なものに,ドイツの経済学者ホフマンWalther G.Hoffmannの例がある。ホフマンは1931年,工業部門を消費財産業と投資財産業に分け,経済の発展につれて,ホフマン比率Hoffmann's ratio(消費財産業の投資財産業に対する付加価値額および従業者数比率)が低下するというホフマンの法則を発表した。ホフマンは,消費財産業とはその産業の商品の最低75%が家計に売られるもの,投資財産業とはその産業の商品の最低75%が企業に売られるものと定義している。そして消費財産業には食品,飲料,衣服,皮革,家具,投資財産業には金属,機械,輸送機械,化学工業が該当するとしている。しかし,このホフマンの法則は,厳密な意味での消費財産業と投資財産業の区別が困難なことや,機械工業の消費財(耐久消費財)生産の比重が高まっている今日,必ずしも現状と合わなくなっている。
そこで一般には,〈ホフマンの法則〉を基にして,消費財産業を軽工業,投資財産業を重化学工業の概念に置き換えて,経済発展と産業構造との関連を分析するようになった。チェネリーHollis Burley Chenery(1918- )は,製造業の成長の中心が鉄鋼業,非鉄金属工業,機械工業,化学工業などの重化学工業であることを実証している。製造工業の付加価値に占める重化学工業の割合を重化学工業化率というが,この比率は経済の発展とともに上昇する傾向がみられる。
これまでの産業構造分析が産業構成論という平面的な分析が中心であったのに対し,W.W.レオンチエフは,1941年に発表した《アメリカ経済の構造1919-1929》のなかで,産業連関分析(〈産業連関表〉の項参照)の手法を利用して産業構造の変化を立体的にとらえようとした。産業構造という概念を明確に定義し,分析したのはレオンチエフが最初といえる。レオンチエフは国の産業構造を形成する要因として,需要サイド,供給サイドの両面をとらえ,需要サイドでは家計,企業,政府,海外の項目別需要構成と各項目の品目別需要構成を明らかにする。供給サイドとしては労働,資本,資源や技術がある。そしてこれらの要因に国際的な要因(国際分業や国際的な産業配置)が加味されて,国の産業構造ができあがる。一国の経済成長には産業構造の変化が伴い,その産業構造の変化を産業の生産技術構造(投入構造)の変化という点まで深化させて分析しようというのが産業連関分析である。
産業構造の決定要因
産業構造の変化を決定する要因は,第1にその国の生産物の需要構造である。経済発展に伴う所得水準の上昇は,消費需要を変化させる。エンゲル法則にみられるように,一般に所得水準が高まるにつれて,食費への配分は低下し,被服費や教育・娯楽費,住居費への支出割合が多くなる。このような一般的傾向が,第1次産業の相対的比重の低下,第2次,第3次産業の発展を促すことになる。1年間に生産された国民総生産のうちどれだけが消費されずに投資(結果的には貯蓄)されたかは,国の経済の発展段階や経済成長率によって,ある傾向をもつ。投資の規模が同じでも,国内産業の発展段階に応じてその影響力は異なる。発展途上国の工業化の初期には,投資財の需要の相当部分は輸入機械によってまかなわれるが,国内産業が発展するにつれ,この輸入機械を国産機械で代替していく。
産業構造の決定要因の第2は,生産要素の供給構造である。天然資源が豊富か貧困か,労働力の量が豊富か,教育水準が高く質も良いか,資本が不足して金利が高くないか,さらには,技術水準が高いか低いか,工業用地,用水,港湾などの輸送施設が整備され,大規模工場が建設できるか,これらの要素の有無,関連のなかで,一国の産業構造が決定される。第3に,その国の貿易構造が産業構造を決定する。輸出構造の重化学工業品の比率はどうか,重化学工業品は工業国向けが多いか,非工業国向けが多いか,軽工業品での非工業国との競合はどうかなど貿易構造の変化が,その国の産業構造を大きく変化せしめる。
日本の産業構造
日本は第2次大戦後,第1次産業に抱えていた豊富で良質な労働力を使い,先進諸国の大型最新技術を導入し,安価な石油に代表される原料資源の安定輸入,大型設備投資と〈投資が投資を呼ぶ〉内需の拡大,大量生産方式によるコストダウンとそれに基づく製品の海外輸出に支えられて高度成長を達成した。国家の目標は,もっぱら先進工業国へのキャッチアップにおかれていた。
天然資源に恵まれぬ日本がこのような高度成長を達成できたのは,一貫して国際競争力を強化して貿易立国たらんとした結果である。しかし1970年代の日本の産業構造は,国外から大きくその根底をゆさぶられることになった。世界的なインフレの拡大によりIMF体制が崩壊,71年8月いわゆるニクソン・ショックにより,ドル防衛策が打ち出され,日本の円も73年2月ついに固定相場制から変動相場制へ移行した。続いて同年10月,第4次中東戦争を契機としておこった第1次石油危機により,原油の公示価格が一挙に4倍となり,1970年からの値上げを加算すると70-73年で実に8倍への引上げとなった。日本は戦後の経済発展を石炭から石油への転換によって進めて,安い石油を大量に使ってきた。しかも石油のほぼ全量を輸入に依存していた。石油製品の値上がりは,これを原燃料とする産業の製品価格上昇を誘発し,経済全体の価格水準をおしあげる結果となった。このため日本の産業構造は大きな変革を余儀なくされた。とくに製造業のうち,石油多消費産業である素材産業は,コスト上昇によって国際競争力が著しく低下した。石油化学工業,アルミなどは,国内の価格騰貴で需要が減退,大幅な需給ギャップが発生,低操業に陥った。これらの産業では安い原料,電力を求めていっせいに海外立地に向かった。造船,砂糖,平電炉,肥料,繊維などでも内外需要の減退で設備過剰に陥り,生産調整,再編成の動きがみられた。一方,石油依存度が相対的に低く,製品価格の上昇が比較的低水準であった家庭用電子製品,自動車などは,輸出の増大を続けた。さらに景気浮揚策としてとられた電力,建設などの投資拡大,消費需要の堅調さに支えられて,流通・サービス業は比較的好調で,新規投資もおこった。このように第1次石油危機を契機に日本の産業は,好調な産業と構造不況産業の差がはっきりと色分けされることになる。さらに79年に第2次石油危機が発生,原油価格はさらに2.5倍以上に急騰した。このように2度の石油危機によって日本の産業構造は変革をもたらされたが,日本は原燃料,食糧の対外依存が極度に高いので,それらを安定的に供給する経済の安全保障が最も重要な国の政策課題となる。
執筆者:北原 正夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「産業構造」の意味・わかりやすい解説
産業構造【さんぎょうこうぞう】
→関連項目格差社会|産業|産業分類
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「産業構造」の意味・わかりやすい解説
産業構造
さんぎょうこうぞう
industrial structure
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...