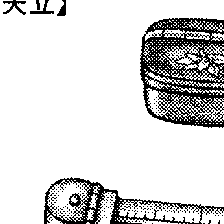や‐たて【矢立】
- 〘 名詞 〙
- ① 矢を立て入れる道具。胡簶(やなぐい)などをいう。
- [初出の実例]「ままきのやたてのひらなるにむすびつけてつかはしける」(出典:散木奇歌集(1128頃)恋)
- ② 「やたて(矢立)の硯」の略。
- [初出の実例]「箙の中より矢立(ヤタテ)取出し、墨筆に和して畳紙を染て」(出典:源平盛衰記(14C前)二九)
- ③ 近世、腰にさして携行した筆記具。墨壺に筆のはいる筒をつけて、帯にはさむようになっている。
- [初出の実例]「旅人も作り字しるす矢立にて 詩の言葉にも遠寺の晩鐘」(出典:俳諧・独吟一日千句(1675)第二)
- ④ 矢を射て物に突き立てること。また、矢が突き立っている状態。
- [初出の実例]「駒をはやめてうつ程に、矢たてのすぎといひけるを」(出典:曾我物語(南北朝頃)七)
- ⑤ 鉄砲をうって山の神に献ずること。猪狩の獲物を分配した後、三度発砲する地と、一度発砲する地とがある。
- [初出の実例]「日向西臼杵郡の山中では狩の始めに鉄砲を一発放ちて山の神に手向くるを矢立(ヤタテ)と云ふ」(出典:地名の研究(1936)〈柳田国男〉地名考説)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
矢立 (やたて)
筆記用具の一種。硯(すずり)と筆を一つの容器におさめたもので,同時に硯の水がこぼれぬようパンヤ,もぐさなどに墨水をしみこませたのが特色である。矢立は〈えびら矢立〉〈矢立の硯〉として文献には鎌倉時代から見えており,形は最初は檜扇(ひおうぎ)の形をとったものであった。のち江戸時代となって墨壺が丸く大きくなり,腰にさして歩くのに便利となった。元禄年間(1688-1704)以後,世の中がぜいたくになるにつれて金銀細工をほどこしたり,陶製のものができ,さらに寛政期(1789-1801)以後は墨壺を筆筒から分離して印籠(いんろう)風につくり〈印籠矢立〉と称するようになった。矢立の材料には黄銅,赤銅,四分一(しぶいち),陶器などがあった。明治時代に万年筆が輸入され,その普及につれて一般には利用されなくなった。
執筆者:遠藤 武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
矢立
やたて
現代の万年筆やボールペンの源をなす日本的な携行筆記用具の一つ。鎌倉時代に武士が檜扇(ひおうぎ)形をした、墨壺(つぼ)・筆を納めた容器を鎧(よろい)の箙(えびら)に入れて持ち歩いたのに始まる。江戸時代から、唐木、金・銀・銅・四分一(しぶいち)その他の金属、牙(きば)、骨、陶磁器その他のものでつくられ、実用品からしだいに趣味的なものへと変わった。その形も、筆入れと墨壺を一つにまとめたものから、これを二分して腰筒にしたり、なかには小判形、長方形のような小ぶりのものをつくりだして風流人にもてはやされた。墨壺の中にはパンヤとか綿を入れて、そこに墨汁を注ぎ、固まると水をさして用いた。筆も長いもの、小さなものを継ぎ軸にして用いた。木製には蒔絵(まきえ)、金属製品には金銀をはめ込んだり非常に手の込んだものが喜ばれ、商人の間では軸を物差しにしたものが流行した。
[遠藤 武]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
矢立【やたて】
筆記用具の一種。硯(すずり)と筆を一つの容器におさめたもの。中世には箙(えびら)の中に入れて陣中に携行した細長い硯箱を矢立の硯と称したが,江戸時代には硯にかわって墨壺をつけるようになり,腰にさして携行した。黄銅,赤銅,陶器などで作られ,元禄以後華美なものが流行,墨壺を別にした印籠(いんろう)矢立などもできたが,明治以後は万年筆が普及してすたれた。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by