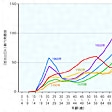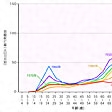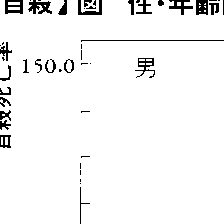自殺(読み)ジサツ(その他表記)suicide
精選版 日本国語大辞典 「自殺」の意味・読み・例文・類語
じ‐さつ【自殺】
- 〘 名詞 〙 自分で自分の生命を絶つこと。自害。自死。
- [初出の実例]「昔説レ法依二悪見論一、一切不実、不レ顧二一切一、投レ岸自殺者、堕二此中一」(出典:往生要集(984‐985)大文一)
- 「自殺(ジサツ)いたせしその後にて、御介錯の儀」(出典:合巻・裙模様沖津白浪(1828)池田宿本陣の場)
- [その他の文献]〔春秋左伝‐昭公二七年〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「自殺」の意味・わかりやすい解説
自殺
じさつ
suicide 英語
suicide フランス語
Selbstmord ドイツ語
自分の生命を自発的、意図的に奪う行為で、自己殺人、自害ともいう。英、仏語のsuicideの語源はラテン語で、sui(自らを)とcaedō(殺す)の合成語である。自殺行為は古代社会から普遍的にみられたもので、日本でも、古くは制度的な自殺(殉死)や武士の切腹(自殺刑)が知られている。近年、日本では「名誉ある自殺」や情死(合意心中)は激減しているが、日本特有な親子心中は後を絶たない。統計からみると、1989年(平成1)から1998年までの10年間の日本における自殺は全死亡の2.5%を占め、男女比は約10対5である。1970年代から1980年代の10年間と比較してみると、その10年間の自殺は全死亡の2%であったから、比率は高まっていることがわかる。しかも、1998年には3.4%と比率をさらに高めている。2007年における自殺者総数は3万3093人で、前年に比べ2.9%増加しており、1998年以降は3万1000~3万4000人の間で推移している(厚生労働省編『人口動態統計』)。
自殺手段は国民性や入手しやすい手段の差によって異なる。アメリカでは銃器による自殺が多いのもこうした理由によっている。日本では縊首(いしゅ)が多く、つねに第1位である。高所からの飛び降りも多く、とくに、高層建物からの飛び降りは急増している。服毒自殺は、1961年(昭和36)以降の催眠剤や農薬の法的規制で全般的に減少しているが、除草剤系農薬による自殺はつねに上位5位以内に入っている。1990年代になると治療用鎮痛・催眠剤やインターネットで外国から購入した催眠剤による自殺もみられる。都市ガスの一酸化炭素ガス含有量の法的規制により、ガス自殺はやや減少したが、その他のガスや蒸気による自殺は依然として多く、上位5位以内に入っている。最近ではインターネット上で呼びかけ集団自殺を行う例もみられる。一般に男性は縊首(とくに老人)や飛び降り、女性は縊首、入水といった手段を選ぶことが多く、いずれも積極的行為を選ぶ。自殺行為の結果、死ぬまでの経過はさまざまである。頸動脈(けいどうみゃく)切創による失血死のように直接的なこともあり、腹部切創後に二次的に急性腹膜炎を起こして死亡するといった間接的なこともある。
自殺の背景としては健康問題(病気、身体障害、老衰、身体的劣等など)がもっとも多く、ついで生活・経済問題である。1990年代に入ると、勤務問題がかかわる企業自殺、いじめ・不登校(登校拒否)・家庭内暴力を背景にした自殺が漸増している。また自殺前、いちおう健康とみられていた者でも、死後の剖検(ぼうけん)によって疾病異常が発見されて、病苦が自殺の背景にあったと推量されることがある。いわゆる変死体を検案する際に、遺書が存在し、その手段、方法、状況が自殺と矛盾がなければ自殺を裏づけることになるが、なかには、自殺を強要し、遺書を残させる状況もありうる。自殺は犯罪ではないが、他人に自殺を唆したり(自殺教唆)、その手助け(自殺幇助(ほうじょ))をすれば自殺関与罪となる。また、無理心中の発案者や親子心中の親が生き残れば殺人罪に問われる。
[澤口彰子]
なお、一定の制度や習慣などに従って行われる自殺をはじめ、意識や知能の障害によって自殺類似の行為が行われることもあり、また実際に事故死や他殺と紛らわしい場合も多いので、これらを区別する必要がある。
かつて哲学者セネカは「自殺は人間の特徴である」と述べたが、古代のプラトンから現代のカミュに至るまで、自殺という行為をめぐって多くの論議がなされてきた。自殺に関する研究を自殺学suicidologyという。
[岩井弘融・高原正興]
世界と日本の自殺
自殺の発生は時代や地域などによってさまざまに変化するが、20世紀初頭から現在までの動向を各国別にみると、1901年から1955年までを通じて自殺率(人口10万対)が高かったのは、日本、スイス、ドイツ、フランス、スウェーデンなどであり、日本は2~5位であった。日本の自殺統計が始まった1899年(明治32)の自殺率は13.7であり、明治末期から大正初期にかけて増加し、1925~1937年(大正14~昭和12)の間は20.0を上回っており、戦前・戦中期の最高は1932年の22.2、最低は戦中の1943年の12.1であった。とくに、1955年から1960年までは日本の自殺率は世界一で、なべ底景気といわれた1958年の25.7が第1のピークであった。そして、その後は減少傾向を続けて、高度経済成長期の1967年に14.2の戦後最低を記録し、1970年にはハンガリー、チェコスロバキア、フィンランド、スウェーデンなどの北欧・東欧諸国の自殺率が高く、日本の自殺率15.3は第9位であった。しかし、1980年代には再び自殺増加期に転じて、1983年から1987年までの5年間は自殺率が19.0を上回り、1986年の21.2で第2のピークを形成した。さらに、自殺者数が一挙に3万人台に増加した1998年(平成10)以降の10年間は、史上最多の自殺者数と自殺率を記録した1999年の3万3048人(26.1)を第3のピークとする自殺多発期を形成している。なお、2007年には、自殺者数3万0777人、自殺率24.4を記録している。また、世界保健機関(WHO)の2004年時調査における自殺率の高い国の順位は、リトアニア、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタンであり、日本は第10位であった。
[岩井弘融・高原正興]
年齢と性
日本の0~19歳の年齢層の自殺者数は、2005年に男382人、女226人、2006年に男395人、女228人を記録しており、他の年齢層に比べてかなり少ない。しかし、過去に青年層の自殺が多かったことは国際的にみても日本独特の現象であり、第1のピーク期における高い自殺率の原因でもあった。たとえば1955年(昭和30)には、15~24歳の年齢層の自殺者数8231人は総数の36%を占めて、20~24歳の年齢層の自殺率は65.4を記録しており、この時期は青年期と高齢期に自殺率が高い山を示すN字型曲線を描いていた(、)。その後、青年層の自殺率は高度経済成長期から急激に低下し、1985年には15~24歳の年齢層の自殺者数1630人が総数の7.0%を占めるにすぎなくなった。この第2のピーク期の自殺率は、加齢とともに右上がりの直線を示す欧米型といわれている。
ところで、第3のピーク期の2006年(平成18)における自殺率(全体23.7)を年齢層別に高い順で見ると、55~64歳35.3、45~54歳32.9、75歳以上29.6、65~74歳28.8、35~44歳26.0であり、85歳以上の男性の高い自殺率を除けば、55~59歳の男性の自殺率58.6が最高値を示している。そして、この時期の自殺率は、男性中年層において高い山を形成する新N字型曲線に移行しているとみることができる。とくに、自殺者数が一挙に3万人台に増えた1998年の増加数8472人のうち男性が78%を占め、50~64歳の年齢層が44%も増加し、未組織労働者、無職者、失業者が圧倒的に多いと報告されている。なお、高齢者層では加齢とともに自殺率が一貫して上昇しているが、その度合いは次第に弱まってきている。
高齢者の場合は、病苦や、配偶者などとの死別・離別によって、希死念慮がつのる傾向がある。そのために、高齢者の自殺は、産業構造の変化によって次世代世帯との紐帯が弱まり、家族・地域の機能の縮小といった「集団の統合の弱まり」による孤独と喪失を基調にしている。2007年に自殺率が30.0を超えた県は、青森・岩手・秋田・新潟・島根・高知・宮崎の7県であるが、これらの各県はいずれも高齢者層の自殺率が高く、農村の貧困と過疎が影響を与えていると考えられる。
また、男性と女性を比較すると、洋の東西を問わず、男性の自殺率が高い。日本もその例外ではないが、外国と比較すると、日本の女性の自殺率は相対的に高い。とくに、明治期から第二次世界大戦前までは、男性100に対して女性は60前後の割合であり、戦後は上昇して1970年(昭和45)には81にまで達したが、その後は下降して、2006年(平成18)には約41まで低下している。同年の女性の自殺率(全体13.2)を年齢層別にみると、20~59歳では12~15台、60~79歳では16~19台、80歳以上で概ね20.0を超えており、加齢とともに上昇する傾向にあり、その自殺率は国際的には依然として高い方である。このような日本の女性の自殺率の高さについては、日本の女性の自我の高まりや社会進出にもかかわらず、ジェンダー意識や家族・地域の前近代的な人間関係が依然として強く、女性の自立を妨げているためと考えられる。
[岩井弘融・高原正興]
自殺の原因・動機
自殺の古典的な研究者として知られるフランスの精神医学者モルセッリHenry Morselli(1852―1929)は、自殺の動機として、精神病、家庭困窮、病苦、激情、不徳、家庭不和、財政的失望、後悔廉恥、失望、不明の10分類を行った。日本の警察庁の動機分類は、家庭問題、健康問題、経済・生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他、不明の8つになっている。
自殺の原因については、これまで多くの学者によって論じられてきた。哲学者ショーペンハウアーは、自殺のなかに強い生への意志をみて、それが生の目標を認識しながらも達成不可能と判断したときに絶望する結果とみた。精神分析学者のフロイトは、生の本能に対する死の本能を想定し、緊張と努力から完全に解放されて、根源的・無機的状態への回帰を目ざす行為として自殺を解釈した。
さらに、精神医学の立場からは、うつ病、統合失調症、ヒステリーなどとの関係が問題とされている。アメリカの精神医学者デビッドソンG. M. Davidsonは、自殺時の精神状態として、生活目標の喪失によって意識野の狭窄(きょうさく)が生じ、調整機能が低下することを指摘した。そのほか一般に精神医学者や心理学者によって、失敗への耐性不足、現実逃避、休息願望、内罰傾向、復讐(ふくしゅう)・攻撃願望、自己顕示願望、名声保持願望などがあげられることが多い。
宗教的な観点からは、日本人の死生観なども問題にされる。生き抜くということよりも死を軽んずる伝統があり、また、厭離穢土(えんりえど)・欣求浄土(ごんぐじょうど)の仏教思想も影響を与えてきたといわれる。死を美化し、ロマンチックなものとみる傾向は、古くは近松門左衛門(もんざえもん)の心中物、明治以後では藤村操(みさお)(1886―1903)、松井須磨子(すまこ)、芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)、太宰治(だざいおさむ)、原口統三(1927―1946)などの自殺に対する賛美や評価に至るまでみられてきた。しかし、このような思想傾向は、時代の変化とともにほとんどみられなくなってきている。
経済的な観点からは、貧困と自殺との関係が問題にされる。一般には、外国では高所得者と低所得者に自殺が多いといわれている。イギリスの社会学者セーンスバリーPeter Sainsburyはロンドンの調査において、自殺と貧困との単純な相関関係は認めがたいと主張した。これに対し日本では、精神医学者の大原健士郎(1930―2010)が、無職業者、職業不安定者に自殺が多いこと、社会学者の中久郎(なかひさお)(1927―2005)が、上位階層の自殺率は低く、低階層では高いことを指摘して、いずれも貧困問題を重視している。人口学者の岡崎文規(あやのり)(1895―1979)は、1900~1960年(明治33~昭和35)の卸売物価指数を用いて自殺と経済周期に関する分析を行い、不況と自殺の増加、好況と自殺の減少とが相関する五つの時期があり、ただ一つこれに合致しない時期(好況で自殺が増大)のあることも述べている。また中は、1948~1958年について完全失業率と自殺率を分析して、両者には明らかな相関関係があることを指摘している。
一般的には、日本の自殺の動向は経済変動に左右される傾向が強く、とくに失業率と高い相関関係にあることは、その後の双方の変化をみても明らかである。1960年代から1970年代初期の高度経済成長期には自殺率が低く、その後の低成長期における失業率の上昇とともに自殺率も上昇した。そして、バブル経済期の1990年前後からの失業率の低下とともに自殺率も低下したが、平成大不況が深刻になって失業率が4%を超えた1998年(平成10)からは、ふたたび自殺率が急激に上昇している。とくに、この時期に中年層の自殺率が高いことは、リストラ、合理化による過重労働、閉塞感や不安感の増大によるところが大きいと推測される。しかし、日本よりも失業率が高いのに自殺率が低い国もあるので、日本の自殺の分析にはその他の社会心理的要因も考える必要がある。その要因の中で注目すべきことは「働くことが美徳」という単一の日本的な価値観であり、それは自己を職業的役割に過度に同一化する態度(役割自己愛)として表れる。
[岩井弘融・高原正興]
自殺の類型
自殺の原因と関連して、その類型化も各方面から行われている。たとえば、『自殺論』(1897)を著したフランスの社会学者デュルケームは、自己本位的(利己的)égöiste自殺、集団本位的(愛他的)altruiste自殺、アノミー的(無規制的)anomique自殺、および宿命的fataliste自殺に分け、現実の自殺にはこれらの混合型もあるとした。また、日本では心理学者園原(そのはら)太郎(1909―1982)が、防衛的自殺、懲罰的自殺、攻撃的自殺、犠牲的自殺、エクスタシー自殺、耽美(たんび)的自殺に分類した。そのほかにもさまざまな分類がある。
なお、心中は日本の伝統とされるが、そのうち母子(父子)心中のごときは、複数自殺というよりもむしろ、他殺プラス自殺である。自殺または心中に際して遺書を残すのはおおよそ全体の5分の1くらいであるが、手記型、詫言(わびごと)型、報告書型、警句型、詩歌型などがあり、弁護や虚飾もあるので、かならずしも原因を明らかに示すものではない。
[岩井弘融・高原正興]
自殺の防止
自殺者はその行動前に無意識的に「助けの声」cry for helpをあげているといわれ、その前兆をとらえることが防止上も重要とされる。「生きていてもしようがない」とか「遠くへ行きたい」などともらす言語的兆候、また、急に黙ったり、身辺整理をするなどの行動的兆候の両面がある。
自殺防止を目的とした「いのちの電話」の福祉サービス(The Samaritans)は1953年、ロンドンの司祭バラーChad Varah(1911―2007)によって始められ、日本でも1971年(昭和46)から活発な活動をしている。
[岩井弘融・高原正興]
『岡崎文規著『自殺の社会統計的研究』(1960・日本評論社)』▽『大原健士郎著『日本の自殺』(1965・誠信書房)』▽『稲村博著『自殺学』(1977・東京大学出版会)』▽『稲村博著『子どもの自殺』(1978・東京大学出版会)』▽『布施豊正著『自殺と文化』(1985・新潮社)』▽『E・デュルケーム著、宮島喬訳『自殺論』(中公文庫)』▽『高橋祥友著『自殺の精神分析』(1994・清和書店)』▽『大原健士郎著『「生きること」と「死ぬこと」――人はなぜ自殺するのか』(1996・朝日新聞社)』▽『高橋祥友著『精神医学から考える生と死』(1997・金剛出版)』▽『川人博著『過労自殺』(岩波新書)』▽『厚生統計協会編・刊『国民衛生の動向』(2008)』
改訂新版 世界大百科事典 「自殺」の意味・わかりやすい解説
自殺 (じさつ)
suicide
Selbstmord[ドイツ]
みずからの意志でみずからの生命を絶つ行為。ヨーロッパ語でも日本語同様に〈みずからを殺す〉という意味の合成語である。したがって,人に犠牲を強いられたり強制されたりして死ぬのは自殺とはいわない。古来,自殺に対する評価も多様であり,宗教上の教義とも深くかかわっている。コーランやタルムードでは自殺を罪悪として厳しく禁止しており,キリスト教も自殺を罪悪としてきた(一時期,凌辱を避けるための婦人の自殺の是非についての論議があった)。ヒンドゥー教においては,自己の意思で自己を解放するとして自殺者をたたえ,また,夫の後を追って焼身して死ぬ未亡人は大いに称賛された。古代ギリシアでは有罪を宣告された犯罪者がみずからの命を絶つことは認められていた。また,仏教徒には焼身自殺をすることによって,社会に抗議する例がみられる(ベトナム戦争中のベトナムの僧尼,日本の江川桜堂を盟主とする〈死なう団〉など)。
直接動機と準備状態
自殺の場合,まず注目されるのは直接動機である。これを年齢別に検討すると,小・中学生の場合は,環境的ストレス,つまり親の叱責(しつせき)とか,両親の離別,学校でのトラブルなどが多く,高校,大学へと進むと,個人的な問題(受験や就職,失恋,前途不安など)での悩みが多くなる。壮年期では,男子は仕事上の問題,女子は家庭的トラブルなどが動機となりやすい。老年期にはこれに加えて,身体疾患などが重視されるようになる。しかしどの例をみても,自殺は準備状態(自殺傾向)と直接動機との間に関数的関係があることに留意すべきである。まず準備状態が発生し,それに直接動機が加わって,自殺が決行される。したがって,自殺の準備状態が非常に強く形成されている場合には,直接動機は予想外に小さなものでも自殺は発生する。逆に自殺傾向が非常に小さい場合は,かなり強力な直接動機が加わらない限り,自殺は生じない。この自殺傾向の要因には,社会・環境的要因,生物学的要因,心理学的要因の三つが考えられる。
自殺の社会学的側面
自殺の社会的要因を研究したのは,フランスの社会学者É.デュルケームである。デュルケームは《自殺論Le suicide:étude de sociologie》(1897)で,社会現象としての自殺(率)の動向を,個人の病態心理的要因や人種,遺伝,気候などの生物学的要因では説明しきれないとし,社会的構造の特性との関連で考えた。すなわち,彼は近代社会に特徴的な自殺のタイプとして,(1)愛他的自殺suicide altruiste,(2)利己的自殺suicide egoïste,(3)アノミー的自殺suicide anomique,(4)宿命的自殺suicide fatalisteの四つに分類した。(1)は社会の統合が過度のため,個人の関心や生命が過小評価される社会において現れ,自殺は義務として強いられ,また,尊敬すべき行為とみなされる場合もある。(2)は社会の統合が弱体なため,人格的自由,責任,独立が規範とされ,社会的規範が個人の行動を規制する機能を失ったとき,個人間の結びつきの弱い者に現れる。デュルケームは統制力や団結性の強いカトリックに比べて,宗教的個人主義の強いプロテスタントにこの傾向が強いとする。(3)は社会の規範喪失状態において現れる自殺で,社会の変動期に価値意識の崩壊による個人の方向感覚の喪失,安定感の消滅から生ずる。(4)は過度の抑圧状態(奴隷や囚人の場合など)において生ずるアノミー的自殺である(アノミー)。
このように自殺は社会構造との関係で説明されてきたが,同一社会構造においても,年齢・性別・地域・季節などの社会的環境の相違によっても違いは生じてくる。世界的傾向として,高齢者,女子より男子,既婚者よりも独身者や離・死別者,農村住民より都市住民,季節としては春に自殺率が高いと統計上いわれている。
自殺の生物学的側面
生物学的要因で最初に問題になるのは遺伝的要因である。自殺そのものが遺伝するとはまず考えられないが,自殺を生じやすい精神病(たとえばうつ病や統合失調症など)や異常性格の遺伝的要因は考えられることである。自殺者多発家系の存在も決してまれではなく,うつ病,統合失調症,異常性格,敏感関係妄想(内気で対人関係に敏感な性格の持主が,困難な社会的状況に置かれたときに抱く種々な妄想)などでは,一般社会人に比べて自殺頻度が高く,なかでもうつ病は自殺の主役である。これらの病気の多くは思春期に好発するが,例外として老年認知症(初期に自殺が多い)やアルコール依存症などがある。救急病院に運ばれてくる自殺企図者の大部分は,うつ病を中心とするうつ状態によって占められている。女子の場合は,月経時の緊張状態が症状を増悪させることがよくある。しかし注意すべきことは,たとえうつ病者であっても,そのなかで自殺を企てる者はごくわずかだということである。彼らの背景にはなんらかの特殊事情,とりわけゆがんだ人間関係の存在することが知られている。また一卵性双生児で,片方が自殺を企てたとしても,他方が自殺を企てない例もかなり多く,自殺者を生物学的要因のみから説明することはできない。
自殺の心理学的側面
自殺者のなかには,幼・小児期に親の欠損状態にあった者や過去に家出や非行の既往をもつ者が多く,とくに子どもの場合,家出は大きな問題で,自殺への一つの注意信号ともなっている。自殺は〈耐えがたい環境からの逃避〉の悲惨な結果とみることができる。非行,反抗,神経症的態度,アルコールや薬物への依存などはすべて,逃避的態度の表現といえ,自殺はその極端な一つの現れなのである。なお自殺者に特有の性格特徴が見いだせるかどうかという点では定説はない。しかし,外界の刺激に反応を起こしやすい性格,つまり,偏倚(へんい)した性格の者に自殺が起こりやすいことは想像に難くない。また自殺者には対人関係がうまくいってないケースが多い。
自殺の日本的傾向
日本は世界有数の自殺国といわれてきた。確かに1901年の人口10万人当りの自殺死亡率はスイス(22.4),ドイツ(20.8)に次いで日本(17.7)であり,1980年の統計でも,ハンガリー(44.9),デンマーク(31.6),オーストリア,スイス(ともに25.7),フィンランド(24.7,ただし1979年の統計),西ドイツ(20.9),スウェーデン(19.4)などに次いでいる(日本は17.7)。これらの国々と比較して日本の場合,65歳以上の高齢者の自殺死亡率が急激に上昇していることが顕著な相違である。また,かつては20歳代に大きなピークをもっていた自殺率が,近年,40歳代後半から50歳代前半に大きな山を描くように変化してきている。この傾向は女子にほとんどみられず,男子特有の現象としてあることに特徴がある(図参照)。この傾向は自殺の理由として,〈経済生活問題〉が増えていることと関連してくる。サラ金(サラリーマン金融)からの借金を苦に自殺する者が急増している傾向や,夫婦が離別ないし死別した場合の自殺率が男子244.5(離別),126.9(死別)に対し,女子の場合にはそれぞれ35.9,41.8であるという統計に示されている。また,日本的特徴の一つとして,都市住民よりも農村住民に自殺率が高いということがある。東北,中国,四国,九州に高率の県が多い(男子では宮崎,島根,岩手,高知,鹿児島の順,女子では岩手,島根,新潟,香川,山口の順である。1980年性・都道府県別自殺訂正死亡率より)。情死や心中(異性心中,一家心中,母子心中)のような集団自殺も日本的特徴といえよう。
以上のような日本の自殺傾向は,デュルケームの分類に従えば,愛他的自殺の範疇(はんちゆう)に含まれよう。このことは日本において都市化が進んでいるにもかかわらず,家族や職場,農山漁村における人間関係や価値意識が変化することなくあることから生ずるといえる。かつて青年は家族制度や封建遺制の狭間に苦しみ,加えて就職,結婚等の問題を抱え,絶望や抗議のために自殺する傾向をもっていた。近年,40~50歳代の壮年層は,企業の中間管理職的立場にあって,家庭内問題を抱えて自殺に走る傾向を示している。この場合,世間にわびて,あるいはわが身の潔白を訴えての自殺,夫の浮気を諫(いさ)めるための自殺(諫死),主人の後を追っての自殺(殉死)など,その手段こそ違うものの武士の切腹と似た意識が働いていよう。また,情死や心中に典型的にみられるように,この世ではかなえられない望みを死をもって〈あの世〉で成就させようという自殺は,死という手段をもって,社会に抗議しようという側面ももつ積極的なものであった。しかし,この種の復讐(ふくしゆう),抗議としての自殺は個我の確立や民主化の過程で,徐々に利己的自殺やアノミー的自殺に推移してきている。高齢化社会日本の今後の課題として,老人が社会保障の不備のため,老後の生活に絶望して自殺する傾向の増加があろう。
執筆者:大原 健士郎
法律問題
自殺ほど,それに対する社会的価値判断が揺れ動き,情熱的に議論され,各論者の感情・価値観等の対立による強い影響を受けた人間の行為は少ない,といわれる。歴史を概観する限りでも,自殺を忌諱すべきものとして社会的に取り扱う傾向は確かに看取されるものの,自殺それ自体を一般的に明確に現代と類似の意味での犯罪であるとして処罰する法思想・伝統の存在は確証しえない。ローマ法では宣誓により生命が国家に帰属せしめられた兵士の自殺未遂のみが処罰された。よくいわれる自殺処罰へのキリスト教の影響も,なるほど,15世紀の教会法大全は自殺を殺人と同じに扱いはするが,続く時代の1532年のカロリーナ刑事法典は刑罰等を科されることを恐れたために自殺する者の財産没収を定めるにとどまるし,1796年のテレジアナ法典も自殺者の正式埋葬を禁ずるにすぎない。そして,18世紀中葉の啓蒙思想の興隆以降は,1813年のバイエルン刑法典を経て,ドイツ全土に自殺不可罰の気運が拡大したのである。イギリス,アメリカでも,自殺はコモン・ロー上の犯罪ではあったが長い間処罰例はないに等しく,イギリスでは1961年の自殺法により,アメリカでは,自殺をコモン・ロー上の犯罪として維持する州でも対応する刑罰の不存在化により,明確に不可罰となった。日本でも《公事方御定書》,新律綱領,改定律例等が不義・姦通の男女の心中に関する罰則等を置いていたにすぎない。現在では,自殺を犯罪とすることは,イスラム世界等なお行末を見届ける必要のある地域はあるものの,日本を含め世界的に過去のものとなったといえよう。これは,刑法と宗教ないし倫理との関係を断ち切り,生命も原則的に個人の自由な処分に服すべき個人的法益としてとらえようという思想への転換傾向を示すものであるといえよう。しかしこの問題はなお未完である。それを示すのが,自殺を不可罰とするにもかかわらず,実質的な自殺に関係する罪,すなわち自殺関与,嘱託殺人,承諾殺人等を残している立法例の存在である。
執筆者:伊東 研祐
自殺の法医学
ある人が死亡した場合,その人が自殺したとするためには,その人に死ぬ意志があったこと,死に至った行為が,死ぬことを目的としたその人の行為であること,その行為によって死ねることをその人が知っていたことが必要である。たとえ,本人に死ぬ意志があっても,他人に依頼して死亡した場合は自殺ではない。逆に,本人に死ぬ意志はないのに,他人にそそのかされ,強制されて,その人の行為で死亡した場合も自殺ではない。このような場合,日本の法律では,依頼された人,そそのかし,強制した人は殺人罪に問われる。また,縊死(いし)した場合のように行為と死亡との間に直接的因果関係がある場合は自殺として問題はないが,腹部を刺して,そのために生じた腹膜炎によって死亡した場合のように,間接的な因果関係の場合も,病死ではなく,自殺である。死亡した人の自殺,他殺,事故死の鑑別は非常に重要であるが,目撃者のないことがほとんどである自殺を,明確にすることは困難な場合が少なくない。一般に,自殺の場合は遺書が残されていることが多く,日記や手紙などに自殺の意志が表明されていることもある。しかし,この遺書を利用して殺人が行われることもある。仏壇に花や水を供えたり,墓参りをしたり,それとなく近親者や友人に別れをし,部屋を片づけ,形見分けをし,近親者の命日,仏壇の前や祖先の墓前を選んだり,身なりを整え,女性では膝を紐で縛って自殺することがある。自殺の場合,死者の表情に苦悶がないことが多く,他人と争った跡もないのが普通である。
自殺の必要条件としては,死亡に至った行為が死亡者自身で行える可能性がなければならない。自殺の手段は,厚生省の人口動態統計(1981)によると,第1位は縊首,絞首およびその他の窒息(54.7%)で,ガス体による中毒(10.9%),入水(7.3%),固体または液体による中毒(6.8%),高所からの飛降り(6.3%)が続いている。
縊首はいわゆる〈首つり〉であり,これによって死亡した場合を縊死というが,古くから自殺の手段としてよく利用されているため,他人が強制して縊首させ,自殺を偽装したり,他の手段で殺害したのち,首をつらせて自殺を偽装することもある。自殺の場合は,踏台になるようなものを用意していたり,傾斜した場所を利用していることが多い。紐状物が切れて床や地面で死亡していることもある。山などで木の枝に紐状物をかけて死亡したものでは,死体が白骨化し,紐状物もなくなった場合でも,木の枝に圧迫痕が残っていることがあり,縊首の決め手になることがある。ガス自殺の場合は,部屋に目張りをしていたり,布団の中にゴム管を引き込んで死亡していることがある。この場合,部屋にガスが充満し,冷蔵庫などの電気製品の火花により引火し,爆発炎上することがあり,事故との区別が困難なことがある。また,他殺死体を自殺死体に偽装するため,ガスを放出することもあるが,死体を解剖検査し,ガスの体内分布を調べることにより自殺を区別することが可能である。入水自殺の場合は,入水場所に履物をそろえて脱いでいることがあり,体が浮上しないように腰や足に石やコンクリートブロックを紐でくくりつけていることもある。死亡後から発見されるまでに数日以上経過し,腐乱していることが多く,身元確認ができないこともあり,また,酩酊状態で死亡しているものでも,自己の過失によって川や海に転落したもの,他人に突き落とされて溺死したものとの区別が,死体解剖などの詳細な検査を行っても,不可能なことがある。高所からの飛降り自殺の場合は,飛び降りた場所に履物をそろえて脱いでいることがある。しかし,自殺とその他の死亡との区別をするため,詳細な検査や捜査を必要とする場合が少なくない。固形または液体による中毒は,薬毒物中毒が主体であり,催眠剤が薬局で自由に入手でき,また,パラチオンなどの毒性の強い農薬が広く使用されていた昭和30年代に流行した。その後,催眠剤や毒性の強い農薬が規制されたため,減少した。この場合,他殺との区別を要するものはまれであるが,誤飲によって死亡した場合との区別を要することがある。刺器や刃器による自殺の場合は他殺との区別を要することが多い。一般に自殺の場合は,ためらい創とか逡巡創といわれる浅い創が致命創の周囲にあったり,自殺の際によく利用される部位,頸,左胸,腹,両手首にみられる。致命的な創は1個のことがほとんどで,使用された刃物が死者の近くにあることが多い。まき割りのような重量のある刃器が使用されることは少なく,ナイフや包丁がよく使われている。他殺の場合は,上肢に刃物を払いのけたり,刃物をつかんだりした際にできる防御創がみられることが多い。
→傷
執筆者:福井 有公
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
最新 心理学事典 「自殺」の解説
じさつ
自殺
suicide
なお,「自殺は,本人が力尽きた状態のときに行なわれる。」「『自殺する』と言っている人は,自殺しない。」などの見方は誤解を含むものであり,実際には,自殺は心身のエネルギーが回復し始めたころに実行されることが多く,また,自殺者の4分の3は生前に自殺の意志を他者に話しているという指摘もある。
自殺の動機については諸説がある。たとえば,ひどいストレス状況にある人間には自殺が最も実行しやすい問題解決行動に見えてしまうという説や,自身の欠点,失敗の事実,期待と現実のギャップなどに直面することを避けるために自殺するという説がある。また動機に関連するものとして,ある人物の自殺が生じた後に他の複数の自殺が引き続き生じる現象(群発自殺とよばれる)が青少年期に好発することが知られている。
自殺は残された人間に長期にわたって苦悩をもたらす。また,自殺を阻止された経験をもつ人の多くは,その後,自殺を防いでくれたことに感謝するといわれている。臨床心理家が自殺の恐れがある人と自殺について話し合うのは,多くの場合,自殺について尋ねられると,人は恐ろしさや恥ずかしさのために言えなかったことを語れるようになり,孤立感が弱まるためである。この時,自殺の方法を具体的に説明する人ほど,自殺の実行可能性が高いと考えられる。自殺の実行可能性が高い場合,臨床心理家は,守秘義務の例外として,関係者と連絡を取るなどの対応を行なうことがある。なお,コミュニティにおけるホットライン・サービスは,自殺の意思をだれにも伝えられないほど孤立している人の意思を受け止め,自殺を思いとどまるよう働きかけるという重要な機能を果たしている。
自殺しようとしている人への具体的介入としては,その人になんらかの精神障害が認められる場合は,その障害の治療に焦点を当てる方法がある。一方,精神障害そのものよりも,その人のもつ自殺したいという考えに焦点を当てる方法もある。たとえば,シュナイドマンShneidman,E.S.は,自殺したい人に特有の視野の狭さに着目し,自殺以外にも問題解決につながるような選択肢があることを気づかせていくような介入を行なっている。
さらに,不幸にして自殺が起きてしまった後,周囲の人間に与える影響を最小限に抑えることを目的とした対応(ポストベンション)も重要である。たとえば,組織集団の中で自殺が生じた場合,その組織には,臨床心理家の協力なども得ながら,構成員たちに,自殺の事実を中立的な立場で伝えたり,身近な人間の自殺を経験した場合に生じうる反応や症状などを説明したり,個別に相談できる機会(カウンセリングなど)を提供したりするなどの対応が求められるといえる。 →気分障害 →統合失調症
〔森田 慎一郎〕
出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報
百科事典マイペディア 「自殺」の意味・わかりやすい解説
自殺【じさつ】
→関連項目いじめ|自殺対策基本法|社会病理学
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「自殺」の読み・字形・画数・意味
【自殺】じさつ
 宣伝〕臣、
宣伝〕臣、 (すい)(刑杖)せらるるを須(もち)ひず。
(すい)(刑杖)せらるるを須(もち)ひず。 ふ、自
ふ、自 することを得んと。
することを得んと。 ち頭を以て檻を
ち頭を以て檻を ち、
ち、 血面を被(おほ)ふ。
血面を被(おほ)ふ。字通「自」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自殺」の意味・わかりやすい解説
自殺
じさつ
suicide
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「自殺」の解説
自殺
世界大百科事典(旧版)内の自殺の言及
【エゴイズム】より
…このようにエゴティズムの極限は社会秩序への志向をまったく欠いているので,その極限の形態は個人主義と完全には重ならない。 E.デュルケームは自殺の一つの類型に利己的自殺suicide egoïsteという名称を与えた。彼によれば,人間はひとりでは生きていく目的を見いだすことができない。…
【殺人罪】より
…例えば,いわゆる植物状態からの生命維持装置の除去や脳死状態の者からの移植のための心臓摘出等は,脳機能の不可逆的停止をもって人の終期とする脳死説の立場からは殺人とはならないが,なお社会通念上大きな反発を呼んでいるのである(〈臓器移植〉の項参照)。 殺人罪に関連する特殊な犯罪類型として,刑法は,人を教唆もしくは幇助(ほうじよ)して自殺させる罪(自殺関与罪)と,被殺者の嘱託を受けもしくは承諾を得てこれを殺す罪(嘱託殺人罪,承諾殺人罪)を定める(202条)。刑は6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮。…
【死神】より
…死死の舞踏死霊【佐々木 宏幹】
[日本]
日本の死神は疫病神とは異なり,身体の健康な者を死に誘うという神である。和歌山県田辺では首つり,投身などの自殺者を見つけたときは2人以上で助けねばならない,1人で助けると死神が救助した者につくからだという。また,死神がつくと死ぬのがおもしろくなるらしく楽しそうに自殺するという。…
【デュルケーム】より
…1902年よりパリ大学教授を務める。おもな著書として《社会分業論》(1893),《社会学的方法の規準》(1895),《自殺論》(1897),《宗教生活の原初形態》(1912)などがある。 デュルケームは,社会的事実を,個々人の心意やそれらの単なる総和には還元できない一種独特の実在としてとらえることを要請し,これを対象としてのみ固有の方法をもった社会学が成立しうるとした。…
※「自殺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...