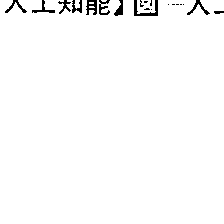共同通信ニュース用語解説 「人工知能」の解説
人工知能(AI)
人間の脳のように物事を学習したり膨大なデータから推測して判断したりできる技術。「ディープラーニング(深層学習)」と呼ぶ手法で大量のデータを解析する。自動運転車の制御技術や病気の早期発見など多分野に応用される。利用者の指示に基づいて文章や画像を作成する「生成AI」が急速に普及している。企業の生産性向上が期待される一方、誤情報拡散や著作権侵害が懸念されている。
更新日:
人工知能(AI)
言語の理解や推論といった人間の知的活動を、コンピューターを用いて再現しようとする技術。性能が急速に向上し、最近は文章や画像をつくる「生成AI」が普及している。仕事の効率化に役立てようと、多くの企業や自治体が導入に乗り出す一方、事実に基づかない情報を生み出す「ハルシネーション(幻覚)」などのリスクも指摘されている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「人工知能」の意味・読み・例文・類語
じんこう‐ちのう【人工知能】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] artificial intelligence の訳語 ) 学習、推論、問題解決、判断、知識表現など人間の能力に近い機能を持ったコンピュータによる情報処理システム。応用分野として、自然言語理解、機械翻訳、コンサルテーション(エキスパート)システムなどがある。AI。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「人工知能」の意味・わかりやすい解説
人工知能
じんこうちのう
artificial intelligence
概論
人工知能は、「計算(computation)」という概念と「コンピュータ(computer)」という道具を用いて「知能」を研究する計算機科学(computer science)の一分野である。誤解を恐れず平易にいいかえるならば、「これまで人間にしかできなかった知的な行為(認識、推論、言語運用、創造など)を、どのような手順(アルゴリズム)とどのようなデータ(事前情報や知識)を準備すれば、それを機械的に実行できるか」を研究する分野である。AI(エーアイ)と略称でよばれることも多い。人工知能という研究分野名は、1956年夏にアメリカのダートマス大学で開催された研究集会(ダートマス会議)で命名された。この会議には、その後の人工知能研究で指導的な役割を果たすマッカーシーJohn McCarthy(1927―2011)、ミンスキーMarvin Minsky(1927―2016)、ニューウェルAllen Newell(1927―1992)、サイモンHerbert Simon(1916―2001)らが参加し、コンピュータによる人間の知的機能のシミュレーションをテーマに議論が行われた。
「知能とは何か」に対する十分な答えは、いまだ存在しない。人工知能の目標の一つは、遂行に知能が必要と思われる特定の課題(たとえば、囲碁を打つ)を対象に、その課題を人間並みあるいは人間以上にうまく行うコンピュータ・プログラムを実現することである。もう一つの目標は、そのようなプログラムの実現を通して、「知能とは何か」の答えに迫ろうというものである。このような目標をもつため、人工知能は、知能に関連した他の研究分野、とくに、哲学、心理学、認知科学、脳科学、言語学などと交差する部分をもつ。
[佐藤理史 2018年6月19日]
人工知能の歴史(第1期)
人工知能の研究は、人工知能という名が生まれる前から始まっている。フォン・ノイマンによるミニマックス法の定式化が1944年。知能をはかるテストとして有名なチューリングテストの提唱は1950年。このころには、シャノンによるチェスの研究も行われた。ニューラルネットワークの祖ともいうべき、マカロックWarren McCulloch(1899―1969)とピッツWalter Pitts(1923―1969)のニューロンのモデルは1943年。機械翻訳の研究も1950年代初期に開始されている。
1960年代の人工知能研究は、探索の時代として位置づけられる。おもに、ゲームなどの「閉じた世界」の問題を対象に、問題の局面(状態)と局面変更操作(オペレータ)によって問題を厳密に定義し、初期状態から終了状態(解)に至る経路をみつけるという探索問題としてとらえ、これを効率的に解く手法が研究された。一般に、初期状態から到達可能な状態の数は、オペレータの適用回数に対して指数関数的に増加する。これを回避する一つの方法はヒューリスティクスの導入であり、それを利用するA*(エースター)アルゴリズムは、この時期の主要な研究成果の一つである。
英語で人間と対話を行うプログラムとして有名なELIZA(イライザ)は、ワイゼンバウムJoseph Weizenbaum(1923―2008)が1966年に開発した。このプログラムの内部には、人間の発言(入力)から応答を生成するためのルールが組み込まれており、あたかも人間の発言内容を理解しているかのようにふるまうことができた。「人工無脳」といった名称でよばれる日本語版のプログラムは、ELIZAの亜流である。
この時期のシステムの実現法は、ルールに基づく記号処理が主流である。マッカーシーによって開発されたプログラミング言語Lisp(リスプ)が、システム構築によく用いられた。一方、非記号処理の代表格であるニューラルネットは、1958年ごろにローゼンブラットFrank Rosenblatt(1928―1971)によりパーセプトロンが提案されたが、1969年に処理能力の限界が示され、研究は一時、下火となった。
[佐藤理史 2018年6月19日]
人工知能の歴史(第2期)
1960年代までの第1期が探索(手続き)の時代とすれば、1970年代から1980年代までの第2期は、知識の時代である。この時期は、人工知能技術を実世界の問題へ応用することが試みられ、エキスパートシステムexpert systemとよばれる専門家代行システムが開発された。有機化合物構造の推定を行うDENDRAL(デンドラル)、血液中のバクテリアの診断の支援を行うMYCIN(マイシン)、コンピュータシステムの構成支援を行うR1などがその代表格である。これらの課題を遂行するためには、その課題に関する専門知識が不可欠である。つまり、やり方(手続き)だけでは課題は遂行できず、専門知識を活用しなければならない。このような背景により、コンピュータにいかにして知識を与えるか(知識獲得)、それをどのようにコンピュータ上で表現・格納しておくか(知識表現)、そして、それをどのように活用するか(推論方式)などが中核的研究課題となり、知識工学(ナレッジエンジニアリングknowledge engineering)という名でよばれるようになった。知識表現では、フレーム、スクリプトなど、関連したひとまとまりの知識を記述する方法が提案されるとともに、黒板モデルのように独立したルール群を協調させて動作させる方法などが考案された。推論方式も、それまでのif-then型ルールによる推論以外に、類推を志向した事例ベース推論、不確実性を扱うベイジアンネットワークなど、多様な方式が考案された。知識獲得の問題は、最後まで未解決として残り、知識獲得ボトルネックとよばれた。これは、知識のなかには人間が意識化できないもの、言語化(記号化)できないものが存在することや、多くの課題遂行において、いわゆる常識が必要なことなどの理由による。機械学習の研究は、この時期から徐々に拡大していくが、その理由の一つは、このような背景による。
この時期の自然言語処理では、ウィノグラードTerry Winograd(1946― )のSHRDLU(シュードル)が有名である。このシステムは、積み木の世界の操作を対象に、構文解析、意味解析、推論による問題解決を実現し、自然言語理解における意味や外部知識の重要性を示した。シャンクRoger Schank(1946―2023)による概念依存関係理論とそれを用いたストーリー理解の研究も、意味理解を志向した研究として有名である。
非記号処理では、多層ニューラルネットとその学習アルゴリズムであるバックプロパゲーション(誤差逆伝播(でんぱ)法)が、コネクショニストモデルとして広く知られるようになり、ニューラルネットが復権した。また、人工生命や遺伝的アルゴリズムなど、生命や進化から着想を得た研究も現れた。
日本では、1982年(昭和57)より「第五世代コンピュータ」プロジェクトが実施され、知識処理用の並列コンピュータ、および、そのコンピュータ上で動作する並列論理型言語が開発された。このプロジェクトは多くの成果を生み出したが、開発された並列コンピュータや並列論理型言語は広く使われるようにはならなかったため、世の中の評価は失敗という形で定着している。プロジェクト終了後、バブル経済の崩壊も相まって、日本の人工知能研究は停滞期に入る。
世界的にも、この時期は、パーソナルコンピュータの普及(ウィンドウズ95が1995年に発売)、インターネットの爆発的普及(1996年ごろ)など、コンピュータとネットワークが社会に浸透した時期であり、これらの陰に隠れて、人工知能はそれほど脚光を浴びなかった。その例外は、IBMが開発したディープ・ブルーDeep Blueとよばれるチェスプログラムで、1997年に世界チャンピオンのカスパロフGarry Kimovich Kasparov(1963― )を破り、大きな話題となった。ロボティクスの分野では、ブルックスRodney Allen Brooks(1954― )がサブサンプションアーキテクチャ(包括アーキテクチャ)という新しい考え方を示した。これは、現在の掃除ロボットのルーツとなった。
[佐藤理史 2018年6月19日]
人工知能の歴史(第3期)
インターネットは急速に拡大し、2000年ごろからは、社会の重要なインフラとなった。ウェブページをみつけるサーチエンジン、百科事典的知識を蓄積するウィキペディア、アマゾンに代表されるインターネット通販などを通し、大量の知識とデータが電子データとしてインターネット上に蓄積されることになった。2000年代後半には、スマートフォンやソーシャルネットワークサービスが出現し、行動履歴などの個人に関わるデータも電子的に蓄積できる体制となった。これらの状況の変化は、現在の人工知能のブームに大きく関わっている。
2010年以降、現在に続く第3期の勃興(ぼっこう)の直接の要因の一つは、IBMが開発したワトソンWatsonが、クイズ番組Jeopardy!(ジョパディ!)で人間のチャンピオンに勝利したことである。英語の質問に英語(の単語)で答えるという形式のクイズで人間を凌駕(りょうが)したことは、衝撃をもたらした。第二の要因は、2012年の画像認識コンテストにおいて、ヒントンGeoffrey Hinton(1947― )らのチームが深層ニューラルネットの学習(ディープラーニング)を使って優勝したことである。第三の要因は、自動車メーカーにとどまらず、グーグルやアップルといったIT企業が自動車の自動運転の研究を推進し、完全自動走行が可能になってきたことにある。これらの要因が相まって、人工知能技術の社会応用への期待が一気に高まった。このブームの真っただ中、2016年には囲碁プログラムのAlphaGo(アルファ碁)が、世界のトップレベルの棋士に完勝し、機械学習・ディープラーニングの力を世に知らしめた。
スマートフォンには音声インタフェースが搭載され、声で命令することが可能となり、スマートスピーカー(AIスピーカー)とよばれる据置き型の装置の普及も始まっている。第3期がこれまでと大きく異なる点は、最先端の技術が、すぐに身近な商品やサービスに反映される点である。機械学習技術は、データサイエンスの中核技術として社会のあらゆる場面で大きな変革を起こすと期待されている一方、人間がコントロールできないものを生み出すのではないかという漠然とした不安も広がっている。
[佐藤理史 2018年6月19日]
研究分野とその特徴
人工知能の研究は多岐にわたっている。情報や知識をコンピュータ上で表現・格納する方法(知識表現)、活用する方法(推論方式)、入出力系(各種メディア処理)、獲得方法(知識獲得・機械学習)などが主要な研究対象である。入出力系では、画像や映像を対象としたパターン認識・画像処理、音を対象とした信号処理・音声認識・音声合成、ことばを対象とした自然言語処理、動くからだを実現するロボティクスなどの分野が人工知能研究から生まれ、それぞれ比較的独立した研究分野に発展している。近年は、とくに機械学習が脚光を浴び、大規模データからのデータマイニングや画像処理、音声認識、機械翻訳などに応用されている。
人工知能研究は「まだ解き方がわかっていない問題」の解き方を考えるという性質上、解き方がほぼ判明した時点で、研究対象から外れていく。このため、時代の推移とともに対象とする問題は変化していくことが避けられない。たとえば、かな漢字変換や郵便番号の手書き文字認識は、過去には人工知能の主要な研究対象であったが、現在はそうではない。コンピュータ応用のフロンティア領域が人工知能であるという見方は、ほぼ的を射ている。
[佐藤理史 2018年6月19日]
人工知能の現状と課題
現在、専門家からみた人工知能(研究)と、世の中の多くの人々が「人工知能」ということばから想起するイメージには大きな乖離(かいり)がある。SF小説、映画、漫画などで描かれる「人工知能」は、主体的意志をもったコンピュータシステムあるいはロボットである。一方、人工知能研究・技術によって実現されているもの(たとえば、AlphaGo)は、単なるコンピュータ・プログラムである。これらのプログラムはプログラムコードに従って「計算」しているだけで、それ以上のことは何も行わない。しかし、これらのプログラムの機能を説明する際、「システムが自ら学習する・推論する・判断する」といった擬人化表現が用いられ、あたかも意志をもった主体であるかのように描写される。このため、上記の乖離が助長される傾向にある。
現在の機械学習の中核は、最適化とよばれる数学技法である。これは、人間の「学習」とは大きくかけ離れており、人間のように学ぶコンピュータが実現されているわけではない。現在のニューラルネットは、神経細胞の数学的モデルを基礎としたネットワークであるが、脳のモデルではない。これらの事実は広く知られているとはいいがたく、前述のような漠然とした不安をもたらす一因となっている。
今後、人工知能がどのように発展していくかは、専門家にも十分にわかっていない。人間の脳と同じようなものがつくれると考えている研究者もいるが、大半の研究者は、当面、そのようなものはつくれないだろうと考えている。もし、SFに出てくるような人工知能が実現できる日がくるのであれば、それは「知能とは何か」に答えがみつかったことを意味する。
[佐藤理史 2018年6月19日]
『中島秀之著『知能の物語』(2015・公立はこだて未来大学出版会)』▽『竹内郁雄編『AI 人工知能の軌跡と未来』(2016・別冊日経サイエンス)』▽『川添愛著『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』(2017・朝日出版社)』▽『人工知能学会編『人工知能学大辞典』(2017・共立出版)』▽『長尾真著『人工知能と人間』(岩波新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「人工知能」の意味・わかりやすい解説
人工知能 (じんこうちのう)
artificial intelligence
人間にみられる種々の知的機能をコンピューターを使い機械的に実現しようとする試みをいう。また人工知能を,知的機能をもった機械を工学的に実現するために行う知能のモデル化の研究ということもできる。現在のコンピューターはフォン・ノイマン型といわれるもので,形式論理に基づく逐次演算を正確に,高速に行う機械であり,人間の頭脳労働のある種の過程の遂行に用いられ,ある一面において人間の頭脳とは比較にならない優れた性能を発揮する。それゆえコンピューターが登場した当初には,万能機械ともてはやされた。しかしながらコンピューターの出す結果は,人間の与えたプログラムを忠実に実行したものであり,はたして人工頭脳の名に値するものであろうかという疑問が起こる。直観的に考えるとか,大胆な推定をして一足とびに結論をうるとか,複雑な情報を認識し理解するとか,というような思考機能は,明確な論理の連鎖にはなっていない。たいていは論理的であるというより,むしろ情緒的な面を多分に含んだ不明確な思考の連鎖である。このような人間のもつ思考機能に対してコンピューターを過大に評価することへの抵抗のあらわれとして,1967年アメリカの数理哲学者ドレイファスHubert Dreyfusは《錬金術と人工頭脳》と題する論文を発表し,現在のコンピューターが人間の頭脳と本質的に異なっていることを明示する四つの領域を指摘した。すなわち,(1)パターン認識,(2)ゲームの実行,(3)自然言語の学習と翻訳,(4)問題解決である。これらの領域は確かに現代のコンピューターでは完全に遂行できない。元来,この種のことは人間でも完全に行えないものであり,経験や勘がものをいう範疇のものである。ドレイファスのこの指摘のように数理哲学的には不完全なものであっても,情報処理の新しい知能的手法をコンピューターに与えることにより,従来人間しか行えなかったことを機械にある程度代行させていこうという研究がなされている。これがいわゆる人工知能の研究である。
研究の歴史
人工知能の思想はA.M.チューリングの知能的機械intelligent machineryに求めることができよう。彼は1950年に《計算機構と知能》という論文で,機械が思考しうるかどうかについて論じた。しかし,これは50年代の半ばまでは思索の域を出なかった。コンピューターが進歩して複雑な仕事をするに十分な能力をもつに至った50年代後半から,前述の意味での人工知能の研究が開始された。人工知能という言葉を最初に使ったのは,マッカーシーJ.McCarthy,ミンスキーM.Minsky,C.E.シャノンらであり,1956年のことだとされる。60年にはマサチューセッツ工科大学で,数値でなく記号を取り扱うことを容易にしたリスト処理用のコンピューター言語LISP(リスプ)がマッカーシーによって作られた。同大学の人工知能研究のリーダーであるミンスキーは61年に論文《人工知能への足がかり》を発表し,この時代の人工知能研究に力強い推進力を与えた。こうして人工知能という言葉が定着することになる。60年代の初期にはチェスやチェッカーなどのゲームの実行,定理の証明などの研究が始められた。64年ころからコンピューターに人間が普通に使う(自然の)音声言語を理解させる音声認識の研究が始まり,高校生の数学の問題を理解して解くプログラムSTUDENTが作られた。60年代初期には,人間なみの知能をもつコンピューターの誕生まで,それほど時間がかからないとする希望的な予測も存在した。しかし60年代末になると,人工知能の達成は予想外にむずかしいと考えられるようになった。
70年代に入ると,外界の知覚的認知と行動を行い,自然言語を理解し,命令を実行し,質問応答をも行うシステム,すなわち,知能ロボットの研究が開始された。一例としてウィノグラードT.Winogradが71年に発表したSHRDLU(シャドルー)システムがあげられる。これはコンピューターのディスプレーに表示される積木に関し,人間と機械が普通に対話できるシステムであった。たとえば,〈赤い立方体を大きな緑の立方体の上に置け〉と人間が言えば,もし緑の立方体の上に四角錘がのっていればそれを移動させてから赤い立方体を積み,人間が各積木の位置をきけばそれに答えるなど,SHRDLUは,積木の形,色,大きさ,位置などを理解しており,自然言語を使って質問応答,命令の実行を行った。これらの研究から,常識すなわち人間のもっている日常的な知識(前記では積木の操作とか位置関係)や対象世界ごとの専門的知識などのたいせつさが認識され,いかなる形式によってコンピューターの中にそれらを表現し,かつまたいかにうまく使うかを中心とした知識表現・利用の研究が盛んになった。なお,実用の域に達したか,あるいは達しつつある応用的研究成果として,知能ロボット,コンサルテーションシステム,数式(数値的でなく記号的な)処理ソステムなどがあり,また文字や図形のパターン認識のシステムがある。
方法論
人工知能の関連する科学,工学・技術の分野は広範である。図はニルソンN.J.Nilssonの示した人工知能方法論の基礎と応用分野との関連図表である。人工知能の基礎を支える研究課題は次のように整理,分類される。(1)問題解決と知識表現 問題解決とは,ある行動とそのもたらす結果についての予測,実施,評価を行うことである。その方法として合理的な推論法と発見的探索法との二つがある。
推論法については一階述語論理(記号論理学)を用いた定理証明がある。定理の証明とは,公理と推論規則が与えられ,それらを組み合わせて結論を導くことであり,人工知能で扱う問題解決の多くは定理証明に帰着する。定理証明はロビンソンJ.A.Robinsonの導出原理による推論法(1965)以来たいへん進歩したが,定理証明法を問題解決に使用してもあらゆる可能な組合せを探索する必要がある。定理や公理の組合せの数学的拡大はまぬがれえない。莫大な量の一般的知識から適切な事実を公理として選択する有効な手段を見いだすことが課題である。
問題には,たとえば囲碁や将棋などのゲームのように,可能な指し手がいくつかあり,その各手に対し相手の可能な指し手が複数存在するというように,その可能性がちょうど木の枝のように広がっている木構造をとる場合や,たとえば一つの町から他の町へいたる道が網の目のように存在するように,ネットワーク構造をとる場合などがある。これらの問題を解決するためにはそれらの〈道〉を順次探索することが必要となる。しかし〈道〉が多岐にわたる場合,そのすべてを探索することは時間的に不可能となり,何らかの方法で探索する〈道〉を限定する必要が生じる。人間のもつ経験に基づいて道を限定しながら行う探索法を発見的探索法という(探索理論)。これらゲームの理論から発展してきた発見的探索法は木探索アルゴリズムや定理証明法と結合して,ゲームのみではなく,知能ロボットの設計とその行動方略においても有用なことがわかってきた。
問題解決において問題解決の手順とともに重要なのは,問題を解くために必要な知識である。コンピューターで知識を処理するためにはその形式化,つまり知識の表現・記述法が必要となる。近年,推論に便利な表現とか行動に便利な表現を志向した,問題解決向きまたは人工知能用のプログラム言語が多数開発されている。
→知識表現
(2)知識獲得の問題 認識によって知識を獲得する知的プロセスを認知ということにしよう。認識が受動的性格をもっているのに対し,認知は能動的性格をもっていて理解を伴わなければならない。認知するためには現在もっている知識(知識ベース)を使って推論し問題解決する必要がある。このようなプロセスをへて知識獲得が行われると考えられる。
(3)自然言語の理解 言語を理解するためには,文法など言語構造についての広範な知識のほかに意味処理の方法を必要とする。言語学でいえば,言語運用に関するモデルを明確にすることが対応する。文(言語表現)にあらわれる環境についての常識と事象自体についての文脈上の知識をも利用することの重要さが明らかにされ,そのような特性をもつ言語理論,文法理論が研究されはじめた。言語解析・理解システムにおいても,知識の表現・記述構造と推論・理解機構の研究が大きな課題となっている。
→自然言語処理
応用的研究
このように今日の人工知能研究では知識の表現構造,推論の方式,知識獲得方式の三つが共通する基盤であるが,これらを基盤として各種の問題を解決したり,科学技術分野あるいは診断・治療用コンサルテーションシステムなどの開発を行う研究分野についてはファイゲンバウムE.Feigenbaumの提唱により知識工学knowledge engineeringと呼ばれている。
人工知能の応用的研究成果の一つは知能ロボットであろう。NASAのジェット推進研究所が開発した火星探査ロボットが有名であるが,このロボットは情景の認識・理解をする視覚と,対象物に近づいてそれを壊さないでつかみとる触角などの知的機能を備えたロボットであって,単なるマニピュレーターではない。そのほか,人工盲導犬,自動車の無人運転などの開発が日本においても行われている。
最近,知識工学の成果として各種のコンサルテーションシステムが注目を浴びている。化合物の分子構造を発見的に求めるDENDRALとか,患者の問診とか各種検査データから治療法を推論する血液伝染病や脳膜炎の診断治療システムMYCIN,あるいは構造体の解析・設計システム(その代表例がSACON)などが有名である。たとえばDENDRALでは,質量スペクトル分析データと核磁気共鳴スペクトル分析データとユーザーの与えるある種の事前条件とから,有機化合物の科学構造を同定する。その能力は大学院化学系博士課程修了者のそれよりまさるといわれており,スタンフォード大学その他で盛んに使われている。MYCIN,PUFF,SACONなどもスタンフォード大学で開発された。日本においても東大病院において心不全の治療に対するコンサルテーションシステムMECS-AIが開発されている。これらのコンサルテーションシステムはエキスパートシステムあるいは知識ベースシステムとも呼ばれ,(1)各分野の専門家が意識して,あるいは無意識のうちに問題を解くのに使っている専門的な知識を抽出し,それをコンピューターで取り扱えるようにした知識ベースと,(2)知識ベースの知識を問題解決に利用するための推論機構からなる。
今後の動向
人工知能の研究と人間の知能の本質の解明とは,最終的に互いに相一致する研究分野であるかもしれないが,現在のところ研究の方法・態度,当面の目標のいずれをとってもかけ離れているようにみえる。その理由は,そもそも人間なみの知的能力を実現するためにどのような研究のアプローチをすればよいかということがまだよくわかっていないからでもある。またその反面では,それがわからなくても機能を狭く限定すれば実用的な機械を作りうる可能性があるし,現在の技術でどこまでやれるかを追求するのも重要なことである。
次に,重要な今後の研究課題をみると,(1)認知科学cognitive science,(2)知識工学,(3)知的コミュニケーション,(4)以上の3者の集大成として総合化認知システムintegrated cognitive systemを実現する総合技術の研究開発が展望される。コンピューターの分野では,逐次演算に代え並列処理を行うことで処理時間を大幅に短縮するもの,あるいは非ノイマン型コンピューターの研究が進められている。また従来の研究の延長線上にある研究,たとえばプログラムの自動作成・自動修正のためのプログラム理論の研究,ある種の高階述語理論の研究,LISPマシンのような高水準マシンの研究,最後にアクター理論とそのファームウェア化などがあるが,これは人工知能研究とコンピューターアーキテクチャーの開発との相互刺激の側面である。
執筆者:田中 幸吉+長尾 真
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「人工知能」の意味・わかりやすい解説
人工知能【じんこうちのう】
→関連項目AI|コンピューター・ゲーム
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人工知能」の意味・わかりやすい解説
人工知能
じんこうちのう
artificial intelligence; AI
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
IT用語がわかる辞典 「人工知能」の解説
じんこうちのう【人工知能】
図書館情報学用語辞典 第5版 「人工知能」の解説
人工知能
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の人工知能の言及
【コンピューター】より
… 逆に,形式的に明解に記述できないものはコンピューターにはうまく扱えない。1950年代半ばに提唱された人工知能が今日に至るまでコンピューターの最大の難問の一つとされているのは,人間の知能,なかんずく人間の常識を,形式的に明解に記述する方法がいまだに発見されていないからである。 記述の問題に起因するこのようなコンピューターの能力の限界を破るために,この項目で述べたノイマン型のコンピューターのモデルではなく,人間の神経回路網をモデルにしたニューラルコンピューターの研究や,小さな記述の種を出発点にして多数のコンピューターを並列に動かして,元の記述からは予期できないような計算の振舞いを創発させる研究が行われている。…
【情報科学】より
…技術面では個別のコンピューターからコンピューターネットワークへとシステムの構成が発展し,さらに直列処理集中制御のノイマン方式を超えて,並列処理分散制御方式の実現への試行が始まった。 人間が行っている知的情報処理をコンピューターに行わせること,これは人工知能と呼ばれ,コンピューターサイエンスの長い間の夢であった。研究初期の課題であったパターン認識はすでに実用の域に達し,さらに進んでパターンの理解,自然言語の処理,意味の理解,知識構造の解明,エキスパート(専門知識)システムの開発へと研究が進んでいる。…
【知識表現】より
…人工知能システムにおいては,問題解決を高度化するために知識ベースに蓄積した専門的な知識に頼ることが多い。コンピューターでは形式的な処理しかできないことを考えると,そのような知識をコンピューター上に表現し,形式的な操作で解が導けるように定式化する必要がある。…
【プログラミング言語】より
…Lispでは関数もS式で書き表せるデータであり,プログラムの中で関数をデータとして組み立てた後,evalと呼ぶ関数によってただちに実行することができる。このことがLispに高い柔軟性を与え,記号処理の機能と併せて人工知能などの分野の研究に多く使われることとなった。反面この柔軟性のために初期のLispはインタープリターに基づく処理系が中心であり,処理速度が遅いという評判を招いた。…
【ロボティクス】より
…この時点では,それぞれの要素技術が未熟であったため,以降,各要素技術に分化して独立に研究がなされてきた。それらは主に,(1)環境を認識するための視覚をはじめとする各種センサーの開発とセンサー情報の処理手法(とくに計算機による視覚機能の代行を目指す研究分野はコンピュータービジョンと呼ばれている)に関する研究分野,(2)認識された環境の状態に基づき,事前にもっている知識などを用いて推論したり,動作を計画するなど,頭脳に当たる部分に関する研究,一般に人工知能Artificial Intelligence(以下,AIと略記)と呼ばれている研究分野,そして(3)実際に行動するための機構の開発・設計・製作およびそれらの制御に関連する研究分野の三つである。 これらの要素技術を系列的に組み合わせれば,知能ロボットが実現できると考えるのは自然である。…
※「人工知能」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...