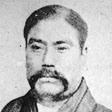日本大百科全書(ニッポニカ) 「岩崎弥太郎」の意味・わかりやすい解説
岩崎弥太郎
いわさきやたろう
(1834―1885)
三菱(みつびし)財閥の創設者。号は東山。天保(てんぽう)5年12月11日、土佐国安芸(あき)郡井ノ口村(高知県安芸市)の地下(じげ)浪人で上農の弥次郎の長男として生まれる。1848年(嘉永1)から高知の紅友舎で、さらに1855年(安政2)から江戸の安積艮斎(あさかごんさい)の塾に学んだ。1859年から藩職につき、1866年(慶応2)には藩の開成館貨殖局に勤務して翌年に二度目の長崎出張を行い、各国の商館との取引で企業家としての腕を磨いた。維新後の1870年(明治3)10月から開成館大阪商会は藩から分離し、九十九(つくも)商会という海運業を行う私商社になり、弥太郎はその指揮者となった。同商会は三川(みつかわ)商会、ついで1873年に三菱商会と改名し、岩崎弥太郎個人の企業になった。彼は強いナショナリズムを唱えて太平洋郵船(アメリカ)、P&O汽船(イギリス)を打ち破り、また大久保利通(としみち)や大隈重信(おおくましげのぶ)など政界と結んで、台湾出兵(1874)や、西南戦争(1877)を頂点とする内乱を鎮圧するための新政府の軍需輸送を独占して巨利を占め、全国汽船総トン数の73%を手中に収めた。これと並行して燃料確保のため高島炭坑を買収(1881)、三菱為替(かわせ)店による荷為替金融と倉庫業の開始(1876)、東京海上保険(現、東京海上日動火災保険)への出資(1878)、官営長崎造船所の貸下げ(1884)など、海運業からの多角化によって三菱財閥の基礎を築き、また吉岡銅山、明治生命保険(現、明治安田生命保険)、千川水道も経営した。弥太郎はつねに強い指導権を把握して「社長専制主義」を確立し、薩長(さっちょう)藩閥政治が確立した「明治十四年の政変」(1881)以後は「政治不関与」を唱えた。郵便汽船三菱会社と共同運輸会社の競争が頂点にあった明治18年2月7日に胃癌(がん)で死亡した。
[三島康雄]
『岩崎弥太郎・弥之助伝記編纂会編『岩崎弥太郎伝』上下(1967。複製版1980・東京大学出版会)』▽『三島康雄著『三菱財閥史 明治編』(教育社歴史新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「岩崎弥太郎」の意味・わかりやすい解説
岩崎弥太郎 (いわさきやたろう)
生没年:1834-85(天保5-明治18)
明治前期の代表的実業家で,三菱財閥の創立者。土佐国安芸郡の地下(じげ)浪人の長男として生まれた。英才を見込まれて1853年(嘉永6)に江戸の安積艮斎に学び,帰国後,土佐藩の吉田東洋や後藤象二郎の知遇を得たが,反骨と直情のため逆境に落ち,新田開発や官林伐採を行う。67年(慶応3)に土佐藩の開成館長崎出張所の下役となり,坂本竜馬やT.B.グラバーらの外国商人と交渉,明治維新後の69年(明治2)には大阪にある藩の大坂商会の幹部。70年同会が藩営を離れた(名称も九十九(つくも)商会に変更)後,71年に彼の私的企業にかえて海運業(三川(みつかわ)商会)を拡大,政府の海運保護と台湾征討・西南戦争による蓄積で内外の競争会社を撃破,海運王となった。社名は73年三菱商会,75年三菱汽船会社,郵便汽船三菱会社(略称三菱会社)。投資先を炭山や銅山,造船や荷為替,保険,貿易,鉄道,土地などに広げ,社長独裁により三菱会社の基礎を固めた。大久保利通,大隈重信,松方正義らの顕官と結んで特権的な助成や優遇をうけ,急激に政商として躍進した。81年から三菱征伐の動きが強まり,長州閥や三井系が82年共同運輸会社を設立,三菱会社との間に共倒れに近い競争がつづいた。この間に彼は病死し,弟の弥之助(1851-1908)が2代社長となり,85年政府の勧告により両社は合同し日本郵船会社が誕生した。なお,海運部門を引き渡した後の三菱会社は,高島炭鉱や長崎造船所などを中心に,海から陸へ転進した。
→三菱財閥
執筆者:旗手 勲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「岩崎弥太郎」の意味・わかりやすい解説
岩崎弥太郎【いわさきやたろう】
→関連項目岩崎小弥太|加藤高明|近藤廉平|東洋文庫|六義園
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「岩崎弥太郎」の解説
岩崎弥太郎
いわさきやたろう
1834.12.11~85.2.7
幕末~明治期の実業家。土佐国生れ。高知藩の開成館長崎出張所・大坂出張所などに勤務して藩の貿易に従事していたが,1870年(明治3)開成館大坂商会を形式上藩営から分離して,九十九(つくも)商会と改称。翌年同商会を引き継ぎ,72年三川商会と改称,さらに73年三菱商会,75年郵便汽船三菱会社とした。同社は台湾出兵の軍事輸送を担当して政府の保護をうけるようになり,西南戦争の軍事輸送も担当した。しかし新汽船会社共同運輸が設立され,83年から弥太郎の死まで同社との激しい競争が続いた。吉岡銅山・高島炭鉱を経営,三菱為換(かわせ)店を設立し,長崎造船所を借りうけるなど,のちの三菱財閥のもとを築いた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「岩崎弥太郎」の意味・わかりやすい解説
岩崎弥太郎
いわさきやたろう
[没]1885.2.7. 東京
明治初期の実業家,三菱財閥の創設者。父は土佐藩の郷士。弥太郎は後藤象二郎の推挙を得て藩営の商社,開成館に勤務し,維新の戦役では大坂の土佐商会にあって藩の兵站を引受けた。廃藩置県に際し,同商会を継承して三菱商会を興し,徹底した商人的合理主義と排外的闘志をもって,政府ことに大隈重信の保護のもとに海運界で独占的地位を築き,さらに鉱山,造船,海上保険にも進出した。もっとも彼の独占は言論界の批判と反三菱,反改進運動を激化させ,三井系の海運会社である共同運輸会社の設立と挑戦という事態を招いた。彼は屈せずに競争し,政府による調停の成立を聞きつつ死亡した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「岩崎弥太郎」の解説
岩崎弥太郎 いわさき-やたろう
天保5年12月11日生まれ。土佐(高知県)の地下(じげ)浪人岩崎弥次郎の長男。安積艮斎(あさか-ごんさい),吉田東洋に師事。長崎,大坂の藩営の商社土佐商会で手腕を発揮。明治6年三菱商会をつくり社長。台湾出兵,西南戦争などでの軍需輸送により海運界を支配。さらに鉱山,荷為替,造船などに事業を拡大し,三菱財閥の基礎をきずいた。明治18年2月7日死去。52歳。名は寛。号は東山。
【格言など】創業は大胆に,守成には小心なれ(遺訓)
旺文社日本史事典 三訂版 「岩崎弥太郎」の解説
岩崎弥太郎
いわさきやたろう
明治時代の実業家。三菱財閥の創設者
土佐藩郷士出身。後藤象二郎らの知遇をうけ,土佐藩の通商に従事。1873年三菱商会を創設し海運業に進出。佐賀の乱・台湾出兵・西南戦争で軍事輸送にあたり巨利を博し,三菱財閥の基礎を確立した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の岩崎弥太郎の言及
【開拓使官有物払下事件】より
…北海道でも函館の豪商はこの払下げに対抗して開拓使の官船・倉庫の払下げを出願し,函館区民の請願・建白運動がおこった。払下反対運動のかげに国会早期開設を唱える筆頭参議大隈重信と岩崎弥太郎(三菱),福沢諭吉の共謀援助があるという説が流布され信ぜられた。政府は10月12日払下げの中止とともに国会開設の詔勅を発し,あわせて大隈重信とその系統の官僚を免職にした。…
【三菱銀行[株]】より
…三菱商事と並んで三菱グループの中核。1870年(明治3)岩崎弥太郎は九十九(つくも)商会(後に三菱商会と改称)を設立し海運業を営んでいたが,76年大阪に為替局を設置,荷為替により荷主に資金を融通した。これを80年に三菱為替店として分離独立したのが三菱銀行の前身である。…
【三菱財閥】より
…岩崎弥太郎が創立し,岩崎一族が支配した三井に次ぐ日本第2の財閥。江戸時代から発起した三井財閥や住友財閥に対抗し,明治以後に没落郷士出身の岩崎家が空拳から政府や軍需と結び,初期の海運中心から鉱業や造船,商業や金融,不動産など国策に呼応して総合財閥となった。…
※「岩崎弥太郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新