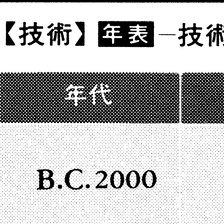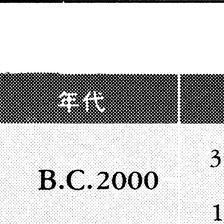精選版 日本国語大辞典 「技術」の意味・読み・例文・類語
ぎ‐じゅつ【技術】
- 〘 名詞 〙
- ① 物を取り扱ったり、事を処理したりする方法や手段。
- [初出の実例]「武芸にすぐれ奇特な技術のある者」(出典:玉塵抄(1563)三五)
- 「其人の技術を以て人民の智徳を進めたるに非ず」(出典:文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉二)
- 「特(ひと)り小説の脚色(しくみ)のみならず総じて美妙の技術(ギジュツ)に在ては」(出典:小説神髄(1885‐86)〈坪内逍遙〉下)
- [その他の文献]〔史記‐貨殖列伝〕
- ② 科学の理論を実際に応用し、自然を人間生活に役立つように利用する手段。
- [初出の実例]「阿蘭之国精二乎技術一也」(出典:解体新書(1774)序)
- 「塩酸曹達は人々普く知る所の海塩にして日常の食味を調し百般の技術に用ること多し」(出典:舎密開宗(1837‐47)内)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「技術」の意味・わかりやすい解説
技術
ぎじゅつ
「技術」ということばほど広く使われる用語は少ない。手法あるいは手段ということばに置き換えても差し支えないところに、最新の意味が含まれているかのように使われる。たとえば、政治技術、経営技術、教育技術、広告技術、スポーツの技術などである。「技術」はまた「科学技術」というように「科学」と並置して使うことが多くなっている。これは、科学的な技術という意味で使うよりは、科学とそれを応用する技術とをひっくるめて使う用語である。確かに科学は技術と接近し、現代では科学と技術とを計画的に結合することが可能となっており、今後さらに「科学技術」の用語は普及するであろう。しかし「技術」は「科学」より早く発生し、人類誕生以来の長い歴史をもっている。「科学」との接近は、1870年代の先進国で、大企業が物理学者や化学者を雇用し、政府が軍備や産業振興のために研究所を設置するようになってからである。それまでは「芸術」や「技芸」とよばれ、「科学」は「自然哲学」とよばれていた。
この「芸術」や「技芸」はギリシア語のテクネtechnē、ラテン語のアルスars(英・仏語のart、独語のKunst)を語源とし、「わざ、業、技、芸」の意味に使われていた。その最初の定義は、フランス百科全書派のディドロによる「同一の目的に協力する道具と規則」である。彼の協力者ダランベールは『百科全書』の序論で、F・ベーコンの「変化させられ加工される自然」という概念を用いて、その歴史をも自然史の一部門に加えた。このように、ある目的をもって活動する人間が創造した手段(道具、後の機械その他を含む)と知識(規則、さらに法則を含む)の体系systemという概念がすでに約2世紀前に確立しているのである。この時代の啓蒙(けいもう)思想の影響を受けて、ゲッティンゲン大学教授ベックマンJohann Beckmann(1739―1811)は、それまで「技芸史」Kunst Geschichteとよばれていた科目に、1772年「技術学」Technologieという呼称を与え、新しい学問領域を提唱した。内容は合目的手段の体系的目録である。このドイツで発生した「技術学」は、英語のテクノロジーtechnologyであり、17世紀から使われていたが、アメリカのジャクソニアン・デモクラシー時代から普及した。技術学の概念は、啓蒙思想から発展した民主主義の成立と深い関係があると同時に、人工的自然史という概念が伴っていることに注意せねばならない。
技術学との区別が問われることばに工学がある。工学engineeringの語源は、ラテン語のingenium、すなわち発明または天才の所産を意味する。エンジニアengineerとは、17世紀の火砲職人仲間のことであり、巧妙な兵器を発明して、これを取り扱う人たちをさしている。ところが、イギリスの万能的天才といわれるスミートンは1771年、civil engineerということばを初めて使用することによって、火砲職人と区別して市民に奉仕する職業人の役割を強調し、同年、その組織Society of Civil Engineeringを結成した。イギリス産業革命の末期、1818年、世界最初の工業専門家の学会Institution of Civil Engineersが創立された。この学会から機械、通信、電気、鉄鋼などの諸学会が分化、独立した。最初のシビル・エンジニアの学会は、運河、港湾、橋梁(きょうりょう)、道路など、いわゆる土木関係の職業人が多かったため、日本ではcivilを「土木」、engineeringを「工学」と訳している。「工学」はその成立の起源から、職業的な技術を意味する。大学の工学部やさまざまな工学会が、現在では一般市民と縁の薄い特殊な職業人の教育と研究を意味しているのは、そうした歴史的起源による。一方、「技術」と「技術学」は、教授の自由、学習の自由を誇りとし、職業教育を求めないゲッティンゲン大学の一般教育から誕生したが、その性格は今日にも及んでいる。しかしその後、ドイツ語のテヒノロギーTechinologieとテヒニークTechnik、英語のテクノロジーtechnologyとテクニクtechnique、ロシア語のテフニカтехникаとテフノロギアтехнология、日本語の「技術」と「技術学」も、厳密に区別して使っているわけではない。ドイツ語のテヒニークを即物的、テヒノロギーを学問の意味に使うことが多いが、英語や日本語ではますます混同され、普通、英語ではtechnology、日本語では「技術」が使われる。しかし、この混同は、「技術」とは何かという本質的な問題を論ずるときに混乱となる。「科学」が「技術」に接近し、「科学技術」に一体化される今日、その起源に立ち返って考えることが必要となってきている。
[山崎俊雄]
技術論
世界の技術論
技術とは何か、技術の概念をどのように規定するかを論じる学問を「技術論」とよんでいる。
産業革命による道具から機械への移行、その経済的意義について、最初に深い関心を寄せたのはマルクスである。マルクスは、ベックマンの後継者をはじめ、ユーアAndrew Ure(1778―1857)の『製造業の原理』(1835)、その他の技術学文献を広く読み、『経済学批判』(1861~1863、草稿)のなかに「機械、自然諸力と科学の応用」と題するノートをまとめ(1968公表)、後の彼の主著『資本論』第1巻(1867)のなかで、批判的な技術史とは「社会的な人間が生産諸器官を形成する歴史であり、それぞれの社会組織の物質的基礎を形成する歴史である」と述べ、道具から機械へ、機械体系から自動機械体系への発達を予測していることはよく知られている。
19世紀70年代以降、新興工業国ドイツに、カントの「物自体の考え」を継承した、技術についての哲学的思索の労作が誕生する。カップErnst Kapp(1808―1896)の『技術の哲学要綱』(1877)、ノワレLudwig Noiré(1829―1889)の『道具と、人類発展史に対するその意義』(1880)は、道具が人間に理性をもたらし、道具は人間の器官が外へ射影されたものであると唱えた。
20世紀に入ると、第一次世界大戦まではドイツ技術の躍進と歩調をあわせ、発明の創造こそ技術の本質であるとし、それが文化の世界を推進させるという楽観論的見解が支配するようになる。ベントUlrich Wendtの『文化力としての技術』(1906)、デュ・ボア・レーモンDu Bois-Reymond(1818―1896)の『発明と発明家』(1906)、デサウエルFriedrich Dessauer(1881―1963)の『技術的文化』(1908)、ツィンマーEberhard Zschimmer(1873―1940)の『技術の哲学』(1914)などがそれである。ついで、ゾンバルトの『技術と文化』(1910)は、技術を合目的な手段体系に拡大解釈し、ゴットル・オットリリエンフェルトの『経済と技術』(1914)は、技術の自立的要素を抽出してみせた。経済学者ゾンバルトとゴットルの著書はドイツ技術論の双璧(そうへき)とよばれる。その技術的合理主義は、産業合理化を進めた資本主義安定期の指導理念となった。経済学者の多くは、その後の技術的改良による産業合理化の社会的帰結である失業問題を論じた。ホブソンの『合理化と失業』(1930)、レーデラーの『技術的進歩と失業』(1931)などがそれである。
第一次世界大戦後のアメリカでは、テクノクラシーtechnocracy(技術主義)の父と仰がれるベブレンが『技術家と価格制度』(1921)を著し、技術主義思想のアメリカ的原型をつくった。1929年、アメリカに端を発した世界大恐慌と、ソ連の五か年計画の発端は、テクノクラシーに代表される技術主義的社会改造論を課題とした。1932年、電気工学者スタインメッツらを中心に「技術家同盟」Technical Allianceが結成され、エネルギー決定論による資本主義的矛盾の解決を図る技術論を展開した。このような風潮のなかで生まれたマンフォードの『技術と文明』(1934)は、その後のアメリカ技術論に深い影響を与えている。彼は恩師のイギリスの生物学者・社会学者ゲデスPatrick Geddes(1854―1932)の技術史観を採用し、人類の歴史を動力と原料の技術的複合体から説明し、機械文明による矛盾の解決を「生」への接近、奉仕の夢に託した。今日のバイオテクノロジーの予言者である。
1930年代が進むにつれてふたたび戦争の危機が迫り、多くの科学者が反戦・反ファシズム運動に参加した。イギリスの物理学者バナールは『科学の社会的機能』(1939)を著し、科学の現状を社会との関連において考察し、当時の研究組織がいかに科学と技術の自由な発展を阻害しているかを指摘し、科学者の社会的自覚を促した。この書は第二次世界大戦中における統一戦線の結成に大きな役割を果たし、その趣旨は第二次世界大戦後の1948年、「世界科学者連盟」が採択した科学者憲章に生かされている。
[山崎俊雄]
日本の技術論
日本で「技術」の概念が論じられるようになったのは第一次世界大戦後の1920年代からである。ことばとしての「技術」は、西周(にしあまね)の『百学連環』(1870)に初めて使われたが、西欧と同様に「技術」も「芸術」もartに包括されていた。技術が社会問題として論じられ始めたのは、米騒動を起点とする1920年代の諸運動の一環としてである。第一次世界大戦中に、日本の工業は飛躍的に発展し、技術者の産業、行政における役割は増大した。それまでの法科万能主義に対して「技術者の覚醒(かくせい)、団結、社会的機会均等」を標語とする革新的な技術官僚、理工農科系出身経営者の諸団体が結成された。しかし日本のテクノクラット運動は、同時に発生した欧米の知識労働者の運動や科学者の反ファシズム運動と連帯する機会を失い、戦争に協力する科学技術動員体制に組み込まれていった。
技術の概念が理論的に研究されるようになったのは1930年代からである。三枝博音(さいぐさひろと)、岡邦雄(くにお)(1890―1971)、服部之総(はっとりしそう)、戸坂潤たちが、1932年(昭和7)に創立した唯物論研究会は、当時の国際的な技術主義と反技術主義の風潮を批判するために技術論を重要な課題とした。戸坂は、技術の領域こそ自然科学と社会科学とを共軛(きょうやく)しうる唯一の体系をなす哲学とみなし、『技術の哲学』(1933)を著した。1933~1935年、技術論をめぐって、戸坂のほか、岡、永田広志、梯(かけはし)明秀(1902―1996)、相川春喜(1909―1953)らが加わり、技術論争が展開された。論争の焦点は技術の主観的契機に置かれ、技術概念の主観化が永田により批判され、相川によって次の結論が与えられた。すなわち「人間社会の物質的生産力の一定の発展段階における社会的労働の物質的手段の複合体であり、一言にしていえば、労働手段の体系に外(ほか)ならない」(相川春喜『技術論』1935)。この帰結、いわゆる「労働手段体系」説は、ブハーリンの引用とされているが、実はブハーリンを批判したレーニンの意見であることがのちに明らかとなっている。この説の要点は、人間労働を可能にしたものの複合体(労働手段体系)に技術の本質をみいだしていることである。隣接概念の「科学」は自然と社会における法則を発見する創造活動であると同時に、その知識の体系(総体)である。科学に主体的要素をもたせるために、技術から主体的要素を取り除くのが労働手段体系のねらいである。もちろん芸術には主体的要素が含まれるから、技術と芸術がアートに一体化されていた近代以前では、技術にも主体性があったが、近代以後では主体性は技術から取り除かれた分だけ科学に与えられつつあるといってよい。
しかし、第二次世界大戦中、日本にも初めて科学技術政策が登場すると、人間主体の根源である労働の概念に技術の概念が代置される傾向が生まれた。相川は「実践的一者の立場」(『現代技術論』1940)に変質し、三木清は「技術は手段であるとともに自己目的であり」、そして「技術は行為であり、行為の形態である」(『技術哲学』1942)というように、技術に主体と客体との統一を求める立場が支配し始めた。この立場は労働手段体系を基本的に支持しながらも、技術を実体としてとらえることに同意できない人たちの見解を代表し、第二次世界大戦後も引き続き唱えられた。
[山崎俊雄]
戦後世界の技術論
第二次世界大戦後の日本では、人間行動の目的意識性と合法則性とを指摘し、その主体性を強調する技術論が自然科学系学者によって提唱された。物理学者の武谷三男(たけたにみつお)はすでに1940年に、「技術とは生産的実践における客観的法則性の意識的適用である」と述べた。この説は1942年相川によって批判されたが、労働を生産的実践に置き換え、意識的適用に技術の本質があるという見解として今日でも流布している。とくに技術は科学の応用であるという俗見に支持されている。
外国では、旧ソ連や東ヨーロッパがもっとも技術論に積極的であった。ズボルイキンA. A. Zworykin(1888―1982)は、かつて「社会的生産の体系における労働手段」(1938)と規定し、科学アカデミー版『技術の歴史』(1962)もこの規定を採用した。モスクワ動力大学のテキスト(1958)では「自然に関する認識に基づいて、人間によって創造される労働手段の総体」と規定している。このように、当時のソ連では、日本の唯物論研究会以来の「労働手段体系」説に近く、日本でいう適用説はまったくみいだせなかった。しかし、1962年の第22回共産党大会で定式化された党綱領に「科学技術革命」論が採用されてからは、この論を特徴づける「科学の直接生産力への転化」という命題をめぐって、当時のソ連国内はもとより国際的にも多くの議論がなされた。『ソビエト大百科事典』(第3版)では、技術を「生産過程の遂行と社会の非生産的サービスのために創造された人間の活動手段の総体」としている。「科学技術革命論」のもう一つの特徴は、生産様式から生産関係の側面を捨象した「技術学的生産様式」を論じていることで、その技術学とは「労働手段と労働対象との結合様式」と定義される。生産力を構成する三つの要素である労働対象、労働手段および労働力と、技術および技術学との関連は1930年代からの国際的な研究課題である。
戦後の日本では、戦前の論者に次いで、山田坂仁(1908―1987)、吉岡金市(1902―1986)、原光雄(みつお)(1909―1996)、田辺振太郎(しんたろう)(1907―1987)、星野芳郎(よしろう)(1922―2007)らが、この技術論論争に加わり、最近でも自然科学と社会科学の両分野から多くの技術論が試みられ、百家争鳴の感がある。戸坂が1930年代初頭に述べたように、技術の本質を明らかにするには、自然科学と社会科学の協同研究によって自然と社会を貫く共通の法則性をとらえる方法論が必要である。なお、戦前・戦後の技術論論争は、中村静治(せいじ)により整理された『技術論論争史』(1975)および内外の技術論を整理した『技術論入門』(1977)のなかで述べられている。
[山崎俊雄]
技術史の研究史
ドイツにおける技術史
技術史の研究と教育は、技術そのものが科学的研究の対象となった時代から始まる。「技術学」という学問領域を独立させたベックマンは、その学問体系の一環として『発明史への寄与』(1780~1805)を著した。彼の弟子ポッペJohann H. M. Poppeの『技術学史』(1807~1811)は技術史学を体系化した最初の文献である。
ドイツの技術史研究は、ドイツの統一後、1870年代から盛んになり、工科系学校の大学への昇格とともに、大学教授は積極的な意欲をもって個別技術学の講義に歴史的記述を採用した。リュールマンC. M. Rühlmannの『一般機械学』(1862~1875)、『工業力学史』(1885)、カールマルシュK. Karmarschの『技術学史』、ルーローの『理論運動学』(1875)、ベックL. Beckの『鉄の歴史』(1891~1903)、ベックT. Beckの『機械製作史への寄与』などが19世紀における代表作である。なかでも『鉄の歴史』は全5巻の膨大な文化史的名著とされている。1900年代初頭、技術史研究は大学教育ばかりでなく現場技術者の全国的組織の運動を母胎として新しい段階を迎える。1856年に数人の青年技術者によって創設された、後の「ドイツ技術者連盟」Verein Deutscher Ingenieure(VDI)が、技術者に歴史を親しませる運動方針をたて、マチョスC. Matschossを中心に技術史研究の組織化を図った。連盟はさらに科学技術文化財の保存に着手、1925年ミュンヘンに「ドイツ博物館」を完成させた。なお連盟は1909年から『技術・工業史年報』を刊行、第二次世界大戦で刊行を中断したが、1965年から季刊誌「技術史」として復刊している。
[山崎俊雄]
イギリスにおける技術史
ドイツ歴史学派経済学の影響を受け、イギリスでは19世紀1870、1880年代より産業革命と個別技術史に関する著書が現れた。その研究の蓄積を受けて機械技術史家ディッキンソンH. Dickinsonらは「ニューコメン協会」を創立、1922年から会誌を発行、その研究には経済史家も参加し、イギリス産業革命の技術史的側面を実証的に解明することに寄与した。このようにイギリスでは、経済史家からの関心が深く、個別技術史家の層が厚い。第二次世界大戦中、弾道学の研究に従事、戦後、技術史やオートメーションの研究に携わったリリーS. Lilleyの『人間と機械の歴史』(1948)における技術を社会と歴史のなかに位置づける試みは、バナールと同様に戦前・戦中の反ファシズム統一戦線と無縁ではない。厚い技術史研究者層をイギリス最大の化学企業ICIが支援し、シンガーChales Singer(1876―1960)らの編集する『技術の歴史』全5巻(1957~1958、のちに2巻増補)が完成した。これは個別技術史家による実証的な個別技術史研究の集大成であり、権威ある定本となっている。
第二次世界大戦後の技術革新による技術記念物(遺物と遺跡)の破壊、消滅を防ぎ、文化財として調査、保存しようという国民運動の理論は産業考古学とよばれる。この学問は1955年イギリスで提唱され、産業革命期の工場や鉱山、鉄道、運河、橋、水車などの残存状態を調査し、その地域に復原して保存するという方法を重視し、時代の対象も古代から現代にまで拡大した。ナショナル・トラストその他の自然保護運動と結合して、1970年代から欧米、日本にもその研究と保存運動が進展し、技術史研究における文献依存の限界を突破し、地域の野外博物館創設を促進している。
[山崎俊雄]
その他の国の技術史
1929年当時のソ連は高等教育機関の教授要目中に技術史の採用を初めて決議した。その最初の試みであるダニレフスキーW. W. Danilevskiyの『18~19世紀技術史概観』(1934)は、日本の技術史研究にも大きな刺激を与えている。1935年ソ連科学アカデミー自然科学史・技術史研究所が設立され、世界最初の技術史の通史テキスト『技術の歴史』(1962)が刊行された。
アメリカでは、フーバー大統領夫妻が16世紀のアグリコラ著『デ・レ・メタリカ』の英語訳を刊行し、1920年代のテクノクラシー時代には技術古典の研究が盛んであったが、技術史の重要性が認識されたのは1957年のスプートニク・ショック以後である。1958年「技術史学会」が創立され、会誌『技術と文化』が発行され、急速に研究と教育が盛んになり、工学教育での技術史の有効性が強調されている。軍大学校のテキスト『技術と西洋文明』(1967)では、発明の企業化inovationと技術の用途的・地域的普及transferの問題が重視されている。
フランスでは、世界最古の技術史博物館であるパリの国立工芸博物館が研究の中心であり、同館のドーマM. Daumasが編集した『通史』全4巻(1926~1978)が刊行されている。オランダでは、アムステルダム大学のフォーブスR. J. Forbes(1900―1973)が古代技術史に他の追従を許さない著作を著している。近世日本と関係の深かったオランダとの技術史研究の交流が望まれる。
中国の技術史は、イギリス人ニーダムの『中国の科学と文明』(1961)が有名である。1957年中国科学院科学史研究所が創設され、会誌が発行されていたが、文化大革命のため停刊された。1980年中国科学技術史学会が創立され、翌年から会誌『自然科学史研究』が発行され、大学のテキストも出版されている。研究は古代の冶金(やきん)技術が多いが、近代化路線とともに近代、現代の研究が増加している。
[山崎俊雄]
日本の技術史
明治初期、福沢諭吉に代表される啓蒙(けいもう)的文明史の時代ののち、横井時冬(ときふゆ)(1860―1906)『日本工業史』(1897)に始まり、日本工学会編『明治工業史』(1931)に至る民間史学者による工業史の独立と個別工学者の協力の時代があった。本格的に技術史が論じられたのは、1930年代の技術論論争ののち、前記のダニレフスキーの邦訳(『近代技術史』1937)が刊行されてからであり、岡邦雄は、技術史が労働手段体系の発達史であり、技術学史は自然科学史の一部門であると唱えた。
自然科学史とともに技術史を研究する唯一の学会「日本科学史学会」が1941年(昭和16)に創立され、同学会編『科学革命』(1961)、『日本科学技術史大系』全25巻(1964~1972)が刊行され、会誌『科学史研究』が季刊で発行されている。技術ないし技術学を自然科学の一部に置くことは国際的にも異論があるが、技術を対象とする技術科学は明らかに自然科学の一部門であり、科学・技術の発展の内的要因と外的要因とを統一した総合的な科学史の建設は、この学会に結集してきた研究者の共通の課題である。科学史から技術を切り離すことは相互の領域を非科学的にするおそれを招くといわざるをえない。
[山崎俊雄]
技術の歴史
技術の起源
すべての起源は本質を研究するうえにもっとも重要である。技術が労働手段と関係があるとするならば、技術は労働の起源にさかのぼってその起源を探らなければならない。そこで想起されるのは、人間を「道具をつくる動物」と定義し、労働価値説の先駆者となったフランクリンである。この労働価値説は、スミス、マルクスの経済学に受け継がれ、人類の起源については、1876年エンゲルスが発表した論文「サルが人間になるにあたっての労働の役割」が現れた。エンゲルスによれば、直立歩行によって手は自由となり、手の自由は自然支配を可能にした。手が労働を生み、労働は人間の社会的協力を必要とした。この社会的な労働のなかから言語が発生し、脳髄とそれに奉仕する感覚器官が進化し、意識や抽象化力、推理力が発達し、これがさらに労働と言語とに反作用して発達を促進したという仮説である。
今日の先史人類学の考古学的実証研究によれば、人類には猿人、原人、旧人、新人の四つの進化の段階があり、放射能を利用して行う年代測定法によって、それぞれの段階の化石と石器の出現の時期が正確に判明するようになった。その結果、直立歩行と道具の創造が人類への進化に決定的役割を演じたという説がしだいに認められている。つまり人間の祖先の出現は数十万年ないし数百万年前、自由になった手で最初の道具をつくりだしたときにさかのぼる。換言すれば、人間は動物と異なり、自らの有機的な身体器官だけでなく、自然の物材を改造した非有機的生産器官を使用し、労働生産性を発展させ、その合目的的活動を拡大する。道具は合目的的活動としての人間労働を質的に規定し、その発達水準を示す客観的存在である。技術を客観的存在とする技術論の根拠はここにある。
[山崎俊雄]
技術学の起源
人間は自然の対象に直接働きかけるのではなく、客観的物材である道具という労働手段を介して働きかける。このことは、労働対象と労働手段との間、両者間の関連を客観的に認識することを可能にする。労働のなかで最初に生まれるのは感性的な認識の成果として得られる経験的な知識である。その知識はさらに労働によって鍛えられて確実なものとなっていく。石器を目的に応じて使い分けているうちに、労働手段と労働対象との相互の関連、両者の結合に関する原始的な技術学の認識が生まれてきた。原始石器から打製石器への移行、火の使用法を習得するにつれて、簡単な分化した労働用具が使われた。弓と矢は、そのなかで最初のもっとも複雑な道具である。
弓矢の出現によって狩猟が基本的な生産部門の一つとなった時代に、もう一つの重要な発明は粘土の土器の焼成である。狩猟の発達は野獣の家畜化と原始的な牧畜の発生を促し、その結果、母系氏族共同体は崩れ始め、父権制家族が発生し、原始的な農業が形成され始めた。その時代は新人の出現する後期旧石器時代である。この時代の最大の発明は、弓の弾力を利用して往復運動を回転運動に変えて孔(あな)をあけるドリルであり、発火のための道具をつくるのにも利用された。漢字の「工」は、穿孔(せんこう)して柄(え)をつけた斧(おの)が字源である。石材は石製の道具ばかりでなく、住居や社会的構造物の建造にも必要となり、地下から計画的に石を採掘する過程で、自然銅を発見し、加工しているうちに、製陶用の炉を使って金属を製錬する方法を知った。磨製石斧(せきふ)を使う新石器時代に、一部の種族は採集生活から農耕生活へ、狩猟生活から牧畜生活へ移り、農業生産力の発展に伴って、性と年齢による自然的分業から、牧畜、農業、手工業の社会的分業が現れ、社会的分業と交換の拡大から、原始共同体のなかに私有財産と階級が発生する。ただし牧畜は日本にはなく、縄文文化が新石器時代にあたる。
[山崎俊雄]
鉄器と科学
原始共同体から奴隷制への移行は、オリエント、インド、中国、日本、ギリシア、ローマなどの古代社会においてなされ、この時代に石器から金属器への移行が最終的に行われた。この時代の最大の技術的成果は鉄の製錬法の習得である。金属の新しい加工法が開拓され、紡織、製陶その他の手工業が確立されていく。手工業と商業の発達につれて都市が形成され、都市と農村との対立が生まれ始める。都市の形成により、宮殿、寺院、城壁などの建築技術が発達し、建築材料に対する需要の増大から鉱山業が発達する。また奴隷の獲得をおもな目的とする戦争のために軍事技術が急速に発達した。しかし、社会の基礎的な生産は奴隷が担っていたので、奴隷所有者は奴隷の重労働を軽減する道具の改良には関心をもたず、一方、奴隷は自分の利益にならない労働生産性の向上には関心を払わなかった。ただ大型の重量物の移動を必要とする建設作業では、多数の奴隷の力を単純に結合するだけではすまなくなり、出力の小さい人間原動機と移動させる重量物との間の伝動機構を必要とし、てこ、斜面、楔(くさび)、ねじ、滑車などの組合せの使用が生まれた。
これらの要素の運動が理論的に解明され、アルキメデスによって固体の静力学が基礎づけられ、ウィトルウィウスとヘロンによって機械学の概念が生み出された。石器時代までは個別的な知識にすぎなかった労働手段への認識が初めて普遍的な知識として体系化・理論化されることとなった。機械学の概念は近代の技術学、さらに技術科学への発展の道を開くものである。力学、機械学のほかに、農業生産の要求に応じて、天文学、数学などの自然科学が誕生したが、肉体労働と精神労働との分離が始まり、両者の間に対立が生まれる。
[山崎俊雄]
道具の専門化
封建制下での基本的な生産関係は、封建領主による生産手段の私的所有と生産労働者である農奴の不完全私有であった。自分の経営を保有する農奴は労働の生産性向上、したがって労働用具の改良に関心をもっていた。これは奴隷制度に比べて大きな前進であった。手工業は同業組合に組織され、親方、職人、徒弟制度の主従関係が生まれる。ここから鉄の犂(すき)と織機が普及し、家畜による農耕、野菜の栽培、水車による製粉、ぶどう酒の醸造などが発達した。中国起源の火薬、紙、印刷術、羅針盤が広く使われるようになるが、道具の多くは手動で、その発達は緩慢であった。
封建制度のもとでは、原動機としての水車とさまざまな伝動機構が発達した。水車はすでに奴隷制度のもとでも知られていたが、奴隷制がその使用を阻んでいた。水車の出力は人間の出力よりもずっと大きく、それまで人力によって動いていた多くの道具が一台の水車で動いた。道具自体の寸法や重量もはるかに大きくすることができた。したがって、水力原動機と道具とを結び付ける伝動機構が大いに発達した。とくに、往復運動を回転運動に転換するクランクと連接棒が重要となり、はずみ車が生まれるに至った。
封建制度の末期、地理上の大発見が相次ぎ、資本主義の本源的蓄積を迎えた。封建制度のなかに資本主義的生産様式が発生し、労働生産性を大幅に引き上げる新しい形態の生産組織としてマニュファクチュア(工場制手工業)が生まれた。マニュファクチュアは、部品別または作業別の分業による協業によって労働過程を単純化し、大量の未熟練労働者を生産に引き入れることを可能にした。労働者は一定の単純な部分作業を繰り返すこととなり、作業用の道具は専門化され、種類が大いに増え、労働生産性が高まった。より出力の大きい水力原動機の使用によって、手の道具、たとえばハンマー、臼(うす)、鋸(のこぎり)、ふいごなどの寸法を大きくすることができた。さらにこれらの道具は、それまで人間の筋力によってなされていた作業を、人間の手によらない機械にかえ始めた。しかしマニュファクチュアでの機械の使用は、補助的な生産過程、たとえば粉砕、混合、送風、揚水などにとどまった。
マニュファクチュアの主要な原動機は水車であり、後の機械の発達に大きな役割を与えたのは時計の構造である。また、この時代には金属に対する需要がますます大きくなり、鉱山業と冶金(やきん)業が一段と発達し、火器の普及に伴う軍事技術者が誕生した。冶金では溶鉱炉の高さが増し、送風がより強力になり、鉱石から銑鉄の連続的な高炉精錬法が出現し、18世紀イギリスでは石炭からつくられるコークスが新しい燃料として採用されるようになった。銑鉄を精錬して錬鉄をつくる方法や金属を加工する諸技術も開発された。
16世紀なかば、日本に鉄砲が伝来し、在来の鉄加工技術がその普及に役だったが、まもなく鎖国によって西欧の高炉への発達の道が閉ざされた。
奴隷制度時代の科学はアラビア人によって継承され、インド、中国の文化と接触してその遺産は豊かになった。ルネサンス期、レオナルド・ダ・ビンチ、コペルニクス、アグリコラらによって、自然の現象と法則の系統的な研究が始まり、近代的な自然科学の基礎が築かれた。奴隷制時代の科学はますます経験に訴えるようになり、ベーコンは経験と実験的研究こそが科学的認識の源泉であると唱えた。機械が散在的に使用されたマニュファクチュアは力学発展の土台となり、ガリレイによって動力学が基礎づけられた。ニュートンは力学をさらに広く体系化し、物体の一般的な運動法則を定式化した。マニュファクチュアの要求と、力学、天文学その他の科学部門で得られた成果が数学の発展を促し、代数学、対数の発見に次いで微積分学が基礎づけられ、18世紀には数学が科学のさまざまな部門で応用され始めた。
[山崎俊雄]
道具から機械への移行
産業革命は、資本主義のマニュファクチュア段階から、より高い段階としての産業資本主義の段階に移行する際に、技術や労働力だけでなく、社会そのものの構造の変化をも伴った変革である。産業革命は道具から機械への移行を妨げる封建的制約のないイギリスの木綿(もめん)生産から始まり、フランス、アメリカおよびドイツで19世紀1860年代に完了した。
産業革命の第一段階は、繊維生産における作業機の出現である。18世紀の中ごろ、新興の木綿工業において、ケイの発明した飛び杼(ひ)が普及するにつれて深刻な綿糸の不足がもたらされ、紡績部門におけるハーグリーブスのジェニー紡績機(1764ごろ)、アークライトの水力紡績機(1769)、クロンプトンのミュール紡績機が相次いで開発され、1825年、ロバーツの自動ミュールによって自動化された作業機が手労働にかわった。一方、立ち後れた織布部分との不均衡はカートライトの力織機の発明を促し、1820年代にはほぼ手織機を駆逐した。
産業革命の第二段階は、万能的原動機、すなわち最初の熱機関である蒸気機関の完成から始まる。その原動機は旧来の揚水機関と違って、回転運動による動力を供給するものでなければならなかった。すでに実用化されていたニューコメン機関がワットにより改良され、1784年に複動回転機関として完成された。この機関は工場や鉱山の動力としてばかりでなく、輸送作業機械、すなわち汽車や汽船に利用され、1830年代から交通機関の変革をもたらした。
産業革命の第三段階は、機械を製作するための作業機、すなわち工作機械の出現を促した。これまでもっとも広く使用されていた工作道具は弓旋盤であり、その作業には高度の熟練と緊張が必要であった。刃物がわずかに外れても加工の精度が損なわれる。そこでモーズレーHenry Maudslay(1771―1831)は、刃物を刃物台に取り付け、刃物台を自動的に送るという送り台付きねじ切り旋盤を1797年に製作した。送り台によって初めて刃物は人間の手から離れ、各種の工作機械を生み出す要因となった。こうして機械が機械を生産するようになったとき、初めて大工業は技術的に自立するようになった。
こうして原動機が同種の、あるいは異種のいくつかの機械を動かすという機械の協業が発生する。同種の機械の単純協業と違う異種の機械の協業は機械体系とよばれる。機械体系の出現は機械材料としての鉄の使用を増大させ、冶金技術の発達を促した。これまでの鉄冶金は木炭の燃料と水力の送風によって行われたが、コークスの燃料と蒸気機関の送風による冶金に移行した。さらに力織機の発達は、織物仕上げに要する染色、漂白部門の変革を促し、1820年代に、無機酸、アルカリ、漂白剤、媒染剤を多角的に生産する無機化学コンビナートがイギリスに出現した。
以上は産業革命における工業発展の技術的側面であるが、産業革命の背景に農業改革および交通業の発展があったことを見逃すことができない。農業改革によって農業が合理化され、農業人口が減少することによって産業革命がおこりえたのである。産業革命の開始とともに、原料、製品輸送量の増大、農業改革による農産物市場の拡大によって、道路交通の改良が促進された。道路工事の技術が改良され、有料道路がイギリス全土に建設され、四輪荷馬車や駅馬車が頻繁に往来した。水路交通は道路交通より早く発達し、とくに沿岸航行は産業革命前までの道路の発達を妨げるほどであった。運河の建設はフランスより1世紀も後れていたが、1760年代から急速に発達し、1790年代のいわゆる運河ブーム時代を出現させた。その起点となったのが、1761年に開通したワースリ運河(ブリッジウォーター運河)である。
産業革命は、イギリスをはじめ、それを経験した国で社会全般に大きな変化をもたらした。その最大の特徴は、産業に機械の使用が普及したことである。しかし、すべての産業に同時に均一に普及したわけではない。羊毛、麻、絹はそれぞれ緩慢な変化を示し、衣料生活の最終工程である裁縫機械の発明とその普及はずっと後のことである。石炭業では輸送機械や排水機械は発達したが、採炭機械ははるかに立ち後れた。機械が普及しなかった多くの産業部門では相変わらず労働者の熟練を必要とした。また機械の普及は、商品の標準化、価格の低下などに役だったが、反面、生産者の個性を製品に表現することを困難にし、芸術を大衆から奪い去るという一面があった。また産業革命とともに機械に対する反感から数多くの機械破壊運動も誘発した。ケイ、ハーグリーブス、アークライト、カートライトらの発明した機械もすべて破壊され、工場は焼き打ちにあった。この機械破壊運動の最高潮は1811~1816年のラッダイト運動である。これは、機械制大工業の発生によって失業に直面した手工業労働者の初期の反資本主義運動であった。機械が労働者を貧窮に陥れるのではなく、生産手段の所有者である資本家階級が労働者を窮乏に陥れることを労働者が知るまでには、時間と経験とを必要とした。
[山崎俊雄]
機械の自動体系への移行
1870年代以降、技術の進歩および技術学の発展に、ある飛躍的段階が訪れた。1873年の恐慌以来、資本主義は独占の段階に入り、1900年恐慌後、さらに資本の集中が大規模に行われた。恐慌は生産の社会的性格と取得との矛盾である。独占段階における資本主義の特徴は、生産力発展の不均等性が著しくなり、技術が質・量ともに発達する大きな可能性が生まれたことである。同時に資本主義が帝国主義の段階に移ったことによって国際間の結び付きが強まり、商品輸出のほかに資本輸出が盛んとなり、資本主義的最強国による世界市場の再分割が始まった。
技術学は大学にも制度化され、企業の独占化が技術の研究投資を可能にした。ベッセマー、ジーメンス、トーマスらによる製鋼技術の変革、パーキン、バイヤーによる合成染料を中心とする合成化学工業の発展、ジーメンスによる発電機の実用化、高圧交流による遠距離電力輸送の開始、発電機駆動用の蒸気タービン、水力タービンの発達は、しだいに電動機を基礎とする機械体系の発達を促した。
科学者と研究機関を自己の手中に収め、巨大な生産手段を所有する独占資本は、技術学の最新の成果を生産に導入しやすい立場にあった。資本が技術学の成果を利用するのは最大限に利潤を獲得するためである。また帝国主義のもとでは技術の発達は軍事技術の役割を増大させる。これまでに例のないほど大規模な軍備拡大競争が始まり、軍事技術の全部門が急速に発達した。銃砲の自動化、化学生産と結び付いた無煙火薬、内燃機関と無限軌道を利用した装甲戦車、ガソリン機関を利用した軍用航空機の大量生産、ディーゼル機関で推進し無線機器を装備する巨大な鋼製の軍艦、電動機を併用する潜水艦などがそれである。他方、独占企業の威力を象徴する鋼材利用の高層建築、海洋での軍事的発言力を増大させる大運河工事なども進み、技術進歩の本来の目標がゆがめられ、技術が死と破壊をもたらすために使われる。
日本に西欧の技術が初めて本格的に移植されたのは幕末における軍事工業においてである。佐賀藩をはじめ、各地に反射炉が建造され、造兵、造船などの洋式軍事工業が幕府や各雄藩によって経営された。たとえば、薩摩(さつま)藩の集成館、幕府の長崎製鉄所、横須賀(よこすか)製鉄所などである。また長崎には海軍伝習所が設けられ、日本最初の軍事技術学の教育機関となった。江戸には洋学所(のち蕃書調所(ばんしょしらべしょ))が設けられ、洋学の振興が図られた。これらの洋式軍事工業を主体とする近代技術の移植は、その後も日本技術の軍事的性格を決定している。1870年(明治3)工部省が設置され、明治維新政府の殖産興業政策が開始された。電信、鉄道、鉱山、冶金、造船、窯業などの技術が積極的に移植され、常備軍と警察網の結集に政策の重点が置かれた。殖産興業の中心はやがて工部省から内務省に移り、貿易に関係の深い繊維工業に模範工場が設けられた。しかし機械の本格的導入は紙幣整理に始まる官業払下げの後である。
殖産興業におけるお雇い外人教師の役割はきわめて大きい。工部省に世界に類例のない工部大学校が設けられ、蕃書調所に源をもつ東京大学は1877年に開設された。ここにも外人教師が招かれ、研究と教育に深い影響を与えた。東京大学は1886年に工部大学校と合併して帝国大学となり、まもなく日本人自身による科学の研究、教育制度が確立された。東京大学を中心とする近代科学の移植は1890年代から成果を現し、国際的な業績が続出した。各分野の学会もこの時期に結成され、国際交流もしだいに活発になった。
第一次世界大戦は、日本の諸産業、とくに電力、化学部門を発展させた。動力は汽力から電力に転換し、遠距離、超高圧電力輸送技術の発達は電動機を普及させ、中小工業を土台とする重化学大工業地帯を形成させた。また、大戦中、多数の研究機関が官公私とも増設され、なかでも民間の大研究所として研究に必要な条件を備えた理化学研究所とその出身者から多くの国際的業績が生み出された。たとえば、本多光太郎(こうたろう)の創立した東北帝国大学金属材料研究所ではKS鋼、MK鋼などの磁性材料が発明され、八木‐宇田空中線、岡部金治郎の磁電管のような独創的な研究が現れた。1929年(昭和4)、日本で最初の国際学会である万国工業会議が開かれ、この年、産業合理化政策が開始され、金融資本の支配のもとで各産業に新技術が採用された。やがて戦時体制の進展とともに、資本家や商工官僚にかわって軍官僚が先頭にたって合理化政策を進め、鉄鋼、軽金属、航空機、兵器など軍需生産につながる技術と技術学にある程度の進歩がみられた。しかし、日本の資本主義のもつ構造的矛盾は拡大され、科学の創意性は摘み取られ、その結果招いたものは、貴重な生命を犠牲とする特殊兵器の乱造であった。
[山崎俊雄]
戦後の技術革新
第二次世界大戦後、日本の技術の復興は傾斜生産方式に始まり、ドッジ・ライン、朝鮮戦争特需を経て軌道にのった。1952年(昭和27)の講和条約発効に始まる合理化はその後の技術の進歩に大きな影響を与えた。史上空前の技術の導入、設備の合理化から、機械の自動化、装置の連続化が重化学工業を進行させ、巨大電力網の再開発、動力の石炭から石油への転換はコンビナートを発展させた。さらにトランジスタの利用、電子顕微鏡・ビニロンの開発、東海道新幹線の建設、産業用ロボット、NC工作機械の普及など国際的な技術革新を生み出した。一方、独占企業本位の地域開発、高度経済成長政策は、日本で最初の石油化学コンビナートである四日市をはじめとして各地に公害をもたらし、産業廃棄物や有毒物による環境汚染は絶望的なまでに進行している。1970年代以降は原子力発電の事故による放射能汚染が心配されている。
第二次世界大戦後の技術革新は、戦争中の反ファシズム諸国における軍事技術学、とくにアメリカ、イギリスにおける電子工学、航空機工学、合成高分子化学、原子力工学などの諸科学の発展が民需に転用されたものである。しかし、戦後の独占企業は、この時期に匹敵する諸科学の成果を生み出しえていない。旧ソ連の人工衛星に対抗するアメリカのアポロ計画が、戦争中のオペレーションズ・リサーチ(OR)を起源とするシステム工学を生み出しただけである。このシステムとは、ギリシア語の「ともに置く」に由来し、日本語では体系・総体とよばれた概念に近い。全体を部分に分解することなく、つねに全体的連関を考慮しつつ最適化を図る設計手法とされる。システムの解析、制御、設計は、これも戦争中に開発されたロケットと電子計算機、とくに後者の革新がそれを可能にし、コンピュータ・ネットワークによる情報工学とともに未来技術の夢が託されている。
日本の技術水準の向上とともに、先進技術輸出国は門戸を閉ざし、資本輸出を条件とする傾向が増えている。1960年代から国際競争の激化とともに日本でもようやく研究投資が本格化し、産学協同の合いことばで基礎研究、開発研究が進められたが、科学を基礎とする自主研究は立ち後れており、技術の自立化にはほど遠い。国内環境を無視した外国技術の導入、軍事技術の無計画な民需転換は自然破壊につながり、技術の自主性と安全性を損なうことは技術史の教えるところである。
技術は人類の誕生以来、人間労働の肉体的制約からの解放をもたらす方向へ発達してきた。道具から機械へ、機械体系から自動機械体系(オートメーション)へと発達するのがその動向である。最近のコンピュータと自動管理システムの発達がそうした動向を保証する技術的基礎である。科学と技術の発達は高い生産力をもたらすことによって、人間の生産的労働を最小限とすることを可能にする。その結果、すべての人々は大きな自由時間を得て、科学や芸術の創造、スポーツを楽しむことができる。そこでは労働は人間に課せられた苦しみではなく、創造に満ちた楽しみとなる。しかし、このような展望は、現代世界の階級的収奪、民族的抑圧の克服を前提とするものである。この克服なくしては、オートメーションも原子力もいっそう大きな災禍を人類にもたらさないとの保証はないのである。
[山崎俊雄]
『戸坂潤著『技術の哲学』(1933・時潮社)』▽『三枝博音著『技術の哲学』(1951・岩波書店)』▽『マンフォード著、生田勉訳『技術と文明』全3巻(1953~1954・鎌倉書房)』▽『ペリキンド他著、野中昌夫訳『人間と技術の歴史』(1960・東京図書)』▽『ズボルイキン他著、山崎俊雄他訳『技術の歴史』(1966・東京図書)』▽『中村静治編『現代技術論』(1973・有斐閣)』▽『リリー著、鎮目恭夫他訳『人類と機械の歴史』(1968・岩波書店)』▽『フォーブス著、田中実訳『技術の歴史』(1956・岩波書店)』▽『シンガー他著、高木純一他訳・編『技術の歴史』全14巻(1978~1982・筑摩書房)』
改訂新版 世界大百科事典 「技術」の意味・わかりやすい解説
技術 (ぎじゅつ)
technology
engineering
技術をどう定義するかをめぐって,かつて日本では有名な論争が展開された。この技術論論争は,〈技術は労働手段の体系である〉とする労働手段体系説と,〈技術は人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意識的適用である〉とする意識的適用説との間で争われた。前者の概念規定を提唱したのは,1930年代の唯物論研究会で,相川春喜,戸坂潤,岡邦雄らがその代表的論客であった。後者の創始者は物理学者の武谷三男であり,太平洋戦争敗戦直後に,この学説が広く知られるようになった。どちらの学説もそれぞれ,技術と呼ばれる現象のもつ基本的特徴をとらえており,それぞれ有効な定義である。また両者は互いに矛盾することもない。分析視角に応じて使い分ければよいのである。にもかかわらず日本で,概念規定をめぐる技術論論争が起こったのは,どちらの学説を支持する人々も,技術の概念規定を,包括的なものでなければならないと考えたことによる。実際には,技術と呼ばれる現象のもつ基本的特徴を余すところなく,一節の文章で記述することは不可能である。技術論論争が当事者以外の関心をほとんど喚起することなく,忘れ去られようとしているのも無理はない。
日常語としての用法をみるかぎり,技術とは最も広義には,人間がある目標をもった行為をなすとき,行為を目標の実現に結びつけるために用いるわざ,を意味する。たとえば論争の技術といった用法がある。しかしより限定的には,もっぱら生産活動に関連づけて技術という言葉が用いられる。人間にとって有用ななんらかの生産物を作り出すことを目標とする行為において動員される道具立て,およびそれらの使用法についての知識の体系,またはその個々の構成要素が,技術と呼びならわされているのである。これ以上分析的に,技術の概念規定を行うことは,特殊な目的をもつ場合を除いて,必要ではない。
技術と科学
過去には技術は,もっぱら経験的知識の蓄積のうえに発達してきた。それを担ってきたのは職人であり,その習得方法は,徒弟制度のもとでの実務を通しての修練であった。職人と学者とは明確に区別されていた。学者的伝統においては主たる対象は〈書物〉であったのだが,職人的伝統では〈自然〉が仕事の対象とされた。また学問を担った人々が社会的地位の高い知識人であったのに対し,技術の担い手は下層の職人であって,両者の間の交流はあまりなかった。これを一言でいえば,科学と技術とが別々の社会活動として併存していた,ということである。
技術というものは有用な生産物を作り出すための手段であるが,そうした手段は必ずしも出来合いのものばかりではなく,ある現実的目標を達成しようとする行為の途上で,新たに生み出さねばならないものである。この場合,直接的に役立たずとも,技術そのものを有用な生産物とみなしうる。それを実現するための人間活動が,技術開発にほかならない。科学研究と技術開発とは,かつてはほとんど結びついていなかったが,今日では密接に結びついている。科学研究の目標は,自然界についての新しい知識を学術論文という形で発表することであり,技術開発の目標は,有用な生産物を作り出すことである。しかし実際には,科学研究が論文発表と同時に,実用的成果の獲得を目標として追求することはなんら差支えないし,また技術者が技術開発の途上で得られた新知識を論文として発表することには,種々の制約がつきまとうけれども,原則的には可能である。このように今日では,科学と技術との間に大規模な相互浸透が起きている。そして,一つの研究開発プロジェクトのなかで,科学と技術が同時に追求されることも珍しくなくなっている。
たとえば制御核融合のプロジェクトについてみると,その究極目標は,商業的に他の電力生産方式と競合できる核融合発電炉を完成することであり,その意味でこれは技術開発プロジェクトである。しかしそれは同時に,プラズマ物理学をはじめとする多くの科学分野の専門家の参加を必要とし,また彼らはその研究成果を学術論文という形で発表することができる。つまりそれは同時に科学研究プロジェクトでもある。またX線天文学を例にとると,この科学分野は宇宙のX線源の物理的性質の解明を目標としており,それは生産活動と直接のつながりはない。しかし人工飛翔体(ロケット,人工衛星)をはじめ,さまざまの宇宙技術を道具立てとして存分に活用することによってはじめて,X線天文学が可能となる。そしてそうした宇宙技術は出来合いのものではなく,科学研究に効果的に役立つために,同時並行的に開発されるのである。以上二つのプロジェクトのうち核融合の場合は,技術が目的で科学が手段という性格が強く,X線天文学の場合は逆に,科学が目的で技術が手段であるとみることができる。だがいずれも,一つのプロジェクトのなかで科学と技術とが連携している好例である。
このように現代では,科学と技術との関係はきわめて密接となり,科学技術という言葉が日常語として使われていることにも象徴されるように,両者はしばしば混同されている。それは現実の趨勢(すうせい)を反映したものであるから,とくに不都合をきたさないかぎり非難するには当たらないが,いくつかの問題点をはらんでいることも否定できない。その一つは,科学と技術とのかかわり合いの変化を歴史的にふりかえることが不可能になる,ということである。科学技術はすぐれて20世紀の産物であり,近代的な工学の成立以前は,科学と技術との関係は疎遠であった。両者を一つのプロジェクトのなかで同時並行的に進める,というスタイルが興隆するのは,さらにのちの第2次大戦期からである。そして将来にわたって科学と技術との間に密接な関係が保たれる必然性はない。また,いきなり科学と技術とを一体のものとしてとらえるよりも,両者をひとまず分析的に区別してその絡みあいの構造を解析したほうが,現代技術についてより深い理解に到達できることもまた明らかである。
技術と工学
科学と技術との中間に位置するのが工学である。工学とは学問分野化した技術のことである。公共的な言葉(数学および厳密に定義された専門用語の体系)でもって定式化できる理論体系を確立し,かつそれを習得させるための教育制度を樹立することによって,技術は工学となる。ただし技術がすべて工学に吸収されるわけではない。技術とテクノロジーtechnology,工学とエンジニアリングengineeringをそれぞれ対応づけようとする流儀があるが,これはあまり適切ではない。日本語の工学という言葉には,学問分野化した技術という含蓄が顕著にあらわれているが,エンジニアリングとテクノロジーとの間には,それほど明確な境界線は引けない。テクノロジーといえば〈学〉としての性格が強調されるとは必ずしもいえない。その意味では日本語のほうが,現代技術を分析的にとらえるうえで適している。たとえば日本語で技術者と工学者とははっきり意味が異なるが,英語ではエンジニアengineerが双方の意味を兼ねて使われている。工学のほかに技術学という言葉があり,工学と技術との中間項として用いられることが多いが,しかしこれは技術論の世界でのみ通用してきた言葉であり,実社会で使われることはまれである。また分析的にも,工学と技術の区別ほど有効性をもつとは考えられない。したがって一般には,技術学という言葉は不要である。
学問分野化されることによって,技術は科学と類似した多くの特徴を帯びてくる。それはまず技術の自律autonomyを助長する。かつては技術は有用な生産物を作るための手段であったが,近代工学の成立以後は,自然界の法則性の解明がそれ自体として目標となる傾向があらわれ,工学者に対する評価基準が,有用な製品を開発することから,新しい知見を論文の形で発表することへと移行する。ここで業績評価の担い手となるのは,工学者のコミュニティ(同業者仲間)であって,その新技術に基づく製品の売手や買手ではない。しかし技術の自律にもおのずと限度がある。大局的にみれば技術は科学とは異なり,生産活動のなかに組み込まれており,自足的なシステムを形づくることはできない。
技術と社会
技術は現実的目標を達成するための道具立てである。一方,人間社会を支配する価値観は,きわめて多様であり,したがってそれぞれの社会ごとに,目標となることがらは異なってくる。そして目標が異なれば,その達成のために援用される(または新規に開発される)道具立ての組合せも,それぞれの目標に適した,互いに異なったものとなる。つまり技術は社会によって方向づけられる。技術には時代と地域を超越した必然的な発展経路は存在しない。たしかに技術は,同一の用途を満たすための製品が,時代を経るにつれて,ますます高性能となり,また量的にも増大する,という意味で累積的な性格をもつ。そうした累積的発展が効果的に行われるようになったのは,近代工学の成立以後と考えられる。専門家集団の成立と,その内部における技術情報の公共的な言葉での伝達システム--それを可能にするのが,近代科学と共通する数量的・実証的方法である--の確立が,累積的発展をもたらしたのである。一足早く科学という人間活動の領域で確立された,累積的発展を可能とするシステムが,工学を媒介として,技術へと波及したわけである。しかし技術が累積的発展の性格をもつことは必ずしも,その発展が単線的に進められることを意味しない。複数の路線があって,それぞれが累積的発展のパターンを示すことがあってもよいし,また一つの社会で路線の切替えが行われてもかまわない。
〈もう一つの技術alternative technology〉(略称AT)の思想は,そのような見地に基づいて登場してきた。その提唱者によれば既成慣行の技術は,生態系を無視して大量生産を指向するものであり,それによって環境破壊や資源浪費がもたらされる。そうした現代技術に基づく工業文明は永続性をもたない。また現代技術は,自然と人間との関係を敵対的なものとするだけでなく,人間相互の社会的関係にもひずみをもたらしている。それは利潤と戦争によって動機づけられた,中央集権的な社会体制を維持するために好適な技術ではあるが,人間の主体性とそれに基づく自由な協同関係の形成を保障する分権的社会にはそぐわない。また現代技術の開発と運用それ自体が,少数のエリート専門家によって独占的に進められており,一般人はそれに異議をさしはさむことはできず,いやおうなしに技術革新に適応させられる。その意味で既成慣行の技術は,反民主的な社会体制を支える主要な動因であるばかりでなく,それ自体としても反民主的である。
〈もう一つの技術〉の提唱者たちは,現代技術の特徴を上述のようにとらえ,それとは異なる選択肢として,生態学的に健全で,人間どうしの敵対的関係を生み出さず,農村型の分権的社会の維持に貢献する新しい等身大の技術の可能性を説く。それはすべての人間が開発と運用に参加することのできる技術である。具体的には,風力発電やソーラーハウスなどの代替エネルギー技術が,その代表例として挙げられることが多い。たしかにそれらは,現代文明を象徴する巨大な原子力発電所と好対照をなす。〈もう一つの技術〉の思想を,エネルギー問題に即して具体化した一つの試みとして,イギリスのロビンスAmory B.Lovinsの〈ソフト・エネルギー・パスsoft energy path〉が挙げられる。一方,第三世界の開発戦略に関しては,先進工業国から先進技術の粋をこらした巨大な生産設備を導入して一挙に近代化をはかるよりも,それぞれの地域の要求に見合った中小規模の技術を広めていくことを重視すべきであるという見解を,〈もう一つの技術〉の提唱者たちはとった。これは〈適正技術appropriate technology〉と呼ばれる。
〈もう一つの技術〉の思想的意義は,技術発展にも複数の路線があり,また技術の選択と社会の選択とが不可分の関係にあることを,単純明快な図式によって示したことにある。エコロジカルな分権的社会を理想化し,既成慣行の工業文明との二者択一を迫るという,社会運動に特有の行き方をとったため,技術と社会のかかわりについての緻密(ちみつ)な分析は妨げられたが,以前からマルクス主義者の間で支持を得てきた,技術進歩と社会進歩とを同盟関係にあるとみなす思想--そこでは,技術進歩が資本主義という経済体制を揺るがす動因となり,また反対に資本主義のもとでは技術進歩が著しくゆがめられる,と考えられた--を否定したことの意義は大きい。〈もう一つの技術〉の思想が,それ自体としていかに粗雑であるにせよ,技術の階級性についての過去のあらゆる議論につきまとっていた技術進歩性善説を乗り越え,技術進歩へのより幅広い理解を可能にしたことは特筆される。
どんな種類の社会問題も,技術的手段によって解決することができ,技術進歩によって引き起こされた社会問題もまた,究極的には技術進歩によって克服される,という見解がある。これを技術万能主義という。だがこれは技術が人間の社会的行為に組み込まれた形でしか存在しないものであることを看過した思想である。社会のすべての成員の間で目標に関する合意が得られていなければ,共通の目標を達成するための技術的手段を動員することはできない。もちろん社会のなかに利害対立がたとえ存在しなくても,社会問題を解決する技術的手段が見つかる保障はまったくない。以上の議論は,技術進歩のもたらした社会問題にも当てはまる。しかし,技術の生み出した問題は技術によって解決されるという思想には,上記の困難に加えて,技術開発という行為の本質に基づく困難がある。有用な生産物を作り出すことが技術開発の目標である。しかし何が有用であるかの判断は近視眼的に下されるのが常である。当座の目標を達成できればよいからである。それゆえ技術開発は刹那的に進められる。それによって明白かつ顕著な災害が発生した場合にのみ,それを解決するための技術的手段が開発され運用されるが,それはつねに後追いにとどまり,また当座の問題が目だたなくなればその任務を終える。しかるに現代技術は時とともに,自然および社会にますます大きなインパクトを与えており,後追いの対策だけでその悪影響を断つことはできない。そこで登場したのが,テクノロジー・アセスメント(略称TA)の考え方である。
テクノロジー・アセスメントの考え方を提唱したのは,アメリカの政治家エミリオ・ダダリオである。この考え方は,技術進歩に社会的制御を加えるための現実的提案として意義がある。しかしその背景にあるのは,技術開発の成果を社会的摩擦をなるべく引き起こさずに社会に定着させるために,技術開発のネガティブな副作用を事前に察知しその打開策を講じよう,という思想である。それは技術開発の推進者の立場からの,その社会的制御のための提案なのである。
技術は社会発展の主要な動因であるといわれる。発展ということが必ずしもポジティブな価値をもつとは限らないと断り書をつければ,この見解は正しい。とりわけ現代では,経済的・軍事的繁栄が技術によって支えられている。国際関係において技術は,経済的・政治的・軍事的なパワーとして機能する。そうした現実をふまえて,〈技術立国〉(テクノ・ナショナリズム)の思想が19世紀以降,技術に関する支配的なイデオロギーの一つとなり,今日に至っている。先進国からの〈技術移転〉を促進し先進国との間の〈技術格差〉を縮めようと後発国が努めるのは,現代技術がパワーとして絶大な影響力をふるっていることの反映である。あらゆる種類のパワーについて成り立つことは,それが無制限に是認さるべきではなく,国際的に規制されねばならぬということである。他国に脅威を与えるという点では,軍事力と技術力との間に本質的な差異はない。日本では明治以来,技術立国の思想が自明の真理として理解されているが,それが弱肉強食のイデオロギーであることは留意されねばならぬ。
技術は元来,軍事ときわめて深いかかわりをもっている。人類文明が拡張指向をとりつづけるかぎり,その手段としての技術が,強さを不断に追求しつづけることは避けがたく,そのことがまた技術と軍事とを結びつけるきずなとなっている。とくに第2次大戦期の科学動員(正しくは科学技術動員)を契機として,多くの先進工業国で,国家の主導性のもとで技術と軍事とが緊密に結びつけられるシステムが作られ,現在に至っている。そこでは科学と技術とを合わせた研究開発費の過半が国家によって支出され,国家負担分の過半が軍事目的に使われることが常識となっている。現在,世界の研究開発費総額の20%が軍事目的に投入されていると推測されているが,この数字は,軍事をつかさどる政府機関が支出する研究開発費のみをあらわしており,軍需産業が兵器開発のために自前で投入する資金(それは兵器の売却によって回収する)が含まれていない。それを加算すれば,研究開発費に占める軍需の比率は大幅に増加する。このように現代技術は,他の人間活動と比較にならないほど深く戦争準備と結びついている。そうした国家主導・軍事中心という現代技術の基本的性格を,最もよく体現しているのは,アメリカの技術である。それと比較すると日本の技術は,民間依存・経済中心という基本的性格を有する。これは世界の主要先進国のうち,日本だけがもつ特異な性格である。それは戦後日本に形成されたきわめて特殊な歴史的環境の所産である。日米安全保障条約のもとで日本の軍事力が,経済力と比較にならないほど弱体でありつづけたため,軍事技術への動機づけが働かなかったのである。しかしこうした歴史的環境はきわめて不安定である。これからの日本技術の構造が欧米型へと接近していく可能性は大きい。そのとき商品化に強いといわれる日本技術が,その性格をどのように変えていくかは,興味深い問題である。日本近代技術史を国際的視野から見直せば,技術発展がいかに社会によって深く方向づけられるかを考えるための恰好の素材が,数多く見つかるはずである。なお技術の歴史については,年表〈技術の歴史〉と各個別技術関連項目を参照されたい。
執筆者:吉岡 斉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「技術」の意味・わかりやすい解説
技術
ぎじゅつ
technique
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「技術」の読み・字形・画数・意味
【技術】ぎじゆつ
 は、皆生生の
は、皆生生の 、王官の一守なり。~
、王官の一守なり。~ 興りてより倉
興りてより倉
 り。今其の技
り。今其の技
 昧(あんまい)なり。故に其の書を論じ、以て方技を序して四種と爲す。
昧(あんまい)なり。故に其の書を論じ、以て方技を序して四種と爲す。字通「技」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の技術の言及
【工学】より
…工学は,古くは軍事技術military engineeringだけを意味した。しかし,18世紀以来,軍事以外の技術civil engineering(現在は土木工学の意味)が発展し,それ以来,工学とは,エネルギーや資源の利用を通じて便宜を得る技術一般を意味するようになった。本項では,後者の意味での近代工学の形成とその教育体制の整備に関して歴史的概観を示す。
[近代工学教育の形成と展開]
フランスの土木工学校École des Ponts et Chausées(1747設立)やフライベルク鉱山学校Bergakademie Freiberg(1765設立)など,18世紀中葉以降,ヨーロッパ各地では各種の技術学校が設立されはじめた。…
【工学】より
…工学は,古くは軍事技術military engineeringだけを意味した。しかし,18世紀以来,軍事以外の技術civil engineering(現在は土木工学の意味)が発展し,それ以来,工学とは,エネルギーや資源の利用を通じて便宜を得る技術一般を意味するようになった。本項では,後者の意味での近代工学の形成とその教育体制の整備に関して歴史的概観を示す。
[近代工学教育の形成と展開]
フランスの土木工学校École des Ponts et Chausées(1747設立)やフライベルク鉱山学校Bergakademie Freiberg(1765設立)など,18世紀中葉以降,ヨーロッパ各地では各種の技術学校が設立されはじめた。…
【技術移転】より
…ある技術が,国境をこえ,あるいは企業から別の企業に,移転または伝播する現象をさす。技術伝播,テクノロジー・トランスファーともいう。…
【技術史】より
…技術は他の分野と違ってその進歩が明確で蓄積的なので,技術の歴史に対する関心は早くからあったように思われるが,必ずしもそうではない。他の分野と同じく最初の技術史は事物の起源を問う神話的なものであった。…
【工芸】より
…宋代の百科事典,《太平御覧(たいへいぎよらん)》の工芸の部によると,それは射(弓を射ること),御(馬を御すこと),書,数(算数),画,巧,そして囲碁などの勝負を争う各種遊戯,これらにかかわる広い範囲での技能のことであった。ただし,このうち抽象的な言語である巧は,今日いうところの工芸技術をも含む,工作に関する技能を意味していた。《周礼(しゆらい)》によれば,巧とは,知者が創造した物(器物)をたくみに述べ,守る技能であった。…
※「技術」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...