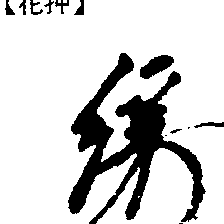精選版 日本国語大辞典 「花押」の意味・読み・例文・類語
か‐おうクヮアフ【花押・華押】
- 〘 名詞 〙 平安中期以降にあらわれた署名。自己の名乗りを楷書体で書いた場合を自署、草書体で書いた場合を草名(そうみょう・そうな)といい、草名がさらに判読できない程度に図案化されると花押と呼ばれる。その意匠によって公家様、武家様、二合体、一字体、別用体などと分類されることもある。判(はん)、書判(かきはん)とも呼ばれる。押字(おうじ)。花押は本来自己の名乗りであるから、自署と花押を共に書くことは故実に反するが、鎌倉時代以降、「頼朝(花押)」のように並べて書くことも広く行なわれるようになった。
 花押 伏見天皇@徳川家康@藤原俊成@源頼朝
花押 伏見天皇@徳川家康@藤原俊成@源頼朝- [初出の実例]「書判 カキハン 本名花押。又近世下加二一文字形一者謂二之割符様一」(出典:書言字考節用集(1717)八)
花押の語誌
中国では、文字を変体に崩すことを「押」といい、崩した形から「花」ともいっており、その字を、古く「花字」とも「押字」とも称したが、後に両方の表現を合わせて「花押」というようになった。
改訂新版 世界大百科事典 「花押」の意味・わかりやすい解説
花押 (かおう)
記号もしくは符号風の略式の自署(サイン)で,判(はん),書判(かきはん),判形(はんぎよう),押字(おうじ)などともいった。花押の起源は自署の草書体にある。これを草名(そうみよう)と呼び,草名の筆順,形状がとうてい普通の文字とはみなしえないまでに特殊形様化したものを花押という。
起源と種類
花押の発生は中国にあって,その時期は遅くも唐代中期と見られている。日本の花押も中国にならって用い始めたと考えられ,その時期は遺存史料の限りでは10世紀前半期ころのようである(933年の坂上経行の花押が初見)。
花押には(1)自署,草名から起こった草名体(例えば三蹟の一人藤原行成)のほかに,(2)諱(いみな)(実名)の偏,旁(つくり),冠などを組み合わせて作る二合(にごう)体(例えば源頼親,源頼朝),(3)諱の一字または他の特定の文字を形様化した一字体(例えば平忠盛の〈忠〉,足利義満の〈義〉,足利義政の〈慈〉,豊臣秀吉の〈悉〉),(4)動物(鳥がよく用いられる),天象等を図形化した別用体(例えば三好政康の水鳥,伊達政宗のセキレイ,大陽義冲の太陽)などがある。平安時代には草名体,二合体が多く一字体も間々用いられたが,鎌倉時代以降はほとんど二合体と一字体が用いられ,別用体はごく一部の武士,僧侶,文人の間に用いられたにとどまる。
花押の発展と武家社会
花押はもと自署の簡略化より起こり,略式の自署または自署の代用と考えられたから,書礼の上で自署より軽礼とされ,また花押を署記する場合は実名を書かないのが原則であった。しかし11世紀以後,貴族以外の身分層の間で実名と花押を連記するものが現れ,ことに中世に入って文書を他人に代筆させる風がとくに武士の間に広まり一般化すると,本文の代筆者(右筆)が差出者の実名まで書いて,本来の差出者は実名の下に花押だけを署記する風が広まった。こうして武家社会では,花押は差出者本人の意思の証憑,文書に証拠力を付与する源泉とみなされ,差出者の人格のシンボルとすら考えられたのである。武家の花押の第2の特徴は,同族・主従などの集団において,成員の花押に類似性が強いことである。例えば鎌倉幕府の執権北条氏の花押が,おおよそ時政型(泰時,経時,重時,政村,時村等)と義時型(時宗,貞時,熙時,高時等)の2類型に分けられる。室町時代には足利将軍家をはじめとして広く守護,奉公衆,奉行人その他諸国の武士の間に,足利尊氏の花押を原型とするいわゆる足利様(あしかがよう)の花押(例えば足利義満,義教,義政,高師直,斯波義将,伊勢貞親,飯尾清藤)が用いられた。江戸時代(とくに前期)には徳川将軍家以下一般武士の間にまで,天地の二線を特徴とする徳川家康の花押にあやかったいわゆる明朝体(みんちようたい)の花押(例えば徳川秀忠,家光,綱吉,吉宗,本多正信,伊奈忠次,前田利長,毛利秀元,大石良雄)が用いられており,これらはその好例である。
公家・禅僧の花押
一方,公家の花押では鎌倉時代の中期以後,筆画を多く複雑にしてことさらに筆順をわかりにくくする傾向が現れ,南北朝・室町時代に下るとともに,この傾向はいっそう強まってゆく(例えば洞院実泰,三条実躬,中山定親,庭田重親,一条冬良,近衛政家,三条西実隆,広橋兼秀,万里小路惟房)。また宋・元から来日した禅僧(蘭渓道隆,無学祖元等)や日本から宋・元に渡って帰国した禅僧(円爾弁円,大休正念,竺仙梵僊等)が,文字の筆画を極端に減省し,あるいは直線,円,点等を組み合わせた符号に近い中国(宋・元代)の花押類型をもたらしたのにはじまって,南北朝時代以降の対元・明通交の発展とともに,このような花押類型が禅僧の間に確固たる位置を占めるとともに,一部の俗界にも影響を及ぼした。後年武士の間で隆盛をきわめる明朝体も,この類型の一つと見ることができる。
武家・庶民の花押
次に武家および庶民層では南北朝以降足利様が普及する中で,ほぼ16世紀ころから上記の公家花押の趨勢とは逆に,筆画の少ない筆順のわかりやすい花押,つまりは書きやすい花押が多くなる。また南北朝ころから一部禅僧の間に始まった印章を文書に押捺する風がやはり16世紀ころから今川,北条ら東国の大名に及び,花押に代えて印章を用いる傾向が強まると,この傾向が逆に花押に影響を与えて(1)花押を版刻にして墨を塗って押したり,花押を双鉤式(籠字(かごじ)式)に刻して,これを押した上で墨を塡めるなどの花押型や,(2)花押を印文のごとくみなして印章に取り入れた花押印などが用いられるようになる。版刻の花押型は中国の元代に使用されたといい,日本でも早く鎌倉時代後期に使用例が報告されているが,戦国時代になると奥州の岩城親隆,古河公方足利高基以下の使用が知られている。籠字式の花押型も天正年間に常陸の楯岡義久がこれを用いたほか,江戸時代に入って大いに流行したようである。次に花押印は,1486年(文明18)に現存最古の使用例があるほか,16世紀末豊臣の武将浅野忠吉がこれを用いている。また1406年(応永13)の春日社造営料木の過所の差出書〈唐院〉の下におされた花押を初見として,81年以降の文書に見られる伊勢山田の行政機関〈三方(さんぼう)〉の花押,永禄初年からの文書に見られる伊勢大湊の合議機関〈老若〉の花押(これを公界(くがい)の印判と呼んでいた)など,花押型を用いた役職の花押が現れたのも,本来個人の自署から起こって個人に帰属する性質をもった花押が,個人を離れた新現象であって,花押と印章の接近,混同のもたらした現象の一つと見ることができる。
印章と花押
以上のような書きやすい花押の普及発展,印章の普及とこれにともなって現れた花押と印章の接近,混同の現象などは,おそらく花押(そして印章)の使用が武士から庶民層に広がり,花押の使用人口が増大したことと相互的因果関連をもつものであろう。しかしこのような現象は他面,本来花押のもっていた使用者個人の独自性を減殺するものであって,その結果,花押の模倣,盗用が容易になるのは免れがたいところである。一つの花押を長年月使用する場合に,花押の形が多少とも変化することは古くから見られる現象であり,改名その他の理由で花押を意識的に変えた事例も鎌倉時代に少なからずあったが,戦国・織豊時代の武士の間で,意識的な花押の変更が広く行われ,また一部の大名に,複数の花押を用途によって使い分ける印章類似の使用法が行われたのは,主として花押の模倣,盗用を予防するためであった。この時代の著しい花押変更の例に,足利義昭の6種,織田信長の8種,吉川広家の17種などがある。
戦国・織豊期の花押
戦国時代の後期から織豊時代にかけて,武士の花押には,下向湾曲型の花押(例えば六角定頼,足利義晴,浅井久政,朝倉義景)が一部に流行し,花押造形の上でも,〈長氏〉の2字を組み合わせて裏返し横にした北条早雲(伊勢長氏),〈長〉の字を右に倒した浅井長政等の花押のごとく文字の転倒や裏返しが行われて,足利様からの脱却傾向が強まった。また〈三〉と〈石〉を重ねた石田三成の花押,〈虎〉の上部に〈介〉を付けた加藤清正(虎介)の初期の花押等に明らかなように,実名を基にした伝統的な花押造形法を離れて苗字や通称を自由に用いたり,織田信長が〈麟〉字を基にして花押を作り,竹中重治が〈千年おゝとり(?)〉の5字を造形化して,平和の世に出現すると伝えられる麒麟(きりん)や鳳凰に彼らの天下統一,平和将来の願いを託した事例が示すように,実名とは離れた願望,信念の文字を形様化する(その嚆矢(こうし)は将軍足利義政の〈慈〉字の花押あたりにさかのぼるが)など,種々の新様式,新傾向が現れる。
江戸時代の花押
江戸時代に入ると,明朝体(当時,徳川判と称せられた)が武士の間に隆盛を極めて,公家や僧侶の一部にも影響を与えたが,江戸後期に入ると,地線を引かずに,運筆の終りの右部分をまるく張り出す形が流行して,幕末期にはこれが上層武士の花押の基本型となった。また陰陽道の人や密教系の僧侶の中から,陰陽五行説などによる花押作りの専門家が現れて,人々のもとめに応じたのも江戸時代の花押の特徴である。さらに,江戸時代に見られた花押の用法の変化は,印章使用の普及と隆盛とは裏腹に,花押使用の場と頻度が著しく減退したことを意味する。武士は公文書でも少なからず印章を用い,私信では花押も印章も用いない例が多くなったし,庶民の間にも印章が普及して,百姓町人が公式の届書等に印章をおすことや,その印影をあらかじめ届けておくことが規定されたのである。
近代の花押
1873年維新政府は,人民相互の諸証書には爪印,花押等を用いず実印を用いるべきこと,実印なき証書は裁判上の証拠とならぬ旨の太政官布告を発して,ここに花押使用の長い歴史はほぼ終わった。のち,上記の太政官布告は廃止されて,花押を署記した証書も裁判上の証拠力をある程度認められることになったが,実生活の上で花押を用いる風は復活しなかった。ただ維新政府の大臣参議,各省の卿大輔等はなお時として公文書に花押を署記し,内閣制度発足後は大臣副署や閣議書類のサイン用に大臣が花押を用いるようになり,閣議書類については今日もその慣例が守られている。また戦前陸軍の上層部に花押使用の風があり,戦後の自衛隊にも一部花押が用いられているようである。
歴史研究と花押
終りに,花押は歴史研究の資料として重要な価値があって,文書の差出者の人名確定や筆跡鑑定に利用されるほか,あらかじめ特定人物の花押の変化を調べて,いわばその人の花押歴を明らかにしておいて,これと特定の文書記録に見えるその人の花押を照合することによって,その史料の作成年代が推定できるなど,史料研究における花押の価値は大きい。そしてこのような研究を可能にするには,詳細正確な花押集が必要であって,《読史備要》(1933,東大史料編纂所)の花押印章一覧や,《書の日本史》第9巻(1976,平凡社)の花押総覧はかかるもとめに応じた一つの試みであるが,目下より大規模な《花押かがみ》が史料編纂所から編纂出版されつつある。
執筆者:佐藤 進一
中国
中国における花押の起源は唐代からであろうといわれる。公私の文書実物の伝存の少ない中国において,あまり多くのことが知られていないが,宋代の官文書で連名者の肩書と姓までを書記が記し,名を各本人が花押で記しているものがある。清代の契約文書では,代筆人が文書本文と併せて署名人の姓名まですべて記したうえで,各本人が自己の名の下に,あたかも判をつくように,花押を記すのが常である。その様式は自己の名とは関係なく二,三の好みの文字を模様のように組み合わせた複雑なものが多い。字の書けない者は単に十の字を記して認めの印とする。これも極端に簡略化された一種の花押であるということができよう。
→印章 →署名
執筆者:滋賀 秀三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「花押」の意味・わかりやすい解説
花押
かおう
自署のかわりに書く記号。印判と区別して書判(かきはん)ともいう。印章と同様に文書に証拠力を与えるもので、個人の表徴として偽作を防ぐため、その作成には種々のくふうが凝らされた。
花押は中国の唐代から現れるが、わが国では平安時代の10世紀のころからしだいに用いられるようになった。初め自署は楷書(かいしょ)で書くのが例であったが、行書から草書に変わり、しだいに実名の二字の区別がつかない図案風のものとなった。これを草名(そうみょう)といい、平安時代に多くみられるが、後世までとくに書状に用いられることが多かった。花押の類型は、作り方からみると草名体のほかに、実名の二字の一部を組み合わせた二合体(にごうたい)、名の一字だけをとった一字体、文字と関係のない図形を用いた別用体、中国の明(みん)代に流行した様式で、天地の2本の横線の間に書く明朝体があり、以上の5類型は江戸時代の有職家(ゆうそくか)伊勢貞丈(いせさだたけ)の分類として有名である。しかしこのほかにも、前記の類型の複合型もあり、苗字(みょうじ)・実名・通称の組合せによるものなど、その様相は複雑である。一字体のなかには変種が多く、実名と関係のない文字を選んで、理想や願望を表したりするものが室町時代以降戦国織豊(しょくほう)期に多くなり、文字を倒置したり裏返しに書くものも現れた。禅僧の花押も一種独特の風味のあるもので、文字よりは符号に近い抽象的な表現になっている。また身分の低い者や無筆の者が用いる略押も花押の一種で、〇や×などの簡略な符号であった。同一人でも草名体と他の形式の花押をもつ例があり、義満(よしみつ)以降の足利(あしかが)将軍のように武家様と公家(くげ)様の花押の2種を使用する例もみられる。また一生の間には花押にも書風の変遷があるが、意識的に、改名・出家・政治的地位の変化などを転機として花押を変えることがあり、偽造を防ぐために頻繁に改作したり、用途によって数種の花押を使い分けることもあった。
花押は時代によってもその様相は変遷する。平安時代は草名体・二合体が主流であり、中世になると二合体・一字体がそれにかわり、さらに前述の新様式が現れ、江戸時代には明朝体がもっとも流行した。花押は自署のかわりとして発生したものであったが、平安末期より実名の下に花押が書かれるようになり、のちには実名と花押を連記する風が生じた。実名と花押の関係が薄れると印章と変わるところがなくなり、さらに花押を彫って捺(お)すようになると、花押も印章化し、花押にかわって印章を捺すことが一般化した。なお、今日でも閣僚などが公式文書に花押を使用することがある。
[皆川完一]

足利尊氏花押

足利持氏花押

足利義稙花押

足利義教花押

足利義尚花押

足利義政花押

足利義満花押

足利義持花押

石田三成花押

今川義元花押

上杉謙信花押

上杉憲実花押

太田道灌花押

織田信長花押

北畠親房花押

楠木正成花押

高師泰花押

後醍醐天皇花押

平清盛花押

武田信玄花押

伊達政宗花押

徳川家康花押

徳川光圀花押

豊臣秀吉花押

日蓮花押

新田義貞花押

藤原頼長花押

北条氏政花押

北条時宗花押

北条泰時花押

細川頼之花押

源頼朝花押

夢窓疎石花押

毛利元就花押
百科事典マイペディア 「花押」の意味・わかりやすい解説
花押【かおう】
→関連項目印章|血判|御内書|朱印状|姓名判断|天正大判|御教書
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「花押」の意味・わかりやすい解説
花押
かおう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「花押」の解説
花押
かおう
押字(おうじ)・書判(かきはん)・判形(はんぎょう)・花書(かしょ)とも。文書の差出人が,本人独自の象徴として書き加える一種のサイン。文書に本人の名前を書くことを自署(じしょ)といい,やがてこれをくずして草書で書くようになり(草名(そうみょう)),さらに字として読みとれないほど記号化されて花押がうまれた。平安末期には定着したと考えられる。自署の代用として発達したため,名前と花押がともに書かれることはないのが原則だったが,やがて名前と花押を連記する者が現れて広く行われた。名前とまったく関係ない字や形を記号化したものもある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「花押」の解説
花押
かおう
書判 (かきはん) ともいう。初め文書に署名することから,だんだんに略式化されたもので,日本での初見は9世紀中ごろ。(1)草名体…署名の草書体から変化したもの,(2)二合体…実名の偏や旁 (つくり) などを合成,(3)一字体…ある一字の形様化,(4)別用体…文字の符号化あるいは象形化したもの,(5)明朝体…天地両線があるのが特徴,に分類される。江戸時代には花押を木判で押すものまでできてくる。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の花押の言及
【印章】より
…武将と禅宗,武将印と禅林印,その影響の上に印判状が出現すると考えるべきであろう。
[花押と印章]
印に代わって繁用されたのは花押(かおう)である。花押は古代の署名に源を発し平安中期から発達したサインの一種で,印章に関係はあるが,書札礼の上からは印章より優位にある。…
【裏判】より
…文書の紙背(裏)に書かれた花押。中世,相手に敬意を示す意味で請文(うけぶみ)の署名の裏に花押を書く習慣があった。…
【署名】より
…法令中の署名なる語を自署の意味に解することは原則的に正しいが,署名であるためには必ず自署であることを要しかつ自署だけでよい,とはいいきれない。 署名は,署名者にその最終的意思を確認させる(署名の主観的理由)とともに,署名者の同一性を明示するため(客観的理由)のものといえるが,これらの必要性は,代署,ゴム印の使用等,自署以外の方法で署名者の名称を記載(名称の記載一般を〈記名〉という)して拇印(または指印)や花押(かおう)(書判)をおすことによっても満たすことができる。それに,日本の一般社会生活では,重要な行為については,自署のうえなお印章を押捺すること(署名押印)をもって正式な形式とし,さらに,押印があれば名称の記載方法を問わない(記名押印,記名捺印)傾向がある。…
【爪印】より
…近世日本の爪印は天皇裁可や吟味物(火付,人殺し,盗賊など重科のもの)には常用されていて,宗門改めには〈15歳以下60歳以上には爪印をさせた〉と文献に見える。1873年(明治6)の太政官布告は,爪印を花押(かおう)とともに裁判上の証拠として無効とし,実印だけの効力を認めた。爪印は墨を爪にぬって紙面に印することよりも,紙面に爪痕をのこす方法がもっぱらとられたため,消えやすく後世にはのこらない。…
【手紙】より
…距離・時間を要し面談の不自由な場合は,両者の確認に差出し(発信人),宛名(受取人)を記し,日時の経過(年月日付)も勘案されることになり,本文以外にこの3項が要求される。とくに謀書(ぼうしよ)(偽書),謀判(ぼうはん)のありうる鎌倉時代以降には,発信人の真なることの証明も必要とされ,その人独自の模倣しがたい自署(花押(かおう))が創出される。私信は内容の秘密性により必然的に右筆(ゆうひつ)には任せられず,自筆にならざるをえない。…
【判鑑】より
…照合用に登録された花押,また,それの多人数分を集録した簿冊。文書に署記された花押(判形(はんぎよう))が本人のものかどうかを確かめるために,あらかじめ花押を登録させて,随時の照合に備えることは,文書が遠隔地間で授受される場合や,文書の真偽が当事者の利害に重大な関係をもつ公文書,契約文書において,とくに必要であったと考えられるが,そのような花押の登録制度がいつから始まったかどうか明らかでない。…
【右筆】より
…それらの人々は京下りの公事奉行である太田氏,三善氏などの一族または末裔が多く,北条一門や外様の有力御家人からなる引付衆に指揮される存在で,引付衆よりは一段下位の身分であり,幕府吏僚としては下層に位置付けられた。関東下知状などの幕府の発給文書は彼ら右筆が清書し,差出者の名判を記す署名部分の花押(かおう)のみ執権,連署,探題などの重役が書いた。したがって文書の筆跡は右筆のそれであって,必ずしも発給者を表すものではない。…
【略押】より
…花押(かおう)の代りに用いられた簡略な記号,符号。略花押ともいい,古文書学上の名辞。…
※「花押」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...