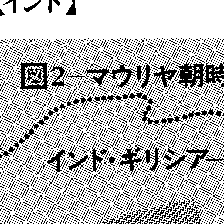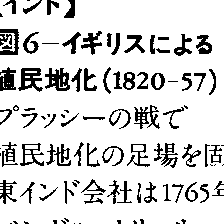目次 地理 地形,地質 気候 農業 鉱業 工業 住民,文化 言語 宗教 政治,法律 ヒンドゥーの制度 ムスリムの制度 イギリス植民地時代の制度 社会 コミュニケーション 歴史 時代区分 インダス文明 アーリヤ人の来住 古代帝国の成立 デカンと西北インド 古典文化の爛熟 諸王国の分立 南インドの歴史と文化 イスラム教徒のインド支配 ムガル帝国 イギリスの進出 1857年の大反乱 民族運動の展開 分離独立へ 西はトバカカール山脈,北はカラコルム,ヒマラヤ両山脈,東はアラカン山脈によって画され,南はインド洋に大きく逆三角形状に突出する一大半島部は,アジア大陸の一部ではあるが,亜大陸と呼ぶにふさわしい規模と相対的独立性とをもち,インド亜大陸と呼ばれる。そこは南アジアとも呼ばれ,インド (バーラト),パキスタン ・イスラム共和国,バングラデシュ 人民共和国,ネパール 王国,ブータン ,スリランカ 民主社会主義共和国およびインド洋上のモルジブ 共和国の7ヵ国からなる(現代の各国についてはそれぞれの項を参照)。その総面積は449万km2 で,旧ソ連邦を除くヨーロッパ大陸の494万km2 にほぼ匹敵する。人口は約12億5000万人(1996)で,世界人口の約21%に達し,中国と並ぶ人口の集住地帯をなす。このうちインド(バーラト)だけで,亜大陸面積の73%,人口の76%を占めている。
地理 地形,地質 インド亜大陸は,大陸部と島嶼部とに大別される。大陸部の地形は,(1)デカン高原,(2)北方の第三紀褶曲山脈帯,(3)両者の間のインダス・ガンガー(ガンジス)流域平野,(4)インド半島両岸の海岸平野,の四つに分かれる。
デカン高原の北限は,アラバリ山脈,デリー市南方,ラジマハール丘陵を結ぶ線にあたる。デカン高原の地質は,先カンブリア時代の片麻岩・花コウ岩層を基盤とし,北西部では白亜紀以降の断層運動の際に噴出した玄武岩台地(デカン・トラップ)をのせている。この玄武岩の風化土がレグール(熱帯黒色土壌 )と呼ばれる肥沃な黒色土である。デカン・トラップより南に向かうにつれて,土壌はラテライト 化した赤色土が多くなっていく。デカン高原は,両端を西および東の両ガーツ山脈が走り,周縁部が高くなった楯状地をなす。標高は前者が1000~1500m,後者が500~600mであって,全体として西高東低の傾動性地塊をなしている。このため高原上を流れる河川は,西ガーツ山脈に水源をもちベンガル湾に向けて東流する。
第三紀褶曲山脈帯は,アルプス・ヒマラヤ造山帯に属する。ここは中生代まではテティス海であった。主として第三紀にはいってから,ゴンドワナ大陸 から分離し北へと漂移したデカン高原の安定陸塊に対して,アジア大陸からの横圧力が働き,それによる造山運動に伴う褶曲作用がその成因である。ヒマラヤ山脈はその主脈で,南から順にシワリク丘陵,小ヒマラヤ山脈(標高2000~3000m),大ヒマラヤ山脈(6000m以上)と移行していく。
インダス・ガンガー流域平野 は,アラビア海のインダス河口デルタから,パンジャーブ,ヒンドゥスターン両平原を経て,ベンガル湾のガンガー・ブラフマプトラ河口デルタへと至る弧状の大沖積平野である。ここは,デカン高原と第三紀褶曲山脈帯とにはさまれた大地向斜帯(褶曲の凹部)にあたり,前記の三大河川水系からの莫大な土砂堆積によって形成された。堆積層は厚く,場所による変動はあるが,深さ2000m以上にも達することがある。平原上はきわめて低平で,ガンガー河口から約1500kmへだたったデリーの標高は216mにすぎない。
海岸平野はインド半島西岸のマラバル,同東岸のコロマンデル両海岸に沿って延びる。ともに狭長で海岸線も単調である。東岸部では,デカン高原上から流下する諸河川が河口部に大きなデルタを形成する。
一方,島嶼部はセイロン島,ミャンマーのアラカン山脈から大スンダ列島へと連なる第三紀褶曲山脈列上に位置するアンダマン,ニコバル両諸島,およびサンゴ礁からなるラカディーブ,モルジブ両諸島を主とする。このうちセイロン島は,第三紀の形成になる北西部の平たん地帯を除いて,デカン高原南端部と同じ性格の安定陸塊を基盤としている。
気候 インド亜大陸は典型的なモンスーン 気候帯に属している。そこでは気温の変化よりも,卓越風向の転換による雨季と乾季の変化が季節を生み出す。北インドを例にとれば,3~5月:プレモンスーン期(その末期が最も暑い),6~9月:南西モンスーン期(雨季),10~11月:ポストモンスーン期,12~2月:北東モンスーン期(乾季)の4期に分かれる。このうち最も重要なのは南西モンスーンである。インド洋上で多湿となった赤道西風が,6月ごろヒマラヤ山脈周辺を北上するいわゆるモンスーン・トラフmonsoon trough(北熱帯低圧部NITCにあたる)に引き寄せられて北東へと方向を転じる。赤道西風が西ガーツ山脈にぶつかって西海岸に大量の雨を降らせて後,ベンガル湾にはいる。そこで同湾を北上してきた気塊と合体して,アッサムからヒマラヤ山脈沿いにヒンドゥスターン平原 を北西上するのが,南西モンスーンである。したがって西ガーツ山脈の山陰にあたるため比較的乾燥したデカン高原西部地方を除くと,南西モンスーンが早く到来する所ほど,雨季が長く降水量も大となる。南西モンスーンの開始日と後退日は,マラバル海岸南端部では5月末と11月下旬,カルカッタ(現,コルカタ)周辺では6月上旬と10月上旬,デリー周辺では6月下旬と9月中旬となる。年降水量も,それぞれ3000mm以上,約1600mm,約700mmとなる。ベンガル湾頭から北西上するとき,南西モンスーンは,デカン高原の西高東低の非対称性地形に助けられて,内陸部に広く雨をもたらす。しかしインダス川の中・下流域になると,南西モンスーンの雨も極端に少なくなり,タール砂漠が広がる。その西方は西アジアにつづく乾燥地帯に属し,そこでは冬に少ない雨が地中海方面からくる低気圧(西方攪乱)によりもたらされる。
北東モンスーンは,ヒマラヤ山脈が障壁となるため,南西モンスーンに比べて弱い。ベンガル湾を通過した北東モンスーンが吹く南インドの南東部,セイロン島北東部を除くと,この時期のインド亜大陸はほぼ全域的に乾季となる。
農業 インド亜大陸の最も重要な産業は農業である。亜大陸の農業は,北インドでは,ほぼ南西モンスーン期を作期とするカリフkharifと10~4月の乾季を作期とするラビrabiに大別される。ラビ作の主要作物は小麦,大麦などの麦類と菜種などの油料作物を主とし,残りの重要作物はカリフ作に属している。米,トウモロコシ,モロコシ,トウジンビエ,シコクビエなどの雑穀はカリフ作の主穀作物である。そのためカリフ作の豊凶に亜大陸の農業は依存している。しかし南西モンスーンは,その開始日,降水間隔(間隔が長期になるといわゆるモンスーン・ブレークmonsoon breakとなる),降水量などが年により変動し,不安定である。このためインド亜大陸の農業は,〈モンスーンの賭〉と呼ばれる。
作物の分布をみれば,米は年降水量1200mm以上線以東の夏雨型地帯に多く,東・西海岸平野とベンガル湾頭から北西に三角形状に延びている。同じく夏雨型でも降水量の少ないデカン高原はトウジンビエ(タール砂漠に近い乾燥地帯),モロコシ(黒色土地帯に対応し,北部では綿花地帯と重合している),シコクビエ(南端の赤色土地帯)の生産地である。これらの北西方にあたる冬雨がかったガンガー川上流域からアフガニスタン国境部にかけて,小麦の生産地帯が広がっている。以上の主穀作地帯では,ヒヨコマメや緑豆類などの豆類の作付けも多く,雑穀作の場合には同じ畑に混播・間作形式で栽培される。
インド亜大陸諸国とりわけインドでは,独立以後の国家建設の目標を工業化と並んで〈農業国でありながら,増大する人口に追いつけない食料生産〉という矛盾の打開においてきた。そのため土地改革と並んで,灌漑化,優良品種・化学肥料の供給などの諸政策を講じてきた。とりわけ大規模な多目的ダムによる河川灌漑また井戸灌漑の拡充が重視されてきた。しかし全耕地面積に占める灌漑面積の割合は,インドでは29%(1978)にすぎない。亜大陸の伝統的な灌漑形式は,インダス・ガンガー流域平原の河川灌漑に対してデカン高原の溜池灌漑であった。ヒマラヤ山系から流下する河川は,南西モンスーンの雨だけでなく融雪水も水源としうるので,流量の季節差は南インドの諸河川より小さい。そのため旧英領時代,独立以後を通じて,パンジャーブ,シンド,ウッタル・プラデーシュ西部では大規模な灌漑用水路の建設が進められてきた。現在そこは世界有数の灌漑農業地帯となっている。1960年代末からの〈緑の革命Green Revolution〉が最も成功したのはこの一帯であり,カリフ作の米とラビ作の小麦の相互乗入れによる米麦二毛作の拡大がみられる。
主穀と綿花以外の重要農作物としてサトウキビがある。サトウキビの作期は12ヵ月以上と長く,灌漑なしには栽培できない。インド亜大陸は世界最大のサトウキビ産地であるが,その多くは村で粗糖に加工されて消費される。そのほかアッサムやスリランカ山地部の茶,西ガーツ山脈南部のコーヒー,コショウなどのプランテーション農業 がある。
鉱業 インド亜大陸諸国はいずれも非産油発展途上国にあたり,中東諸国からの大幅な入超に苦しんでいる。石油・天然ガスの資源探査が進められた結果,インドではアッサムと西海岸のキャンベイ湾周辺で油田が,またパキスタンでは北西辺境地方東部で油田,シンド地方で天然ガス田が発見・開発されている。しかし国産エネルギーの中心は石炭で,インド北東部のダモーダル炭田は世界有数の埋蔵量をもつ。農村での燃料としては乾燥牛糞が広く使用され,乾燥地帯では唯一の燃料源となっている。その他の鉱産資源では,オリッサ州北東部とゴアの鉄鉱石がある。
工業 17世紀にはインド亜大陸は,世界における綿・絹工業の中心であった。その伝統は今も各種の農村工業・家内工業に残っている。第2次大戦前の主要な近代工業は,19世紀中期にさかのぼるカルカッタのジュート工業,ボンベイ(現,ムンバイー)やアフマダーバード の綿工業,および1911年創立のジャムシェドプル の製鉄業などにすぎなかった。第2次大戦中には非鉄金属,機械,化学肥料,薬品などの諸工業が各地に成立した。これを引き継いで独立以後,各国は数次の五ヵ年計画により工業化を推進した。インドを例にとれば,1950-51年を100とした1977-78年の生産指数は,銑鉄563,電力1739,窒素肥料2万2367,自動車508,綿糸211,綿布193となっている。その結果インドやパキスタンでは,工業は国民総生産の15%(1979)を占めるにいたったが,その比率はなお農業の半分以下である。各国とも工業の大都市への地域的集中ははげしく,インドではボンベイをもつマハーラーシュトラ,カルカッタをもつ西ベンガル,アフマダーバードをもつグジャラート,マドラス(現,チェンナイ)をもつタミル・ナードゥの上位4州で工業生産額の55%(1976)を占めている。パキスタンでも最大都市カラチ周辺に集中している。応地 利明
住民,文化 インド亜大陸は,その自然環境のみならず,そこに住む諸民族の社会・文化が織りなす複雑さの点でも,他に類例をみないほどの驚くべき多様な世界を呈示している。
この多様性は,この亜大陸の独特な地理的位置と,この地を舞台として繰り広げられた長い歴史とにまずその理由を求めることができよう。有史以前から,数多くの民族移動の波が相次いでこの地に打ち寄せてきた。類型は必ずしも明確に区分できないが,人種的には,ベッドイド,ニグロイド,モンゴロイド,コーカソイドの大きな人種型がこの地に併存し,また混交している。歴史的にみると,まず有史以前の先住民としてニグロイド型とベッドイド型の人種が存在した。後者は,インド半島全域に広がっていたものと推察されている。その上に,西北方から侵入してきたコーカソイド型の人種がいくつもの波となって重なり広がっていた。インダス文明(前2300-前1800)を形成した人びとの中に多数のこの型の人種が含まれている。また,インド・アーリヤ族 (前1500-前1200ころに侵入)はこの型の別の種族であった。ベッドイド型の人種は,今日ではスリランカ南部,インド南部の森林地帯の少数部族,さらにインド中部の丘陵地帯の多くの部族にその特質がみられる。ニグロイド型は,典型的な形質ではインド亜大陸内部には見いだされず,わずかにアンダマン諸島民 の中に存在している。一方,インド北部の大部分の地域とパキスタンにかけてはコーカソイド型が多数で,南インドの大部分の住民も基本的にこの型に属するとされている。最後に,モンゴロイド型はヒマラヤ地域とこれに隣接するインド東北部に分布が集中していて,インド半島部にはその痕跡はない。
地理的な特徴をみると,インド亜大陸は峻険な山脈によって区切られ,広大な海によって囲まれて,他とは隔絶したひとつの巨大な閉鎖空間を形づくっている。すなわち,半島部の東西にはベンガル湾とアラビア海,南にはインド洋をひかえ,内陸部の北には雪峰の連なるヒマラヤ山脈が何重もの大きな壁を形成し,またその東西に走る支脈が,亜大陸を外から包みこむ形に広がっている。陸路を通ってこの地に入るには,西北あるいは東北のわずかなルートしか存在しなかった。これらの経路から侵入してきた各民族は,ほとんどの場合,彼らの本来の根拠地との密な連絡をもはやもつことなく,亜大陸の中に定住してゆく。各民族は,その人種的・文化的な性格を保ちながらも,他民族と混住し,相互に影響を及ぼしつつ共存していった。わずかの例外(たとえば,東南アジアへの移住)を除いては,この地からの他地域への進出はなかったといってよい。かくして,この地域はひとつの文化圏として独自の文化の形成と発展をはぐくんでゆくこととなった。
現在のインド亜大陸の文化の多様性を最もよく表しているのは,この地域で使用されている言語の数の驚くべき多さである。たとえばインド(バーラト)の1961年度の国勢調査では,人々が自分の母語としてあげる言語の数は,実に1500を超える。話者人口が100万を超える言語だけでも33を数える。これらの言語は,言語学の系統分類の上では,インド・アーリヤ系,ドラビダ系,アウストロアジア系,チベット・ビルマ系の諸言語に分かれる。これらの現在の使用地域の概要は,最も話者人口の多いインド・アーリヤ系諸言語は,北インド全域,中部インド,パキスタン,バングラデシュ,スリランカで用いられ,次いでドラビダ系は南インドの全域で,アウストロアジア系は中部インド丘陵地帯の諸部族に,またチベット・ビルマ系諸語はヒマラヤ地域とインドの東北部山地諸部族でそれぞれ用いられている。ちなみに,先述の人種区分と言語集団との間には必ずしも一致した関係は見いだされない。その理由は,歴史の長い歩みの中で諸民族間の相互影響,混交が起こってきたからである。たとえば,南インドにおいては,ほぼ全域にわたってドラビダ系諸語が用いられ,これは形質遺伝の特性や民族のいかんにかかわらない。また,ベッドイド型人種に属するとされる中部インドのゴンド族の一部などはインド・アーリヤ系の言語を用いている。インド(バーラト)では,インド・アーリヤ語系のヒンディー語への国語化政策が進められており,現在はヒンディー語と英語が公用語とされている。ただし,1971年度国勢調査ではヒンディー語を母語とする人口は全体の約25%である。各地域の言語と公用語とのバイリンガル(二重言語併用)現象は当面避けられないであろう。
宗教面にもこの地域の多様性は容易に見てとれる。インドを例にとると,ヒンドゥー教,シク教,ジャイナ教,仏教があり,またそのほかに各部族のそれぞれの宗教形式がある。中世以降に流入,伝播したものは,イスラムとキリスト教がおもなものである。これらの中でヒンドゥー教徒は,全体の約83%と圧倒的多数を占める。ヒンドゥー教の信仰とこれを基盤とする生活慣習は,インド亜大陸の住民の社会と文化に統一的な特徴を与えているということができる。他の諸宗教の人口分布が地域的にほぼ限定されたまとまりをもつのに対し,ヒンドゥー教はインドの全域にわたる広がりをもっている。ヒンドゥー教とは,侵入民族であるアーリヤ人が定着して社会の上層階級として統治を進める過程で,彼らの宗教形式と先住民族のそれとが融合されてしだいに形成されたもので,人びとの生活様式の全般にわたって規制をする点に特色がある。この意味で,ヒンドゥー教は言語,人種などを異にする多様な社会集団の文化にひとつの特色ある統一性を付与している。
ヒンドゥー教と不可分に結びつくのが社会制度としてのカースト 制である。独自の伝統文化を保持する,部族諸社会を除いて,亜大陸のほとんどすべての社会は,程度の差はあれ,カースト制の原理のもとにあるといってよい。その典型がヒンドゥー教社会である。ヒンドゥー教徒は生れによってヒンドゥーとなるのであり,社会的には多数のカースト集団のいずれかに帰属する。カースト制においては,人は生れによってカースト小集団(ジャーティ)に所属し,この地位は一生変わらない。ジャーティ集団は厳格な内婚制をとり,その成員の他集団との婚姻関係を認めない閉鎖性をもつ。経済的には,各ジャーティ集団には世襲の定まったひとつの専門職業があり,一定の地域社会の中で他の諸ジャーティと経済的に相互依存の関係に立つ。一方,宗教的には,〈浄〉〈不浄〉の観念に基づく上下の序列関係が諸ジャーティの間に設けられ,共同飲食の禁忌などの相互接触の規制が厳しく立てられる。社会・経済・宗教の三つのカテゴリー区分に基づくカースト制の枠組みは,すべてのヒンドゥー農村地域に共通している。さらにこの社会構造はヒンドゥー教社会に隣接する他の社会にも広く影響を及ぼしている。たとえば,パキスタンなどのイスラム村落社会でも基本的にはカースト的な社会構造が見いだされる。この意味で,ヒンドゥー教ならびにカースト制は,インド亜大陸に〈インド世界〉と呼ばれうる統一性を与えるものということができる。
伝統的な〈インド世界〉の人々の思考枠組みは,自己の属するカースト集団とその集合体としての地域社会と文化の中に限られてきた。しかし,近代教育の普及や近代的職業の形成などによって,一方では,カースト制の変化の兆しも現れてきている。とりわけ,都市を中心とする新しい知識層(官僚,産業界・学界の指導層など)とこれまでになかった中産階級の形成は,地域的なカースト制の枠を越えたつながりをつくりだし,また,都市労働者の間にはカースト制に基づく行動様式に変化が起こりつつある。徐々にではあるが,伝統的なインド社会のあり方は形を変えてゆきつつある。井狩 弥介
言語 インド亜大陸は,過去数千年の間に見られた大規模な民族移動の主要な経路の一つの上に位置するため,古くから多数の人種・民族の波を迎えてきた。その結果,インド亜大陸で話される言語は,そこに到来した人種それぞれのもたらしたもの,およびそれら相互の接触から生じた言語が併存・干渉し,地理的にも社会的にも複雑な分布を示している。すなわち,
(1)アフリカから来て,アンダマン諸島,マレー半島方面に進んだネグリト系種族は,大集団としてインド亜大陸に定住することはなかったが,次に来た人種の言語に影響を与えている。
(2)次いで,地中海地方の種族の一支派でパレスティナ地方からやって来たとされる種族の言語にネグリト族の言語の影響が及び,アウストロアジア系の言語(アウストロアジア語族 )となった。古くは広い地域に分布したらしいが,今日では中部と東部のインド,バングラデシュなどの山岳・丘陵地帯で,数万人から1万人ぐらいの少数部族民により話される言語となっている(サンタール語,カーシ語など)。インド亜大陸の総人口の1.3%を占める。
(3)3番目には,地中海地域から前3500年ごろにドラビダ族がインダス川流域に到達し,高度の都市文明を築いた。彼らはやがて,次に来たアーリヤ族に押されて南インドに下り,彼らの言語が分化してタミル語,テルグ語などになったが,ブラーフーイー語 のように,もとのバルーチスターン に残存している場合もある。この系統の言語(ドラビダ語族 )には千万人単位の話者人口をもつものが四つあり,全人口の21%を占める。
(4)4番目の種族は,チベット・ビルマ方面から入って来た人たちで,彼らのチベット・ビルマ語派 系の言語はヒマラヤ山系と東北インド,バングラデシュの山岳・丘陵地帯に分布し,数十万人から1万人弱の少数部族民により話されている(ネワール語,マニプリー語など)。全人口の0.85%。
(5)5番目にインドに入って来たのは,ウラル山脈南方に源をもつ種族で,このうち前1500年ころにインドに定着した支派はインド・アーリヤ族といわれる。先住の諸種族を南部および周辺部に押し出し,南インドを除くインド亜大陸のほぼ全域に居住する。この種族の言語はインド・アーリヤ語といわれ,歴史的にベーダ語,サンスクリット語,諸プラークリット語,諸アパブランシャ語などの段階を経てしだいに分化し,10~13世紀ころには今日の北インドの主要な民族語を生み出すこととなった。ヒンディー語,ベンガル語,マラーティー語などがそれで,それぞれ数百万人から1億人の話者人口をもち,全人口の73%を占める(インド語派 )。
インド亜大陸にはこのように,5系統の種族が次々と移動して来て,あるいは通過し,多くはそこに定住して,相互に影響を及ぼし合った。このことに関する例を,先住諸種族の言語が,後から来たインド・アーリヤ族の言語に与えた影響という観点に限定してあげれば,ガンガー川の意の〈ガンガー〉という語は,アウストロアジア語系諸族が〈川,水路〉の意に用いた普通名詞であったし,インド・アーリヤ系の言語に早くから認められた反舌音はドラビダ系言語の特徴を受け入れたものであり,屈折語 であったインド・アーリヤ語系の言語が今日では膠着語 のような側面をもつようになったのは,内的変化のほかにドラビダ諸語の影響もあったと考えられる。
上述のような歴史の過程から生じた今日のインドの言語事情が,かなり複雑であろうことは十分に予測される。北インドの俚謡に,〈4里(コース)ごとに水が変わり,8里行けば言葉が変わる〉というのがあり,イギリス統治下のインドの言語・方言を調査したグリアソンG.A.Griersonによれば,インドには179の言語と544の方言があるとされるのは,言語分布の複雑さを裏づけるものといえなくはない。しかしながら,先の俚謡は,同じ言語(方言)を話す人々の間でも,表現の微妙かつ部分的な差異に着目したときにしばしばなされる誇張であり,グリアソンのあげる179の言語のうち実に116は話者人口の比率が0.85%にすぎないシナ・チベット語族 に属している。こういう心情的な誇張や数字の絶対化を除外して考えるなら,話者人口が多く文化的に重要な民族語は,インド(バーラト)ではヒンディー語 ,ベンガル語 ,オリヤー語,アッサミー語,カシミーリー語,パンジャービー語 ,マラーティー語,グジャラーティー語 ,シンディー語(以上インド・アーリヤ語族),タミル語 ,テルグ語 ,カンナダ語,マラヤーラム語(以上ドラビダ語族)の13,パキスタン・イスラム共和国ではパンジャービー語,ラフンダー語,シンディー語,バルーチー語の4,バングラデシュ人民共和国ではベンガル語のみ,ネパール王国ではネパール語とネワール語の2,スリランカ民主社会主義共和国ではシンハラ語とタミル語の2である。とはいえ,少数者の言語の一つとされるサンタール語は300万人の母語であり,いまはインドにほとんどいないネグリト族の言語もインドの言語の形成に少なからぬ貢献をしていること,および数万人という単位の話者をもつにすぎない言語に固有の民謡・民話などが伝えられていることに思いをいたすなら,話者人口が相対的に少なく,現時点で強力な文化的勢力をもたない言語といえども,ないがしろにすることはできない。
上掲の言語を表記する文字は,インド,バングラデシュ,ネパール,スリランカにおいてはブラーフミー文字 系統であり,パキスタンではアラム文字系統のアラビア文字を一部改めたものが使われている。少数部族民の言語は,上記の有力な文字のどれかを採る場合と,ローマ字を採る場合がある。
これらの民族語とは別に,公用語,文化語などが民族語と一部で重なりながら存在する。サンスクリット は,バラモン文化の有力な媒体の一つとして今なおインド亜大陸の多くの地域で重んじられている。ペルシア語,アラビア語はこの地域のイスラム文化を担う人々には欠かせない存在であり,ヒンディー語のもとになった方言にペルシア語,アラビア語の語彙が取り入れられてできたウルドゥー語は,パキスタンの公用語であるほかインドの文化語でもある。英語は旧統治国イギリスの言語であるが,インド亜大陸の地域間の交流の媒体として今なおエリート層に重んじられ,亜大陸の国政・教育・文化などの面で機能しているので,単なる外国語とすることはできない。
インド亜大陸内での人と物の往来が密になるにつれて,言語間の接触の機会が増えてくる。その結果,少数民族の構成員は周囲の有力な言語を併用し,有力な言語の使用者も出身地を離れて生活するときは行先の言語を併用する。出身地を異にする大集団を抱えこむ大・中の都市では,そこでの共通語のほかに各集団の民族語も日常生活で使われているので,デリーの市内でベンガル語,タミル語などの文字で書いた看板を見ることがある。これは,都市においても出身地域(民族)を同じくする人々が自分たちの集落を形成することがあるためで,民族語の観点からはモザイク状の分布を示すことになる。
インド亜大陸の言語の中には,社会的な方言の差異をもつものがある。すなわち同じ村の中でも,北インドのヒンディー語圏では〈不可触民〉とその上の諸ジャーティの方言との間に音韻体系のような基本的な点で著しい違いがあり,南インドのカンナダ語圏では,バラモンとその下の諸ジャーティの方言の間に大きな差異がある。これらは,同じ地域にあっても社会が身分・階層により区切られ,また各集団が独自の生活習慣と価値基準を保持するべく志向しているためである。坂田 貞二
宗教 1921年にインダス川の流域において本格的な発掘が開始され,前2300-前1800年を中心に,現在のパキスタン領内のモヘンジョ・ダロ とハラッパーを二大中心地として,高度に発達した都市文明が栄えていたことが明らかとなった。その出土品の中には当時の宗教や慣習を暗示しているものがあり,インダス文明の担い手は母神崇拝,樹神崇拝,動物崇拝,性器崇拝などを行い,ヨーガの修行や沐浴を実践していた可能性があるが,このインドの最初期の宗教に関しては推測の域を出ない。
この文明の終末とほぼ同じころ,アーリヤ人 がヒンドゥークシュ山脈 を越えて西北インドに進入し,この文明の遺跡に近いパンジャーブ地方に定着して,前1200年を中心に《リグ・ベーダ 》を編纂した。その後,前500年ころまでに主要なベーダ聖典が編纂され,いわゆるバラモン教の根本聖典が成立した。《リグ・ベーダ》の宗教は多神教であり,主として太陽神や火神などの自然神や司法神バルナ(水天)や武勇神インドラ(帝釈天)のような擬人化された神々が崇拝されている。しかし神殿や神像を用いず,祭主の家の中か草の生えている平地などに祭壇を設け,祭火を燃やし,神を勧請し,祭菓,動物(多くは牡ヤギ)の犠牲,神酒ソーマを供えて,神を喜ばせ,その報酬として勝利,子孫・家畜の増加,長寿を得ようと願った。祭式の規定はしだいに複雑化し,それとともに祭式万能主義的風潮を生み,それをつかさどるバラモン階級は最高位を占めるにいたった。しかしやがてそのバラモン中心の制度が崩壊していくが,それから起こる不安感から,厭世的気運が醸成され,苦行主義が広まった。かつて祭式に与えられた位置が苦行に与えられ,神秘的・瞑想的知識が重視され,祭式行為も内面化され,ついにベーダ聖典の終結部を成すウパニシャッド として結実し,宇宙の根本原理であるブラフマンと個人存在の本体であるアートマンとは同一であるとする梵我一如の思想を生み出した。またウパニシャッドにおいては輪廻と業の思想が成立し,前7,前6世紀には急速に人々の間に広まった。
このようなバラモン教の動向と社会変動を背景に,前6,前5世紀ころ多くの反バラモン教的自由思想家たちが輩出したが,その中でも共にクシャトリヤ階級出身のマハービーラとゴータマ・ブッダ がそれぞれジャイナ教と仏教を創始し,勢力を拡大した。ジャイナ教はベーダを否定する無神論的多元論に立脚し,四姓制度を認めず,不殺生を強調し,苦行主義をとり,業を滅して解脱を求めるべきことを説いた。ジャイナ教はインド国内にとどまったが,今日に至るまでその勢力を保持し続けている。一方,仏教は形而上学的諸問題を,益なきこととしてその論争に参加せず,論争を超越し,人間の真に生きるべき道である法dharmaを追求した。いっさいは苦であると認識し,その根源を妄執(タンハーtaṇhā,渇愛)に見いだし,その妄執を断じて涅槃を実現するようにすすめた。四姓制度を否認し,苦行主義を捨てて八正道すなわち中道の実践を説いた。仏教はアショーカ王の保護のもとに,国外にも伝播し,多くの異なった解釈を生み,たくさんの部派に分かれ,ジャイナ教と異なって複雑多様な展開の跡を示すが,しだいに保守的傾向を強めていった。他方,前1世紀ころから,仏陀を信仰の中心に置いて,仏徳をたたえ,菩薩行を説く新しい運動が主として在家の信者の間から起こり,彼らは旧来の仏教を小乗と貶称し,自ら大乗と称し,膨大な大乗経典を編纂し,民衆の支持を得てその勢力は内外に及び,遠く日本にまで達した。しかし7世紀以降,相対的にその勢力は低下し,ヒンドゥー教の勢力が伸張する中で,8世紀になると密教が成立し,しだいにインドの土着的要素やタントリズムとしてのヒンドゥー教と融合していくうちに独自性を失い,ついにイスラム教徒のために,1203年,仏教の一大中心地であったビクラマシラー寺を破壊され,仏教修行者の拠点を失って,インド社会の表面から消滅した。
ヒンドゥー教は,広義には,バラモン教をも含むが,狭義には,およそ前3,前2世紀に,まだ仏教が有力であったころから,土着の信仰・習俗などの諸要素をバラモン教の中に包摂し,新しい宗教として徐々に成立してきた複雑な複合体をいう。その崇拝の対象は多種多様であり,強大な勢力をもつ神々から山川草木に至るまでが対象となる。ベーダ聖典において有力であった神々は退き,ブラフマー(梵天),ビシュヌ,シバの三大神格を中心に展開したが,ブラフマーは中世以降多くの信者を得ることができなかった。しかしビシュヌはラクシュミーを神妃として化身(アバターラavatāra)の理論によってクリシュナ信仰やラーマ信仰や仏教をも包摂した。シバは,恐ろしいカーリーあるいはドゥルガー女神と同一視されるパールバティーを神妃とし,南インドではナタラージャとして,また広く男根リンガとして崇拝される。これらの神々を中心に宗派間の対立も見られるが,三神は一体であるという思想も現れた。またシバ神の神妃の性力シャクティの崇拝は,タントリズムの重要な要素を占め,中世以降のヒンドゥー教に特色を与えている。また牛などの動物,トゥルシーなどの草木,ガンガー川などの河川やワーラーナシーなどの聖地の崇拝も行われている。儀礼としてはベーダの犠牲祭(ヤジュニャyajña)に代わって供養(プージャーpūjā)が行われ,神々は神像の形で礼拝され,あたかもたいせつな客人のように扱われ,足を洗う水,香華,灯火,穀物などを供えられ,さまざまな供養を受ける。全国的な規模で行われる祭礼には春の祭りホーリーや収穫祭ディーワーリーなどがある。聖典としては,ベーダ聖典がシュルティ(天啓聖典)として最も権威あるものとされ,そのほかに《バガバッドギーター 》を含む《マハーバーラタ》と《ラーマーヤナ》という二大国民的叙事詩,プラーナ文献,《マヌ法典》などの多数の法典類がスムリティ(聖伝文学)として尊重される。また高度の哲学的・神学的思弁を示す哲学的諸文献群や各宗派の聖典であるサンヒター,アーガマ,タントラなど重要な文献が多数作成された。ヒンドゥー教ではあらゆる種類の,しばしば相矛盾した思想・教義も説かれているが,中心的な思想はウパニシャッド以来の業・輪廻・解脱であり,輪廻からの解脱が人生の四大目標の中でも最高の目標と見なされている。四姓制度と結合したカースト制度や学生期をはじめとする四生活期(アーシュラマ)の制度はヒンドゥー社会を特色づけている。
イスラム教徒(ムスリム)のインド侵入は8世紀ころにまでさかのぼることができるが,初めはヒンドゥー教のインドになんらかの痕跡を残すようなものではなかった。しかし11世紀以後に北インドに侵入したイスラム教徒は略奪,放火,破壊をほしいままにし,1206年インドに初めてイスラム王朝(奴隷王朝,1206-90)が成立し,1857年ムガル帝国が滅亡にいたるまでの約650年間,インドはムスリム政権の支配下に置かれた。しかしヒンドゥー教徒は,他の地域では見られないほど,宗教的にも社会的にも自由であったといわれている。それにもかかわらずムスリム人口の約9割はヒンドゥー教からの改宗者であったといわれ,大規模な改宗は15,16世紀に起こったようであり,改宗の理由はムスリム政権の確立と拡大などがあげられるが,最大の理由はカースト制度であったといわれている。外来の宗教の中で,絶対唯一神アッラーを崇拝する一神教であり,カースト制度を否認し,偶像崇拝を排するイスラムほどインドの社会や思想などに,大きな影響を与えたものはない。またイスラムについてみると,正統派ウラマー よりも,神と人間の一体性を説き,異端視されていたイスラム神秘主義者スーフィー たちの方がはるかに広く深い影響を与えた。スーフィー教団としてはチシュティー教団,スフラワルディー教団,カーディリー教団,ナクシュバンディー教団という正規の四大教団のほかに,変則的な教団や未組織の教団などもある。イスラムの浸透は,ヒンドゥー教の側に改革思想が生まれる契機となり,15世紀末偶像崇拝やカースト制度に反対する,ヒンドゥー教とイスラムとの混交した宗教であるシク教がナーナクによって創始された。
キリスト教のインドへの伝播はかなり古い時代にさかのぼり,伝説では十二使徒の一人聖トマスがマドラス地方に伝道し,72年にマイラポールで殉死したといわれる。6世紀までにはシリアのネストリウス派のキリスト教徒がコーチンに来住し,現在もその伝統は存続しているが,その大部分はローマ教会に属している。ローマ・カトリックは1510年にゴアに定住したポルトガル人によって西部インドに伝えられた。17世紀にはプロテスタント宣教師が南インドに入った。また遅くとも10世紀ころまでにはユダヤ教徒がコーチンに来住した。また8世紀にアラブの支配から逃れて,ペルシアからインドに移住したパールシーPārsīと呼ばれるゾロアスター教徒もおり,17世紀以降インドにおけるイギリス勢力の拡大に伴って彼らの社会的・経済的活動は活発になっていった。19世紀以降,キリスト教宣教師の活動や西洋思想の移入の刺激を受けて,ヒンドゥー教徒の間に,ブラフマ・サマージ,アーリヤ・サマージなどの宗教・社会改革運動が起こったが,1875年にニューヨークに設立され,82年にその本部がマドラスに移された神智学協会の活躍も見のがせない。このほかに種々の部族の中で信仰されている諸宗教も存在する。1971年の国勢調査によると,インド(バーラト)の宗教別人口は次の通りである。
ヒンドゥー教徒 4億5329万 (82.7%)
イスラム教徒 6142万 (11.2%)
キリスト教徒 1422万 (2.6%)
シク教徒 1038万 (1.9%)
仏教徒 381万 (0.7%)
ジャイナ教徒 260万 (0.5%)
その他(パールシー,ユダヤ教徒など)
222万(0.4%)
計5億4795万
注目を引くのは仏教徒の人口である。1951年から61年の10年間に18万人から325万6000人に急上昇し,71年にはジャイナ教徒の数を凌駕するにいたったが,これは不可触民の間に四姓平等を説く仏教を広めようとした不可触民出身のアンベードカル (1891-1956)のネオ・ブッディスト(新仏教徒)運動によるのである。前田 専学
政治,法律 インドの政治と法律については,歴史の上からヒンドゥー,ムスリム(イスラム教徒),イギリス(植民地時代)の三つの制度に分けて述べるのが便宜である。
ヒンドゥーの制度 ヒンドゥーの古代国家は前6,前5世紀にガンガー中流域で形成された。王は農業の拡大を背景として権力を増し,それまでの部族的束縛を破って,都城を築き,自己の軍隊と官吏をもって領域を支配した。その中でマガダ国は近隣諸国を併合して最も有力な国家となり,その国家体制を完成させたのがマウリヤ朝 の古代統一国家である。この発展過程で,ヒマラヤから大洋に至る広大なインド亜大陸はひとつの世界として意識され,ひとりの国王(チャクラバルティンCakravartin,転輪聖王(てんりんじようおう))が支配するのが理想とされた。だがマウリヤ帝国以後,グプタ帝国などの強大な王国が見られたが,南北インドを統一支配するヒンドゥー国家は出現せず,諸王朝の分立割拠が一般的状況となり,各王朝はそれぞれ地方の社会と文化と密着したものとなった。
インドで政治・法律に関する著作が始まるのはマガダ国の拡大のころであって,2種の文献がバラモンによって作られた。その1種は領土の獲得と統治の指導書で,行政,司法,外交,軍事の広範な問題について原理と具体的施策を示したものである。それらは今日ほとんど残っていないが,唯一の文献はマウリヤ帝国の宰相カウティリヤの著作と伝えられる《実利論(アルタシャーストラ)》で,諸論著を集大成した傑作である。他の1種はダルマ・シャーストラ(法典)と呼ばれ,宗教的義務や生活規範ばかりでなく,王の職務や法律を規定し,《マヌ法典》がその最も有名なものであり,《実利論》よりも後世に大きな影響を与えた。これらの古典によれば,クシャトリヤたる王はバラモンの補佐を受けて統治し,国土と人民を保護し,その報酬として租税を享受する。王の職務として強調されたのは,太古から伝えられた法を実践し,とくにバルナ (種姓)の混乱を防ぎ,バルナによる社会秩序を維持し確立することであった。王の地位は世襲的であるが,長男子継承の原則は必ずしも定まっておらず,王子たちは中央・地方の要職を占め,女帝も例外的に知られている。王を補佐するのはプローヒタpurohita(宮廷祭官)などのバラモンであって,彼らは行政や軍事の職に多く採用された。これらの古典は3世紀までに完成し,バラモンの宗教と文化を採用したグプタ朝はこの政治理念を尊重し,それ以後長く踏襲された中央・地方の政治体制を樹立した。それと同時に,バラモンに対する村落,土地の〈施与〉が一般化し,バラモンは地方の社会秩序の維持にあたり,ヒンドゥー教とバルナ秩序の浸透に努めた。とくに8世紀以後には,各王朝は伝説上の太古の王の後裔と称して,王朝の権威と支配の正当性を誇示するようになり,諸王朝の割拠状態が著しくなるにつれ,各地方で領主層が台頭しその勢力が強まり,政治権力の分散化が進んだ。後世ラージプートと呼ばれるカーストが形成されるのもこの時期である。一方,村落には古くから自治自律的な機関が存在し,村長や村老によって運営された。とくに南インドの村落機関は有名であって,詳しい運営手続の規則が定められていた。都市の商人や職人も職業的な組合を組織し,その有力者たちは王朝の地方支配の一翼を担わされた。
ムスリムの制度 13世紀以後のデリー諸王朝(デリー・サルタナット)は異民族出身のムスリムが築いたもので,彼らの故地がモンゴルに占領されたため切り離され,インドに定着した国家となった。諸王朝はムスリム国家の理念とイスラム法を尊重したが,大多数を占めるヒンドゥーには改宗を強制せず,またヒンドゥーの社会制度に干渉せず,彼らの政治制度を利用して支配した。ムスリムの行政制度はアッバース朝以来東方イスラム世界で発達した制度を踏襲し,中央には,宰相と軍司令官のほか,財政・租税を担当する大臣,外交などの文書を扱う大臣が重要であり,地方には中央に準じた組織が整えられた。ムスリムの貴族・官吏・軍人の支配層はさまざまな民族・部族の出身者から構成された。彼らには征服地の一部が給与として支給されたが,君主権の強大化を図った王は貴族たちを抑制し,徴税政策などを改めて財政の確保に努めた。だが支配層は部族を軸として党派を組んで党争し,しだいにトルコ系部族よりもアフガン系部族が有力となった。
ムガル帝国 では,第3代皇帝アクバルが支配体制を確立し,それはデリー諸王朝,とくにシェール・シャー の制度を発展させたものである。第1に,スーバ(州)からパルガナ(郡)に至る地方支配体制を整備し,中心的な地域では,土地を測量して生産物によって単位面積の地税を定め,それを銀貨で徴収するなど,安定した財政を確保した。第2に,軍事・行政の全家臣に対してマンサブ(位階)を定め,各マンサブにそれぞれ騎兵と馬を割り当て,給与としてジャーギールと呼ばれる土地を与え,そこからの租税でまかなわせた。アクバルのとき,高位のマンサブを与えられたのはムスリムが圧倒的であったが,ラージプートを主とするヒンドゥーをも優遇した。その後マンサブを与えられた者の数は増大し,とくにラージプート,次いで第6代皇帝アウラングゼーブのときにはマラータの数が多くなった。このとき,軍事支出の増大とジャーギールの不足から帝国の財政は悪化し,そのうえアウラングゼーブのヒンドゥーに対する強圧的な政治的・宗教的政策が加わって,ザミーンダール層(ザミーンダーリー制度 )の反抗が強まり,それが帝国滅亡の原因となった。
イギリス植民地時代の制度 イギリス東インド会社 のインド統治は,国王の特許状によって権限が賦与され,政府と議会の監督のもとにおかれた。ムガル帝国からは領有の権原や地税徴収の原則などを引き継いだが,従来の統治と異なり,イギリスの独裁的統治であった。統治の最高機関はロンドンの会社理事会,インドでの最高責任者はベンガル総督であり,マドラスとボンベイの2管区の知事は総督のもとにおかれた。彼らはインド旧来の制度を蔑視し,インド人を信用せず要職につけなかった。この統治ではインドの富の収奪,イギリス製品の市場と原料供給地の確保が配慮されて,人口100万の県単位までイギリス人職員が配置され,徴税中心の地方支配体制が整備された。
1833年,東インド会社は商業活動を廃止して純然たるインド統治機関となり,ベンガル総督はインド総督となった。そのもとに新たに立法参事会が設けられ,そこで制定される法律はイギリス議会制定法に準じた効力をもつことになり,それと同時にマドラスとボンベイの立法権は停止された。法についていえば,インド人の家族,カースト,宗教に関してはヒンドゥー法やイスラム法という各宗教徒の法が適用され,その古い法律文献が法源とされた。刑法ではボンベイ管区を除いて旧来の法であるイスラム法が採用されたが,イギリス人の理念に合致しない点はしだいに修正された。このほか,総督や知事が制定した法律は行政の細目と司法手続に関するものが多く,農民の土地の権利は規定されなかったが,徴税に関する法律はこれに多大な影響を与えた。東インド会社は全領域に行政・徴税機構と並んで裁判所機構を配置した。それ以外に管区都市に設置された国王の裁判所たる最高法院とロンドンの枢密院とが高い権威をもち,裁判所を通じて法の空白,不明確なところにしだいにイギリス法が導入された。この時期の政治と法には当初試行錯誤的な施策が多かったが,19世紀になるとベンサム学派の思想の影響が顕著になったことが指摘されている。
次いで1858年,インド大反乱(セポイの反乱)の衝撃を受け,イギリスは東インド会社を廃止してインドを政府の直轄下におき,その後行政,軍事,司法の改革を行い,支配体制を再編成した。行政の面では,3管区以外にも州を新設して長官を派遣し,総督以下の管理体制を明確化して整備した。当時,小作人の権利の保護,農民債務の救済,飢饉など深刻な問題が山積し,政府はこれに対処せざるをえなかった。大きな問題はインド人の登用であった。イギリスの制度と文物を学んだインド人知識階級はその数を増して,彼らの政治的権利の要求,人種差別の非難は強くなった。イギリス側は統治の安定のためにもインド人を登用せざるをえず,中央・地方の立法参事会議員,高等裁判所判事や高等文官にインド人を任用した。この任用にはすでに宗教徒別の配慮が加えられていた。司法の面では,高等裁判所以下の裁判所制度と並んで,法体制を整備することが重要な課題であった。1860年インド刑法典をはじめとして,インドの状況に合致する範囲でイギリス法をもとにした法典が次々に制定されて,大規模にイギリス法が導入され,またパンジャーブなど諸地方の重要な法律が多く制定されて,インドは組織化された法体系をもつ国となった。
20世紀に入って,ベンガル分割反対運動を経て独立運動が激化すると,イギリスは統治法改正によって一定の権限をインド人に委譲することで対処した。まず中央・地方の立法参事会のインド人議員を増加し,第1次大戦後の1919年には中央と州の議会議員を選挙によって選出し,州行政のうち農業,教育,衛生などの事項をインド人にゆだねた。次いで35年には,藩王国を含めてインド連邦制を構想し,連邦と州の立法・行政の大幅な権限をインド人の議会と内閣に委譲することにしたが,総督と州知事は最終的権限を握り,藩王国問題には手を触れさせなかった。この過程を通じて,議会選挙の有権者の範囲は拡大されたが,ムスリムに独自の議席を設け,宗教徒間の対立を醸成した。一方インド人の独立運動は国民会議派が主導して進められ,ガンディーの説くサティヤーグラハという非暴力抵抗が運動の精神となったが,20年代以後には社会主義が叫ばれ,また農民運動と労働運動が独立運動の要素となった。
第2次世界大戦後,イギリス側は行政・軍事の面でインドを統治する実力を失い,高等文官を供給することができず,あらゆる官職のインド人化が急速に進んだが,パキスタンの分離を叫ぶムスリム連盟はムスリムを代表する政党と見なされ,国民会議派と激しく対立したため,インド独立は遅れた。46年には内閣使節団構想に基づいてインド人の中間政府と憲法制定会議が発足したが,後者にはムスリム連盟は参加せず,47年にインド,パキスタン2国が自治領として独立した。山崎 利男
社会 インド社会の特徴としては,しばしば合同家族,カースト 制度,村落共同体の3者があげられる。インド社会の基礎単位は家族であり,合同家族とは結婚した息子たちが財産,生計,祭祀を共同にして生活する形態の大家族である。合同家族はとりわけ上層カーストの富裕な人々の間に多く見られるが,その他の家族でも合同家族を理想とし,その理念に基づいて互いに助け合っている。どの家族も必ず特定のカーストに属する。仏教やイスラムなどに改宗した非ヒンドゥー教徒でも,改宗前に所属したカーストに応じて新しいカーストをつくっているか,宗教徒集団自体がカーストと同様に見なされている。カーストは村落や都市をこえた地域で形成されており,主要な言語地域ではその数は100以上である。カーストの特徴をあげれば,(1)それぞれ他から区別される名称をもち,その成員身分は世襲的で生まれたときに決まり,カーストの規則を破って追放されるかあるいは明瞭な手続で改宗しないかぎり,死ぬまでそのカーストから変わることができない。(2)婚姻は同じカーストの成員の間で行われる。(3)カーストの名称の多くがそれぞれの仕事を示しているように,カーストは職業と結びつきをもっている。その成員はかつて同じ特定の職業をもっていたと信じ,今も多くの成員がこの伝統的職業に従事している。しかもこの職業から離れても,カーストの所属は変わらない。(4)同じカーストの成員は宗教儀式,食事をはじめとして慣習を共通にしており,食事をいっしょに食べることができる間がらであって,生活を相互に規律している。この規律を維持する自治的機関はパンチャーヤットと呼ばれる。とくに成員が共同して彼らの権益を主張し,あるいはそれを擁護する必要のある中層と下層のカーストの間では,パンチャーヤットの活動は顕著である。このような特徴をもつカーストは,バラモンを最上層,不可触民を最下層として,ヒエラルヒーをなし,各カーストはその中にランクづけられており,下層カーストに対してはけがれの観念によって宗教上・社会上の差別が行われ,その差別はカルマ(業 )の理念に正当化されている。そして各カーストはバラモン,クシャトリヤ,バイシャ,シュードラの有名な四つのバルナ(種姓)か,その外におかれ差別を受けた不可触民のいずれかに属すると考えられている。このバルナ制度はさまざまなカーストを全インドにわたってランクづける枠としての機能を果たしている。だがバラモンと不可触民を別とすると,中間層のカーストのランクは必ずしも明瞭ではなく,村落によって相違することが多い。またあるカーストはバラモンと主張するが,地域社会はそれを認めずシュードラと見なしているように,各カーストとバルナ姓との関係には問題がある。
村落共同体はいくつものカーストに属する家族によって形成される基礎的な地域的集団である。そこでは土地所有の上で優位を占めるカーストが支配的地位を占めており,これは支配カーストdominant casteと呼ばれる。このカーストを中心としてさまざまなカーストがあり,村落生活と農業生産のために必要な仕事を分業している。村落は人々の生活の単位であるとともに政治・行政の末端単位でもある。村長が徴税,治安,行政の責任者であり,村書記が徴税のため土地所有などの記録を保持しており,村長のもとで自治自律的機関たるパンチャーヤットが村落の社会的規律を維持している。村落形態はベンガルや西海岸地帯を除いて集村であり,村と村の居住区域間はふつう数kmも隔たっているが,村落は決して孤立したものではなく,数村落がまとまって一つの小さな経済圏・生活圏をなし,そこに市が定期的に開かれている。
このインドの特色ある社会は決して太古から存在して変わらなかったわけではない。歴史的にいえば,村落社会は前7世紀ごろガンガー川流域の開拓の進展を背景として成立し,そのころバラモンによって4バルナ制度も樹立された。その後数世紀間この先進地域の国家と農業の発展,宗教と文化の進歩はめざましく,それらはしだいに諸地方に広まって,各地方ではそれぞれ独自の村落社会が形成された。4バルナ制度は《マヌ法典》において完成した規範がつくられたが,そのまま行われたわけではなく,バラモンのほかは,身分,階級,官職の名称をつけて記されるのがふつうであり,《マヌ法典》と違って,バイシャは商人,シュードラは農民という観念も生まれ,4バルナの外の不可触民はきびしく差別された。8世紀以後,土地所有階級が村落の農業生産を支配し,彼らの中から領主層が台頭すると,彼らは郷村で排他的な集団を形成してカーストとなり,バラモンと彼らの支配のもとで農業生産と村落生活のため手工業やさまざまな仕事に従事していた職業集団は世襲化して,それぞれカーストを形成した。こうして村落社会は諸カーストのヒエラルヒーをなす社会となり,けがれの観念とあいまって,差別の慣行は著しくなった。13世紀以後のイスラム教徒のインド支配は従来の政治・社会体制の上に乗ったため,カースト制度は温存されていよいよ厳格となり,また村落内の分業体制が進み,職人たちに対する報酬は一定額の穀物などを現物で支給することが慣行となり,土地所有者と職人との関係も世襲化した。こうして村落のカースト制度はムガル帝国時代の16,17世紀に完成したが,このとき貨幣経済の普及,市場の発達などによって崩壊もまた始まり,イギリス植民地時代の19世紀に大きな変化をとげた。山崎 利男
コミュニケーション インド亜大陸では,多数の民族が独自の言語と生活様式を保持しており,また多くの地域社会内で上下の身分差が著しいため,横にも縦にもコミュニケーションが制約されることがある。そこでは,意思・情報の相互的な伝達だけでなく,中央から地方へ,上位者から下位者へといった一方的な伝達も,重要な位置を占めることになる。
今日のインド亜大陸では,伝統的なコミュニケーションの方法と近代的な方法とが併存している。村落での公示が今なお,太鼓をたたきながらふれ回るという方法でなされる一方で,村落をこえたレベルでは官報,新聞,ラジオといったメディアによって公示がなされているのである。村落での伝統的なコミュニケーションと意思決定は,同一ジャーティの構成員にかかわる問題の場合,そのジャーティの長老の協議によるのがふつうである。場合によっては,近隣諸村からも同一ジャーティのメンバーが加わることもある。複数のジャーティの構成員にかかわる事がら,全村的な問題については,村の支配層を形成する諸ジャーティの長老が協議する。いずれの場合も,上位者,長老の見解が方向を決する傾向が見られるが,詳しく観察するとその方法は必ずしも上意下達とは断じられない。というのは,階層,年齢,性別などの点での下位者は上位者に対して自分の主張をすることが少ないが,上位者は下位者の意向を察しそれを全体の決定に反映させることができるときに信望を得られるので,下位者への配慮を怠れないからである。さらに,村内の伝統的なコミュニケーションと意思決定は,当事者の主張と村内の事情を勘案して,決定・裁決というよりは調整・調停に近い方法でなされることが多い。
しかしながら独立後は,形式的には民主的な村落自治制度が多くの地域で導入され,村内の全成年者の選挙により村長と村議員を選べるようになったため,上述の伝統的な慣習との間に種々の問題をはらむようになった。伝統的な秩序の中で経済的・身分的に上層の者が村政の中枢に位置するときは,慣習と新制度が一元的に機能しうるが,多数派でありながら身分的に下位のグループが村政を握った場合,上位者グループの協力が得られないことが多い。そこでは,上位者と下位者の対立が生じて有効な村政が行えないという事態にいたる。また,新旧制度および諸勢力の対立にまで及ばなくとも,新制度の発足に伴い,慣習的に村を統治していた層の構成員の,統治者としての責任と自負が薄れてきた一方,新制度には行政的にも財政的にも十分な裏づけがないという現実があり,村落のコミュニケーションは過渡期にあるといえる。そういう条件下でしばしば生ずるのは,村内の有力ジャーティの間の勢力争いである。これは,ある有力ジャーティがいくつかの下位ジャーティを抱きこみ,別の有力ジャーティが他の下位ジャーティを従えるというふうに村落そのものを分裂・対立にもちこむことが多い。同一ジャーティ内の有力者間の対立からも,同じようなことが生じる。
都市には出身地を異にする人々が住み,近代的な条件のもとで暮らしているので,伝統的なコミュニケーションは成り立ちがたいように見えるが,現実には,大都市の上層民は別として,そこの中・下層民,中・小の都市在住者は,伝統的なコミュニケーションの方法にたぶんに依存している。大都市と古くからの中都市では,特定の地域の出身者がある区画に集中的に居住し,彼らの故郷の食物と生活様式を保存しながら暮らしていて,自分たちの出身地の言語を媒体とする学校を設立し,子弟の教育を行う場合もある。したがって都市の中にインドの各地方の居留地ができているという観を呈する場合がある。そこでは,全インド的な祭礼のほか,各地の祭礼が故郷におけるのと同じように行われるので,その都市全体としては日常生活を営んでいる中で,ある区画だけで祭礼の行列がにぎやかに進むという現象が見られる。中層民・下層民は,都市においてもこうして出身地域の人間とその生活様式の中で暮らす傾向が強いが,実業家,高級官僚,専門職などの上層民は,各自の出身地域の文化と生活様式だけでなく,英語を使って西欧化した生活を取り入れながら,出身地域の枠を超えた交際をする。
コミュニケーションの手段には,ラジオ,新聞・雑誌,映画,テレビなどの近代的なものと,それらにいくぶん依存しながらも別の体系をなす,〈口コミ〉(口頭によるコミュニケーション)や巡礼といった旧来のものがある。ラジオは電池式の比較的安価な受信機が普及したため,電気の供給のない(あっても安定しない)村落でも広く聴取されている。音楽やニュースなどのほかに,農事番組が高い関心を呼んでいる。新聞は全国紙,地方紙ともインドの大きな人口に比して部数が少なく,普及率が低い。都市の上層と中層の人々だけのものにとどまっている。村落では,バス便に託して届けられるのを村一番のインテリが読むという場合があるが,多くの村では学校も含めて1部の新聞もはいってこない。このように新聞が普及しない原因は,外的には識字率の低さ,広大な国土での輸送の困難,所得水準に比べて高くつく購読料などがあげられ,新聞の内容からは,多くの全国紙が大都市中心の記事構成をとっていること(例えばデリーで発行された全国紙は,700km以上離れたワーラーナシーに配られる分も,停電・断水の予告,映画の案内をデリーについてのみ掲げ,ワーラーナシーとその近辺についての都市情報は皆無である),地方紙のうち英字紙はその地方の名門の人々の消息記事風のものを多く載せ,民族語による地方紙の記事の多くが全国的な英字紙の翻訳調のものであることなどに求められよう。ただし,民族語による地方紙の中には,ワーラーナシーで発行されているヒンディー語日刊紙《アージュ》のように,発行地だけでなく,地方都市,田舎町にまで通信員を派遣し,電報・郵便などによりきめ細かい記事を集めて読者の要請にこたえているものも,少数ながらある。雑誌は新聞社系のもの,出版社系のものに大別され,新聞社系のものは宅配,出版社系のものは街頭のスタンド売りにより読者の手に渡る。書店は数が少ないうえに雑誌を置かないところが多いので,雑誌の販路としてはほとんど機能していない。
映画の普及と人気は大きい(インド映画 )。人口1万人未満の田舎町にも常設館がある。大都市の上等の席は,上層の人たちの社交場でもある。都市の場末の映画館の安い席には,手軽な娯楽を求める低所得者が文字どおりひしめきあいながら押しかける。また,映画音楽はラジオを通じても広がり,民衆の夢を代弁している。有力な映画館や街頭で,主題歌の歌詞パンフレットを求め,後日それを読みながら歌う人が多い。したがって,映画を見ない人にも,映画音楽は愛唱される。テレビは,大都市と州都を中心とするごく一部の地域でのみ受像ができる。受像機がいまだに高価であることも原因で,普及率は低い。しかし近隣の交際が密なため,インドの劇映画の名作を放映する日曜の夜には,テレビのある家の居間に近所の人がおおぜい集まる。郵便は,山間僻地をもよくカバーしている。場所によっては1人の配達人が10ヵ村ぐらいを担当するので,到着に要する日数が長いうらみがあるが,故郷を離れて出稼ぎにきている人が都会の郵便局の前に座る代書屋に手紙を書いてもらい,また月給日になると仕送りをする人が為替の窓口に長い列をつくるのは,郵便がいかに普及し,重要な役割を果たしているかを物語るものである。
これらとは異なるコミュニケーションの手段・方法では,巡礼 が有力である。巡礼は,家族または近隣の人が何人か集まって日帰りで近くの聖地を訪れる場合,町会,職場の有志が団体で数泊の巡礼に行く場合,教団・教派の主催で本山やゆかりの地を数十日かけてめぐり歩く旅など,さまざまな形態があるが,そこでは行をともにする巡礼集団内でのコミュニケーションはもちろん,聖地で行きあった別の集団とのやりとり,聖地の住民と関係業者らとの交流が成り立つ。結婚式も,村落にあっては通常の身分秩序の枠をいくぶんゆるめた人の出入りがあること,都市では親類のほかにさまざまな職能の近隣の人々の応援を求める一方でその人たちを招待することにより,人の交流,情報の交換に大きく寄与している。中・上位層の家に嫁いだ女性が,主として雨季に1ヵ月以上にわたって毎年のように里帰りするのも,実家と婚家のコミュニケーションをよくしている。
全体として今日のインドのコミュニケーションの情況を見るとき,公権力や大きな勢力をもつ集団は,情報を十分に発表しておらず,また発表された情報の伝達の方法も整備されているとはいえない。そこにはしばしば,情報不足に起因する欲求不満とデマが生じ,それが暴動にまでいたることがある。列車やバスの行先表示の不親切さ,運行情報の不十分さ,食糧の配給情報の不足と長時間にわたり待たされるやりきれなさなどは,日常的にやりばのない不満と弱者間の争いの原因になっている。そこでの自衛手段として人々が依存するのが〈口コミ〉である。公的なルートで十分な情報が得られない場合,公的機関内にいて出身地,階層などを同じくする人に接近して情報を得て,口づてにそれを流すのである。〈口コミ〉はまた,公的な情報の補完以上の役割も果たす。農産物の市況は,新聞,ラジオで迅速に伝えられるが,在村の富農層の間ではそれよりも早く仲間うちからの情報が流れ,適切な判断と行動の助けとなる。〈口コミ〉に一定の様式が付加されたときの情報伝達は,実にみごとである。巡礼地ブリンダーバンのある信徒会館で朝・昼・晩に分けて連日催される行事は,特別な掲示などはいっさいなされていないにもかかわらず,それぞれの開始時間になると近くの巡礼宿に泊まっている人,住民などが続々と集まって来る。主催者の努力で年中行事に近い形で定着してきていることが,〈口コミ〉情報と相まって有効に人に情報を伝えているのであろう。
結局,インドでのコミュニケーションは,公的な機関,新しい制度による情報と機能の不足不備を,伝統的な方法が代替・肩代りすることによって,全体のシステムをなしているというのが現状であろう。カースト 坂田 貞二
歴史 時代区分 文献から知られるインド亜大陸の歴史は,アーリヤ人の来住をもって始まる。それ以後今日に至る約3500年のインドの歴史は,次の4時代に区分されることが多い。(1)古代(ヒンドゥー時代) アーリヤ人の来住から13世紀初頭のイスラム教徒(ムスリム)の政権成立まで。(2)中世(イスラム時代) 13世紀初頭からイギリスのインド支配が開始される18世紀半ばまで。(3)近代(植民地時代) 18世紀半ばから1947年の独立まで。(4)現代 独立以後。以上の時代区分は,支配者の奉ずる宗教や支配民族の交代など政治的・宗教的な理由からなされたものであり,亜大陸の社会・経済の発達を示す区分とは必ずしも一致しない。
18・19世紀のヨーロッパ人の間には,インドの社会を停滞的なアジア社会の典型例とみる学説が有力であったが,こうした停滞社会論は,今日では否定されている。近年,多くの歴史家によって,インド社会が一定の発達段階を経て今日に至ったことを立証する試みがなされてきた。そこでは,(1)インド古代を奴隷制社会としてとらえることができるかどうか,(2)グプタ朝末期以後のインド社会の変化(都市と商業の衰退,地域社会の自給自足化,領主層の台頭など)を封建制としてとらえることができるかどうか,(3)ムガル時代中期以後のインド経済の発達を資本制経済成立の前段階としてとらえることができるかどうかなど,さまざまな問題が検討されている。しかし史料上の制約もあり,新しい時代区分は学説として確立するまでにいたっていない。
インダス文明 インド亜大陸には洪積世の時代から人類が住み,各地に旧石器文化,新石器文化の遺跡を残している。今日の亜大陸に居住する諸民族のうち最も早くこの地に住みついたのは,中部・東部の丘陵地帯に分布するアウストロアジア系の民族である。その後,一説によると前3500年ころ,西方からドラビダ系の民族が到来し,しだいに亜大陸の奥深くまで居住域を広げていった。前2300年ころ,インダス川の流域を中心とする広大な地域に青銅器時代の都市文明(ハラッパー文化)が興り,前1700年ころまで栄えた。モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)とハラッパーがこの文明を代表する二大都市遺跡であり,いずれも焼成煉瓦をふんだんに用い一定の都市計画のもとに建設されていた。この文明を担っていたのはドラビダ系の民族らしいが,文字の解読が遅れているため確実なことはわからない。また文明の起源と消滅の原因についても謎に包まれている。しかし当時の文化要素の中には,宗教的沐浴の風習,地母神,樹神,牡牛の崇拝,シバ神らしい神の崇拝をはじめ,後世のインド文化に引き継がれたものも多い。
アーリヤ人の来住 インド・ヨーロッパ系の言語を話すアーリヤ人は,はじめ中央アジア方面で遊牧生活を営んでいたが,その一分派がインダス文明のすでに衰退した前1500年ころから徐々にパンジャーブ地方に移住した。そして部族の首長(ラージャン)に率いられ,ダーサと呼ばれる先住民を征服しつつ,牧畜を主とし農耕を従とする半定着の生活を始めた(前期ベーダ時代,前1500-前1000ころ)。当時の生活では牛が最も重要な財産であり,農作物としては大麦の栽培が中心であった。アーリヤ人はパンジャーブで先住農耕民との間に人種的・文化的な混血・融合を深めたが,やがてその一部は前1000年ころからガンガー川上流域へと進出し,この地で農業社会を完成させた(後期ベーダ時代,前1000-前600ころ)。前800年ころになると鉄器の使用が始まり,水稲栽培も広く行われるようになった。こうした経済の発達を背景に司祭階級や王侯が活躍し,前者によってバラモン教の諸聖典が編まれ,後者によって行政制度や徴税制度が整えられた。またこのころカースト制度の初期の形態であるバルナ(種姓)制度が成立し,社会はバラモン(司祭者)を最高位とし,クシャトリヤ(王侯,武士),バイシャ(庶民),シュードラ(隷属民)と続く四つの基本的身分に分けられた。
古代帝国の成立 前600年ころになると,政治・経済・文化の中心はさらに東方のガンガー川中流域へと移った。また各地に都市が興り,それぞれの都市を首都とする諸国が互いに争うようになった。十六大国と総称される当時の有力諸国のうち,やがて君主制を発達させたマガダ 国が強大となり,前5世紀初めころガンガー川中流域に覇を唱えた。貨幣の使用が始まったのもこのころであり,都市では商人の活動が盛んであった。また,厳格な身分制度と祭式至上主義に立つバラモン教に対抗して,思索や修行を重視する仏教,ジャイナ教などの新宗教が興り,都市で身分制度にとらわれずに活動していた王侯や商人に支持された。
マガダ国はその後も着実に領土を広げ,前4世紀半ばにはガンガー川流域のほぼ全域を支配下に置いた。一方,インダス川の流域は長期にわたりアケメネス朝ペルシアの属州になっており,続いてアレクサンドロス大王に征服され(前326-前325),その帝国に併合された。しかしこの地のギリシア人勢力は,大王の死後ほどなく,マガダ国に興ったマウリヤ朝 によって一掃された。この新王朝のもとでインド史上初めて両大河にまたがる統一帝国の成立をみた。マウリヤ朝は第3代のアショーカ(在位,前268-前232ころ)の時代に最盛期を迎え,帝国の版図は半島南端部を除く亜大陸のほぼ全域に及んだ。帝国はアショーカの死後に分裂と衰退への道を歩んだが,約1世紀にわたる亜大陸統一の結果,ガンガー川流域の先進文化が周辺地域に伝えられ,それぞれの地で根を下ろした。
デカンと西北インド マウリヤ帝国の成立に伴い亜大陸全域で経済と文化の発達が見られた。こうした経済的・文化的発達を背景に,帝国崩壊の後,亜大陸の各地でガンガー川流域の国家をしのぐ強大な国家が興った。その一つサータバーハナ朝 は,最盛期(2世紀)にデカンのほぼ全域を支配し,半島東西の諸港を拠点とする外国貿易によって富み栄えた。西北インドでは,前2世紀の初頭以来ギリシア人,サカ族,パルティア人の侵入が相次いだ。その後,1世紀半ばごろバクトリア方面からクシャーナ族が侵入し,中央アジアから中部インドに及ぶ大国家を建設した(~3世紀初め)。クシャーナ朝 は漢とローマを結ぶ東西交通路の中央をおさえて繁栄し,またこの王朝のもとで大乗仏教の確立とガンダーラ美術の開花とがみられた。
マウリヤ帝国の滅亡からグプタ朝の成立に至る約500年間は,政治的にみれば異民族の侵入が続き諸王国が乱立する不安定な時代であった。しかし経済的にみれば都市の商業活動が盛んな時代であり,また文化的には仏教,ジャイナ教が栄え,バラモン教と土着の宗教とが融合したヒンドゥー教の形成が進んだ。ヒンドゥー教の聖典《マハーバーラタ》と《ラーマーヤナ》が現在の形にまとめられたのも,ヒンドゥー教徒の生活を規定した《マヌ法典》が編まれたのもこの時代である。
古典文化の爛熟 サータバーハナ朝とクシャーナ朝は3世紀に入ると衰えたが,4世紀の初めにガンガー川の中流域にグプタ朝 が興り,北インドを統一し,デカン方面へも政治的影響力を及ぼした。グプタ朝時代はインド古典文化の黄金時代として知られる。宗教の分野ではバラモン教哲学が復興し,ヒンドゥー教が隆盛に向かった。ヒンドゥー教寺院が建てられるようになるのも,このころからである。仏教はそれまでの勢いを失ったが,教理研究は高度に発達した。文学ではカーリダーサがサンスクリット語の詩や戯曲を書き,美術ではグプタ式仏像やアジャンターの壁画に代表される洗練された純インド的様式が確立した。数学も発達し,このころ〈ゼロの発見〉がなされた。
諸王国の分立 グプタ朝は5世紀後半になると,フーナ(エフタル)族の侵略や諸侯の独立のために衰退し始めた。これ以後イスラム教徒の政権がデリーに成立するまでの約550年間,北インドはハルシャ王の時代(7世紀前半)などわずかな期間を除き,群雄が割拠する分裂状態に置かれていた。そうした群雄の中では,西部インド,中央インドに興ったラージプート族の諸王国が名高い。この間,都市と商業が衰え,農村社会の自給自足化が進んだ。多数のカーストの集合体から成るインド独自の村落は,この時代に徐々に形成されたものらしい。また都市の商工業者や王侯によって経済的に支えられてきた仏教が衰え,村落社会を基盤とするヒンドゥー教が王侯や一般大衆の間に完全に定着した。地方政権の分立したこの時代にはまた,各地で地方語が発達し,文学や美術の分野で特色ある地方文化が興っている。
南インドの歴史と文化 ドラビダ人の住む南インドには,すでに前3世紀のアショーカ王の時代にいくつかの独立国家が存在していた。その後もドラビダ人は,北インドから伝わった諸制度を採用しつつ,大小多数の王国を建設してきた。南インドに興亡した諸王朝の中でも,9世紀中ごろタミル地方に興ったチョーラ朝がとくに名高い(~13世紀)。この王朝は,南はスリランカを征服し,北はガンガー川流域にまで兵を送った。さらに海上貿易を有利に導くため海軍を東南アジアに遠征させている。ドラビダ人はまた,彼ら独自の文化と仏教,ヒンドゥー教に代表される北インドの諸文化を融合させ,特色ある文化を発達させた。文学では,ドラビダ語の一派であるタミル語の文学(サンガム文学)が注目される。美術ではパッラバ朝(3~9世紀)の石刻寺院建築やチョーラ朝のブロンズ彫刻などの新しい様式を生み出した。ヒンドゥー教の改革派であるバクティ(絶対帰依)信仰は,8世紀ごろ南インドに興り,やがて全インドに広まった。南インドの住民の海上活動もまた歴史上重要である。ローマ,アラビアなどの西方世界との海上貿易や,東南アジア,中国との貿易には,南インド商人の活躍が目だった。
イスラム教徒のインド支配 8世紀初めにウマイヤ朝のアラブ軍がインダス川下流域を征服したが,この後の3世紀間,イスラム教徒はそれ以上亜大陸内部に進出することはなかった。彼らの組織的なインド侵略が始まるのは,アフガニスタンにガズナ朝とゴール朝が相次いで興ってからである。トルコ系の両王朝は11世紀初頭から侵入・略奪を繰り返し,分立抗争していたヒンドゥー教徒の諸国を破って,しだいにインド支配の足場を固めた。そして1206年,ゴール朝の将軍で奴隷出身のクトゥブッディーン・アイバクが,デリーで独立してインド最初のムスリム王朝(奴隷王朝)を創始した。その後の320年間,デリーに都を置きデリー・サルタナット(デリー・スルタン朝)と総称される五つのムスリム王朝が交代した。デリーの政権は14世紀初めに南インドにまで支配権を及ぼしたが,同世紀の半ばに弱体化し,その結果,亜大陸各地にイスラム,ヒンドゥー教を奉ずる諸王国の独立をみた。そのうちのビジャヤナガル王国(14~17世紀)は,デカン南部に興り,近隣のイスラム諸政権に対抗しつつヒンドゥー教とインド古来の伝統を守った。この王国はまた海上貿易で巨富を得た。その繁栄のもようは15世紀末からこの地に来航したヨーロッパ人の伝えるところでもある。
イスラム教徒は,インド侵略の初期にヒンドゥー教の寺院や偶像を破壊したため,社会の混乱は大きかった。しかし,インドの土地と住民の永続的な支配を目指すようになるとその態度を改め,旧来の社会や統治機構を崩さずその上に君臨するという現実的な政策を採用し始めた。この時代にイスラムに改宗するインド人も増えたが,それは権力者による強制を伴ったものではなく,主としてイスラム商人や,市井で布教にあたるスーフィー(イスラム神秘主義者)たちの平和的な宗教活動によるものであった。一方,南インドで発達したヒンドゥー教のバクティ信仰が北インドでも流行し,一部でイスラムとの融合もみられた。ドームとアーチを伴った建築様式が西方イスラム世界から導入されたのも,この時代である。また書写に紙を用いることが始まり,しだいに従来の葉や樹皮に取って代わった。
ムガル帝国 1526年,ティムールの直系子孫のバーブルは,アフガニスタンから南下してサルタナットの軍を破り,デリーに入城してムガル朝を創始した。彼の孫で第3代のアクバル(在位1556-1605)は,版図をデカンの一部を含む北インド全域に広げるとともに,税制・官僚制の改革,新都アーグラの建設,ヒンドゥー教宥和政策など意欲的な政策を実施し,帝国の基礎を固めた。アクバル以後,ムガル帝国の繁栄は続いた。しかし帝国の版図が最大となった17世紀末には,相次ぐ戦争の出費,宮廷の浪費,経済政策の失敗などのために財政状態は悪化しており,またヒンドゥー教徒に対する抑圧策が国内各地の反乱を招いた。18世紀に入ると帝位継承の争いや諸侯の離反・独立が相次ぎ,さらに西部デカンにおけるマラータ族やパンジャーブにおけるシク教徒の勢力の強大化,ペルシア軍,アフガン軍の侵入も重なって,帝国の領土は急速に縮小した。
ムガル時代には,亜大陸の各地で商業が発達した。また地税の銀納化も行われ,農村地域における経済活動も活発化してきた。亜大陸各地におけるこうした経済的向上が,ムガル帝国の分裂と地方政権の成立を促したとみることもできる。
ヒンドゥー教が多神崇拝と偶像崇拝を極度に発達させた宗教であるのに対し,イスラムは偶像を厳しく禁ずる一神教である。ヒンドゥー・イスラム両文化は,このように異質のものであったが,インドにおける長年の接触の結果さまざまな面で融合し,ここにインド・イスラム文化の成立をみた。インド古典のペルシア語訳が宮廷で読まれ,北インドの言語にペルシア語の要素が加わったウルドゥー語が発達した。宗教では,ヒンドゥー教の改革派で一神教的傾向をもつシク教が成立し,美術の面では第5代皇帝シャー・ジャハーンの時代を頂点とする建築活動や,ペルシアの細密画の影響を受けたムガル絵画,ラージプート絵画などの流行がみられた。
イギリスの進出 1498年,バスコ・ダ・ガマの船隊がカリカットに来航し,ここにヨーロッパとインドは直接結ばれることになった。16世紀を通じてヨーロッパ人によるインド貿易はゴアに総督府を置くポルトガルに独占されていたが,17世紀に入るとイギリス,オランダ,フランスが貿易競争に加わった。1600年に設立されたイギリス東インド会社は,東南アジアでオランダと争って敗れた後インド経営に力を注ぎ,まずポルトガル,オランダを圧倒し,18世紀半ばにはフランスを退けた。インドに到来したヨーロッパ人の目的は,当初はインドの産物の入手という純商業的なものであったが,やがて軍事力を背景にインドの土地と住民に政治的な力を及ぼすようになった。1757年のプラッシーの戦はこうした侵略的なインド経営を象徴するできごとであり,この戦いでベンガル太守軍を破ったイギリス東インド会社は,インド植民地化の足場を固めた。
18世紀のインドはムガル帝国の衰退期にあたり,各地に地方政権が乱立していた。軍事力に勝るイギリスは,こうした好機をとらえ,征服・併合および軍事保護条約締結(地方政権の藩王国化)という和戦両策を巧みに用いて土着政権を圧倒し,同世紀半ば以後の約1世紀間に亜大陸のほぼ全域を直接・間接の支配下に置いた。東インド会社はもはや貿易会社ではなく,インド人から徴収した地税収入を主たる財源とし,インドの土地と人民を統治する機関となっていた。〈インドの富〉はこうしてイギリスに流出し,イギリス本国の産業資本の育成に貢献した。
イギリスにおける産業革命の進行に伴い,インドが原料生産地および商品市場として見直されるようになると,新興の産業資本家や商人の間に貿易自由化を求める声が高まった。東インド会社に対する監督を強化しつつあったイギリス本国政府は,こうした声にこたえて会社の貿易独占権を廃し(1813),続いて会社の商業活動を全面的に停止させた(1833)。またカルカッタ駐在のインド総督を頂点とする植民地支配の体制を固めた。
1857年の大反乱 イギリスの進出はインド社会に大きな変化を引き起こした。綿布はかつてインドの最も重要な輸出品であったが,マンチェスター産の安価な機械織綿布との競争に敗れ,都市の木綿工業は大打撃を受けた。また,綿花,アヘン,インジゴ,ジュート,茶などの輸出用作物の栽培,商品経済の浸透,新しい土地制度・徴税制度の採用などによって,伝統的な村落社会は崩され,土地に対する旧来の権利を奪われた農民は,不安定な困窮生活を強いられた。一方,イギリスは植民地支配の一環として,資源の開発,道路・鉄道・灌漑施設などの建設,通信網の整備などに力を注ぎ,また新たな司法制度やイギリス流の教育制度を導入したりした。ヨーロッパ思想の刺激を受けた都市の知識人の中には,カースト社会を批判し女性の地位改善を求める運動や,ヒンドゥー教改革運動を始める者も現れた。
イギリスの進出に対するインド人のさまざまな不満は,1857年にセポイ(シパーヒー)と呼ばれる東インド会社のインド人傭兵が起こした反乱を機に爆発した。反乱軍がデリーを占領してムガル皇帝を擁立すると,旧王族とその臣下,旧地主や農民などが,カーストと宗教の区別を超えて参加し,反乱は中部・北部インドに波及した。乱そのものは2年後にはまったく鎮圧されたが,広い層の人びとが参加したこの大反乱の中に,インド民族運動の第一歩を見ることができる。この反乱にくみしたムガル皇帝は廃位され,ムガル朝は完全に滅んだ。一方,いっそう強力な支配体制の確立を迫られたイギリスは,1858年に東インド会社を解散させ,インドを本国政府の直接の支配下に置いた。さらに77年にはビクトリア女王がインド皇帝を兼ね,ここに直轄領と藩王国とから成るインド帝国が完成した。
民族運動の展開 19世紀後半になると,インドでは土着資本による綿工業や,イギリス資本の近代工業が興った。インド人労働者の数が増し,彼らによる待遇改善運動も発生している。農村では地主への土地集中で貧困化した農民が,しばしば暴動を起こした。またヨーロッパ式の近代教育を受けた知識人の数も増えた。彼らは弁護士,ジャーナリスト,官吏などとして活動していたが,イギリスのインド人差別を不満とし,植民地支配に批判の目を向けるようになった。こうした情勢を背景に,85年にボンベイで第1回の国民会議が開催された。全インド国民会議派の誕生である。国民会議派 の活動は初め穏健なものであったが,イギリスの帝国主義的な植民地政策が露骨化すると反英の傾向を強めた。そして1905年ヒンドゥー・イスラム両教徒を反目させ民族運動を分断しようとするベンガル分割法が施行されると,スワデーシー(国産品愛用),スワラージ(自治獲得)のスローガンを掲げて,イギリスに真正面から対抗した。綿工業をはじめとする産業に進出しつつあった民族資本家は,このスローガンを支持した。しかし,イギリスの弾圧と懐柔によって運動は分断され鎮静化した。分割法そのものも,11年に撤回され,また同年に首都が反英運動の温床カルカッタからデリーに移された。一方,ヒンドゥー教徒を主体とする国民会議派の運動に少数派としての不安を抱いたイスラム教徒の有力者たちは,分割統治を目指すイギリスの勧奨のもとに全インド・ムスリム連盟を組織した。イギリスはその後も,イスラム教徒に有利な宗教別分離選挙制度を導入するなど,巧みな分割統治政策を進めた。
第1次世界大戦が始まると,インド人は多大の犠牲を払ってイギリスに協力し,その代償として自治権を漸次付与するという公約をかち取った。しかし戦後の19年に制定されたインド統治法ではその公約は十分に果たされておらず,かえって民族運動の弾圧を目的としたローラット法が施行されたため,インド人の失望は大きかった。この時期に反英運動の指導者として登場したのがM.K.ガンディーで,彼はローラット法に反対してハルタル(罷業)を宣言し,また20年から22年にかけて国民会議派とムスリム連盟を指導して非暴力不服従運動を展開した。ガンディーの指導のもとで民族運動は一般大衆を加えた全インド的な運動へと脱皮した。
分離独立へ 国民会議派は,外部からたび重なる弾圧を受け,内部においては主義を異にする各派の対立に悩みながらも,反英運動の指導集団としての地位を失わなかった。そして1929年の大会で完全自治(プールナ・スワラージ)を決議し,30年から34年にかけて再びガンディーの指導下に不服従運動を展開した。また国民会議派はインド統治法の改正を目的として開かれた3回の英印円卓会議 (1930-32)のうち2回をボイコットしたが,州自治制を認めた新統治法(1935)に基づく37年の第1回州議会選挙には打って出て,11州のうち6州で過半数の議席を取り内閣を組織している。しかし,第2次世界大戦が始まると,完全独立を要求してイギリスとの対決に踏み切った。イギリスはこれに対して弾圧で臨み,ガンディーをはじめとする指導者を投獄し,国民会議派を非合法団体とした。
ムスリム連盟は,第1次世界大戦中から戦後にかけて,トルコのカリフを擁護する運動(ヒラーファト運動)の必要から国民会議派と提携し反英運動を進めたが,その提携も1922年には崩れ,両派は再び対立するにいたった。連盟はその後ジンナーに指導されて親英・反会議派の道を歩み,40年にはイスラム教徒の国パキスタンの建設を目標に掲げた。第2次世界大戦で疲弊したイギリスは,植民地インドを維持してゆく力を失っていた。大戦後,労働党内閣のもとでインド独立のための準備が進められたが,分離独立を主張するムスリム連盟と,これに反対し統一インドの独立を求める国民会議派との対立が激化した。調停は難航し,結局47年8月に,インド亜大陸に二つの国家,インドと,東西の両部分から成るパキスタンとが誕生した。山崎 元一