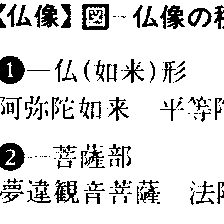精選版 日本国語大辞典 「仏像」の意味・読み・例文・類語
ぶつ‐ぞう‥ザウ【仏像】
- 〘 名詞 〙 仏の姿を彫刻や絵画にあらわしたもの。仏教での礼拝の対象となる。ただし、如来像だけをさす場合と広く仏教諸尊像をさす場合とがある。
- [初出の実例]「合仏像弐拾壱具伍躯肆拾張」(出典:法隆寺伽藍縁起并流記資財帳‐天平一九年(747))
- 「昔、良秀とて、巧に仏像を画く人ありけり」(出典:尋常小学読本(1887)〈文部省〉五)
- [その他の文献]〔五代史‐周世宗紀賛〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「仏像」の意味・わかりやすい解説
仏像
ぶつぞう
仏陀(ぶっだ)の形を絵画、彫刻その他の造形形式によって表現したもの。厳密には仏(ぶつ)とは如来(にょらい)のことで、仏像とは如来像を意味し、ほかの像は菩薩(ぼさつ)像、明王(みょうおう)像などとよぶべきだが、現在では仏教関係の彫像を広く仏像といっている。また絵画で表現されたものは一般に仏画といい、仏像といえば彫像に限るのが普通である。仏教伝来以後の日本の彫刻の歴史はほとんど仏像によって占められている。
[佐藤昭夫]
起源と展開
仏像は釈迦(しゃか)在世当時からあったとする説もあるが、仏像が現れるのは仏滅後500年ほど経てからである。インドでは聖なるものを人間の形で表すことに抵抗があったが、このタブーを破って仏像がつくられたのはクシャン朝の紀元後100年ごろで、ヘレニズム文化の洗礼を受けた西北インドのガンダーラ地方と、インドの造形美術の伝統がある中インドのマトゥラ地方でほぼ同時期に始まったと考えられる。
ギリシア彫刻の影響を受けたガンダーラ様式は、西域(せいいき)を経て中国に入り、朝鮮を通って日本にも達した。一方、マトゥラ地方の彫刻はガンダーラ彫刻と異なり、量感に富み、優れた裸体彫刻の特色を備えていたが、さらに発達、洗練されて4世紀なかばから7世紀なかばにかけてグプタ期の完成した仏像をつくりあげた。以後は仏像は衰えをみせ、8世紀に入ってパーラ期にいったん密教像が盛んとなるが、13世紀ごろから仏教とともに急激に消滅する。
北へ向かったガンダーラの仏像はアフガニスタンを経て西域に入り、シルク・ロードを逆にたどって砂漠のオアシス都市に点々と仏教遺跡を残して中国に達した。仏教が中国に伝えられたのは前漢の哀帝の元寿元年(前2)、仏像がつくられ始めたのは2世紀の中ごろと考えられるが、4世紀の銘のある金銅(こんどう)仏があり、こうした初期の像にはガンダーラ仏の影響がはっきり残されている。353年に中国の西端敦煌(とんこう)に千仏洞がつくられ、その後多くの石窟(せっくつ)が開かれた。陝西(せんせい)省、甘粛(かんしゅく)省など西方にも多くの遺跡があり、有名な雲崗(うんこう)石窟は5世紀なかばからの経営である。このころになると、仏像は中国的な表現と力強さを備え、六朝(りくちょう)、隋(ずい)を経て唐に入ると、インドのグプタ様式の影響を受けた豊満な肉体をもつ像に変貌(へんぼう)する。日本の白鳳(はくほう)末から天平(てんぴょう)期の彫刻はまさにその影響下にある。宋(そう)代以後、仏像制作はしだいに衰えていった。
朝鮮半島に仏教が入ったのは三国時代、4世紀末から5世紀にかけてのことで、3国のうち高句麗(こうくり)は中国の北方様式を受け、百済(くだら)はやや南の江南の様式を取り入れた。新羅(しらぎ)の半島統一以後は、唐の影響を受けて慶州の石窟庵(あん)の像にみられるような優美な作品を残している。この時期以後は中国と同様、朝鮮半島の仏像彫刻もしだいに衰えていく。
仏教の日本公伝は538年(欽明天皇4)とされるが、仏像が日本で本格的につくられるようになったのは飛鳥(あすか)時代も7世紀に近くなってからで、最初は法隆寺釈迦三尊像のような中国北魏(ほくぎ)の様式を受けた象徴的な作風が主流であったが、別に法隆寺百済観音(かんのん)像や中宮寺菩薩半跏(はんか)像のような優美な系統や、朝鮮の直模のような像もみられる。7世紀後半になると、唐風の写実的で豊満な表現になり、やがて8世紀の天平彫刻の黄金時代を迎えると、写実的傾向はさらに強くなり、生き生きした彫刻性が発揮された。
平安時代に入り、9世紀には密教の輸入、木彫の流行によって仏像の性格が一変し、威力と神秘性を備えるようになる。10~12世紀に至って他の文化と同様に仏像にも和風化傾向がおこり、平等院鳳凰(ほうおう)堂阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)のような典麗な定朝(じょうちょう)様式が流行した。鎌倉時代の13世紀には天平復古が唱えられたが、実際には天平の理想化された写実とは異質の、東大寺南大門の仁王(におう)像のような現実的なものへの追求がみられる。やがてこの写実主義も形式化し、南北朝の14世紀ごろから造像量は多くなるものの、しだいに衰退してその後は息を吹き返すことなく、今日に至っている。
[佐藤昭夫]
仏像の種類と特徴
経典には非常に多くの仏菩薩(ぶつぼさつ)が説かれ、密教における世界観を表現した「両界曼荼羅(りょうかいまんだら)図」にも2000体近い像が描かれているが、実際に造像されるのは、如来(にょらい)では釈迦(しゃか)、阿弥陀(あみだ)など数尊にすぎず、菩薩以下を含めても30尊程度である。それらの仏像を大別すると、如来、菩薩、明王(みょうおう)、天部(てんぶ)、神将(しんしょう)などで、これに比丘形(びくぎょう)などを加える場合もある。
[佐藤昭夫]
如来
如来とは梵語(ぼんご)のtathāgataの漢訳で、真理の体得者、悟りを開いた者の意である。仏という語はブッダ(仏陀Buddha)をさし、原始仏教では釈尊(しゃくそん)、つまり釈迦だけが如来であったが、のちには意味を拡大して、多くの像が加わって、釈尊と同列の神格を与えられた如来全般をさすようになり、系列化された。
如来の姿は人間の形を基本とし、これに三十二相八十種好(しゅごう)(随形好(ずいぎょうごう))と称する、人間とは違った宗教上の理想的な特色をもつ。
三十二相のうち造形的に表現しうるものは、縵網相(まんもうそう)(手足の指の間の水かき様の網。これで衆生を救い上げる)、身金色(しんこんじき)相(全身が金色に輝く)、丈光(じょうこう)相(全身の光によって身体の周囲に一丈の余光が輝く。光背(こうはい)はこれを形象化したもの)、頂髻(ちょうけい)相(肉髻(にっけい)相ともいい、頭頂に椀(わん)のような肉の盛り上がりがある)、白毫(びゃくごう)相(眉間(みけん)の白く細い巻毛。これも光り輝くので彫刻では水晶をはめ込んで表す)などである。このほかにも、頭髪は1本ずつ巻き貝のように右巻き(螺髪(らほつ))で青色をしており、掌(てのひら)と足の裏には船の舵輪(だりん)のような千輻輪(せんぷくりん)という文様がある、などの特色がある。この三十二相は経典により多少異なり、一定していないが、もっとも普遍的なのは『大智度論(だいちどろん)』に説くもので、八十種好は三十二相をさらに細かく規定したものである。
如来は出家の姿なので、菩薩とは違って装身具はいっさい着けず、基本的には裳(も)の上に1枚の衲衣(のうえ)(法衣(ほうえ))をまとっただけの姿が多い。衲衣は通肩(つうけん)といって両肩を覆う着法と、偏袒右肩(へんだんうけん)という右肩を露(あらわ)すものとがある。通肩は外出遊行の場合、偏袒右肩は屋内とか礼装の場合だが、後世には混同されて坐像(ざぞう)でも通肩の像がある。ただし大日(だいにち)如来だけは菩薩と同様の姿をとり、初期の釈迦像にも菩薩形のものがある。
如来像どうしの区別はなかなかむずかしい。如来は原則として手に何も持たず、わずかに薬師如来が左手(まれに右手)に薬壺(やくこ)を持つだけである。したがって、如来は手の形で区別するしかない。この手の形を印相(いんぞう)という。
[佐藤昭夫]
釈迦如来
釈迦は仏教の開祖で、長い布教生活ののち80歳の生涯を終えた実在の人物だが、日本では仏教で信仰される架空の仏たちと同列に扱われる。インドではもっと人間的な形で信仰され、釈迦の現世の伝記および前世における伝記の本生譚(ほんじょうたん)(ジャータカ)によって仏像がつくられ、礼拝(らいはい)された。しかし仏教東漸の過程で、人間釈迦としてよりも、仏法のなかの釈迦、単なる一如来へと性格が変わる。日本で釈迦伝関係の仏像といえば、誕生仏、涅槃(ねはん)図や涅槃像、絵画で出山(しゅっせん)釈迦、金棺出現くらいで、それ以外はほとんどない。とくに本生譚を取り上げたものは玉虫厨子(たまむしずし)台座の側面の「施身聞偈(せしんもんげ)」「捨身飼虎(しゃしんしこ)」の2図の例があるのみである。
釈迦の手印でいちばん多いのは施無畏(せむい)、与願(よがん)の印である。降魔(ごうま)印の像は日本では少ないが、インド、中国などでは多い。釈迦説法の姿は転法輪(てんぽうりん)印、坐禅(ざぜん)の姿は禅定(ぜんじょう)印あるいは法界定(ほうかいじょう)印を結ぶ。同じ釈迦像でも地域、時代、宗派によって異なる場合があり、前述の印も釈迦固有ではなく、他の如来が同じ印を結んでいることもある。
[佐藤昭夫]
阿弥陀如来
釈迦は自らの悟りのための仏であるが、阿弥陀如来は人間が免れえぬ死の問題を解決してくれる仏である。阿弥陀如来は四十八願という多くの願をたて修行を積んで、西方はるか十万億土のかなた極楽浄土にあり、人の生命が終わろうとするとき迎えに来て(来迎(らいごう))、その魂を極楽に導くと経典は説いている。そのためには、阿弥陀への帰依(きえ)、念仏修行や功徳(くどく)を積み重ねることが必要とされる。浄土とは仏の住む世界で、一つの仏がそれぞれ浄土をもっており、したがって仏の数だけ浄土もあるので、人はそれぞれ自らの信ずる仏の浄土へ往生することを願うわけだが、浄土往生といえば阿弥陀の極楽往生がもっぱらとなっている。
来迎のあり方にも、死者の生前の功徳によって、上の上から下の下まで九通りがある。上の上(上品上生(じょうぼんじょうしょう))の場合は阿弥陀が観音(かんのん)・勢至(せいし)の2菩薩のほか25人もの菩薩を連れ、音楽を奏しながらやってくるが、中、下になるにしたがい菩薩の数も少なくなり、下品下生(げぼんげしょう)では阿弥陀一尊だけが迎えにくる。この九通り(九品(くほん))は、それぞれ異なる印で表される。
その阿弥陀の世界を描いたのが阿弥陀浄土図で、8世紀初頭と思われる法隆寺壁画にもみることができる。その後9世紀~10世紀に天台宗を中心に阿弥陀信仰が高まり、平安末以後は阿弥陀一尊を信仰する浄土宗、浄土真宗が盛行する。
阿弥陀の手印には、弥陀の定印(じょういん)(禅定印。釈迦のとはやや異なる。上品の三印がこれに当たる)、釈迦と同じ説法印(中品の三印)、来迎の際の来迎印(下品の三印)がある。
阿弥陀像は釈迦像とまったく同じであるが、異例として五劫思惟(ごこうしゆい)阿弥陀像は、衆生を救うため長い間思索・修行を続けたので髪が伸び、頭部の螺髪が大きく張っている。天台宗の常行三昧(じょうぎょうさんまい)堂の本尊の阿弥陀像は宝冠を戴き髷(いただきまげ)を結い、衣の襟を頸(くび)まで詰めている。真言(しんごん)宗系の紅頗梨(ぐはり)阿弥陀像も宝冠と髷をつけ、朱色の衣を着た姿である。
[佐藤昭夫]
薬師如来
薬師如来は薬師(くすし)、つまり医薬に関する仏で、人間の心と身体の医者といえよう。仏教本来の悟りからは外れた現世利益(げんぜりやく)的な仏であるが、それだけに多くの信仰を集めている。薬師は東方浄瑠璃(じょうるり)世界の主で、そこにはつねに妙(たえ)なる音楽が流れている。音曲(おんぎょく)の浄瑠璃の語源もここにある。この仏は如来のうちでただ一例、手に持物(じもつ)(薬壺)を持つ。普通は左手だが、右手に持つものもあり、奈良・平安期の古い像では薬壺を持たないものもある。三尊形式では日光(にっこう)・月光(がっこう)の両菩薩を左右に配するほか、十二神将という武装神を守護神として配することがある。
[佐藤昭夫]
弥勒如来
弥勒は半跏(はんか)思惟の菩薩としてつくられることが多いが、如来形で表されることもある。釈迦の滅後56億7000万年(または76億5000万年)後にこの世に降(くだ)り、釈迦の救いに浴さなかった人々を救ってくれる仏で、その際には釈迦と同じ如来の姿となるが、それまでは兜率天(とそつてん)で、いかに人を救うかを考えている。これが弥勒菩薩半跏思惟像である。この姿はインドや中国では太子(釈迦)思惟像とされたが、朝鮮に入って新羅(しらぎ)や百済(くだら)で弥勒信仰が高まり、弥勒思惟像として日本へ伝わった。わが国の古代の弥勒像はほとんどが菩薩半跏像であるが、鎌倉時代に入ると如来像として信仰されることが多くなる。これは一日も早い弥勒の下生を待ち望む人々の願望の結果といえよう。弥勒の手印には特定のものはなく、釈迦と同じ施与(施無畏与願)印か、降魔印または他の印をとることもある。
[佐藤昭夫]
盧遮那仏
前記の仏たちののちに考え出された仏で、この世に釈迦が出現したように、他の世界でも釈迦が現れてその世界の人々を救う。その世界は無数にあり、釈迦もまた無数である。これら多くの釈迦とその世界を統合するのが盧遮(舎)那仏だとされる。東大寺の盧舎那仏(大仏)はよくそれを示しており、蓮華(れんげ)座の蓮弁は千葉あり、一葉が一つの世界で、それぞれに釈迦がいる。それをつかさどるのが大仏である。これは『華厳(けごん)経』や『梵網(ぼんもう)経』に説かれている仏教における壮大な宇宙観を示している。
[佐藤昭夫]
大日如来
こうした盧遮那仏に対する考え方をそのまま密教のうえに移したのが大日如来で、曼荼羅(まんだら)の主尊であり、いわば宇宙の中心となる仏格である。別名摩訶毘盧遮那(まかびるしゃな)如来といい、「摩訶」とは大という意味で、密教における盧遮那仏ともいえる。
大日如来の姿・形は普通の如来と異なり、頭上に宝冠、胸や手足に豪華な飾りをつけ、後述する菩薩とまったく同じ姿である。大日如来が普通の如来とは違った如来、つまりキング・オブ・キングズの意味もあるようだが、その起源からはもうすこしむずかしい理由があると思われる。
密教の宇宙観を図化した曼荼羅に「金剛界(こんごうかい)曼荼羅」と「胎蔵界(たいぞうかい)曼荼羅」の2種があり、もともと前者は『金剛頂経(こんごうちょうぎょう)』、後者は『大日経』という異なった典拠によって成立しているが、この二つは表と裏、陰と陽、因と果という二つの対立概念を示しており、それぞれの中心に大日如来が存在する。金剛界の大日如来は智拳(ちけん)印を結び、これは行動の直前の姿である。胎蔵界の大日如来像は、膝(ひざ)の上で法界定印という坐禅の形をとる。
[佐藤昭夫]
菩薩
菩薩は菩提薩埵(ぼだいさった)bodhisattvaの略で、如来となるために「道を求め、修行している者」の意。如来を中心の仏とすればそれを助ける者、如来が教理を説く者とすればその実践面を担当するのが菩薩である。いわば次の時代に如来となるべき者と考えてよいだろう。
菩薩は釈迦が出家する以前の王子の姿によっている。釈迦は成道して如来になったが、それ以前は菩薩であったとされるからである。菩薩の頭部は螺髪ではなく、普通の髪で髷(まげ)(宝髻(ほうけい))を結い、余った髪を肩に垂らしている(垂髪(すいはつ))。宝冠のほかに首飾り(胸飾(きょうしょく))をつけ、それには房が垂れており、これを瓔珞(ようらく)という。上半身はほとんど裸形で、左肩から右脇腹(わきばら)にかけて条帛(じょうはく)、肩から両腕を通して両裾(すそ)へ天衣(てんね)という帯状の布帛(ふはく)をつける。腰には裳(も)というスカートのようなものをはく。これはインドの貴人の姿である。またこの菩薩に属するものに地蔵があるが、これは比丘形(僧形)で表される。
菩薩は独尊としても礼拝されるが、如来を中心に両脇に侍して安置されることも多い。中央にあるものを中尊、それに侍するものを脇侍(わきじ/きょうじ)といい、普通は三尊一組のものが多く、如来と菩薩の組合せは、例外もあるがほぼ一定している。中尊の名が不明でも脇侍像によって推定することができる。その代表的な組合せは次のとおりである。
釈迦如来・普賢(ふげん)菩薩、文殊(もんじゅ)菩薩
阿弥陀如来・観音菩薩、勢至菩薩
薬師如来・日光菩薩、月光菩薩
弥勒仏・法音輪(ほうおんりん)菩薩、大妙相(だいみょうそう)菩薩
盧遮那仏・観音菩薩、虚空蔵(こくうぞう)菩薩
[佐藤昭夫]
観音菩薩
正しくは観世音(かんぜおん)菩薩といい、菩薩のなかでもっとも信仰を集めている。観音像は宝冠や額(ひたい)の上に標識として小さな阿弥陀像をつけ、蓮華を持つことが多い。観音にも多くの種類があるが、その根本となるのが聖(しょう)(正)観音で、奈良時代以前は頭部1、手足2本ずつの普通の人間の姿であったが、衆生を救うために多くの能力や力を必要とするとされ、密教のなかから多面多臂(ためんたひ)の像が考え出された。その代表的な例が千手(せんじゅ)観音や十一面観音である。こうした多面多臂の観音はすでに奈良時代からつくられ始めており、法隆寺の壁画にも十一面観音が描かれている。これらは聖観音が変化した形というので変化(へんげ)観音とよばれ、33あるいは108種類もあるという。
千手観音はまさにその能力の直接的な表現で、頭上に10ないし11の菩薩頭部をつけ、1000本の手をもち、その一つ一つに眼(め)があり、千手千眼(げん)観音ともいう。1000本の手をつけるのは彫刻の造形バランス上むずかしいので、省略して42本として表現することが多い。合掌する手は観音本来のもので、その他の40本の1本ずつが25本分に相当する。唐招提寺(とうしょうだいじ)金堂の千手観音像は実際に1000本の手をつけた例で、九百数十本が現存する。千手観音には眷属(けんぞく)として二十八部衆、風神・雷神を付属することが多い。
千手観音と同様に頭上に菩薩頭部をつけているのが十一面観音である。普通、髻(もとどり)の上部に如来頭部を配し、髻の周囲に菩薩頭部を置く。頭上に10面をつけ、本当の顔(本面(ほんめん))とともに11と数えるものと、頭上だけに11面を配するものとがある。このほか、二十五面観音の例や、法隆寺の唐伝来の九面観音もある。また滋賀・渡岸寺(どうがんじ)像のように本面脇に1面ずつ、頭上に8面の変則的な例もある。
如意輪(にょいりん)観音は、平安期以後、密教とくに真言宗で重要な像とされ、6本の手があり、その1本に如意宝珠(にょいほうじゅ)を、別の手に法輪(ほうりん)を捧(ささ)げ、右の脚を立て膝(ひざ)にした坐像で表現される。如意宝珠も法輪も仏教のシンボルで、法輪は投げて使う武器で、一つの力の表現である。奈良時代には二臂半跏坐の像もつくられた。
不空羂索(ふくうけんじゃく)観音は、手に羂索という一種の綱を持ち、この綱で苦界に沈む多くの人々を救う。その姿は経典によって異なるが、一般的には三眼六臂の像である。肩に鹿皮(しかがわ)をまとっていることから春日(かすが)の鹿になぞらえ、春日神社の本地仏(日本の神はインドの仏の変化だとする説で、そのもとになった仏をいう)が不空羂索観音だとされ、藤原一族の守護仏として尊崇された。
馬頭(ばとう)観音は、後世、馬の安全祈願や馬の供養のために祀(まつ)られるが、もともとは馬のような強大な力を発揮する菩薩である。ヒンドゥー教の最高神ビシュヌの馬に化身する説話などが仏教にも取り入れられたものであろう。この観音が、慈悲を主張する菩薩のうちただ一つだけ忿怒(ふんぬ)の形相をしているのは、もともと明王像として成立したのが、観音に転化したためである。
[佐藤昭夫]
勢至菩薩
観音と同じく阿弥陀の脇侍として、観音が向かって右(左脇)にいるのに対し、向かって左(右脇)に控える。姿形は観音に似ているが、観音が頭上に小さな阿弥陀像(化仏(けぶつ))をつけるのに対し、勢至菩薩は水瓶(すいびょう)をつけていることが多い。勢至は観音と違って独尊で信仰されることはきわめてまれである。
[佐藤昭夫]
普賢・文殊菩薩
この2菩薩は釈迦如来の脇侍として、蓮華座上に立ったり座ったりしている。普賢は白象に乗り、文殊は獅子(しし)の上にいることも多い。『法華経(ほけきょう)』によれば、普賢菩薩は六牙の白象に乗って東方からきたり、法華経信者を守護するといわれる。その法華経は女人往生を説くので、普賢菩薩は女性のための仏として独尊でも信仰された。十羅刹女(らせつじょ)という10人の女神を従えたものもある。普賢菩薩の変化として二臂あるいは二十臂で、一身三頭の象に乗る普賢延命菩薩があるが、その下には輪宝があり、これを500頭の象が支えている。
文殊菩薩は俗に智慧(ちえ)の文殊といわれ、理性をつかさどる。文殊像は、獅子に乗り4人の従者を従え、海を渡ってくるという渡海文殊像が多い。また文殊の穢(けが)れのない理性を象徴して童子の姿、すなわち稚児(ちご)文殊としてつくられることも多く、さらに聖僧(しょうそう)文殊といって老僧の姿でもつくられる。文殊像は頭の髻の数によって一髻(けい)、五髻、六髻、八髻文殊がある。持物は剣と経巻を納めた箱(梵篋(ぼんきょう))で、梵篋を蓮(はす)の花の上にのせて持ったり、剣のかわりに金剛杵(こんごうしょ)という武器を持つこともある。いずれも智慧のシンボルである。
[佐藤昭夫]
日光・月光菩薩
この二尊は薬師如来の脇侍で独尊は少ない。他の菩薩との区別はむずかしいが、蓮華を持ち、花の上に日輪(にちりん)・月輪(がちりん)を置くこともあるが、かならずとはいえない。
[佐藤昭夫]
弥勒菩薩
菩薩形で表された弥勒像で、半跏思惟像が多いが、普通の菩薩坐像の形をとり、手に弥勒の象徴とされる塔をのせている例もある。
[佐藤昭夫]
地蔵菩薩
僧形で袈裟(けさ)を着けているものもある。釈迦滅後、弥勒出現までの長い末法の時期に衆生を救う役目をもつとされ、大衆の信仰を集めている。その救いは信仰を知らない子供にも及ぶので、子供の守護仏でもある。さらに地獄や六道(ろくどう)という恐ろしい世界から人々を救うのが六道地蔵、六地蔵で、これが転化して道案内、道しるべとしての辻(つじ)の地蔵となる。鎌倉時代以後は閻魔(えんま)王と同体とされ、閻魔十王といっしょに造像されることが多い。その形は平安時代までは左手に宝珠、右手は下げて掌を見せる像がほとんどだが、鎌倉以後になると右手に錫杖(しゃくじょう)を持った像が多くなる。珍しい例だが、奈良・長谷寺(はせでら)の十一面観音像は地蔵との合体像といわれ、右手に錫杖を持つ。
[佐藤昭夫]
虚空蔵菩薩
名のとおり虚空の神格化で、姿や持物は一定しない。空に対する信仰として、北斗星の神格化である妙見(みょうけん)菩薩がある。
[佐藤昭夫]
明王
明王像はインド古来のバラモン教の神々を吸収したもので、のちに密教の重要な像となった。非常に強い力をもち、忿怒(ふんぬ)の形相で悪を打ち砕く仏の使者である。如来はあるときは優しい菩薩として衆生を済度し、ある場合は明王のように恐ろしい姿で威力によって仏法に導くという。多面多臂、多眼多脚の怪奇な姿の像がほとんどである。
[佐藤昭夫]
不動明王
不動明王のみ人間と同じ姿で、右手に倶利迦羅剣(くりからけん)を持ち、左手に羂索を握る。背中には火焔(かえん)をかたどった光背を負い、岩石上か、岩を象徴化した瑟々(しつしつ)座にのる。平安初期には坐像が多いが、中期ごろから立像もつくられている。上半身裸形、腰に布を巻くだけの姿で、インドの奴婢(ぬひ)、奴隷の姿からきている。
[佐藤昭夫]
降三世明王
三面八臂、足下に男女の像を踏む。これはヒンドゥー教のシバ神(大自在天(だいじざいてん))とその妻烏摩(うま)で悪の象徴である。不動明王はこのシバ神が仏教に取り入れられたものだが、ここではシバ神は逆に征服された形になっており、これは、これらの神格が仏教に取り入れられた時期や思想の相違による。8本の手のうち6本は弓、矢、剣などの武器を持ち、他の2本は胸前で小指を絡ませる合掌印を結んでいる。
[佐藤昭夫]
軍荼利明王
三眼八臂、すさまじい形相で、両腕、両脚に蛇を巻き付けている。
[佐藤昭夫]
大威徳明王
牛に乗り、六足尊(そくそん)といわれるように、六面、六臂、六脚の像。通常は座した牛の上に座るが、疾駆する牛の上に片脚で踊るように立つ像もある。
[佐藤昭夫]
金剛夜叉明王
三面六臂で、正面の顔は五眼である。
以上の五体は不動明王を中心に五大明王(五大尊)ともいわれ、護国の尊像でかつ個人の身を護(まも)り、悪魔を退散させる現世利益の神として広く浸透した。平安・鎌倉期にはお産のときに五大明王に加持祈祷(かじきとう)して安産を祈った。
[佐藤昭夫]
愛染明王
その名や弓矢を持つ姿から西欧のキューピッドと同じ役柄と誤解されがちだが、実は逆で、修行の妨げとなる愛欲を抑えて、浄菩提心、つまり清く正しい心に変えさせる力をもつ。身色も円光背も真紅、頭上に獅子冠を戴き、六臂である。平安中期から信仰が高まったが、遺品は鎌倉以後に限られる。
[佐藤昭夫]
孔雀明王
明王のうちではもっとも早く成立し、日本でも奈良時代に造像された。悪虫、毒蛇を食う孔雀の神格化で、その力が悪魔降伏(ごうぶく)に役だつと考えられた。羽根を広げた孔雀の座に座す姿で、優しく、菩薩のような姿は明王像としては珍しい。
[佐藤昭夫]
天部・神将
天部・神将像は仏教成立以前からあったインドの他宗教の神々を吸収したもので、自然神が多い。帝釈天(たいしゃくてん)(雷神インドラ)、梵天(ぼんてん)(宇宙最高原理をつかさどる神ブラフマー)、吉祥(きちじょう)天(福徳の女神)、弁才天(海の神で音楽・福徳の女神)などがあり、四天王、十二神将もこれに属する守護善神である。天部像には俗形、武装、冠や冑(かぶと)を戴くものなど、種類が多く、服装・姿態もまちまちで、仏像のうち女性像があるのはこの天部像だけである。神将像は多く武装で忿怒像が多い。このほか鬼神像(天竜八部衆(てんりゅうはちぶしゅう)など)、力士形(金剛力士など)、童子形(不動明王に従う制吒迦(せいたか)童子・矜羯羅(こんがら)童子など)もこれに含まれる。
[佐藤昭夫]
比丘
比丘は頭を丸めた僧侶(そうりょ)の姿で、祖師、高僧像がほとんどだが、地蔵菩薩のように形のうえではこれに属するものもある。そのほか垂迹(すいじゃく)像といい、修験道(しゅげんどう)の尊像である蔵王権現(ざおうごんげん)とか僧形八幡(はちまん)神像のように、神仏混淆(こんこう)思想から生まれた像もある。
[佐藤昭夫]
姿勢と寸法による分類
仏像をその姿勢から大別すると、立像(りゅうぞう)、坐(ざ)像、臥(が)像がある。立像には直立像のほか、遊行(ゆぎょう)像(片脚を一歩前に出し歩行の形をとる)、蹴立(しゅうりつ)像(邪立(じゃりつ)像ともいい、一方の脚を蹴上(けあ)げた形で、明王像、天部像に多い)があり、坐像では結跏趺坐(けっかふざ)像(脚をあぐらのように組んだ形)がもっとも多く、左脚を上に組むのが降魔(ごうま)坐、右脚を上にしたのを吉祥坐という。半跏坐は弥勒菩薩などに多く、普通、左脚を踏み下げている。倚(い)像は腰掛けて両脚を下ろした形で、インド、中国には多いが、日本の仏像には少ない。下げた脚を交差したのを交脚倚像という。臥像は横臥した姿の像で、涅槃(ねはん)像に限られる。
経典によると仏の背の高さは一丈六尺(約4.8メートル)で、この寸法を基本とし、これを丈六(じょうろく)像といい、立像ではそのまま一丈六尺あり、坐像では半分の八尺の像を、立てば一丈六尺あるということから丈六像という。この丈六を何倍かにするとか、何分の1かにした寸法で像がつくられる。たとえば半丈六像といえば、立像八尺、坐像四尺の像をいう。このほか人間の等身に基準をとった立像五尺(約1.5メートル)、坐像二尺五寸(約76センチメートル)があり、特殊なものに約一尺二寸~一尺八寸(約36~54センチメートル)の一磔手半(ちゃくしゅはん)像(磔とは手首から肘(ひじ)までの寸法)、約三寸五分(約10.6センチメートル)の五指量(しりょう)像などがある。
[佐藤昭夫]
手印
仏教とくに密教では多くの像があり、それに応じて手印が規定されている。初めはさほど厳格ではなかったが、密教がヒンドゥー教の行事を取り入れて印契を重視するようになってから、細かく規定された。密教では数百の手印が記録されており、地域的にもインド、チベット、中国などで異なった印相が行われている。手印のおもなものは次のとおりである。
(1)阿弥陀の定印(じょういん) 阿弥陀如来の禅定印ともいう。右手を左手に重ね、人差し指を立て、親指をその指頭につける形。
(2)説法印(転法輪印) 法輪とは真理を意味し、これを転ずるというのは説法をすることである。
(3)来迎印(安慰印) 来迎の阿弥陀の印。左右逆の場合もある。
(4)阿弥陀の九品(くほん)印 人は生前の行いにより極楽往生の仕方に九通りあり、阿弥陀の迎え方も異なり、印の結び方にも前記(1)~(3)を基本とした九種がある。これが九品印である。
(5)施無畏(せむい)印 一切衆生(いっさいしゅじょう)のさまざまな恐怖をとどめ、そこから救済するという意味の印で、普通、与願印と組み合わせて用いられる。
(6)与願印 仏が大衆の求めるものを願によって施し与うることを表したもの。施無畏印とともに施願印、施与印という。
(7)法界定印(禅定印) 坐禅の際に結ぶ印。釈迦如来や胎蔵界大日如来に多い。阿弥陀の定印の指を立てない形。
(8)智拳(ちけん)印 金剛界大日如来の印。この印を結ぶと現世の煩悩(ぼんのう)を消して仏智に入ることができるとされる。
(9)合掌印 各種の合掌によってつくられるもので、金剛合掌、堅実合掌、叉手(しゃしゅ)合掌、帰命(きみょう)合掌などがある。
(10)降魔(ごうま)印(指地(しじ)印、触地(しょくち)印) 釈迦八相の一つである降魔、つまり釈迦が菩提樹下で悟りを開こうとしたとき、これを妨げようとした欲界の六天を降伏させたときの印で、日本では単独の像ではほとんどつくられていない。
[佐藤昭夫]
契印
手印と同様に持物にもそれぞれに意味があり、たとえば聖観音菩薩の蓮華は「大悲応物、不染不苦」を意味し、大慈悲の象徴である。また文殊菩薩は剣によってよく衆生の煩悩を取り除き、経巻は計り知れない智慧を意味している。そのほかおもなものをあげると、十一面観音の水瓶と蓮華、地蔵菩薩の宝珠と錫杖、鬼子母神(きしもじん)の吉祥果、火天の仙杖、千手観音の宮殿や武器、不動明王の剣と羂索、愛染明王の弓箭(きゅうせん)、多聞(たもん)天(毘沙門(びしゃもん)天)の宝塔など40種以上で、各尊によって持物が異なるので、それによって像が識別できる。
[佐藤昭夫]
仏像の制作
材料と技法
日本では大部分が木造だが、金属、乾漆(かんしつ)、塑土(そど)、石、まれには紙も用いられる。
[佐藤昭夫]
木造
ヒノキが圧倒的に多く、他の材は時代・地域によって使用の仕方に厚薄がある。飛鳥(あすか)・白鳳(はくほう)の7世紀にはクスノキが多い。天平(てんぴょう)の8世紀には乾漆、塑土が多く用いられ、木彫は少ないが、乾漆像、塑像の芯木(しんぎ)にはヒノキが用いられた。9世紀には木彫が造像の主流となり、ヒノキがおもに使われた。この時代には仏教が地方にも伝播(でんぱ)し、各地で特色ある材を用いた。関東・東北ではカツラ、ケヤキ、サクラなど、九州ではクスノキ、カヤが多い。珍しい材としては、南アジア産の香木、白檀(びゃくだん)や栴檀(せんだん)を用いた檀像がある。
木彫像には像の体躯(たいく)の中心部を1本の木でつくりあげた一木造(いちぼくづくり)と、2個以上の材をあわせてつくった寄木(よせぎ)造とがある。一木造でも、像の中心となる頭部・胴部以外の突出部、立像(りゅうぞう)なら腕、坐(ざ)像で腕や膝(ひざ)などは別の材を継ぐ。背部から内刳(うちぐり)といって像内を刳(く)り取り、背板という蓋板(ふたいた)を別につくって当てる。これは、木材の中心部をとらずに彫刻すると、芯部と表面との乾燥度の相違で干割(ひわ)れができ、像をだいなしにするからで、それを防ぎ、像の重量を軽減するためである。立像は背面から、坐像は背面や像底から刳るが、背面から刳る内刳をとくに背刳(せぐり)という。一木造は飛鳥期から平安期のなかばにかけて多くつくられた。
寄木造は頭や体部などの躯幹部を前後・左右2個以上の材を規則正しく継ぎ合わせて構成したもので、その先駆は1006年(寛弘3)作と推定される京都・同聚院の不動明王像である。これは躯幹を前後左右から箱のように材を組み合わせ、背面材はさらに左右に分かれ、内部には大きく内刳が施されている。寄木造は12世紀にさらに進んで、頭部と体部を別材でつくり、他は多くの材を組み合わせていっそう便化された。こうして、大像でも一木造のような巨材を必要とせず、深い刳りを入れることで重量を軽減でき、分業制作も可能になって、平安後期のおびただしい造像の注文にも応じられるようになった。このような寄木造の材の寄せ方の規則を木寄(きよせ)法あるいは寄木法とよんでいる。
木彫のもう一つの技法に割矧(わりは)ぎがある。一木造を制作する工程の途中で、像を前後または左右に鑿(のみ)で割り離し、内部に大きく刳りを施したうえでふたたびあわせて仕上げる。さらに頭部と体部とを離すのを割首とよぶ。割矧ぎは一木造と寄木造の中間的技法である。一木造の量感・質感をとどめたまま深い内刳ができるため、技術者を大量に動員できない地方の仏師にとっては便利な方法で、寄木造が盛んになった平安後期以後も長く利用された。
また12世紀なかばに、この寄木造の内刳を利用して、彫像の眼(め)に水晶を裏から当て、人間の眼のような輝きをもたせる玉眼(ぎょくがん)が考案された。
木彫像の仕上げには漆箔(しっぱく)、彩色、切金(きりかね)などの方法が用いられる。彫刻を終わった像の矧目(はぎめ)は細く溝を彫り、「こくそ漆(うるし)」(漆に木粉や抹香(まっこう)を混ぜたもの)を詰めて矧目を目だたなくし、上から麻布を漆ではり、砥の粉(とのこ)を混ぜた下地漆で布目をつぶし、砥石で研(と)ぎ上げたあと漆を何回か塗り、さらに漆で金箔をはるのが漆箔像である。彩色の場合には、下地に白土や胡粉(ごふん)を塗り、その上から彩色したり、金泥(きんでい)を全身に塗る。檀像やその風をまねた檀像様彫刻、鑿目(のみめ)を強調した鉈彫(なたぼ)り、立木仏(たちきぶつ)などでは、瞳(ひとみ)や眉(まゆ)、ひげに墨を、唇に朱をさし、あとは木肌のままとする。
また彩色の上に切金(截金)といって金箔の細線で文様を描き出す技法があり、金泥彩の上に切金を施すのは鎌倉初期の名工快慶が得意とした。盛り上げ彩色は仏像の衣に刺しゅうのような文様をつける技法で、胡粉で文様を盛り上げる。これには鎌倉地方で行われたような、粘土に膠(にかわ)を加えたものを型に入れ、花や葉、法輪などの文様をつくり、乾かないうちに仏像の衣の部分に漆で貼(は)り付ける土文(どもん)という技法もあり、鎌倉時代後半から南北朝・室町時代の像にその例がみられる。
[佐藤昭夫]
金属造
金、銀、銅、鉄を主とし、まれに真鍮(しんちゅう)像もある。技法的には鋳物(いもの)、打物(うちもの)(鍛造)、彫金がある。金仏は奈良時代には正倉院文書にみられ、藤原時代にもつくられた記録はあるが、現存するものはごく少ない。銀製の像は現存遺品では興福寺東金堂から発見された等身像と思われる仏像の腕、東大寺三月堂不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん)像の宝冠の化仏(けぶつ)など奈良時代のものや、滋賀・浄厳(じょうごん)院の阿弥陀如来(あみだにょらい)像(鎌倉時代)などだが、藤原時代にはその色調が珍重され、記録では銀仏のほうが金銅(こんどう)仏より制作の記事が多い。
銅製鋳物の像は普通、金鍍金(めっき)を施すので、金銅仏という。現在のブロンズに近い錫(すず)、鉛などとの合金で、その成分は一定しない。金銅仏の鋳造方法はおよそ二つに大別される。一つは蝋(ろう)型鋳物で、飛鳥・奈良時代の金銅仏はほとんどこれである。もう一つは木や土の原型から外型(雌型)をとる割込(わりこめ)型である。像内に空洞をとる場合は一回り小さい中型を入れ、両者の間に溶銅を流し込む。こうしてつくられた像は、鋳損じた部分を補修し、表面をきれいに鏨(たがね)で削り、磨き上げて水銀鍍金(アマルガムめっき)を施し、さらに髪、眉目、唇、衣などに彩色をする。ほかに原型の上に銅板を置いて槌(つち)で打ち出した押出仏(おしだしぶつ)が7、8世紀に流行し、鉄製鋳造の鉄仏も鎌倉時代以後の東日本に多い。
[佐藤昭夫]
乾漆造
漆を材料とした東洋独特のもので、日本には7世紀ごろ中国から技法が輸入された。乾漆像にも2種あり、一つは脱活(だっかつ)乾漆(脱乾漆)で、粘土で像のだいたいの形をつくり、その上に麻布を等身像で7、8枚漆で貼り重ね、形のできたところで内部の土を掻(か)き出し、空洞に木で骨組をつくり、表面にこくそ漆(うるし)を盛り上げ、漆箔や彩色をする。東大寺三月堂不空羂索観音像、興福寺の八部衆像や十大弟子像はこれである。他の一つは木心(もくしん)乾漆といい、木でだいたいの形をつくり、こくそ漆を盛り、細部の表現をする。なかには細部まで木で仕上げ、ごく薄くこくそ漆をかけた像もある。材料の可塑性が奈良時代の写実的作風と合致して流行したが、手間がかかり値段も高いのでしだいに衰えた。
[佐藤昭夫]
塑造
塑とは粘土のことで、土でつくった彫像の意で、奈良時代に流行した。広義には現在の石膏(せっこう)像も塑像の一種である。東洋では古くから用いられ、捻(ねん)、摂(しょう)、塑(そ)、素(そ)、泥(でい)などとよばれ、焼成しない土製像をさす。源流は西域(せいいき)にあるといわれ、敦煌(とんこう)や麦積山(ばくせきざん)の石窟(せっくつ)寺院に多くの遺品がある。日本には7世紀ごろ伝わり、奈良當麻寺(たいまでら)弥勒(みろく)如来坐像が完形のものの最古の例である。技法は芯木に藁(わら)や縄を巻き、粘土をすこしずつつけては乾燥させる。表面にいくにつれて土は細かいものを用い、粘着力を増すために膠(にかわ)や苆(すさ)を混ぜる。細部は麻布を巻いた針金を芯とすることもある。仕上げには彩色や漆箔をする。写実的表現に適するというので奈良時代には盛んにつくられ、法隆寺五重塔の塑像群、東大寺法華(ほっけ)堂の日光(にっこう)・月光(がっこう)両菩薩(ぼさつ)像と執金剛神(しっこんごうしん)像、戒壇院四天王像などの名作を残したが、他の時代にはほとんどなく、わずかに鎌倉時代の肖像彫刻に二、三の例があるにすぎない。こうした乾漆像や塑像には、後世の玉眼のように眼(め)に黒曜石やガラス玉をはめた例もある。
[佐藤昭夫]
石造
東洋諸地域にみられ、石窟内の壁面に彫られたものや岩壁を利用した磨崖仏(まがいぶつ)(摩崖仏)をはじめ、独立した石塊に丸彫り・浮彫りした像があるが、インドや中国に比べると、日本では彫刻に適する石材が乏しく、数も少ない。古代の石仏の多くは凝灰岩で、石肌に独特の美しさがあるが、耐久性には欠ける。最古の遺品に、7世紀後半の作と思われる、表情の愛らしい奈良・石位(いしい)寺の三尊像がある。8世紀では良弁(ろうべん)作といわれる奈良・頭塔(ずとう)石仏群が奈良風の典麗な浮彫りとして有名。平安時代になると北九州、北陸、関東などで磨崖仏がつくられた。とくに北九州一帯は阿蘇(あそ)の溶岩によって日本最大の石仏の宝庫となっている。なかでも大分県の臼杵(うすき)石仏は優秀な作例である。栃木県大谷(おおや)の石仏群は、凝灰岩の大谷石に浮彫りし、漆食(しっくい)で表面を仕上げたものである。鎌倉時代には、仏教の大衆化によって石仏造立は盛んになるが規模も小さく、丸彫り像が多くなる。鎌倉時代以後も日本全国にみられ、花崗(かこう)岩、安山岩、凝灰岩、砂岩などさまざまな石材を使用しているが、芸術的に目だつ作品は少ない。
[佐藤昭夫]
造仏の順序
仏像制作の順序は、木彫を例にとると次のとおりである。まず造像の願をたてた発願者は僧侶(そうりょ)と相談して仏師を決定する。仏師と経済的・技術的な打合せをするのを造仏支度(したく)という。次に材料を整えるが、木彫の材を御衣木(みそぎ)といい、高僧によって材や工具を清める御衣木加持(みそぎかじ)を行う。仏師が御衣木に最初の斧(おの)を下ろす儀式を斧始(おのはじめ)といい、材は仏師の仕事場である仏所(ぶっしょ)に運ばれて工事が開始される。その間、発願者ら関係者はしばしば検分といって立会い検査をする。藤原時代の貴族は感覚も優れていたから口やかましく欠点を指摘したという。できあがった像は仏所から寺へ運ばれ、予定の堂内の壇上に据えられる。これを奉渡、奉居という。そして荘厳(しょうごん)が施され、吉日を選んで像の眼に瞳をかき入れる開眼(かいげん)供養が行われる。わが国最大の開眼供養は752年(天平勝宝4)4月の東大寺金堂盧舎那(るしゃな)仏(大仏)の開眼会(え)で、参集の供養僧一万といわれる。
造仏あるいは修理の際、像身や付属物の一部に造立や修理の次第、仏師や発願者名、年紀などを記したものを造像銘といい、造像の直接的資料として重要である。その形式はさまざまで、造像経過や経文などを記したものもあれば、ごく簡単な年紀のみの場合もある。記入の場所は、金属像や石像では仏身の背面や光背(こうはい)裏、台座などの外面に陰刻または陽刻する。木彫では胎内、台座内部、蓮弁(れんべん)裏、光背裏、足枘(ほぞ)などに墨書または朱書する。また仏像の胎内には小仏像(胎内仏)、経巻、銘札をはじめ故人の遺品など、さらに五穀や鏡などさまざまな納入品を納める場合がある。
なお、仏像や仏堂を装飾することを荘厳といい、その用具を荘厳具という。これには直接仏体につける身(しん)荘厳と、仏体から離れた荘厳がある。また仏の身体から発する光を形象化したのが光背で、完備した仏像にはかならず光背が付属する。光背は厳密には荘厳具ではないが、造像法からは荘厳具に含めて考えられる。
[佐藤昭夫]
『望月信成・佐和隆研他著『定本仏像――心とかたち』(1971・日本放送出版協会)』▽『南日義妙著『仏像をたずねて――日本仏像百科事典』(1972・文進堂)』▽『久野健編『仏像事典』(1975・東京堂出版)』▽『佐藤昭夫著『仏像をみる人のために』(1979・玉川大学出版部)』▽『町田甲一著『仏像――その意味と歴史と美しさについて』(1979・実業之日本社)』▽『杉山二郎著『仏像』(1984・柏書房)』▽『久野健編『仏像集成3 日本の仏像』(1985・学生社)』▽『久野健編『東洋仏像名宝辞典』(1986・東京堂出版)』
改訂新版 世界大百科事典 「仏像」の意味・わかりやすい解説
仏像 (ぶつぞう)
定義
仏教において主として礼拝の対象とされる彫刻や絵画による形像。一般的には彫像のみを指すことが多く,絵画によるものは仏画と呼んで区別する。仏画についてはその項を参照されたい。また仏陀の像のみを指す場合と,仏教の尊像すべてを総称して仏像と呼ぶ場合とがあり,前者を仏陀像,後者を仏教像として区別する必要がある。仏陀像は元来は仏教の開祖である釈迦仏に限られていたが,やがて過去仏や千仏の思想を生み,大乗仏教では阿弥陀,阿閦(あしゆく),薬師,毘盧遮那(びるしやな),大日(だいにち)などの仏陀(如来ともいう)が考え出された。また密教独得の特殊なものとして仏頂尊勝や仏母の信仰がある。菩薩とはもともと釈迦の成道(じようどう)以前(悟りを開く以前で,前世をも含む)の呼称で,大乗の菩薩と区別して釈迦菩薩と呼ぶこともある。将来に仏陀となる弥勒(みろく)菩薩の起源は古く,大乗仏教では観音,勢至(せいし),文殊,普賢,日光,月光,地蔵など,密教では金剛薩埵(さつた),五秘密,普賢延命,准胝(じゆんてい),多羅,虚空蔵などの多数の菩薩を生んだ。また不動その他の明王は忿怒(ふんぬ)の形相をした密教特有の尊像で,発生的にはヒンドゥー教のシバ神と密接に関連する。また,古くから仏教にとり入れられたインドの神々など仏法を守護する異教の神々を天と総称し,梵天,帝釈(たいしやく)天,吉祥(きつしよう)天,弁才天,竜王,夜叉,訶梨帝母(かりていも)(鬼子母(きしも)神),摩利支(まりし)天,大黒天,聖天など,また四天王,八部衆,十二天などの一群の神々がある。このように仏教尊像を日本では仏(如来),菩薩,明王(みようおう)(忿怒),天部と分類し,さらに星宿,鬼神の類,神仏習合による垂迹(すいじやく)神,羅漢や高僧をも加える。
起源
仏像は仏教徒の礼拝対象であるから,仏教の歴史の最初から仏像があったと考えられがちであり,〈釈迦在世中にウダヤナUdayana(優塡(うでん))王が栴檀で造ったのが最初の仏像である〉と記す仏典もある。しかし,ヤクシャ(薬叉,夜叉),インドラ(帝釈天),ラクシュミー(吉祥天)などのインドの神々は仏教の守護神として紀元前から製作されているが,仏陀像はもとより菩薩や高僧の像も釈迦の死後数百年間は表現されず,信者が礼拝対象としたのは釈迦の遺骨を納めたストゥーパであった。また釈迦の事跡を描いた仏伝図では,菩提樹,台座,足跡,法輪その他で仏陀の存在を示唆するという不便な方法をとり,主役の仏陀を表現することはまったくなかった。この伝統を破ってはじめて仏陀の姿を表現したのは,紀元後100年ころにガンダーラ地方において,次いでマトゥラーにおいてであった。古くから守護神像を製作していたのであるから技術的に仏像を表現できなかったのではなく,なんらかの理由で製作するのを避けていたに相違ない。またそのような強い制約を破って仏像製作にふみきったのも理由あってのことと思われる。なぜ仏陀の姿を表現しなかったのか,またなぜ表現するようになったかについては,さまざまな説が出されているが,まだ満足な答は得られていない。ただ仏像が出現した北西インドで同じクシャーナ朝時代に大乗仏教の興起をみたことから,仏像の出現に大乗仏教が関与したことが古くから説かれ,近年あらためて仏教史の立場から強く主張されている。しかしながら遺品によってこれを証明することはできず,一般に美術史家はこの説に否定的である。いずれにしろガンダーラ美術はヘレニズムやイラン文化などのさまざまな西方の文化の影響を受けて発生し,それらにおける神像製作が仏像出現の一因となったことは疑い得ない。通説では,仏陀の像はまず仏伝図浮彫に仏弟子や信者と同じ大きさに表現され,しだいに仏陀のみが大きく示されるようになり,やがて単独の仏陀像が出現したとされる。
初期仏像の様式
初期のガンダーラ仏は,カールした長髪を頭上で束ねた肉髻(につけい),西洋人風の容貌,両肩を覆う(これを通肩(つうけん)という)厚手の衣に深く刻まれた襞(ひだ)などを特色とし,表現は具体的・現実的な傾向が強い。一方,初期のマトゥラー仏には外来の表現技法の影響は認められず,純インド的な美意識に基づき,巻貝形の肉髻,野性的な風貌,右肩を露出した(偏袒右肩(へんだんうけん)という)薄手の衣などを特色とし,観念的な理想美を追求している。クシャーナ朝時代にはガンダーラ地方とマトゥラーとで仏像製作をほぼ独占し,像容・表現ともにまったく異なっていた両者もやがて互いに影響しあい,3世紀になると頭髪を螺髪(らほつ)とするものが出現し,仏陀像の基本形ができあがった。
仏陀像はほとんどが釈迦像で,クシャーナ朝時代でも少し時期が遅れると阿弥陀のような大乗の仏陀も造像された。ただし釈迦像と他の仏陀とでは像容に差がなく,刻銘によってはじめて尊名を判定しうる。また仏陀像とともに菩薩像も造られるようになり,多数の遺例があるが,刻銘からその名が知られるのはごくわずかである。通例さまざまな装身具をつけていて,当時の貴人の姿を写したと考えられている。図像上の特徴から尊名を判別しうるのは,弥勒(みろく)と観音ぐらいで,仏陀像と同様に種類は少ない。水瓶(すいびよう)を持つ菩薩を弥勒とするならばその例はかなり多い。また蓮華または花綱を持つ菩薩を観音とすると,その例も少なくないが,中国や日本で観音の標幟とされている宝冠に化仏(けぶつ)をいただくのはごくわずかである。仏陀像にせよ菩薩像にせよ,まだその図像は定型化されるに至らなかったとはいえ,クシャーナ朝時代にその基本形は成立していた。そして,仏教徒の礼拝対象として仏像の製作は活発化の一途をたどり,仏教の流布するところには仏像も伝えられ,アジアの各地で独自の展開を遂げたのである。
造像の展開
インド
ガンダーラ地方とマトゥラーとで造りはじめられた仏像は,すでに2世紀後期には南インドのアーンドラ地方に伝えられ,まずアマラーバティーで,次いでナーガールジュナコンダで製作がさかんとなった。グプタ朝の北インド征服が完成したチャンドラグプタ2世(在位376ころ-414ころ)の治世に,一時停滞していた北インドの造形活動はふたたび活況を取り戻し,やがて洗練された技法により均整のとれた崇高な美しさをそなえた仏像を生み出すようになった。ストゥーパに従属していた仏像が,本尊としての地位を獲得するようになったのもこの時代である。グプタ様式の造像は帝国の領域内のみならず,同盟関係にあったバーカータカ朝治下のアジャンターなどデカン北部にも及んだが,その中心はマトゥラーとサールナートで前者は5世紀前期から中期に,後者は5世紀末期に最盛期を迎えた。この両者の作風はインドはもとより東南アジアや中央アジアにも多大の影響を及ぼした。
グプタ朝時代以後は仏教の衰退とともに表現もしだいに形式化し,力の充実した作品は少なくなる。しかしパーラ朝時代には密教が隆盛し,多面多臂像や忿怒像が生まれ,尊像の種類が格段に増加した。それにともなって図像が整備され,造像法が定式化した。1200年前後の仏教の滅亡とともに,インドにおける仏像製作も幕を閉じる。インドの造像活動の担い手は俗人であり,密教の場合を除けば仏像製作に比丘はあまり関与しなかったようにみえる。個々の美術作品が大乗および小乗のいずれに帰属するかは明らかにしがたく,通仏教的なものが大多数であることもそのことを示している。なお造像の用材は石が主体で,塑像,テラコッタ像,金属像もあるが,木彫像はまったく遺っていない。
スリランカ,東南アジア
仏教の東南アジアへの伝播にともない,この地域でも仏像製作が一般化し,初期にはインドの影響が強いが,やがてそれぞれの民族的性格が顕著になり,独自の作風を形成した。スリランカでは4世紀ころからインドのアーンドラ様式の影響下に仏像製作がはじまった。偏袒右肩にまとった衣が体に密着し,衣の全面にほぼ等間隔に陽刻線による襞を密集させるのが特色である。ポロンナルワでは12世紀に巨大な磨崖(まがい)像が造られた。13世紀以後は石にかわってブロンズその他の金属像が多くなり,襞はこまかく波打ち,頭上に火焰形をいただくようになり,形式化が進んだ。小乗上座部系の仏教が優勢であったため釈迦像が主体であるが,観音などの大乗の菩薩像や密教系尊像もある。
ビルマ(現,ミャンマー)ではパガン朝(1044-1287)治下に造形活動が最も隆盛した。この王朝の諸王は小乗仏教の信奉者で,仏像は釈迦仏か過去四仏に限られ,インドのパーラ様式を踏襲している。
タイでも小乗上座部仏教が主流を占める。まずドバーラバティ時代(7~11世紀)にはインドのサールナート系の衣が薄くて透けるような仏像を遺し,スリウィジャヤ国の支配下にあった南部では8~9世紀にきわめて洗練された大乗の菩薩像を造った。11~13世紀には中部や東部でクメール族による造形活動がおこなわれた。13世紀以後のタイ族の支配期には民族的要素を濃くしてゆくとともに,しだいに生気に乏しいものとなった。
カンボジアではクメール族の卓越した芸術的天分によって先アンコール期(5~8世紀),アンコール期(9~15世紀)にヒンドゥー教美術が盛行し,仏像にも少数ながら秀作を遺している(アンコール朝)。特にローケーシュバラ(観音)信仰に基づく菩薩像が注目され,仏陀像はとぐろを巻くコブラに座る形式が多い。ラオスやベトナムには見るべき遺品は少ない。
東南アジアの仏教彫刻で最も評価の高いのはインドネシア,ことに中部ジャワのそれである。中部ジャワでは大乗仏教徒であったシャイレンドラ朝の諸王によって8~9世紀に造形活動は頂点に達し,典雅で迫力のある彫刻を生んだ。なかでもチャンディ・ムンドゥットの本尊である高さ約3mの仏倚座(きざ)像とその脇侍(きようじ)菩薩は均整のとれた体軀に力がみなぎり,東南アジアの仏像の最高傑作と称賛され,その外壁の密教系の浮彫菩薩像もすぐれている。またボロブドゥールにはもともと504体もの傑出した等身大の仏座像があり,回廊壁面の長大な浮彫の芸術性の高さも注目される。13世紀以降東部ジャワでヒンドゥー教と仏教とが混合して特異なシバ・ブッダ信仰を生んだが,芸術的香気は失われてゆく。
中央アジア
仏像伝播の第2のルートは,北西インドから中央アジアを経てさらに東方に伸びるそれである。中央アジアでの仏教の造形活動は2世紀から9世紀に及び,この地が東西文化の交流の舞台であったためにイランをはじめとして西方の諸文化が流入し,さらに唐代には中国の影響も濃くうかがえる。彫刻はこわれやすい塑像が主体であり,過酷な自然条件に加えて人工的な破壊もあって遺品は少ない。まずアフガニスタン東部はガンダーラ文化圏に属し,まず石彫が,次いで塑造彫刻が栄えた。ヒンドゥークシュ山中のバーミヤーンでは巨大な磨崖仏が造られ,フォンドゥキスターンやタパ・サルダールの塑造美術はアフガニスタン仏教美術の末期を代表し,中央アジア的な性格を濃くしている。
西トルキスタン(ソ連領中央アジア)では近年急速に発掘が進んでいるものの,未解明なところが少なくない。オクソス川(アム・ダリヤ)北岸のカラテペやファヤズテペではクシャーナ朝治下の2~4世紀に石灰岩や塑土を用いてガンダーラ風の仏像が製作された。7~8世紀のアジナテペやクバ出土の塑造彫刻はアフガニスタンの末期のそれと共通するところが多い。
東トルキスタンでは天山南路の南北両道沿いに遺跡が点在し,北道では石窟が開かれたが,岩山のない南道では寺院は煉瓦や木で造られた。その北道の石窟でも礫岩質のもろい石質のゆえに石彫は発達せず,塑造を主体とし多くは彩色がほどこされ,金属製や木造のものもある。南道ではホータンにおいてクシャーナ朝が北西インドから勢力を伸長させたとき仏教の造形活動がはじまった。大谷探険隊が将来した金銅仏頭(3~5世紀)は中央アジアでは最も早期の遺品の一つで,パキスタン北部のスワート地方の石仏との類縁が指摘されている。またラワクのストゥーパ外壁を飾っていた80体以上の塑像群にはガンダーラ,マトゥラー,さらにはイラン的な要素も認められる。南道の東端に位置するミーラーンの第2古址の塑造仏座像にはインドのグプタ様式を思わせる豊かさがある。北道のトゥムシュク遺跡の塑像は額が広く目鼻口が中央に寄った顔貌に特色があり,洗練された造形感覚を示す。北道のほぼ中央部のクチャ地区のクムトゥラ石窟の塑像には美しい彩色が遺り,インドやイランの作風のみならず中国の唐様式も看取しうる。東に進んでショルチュク,さらにカラホージョの塑像も時代が下るとともに唐様式が濃厚になる。
ラマ教圏
インドにおける末期の仏教,ことに密教はネパールからチベットに伝えられてラマ教を生み,さらにモンゴルや満州へと広まり,日本の密教とは別個の系統を形成する。本初(ほんじよ)仏(アーディ・ブッダĀdi-buddha)から五仏が生じ,さらにそれからあらゆる仏,菩薩,明妃(みようひ),護法神が流出するという膨大な数の尊像の体系をつくりあげた。ヤマーンタカのような怪異な忿怒像,ヤブ・ユムと呼ばれる男尊と女尊の抱合像が特に多い。ネパールから中国北部にかけて多数の青銅像が分布し,ことに清朝のそれは図像学的に重要である。しかし多くは形式化し芸術性に乏しい。
執筆者:肥塚 隆
中国
中国はインドとはまったく異なる文化的伝統を保持する国だけに,そこに入った仏教が変容を余儀なくされたことは当然であり,仏像の表現にもそれが及んだ。しかし,最も古いと考えられる遺品にはインド的な要素の残存が大きく認められる。中国における造像は,文献的には,2世紀後半にはじまる。1980年代に入って,江蘇省連雲港市の孔望山漢代磨崖像中に仏像および仏伝の表現が認められ,それらが後漢末,つまり2世紀後半の作品という説が出された。それより前,四川省楽山県麻浩崖墓出土の浮彫断片,同省彭山県崖墓出土の陶片,古越磁で神亭と呼ばれる種類の壺などに付された貼付文様,そして三角縁仏獣鏡など3種の鑑鏡類が後漢末から東晋の仏像表現の例としてあげられている。4世紀になると銅造菩薩立像(京都,藤井斉成会)をはじめいくつかのガンダーラ風の金銅仏の存在が知られ,なかでもサンフランシスコ・アジア美術館蔵の銅造如来座像は後趙の建武4年(338)の銘をもち,ガンダーラ風を基にした中国化の様式が認められる。このころ敦煌に莫高窟が開窟され,以後中国では石や銅をおもな材料とする単独像と,石窟や磨崖の造像が盛行する。その最盛期は南北朝の北魏に代表される5世紀末~6世紀初期と,唐代の盛時7世紀末~8世紀前期を中心とする時期であろう。質・量ともに特筆すべきものがあり,特に前者は,これまでのインド的な肉体と衣服の表現における写実から,漢文化の伝統である形象主義的な服制と威容の表現に仏像を変容せしめたことが注目され,後者は仏像に内在する理想像の追求と人体の写実との調和を実現した点に意義がある。
石窟造像でその代表的な例を示せば,前者では雲岡石窟のいわゆる曇曜五窟と竜門石窟の賓陽中洞,後者では奉先寺洞を中心とする竜門の唐代窟であろう。また唐代造像の写実的な傾向は塑造や乾漆造の技法によって助長された。塑造技法は仏像東漸の早くから石窟造像に用いられ,乾漆は木彫技法とともに南北朝時代の江南に文献上の例を認めうる。これらの技法は石彫や鋳造の技法とともに以後も用いられ,仏像の表現自体は唐代後半の密教尊像や,五代と遼それぞれの地域的な変化などに対応する特色あるものを生んだが,全般的な宗教美術の低調による形式主義と,現実的な世相を反映した写実主義によって質の低下をきたし,ふたたび唐代の造形的高さを生むに至らなかった。
朝鮮
朝鮮半島に仏像が伝来したのは4世紀後半で,北部の高句麗にはじまり,百済,新羅の順と考えられているが,あまり明確にすることはできない。遺品の上で最も古いと考えられるのは延嘉7己未年(539?)の韓国国立中央博物館所蔵の銅造如来立像をはじめとするいくつかの小金銅仏である。これらは銘品をまじえるものの,それが干支だけであったり,ほかに確かめられない年号であるため,年代決定に問題を残している。しかしそれらの表現は中国の6世紀初めの作風を受けるもので,高句麗は北魏との,百済は南朝の宋との関係を歴史・地理的に想定されているが,いずれにせよ身体・服制ともに漢化された仏像が基になっている。種類・形式ともに多様な中国での様相の大部分が輸入されたと思われるが,なかでは半跏思惟(はんかしい)形の菩薩像が特殊な信仰を受けて,統一新羅時代初期まで流行した。統一新羅時代になると唐の影響が強く,像種,様式,技法などあらゆる面でその直模的な造像がおこなわれたが,一般に中国仏よりもやさしさがあり,親しみやすい表現のものが多い。慶州石窟庵の諸像はこの時期の代表的な作で,その格調の高さは盛唐の作品に劣らない。慶州南山の諸所に遺る石仏や,新羅仏と総括され日本をはじめ諸外国にまで散在する多数の小金銅仏も,この時代の仏像盛行を物語っている。高麗時代以後は造像の規模が著しく減少するが,なかで鉄仏の製作が盛んであったこと,また統一新羅以後,触地印(そくちいん)と智拳印(ちけんいん)の如来像が目だつことなどが注意される。全般的にみて像種が比較的とぼしいことと考えあわせて,この地に密教が根付かなかったことが関連すると思われる。
日本
日本の仏像の初見は6世紀半ばころの朝鮮半島からの舶載で,それは仏教自身の公伝とほぼ時期を等しくする。そのころ造寺・造仏関係の工人たちの渡来も伝えられ,日本の仏像はまさに半島のそれの輸入,直模であったといってよいであろう。正史の伝える日本での本格的な造像の最初は,606年(推古14)の飛鳥(あすか)寺本尊,金銅丈六釈迦像で,これは損傷・補修甚だしい状態であるが同寺に伝世する像(飛鳥大仏)にあたると考えられている。これらの仏像の様式は半島経由とはいいながら,中国の6世紀前半の様式を忠実に学ぶもので,材料としては銅と木が主体であった。以後も日本ではこの二つの材料が造像の主流を占め,特に平安時代以降,木彫像が8割を超え,石像が少ないのが特色といえよう。奈良時代は半島における統一新羅と同様に中国唐代の強い影響下にあり,材質の上でも乾漆と塑の技法がおもに用いられた。その写実と理想のかねあいのみごとな造形性は,中国にこの種の遺品の少ない現在,世界的に高く評価される。
密教は奈良時代の末ころから日本に入り,平安初頭の真言・天台両宗によって興隆をみた。中国大陸や朝鮮半島に遺例の少ない密教造像は日本でおおいに発展した。やがてその中から浄土教が起こるや阿弥陀如来を中心とする造像の中に,平安貴族社会の趣向を反映しながら,日本的な造形感覚を顕示したのである。次の鎌倉時代はこの奈良・平安両期の仏像を範としながら,新しい時代の現実的な写実を駆使して独自の仏像様式をつくりあげたが,やがて中国宋代以後の仏教および造像の衰退と歩調を合わせるように,造形の質をおとしていった。
仏像に関する用語
仏像の種類・名称については冒頭で触れたが,これらを礼拝対象としてみた場合,一寺あるいは一堂の中心的な仏像を本尊といい,その両脇に随侍の形で配置される尊像を脇侍と呼んでいる。この一組が3体以上で構成される場合,本尊を中尊と呼ぶことが多い。〈阿弥陀三尊〉のように中尊が如来,脇侍が2体の菩薩像である場合が一般的である。またこうした1セットが個人的な礼拝対象となったり(念持仏(ねんじぶつ)),旅に携帯しやすいようにつくられたり(枕(まくら)本尊)する。特殊な形態として龕(がん)像,碑像,幢(どう)像,懸仏(かけぼとけ)などがある。
材質
造像の面からみると,絵像を別にすれば,インドから朝鮮半島までの仏像の主要材料である石(石窟,磨崖造像を含む。石仏),日本でおもに用いられた木(木彫),全地域にわたって多くおこなわれた銅(金銅仏)が目立った材質であるが,〈造像の展開〉のなかでも触れたように,塑造と乾漆も大きな比重を占めている。特に塑造技法のうちの型による大量生産的な技法は塼(甎)仏(せんぶつ)を生み,泥像や押出仏(おしだしぶつ)と関連し,また印刷による印仏(いんぶつ),摺仏(すりぼとけ)とともに仏像の普及に寄与している。なお種々の経典に造像法が説かれているが,木を用いる場合はまず白檀などの香木があげられ,その代用材としての柏(現在のカヤ,ヒノキなどの針葉樹系か)の使用がすすめられている。これが中国唐代以後の檀像のさまざまな展開をうながしたと考えられている。また,鋳造での鉄(鉄仏)金,銀(銀仏)の使用,織成像,繡(しゆう)仏など特殊な造像も知られている。
法量
仏像の大きさは,まず経典に説かれる釈迦の仏身長である丈六(じようろく)が基準となる。これは1丈6尺の略で,常人はその半分の8尺であるとされる。この尺度の基準が現今の曲尺(かねじやく)と同一でないことはいうまでもないが,中国以東の諸国ではこれを周尺(中国南北朝時代の北周で用いられた尺度という)と,唐尺の一種(日本の曲尺に近い長さ)のおよそ2種に置き換えて造像の基準とした形跡がある。前者は後者のおよそ4分の3にあたる。また座像の場合は全高の半分,つまり丈六の座像は8尺で,2.424m前後,周丈六は1.818m前後になるわけである。しかし時代によって計測の仕方が必ずしも同一ではなく,少なくとも日本の平安時代以降は仏像の髪際から下を測った寸法で高さを決めていることが多い。したがって丈六,周丈六ともに頭頂からの実寸がもう少し高い像が多くみられる。また丈六を基準として,その半分の半丈六つまり8尺,その半分の4尺,10分の1の1尺6寸あるいは周丈六を1丈2尺に換算しての同様な基準を用いて製作された仏像が普通である。ほかに,〈聖徳太子と等身〉というような常人にほぼ等しい高さや,〈一磔手半(いつちやくしゆはん)〉という人間の掌を広げた大指と中指の間の長さ(これには異説もある)なども基準とされている。いわゆる大仏も例外ではなく,東大寺大仏も当初は周丈六の10倍の座像,つまり6丈が目標とされたかと思われる。
形相
仏教諸尊像の4部類のうち,仏(如来)は仏(如来)形といって歴史的ブッダである釈迦の成道(じようどう)後の姿が基本となるから,インドにおける出家ないし修行者の形をとる。本来一枚の衣で身を包み,いっさいの装身具を排除する。しかし仏が超人的な存在であることを強調する傾向が生じた結果,身体的特徴として三十二相とか八十種好(三十二相をさらに詳しく説いたもの)といった特徴が付与されるようになった。白毫(びやくごう)相といって眉間(みけん)に白色の光を放つ珠をはめたり,肉髻相といって頭頂にいちだん高く盛りあがった部分をつくったりするのがそれである。これらの形状は史的展開の中でかなり変化し,特に衣服の上では6世紀以降,中国以東の諸国でおこなわれた形が,それ以前と区別される。すなわち,裙衣(くんい)(裳)で下半身を覆い,次に僧祇支(そうぎし)(掩腋衣)という肩衣をつけ,上に僧伽梨(そうぎやり)(大衣)を着るのであるが,このうち僧祇支にあたる部分はなにもつけなかったり,あるいは偏衫(へんさん)であるとか横被であるとか,その名称・形状を異にするものをつけるようで,地域・時代で異なる場合も考えられる。また僧伽梨のつけ方に2法あり,両肩を覆う通肩と,右肩をはずす偏袒右肩(へんだんうけん)では,そのあらわす意味内容を異にする場合がある。なお,仏部でも大日如来は例外的に菩薩形をとる。
菩薩形はやはり釈迦の出家以前の姿が基本にあるので,インドの当時の貴族の形容と考えられている。したがって頭上は大きく髪を結いあげ,宝冠その他の装身具をつけ,腰には裳をつけ,裸形の上半身にはときに条帛とか天衣(てんえ)といわれる細長い布をまとう。中国にいたる以前の例では足にサンダルをはくものがあり,中国以東では上半身に下着様のものを着るものなどがある。菩薩部は本来慈悲相であるから,おだやかな常人の身体表現を基本とするが,ときに忿怒形をとる場合があり,明王や天部とまぎらわしいことがある。これに対して天部は本来異教の神格を仏教にとり込んで護法神としたものであるから,その神格に応じたいろいろな形相を示し,温和な神格は菩薩形と区別しがたいこともある。またこの部には明らかな女性神もあって,その服制は地域・時代に応じた変化を示している。しかし,だいたいにおいて外敵を防除する使命をもっているから,その表情・姿態ははげしい表現をとり,四天王や十二神将などは甲冑に身をかためている。同じようにはげしい忿怒の表現をとる明王部は,密教の中で,インドから中央アジア辺の異形神をヒントとして,精神的な外敵調伏を目的として成立したものだけに,服制や装身具の基本形は菩薩形を借りながら,その忿怒相の表出には,多面多臂という身体的異相,髑髏(どくろ)や蛇をあしらった環釧などさまざまな工夫がなされている。多くの像種が中国以東でその像容に変化をきたしている中で,この明王部は比較的それが少ないものといえよう。
姿勢
諸尊像の姿勢には大別して2種ある。立像と座像である。立像には両足をそろえて直立した正立形と,一方の足をゆるめ,もう一方の足に重心をゆだねた屈斜形がある。三尊像の両脇侍に屈斜姿勢が多く,この場合,中尊は座形が普通である。座像では両足の甲を他方の足の大腿部にのせる形の結跏趺坐(けつかふざ)が普通であるが,これには左右の足のいずれを上にするかで吉祥坐と降魔(ごうま)坐の別がある。日本の天台系の造像は右足を外にする吉祥坐といわれ,そこに意味付けもおこなわれているが,異論もある。いずれにせよこれらは全跏ともいわれ,その片足を外すのを半跏という。これには単に外すだけのものと,外した足を踏み下げるものとあり,後者のなかに,左足を踏み下げ,右手の臂を右膝につき,その指先を頰に当てる半跏思惟形があり,これが中国の南北朝時代に釈迦の前身である悉達多太子の姿として信仰され,やがて朝鮮半島の三国時代から日本の飛鳥・白鳳時代にかけて,弥勒菩薩とも考えられて流行した。両足を折って座る姿勢にはまた両足先を下腹部にあてるように交差させた形もある。これはむしろ仏教以前のインド古来の座り方であり明王,天部に多く,結跏趺坐はどちらかというと仏教的な成立とする考え方もある。坐形にはまた両足を平行状に踏み下げるもの,それを交差させるものなどもあり,これらは北方の騎馬民族の習性が仏教尊像にとり入れられたという考え方があるが,ともかく中国以東における初期の仏像の中で,前者は仏形の,後者は菩薩形の弥勒である場合が多いのも注意をひく。これら以外の姿勢では,釈迦生誕時の,一方の手を上げ,他方の手を下げたいわゆる誕生仏の立形と釈迦涅槃時の臥形,また釈迦遊行の姿である径行像や阿弥陀如来単独または観音・勢至をともなった三尊での来迎(らいごう)形など,ときに運動を示すものがあり,明王,天部の中には特殊な立勢,坐勢を示すものも少なくない。
印相
両手の示す形状は,それぞれその尊像に特有の内面的な意味を象徴するという考え方のもとに印相(いんぞう)と呼ばれて重視される。仏形での基本的なものは座った脚部の上に両掌を重ね,左右の大指頭を合わせた禅定印で,これは釈迦禅定の際の手の形といわれ,釈迦降魔のときの印である右掌を右膝前に伏せる印,説法時の印,施無畏と与願の印(この二者を併せた形(施無畏・与願印)は古くは諸仏に共通の印でもあった)などがある。阿弥陀には来迎の諸印,大日では金剛界の智拳印など,その尊像によっていろいろに定まった印相があり,持物にも特色がある。それも上記のように場合によって異なるなど,さまざまな展開を示した。
荘厳具
こうした仏教の諸尊像は,身につける物のほかに,像の背後にあってそれを飾る光背,像の下にあってこれを保持する台座,像の上に懸けられる天蓋などの荘厳具(しようごんぐ)を持つのが普通である。光背は,仏像発生の初期には,仏の発する光明を具象化する意味で,仏像の頭部の背後に付せられた円形のみであったが,だんだん複雑,華麗な形式をつくり出すようになり,日本の場合,多く頭部,体部それぞれの背後に円相が当てられ(二重円相),その基部に光脚,周縁に火焰や唐草などの文様帯をあしらった二重円相光が基本とされるようになった。台座も,早くに箱を重ねたような形の宣字座があり,やがて蓮花の形を基に種々の付属物を組み合わせて多重に組み上げた蓮花座が一般的になった。これらの光背,台座はおもに仏・菩薩のものであるが,明王,天部は,忿怒尊によく用いられる火焰光や岩座をはじめ,たとえば不動明王の瑟瑟(しつしつ)座や吉祥天の荷葉座など,その像種に特有の台座が用意されている。また文殊菩薩の獅子,普賢菩薩の象,あるいは四天王が踏みつける邪鬼なども台座の一部と化している。天蓋は蓮花をかたどる円蓋と,格天井(ごうてんじよう)を思わせる方蓋が基本となり,さまざまの組合せや変形がつくられている。なお光背には三尊像を一光中におさめる一光三尊(いつこうさんぞん)形の光背があり,仏像を安置する堂内には,これら荘厳具を含めて,地面より区別する須弥壇(しゆみだん)がしつらえられるのが普通である。こうした仏像の形相上の細部は,史的展開の中で変化してはいるが,基本的には一貫性があり,尊像の区別の手掛りとなる。
執筆者:田辺 三郎助
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「仏像」の意味・わかりやすい解説
仏像【ぶつぞう】
→関連項目開眼供養|丈六|仏画
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仏像」の意味・わかりやすい解説
仏像
ぶつぞう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「仏像」の解説
仏像(ぶつぞう)
仏の姿を刻んだ形像のこと。『増一阿含経』(ぞういつあごんきょう)は,釈尊(しゃくそん)の在世当時すでに,仏の不在を嘆いたウダヤナ(優填)王によって仏像がつくられたと伝える。しかし実際には,1世紀頃にヘレニズム文化の影響を受けたガンダーラ地方と,ほぼ同時期に独自に中インドのマトゥラー地方で最初の仏像が出現したと考えられる。そして,一度仏像が刻まれると,礼拝の対象として仏教には欠かせないものとなった。大乗経典には,造像の功徳が大いに讃えられている。仏像には,仏教で信仰の対象とされるすべて,すなわち,(1)釈迦(しゃか),阿弥陀(あみだ),大日(だいにち)などの如来(にょらい)像,(2)観音,文殊(もんじゅ),弥勒(みろく),地蔵などの菩薩(ぼさつ)像,(3)不動,愛染(あいぜん)などの明王(みょうおう)像,(4)帝釈(たいしゃく),弁財などの天部像,(5)十六羅漢(らかん)などの羅漢像,(6)弘法大師や道元(どうげん)禅師などの各宗の祖師,高僧の像などが含まれる。また,彫像と画像の別や,材料とか形状の別,彫り方の違いなどにより細かな分類がある。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「仏像」の解説
仏像
ぶつぞう
仏教では,はじめ偶像をつくらなかったが,ガンダーラ美術においてギリシアの神像彫刻の影響をうけてはじめて仏像がつくられた。中国などに伝播し,百済から日本に仏教が伝来したときは仏像を伴っていた。仏像は経典と儀軌 (ぎき) (儀式のきまり)によって造形され,一般に如来・菩薩・明王・天の4部に大別される。如来は仏で,すべて出家の姿で法衣をつけるだけであり,装身具はない。菩薩は如来に従って法を学ぶもので,温顔・上半身裸体,下半身に裳 (も) をつけ冠を戴 (いただ) き,胸飾や腕釧 (うでくしろ) などの装身具をつける。明王は密教の理論によって如来の真意を奉じて悪を破砕 (はさい) する使者なので,焔髪・怒眼,牙をむき,武器をもち忿怒 (ふんぬ) の形相をする。天はバラモン教や民間信仰の神々を仏教の守護神としたもので,四天王・十二神将など種類が多い。如来と菩薩の三尊〔釈迦如来と文珠・普賢菩薩:阿弥陀如来と観音・勢至菩薩:薬師如来と日光・月光菩薩〕の組合せが多くみられる。素材から鋳造による金銅像・粘土製の塑像・漆を用いた乾漆像・木像(一木造・寄木造)・石像などがあり,姿勢から立像・結跏趺座 (けつかふざ) 像・半跏趺座像・倚像 (いぞう) (両足を平行に垂下)などの区別がある。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の仏像の言及
【インド美術】より
…古代後期は,グプタ朝の繁栄を背景にインド古典文化が高揚し,造形美術の面でも古典様式の完成をみた時期である。仏教美術では仏像制作に重点がおかれ,マトゥラーとサールナートとの二大工房において,高い精神性をそなえた理想美の典型ともいうべき仏像が成立した。一時停滞していた西インドの石窟造営は5世紀後期から再び盛んになり,壁画や彫刻で華麗に飾られたアジャンターその他の石窟が出現した。…
【ガンダーラ美術】より
…しかしまだ仏教的な主題を扱わず,次のクシャーナ時代に本格的な展開を見た。すなわち1世紀末期に仏像が仏伝図の主人公として出現し,2世紀前期に単独の仏像が成立した。やや遅れて大乗仏教に関する彫像も現れるが,仏像出現に大乗仏教が関与した証拠はない。…
【スリランカ美術】より
…
[彫刻その他]
彫刻はインドと同様ストゥーパの装飾として始まり,アヌラーダプラなどの古塔のワーハルカダの浮彫が早期の例である。仏像は3世紀以前にはさかのぼりえず,初期のものはインドのアーンドラ美術の影響が顕著であり,ことに体に密着した衣に陽刻線による襞をほぼ等間隔に密集させる手法は後世まで続いた。またアヌラーダプラ南西部のイスルムニヤの人物や動物の磨崖浮彫には,インドのパッラバ様式(7~9世紀)が濃厚である。…
【仏教美術】より
…しかし釈迦滅後5~6世紀の長期間,釈迦(仏)の造像は絶対にみられず,上記の装飾に仏は塔,樹木などのシンボルで表現された。しかし,2世紀ころ,ガンダーラにおける仏像出現によって,このタブーは破られた。さらに大乗仏教が興ると,〈法〉は生身の釈迦を超えて普遍化し,〈法〉を求めて精進すれば衆生も如来たりうるという菩薩道が重視される。…
※「仏像」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
グリーンランド
北大西洋にある世界最大の島。デンマーク自治領。中心地はヌーク(旧ゴートホープ)。面積217万5600平方キロメートルで、全島の大部分は厚い氷に覆われている。タラ・ニシンなどの漁業が行われる。グリーンラ...
お知らせ
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新