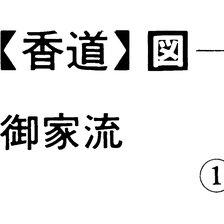精選版 日本国語大辞典 「香道」の意味・読み・例文・類語
こう‐どうカウダウ【香道】
- 〘 名詞 〙 一定の作法のもとに香をたき、そのかおりを賞翫する芸道。供香(そなえこう)、空薫(そらだき)と香合(こうあわせ)、薫物合(たきものあわせ)、聞香(ききこう)、組香(くみこう)などを総括していう。香。
- [初出の実例]「東山慈照院殿、始て香道の法を立らる」(出典:随筆・本朝世事談綺(1733)三)
改訂新版 世界大百科事典 「香道」の意味・わかりやすい解説
香道 (こうどう)
香木を素材とする聞香(ぶんこう)/(もんこう)の芸道を香道という。日本独自のもので他に類例をみない。成立は室町時代末期であるが,奈良時代以来の前史がある。
前史
香木が登場する奈良時代の香は,もっぱら神仏に供えられたが,平安時代には部屋にたきこめたり,着物に移香するための空薫(空香)物(そらだきもの)(練香(ねりこう))が盛行,精緻な発達をみせた。やがて,その艶麗華雅な創作を鑑賞し,2種の薫物の優劣を競う薫物合(たきものあわせ)が興る。根合,歌合,貝合,花合などと同様合せ物である。鎌倉・室町時代になると武士の興隆に伴って,華麗な薫物に代わって幽玄なる一木の沈香(じんこう)が尊重され,香合(こうあわせ)も香木で興行される。武士の精神生活・美意識に対する禅の影響が認められる。闘茶は12世紀末に始まるが,14世紀中葉には《建武記》の中の〈二条河原落書(首)〉にみられるように〈茶香十炷(さこうじつちゆう)の寄合〉(それぞれ10種の茶香を判別する闘茶と聞香の競技)が流行し,《太平記》に記された佐々木道誉(高氏)のような豪奢を誇示する焚香(ふんこう)にとどまらず,寄合芸能としての香筵(こうえん)(香席)の成立をみるのである。この風潮は堂上も例外ではなく,15世紀に入ると御所,御内儀などで名香合,薫物合,十炷香,十種香がしばしば催され,それも,ほとんど懸物(賭事)をともない,ときには〈終夜催〉〈呑酒夜更〉〈大酒終夜〉などと《実隆公記》などに記されているごとく,夜を徹して行うありさまであった。室町末期の乱世では堂上も地下(じげ)も,来世に浄土を欣求(ごんぐ)するか,現世の刹那享楽に耽溺するかの風潮の中で,茶香の世界も〈京中の踊躍,鉦鼓耳に満つ〉(《実隆公記》)という狂踊と変わるところがない。このため1458年(長禄2)〈沈麝艶色をたのしむこと禁ぜらるべきよしおほせ出さる〉(《蔭涼軒日録》)という始末であった。このころの十炷香,十種香が江戸以降のそれと同一であると断定はできないが,桃山時代の志野宗温《宗温香記》,蜂谷宗悟《香道軌範》には同一を示唆する記述がある。
名香合(めいこうあわせ)は東山殿で催されたおりの記録《五月雨之記》によれば,連衆が2組に分かれて所持の名香を出香し,その優劣を競うとともに,その継ぎ様を香の風情,香銘の出典,来歴などを勘考して判定するものであり,判者の判詞から評定の内容をうかがうことができる。鑑賞力と同時に文学的教養,美的感受性が問われ,そこには歌合の影響が認められるのである。さらに連衆が前の人のたいた香を基に連歌式要領でたき継いで鑑賞する〈炷継香(たきつぎこう)〉では宗祇などの連歌の考え方が基盤にあるとみてよいであろう。こうして香合や炷継香は組香を中心とする香道の成立を準備したのである。
香道の成立と沿革
香道の成立については享保(1716-36)ころの大枝流芳(おおえだりゆうほう)(岩田漱芳)以来南北朝の婆娑羅(ばさら)大名佐々木道誉を始祖とする説があるが(《読史備要》),道誉は香木に執心した収集者ではあっても,その香は闘香であり香道ではない。香道家は流派を問わず三条西実隆(尭空)を始祖と仰いでいる。三条西内府が御香所預を歴任したため御所における香の権威と目され,また宗祇,牡丹花肖柏(ぼたんかしようはく),相阿弥(そうあみ),武野紹鷗(たけのじようおう)ら当代の文化人との交遊で中心的な碩学として都鄙に声望高かったためであろう。古今伝授が常縁,宗祇,実隆と相伝されたことは世の知るところである。香道成立期の文化的象徴であったのである。
香道の創成は唐物の書院茶から草庵の侘茶へ展開する茶道の成立と分かちがたく結ばれている。道具の共有(帛紗(ふくさ),地敷(じしき),棚,札),様式の等同(十種香と十種茶)はいうに及ばず,茶人にとって香は茶の一部であった。紹鷗,宗易(千利休),津田宗及,山上宗二は武辺隆生(建部隆勝)に香を学び,宗易は宗二に〈香ノ事ハ坂内宗拾(曾呂利新左衛門)ニ問ベシ〉と語ったという記述が《山上宗二記》にみられる。そのほか《南方録》にも茶の記述のみならず,香木・香炉など香に関しての詳細な記載がある。
桃山時代までの香はわずかの組香はあっても,その中心は香合,炷継香であった。しかしもともと中国から伝来した香道具もこの時代に定着し,香炉の扱い方,香の継ぎ方などの式法も一応の定式化を完了した。さらに決定的なのは,日本文学の道統が志向する美的世界に香が重ね合わせられてゆく方向がこの時期に定着したことである。創成者たちの教養を反映させながら,沈香木の幽佳と文学的主題とが結合した組香という日本独特の試みが香道の中心となるのである。
流派
香道家の伝承では三条西実隆が志野宗信や相阿弥とともに香道創成に尽力したとされている。実隆から三条西家の代々そして烏丸光広など堂上公卿に伝わった流派は10代目に伯家神道白川家学頭猿島帯刀家胤にいたって地下に伝わり,三条西流または御家流と呼ばれた。御家流の相伝は,師匠について奥義を極めた弟子には免許皆伝の印可証明が与えられ,取得者は自分の弟子にも秘伝と相伝の権利のすべてを伝える方法で,家元制度とは異なる完全相伝制であった。元来,堂上ではそれぞれの家が蹴鞠の飛鳥井家・難波家,花道の梶井宮家,琵琶の西園寺家のように家の芸を世襲していたが,和歌と香道には特定の家はなかった。この2道は実力を基本としていたのである。しかし,御家流も師弟相伝の系譜は明確で血脈と呼ばれている。現在は尭空20代実謙を御家流宗家としている。
志野宗信の流れは志野流と呼ばれるが,子息参雨斎宗温,孫不寒斎省巴の後,当時香道の権威と目された建部隆勝の推輓により蜂谷宗悟が4代目を継承し,以後蜂谷家が茶道とともに香道の軌範を整え,享保ころには家元制度を確立して現代の蜂谷宗由にいたっている。
このほか,相阿弥流,建部流,園流,風早流,米川流,大枝流,里見流などの諸流が香道の記録に知られるが,これは御家流の完全相伝制の結果であると思われる。このうち現在残るのは御家,志野の2流のみであるが,19世紀初頭までは米川流も整備された大部の伝書と華麗な香道具を生み出しており,相当な勢力を維持していたことは間違いない。
米川流祖米川常白(小紅屋三右衛門,?-1676)は,隆勝の流れをくむ曾呂利新左衛門(通称,香ききの伴内)を師と仰ぐ相国寺芳長老蘭秀和尚の弟子で,彼により香道が一変したとされる達人である。生涯聞きはずしたことはなく,香ききに止まらず,無双の香しり(香の位を聞きわける)であったため,禁裏御用の紅粉を業としていたが,香道家のあいだでは東福門院の香の相手を務めたと伝えられている。六国五味(りつこくごみ)の確立に貢献し,もっぱら御所で興行されていた組香を地下に伝え,香道隆盛の礎を築いたため,常白を香道中興の祖とする。
享保から弘化まで(1716-1848)の志野流入門帳2冊によれば,総数約2500名のうち武家が3分の1,町人が約半分をしめ,武家社会のみならず町人階層の勃興による普及を背景に香道は2000以上のおびただしい組香を産み出した。しかし,実際には御家流で古十組,中十組,新十組,外組,志野流では内十組,三十組,四十組,五十組,外組といった基本的な組香が繰り返し催されたにすぎない。香道では相当の境地に到達するまでは新しい組香の創作は禁制である。
香道が最盛期を迎えたのは享保・元文(1716-41)以降である。一部には行過ぎもあり,空華庵忍愷(にんがい)律師の《香会余談》に組香を〈商人職人農民迄みだりにもてはやし,香道の宗匠と云者都鄙に徘徊伝授指南などののしる人あまた有〉というのがこの時代である。また忍愷をはじめ大口含翠,大枝流芳,樋口淳叟,宮崎詮恭,菊岡晴行・沾涼(せんりよう)兄弟,叢香舎春竜,牧文竜,江田世恭,関弥五郎親卿,上野宗吟らが輩出して,香道研究と伝書の執筆が質量ともに頂点に達した。なお流芳には10種以上の香道刊本がある。彼は含翠から御家流を,常伯の甥玄察の弟子眉山から米川流をも授けられた人物で,多くの研究家を育成した。また煎茶や文房具にも通じていた。
香道の普及
香道具が様式を整えたのは江戸初期である。大名家の婚礼道具に香道具は欠かせない。将軍家光の息女千代姫尾州家祝言の際の〈初音(はつね)〉の調度は名人幸阿弥長重による代表的な蒔絵道具である。伝承された香道具に大名家の家紋の入ったものが多いのは製作の事情を物語っている。もちろん富裕町人などの婚礼道具としての香道具も相当に現存する。
→香道具
香道は普及しにくい条件が多いが,元禄以降の女子用〈往来物〉,女鑑の類には香木・組香・香席心得のほか掛香(かけこう)(香を袋に入れ部屋に掛けておくもの)の処方などについて詳細な説明がある。実際の稽古はともかく,教養常識としての香道は庶民階層に及んでいたのである。御家流香道皆伝者の系譜である香道血脈にも,幕末には必ずしも大身の家柄に限らず,与力や金座役人の一族も登場する。また稽古用の香木は市井の薬種商で取り扱っていたことは香道の底辺をうかがわせる。
香道に手の届かない人々にとっても香は憧れの的であり,とくに伽羅(きやら)は珍重され,化粧用のみならず,すばらしいもの,高貴,良質,豊饒,稀有なるものの代名詞であった。関白や大大名といえども慎重に扱うべき貴重品であり,分限者も疎略にすべからざるものであった。前関白近衛信尋から伊達政宗に宛てた手紙にも名香渇仰の様子がうかがえる。御所や将軍も名香献上には丁重な対応をしている。
香道と茶道
香道はその創成期に茶道と同根であったのみならず,茶の作法と香を結合する試みが後年にいたってもみられるのである。香道家のほとんどが茶の心得があるという事情は現在でも変わらないが,両者の志向するところが同一であると断言することはできない。香道が組香を重視するにしたがい,文学の美に依存する面が強化され,この意味では香道の発生母体である堂上公卿の美意識が温存されている。茶道の指導理念であるわび,さび,禅といった精神性の強調はみられない。香は倫理に立ち入ることなく,あくまで美的境地にとどまるのである。しかし香にも〈香の十徳〉(《松屋筆記》)なるものがあり,感動鬼神,清浄心身,能除汚穢,能覚睡眠,静中成友,塵裡偸閑,多而不厭,寡而為足,久蔵不朽,常用無障といった徳があげられているが,これは茶道との習合の中で成立したものとみられる。香道の要は一木の沈香を賞翫し,その美を窮めるにあるが,その修錬の方途として組香という文学と香との結合に想到した。世界の諸民族で芳薫を珍重しないものはないが,文学的雅境を匂いに構成した文化は日本のみである。日本独自の美に対する愛惜と特異な思惟様式を香道にみることができるのである。
香席
聞香の香席を香筵と呼ぶが,その構成は,原則的には茶道と同様のものが多く,香木をたく香炉を所作する香元と,客である連衆の共働による。香元は香木が最もよい状態で聞けるように火加減し,進捗状況をみながら香炉を回す。連衆には香席法度と呼ばれ,香水を用いて席に臨んだり,粗末に香を聞いてはならないなどいくつかの心得がある。組香興行のおりは執筆という書き役により香筵の記録が作成される。奉書紙1枚にそのときの組香名,使用した香木を示す香組,連衆名とそれぞれの回答および成績,年月日,場所,香木を組んだ出香者,香元名,執筆者名が記される。この記録は連衆のうちで最高点者に与えられ,同点の場合は上席の者に与えられる。記録の様式は桃山時代にはすでに定まっていた。盤物(ばんもの)の場合には香札や立物を扱う助技がつく。
伝書
香道の伝書はその創成の当初から漸次述作され,御家流,志野流,米川流を問わず相伝に際しては宗匠秘蔵の伝書・聞書の筆写を許されるため17世紀後半から18世紀初期には相当大部な伝書群が成立しているのである。もちろん伝書はそのほとんどが秘書であり,みだりに他見を許さぬ性質のものであるから,流布伝承にもおのずから限界がある。書写を重ねる間に多くの異本を生み出したが,まだその校訂も全然なされていない現状である。
→香木
執筆者:神保 博行
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「香道」の意味・わかりやすい解説
香道
こうどう
香木(こうぼく)を焚(た)き、その薫りを鑑賞することによって人間形成を図る情操教育の一分野である。したがって、それは単なる遊びではなく、その内容には倫理的・芸道的行為を含み、一定の作法のもとに行われる。
[三條西公正]
歴史
日本には6世紀(飛鳥(あすか)時代)に仏教とともに沈香(じんこう)(伽羅(きゃら))が伝わり、最初の間は僧侶(そうりょ)によってもっぱらインドの風習に倣って、仏前を浄(きよ)めるための供香(そなえこう)として寺院で用いられ、僧侶の間では心身を浄めるための塗香(ずこう)としても使用された。やがて7世紀(奈良時代)の後半ごろになると、宮廷を中心として上流貴族階級でも実用とし、部屋や衣服に香(薫物(たきもの)を含む)を焚きしめる空薫物(そらだきもの)(空炷物、空香)が流行する。たとえば、10世紀(平安時代)ごろ盛んに行われた衣服に香を焚きしめる場合には、火取(ひとり)に香を焚き、その上を籠(こ)で覆い、その籠に衣服をかけて、香気を衣服に浸透させる。のちには籠が金属製になり、火取香炉とセットになったものが考案された。これを火取母(ひとりも)とよんでいる。なお衣服に香を焚きしめる風習は、時代が進むにつれて一般庶民の間にも普及し始めた。籠のかわりに木の棒でつくったものを用い、これを伏籠(ふせご)とよんだ。この変化は、衣服が装束から和服(小袖(こそで))に移行したために出現したのである。
また衣服に焚きしめる場合に用いる香は、主として薫物(練香(ねりこう))であって、香木ではない。人為的に創作調製された芳香物質である。したがって調製者の感覚でそれぞれ微妙な相違ができる。代表的処方に「承和の方」「八条宮の方」「閑院左大臣の方」などがあり、薫物方の規範とされている。
薫物にはこのように微妙な相違が生まれるので、一方ではその差違が遊びの世界にも取り入れられた。それを薫物合(たきものあわせ)とよんで、平安貴族の間に教養の一具として重要な地位をつくりあげた。教養の一具としての遊びであるから、そこでは博識経験豊かな人を判者として催されるのが常道である。もし適者を得られない場合には、参加者全員の合議で優劣を判定する。この場合の判定を衆議判(しゅうぎはん)という。判者は薫物の調製の巧拙、銘の適・不適、たちかた(香り)の良否などを主として判定する。優劣を競うので1回に2種の薫物が必要で、その回数に従って何種薫物合とよばれたのである。たとえば六種薫物合といえば、12種のそれぞれ異なる薫物が用意され、6回行われる仕組みである。これが15世紀(室町時代)ごろには沈香木で行われるようになり、名香合(めいこうあわせ)とよばれるのである。1501年(文亀1)5月29日に志野宗信(そうしん)ほか十数人で催した名香合は有名である。この名香合から派生したものに炷継香(たきつぎこう)がある。これは当時流行していた連歌の法則を応用して、香銘の連絡の仕方に興味の重点が置かれ、その飛躍のおもしろさが流行の中心となっていたのである。優劣を競う精神と比べて、平和な文芸世界に人々の気持ちが移行し始めた兆候が、こうした遊びの面でもうかがえるのである。平和な詩の世界の実現に興味が移っている点を見逃すことはできない。こうした気運が文芸的な組香(くみこう)の出現を全うしたのである。
組香は14世紀末ごろから十炷香(じっちゅうこう)という名称で文献に現れてくるが、その流行期は炷継香ののちになるから、炷継香の次の世代の遊びとみるのが妥当であろう。2種以上の香木を使用して、一定の題名のもとに遊びが展開されるところに特徴がある。従来の香遊びにはみられなかった新鮮味があり、ここでは優劣を競うのではなく、題名を十分に香気で表現できたか否かに興味の焦点が絞られるのである。
また一方では、組香が創作できる点にも従来の遊びより優れたものがある。創作ができるゆえに組香として今日に伝わっているものは約1000種にも及ぶが、そのうちで有名なものをとくに三十組組香とよび、しばしば行われている。三十組組香は、16世紀ごろまでに成立しているもの10組を古十組(ことくみ)、17世紀に成立したものを中(なか)十組、18世紀に成立したものを新(しん)十組と称し、代表的作品としている。古十組とは、十炷香、花月香、宇治山(うじやま)香、小鳥香、郭公(ほととぎす)香、小草香、系図香、源平香、焚合十炷香、鳥合(とりあわせ)香のこと、中十組とは、名所香、源氏香、競馬香、三炷香、矢数香、草木香、舞楽香、四町香、住吉香、煙争香のこと、新十組とは、花軍(かぐん)香、古今香、呉越(ごえつ)香、三夕香、蹴鞠(けまり)香、鶯(うぐいす)香、六儀(りくぎ)香、星合香、闘鶏香、焚合花月香のことである。
これらの組香は、その題名が異なるように、遊び方もそれぞれ違う。すなわち、異なる組織で創作されているのである。わかりやすく解説するために「宇治山香」を述べてみよう。「宇治山香」は喜撰(きせん)法師の「わが庵(いほ)は都のたつみしかぞ住む世を宇治山と人は云(い)ふなり」という和歌を典拠としてつくられた組香で、16世紀ごろから香人の間にはよく知られていたのである。宇治山香という題名はもちろん和歌のうちにある「世を宇治山と」からつけられたもので、その組織は和歌の各句を独立させ、これを構成要素としている。したがって要素は五つになる。これにそれぞれ異なる種類の香木を配分する。配分される香木の量は、後世では2ミリメートル四方くらいの小片であるが、初期にさかのぼるほど、小さく削ったものを使用していた。「香は国の宝なり」といわれ、きわめてたいせつに使用されたものである。
宇治山香では、あらかじめ香木の小片を2個ずつつくり、それを1個ずつ香包に入れる。一つのほうを試香包、他の一つを本香包という。試香包は表面に、本香包は内面の奥に、たとえば「わが庵は」と書き記して香の名称とする。この組香では試香五包を和歌の句の順序で炷き、次に本香となった場合には、香包をよく混ぜてから一包を取り出して炷き、その一包がなんであったかを答える仕組みである。すなわち「わが庵は」とか「しかぞ住む」と答えればよいのである。連衆の答えを一枚の紙に席次順に記入する者を執筆といい、香を炷く者を香元(こうもと)という。記録ができあがったとき、香元がたいた香がなんであったかを発表する。だいたいこれでこの遊びは終わるのであるが、執筆が記録を作成する間に、連衆には、いま炷かれた香について種々の問題が残されているのである。たとえば、炷かれた香が「わが庵は」であったと仮定し、それが伽羅であったとする。伽羅は香道で使用する香の最上のものであるから、それが「わが庵は」に用いられていることによって、その庵がりっぱなものであったか、それともその庵が喜撰法師の気に入りの物であったかを示しているといちおう解釈すべきである。
しかしまた一方では、世捨人の僧侶の草庵(そうあん)で、人も住んでいない所の庵を表現するのにはふさわしくないので、伽羅のかわりに真南蛮(まなんばん)か寸聞多羅(すもたら)のほうがよいなどの意見が生まれてくるところに、組香の高次性が存するのである。それゆえに香組をする者(出香者)は、組香の構成要素に配する香の選び方に苦心するし、楽しさもわくのである。そのうえ、香の銘も適当でなければならない。なぜかといえば、その銘が構成要素に対して補助的役割を帯びているからである。たとえば、新築したばかりの庵に対して、「荒れたる宿」という香銘では不適当で、それよりは「山家」などを用いたほうが無難であろう。以上「宇治山香」の一要素について述べたが、同様のことが他の各要素についてもいえる。
香遊びが香道として発足したのは16世紀末以来のことである。従来宮廷を中心として公家(くげ)の間で催されていた香の遊びが、一般に普及し始めた結果、公家では宮中の御香所にも奉仕していた三条西実隆(さんじょうにしさねたか)と、武家では将軍足利義政(あしかがよしまさ)に仕えていた志野宗信(そうしん)が、それぞれ一流派の始祖と仰がれ、実隆を流祖とするものを御家(おいえ)流、宗信を流祖とするものを志野流と称し、今日まで斯道(しどう)に重きをなしている。このほか、重要な流派に米川常白(よねかわじょうはく)を流祖とする米川流、大枝流芳(おおえだりゅうほう)を流祖とする大枝派があるが、いずれも一時的存在であった。また個人では建部隆勝(たけべりゅうしょう)をはじめ、藤野専斉、関親卿、江田世恭、伊予田勝由、勝井錦水らが斯道に造詣(ぞうけい)が深いので有名である。
[三條西公正]
『三條西公正著『組香の鑑賞』(1965・理想社)』▽『三條西公正著『香道――歴史と文学』(1971・淡交社)』▽『一色梨郷著『香道のあゆみ』(1968・芦書房)』▽『杉本文太郎著『香道』(1969・雄山閣出版)』▽『早川甚三「香の歴史」(『伝統と現代』10所収・1969・学芸書林)』▽『長ゆき編『図解 香道の作法と組香』増補改訂版(2000・雄山閣出版)』▽『香道文化研究会編『香と香道』増補改訂版(2002・雄山閣出版)』▽『神保博行著『香道の歴史事典』(2003・柏書房)』▽『北小路功光・北小路成子著『香道への招待』(2004・淡交社)』
百科事典マイペディア 「香道」の意味・わかりやすい解説
香道【こうどう】
→関連項目香|香合|香炉|蘭奢待
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「香道」の意味・わかりやすい解説
香道
こうどう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「香道」の解説
香道
こうどう
沈香木を銀葉(ぎんよう)をへて間接的にたき,その香りを賞翫して人格形成をはかる芸道。室町時代に佐々木導誉(どうよ)(高氏)を頂点とする婆娑羅(ばさら)の美意識から茶道・華道とともに創成期を迎えた。平安時代以降の練香(ねりこう)から沈香木のみをたく時代へと移行した。沈香木の香りに六国五味(りっこくごみ)という分類が確立し,練香による薫物合(たきものあわせ)から沈香木による名香合や組香へと発展した。しかし,実際に香道が大成したのは江戸初期で,三条西家の御家流と蜂谷家に伝えられた志野流をはじめ,建部(たけべ)流・米川流・風早(かざはや)流・大枝(おおえだ)流などが活躍。香道の最盛期は18世紀で,その後は茶道や華道のような普及はみられなかった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「香道」の解説
香道
こうどう
平安時代の貴族間に薫物合 (たきものあわせ) などの遊戯があり,鎌倉末期,禅宗の盛行とともに,香木をたく風習が武家社会にも盛んとなった。室町末期に三条西実隆 (さんじようにしさねたか) (御家流)・志野宗信 (そうしん) (志野流)らの流派が生まれ,香道を確立した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
日本文化いろは事典 「香道」の解説
香道
出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...