ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「神の母」の意味・わかりやすい解説
神の母
かみのはは
「テオトコス」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「テオトコス」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈神を生んだ者〉〈神の母〉を意味する聖母マリアの尊称。日本の正教会では〈生神女(しようしんじよ)〉と訳す。…
…旧約聖書にはモーセとアロンの姉妹の名として出てくるし(《出エジプト記》15:20),新約聖書でもマリアの名をもつ人物はマグダラのマリア以下何人もいるが,一般にマリアといえばイエス・キリストの母,いわゆる聖母を指す。東方では4世紀以降,とくに431年のエフェソス公会議以降テオトコス(〈神を生んだ者〉の意)と呼ばれることが多く,他にパナギアPanagia(〈至聖なる女〉の意),メテル・テウMētēr Theou(〈神の母〉の意。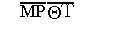 と略す)などと呼び,マリアということはむしろ少ない。…
と略す)などと呼び,マリアということはむしろ少ない。…
…国家形成は10世紀ころで,966年のキリスト教導入により,芸術音楽は西欧文化と結びついて発展した。
[中世]
11世紀から15世紀末までは,キリスト教の普及につれてグレゴリオ聖歌が広まり,民族的な宗教歌《ボグロジツァ(神の母)》も生まれた。14世紀には西欧の多声歌も歌われ,オルガンが各地で建造された。…
※「神の母」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新