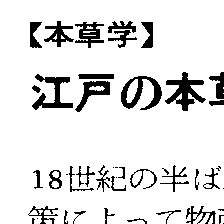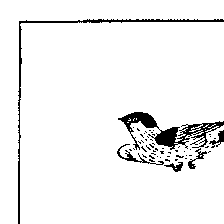共同通信ニュース用語解説 「本草学」の解説
本草学
動植物、鉱物を医薬として利用するための中国由来の学問。日本には奈良時代に伝来し、江戸時代に盛んになった。自然を和歌や漢詩に詠み、精密に写生する日本の伝統文化と蘭学が混ざり合い、西欧の博物学に近い日本特有の研究になった。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「本草学」の意味・読み・例文・類語
ほんぞう‐がくホンザウ‥【本草学】
- 〘 名詞 〙 中国の薬物学で、薬用とする植物、動物、鉱物につき、その形態、産地、効能などを研究するもの。薬用に用いるのは植物が中心で、本草という名称も「草を本とす」ということに由来するという。神農氏がその祖として仮託されるが、古来主として民間でのさまざまな経験が基礎となって発展したもので、梁の陶弘景、唐の陳蔵器らが各時代の整理者として名高く、明にいたって、李時珍によって集大成された。日本では奈良朝以降、遣唐使によって導入され、江戸時代に全盛をきわめた。貝原益軒以後は、中国本草書の翻訳、解釈などにとどまらず、日本に野生する植物・動物などの博物学的な研究に発展し、明治に至って、主に植物学、生薬学に受け継がれた。赭鞭(しゃべん)の学。本草。
- [初出の実例]「止二於福建一十八年、得二本草学一帰」(出典:皇国名医伝(1851)中)
改訂新版 世界大百科事典 「本草学」の意味・わかりやすい解説
本草学 (ほんぞうがく)
中国の,薬物についての学問をいい,薬物についての知識をまとめた書を本草書という。薬物についての研究は本草書を中心にして行われ,その成果はこれらの書のなかに蓄積されてきた。本草の語源については《漢書》芸文志に経方の説明として〈経方は草石の寒温に本づき(経方者本草石之寒温)云々〉とあるのによるとか,後蜀の韓保昇の〈薬は草薬がもっとも多いから〉という説などあって定説はない。またこの語ができた時期も不明であるが,前漢の末期に存在していたと《漢書》に記録されている。ただし,その内容がどのようなものであったかは不明である。
一方,本草書がまとめられるようになったのは一般に漢代と考えられていて,2~3世紀のころには神農とか雷公,桐君などの人名を冠した書が存在したとされている。それらはすべて失われてしまい,《神農本草》だけが陶弘景の書に取り入れられて,その内容を現在まで伝えている。しかし,陶弘景以前の本草書は筆写の過程でかなりの異本を生じていたらしく,内容が確実に残るようになったのは500年ころに陶弘景が本草書の定本を作る目的で編纂した《神農本草経》からである。漢の時代に本草の成立に関係したのは方士たちであり,初期の本草書は神仙方術的な色彩の濃い書であったといわれる。たしかに《神農本草》の文には不老長生などの語句があるが,それに記載されている薬効が当時の薬の使い方をよく反映していることなどから,編纂の主目的が臨床応用にあったことは否定できない。陶弘景の書,とくに彼が自分の知識を注として付加した《神農本草経集注》は隋から唐の初期にかけては,医学生養成のための国家機関で教科書にされ,標準的な薬物書として用いられた。しかし,本草書は実用書であるため,つねに最新の知識が要求され,改訂の必要が生ずる。そこで唐の《新修本草》(659撰)から宋の《政和本草》(1116刊)まで数種の本草書がそれらの欠点を補うために編纂され,医薬の基準書としての性格も備えるようになった。これらはいずれも《神農本草経》を出発点として,前代の書の文はそのまま残し,新しい薬品と新しい知識を付け加えるという方針をとった。《政和本草》とそれとほとんど同内容の《大観本草》(1108刊)は完本が残っているため,そのなかから失われてしまった前代の書の内容を類推することができる。《政和本草》と《大観本草》はその後も長く用いられたが,明末の1596年ころに李時珍が《本草綱目》を著してからは重視されなくなり,本草書といえば《本草綱目》が代表するようになった。
これらの書は冒頭を総論にあて,その編纂の目的などを述べたのち,薬物の処理加工法,調剤法,分量,服薬法,配合禁忌,疾患ごとの使用薬物,引用書などを整理して記述している。これらは編纂時の薬物についての考えを知るために有用である。各論の項では薬物を玉石,草,木など起源によって分類し,それぞれの薬物については,《政和本草》《大観本草》の2書では寒熱とか甘酸といった性状,薬効,別名,産地,採薬時期と採薬後の処理法を述べた《神農本草経》の文を引用したのちに,陶弘景以下の諸家の見解を注として加え,さらに医書から簡単な使用例を引用し,《図経本草》の薬図も併載している。《本草綱目》では釈名(別名とか薬名の由来)に続いて,それまでの諸家の説を集解(性状,産地など),主治(薬効),発明(薬理)などの項に分けて引用すると同時に自説も記述し,最後に付法として簡単な処方を引用している。これらの本草書はいずれも薬物についての成立当時の知識を網羅したもので,《政和本草》と《本草綱目》はそれぞれ薬品数1748と1903を包含する30巻と52巻の書になっている。
しかし,このような大著は一般の臨床医家が使うには不便であるし,他方どんなに大きな書でも薬物についてのすべての情報を収載することは不可能である。そこで,これらの書にもれたものを補うための《本草拾遺》(739,陳蔵器撰),《本草綱目拾遺》(1800ころ,趙学敏撰)とか食事療法に重点を置いた《食療本草》(700ころ,孟詵撰),薬効原理をまとめた《湯液本草》(1248,王好古撰),実用を主眼とした《本草蒙筌》(1565,陳嘉謨撰),《本草備要》(1682ころ,汪昂撰)など,小型ではあるが使用目的を明確にした本草書が作られた。
中国は歴史もきわめて古く,国土も広大である。同じ名称の薬品でも時代によって内容が異なったり,同じ時代でも産地によって異なることがある。したがって明以後の薬物を研究するためには《本草綱目》を中心にした各書を,宋以前では《政和本草》と《大観本草》に引用されている該当する時代の本草書の説を参考にしなければならない。また中国では動植物などに関するいわゆる博物学という分野は存在せず,それらの知識は本草書のなかに蓄積されているから,本草書はそれらの分野の研究にも不可欠である。
執筆者:赤堀 昭
植物学としての本草学
中国と日本で独自に発達し,リンネに始まる二命名法に従わない博物学的な植物学が本草学の中心であるが,これに限らず近代科学以前の植物学一般をさして,広く本草学ということもあり,その場合にはヨーロッパでいうハーバリズムherbalismをもこれに含める。
洋の東西を問わず,植物学は実学として始まったものであり,多様に分化した植物の種差が識別されるようになったのも,有用なものとそうでないもの,害悪となるものとそうでないものとを識別することがきっかけの一つであったろう。したがって,植物の記録は,医薬や食用に供する有用植物の要覧作りであった。ヨーロッパのハーバリズムはテオフラストスに始まり,その《植物誌》は植物学書の始まりとされる。P.ディオスコリデスの《薬物誌De materia medica》には約600種の植物とその用法が記され,1世紀に公にされてから長いあいだ植物薬学の基準となっていた。その後,13世紀のアルベルトゥス・マグヌスの《植物論De vegetabilibus》を除けばめぼしい業績はなかったが,16世紀に至ってディオスコリデスの追加訂正の形でブルンフェルスO.Brunfels,フックスL.Fuchs,クルシウスC.de Clusiusらの植物の図解が次々と世に出たほか,16世紀末にはA.チェザルピーノの《植物学De plantis libri》がまとめられた。コルドゥスV.CordusやボーアンG.Bauhinらが薬物学としての植物学を大成させていくのと並行して,17世紀末から18世紀初頭にかけて,レイJ.RayやトゥルヌフォールJ.P.de Tournefortが種や属の概念を確立し,18世紀のリンネによる近代植物学への基礎固めが始められることになる。
日本の本草学は中国から輸入された。奈良時代に,中国から《新修本草》が輸入された記録があり,中国ではこの書は残されていないのに,日本に全21巻中10巻が保有されている。その後も盛んに中国から本草学が導入されたが,漢籍を日本風に理解したのと呼応して,植物学でも,中国で記述された種を日本風に解釈するにとどまっていた。やっと18世紀になって,貝原益軒の《大和本草》(1709)や稲生若水の《庶物類纂》(未完),小野蘭山《本草綱目啓蒙》(1806)などによって日本風の本草学が集成されていった。江戸時代末にはC.P.ツンベリーやP.F.vonシーボルトなどを介して西洋本草学の影響が及び飯沼慾斎《草木図説》(1852),岩崎灌園《本草図譜》(1828)などが出版され,日本の植物についての高い知見が示されていった。コラム参照。
執筆者:岩槻 邦男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「本草学」の意味・わかりやすい解説
本草学
ほんぞうがく
本草書をひもとき、薬物の歴史を明らかにする学問。伝統薬物には、長い歴史を経る間に、その名称や基源が変化しているものも多い。とくに漢薬にはその傾向が強く、現在でも多くの異物同名品があり、いずれの薬物を使用すべきかが不明確であることも少なくない。こういった場合には、本草学的に解決するという方法(本草考察)がとられる。本草考察においては、古来の正品を明確にすることはもちろん、その薬物の基源や薬効などの歴史的変遷についても言及する必要がある。したがって、調査対象となる文献は、いわゆる本草書のみならず、医方書、歴史書、小説、地理書、その他といった幅広い分野の書籍に及ぶこととなる。
本草考察を行うに際して、もっとも注意すべきことは、参考とする本草書の版本である。本草書は、翻刻が重ねられるうちに、その内容が変化しているものである。したがって、同一書名といえども、版本によってかなり内容を異にする。原本にあたるのが最良であるが、原本が散逸しているものも多く、実際には困難である場合が多い。こうしたことから、できるだけさまざまな版本を参照することが望まれるが、版本によって異なる内容があるときは、それが単なる翻刻の誤りか、意図のある改作かを洞察する必要がある。後者である場合は、その時代背景を知ることは本草考察において重要である。時代背景としては、政治的背景のほか、作者の出身地、勉学地などがあげられる。また、校定本の場合には、校定者によって内容が大きく異なるため、とくに注意が必要となる。『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』の校定本においては、収載品目すら異なっている。本草考察において、もう一つ重要なことは、本草書のなかには、孫引きによって書かれた書物も多く、かならずしもその内容が、その時代を反映しているとはいいがたいということである。したがって、書物から得られる知識は、あくまでも時代的変遷の流れのなかでとらえるべきで、誤った先入感をもつことは、正しい考察の妨げとなる。
[難波恒雄・御影雅幸]
百科事典マイペディア 「本草学」の意味・わかりやすい解説
本草学【ほんぞうがく】
→関連項目伊藤圭介|木村蒹葭堂|白井光太郎|並河天民|竜骨(薬)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「本草学」の解説
本草学
ほんぞうがく
古代中国に始まった動・植・鉱物など天産物の薬用を研究する学問。おもに草を対象としたので本草の名がうまれたという。最古の本草書は500年頃に陶弘景(とうこうけい)が編纂した「神農本草経」で,その後経験の蓄積と漢方医学の発達にともなって順次改訂され,唐の蘇敬(そけい)らが「新修本草」,宋の唐慎微(とうしんび)が「経史証類備急本草」を編纂。明末の李時珍(りじちん)が「本草綱目」を編纂して集大成される。日本には「新修本草」が奈良時代に,「経史証類備急本草」が平安末期に渡来し,和産物・和名と照合・同定する名物学がおこった。江戸時代になると「本草綱目」の移入・消化が行われ,博物学的色彩の濃い日本的な本草学が隆盛。その集大成の書として小野蘭山(らんざん)の「本草綱目啓蒙」などがうまれた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「本草学」の解説
本草学
ほんぞうがく
薬用を目的に動・植・鉱物を研究。中国におこり,古代に渡来し,漢方医学と並んで発展した。平安時代には『倭名類聚抄』など本草書の著述がある。江戸初期に明の『本草綱目』が紹介されて以来儒学者・医者の間で盛行。貝原益軒の『大和本草』,稲生若水 (いのうじやくすい) の『庶物類纂』,小野蘭山の『本草綱目啓蒙』などを生んだ。江戸後期,蘭学・オランダ医学の発展とともに博物学の傾向を強め,動物・植物・鉱物・薬物の諸学に分化した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の本草学の言及
【医薬品】より
…その代表的なものが,後漢(1~3世紀)のころの《神農本草》と,《傷寒論(雑病論)》である。前者は,西方山地に発達したとされる〈薬効ある自然物〉に関する知識をまとめたもので,中国医学における薬学(本草学)の基礎となったものであり,後者は,身のまわりに存在するありふれた薬物(生薬)を適宜に組み合わせて,その総合的効果が十分に発揮できる特定の条件の疾病に用いるという,当時の江南地方の医術における経験が整理され,一定の薬物を配合した処方に適応する条件(これを証という)という根本概念を把握し,体系化したものである。 漢方医学は,高度な臨床治療体系をもち,非常に実用的なものであり,観念的,神秘的な色彩のまったく認められない実践的医学体系であった。…
【生薬】より
…生薬という言葉は1880年大井玄洞がドイツ語のPharmakognosieに対して〈生薬学〉の訳語をあてたことに始まる。古来〈きぐすり〉という言葉があり,和漢薬の研究に対しては〈本草学〉という語があったが,近代科学の1分野として取り扱うという意味から新しく造られた言葉である。Pharmakognosieという語は1815年ザイドラーSeydlerが論文の標題に用いたのが最初で,1832年マルティウスT.W.C.Martiusの《生薬学の基礎Grundriss der Pharmakognosie des Pflanzenreiches》にこの名称が用いられ,今日に至っている。…
【植物学】より
… 博物学の祖とされるアリストテレスには植物学の著述は残されておらず(彼が植物園をつくっていたともいわれ,植物学に関心がなかったとは思えないが),その弟子のテオフラストスの《植物誌Historia plantarum》などが植物学のはじまりといわれる。中世には本草学herbalismという記載を主とした時代があった。近代植物学は研究機器のめざましい発達とともに,生命現象の解析に大きな成果を上げつつある。…
【円山四条派】より
…第1は南画(文人画)へ,第2は伊藤若冲,曾我蕭白ら表出性の強い画家群へ,そして第3は写生を重視する円山派へと発展した。この基盤として,本草学に象徴されるような当時の文化全般にわたる客観的実証的傾向が指摘できよう。 応挙ははじめ狩野派の一分派である鶴沢派に学んだが,玉条とすべきは粉本でなく写生であることに開眼,これを基礎として新画風の確立へ向かった。…
※「本草学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...