海の事典 「エクマン螺旋」の解説
エクマン螺旋
出典 (財)日本水路協会 海洋情報研究センター海の事典について 情報
出典 (財)日本水路協会 海洋情報研究センター海の事典について 情報
Ekman spiral
⇒ エクマン吹送流
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
…海面では海流が風に対し北半球では風下右方向(南半球なら左方向)に45度ずれて流れ,深さと共に流速が減ると同時に流向が変化していることがわかる。図2によって示される流れをエクマン流,またはエクマンらせんと呼ぶ。エクマン流の代表的な厚さ(ほとんど流れがなくなる深さ)は で表されるが,この値はAを渦粘性係数としても,現実の海ではたかだか10m程度で,海の深さ全体のうち表層のごく一部を占めているにすぎない。…
で表されるが,この値はAを渦粘性係数としても,現実の海ではたかだか10m程度で,海の深さ全体のうち表層のごく一部を占めているにすぎない。…
…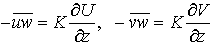 ここでKが高さに関係なく一定とし,地表(z=0)で平均風速が0(U=V=0),高さが高くなれば(z→∞),平均風速は地衡風に等しくなる(U=Ug,V=Vg)として方程式を解くと図2のようになる。これはエクマンらせんと呼ばれ,スウェーデンの海洋学者V.W.エクマンが1905年に初めて海流の運動を説明するために提案したものである。地表面近くでは地衡風の風向と約45゜の差が生じているが,実際は,地表面の粗さ,成層の安定度およびfの値によって左右されることから,45゜より小さい値を示している。…
ここでKが高さに関係なく一定とし,地表(z=0)で平均風速が0(U=V=0),高さが高くなれば(z→∞),平均風速は地衡風に等しくなる(U=Ug,V=Vg)として方程式を解くと図2のようになる。これはエクマンらせんと呼ばれ,スウェーデンの海洋学者V.W.エクマンが1905年に初めて海流の運動を説明するために提案したものである。地表面近くでは地衡風の風向と約45゜の差が生じているが,実際は,地表面の粗さ,成層の安定度およびfの値によって左右されることから,45゜より小さい値を示している。…
※「エクマン螺旋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...