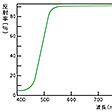日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
ストロンチウムクロメート
すとろんちうむくろめーと
strontium chromate
SrCrO4の組成で、古くからシトロンエローの名で絵の具として使われてきたが、近年水溶性樹脂の開発に伴い、さび止め顔料として脚光を溶びるようになった。硝酸ストロンチウム(Ⅱ)Sr(NO3)2とクロム酸ナトリウムNa2CrO4の各水溶液を反応させて得られるが、生成物の一つである硝酸ナトリウムNaNO3が混入すると、さび止め効果のない可溶性の成分が増えることになり、塗膜に悪影響を与える。貯蔵中変質せず、耐熱性はジンククロメートよりもよい。溶解度はZPC(塩基性クロム酸亜鉛カリウム)型ジンククロメートの約2分の1(4~7%)、CrO42-の溶出量はやや少ないが、長期にわたり持続する。同じ系のバリウムクロメートも絵の具のほかさび止め顔料に用いられている。
[大塚 淳]