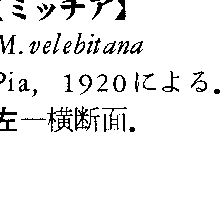改訂新版 世界大百科事典 「ミッチア」の意味・わかりやすい解説
ミッチア
Mizzia
古生代二畳紀にテチス海域の暖かい極浅海部で栄えた,緑藻植物カサノリ科の石灰藻で,絶滅属の代表の一つ。模式種M.velebitanaはユーゴのベレビト山地産。球型の節間部が数珠つなぎにつながって立つという,現生のウスガサネ属に似た形態をもつ。垂直にたつ中軸のまわりには規則正しい栄養体の枝が輪生して,枝の間に炭酸カルシウムが沈着する。配偶子囊はウスガサネのように枝の先端部にできずに,たぶん中軸のなかにあったらしい。死後ばらばらに離れた節間部が局地的に密集して,“ミッチア石灰岩”や“ミッチア苦灰岩”をつくり,造岩生物として重要な役割を演ずる。北アメリカ,南~東ヨーロッパ,北アフリカ,中近東,東南アジアなど分布が広い。日本では岐阜県美濃赤坂金生山が有名な産地で,A.カルピンスキーの詳しい研究(1908)で知られている。
執筆者:小西 健二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報