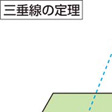ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三垂線の定理」の意味・わかりやすい解説
三垂線の定理
さんすいせんのていり
theorem of three perpendiculars
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の三垂線の定理の言及
【垂線】より
…平面αとその上にない点Pがあるとき,Pからα上の任意の直線lに垂線を下ろして,その足をRとし,次にα上でRにおいてlに立てた垂線をmとして,Pからmに下ろした垂線をnとすれば,nはPからαに下ろした垂線となる(図3)。この事実を三垂線の定理と呼んでいる。【中岡 稔】。…
※「三垂線の定理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...