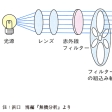日本大百科全書(ニッポニカ) 「光電光度計」の意味・わかりやすい解説
光電光度計
こうでんこうどけい
photoelectric photometer
物質を透過した光の強さを光電管または光電池により電気信号に変換し、電流値もしくは電圧値をメーターで読み取るかあるいは記録する方式の光度計を総称して光電光度計という。光電光度計には大別して次の二つのタイプがある。一つは単色光器(モノクロメーター)として精密なプリズム分光器や回折格子分光器を備えた光電光度計で、これを光電分光光度計という。他は簡単なフィルターを用いて、ある幅をもつ波長帯の光を得るようなフィルター型光電光度計である。後者のタイプのものを光電比色計photoelectric colorimeterという。装置の主要部分は光源部、単色光部、光量調節部、試料室セル部、光電変換部、検出部からなる。
[成澤芳男]