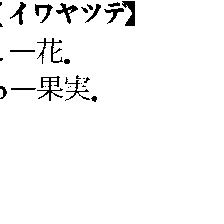改訂新版 世界大百科事典 「イワヤツデ」の意味・わかりやすい解説
イワヤツデ
Aceriphyllum rosii Engler
朝鮮半島や中国東北に自生する1属1種のユキノシタ科の多年草で,日本ではしばしば観賞用として栽培される。タンチョウソウともいう。落葉性で,横にはった太い根茎があって,毎春,そこから新しい葉と花茎を出す。葉には20~30cmの長い柄があり,葉身とともに毛はない。葉身は,カエデやヤツデのように掌状に深く裂け,表は緑色,裏は淡緑色で,浮き出た脈が目立つ。春先に集散状の花序に多くの白い花をつけるが,花序の枝は,初め外側に巻いている。萼裂片は5~6枚で,長さ約5mm,白色で花弁状である。花弁は5~6枚,白色で,萼裂片より短く,おしべは5~6本で,萼裂片と向かい合ってつき,花弁より短く,葯は暗紅色。子房は半下位で,2心皮からなり,2本の花柱がある。ユキノシタ属やアラシグサ属に近いものであろう。
執筆者:若林 三千男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報