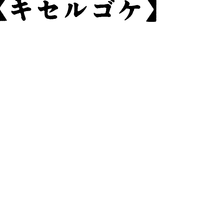改訂新版 世界大百科事典 「キセルゴケ」の意味・わかりやすい解説
キセルゴケ
Buxbaumia aphylla Hedw.
配偶体が極端に退化したキセルゴケ科の蘚類。北半球の高緯度地域に分布し,日本では全国の山地に稀産し,薄い腐植質でおおわれた土上や岩上に散生する。配偶体は肉眼ではほとんど認められないほど小さい。雌雄異株。胞子体は雁首(がんくび)の大きい煙管(きせる)に似ており,外見は菌類の子実体(キノコ)を思わせる(実際,古い時代には菌類の一種とみなされていた)。蒴柄(さくへい)は太く,長さ5~10mm,蒴は広卵形で明瞭な背腹性を示す。和名のキセルゴケ,英名のfairy spoonはいずれも胞子体の形状に由来する。本種に近縁のクマノチョウジゴケB.minakatae Okam.は深山の腐木上に稀産する。キセルゴケと異なり,蒴柄がごく短く(約3mm),蒴は長卵形である。南方熊楠が和歌山県熊野で発見した標本に基づき命名された。
執筆者:北川 尚史
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報