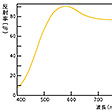日本大百科全書(ニッポニカ) 「チタン黄」の意味・わかりやすい解説
チタン黄
ちたんき
titanium yellow
クロムチタン黄と同様、母格子は酸化チタン(Ⅳ)TiO2(二酸化チタンともいう。ルチル型)にニッケルとアンチモンとが固溶した黄色顔料。チタンエローともいうが、名称は元素のチタンとは無関係である。酸化チタンの製造工程中で得られるメタチタン酸をTiO2の原料とし、これに水酸化ニッケル(Ⅱ)Ni(OH)2、酸化アンチモンⅢSb2O3を配合する。配合の一例はモル比でTiO2:NiO:Sb2O3=90:2:8。加熱中アンチモンは酸化されSb5+となり、NiSb2O6の三重ルチル型化合物を生成し、これが改めてTiO2に固溶すると考えられる。一般の無機顔料中では耐光性、耐候性、耐熱性、耐薬品性ともに大、隠蔽(いんぺい)力はルチル型酸化チタンより大きい。着色力は弱いが、この顔料は、着色顔料と隠蔽用顔料の二面を考慮すべきであろう。塗料、ゴム、プラスチック、印刷インキなどに用いられる。クロムチタン黄と異なり、セラミックスの分野では用いられない。
[大塚 淳]
[参照項目] |