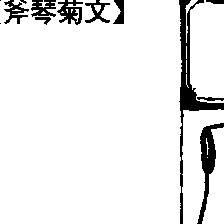改訂新版 世界大百科事典 「斧琴菊文」の意味・わかりやすい解説
斧琴菊文 (よきこときくもん)
江戸時代に流行した判じ物文様。斧(よき)と琴と菊を表して〈良きことを聞く〉にかけたもの。江戸前期から小袖の文様に使われたが,滑稽本《浮世風呂》に〈よきことをきくといふ昔模様。謎染の新形浴衣(ゆかた)〉とあるように,文化年間(1804-18)以降流行をみた。またのちにこの文様は尾上菊五郎の歌舞伎衣装にも採用された。おそらく1815年に襲名した3世菊五郎がその芸名の菊にちなみ,また当時流行していた市川団十郎の〈鎌輪奴(かまわぬ)文〉にはり合って取り入れたものと思われる。これは歌舞伎文様として浴衣に染められ,ことに江戸の女性に好まれたが,多くは斧と菊を形で,琴を文字で縦縞風に並べて表された。
執筆者:上田 敬二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報