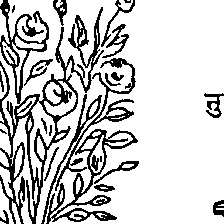改訂新版 世界大百科事典 「トゥルシー」の意味・わかりやすい解説
トゥルシー
tulsī
ヒンドゥー教,とくにビシュヌ派の人々が聖草とし崇拝の対象とする多年草。シソ科のメボウキの一種のカミメボウキOcimum tenuiflorum L.(=O. sanctum L.)で,英名sacred basil,holy basil。よく枝分れし,高さ30~60cm,茎の基部は木質化することがある。その葉はハッカの芳香をもち,咳止めなどの生薬としても用いられる。砂地に多く自生するが,信者は家の庭や沐浴場に砂の塚または石の鉢を設け,そこに植えたものに毎日プージャーをささげる。夜は灯明をあげ,夏の乾季には孔をあけた水瓶を枝に掛ける。毎日水をささげるだけで解脱できるともいわれる。とくに罪,穢れ(けがれ)を浄める力が強調され,見るだけで,触るだけで罪障をはらうとされる。したがって臨終の信者の枕もとにはトゥルシーの枝を置く。口に根をふくませ,顔や胸に葉をのせ,水に浸した枝で体中に散水する儀礼を行う場合もある。トゥルシーはビシュヌに信愛をささげ妻になりたいと願った女性が,正妻ラクシュミー(吉祥天)に呪われて木にされたもので,ビシュヌの保護下にあるとされ,〈ビシュヌの妻〉とも呼ばれる。したがってその枝や葉をビシュヌにささげる儀礼も数多く,そこでも大きな功徳が説かれている。
執筆者:高橋 明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報