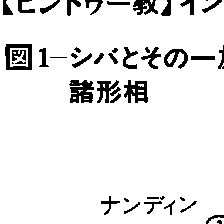翻訳|Hinduism
精選版 日本国語大辞典 「ヒンドゥー教」の意味・読み・例文・類語
ヒンドゥー‐きょう‥ケウ【ヒンドゥー教】
- 〘 名詞 〙 [ 異表記 ] ヒンズーきょうインドの民族宗教。本来、宗教という狭い意味のみではなく、インドの伝統的・民族的な制度・慣習の総体の呼称で、宗教的・倫理的・社会的な行為の規範すべてを内容とする。全体を統一する教団組織は存在せず、宗教的信仰としても種々雑多で、あらゆる段階の宗教を包含する多様性を示す。その時に応じて祭祀の対象となる特定神格を最高神視する交替神教で、業(カルマ)に基づく輪廻と、それからの解脱を説き、最高実在ブラフマンとアートマン(我)との合一によって解脱にいたる方法を説く。インド教。バラモン教。
改訂新版 世界大百科事典 「ヒンドゥー教」の意味・わかりやすい解説
ヒンドゥー教 (ヒンドゥーきょう)
Hinduism
本来,渾然とした宗教・文化の複合体に対する便宜的な呼称であり,明快な定義を与えることは不可能である。〈ヒンドゥーHindu〉とは,今日のパキスタンを流れるインダス川(サンスクリットでSindhu)の名称に起源をもつペルシア語であり,〈インダス川の流域の人々〉を意味したが,インド(この場合現在のインド(バーラト)のみならず,その近隣諸国をも含むインド亜大陸といわれる地域)に侵入して来たイスラム教徒が自分たちと宗教を異にするインダス川の流域の原住民をヒンドゥーと呼び,〈インド人〉を意味するにいたった。これが英語などのヨーロッパ語にも採り入れられて,ヒンドゥーの宗教・文化を指すのにイズムを付し,ヒンドゥイズムという語がつくられた。ヒンドゥー教はこの語の邦訳である。しかしこの語に正確に対応するインドの言葉はない。ヒンドゥー教徒の中には,自分たちの宗教を〈サナータナ・ダルマSanātana-dharma(永遠の法)〉とか〈バイディカ・ダルマVaidika-dharma(ベーダの法)〉と呼ぶ人もいるが,それほど一般的とはいえない。
ヒンドゥー教という語は,しばしばバラモン教と区別して使用されることがある。この場合には,バラモン教は仏教興起以前に,バラモン階級を中心に,ベーダ聖典に基づいて発達した宗教を指す。他方ヒンドゥー教は,およそ前6~前4世紀に,ベーダ文化の枠組みが崩壊して,バラモン教が土着の民間信仰などを吸収して大きく変貌を遂げた形のものを指している。しかし両者はまったく別のものというわけではなく,広義にヒンドゥー教という語を用いる場合には,バラモン教をも内に含んでいる。
ヒンドゥー教は,日本の原始神道と同じく特定の教祖によって創始されたものではなく,インドの地にいわば自然に生まれたものである。ヒンドゥー教を意味する適当な言葉がインドの諸言語にないという事実が示唆するように,ヒンドゥー教は個人個人によって意識された信仰の体系であるというよりも,むしろ宗教的な観念や儀礼と融合した社会習慣的性格を多分にもっている。入信や改宗によってヒンドゥー教徒となるのではなく,ヒンドゥー教徒の子として生まれることが,ヒンドゥー教徒の資格を得ることにほかならない。このような性格は,ヒンドゥー教が,仏教やキリスト教などの世界宗教に対して,ユダヤ教などとともに民族宗教と呼ばれる理由の一つである。しかしヒンドゥー教がインドを越えて伝播したこともあり,またそのインドそのものがヨーロッパに匹敵する一つの世界であるなどの理由で,民族宗教であるということに疑義をさしはさむ学者もいる。ヒンドゥー教は複雑多様な複合体であって,いわゆる〈宗教〉という言葉の意味を逸脱している。神あるいは絶対者をとってみても,ヒンドゥー教は一元論も一神教も,二元論も多神教も,はては無神論をもその中に含んでいる。ヒンドゥー教は,キリスト教などが排他的性格をもっているのと対照的に,途方もないほどの包摂力をもち,あらゆるものを吸収し,成長する。したがってヒンドゥー教は,ピラミッドの頂点に立つ極度に発達した哲学体系からその底辺にある最も原始的な信仰や呪術をもその中に取り込んでいる。ヒンドゥー教は高度の神学や倫理の体系を包括しているばかりではなく,カースト制度やアーシュラマ(生活期)制度をはじめ,人間生活の全般を規定する制度,法制,習俗などを内包している。ヒンドゥー教は宗教というよりもむしろ生活法a way of lifeであるといわれるのも,以上のような性格に由来している。
歴史
前2300-前1800年を中心に,現在のパキスタンの領内にあるモヘンジョ・ダロとハラッパーを二大中心地としてインダス文明が栄えていたが,この文明の終末とほぼ同じころアーリヤ人が西北インドに進入し,この文明の遺跡の近く,パンジャーブ(五河)地方に定着して,前1200年を中心に《リグ・ベーダ》を編纂した。その後,前500年ころまでに主要なベーダ聖典が編纂され,バラモン階級を頂点とするバラモン教の全盛時代を迎えた。しかし前500年ころになると,社会的大変動を背景に,反バラモン教的自由思想家が輩出し,仏教,ジャイナ教が成立した。まだ仏教が宗教・思想界の主流をなしていた前2~後3世紀ころ,ベーダ文化の枠組みが崩壊して,バラモン教が土着の非アーリヤ的民間信仰,習俗などの諸要素を吸収し,大きく変貌を遂げてヒンドゥー教が成立するにいたった。
ヒンドゥー教は,バラモン教を基盤としているとはいえ,次のような過程を経て,今日見られるヒンドゥー教が形成された。(1)哲学諸体系の形成と《マハーバーラタ》やその一部をなす《バガバッドギーター》,東南アジア一帯にも大きな影響を与えた《ラーマーヤナ》,またヒンドゥー法典の基盤である《マヌ法典》など,ヒンドゥー教の中核を成す聖典の成立(紀元前後以降),(2)宗派の成立(1~2世紀以降),(3)強いバクティ思想の台頭(600-800以降),(4)タントリズムの形成(800以降),(5)イスラムの浸透(13世紀以降),(6)イギリスの支配,キリスト教の伝播,西洋文明との接触(1800以降)。
聖典
ヒンドゥー教の聖典は実に膨大な数と量に及んでいるが,コーランや聖書ほどの地位と権威をもつ聖典はない。聖典の中で最も根本的で最も古い聖典はベーダである。ヒンドゥー教徒はベーダに対して絶対的な権威を認めて〈天啓聖典(シュルティ)〉と呼び,人間によっても神によっても作られたものではなく,いにしえの聖仙が神秘的霊感によって感得した啓示であると考えている。しかしそれはいわば名目的であって,すべてのヒンドゥー教徒が,つねに等しく絶対的なものとして尊崇してきたわけではなく,今日においてはこれを読みうるヒンドゥー教徒はほんのわずかにすぎない。ヒンドゥー教徒にとって,天啓聖典に次ぐ権威を与えられている文献群に〈古伝書(スムリティ)〉がある。これは聖賢の著作と考えられており,次のような聖典を含んでいる。(1)インドの国民的二大叙事詩《マハーバーラタ》(〈バラタ族の戦争を語る大史詩〉の意)と《ラーマーヤナ》(〈ラーマ王行伝〉の意) 前者は,伝説では仙人ビヤーサに帰せられ,前10世紀ころ西北インドに起こったと推定されるバラタ族親族間の大戦争の記憶に基づき,約10万頌からなる(ホメロスの二つの叙事詩のおよそ8倍)長編である。後者はインド最初の詩人バールミーキの作とされ,もと東インドに伝わった悲劇のラーマ王子の愛と戦争の物語に題材をとったと推定され,前者のおよそ4分の1の分量ではあるが,美文調文学の嚆矢とされるほどに文体は洗練されている。両叙事詩のインドの宗教,文化に与えて来た影響は量りしれないものがある。ヒンドゥー教の聖典中,今日でも最も愛唱され尊崇されている《バガバッドギーター》は前者の一部である。(2)プラーナ(〈古譚〉の意) 自ら〈第五のベーダ〉と称し,一般大衆のヒンドゥー教に関するいわば百科事典ともいえる聖典である。宗派的色彩が濃厚で,だいたいビシュヌ派か,シバ派のいずれかに属している。18の大プラーナと18の副プラーナとが現存しているが,なかでも《ビシュヌ・プラーナ》と《バーガバタ・プラーナ》とがとくに尊重されている。(3)法典 法典中の白眉といわれる《マヌ法典》をはじめ,ヒンドゥー教徒の日常の行動を規定する多数の法典がある。法典における法の概念はかなり広く,今日の法律的規定とみなされるものはそのほんの一部にすぎず,宇宙創造説,ヒンドゥー教の諸教養,一生を通じて行うべき通過儀礼,種々の義務や贖罪などをも含んでいる。このほかに,天啓聖典にも古伝書にも入れられていないが,重要な文献が数多く存在している。その一つは,ヒンドゥー教の最も高度な哲学的思弁を示す哲学的諸文献である。ヒンドゥー教の代表的な哲学体系は6種あり,各体系はそれぞれの基本的文献をもち,それに対してたくさんの注釈文献が残されている(六派哲学)。ヒンドゥー教の各宗派の基盤となる聖典も編纂され,ビシュヌ派的な性格をもつ〈サンヒター〉,シバ派的な性格をもつ〈アーガマ〉,タントリズム的性格をもつ〈タントラ〉と称する聖典が成立した。これらのものはすべて雅語であるサンスクリット(梵語)で書かれた文献であるが,それ以外の言葉で書かれた聖典も数多く存在している。たとえばヒンディー語で書かれたカビール(1440-1518)の宗教詩やトゥルシーダース(1532-1623)の《ラーム・チャリット・マーナス》,マラーティー語で書かれたナームデーオ(15世紀前半)やトゥカーラーム(1608-49)の宗教詩,南インドのタミル語で書かれた《ティルムライ》,俗に〈タミル・ベーダ〉といって貴ばれる賛歌集など,枚挙にいとまがない。
神格
ヒンドゥー教が本来多神教であり,複雑な複合体であることを反映して,神格も多種多様である。強大な勢力をもつ神から,山川草木に至るまでが崇拝の対象になる。また時代によっても変遷がある。たとえば,《リグ・ベーダ》の時代に有力であり,人々に最も愛好された武勇神インドラ(仏教に入って帝釈天となる)や人々に恐れられた司法神バルナ(仏教に入って水天となる)などは,次の時代には勢力を失った。今日のヒンドゥー教で,インド全域にわたって崇拝されている神はビシュヌとシバとである。ヒンドゥー教はこのほかにブラフマー神(梵天)を加えた三つの神格を中軸として発達してきており,ブラフマー神は宇宙の創造を,ビシュヌ神は宇宙の維持を,シバ神は宇宙の破壊を任務としていると信じられている。しかしブラフマー神は中世以降勢力を得ることができず,他の2神を中心に展開してきている。そのうちビシュヌ神は元来太陽神で,ベーダ時代にはあまり目だたない存在であったが,大叙事詩以来主要神格の一つとされ,とくに慈愛に満ちた神として崇拝される。女神ラクシュミー(仏教で吉祥天となる)を妃とし,十種の化身(アバターラ)を現して人類を救済するという。その化身には,魚,亀,猪,人獅子,小人バーマナ,斧を手にするラーマ,ラーマ,クリシュナ,仏陀,カルキがあり,最も重要な化身は《バーガバタ・プラーナ》などの中で活躍するクリシュナである。叙事詩《ラーマーヤナ》の主人公であるラーマはそれに次いで重要である。仏教の開祖仏陀も,ビシュヌ神の第9番目の化身とされていることは注目に価する。カルキは,未来の救済者で,仏教の将来仏である弥勒仏の影響があるといわれている。シバ神はベーダ時代の恐ろしい暴風神ルドラを起源としている。彼は二つの面を同時にもっている。破壊者としてのシバ神は,いっさいを破壊する時間マハーカーラ(日本では七福神の一つである大黒天となる)として恐れられ,他方ではその名シバ(〈吉祥〉の意)が示すように,恩恵を与える神として崇拝される。彼はヒマーラヤ山中にあるカイラーサ山でヨーガの修行を行う苦行者であり,美しい女神パールバティーを妃とし,ガネーシャ(日本で聖天となる)とスカンダ(日本で韋駄天となる)を息子とし,牡牛ナンディンを乗物としている。彼はまた生殖をつかさどりしばしば円筒形の男根,リンガの形で崇拝される。南インドでは,ナテーシュバラ(舞踏者の神)と呼ばれ,演劇の保護者として崇敬されている。ヒンドゥー教の本質は多神教であるが,ヒンドゥー教の中のビシュヌ派に属する者は,ビシュヌ神が最高唯一の神であって,シバ神はビシュヌ神から開展したものであるとみなす。シバ教徒は逆に,ビシュヌ神をシバ神から開展したものと考える。この傾向は,ときとして両派に摩擦を起こさせるが,しかし寛容の精神から両派を調和させる努力もなされている。すなわち,ビシュヌ神とシバ神とは同一神の別名にほかならない,と主張されることもあり,さらにまた宇宙の最高原理がブラフマー神として創造し,ビシュヌ神としてこれを維持し,シバ神としてこれを破壊するとする〈三神一体(トリムールティ)〉の説が表明されることもある。女神は非常に古くから崇拝されてきてはいるが,ヒンドゥー教のパンテオンの中で重要な位置を占めるに至るのは中世になってからである。とくにシバ神の妃であるパールバティーは有力であり,慈愛に満ちた側面を示すときには,マハーデービー(大女神),サティー(貞女),ガウリー(白女)などと呼ばれ,恐ろしい側面を現すときにはドゥルガー(近寄り難い者),カーリー(黒女),チャンディー(恐ろしい女)などと呼ばれる。そのほか,多数の神々が崇拝され,なかにはクベーラ(バイシュラバナ。日本では毘沙門天,多聞天となる),サラスバティー(弁才天といわれる)などのように,日本で崇拝されている神々もある。またヤクシャ,ガンダルバなどの半神半人,牛,猿などの動物,シェーシャなどの蛇,アシュバッタ樹やトゥルシーなどの草木,カイラーサ山などの山,ガンガー(ガンジス)川などの河川やワーラーナシーなどの聖地の崇拝,ブートなどの精霊崇拝も見のがすことはできない。
宗派
ヒンドゥー教でもその展開の過程において宗派が生じたが,その多神教的性格を反映し,異なった宗派は異なった主神を中心とするグループとして現れた。大部分の宗派はビシュヌ派とシバ派の二つのグループに分けられる。今一つの重要なグループとしてシャクティ派(性力派)があるが,これもいわばシバ派の特殊な発展と考えられる。
(1)ビシュヌ派はビシュヌ神を主神とし,神への信愛(バクティ)を強調する。バーガバタ派を核とするが,マドバ派,バッラバーチャーリヤ派,チャイタニヤ派などはこの系統に属する。また聖典〈サンヒター〉を伝持するパンチャラートラ派の流れを汲むものにシュリー・バイシュナバ派,ラーマーナンダ派,カビール派などがある。シク教もこの流れの発展したものである。(2)シバ教はシバ神を主神とするグループでカーパーリカ派,パーシュパタ派,シバ聖典派,リンガーヤタ派(またはビーラ・シャイバ派)などがこれに属する。(3)シャクティ派はシバ神の妃ドゥルガーまたはカーリーを崇拝するグループで,タントラ派といわれることもあるが,シャクティ派とタントラ派とは必ずしも同義語ではない。しかし前者は後者の代表である。シバ神は宇宙の根本原理ブラフマンと同一視され,まったく非活動的であるが,神妃ドゥルガーは活動面を象徴するようになり,その活動力をシャクティ(性力)と称し,それに基づく救済を説く。この派は仏教の中の密教に大きな影響を与えた。しかしヒンドゥー教の場合には,宗派といっても漠然としたものであり,組織化された教団,教会と呼べるほどのものではない。また,ヒンドゥー教寺院はインド各地に無数に存在しているが,それぞれ独立したものであってそれらを統括する横の組織がない。社会的組織はカーストによって代用されているように思われる。中世インドにおけるイスラム,とくにイスラム神秘主義(スーフィズム)の浸透は,16世紀ころから,ヒンドゥー教に,ヒンドゥー教とイスラムとの融合と宗教改革の気運を生み,カビール道派やシク教などが成立した。その後ムガル王朝が滅亡し,1858年インドがイギリスの直轄植民地となり,キリスト教や西洋の思想文物との直接接触などを契機として,19世紀から20世紀にかけて,ヒンドゥー教には再び宗教改革あるいはルネサンスと呼ばれる大きな変動が起こり,新しい宗派が成立した。1828年カルカッタに設立されたブラフマ・サマージがヒンドゥー教改革運動の先駆となった。その後,プラールタナー・サマージ,アーリヤ・サマージ,神智協会(神智学),国際的に活躍しているラーマクリシュナ・ミッション,シュリー・ナーラーヤナ法普及協会などが設立された。
思想
ヒンドゥー教はドグマをもたないといわれることがある。これは妥当ではあるが,ヒンドゥー教がまったく教義をもたないということではない。実際は,考えうるあらゆる種類の,しばしば相矛盾した思想・教義すらも説かれているのである。そのいずれもがヒンドゥー教の教義であり,その中のいずれか一つあるいは若干を取り出してヒンドゥー教の教義であるということは必ずしも妥当であるとはいえない。相互に論争があるとはいえ,多種多様な教義が同時に併存することができ,他の宗教に往々にして見られるような正統と異端をめぐる厳しい対立・抗争とは無縁であるという意味において,ヒンドゥー教はドグマをもたないのである。ヒンドゥー教のこの性格は,その教義を総括的に概観することを困難にしているが,ヒンドゥー教にとって中心的であり,かつできる限り広く容認されていると目される思想のみに焦点を当てることにしたい。
(1)宇宙観 宇宙の創造には種々の説がある。絶対者ブラフマンが遊戯(リーラー)のために宇宙の創造を行ったとしたり,あるいはまた,この現象世界はブラフマンの幻力(マーヤー)によって現出されたもので,本来は幻影のように実在せず,ブラフマンのみが実在するにすぎないと説かれることもある。また梵天の卵の中でブラフマー(梵天)が活発となって宇宙を創造し,次いで動物,神,人間などを創造したとも説明される。この宇宙の上半分と下半分とにそれぞれ七つの階層があり,両者の中間に大地がある。大地はメール山(須弥山)を中心とする円盤であり,七つの大陸と七つの海をもつ。真中に神々が住むメール山がそびえ立つ大陸がジャンブ・ドビーパと称され,その重要部分がバーラタバルシャ,すなわちインドである。この宇宙は梵天の1日の間,すなわち,カルパ(劫,地上の43億2000万年)の間持続し,1日が終われば再び宇宙は梵天に帰入する。これは梵天の夜で,昼間と同じ期間続く。宇宙はカルパごとに創造と帰滅を繰り返す。1カルパは1000マハーユガに相当し,1マハーユガはクリタユガ,トレーターユガ,ドバーパラユガ,カリユガから成り,後のユガは前のユガよりも人間の信仰・道徳性などにおいて低下しており,現在は前3102年に始まった暗黒期にあたるカリユガに当たっており,この期の終りに大帰滅が起こるといわれている。
(2)業と輪廻 人間は死んで無に帰するのではなく,各自の業のために,来世において再び新しい肉体を得る。このように生死を無限に繰り返す。これが輪廻である。現在の苦しみに満ちた人生も,無限の過去から永遠の未来にわたって続く生存の一こまにほかならない。業とは,サンスクリットのカルマンkarmanの訳語である。これは行為を意味するが,業の説によれば,あらゆる行為は,それが身体による行為であろうと,言語活動であろうと,精神活動による行為であろうと,必ずなんらかの結果の原因となるものである。業は,その行為者が,その結果を経験しない限り消失しない。各自は過去世で行った業の結果として,現在の人間としての肉体をもっているが,その肉体を生み出した業の結果を経験し尽くしたとき,死とともに肉体は滅する。しかし現世で生きている間に行って蓄積した業は滅しない。各自の内にある霊魂(アートマン)は不滅であり,死に際して目に見えない微細な身体を得,各自の業を伴って次の生存に赴くのである。その業が善業であるか悪業であるかによって,霊魂が来世で得るべき身体が,神であるか,人間であるか,動物であるか,地獄の存在であるかが決定される。現在の各自の性格や,階級や,幸・不幸などのいっさいは,過去に行った業の果報にほかならない。業・輪廻の思想はウパニシャッドのなかで初めて明確な形を取り,ヒンドゥー教の中核的な教義となったが,本来運命論や決定論とは本質を異にしている。
(3)法(ダルマ) これは元来〈たもつ〉〈支持する〉を意味する動詞の語根から作られた名詞で,〈習慣〉〈風習〉〈義務〉〈善〉〈徳〉〈真理〉〈教説〉〈宗教〉など多くの意味をもっているが,簡単にいえば〈行為の規範〉である。ヒンドゥー教にはこのようなダルマをまとめた法典群があり,人の生活の全般にわたって規定しているが,その中心的課題は〈種姓法〉と〈生活期法〉である。種姓法はバラモン,王族,庶民,隷民の4階級(バルナ)のおのおのに課せられた法である。生活期法は学生期,家住期,林棲期,遊行期という人生の4時期(アーシュラマ)のおのおのについて規定されている規範である。ヒンドゥー教徒は各自の生まれた種姓と,現に属する生活期に対して規定された法を実行しなければならない。しかも各自に課せられた法を,事の成否や利害を考慮することなく,利己心を離れて実践することが勧められている。今日では生活期の制度はほとんど実行されていないが,今なおヒンドゥー教徒の人生の理想と考えられている。種姓制度はカースト制度と結びついて,今日も農村社会を中心に根強いものがある。ダルマの実践は,物質的・経済的利益を追求する実利(アルタ),愛情・性愛を追求する愛欲(カーマ),および次に説明する解脱とともにヒンドゥー教徒の人生の四大目的とされている。
(4)解脱 法,実利,愛欲はたとえ実現されたとしても,得られる結果はせいぜい天界に生まれることが最高の果報であり,結局,輪廻の中にとどまっているにすぎない。そこでウパニシャッドの思想家たちはさらに進んで,業・輪廻からのまったき自由,すなわち解脱(モークシャ)を追求するにいたり,解脱が人生の最高の目的とされた。それを実現する方法として,行為の道,知識の道,信愛(バクティ)の道という三つの道が説かれ,とくに信愛の道は万人に実践可能であり,7~8世紀ころから大きな宗教運動となって展開し今日にいたっている。
業,輪廻,解脱の問題は,一般のヒンドゥー教徒にとって切実な問題であったばかりではなく,思想家たちにとっても重要な課題であった。種々事情を異にするとはいえ,ヒンドゥー教の頂点を形成する六つの代表的哲学体系(六派哲学),サーンキヤ,ヨーガ,ニヤーヤ,バイシェーシカ,ミーマーンサー,ベーダーンタが成立し,理論的・体系的に解脱とその方法を考究した。なかでもウパニシャッドに立脚するベーダーンタはインド思想の主流を形成し,現代のインドの知識人の代表的な哲学となっている。
生活
ヒンドゥー社会の基礎をなしているのは,先に言及した種姓制度,カースト制度であるが,そのほかにゴートラの制度がある。すべてのバラモンはある聖仙(リシ)の子孫とされ,ゴートラはその聖仙にちなんで命名されている。同一の聖仙の子孫は同じ氏族に属するとされ,同一氏族同士の婚姻を禁じている。これは本来バラモンの制度であるが,王族,庶民にも受け入れられ,同一のゴートラに属するものの間の結婚を禁止している。他方カースト制度は族内婚を規定しているが,サピンダすなわち父の家系で7代,母の家系で5代以内の親族の間での結婚は禁じられている。個人の一生は,生活期の制度によって,理想的には学生期,家住期,林棲期,遊行期の4時期に分けられている。ヒンドゥー教徒の挨拶は一般に時間に関係なく,お互いに合掌して〈ナマス・テー〉(〈あなたに敬礼する〉の意)という。男子のヒンドゥー教徒は,伝統的な人は今日でも頭頂に少し髪を残している。この髪をちょんまげのように束ねたものをシカー(またはチューダー)という。女性はクンクムと称する印を額につける。また寺院に参拝したときに,バラモン僧が祝福の印としてクンクムをつけてくれることがある。また男性はビャクダンまたはサフランの粉末を油で練って,煤を混ぜて黒色にしたティラクと称する印を額に付けることもある。伝統的には,とくにバラモンの高僧に会うときには,男子はドーティと称するインド服を,女子は1枚の縫目の無い布から作られたサリーを着用する。バラモンは非暴力の精神から菜食主義を守り,とくに牛の崇拝から牛肉を忌避する。ヒンドゥー暦は太陰暦であり,今日もなお宗教的目的に使われている。紀元にはビクラマ紀元(前58),シャカ紀元(78),グプタ紀元(320),ハルシャ紀元(606)などがあるが,北インドではビクラマ紀元が最もよく使われた。
儀礼
ヒンドゥー教では偶像崇拝が盛んで,毎朝,川や貯水池などで沐浴してシバ神などの神像を礼拝してから食事をする。ベーダの儀式はヤジュニャといわれるが,ヒンドゥー教の儀式はプージャー(供養)である。ちょうどたいせつな客人を扱うように,神像の座位を水で清め洗足を行い,花やベーテルの葉を供える。朝,音楽,ベルの音,ホラガイの音で神像を目覚めさせ,洗って後着物を着せ,花,花環,香,灯火で敬意を表し,食物を供え,夜には神妃のいる寝室に移す場合もある。ときとして神像の前でヤギなどが犠牲にされることがある。儀礼には念珠を用い,マントラ(神歌)が唱えられ,御詠歌に似たバジャンが熱狂的に歌われることもある。またヤントラという象徴的・神秘的図形が用いられ,卍(まんじ)がスワスティカー(幸福の印)として使われ,儀式を行うためにマンダラ(曼荼羅)と称する一定の円形の場所を設ける場合もある。宗教的なめでたさ(吉祥)の象徴として種々の花が用いられるが,とくに蓮華はその代表である。ヒンドゥー教徒はまた聖地を崇拝し,聖地巡礼を行う。聖地は多数あるが,なかでも北のドバーラカー,西のワーラーナシー,東のジャガンナート,南のラーメーシュワラの四つが主要なものである。インドには,無数といってよいほどの寺院があり,現在も造られつつあり,また僧院(マタ)やアーシュラム(道場)もある。
儀礼の中でも,個人の一生を通じて行うべきおよそ40にも達するサンスカーラと呼ばれる通過儀礼,とくに誕生祭,男子が正式にヒンドゥー社会の一員となる入門式,結婚式,葬式は重要である。家庭内の儀礼としては,家住期に毎日行うよう規定されている宇宙の根本原理ブラフマンのためにマントラ(真言)を唱えるブラフマン祭,いっさいの神々の供養を行うバイシュバデーバ祭,いっさいの生物に供物を与えるバリ供養,祖霊を供養する祖霊祭,客人を供養するアティティ祭という〈五大祭〉が中心をなしている。年間に行われる祭りの数は多数に上るが,代表的な諸神をまつる春の祭ホーリー(2~3月),とくにベンガルで盛んなドゥルガー女神の祭ドゥルガー・プージャー(9~10月),ラーマ王子が悪魔ラーバナを征伐した記念のダシャハラー祭(10月),灯火をともし,ラクシュミー女神をまつる灯火祭ディーワーリー(10~11月)などが主要なものである。これらのほかに,ケーララ地方には収穫の祭オーナム,南インドの収穫祭ポーンガルなど地方的な祭りもある。またインド各地では音楽とともに《マハーバーラタ》などの聖典を読誦解説するハリ・カターやプラバチャナも行われている。
伝播と現状
ヒンドゥー教は民族宗教的性格が濃厚ではあるが,インドの商人や移民とともにインドを越えて伝播していった。インドの商人などが香料を求めてインドネシアのスマトラ,ジャワなどの島に行ったのは西暦紀元の初めといわれるが,今日ジャワ諸島に残っているボロブドゥールなどの多数の遺跡はヒンドゥー教や仏教の混交した当時の宗教を示唆している。またバリ島では今でもヒンドゥー教が信奉され,200万の信徒がいるという。おそらく4世紀ころからネパールのカトマンズ渓谷にヒンドゥー教と仏教の混交文化が発展し始め,現在のネパール王国はヒンドゥー教を国教としている。またスリランカには総人口の18%を占めるヒンドゥー教徒がおり,その大部分は南インド,タミル・ナードゥ州からの移民であるといわれる。1991年の国勢調査によると,インド(バーラト)のヒンドゥー教の信徒数は,その総人口の82%に相当する7億1434万人である。
執筆者:前田 専学
音楽
ヒンドゥー教音楽は,バクタ(信仰者)によるバクティ運動(バクティ)と称される,民衆化の動きに端を発している。このバクティ運動は,タミルの土地で早くから大衆の前にひらけ,アールワールと呼ばれる詩人たちの,ビシュヌ神に対する情熱的な信仰の表明として,タミル語で歌われた。これらはプラバンダprabandhaと呼ばれる。ベンガル地方では,チャイタニヤが現れ,ラーダーとクリシュナとの愛を主題としたキールタンKīrtanの歌によって多くの信徒を集めた。太鼓,シンバル,一弦琴などに合わせて自ら歌い踊る詠歌行進であった。北インドでは,神の唱名を繰り返す唱歌から発達したバジャンによって信仰が広められた。女流詩人ミーラー・バーイー(1498ころ-1563ころ)は,シバ信仰の家柄に生まれたが,クリシュナへの信仰に篤く,神の前に座し,神に話しかける形の,地方語で書かれた詩はたいへん美しく,現在なお愛唱されている。また有名なトゥルシーダース,カビールなどもバジャンの音楽様式の発展に大きく貢献している。現在はキールタンもバジャンも芸術歌曲としての地位を占めるが,その根本は宗教歌である。
ヒンドゥー教音楽としては,以上のアールワールのプラバンダ,キールタン,バジャンのほかに,一般に,ベーダ聖典に基づく典礼音楽である《サーマ・ベーダ》の詠唱もこれに含められる。いずれにせよ,インドの一般の生活においては,宗教と世俗との区別はつけられず,芸術音楽においても,バウルと呼ばれる吟遊詩人による音楽,民謡などにおいても,信仰の姿勢が保たれている。
執筆者:島田 外志夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヒンドゥー教」の意味・わかりやすい解説
ヒンドゥー教
ひんどぅーきょう
Hinduism
インドで信奉されている宗教の一つ。インド教といわれる場合もある。本来、宗教・文化の渾然(こんぜん)とした複合体に対する便宜的な呼称であり、正確な定義を与えることは不可能。「ヒンドゥー」Hinduとは、インダス川の名称に起源をもつペルシア語であり、「インダス川の流域の人々」を意味したが、のち「インド人」を意味するに至った。これが英語などにも取り入れられて、ヒンドゥーの宗教・文化をさすのにヒンドゥイズムという語がつくられた。ヒンドゥー教はこの語の邦訳である。
[前田専學]
特質
広義のヒンドゥー教はバラモン教をも内に含んでいるが、ヒンドゥー教という語はバラモン教と区別して使用されることがある。この場合には、バラモン教は、仏教興起以前にバラモン階級を中心にベーダ聖典に基づいて発達した宗教をさす。他方、ヒンドゥー教は、紀元前6~4世紀にベーダ文化の枠組みが崩壊し、バラモン教が土着の民間信仰などを吸収して大きく変貌(へんぼう)した形のものをさしている。しかし両者はまったく別のものというわけではない。ヒンドゥー教は多神教であり、特定の開祖をもたず、その起源も明確ではなく、自然に形成されたもので、宗教的な観念や儀礼と融合した社会習慣的性格を多分にもつ。一般に民族宗教といわれるが、インドを越えて伝播(でんぱ)したこともあり、またインドそのものがヨーロッパに匹敵する一つの世界であるなどの理由で、それを否定する学者もいる。ヒンドゥー教は、途方もないほどの包摂力をもち、極度に発達した哲学体系から、もっとも原始的な信仰や呪術(じゅじゅつ)をもそのなかに取り込んでいる。そのうえに、カースト制度やアーシュラマ(生活期)制度をはじめ、人間生活の全般を規定する制度、法制、習俗などを内包している。ヒンドゥー教はおよそ「宗教」という概念を逸脱している。
[前田専學]
沿革
インダス文明が現在のパキスタンの領内にあるモヘンジョ・ダーロとハラッパーを二大拠点として紀元前2300~前1800年を中心に栄えていた。しかし紀元前1500年ころアーリア人が西北インドに進入、パンジャーブ(五河)地方に定着し、紀元前1200年を中心に聖典『リグ・ベーダ』を編纂(へんさん)した。その後、紀元前500年ころまでに主要なベーダが編纂され、バラモン教の全盛時代を迎えた。しかし紀元前500年ころ、社会的大変動の結果ベーダ文化の枠組みが崩壊して反バラモン教的自由思想家たちが輩出し、仏教やジャイナ教が成立した。仏教が宗教・思想界の主流をなしていた紀元前2~後3世紀ころ、バラモン教が土着の非アーリア的民間信仰・習俗などの諸要素を吸収し、大きく変貌を遂げてヒンドゥー教が成立した。ヒンドゥー教はバラモン教を基盤としてはいるが、(1)固有の聖典の編纂と哲学諸体系の成立(紀元前後以降)、(2)宗派の成立(紀元1~2世紀以降)、(3)強いバクティ(信愛)思想の盛行(600~800年以降)、(4)タントリズムの形成(7世紀以降)、(5)イスラム教の浸透(13世紀以降)、(6)イギリスの支配、キリスト教の伝播、西洋文明との接触(1800年以降)、などの過程を経て、今日みられるヒンドゥー教が形成された。
1971年の国勢調査によると、インド共和国のヒンドゥー教徒は総人口の82.72%(4億5329万人)に達しているという。インドは世俗国家であるが、同じく国民の多数がヒンドゥー教徒であるネパールでは2006年までヒンドゥー教を国教としていた。インドネシアのバリ島では200万のヒンドゥー教徒がおり、またスリランカではヒンドゥー教徒が総人口の18%(約277万人)を占めている。
[前田専學]
聖典
聖典中最古のものはベーダである。ヒンドゥー教徒はベーダに対して絶対的な権威を認めて「天啓聖典」とよぶが、それはいわば名目的であって、すべてのヒンドゥー教徒がつねに等しく絶対的なものとして尊崇してきたわけではない。コーランやバイブルほどの絶対的権威をもつ聖典をもたないが、膨大な数と量の聖典を編纂した。天啓聖典に次ぐ権威を与えられている聖典に「古伝書」があり、次のようなものを含む。
(1)インドの国民的二大叙事詩『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』。今日もっとも愛唱・尊崇されている『バガバッド・ギーター』は前者の一部である。
(2)一般大衆のヒンドゥー教に関するいわば百科事典ともいえる聖典『プラーナ』。
(3)『マヌ法典』をはじめとする多数の法典。
このほかにも重要な文献が数多く存在している。その一つは、ヒンドゥー教のもっとも高度な哲学的思弁を示す多数の哲学的諸文献である。また「サンヒター」「アーガマ」「タントラ」という、それぞれビシュヌ派的、シバ派的、タントリズム的性格をもつ、中世以降のヒンドゥー教の各宗派の基盤となる聖典も編纂された。これらのものはすべて雅語であるサンスクリット語(梵語(ぼんご))で書かれた文献であるが、それ以外のことばで書かれた聖典も数多く存在している。
[前田専學]
神々
ヒンドゥー教では、強大な勢力をもつ神々から、山川草木に至るまでが崇拝の対象になり、また時代によっても変遷がある。たとえば、『リグ・ベーダ』の時代に有力であった武勇神インドラ(仏教で帝釈天(たいしゃくてん))や司法神バルナ(水天)などは、次の時代には勢力を失った。今日のヒンドゥー教でインド全域にわたって崇拝されている神はビシュヌ神とシバ神とである。ヒンドゥー教はこのほかにブラフマー神(梵天(ぼんてん))を加えた三つの神格を中軸として発達してきた。しかしブラフマー神は中世以降勢力を得ることができなかった。そのうちビシュヌ神は元来太陽神で、大叙事詩以来主要神格の一つとされ、女神ラクシュミー(吉祥(きちじょう)天女)を妃とし、10種の化身(けしん)を現して人類を救済するという。もっとも重要な化身はクリシュナとラーマで、仏教の開祖仏陀(ぶっだ)(釈迦(しゃか))も、その9番目の化身とされている。シバ神は暴風神ルドラを起源とし、破壊者としてのシバ神は、いっさいを破壊する時間マハーカーラ(日本では七福神の一つである大黒天)として恐れられ、他方では恩恵を与える神として崇拝される。美しい女神パールバティーを妃とし、ガネーシャ(日本で聖天(しょうてん))とスカンダ(日本で韋駄天(いだてん))という息子をもつ。生殖をつかさどり円筒形の男根リンガの形で崇拝される。
ヒンドゥー教の本質は多神教であるが、ビシュヌ神とシバ神とは同一神の別名にほかならないと主張されることもあり、さらにまた、宇宙の最高原理がブラフマー神として創造し、ビシュヌ神としてこれを維持し、シバ神としてこれを破壊するとする「三神一体」の説が表明されることもある。女神は非常に古くから崇拝されてきてはいるが、重要な位置を占めるに至るのはタントリズムが盛行する中世になってからである。とくにパールバティーは有力であり、ドゥルガー(近寄りがたい者)、カーリー(黒女)などともよばれる。そのほか多数の神々が崇拝され、サラスバティー(弁才天)などのように、日本で崇拝されている神々もある。またヤクシャ、ガンダルバなどの半神半人、ウシ・サルなどの動物、シェーシャなどのヘビ、アシュバッタ樹やトゥラシーなどの草木、カイラーサ山などの山、ガンジス川などの河川やワーラーナシなどの聖地、ブートなどの精霊崇拝も見逃すことはできない。
[前田専學]
宗派
ヒンドゥー教では、異なった宗派は異なった主神を信奉するグループとして現れた。大部分の宗派はビシュヌ教とシバ教の二つのグループに属する。いま一つの重要なグループとしてシャクティ派(性力派)があるが、これもいわばシバ教の特殊な発展と考えられる。
(1)ビシュヌ教はビシュヌ神を主神とする。そのうち、バーガバタ派の系統に属するものにマドバ派、バッラバーチャーリヤ派、チャイタニヤ派などがある。またパンチャラートラ派の流れをくむものにシュリーバイシュナバ派、ラーマーナンダ派、カビール派などがある。シク教もこの流れの発展したものである。
(2)シバ教は、シバ神を主神とし、カーパーリカ派、シバ聖典派などがこれに属する。
(3)シャクティ派は、女神ドゥルガーまたはカーリーの活動力をシャクティ(性力)と称し、それに基づく救済を説く。
しかしヒンドゥー教の場合には、宗派といっても漠然としたものであり、組織化された教団・教会とよべるほどのものではない。16世紀ころから、ヒンドゥー教に、イスラム教との融合と宗教改革の気運が生じ、カビール道派やシク教などが成立した。1858年インドがイギリスの直轄植民地となり、キリスト教や西洋の思想文物との接触などを契機として、19世紀から20世紀にかけて、ヒンドゥー教にはふたたび宗教改革あるいはルネサンスとよばれる大きな変動が起こり、ブラフマ協会、アーリヤ協会、ラーマクリシュナ・ミッション、シュリー・ナーラーヤナ法普及協会などが設立された。
[前田専學]
教義と実践
ヒンドゥー教では、あらゆる種類の、しばしば相矛盾した思想・教義すらも説かれ、そのいずれもがヒンドゥー教の教義であり、他の宗教に往々にしてみられるような正統と異端をめぐる厳しい対立・抗争とは無縁である。このために、その教義を概観することはきわめて困難であるが、ヒンドゥー教にとって中心的であり、かつできる限り広く容認されていると目される思想のみに焦点をあてることにしたい。
[前田専學]
宇宙観
宇宙の創造には種々の説がある。絶対者ブラフマンが遊戯(リーラー)のために宇宙の創造を行ったとしたり、この現象世界はブラフマンの幻力(マーヤー)によって現出されたもので、本来は幻影のように実在せず、ブラフマンのみが実在すると説かれることもある。宇宙の中間にある大地は、メール山(須弥山(しゅみせん))を中心とする円盤で、七つの大陸と七つの海をもつ。メール山が真ん中にそびえ立つ大陸がジャンブ・ドゥビーパと称され、その重要部分がバーラタ・バルシャ、すなわちインドである。この宇宙は、ブラフマー(梵天)の1日の間、すなわち1カルパ(劫(こう)、地上の43億2000万年)の間持続し、1日が終わればふたたび宇宙は梵天に帰入する。宇宙は1カルパごとに創造と帰滅を繰り返す。1カルパは1000マハーユガに相当し、1マハーユガは4期からなり、後の期は前の期よりも人間の信仰・道徳性などが低下しており、現在は紀元前3102年に始まった暗黒期であるカリ期にあたり、この期の終わりに宇宙の大帰滅が起こるといわれている。
[前田専學]
業と輪廻
人間は死んで無に帰するのではなく、各自の業のために来世においてふたたび新しい肉体を得る。このように生死を無限に繰り返す。これが輪廻(りんね)である。業(ごう)とは、行為を意味するサンスクリット語のカルマンkarmanの訳語。あらゆる行為は業として蓄積され、業は、その行為者がその果報を経験し尽くさない限り消失しない。業・輪廻の思想はウパニシャッドのなかで初めて明確な形をとり、ヒンドゥー教の中核的な教義となったが、本来人間の自由意志を否定する運命論や決定論とは本質を異にしている。
[前田専學]
法(ダルマ)
サンスクリット語のダルマは、習慣、義務、教説など多くの意味をもっているが、簡単にいえば行為の規範である。ヒンドゥー教にはダルマをまとめた法典群があるが、その中心的課題は種姓法と生活期法である。種姓法はバラモン、王族、庶民、隷民の4階級(バルナ)のおのおのに課せられた法である。生活期法は学生期、家住期、林棲(りんせい)期、遊行(ゆぎょう)期という人生の4時期のおのおのについて規定されている規範である。各自の生まれた種姓と現に属する生活期に対して規定された法を、事の成否や利害を考慮することなく、利己心を離れて実践することが勧められている。ダルマの実践は、物質的・経済的利益を追求する実利(アルタ)、愛情・性愛を追求する愛欲(カーマ)、および次に説明する解脱(げだつ)とともに、ヒンドゥー教徒の人生の四大目的とされている。
[前田専學]
解脱
ダルマ・実利・愛欲はたとえ実現されたとしても、得られる結果はせいぜい天界に生まれることが最高の果報であり、結局、輪廻のなかにとどまっているにすぎない。そこでウパニシャッドの思想家たちはさらに進んで業・輪廻からのまったき自由、すなわち解脱(モークシャ)を追求するに至り、解脱が人生の最高の目的とされた。それを実現する方法として、行為の道、知識の道、信愛(バクティ)の道という三つの道が説かれ、とくに神に対する信愛の道は万人に実践可能であり、7、8世紀ころから大きな宗教運動となって展開し今日に至っている。業・輪廻・解脱の問題は、一般のヒンドゥー教徒にとって切実な問題であったばかりではなく、思想家たちにとっても重要な課題であった。種々事情を異にするとはいえ、ヒンドゥー教の頂点を形成するサーンキヤ学派をはじめとする六つの代表的哲学体系(六派哲学)が成立し、理論的・体系的に解脱とその方法を考究した。なかでもウパニシャッドに立脚するベーダーンタ学派はインド思想の主流を形成し、現代のインドの知識人の代表的な哲学となっている。
[前田専學]
儀礼と祭り
ヒンドゥー教では偶像崇拝が盛んで、毎朝、川や貯水池などで沐浴(もくよく)してシバ神などの神像を礼拝してから食事をする。儀礼には念珠を用い、マントラ(神歌)が唱えられ、御詠歌に似たバジャンが熱狂的に歌われることもある。ヒンドゥー教徒はまた聖地を崇拝し、聖地巡礼を行う。儀礼にはヤントラという象徴的・神秘的図形が用いられ、卍(まんじ)がスバスティカ(幸福の印)として使われ、儀式を行うためにマンダラと称する一定の円形の場所を設ける場合もある。儀礼のなかでも、個人の一生を通じて行うべきおよそ40にも達するサンスカーラ(通過儀礼)、とくに誕生祭、男子が正式にヒンドゥー社会の一員となる入門式や、結婚式、葬式は重要である。年間に行われる祭りの数は多数に上るが、代表的な諸神を祀(まつ)る春の祭りホーリー(2~3月)、ベンガルで盛んなドゥルガー女神の祭りドゥルガー・プージャー(9~10月)、ラーマ王子が悪魔ラーバナを征伐した記念のダセーラ祭(10月)、灯火をともし、ラクシュミー女神を祀る灯火祭ディバーリー(10~11月)などが主要なものである。
[前田専學]
『中村元著『インド思想史』(1967・岩波書店)』▽『中村元著『ヒンドゥー教史』(『世界宗教史叢書6』1979・山川出版社)』▽『山崎利男著『神秘と現実――ヒンドゥー教』(『世界の宗教6』1969・淡交社)』▽『中村元・笠原一男・金岡秀友編『アジア仏教史 インド編Ⅰ・Ⅴ』(1973・佼成出版会)』▽『辛島昇編『インド入門』(1977・東京大学出版会)』▽『前田専學著『ヒンドゥー教』(『世界の宗教』所収・1978・仏教伝道教会)』▽『早島鏡正・高崎直道・原実・前田専學著『インド思想史』(1982・東京大学出版会)』▽『L・ルヌー著、渡辺照宏・美田稔訳『インド教』(白水社・文庫クセジュ)』▽『辻直四郎著『インド文明の曙』(岩波新書)』▽『荒松雄著『ヒンドゥー教とイスラム教』(岩波新書)』
百科事典マイペディア 「ヒンドゥー教」の意味・わかりやすい解説
ヒンドゥー教【ヒンドゥーきょう】
→関連項目インド料理|エレファンタ石窟|エローラ|サティー|シカラ|ジャイナ教|ネオ・ブッディスト運動|バジャン|バーダーミ石窟|ビマーナ|仏教|ブリハディーシュワラ寺院|ホーリー|民族宗教|ムガル帝国
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「ヒンドゥー教」の解説
ヒンドゥー教(ヒンドゥーきょう)
Hinduism
ヒンドゥーは,「インダス川」を意味するサンスクリットのSindhuに由来するペルシア語で,インドに侵入したイスラーム教徒がインド人をさすのに用いた。この語が英語などに導入され,インドの宗教,文化の総称としてHinduismがつくられた。広義にはヴェーダの文化も含むが,普通は前6世紀頃から文献に現れる宗教,文化をさす。仏教,ジャイナ教により否定されたヴェーダの権威の再確立の努力と並び,非アーリヤ的土着文化の吸収とそれのバラモン教化に特徴づけられる。マヌ法典による新たなイデオロギーの確立,六派(ろっぱ)哲学などヴェーダの権威にもとづいた世界観,『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』,プラーナなどの神話,宗教儀礼を骨格とする。バクティ運動,タントリズムの形成,スーフィズムの影響を受けた宗教改革,イギリス支配下の社会改革運動などさまざまな変容を示す。現代,永遠のダルマを標榜し,反イスラーム,反キリスト教の運動を展開するヒンドゥー教原理主義が台頭してきた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヒンドゥー教」の意味・わかりやすい解説
ヒンドゥー教
ヒンドゥーきょう
Hinduism
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「ヒンドゥー教」の解説
ヒンドゥー教
ヒンドゥーきょう
Hinduism
宗祖はなく,インドの民族宗教で,かつ社会的伝統や倫理体系を含む。インド人口の約83%,約8億人が信仰する。アーリア的なバラモン教と非アーリア的な土着信仰が,前10世紀から後4世紀のグプタ朝統一までの1400年間にしだいに融合して成立した。自然崇拝が基本で,シヴァ・ヴィシュヌ・ブラフマーの三大神が信仰の中心。霊魂の不滅と輪廻 (りんね) の思想を根本とするが,教義は多様である。ヴァルナを認め,社会生活に大きな影響力を有している。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のヒンドゥー教の言及
【インド】より
… 宗教面にもこの地域の多様性は容易に見てとれる。インドを例にとると,ヒンドゥー教,シク教,ジャイナ教,仏教があり,またそのほかに各部族のそれぞれの宗教形式がある。中世以降に流入,伝播したものは,イスラムとキリスト教がおもなものである。…
【住居】より
…すなわち,寝室・台所―内―女性―家族と,接客空間―外―男性―外来者という対照である。周知のとおりイスラムやヒンドゥー教を信奉する民族においては,この二元性が強い規制として働くし,その強度に差はあっても東アフリカのダトーガ族やマサイ族のような一夫多妻制における〈女の家〉と〈男の家〉といった対比の形も見られる。このような分割原理が広く存在することは,生物学的レベルに根差した日常生活における男女の役割分担の普遍性の現れと見ることもできる。…
【バクティ】より
…インドの宗教,とくにヒンドゥー教における重要概念。これは,最高の人格神に,肉親に対するような愛の情感を込めながらも絶対的に帰依することであり,ふつう〈信愛〉と訳されている。…
【バラモン教】より
…ヒンドゥー教の前身で,しかもその核となっている宗教,社会思想。〈バラモン教Brahmanism〉という語は近代になってからの英語の造語であるが,これに最も近い意味をもつサンスクリットは,おそらく〈バイディカvaidika〉(ベーダに由来するものごと)である。…
※「ヒンドゥー教」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...