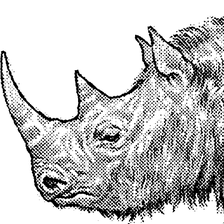改訂新版 世界大百科事典 「ケサイ」の意味・わかりやすい解説
ケサイ (毛犀)
wooly rhinoceros
Coelodonta antiquitatis
2万~10万年前の大氷河時代の終りに,ヨーロッパから北アジアにかけて広く分布していた大型で毛深いサイ。シベリアのツンドラ地帯で氷漬で保存のよい化石が発見されるが,1907年と29年にポーランドの油田地帯のガリツィア地方のスタルニアで発見されたものは,塩水と石油の歴青分がからだにしみこみ,軟体部がよく保存されていて,クラクフの博物館に陳列されている。このサイは,頭骨の長さが85cm以上のものもあり,体長は3m前後,サイとしては大型である。頭は長細く,幅が広く,鼻と前頭骨の上に毛をよりあわせたような長い角(20cm前後もある)が2本ある。アフリカの2角のサイと同じだが,ケサイは1対の牙状の切歯が上下のあごに発達することなど,むしろ現在のスマトラサイに近い。また,鼻中隔の構造が複雑であり,鼻吻(びふん)部が下方に曲がり,鼻孔部が外気にさらされないようになっていたり,10cmもの長い毛がからだ全体をおおっていることは寒冷気候への適応を示している。臼歯の歯冠が高く,セメント質が発達することは草原の生活への適応を示し,寒冷なツンドラ地帯から乾燥した温和な草原まで幅広い生活をしていたと思われる。旧石器時代後期の洞穴の壁画にも見られるが,マドレーヌ期ごろには絶滅してしまった。
執筆者:亀井 節夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報