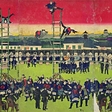日本大百科全書(ニッポニカ) 「出初式」の意味・わかりやすい解説
出初式
でぞめしき
公式には消防出初式という。消防団が新年最初に行う演習の儀式。1月2日の仕事始めと一連のものであるが、東京では1月6日に行われ、全国的にほぼ統一された。日本の消防組織は、江戸幕府が大名火消、旗本火消(定火消(じょうびけし))を設置したのが始まりだとされており、その組織が整ったのは1658年(万治1)であった。1718年(享保3)町奉行(ぶぎょう)令によって町火消を設けたが成果があがらず、1720年改組し、「いろは四十七組」(のち四十八組)が発足した。出初式は町火消の初出(はつで)行事で、「いろは四十八組」の江戸町火消は、それぞれの纏(まとい)を奉持して町を練り歩き、梯子(はしご)乗りの妙技を披露した。1948年(昭和23)の「消防法」によって自治体消防が発足してからは、消防団のパレードや一斉放水、優良団員の表彰などの行事が多い。
[井之口章次]