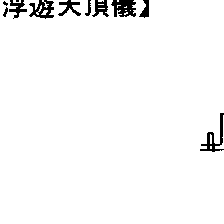改訂新版 世界大百科事典 「浮遊天頂儀」の意味・わかりやすい解説
浮遊天頂儀 (ふゆうてんちょうぎ)
floating zenith-telescope
天文緯度観測専用の望遠鏡。1900年にイギリスのクックソンが発明した天頂儀の一種。水準器のかわりに,水銀槽の上に浮かしたフロートに望遠鏡を固定し,子午線を通過する南北1対の星を写真乾板に撮影し,2星間の距離を測定して天文緯度を求める。岩手県水沢市の緯度観測所のものは,口径17.8cm,焦点距離179cmで,1939年から観測を続けている世界唯一の望遠鏡である。
執筆者:若生 康二郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報