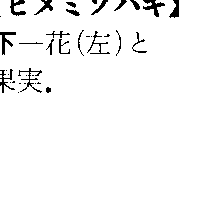改訂新版 世界大百科事典 「ヒメミソハギ」の意味・わかりやすい解説
ヒメミソハギ
Ammannia multiflora Roxb.
水田や原野の湿地に生えるミソハギ科の一年草。茎は高さ20~30cmで直立し,上部で分枝する。葉は対生し,線形または披針形で,基部は耳形に張り出して茎を抱く。全体に毛がなく,枝の上につく葉は小型になる。花は小さく,夏から秋にかけて葉腋(ようえき)にむらがってつき,径約1.5mm。萼は筒円錐形で4稜があり,先は4裂して三角形の萼歯となる。花弁は4枚でごく小さい。おしべは4本。めしべは1本で子房上位,先に1本の花柱がある。果実は球形の蒴果(さくか)となり,径約2mm,熟すと不規則に裂けて中から多数の小さい種子が出る。アジア,東南アジア,オーストラリア,東南ヨーロッパ,北アフリカの水湿地に広く分布し,水田雑草の一つである。ミソハギに似て小型であるのでヒメ(姫)ミソハギといわれるが,ミソハギ属ではなく,一名ヤマモモソウとも呼ばれる。近年,農薬の影響を受けてひじょうに少なくなった。
執筆者:村田 源
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報