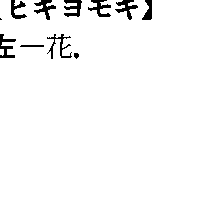ヒキヨモギ
Siphonostegia chinensis Benth.
低山地の草原に生えるゴマノハグサ科の半寄生の一年草。貧弱な根から直立する茎は,高さ30~70cm。葉は下部で対生,上部で互生し,卵形で,広線形の裂片に深く裂け,長さ1.5~5cm,幅1~3cm,全体に短い毛がある。8~9月,上部の葉のわきに,鮮黄色で上唇下側が赤褐色の目だつ唇形花冠をもつ花をつける。花は筒状で,10本の縦条のある萼に包まれ,長さ2.8cm,上唇は左右に扁平な筒状で,先がとがる。果実は狭長楕円形の蒴果(さくか)で,長さ14~17mm。南千島,北海道から琉球までの日本全土,朝鮮,中国に分布する。中国では全草を解熱に用いる。
ヒキヨモギ属Siphonostegiaは東アジアに2種,西アジアに1種ある。オオヒキヨモギS.laeta S.Mooreは乾いた草地に生え,全体に腺毛があり,花は灰黄色。本州の関東以西,四国と中国中部に分布する。
執筆者:山崎 敬
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヒキヨモギ
ひきよもぎ / 蟇蓬
[学] Siphonostegia chinensis Benth.
ゴマノハグサ科(APG分類:ハマウツボ科)の半寄生性の一年草。茎は直立し、高さ30~70センチメートル。葉は卵形で長さ1.5~5センチメートル、広線形の裂片に深く裂ける。初秋のころ、枝先の葉腋(ようえき)に黄色花を開く。花冠は唇形で長さ1~1.7センチメートル、上唇は鎌(かま)形で先はとがる。萼(がく)は筒状、10本の脈がある。低山の草地に生え、日本、および朝鮮半島、台湾、中国に分布する。近縁種オオヒキヨモギは全体に腺毛(せんもう)があり、花は灰黄色である。関東、東海地方、近畿地方、中国地方、瀬戸内沿岸など、年降水量の少ない地方の林縁に生え、中国にも分布する。
[山崎 敬 2021年9月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヒキヨモギ(引蓬)
ヒキヨモギ
Siphonostegia chinensis
ゴマノハグサ科の半寄生の一年草。日本全土をはじめ東アジアに広く分布し,日当りのよい草地に生える。茎の高さ 30~60cmとなり,表面はざらつく。葉は三角形で羽状に深裂し,翼のある柄をつける。花は8月頃,葉腋に長さ2~3cmの淡黄色の唇形花をつける。花冠は2唇形で下唇は3裂する。 蒴果は萼筒に包まれ,楕円形の多数の種子がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by