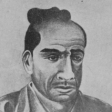日本大百科全書(ニッポニカ) 「久米栄左衛門」の意味・わかりやすい解説
久米栄左衛門
くめえいざえもん
(1780―1841)
幕末の技術者。讃岐国(さぬきのくに)(香川県)大内郡引田郷(ひけたごう)(東かがわ市)馬宿(うまやど)の船乗り兼農家に生まれる。大坂の間重富(はざましげとみ)に数理、天文、測量などを学んだ。帰郷後も天文観測を続け、また伊能忠敬(いのうただたか)の来藩の際にはその接伴案内をした。1809年(文化6)高松藩天文測量方御用となり、のち士分に取り立てられ久米姓を名のった。ぜんまいと火打(ひうち)石を組み合わせて連続して火花をおこす鋼輪(こうりん)仕掛けの輪燧佩銃(りんすいはいじゅう)、生火銃・鎗間銃(そうかんじゅう)(雷管銃)、風砲(空気銃)など銃砲の改良や発明に尽くした。また農業用揚水機をくふうして畜力利用の「養老滝」を考案。殖産興業に努力し、塩田の築造、鉱山の排水、港湾や河川の改修などに従事した。とくに坂出(さかいで)に131町歩(約130ヘクタール)の塩田を開発した業績は大きかった。
[菊池俊彦]
『岡田唯吉編『讃岐偉人久米栄左衛門翁』(1964・鎌田共済会)』