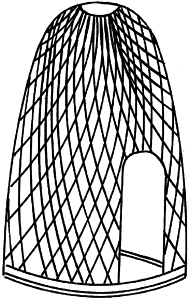関連語
精選版 日本国語大辞典 「助炭」の意味・読み・例文・類語
じょ‐たん【助炭】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「助炭」の意味・わかりやすい解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
食器・調理器具がわかる辞典 「助炭」の解説
じょたん【助炭】
世界大百科事典(旧版)内の助炭の言及
【せんべい(煎餅)】より
…表面が膨れあがって鬼面のようになるので,鬼せんべいと称された。それを売り歩く行商人がいて,餅を入れた籠と火鉢をおさめた助炭(じよたん)とを一荷にして担いでいた。やがて鉄の焼型にはさんで焼くようになり,また,鶏卵,みそ,ゴマ,ケシなどの副材料を配合するなどして,小麦粉系のせんべいは多彩になっていった。…
※「助炭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...