日本大百科全書(ニッポニカ) 「ジメチルジクロロシラン」の意味・わかりやすい解説
ジメチルジクロロシラン
じめちるじくろろしらん
dimethyldichlorosilane
有機ケイ素化合物の一つ。常温で無色の液体。水に対してきわめて不安定であり、容易に反応して塩化水素を発生するため、刺激臭がある。
製法は、金属ケイ素と塩化メチルを触媒存在下で高温で反応させると他のメチルシラン類とともに得ることができ、蒸留で精製する。ポリジメチルシロキサンHO(SiMe2OSiMe2)nOHはこの物質が原料であり、条件により重合度を変えることができるので、工業的に非常に有用な原料である。合成化学的にはジオールの保護のためのシリル化剤として有用である。
[西山幸三郎]
[参照項目] |
[補完資料] |

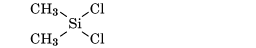
 )1.4055
)1.4055