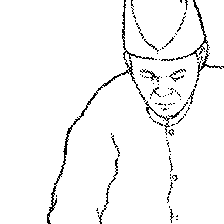カチャピ
kacapi[インドネシア]
東南アジアに広く分布する撥弦楽器。舟形の胴体に多くの弦を張ったチター属のものと,細長い棹を有し2~数本の弦を張ったリュート属のものとに分類される。また地域によって名称が少しずつ異なる。チター属の代表的なものは,ミンダナオ島のクジャピ,ジャワ西部のカチャピで,特に後者は歌や笛と組み合わされ音楽的にきわめて芸術性の高いものである。リュート属のものには,スマトラのバタク族のカチャピ(ハサピ),スラウェシのブギス族のカチャピ,カリマンタンのダヤク族のサペ(サンベ,イムパイ)がある。タイではクラジャピと呼ばれる。多くの場合歌の伴奏や叙事詩の弾き語りに用いられる。
執筆者:田村 史子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
カチャピ
かちゃぴ
kacapi
インドネシアの弦鳴楽器の一種。クチャピkěcapiともいう。これには次の2種がある。
(1)スンダ(西ジャワ)地方のチター属の撥奏(はっそう)楽器。7~24本の金属弦が木製の舟形の胴に張られ、胴側面の糸巻と響板に立てられた可動の駒(こま)(柱(じ))によって調弦される。義甲(ぎこう)を用いず生爪(なまづめ)で奏す。この舟形(大小2種)のほかに、携帯可能の箱形もあり、いずれも、歌の伴奏、器楽合奏に広く用いられる。
(2)スマトラ、スラウェシ(セレベス)、ボルネオ島などのリュート属の撥弦楽器。たいてい1~2弦。この種は、名称や形をすこしずつ変えて、タイ、カンボジアなどにも広く分布している。
[川口明子]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
カチャピ
インドネシア,西部ジャワのツィター属撥弦楽器。舟形の木製共鳴胴に金属弦を7〜24本を張り,両手の指で弦をはじいて鳴らしたり,音を止めたりする。古典吟誦詩トゥンバンの伴奏を務める室内合奏に用いられる。古代叙事詩パントゥンや豊作祈願の秘儀の踊りの伴奏にも。最近では共鳴胴が平らな台形に変わり,響板に電気増幅装置をつけたものもある。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のカチャピの言及
【フィリピン】より
…ゴングを横にねかせて枠の上に並べたクリンタンkulintangを中心とするアンサンブルは,[5音音階]とコロトミック(コロトミーcolotomy音楽的句読法)な規則正しい時間分割を最大の特徴としている。フィリピンの代表的な楽器としては,このほかに[口琴](竹製のクビン,金属製のオンナ),舟形撥弦のクジャピ([カチャピ]),[ノーズ・フルート],割れ目太鼓,搗奏竹筒,鉢巻式歌口の笛などがある。声楽は北部の自由リズムとファルセット多用の合唱や語り的独唱,南部のイスラム教徒による装飾音の多い歌唱などに特徴がある。…
※「カチャピ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by