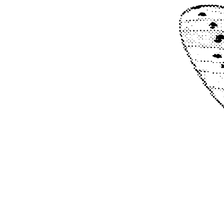クワゴマダラヒトリ
Spilosoma imparilis
鱗翅目ヒトリガ科の昆虫で,幼虫はクワの害虫として知られているが,かなり多食性でバラ科,ブナ科,スイカズラ科植物の各種に寄生する。十分成長した幼虫は体長5cmに達する毛虫となる。若齢の間は葉に糸を吐いて丸めた巣で集団生活をし,葉脈を残して網目状に食害する。若齢幼虫で越冬する。翌春再び葉を食べ,老熟すると分散し,春の終りころに褐色の体毛を混ぜた粗い繭をつくって蛹化(ようか)。成虫は9月ころに羽化し,食樹の幹や枝に卵をかためて産みつけ雌の尾毛で覆う。雄は褐色を帯びた黒色で,黒紋を連ねるが,雌は雄よりはるかに大きく,翅は白色に近いクリーム色,前翅には雄と同じような黒紋が多数あるが,その色は薄い。雌雄とも灯火に飛来する。北海道から九州まで各地にごくふつうに見られる。
執筆者:井上 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
クワゴマダラヒトリ
くわごまだらひとり / 桑胡麻斑灯蛾
[学] Spilosoma imparilis
昆虫綱鱗翅(りんし)目ヒトリガ科に属するガ。はねの開張は雄40ミリメートル内外、雌50ミリメートル内外。雌雄によって、大きさのほか色彩がまったく異なる。雄のはねは黒褐色で、黒紋を連ねる。雌は黄白色の地に多数の黒紋をもつ。腹部は赤黄色であるが、雄では黒みを帯びる。年1回の発生で、9月ごろ成虫が出現する。よく灯火に飛来する。北海道から屋久(やく)島までと、中国大陸に分布する。幼虫は黒っぽい毛虫で、背面に細長い白紋を連ね、各節に橙黄(とうこう)色紋をもつ。クリ、コナラ、ヤナギ、サクラなど多くの樹木に寄生するが、クワの害虫として知られている。若齢の間は糸を吐いて巣をつくり、集団生活をする。7月ごろ葉間に茶褐色の体毛を混ぜた薄い繭をつくって蛹化(ようか)する。若齢幼虫で越冬する。
[井上 寛]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「クワゴマダラヒトリ」の意味・わかりやすい解説
クワゴマダラヒトリ
鱗翅(りんし)目ヒトリガ科の1種。雄は開張30mm内外,暗褐色,雌は開張55mm内外,白色。雄雌ともに黒点を散らす。日本全土と中国に分布。幼虫はクワノスムシ(桑の巣虫)とも呼ばれ,クワまたはバラ科植物の葉を食べる害虫。成虫は年1回夏に現れる。
→関連項目ヒトリガ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
クワゴマダラヒトリ
学名:Spilosoma imparilis
種名 / クワゴマダラヒトリ
解説 / オスとメスで、はねの色がまったくちがいます。
目名科名 / チョウ目|ヒトリガ科
体の大きさ / (前ばねの長さ)♂20~23mm、♀28~32mm
分布 / 北海道~九州
成虫出現期 / 8~9月
幼虫の食べ物 / クワ、クリ、コナラなど
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by