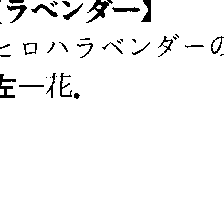翻訳|lavender
精選版 日本国語大辞典 「ラベンダー」の意味・読み・例文・類語
ラベンダー
改訂新版 世界大百科事典 「ラベンダー」の意味・わかりやすい解説
ラベンダー
lavender
ヨーロッパの香料作物として有名なシソ科の半木本性植物。精油を採取するため栽培される植物の基本になったものはトゥルーラベンダーLavandura angustifolia Mill.(=L.spica L.)(英名true lavender,common lavender)であるが,栽培される系統の多くはヒロハラベンダーL.latifolia Med.(英名spike lavender)が多少とも交雑した雑種であると考えられている。
トゥルーラベンダーは地中海からアルプス地方に原産する多年草で,草丈は約1mになり,夏にライラック色の花を長い花梗に6~10花ずつ輪状につけ,全体として穂のようになる。ヒロハラベンダーは,より木質化した茎を有し,葉は幅が広く,開花時には花茎は多少とも分枝することで区別され,西部地中海地域に分布する。寒さにもやや弱い。ラベンダーは日本では文化年間(1804-18)に記載があり,当時すでにヨーロッパから渡来していたと考えられる。主産地はフランス,イタリア,スペインで,日本では現在は北海道と長野県で栽培されている。花が8分咲きのときが最も精油収量が高く,北海道の例では,7月に花穂の下1葉から鎌で刈り取って収穫する。生の花穂を水蒸気蒸留すると0.5~0.8%の黄色の精油(ラベンダー油)が得られ,セッケン,化粧品などの香料とされる。昔は薬用にも使われた。欧米では観賞用にも栽培され,園芸品種もいくつか知られている。繁殖は5月に挿木し,秋または翌年4~5月に定植する。
執筆者:星川 清親
語源,民俗
ラベンダーの名は,一説には古代ローマ人が浴槽に入れて芳香を楽しんだことから,ラテン語のlavare(〈洗う〉の意)に由来するといわれる。その芳香油(ラベンダー油)は古くから需要の高い商品であり,干した花でポプリも盛んに作られた。これをたんす(簞笥)に入れれば虫よけになるといい,ここから英語の〈たいせつに保管するto lay(up)in lavender〉との成句も生じた。この花に毒蛇がすむとして花輪に加えることを嫌うのは,ローマ時代からの習慣といわれている。花言葉は〈清潔,新鮮〉〈貞節〉など。
執筆者:荒俣 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラベンダー」の意味・わかりやすい解説
ラベンダー
らべんだー
lavender
[学] Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula vera DC.
シソ科(APG分類:シソ科)の小低木。地中海沿岸地域の原産で、香料作物として栽培され、南フランスが主産地として名高い。高さ約60センチメートル、茎に白い軟毛が密生するため灰白色にみえる。葉は細く長さ約5センチメートル、幼茎では輪生、成長につれて対生となる。初夏に長さ30センチメートルの花茎を多数直立し、美しい紫色の唇形花を10個ほど輪生する。花は径約1センチメートル。植物体全体に芳香があり、花が開くころに刈り取り、蒸留法によって香油をとる。これをラベンダー油とよび、主成分は酢酸リナリルである。花だけからとるものがもっとも品質が優れる。ローマ時代には入浴用の香水として用いられたので、ラテン語の「洗う」という意味のlavareがラベンダーの名のもとになった。現在も多く栽培され、化粧品の香料、香水に用いられる。薬用には神経痛などに用いられ、また軟膏(なんこう)や塗布剤の香料にも使われる。日本へは江戸時代、文化(ぶんか)年間(1804~1818)に渡来し、現在は北海道でおもに栽培されている。日当りのよい湿気のある土地でよく育つ。
[星川清親 2021年9月17日]
文化史
古代のギリシアで栽培され、花冠や花輪に使われていた。テオフラストスは、種子から育てると述べている(『植物誌』)。ディオスコリデスはフレンチ・ラベンダーL. stoechos L.の産地としてストエカデス諸島をあげ、痛み止めや解毒剤に混ぜると記述している(『薬物誌』De materia medica)。カンフェンを含み、ヨーロッパではけいれんや喘息(ぜんそく)の民間薬にされた。香水や花を磁器の色づけにも使った。花はポプリの代表的な材料である。
[湯浅浩史 2021年9月17日]
食の医学館 「ラベンダー」の解説
ラベンダー
最盛期になると、紫、白、ピンクなどの花を一斉に咲かせるとともに、草全体から気品ある芳香を放つため、「香りの女王」とも呼ばれます。
また、中世ヨーロッパでペストが流行したとき、ラベンダー畑で働いていた人は感染を免れたといわれるように強い抗菌作用をもち、効用の面でも優秀。ちなみに、ラベンダーの品種は28種類ありますが、薬用としては、イングリッシュ・ラベンダーがもっともよく用いられています。
ラベンダーには、抗菌、鎮痛、消炎、けいれん止め、循環器の活性化、胆汁(たんじゅう)の分泌促進(ぶんぴつそくしん)といった作用があります。
具体的症状としては、頭痛、とくに鋭い頭痛をやわらげるほか、消化不良、胃炎、腹部膨満、神経衰弱などに有効。
○外用としての使い方
精油を吸入に用いれば、かぜやぜんそくの症状緩和に役立ちます。また、ハーブティーを湿布や入浴剤に用いれば、打ち身、ねんざ、やけど、湿疹(しっしん)にも効果があります。
おりものが気になるときは、ハーブティーで腟(ちつ)洗浄するといいでしょう。
ただし、妊娠中の人は多用するのを避けてください。
〈ハーブティーやジャム、ゼリーの香り付けにピッタリ〉
○食品としての使い方
ハーブとしてのラベンダーは、花の部分を利用します。ハーブティーやジャムのほか、酢につけてラベンダービネガーにしたり、ゼリー、シャーベット、カクテルの香り付けにもピッタリ。
また、ポプリやハーブピローなど、クラフト材料にも広く用いられています。
百科事典マイペディア 「ラベンダー」の意味・わかりやすい解説
ラベンダー
→関連項目精油
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
色名がわかる辞典 「ラベンダー」の解説
ラベンダー【lavender】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ラベンダー」の意味・わかりやすい解説
ラベンダー
Lavandula officinallis; lavender
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「ラベンダー」の解説
ラベンダー
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...