関連語
精選版 日本国語大辞典 「定率法」の意味・読み・例文・類語
ていりつ‐ほう‥ハフ【定率法】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定率法」の意味・わかりやすい解説
定率法
ていりつほう
declining balance method
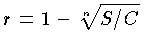 ( C は取得原価,S は残存価額,n は耐用年数) S が0であれば r は1となるから,残存価額が0のときには定率法を適用できない。毎期首の帳簿価額および毎期の減価償却費が (1-r) を公比として逓減するため,逓減残高法ともいわれる。日本では実際には上記計算式を用いて償却率の算出を行う必要はなく,税法における「減価償却資産の耐用年数に関する省令」において耐用年数ごとの償却率が算出されているのでそれを用いればよい。この方法は定額法とともに税法で規定されているため最も広く利用されている。さらに定額法に比べて償却の初期に多額の減価償却費を計上できるので,償却の繰上げ効果が期待でき投下資本の早期回収に役立つ。すなわち設備投資の初期には節税効果が期待できるということでもある。さらに毎期首の帳簿価額に対し,毎期一定率の償却率を乗じればよいので計算が容易であるなど利点が多い。
( C は取得原価,S は残存価額,n は耐用年数) S が0であれば r は1となるから,残存価額が0のときには定率法を適用できない。毎期首の帳簿価額および毎期の減価償却費が (1-r) を公比として逓減するため,逓減残高法ともいわれる。日本では実際には上記計算式を用いて償却率の算出を行う必要はなく,税法における「減価償却資産の耐用年数に関する省令」において耐用年数ごとの償却率が算出されているのでそれを用いればよい。この方法は定額法とともに税法で規定されているため最も広く利用されている。さらに定額法に比べて償却の初期に多額の減価償却費を計上できるので,償却の繰上げ効果が期待でき投下資本の早期回収に役立つ。すなわち設備投資の初期には節税効果が期待できるということでもある。さらに毎期首の帳簿価額に対し,毎期一定率の償却率を乗じればよいので計算が容易であるなど利点が多い。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
人材マネジメント用語集 「定率法」の解説
定率法
・fixed rate method
・減価償却の計算方法の1つで、固定資産の価値が毎年定率で下がると考える。
・未償却算残高に、償却率を用いて減価償却費を計上していく
・一年当りの減価償却費=未償却残高×償却率
・定率法は、使用年数に比例して効率、価値が逓減する資産に適している。初期に多額の費用を計上するので早期の節税が可能となり資金繰りに貢献するというメリットがある。逆に耐用年数期間の後半の減価償却の目減りすることがデメリットである。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
世界大百科事典(旧版)内の定率法の言及
【減価償却】より
…もちろんその結果,費用化分は収益から回収され,固定資産の取替資金として役立つし(取替資金計算目的),また費用化された減価償却の累計額を考慮することによりその時点の固定資産の財産的価値を把握するのにも役立つ(財産計算目的)が,いずれにも限界があり,本質的目的とはされえない。
[減価償却法]
減価償却の計算方法には種々のものがあるが,一般的方法としては定額法,定率法,産高比例法があげられる。(1)定額法とは,毎事業年度の償却額が一定額となるような計算方法で直線法とも呼ばれ,つぎの算式で計算される。…
※「定率法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

