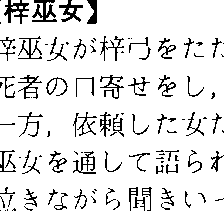改訂新版 世界大百科事典 「梓巫女」の意味・わかりやすい解説
梓巫女 (あずさみこ)
関東地方から東北地方にかけて分布する巫女の名称。梓弓は古代より霊を招くために使われた巫具で,これを用いてカミオロシ,ホトケオロシをすることから梓巫女の名がおこった。能の《葵上》には照日と呼ばれる巫女が梓弓の弦をはじいて口寄せする謡がある。津軽地方のイタコは〈いらたか念珠〉を繰ったり弓の弦を棒でたたいて入神状態になる。また,陸前地方の巫女であるオカミンたちはインキンと称する鉦(かね)を鳴らしながら入神する。神がかりのおりに用いる巫具はさまざまであるが,梓巫女は竹の棒で棒弓の弦を打ち,ブルンブルンと発する音によって神がかるのである。また,梓巫女は県(あがた)巫女,イタコなどと同様に諸国を巡遊する歩き巫女の系譜をひき,梓弓を打ち鳴らし,その単調なリズムと経文のような神語りで口寄せをし,ミコ神や八幡,神明その他の信仰を広めると同時に,オシラ祭文などを語り伝えた。
執筆者:佐野 賢治
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「梓巫女」の意味・わかりやすい解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...