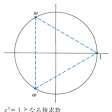関連語
精選版 日本国語大辞典 「累乗根」の意味・読み・例文・類語
るいじょう‐こん【累乗根】
- 〘 名詞 〙 その累乗がaになる数のaに対する称。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「累乗根」の意味・わかりやすい解説
累乗根
るいじょうこん
nを2以上の整数とするとき、n乗してaになる数、つまり、xn=aとなる数xを、aのn乗根といい、二乗根、三乗根、……を総称して、aの累乗根という(べき根ともいい、羃根(べきこん)、巾根(べきこん)とも書く)。aの二乗根(平方根)、三乗根(立方根)は累乗根の一つといえる。
実数の範囲で考えるとき、次のことがいえる。nが奇数のとき、実数aに対して、aのn乗根はただ一つある。これを と表す。nが偶数のとき、正の数aに対して、aのn乗根は正・負一つずつある。その正のほうを
と表す。nが偶数のとき、正の数aに対して、aのn乗根は正・負一つずつある。その正のほうを と表す。負のほうは-
と表す。負のほうは- となる。とくにnが2の場合は、
となる。とくにnが2の場合は、 と書かずに
と書かずに と書く。また、nが偶数のとき、負の数aのn乗根は存在しない。
と書く。また、nが偶数のとき、負の数aのn乗根は存在しない。
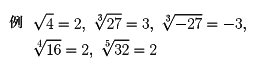
正の数a、bの累乗根については、次の法則が成り立つ。
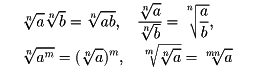
以上は実数の範囲での累乗根である。いま複素数の範囲で考えると、0と異なる数に対して、そのn乗根は、ちょうどn個存在する。とくに、1のn乗根を考えると、n個あり、それらは複素平面上で表すと、原点を中心とする半径1の円周上にあって、1を一つの頂点とする正n角形の頂点となる。
[三輪辰郎]
[参照項目] |
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「累乗根」の意味・わかりやすい解説
累乗根
るいじょうこん
root
 ,(2) a が正,n が奇数のとき
,(2) a が正,n が奇数のとき  ,(3) a が負,n が偶数のとき,存在しない,(4) a が負,n が奇数のとき
,(3) a が負,n が偶数のとき,存在しない,(4) a が負,n が奇数のとき  ,の四つの場合にかぎられる。一方 a が 0でない複素数のとき,方程式 xn=α(α≠0)を満足する複素数 x は,α=a+ib を表す点(a,b)の極表示に関する動径を r,偏角をθとするとき,絶対値が r の n 乗根,偏角がθ/n およびそれに 2π/n の整数倍を加えた合計 n 個の極座標で表される値である。(→累乗)
,の四つの場合にかぎられる。一方 a が 0でない複素数のとき,方程式 xn=α(α≠0)を満足する複素数 x は,α=a+ib を表す点(a,b)の極表示に関する動径を r,偏角をθとするとき,絶対値が r の n 乗根,偏角がθ/n およびそれに 2π/n の整数倍を加えた合計 n 個の極座標で表される値である。(→累乗)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「累乗根」の意味・わかりやすい解説
累乗根 (るいじょうこん)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の累乗根の言及
※「累乗根」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...