関連語
精選版 日本国語大辞典 「鍔」の意味・読み・例文・類語
つば【鍔・鐔】
- 〘 名詞 〙
- ① 刀剣装備の付属金具。柄を握る拳(こぶし)の防御具。金属や革・角の類で作り、形や大きさは種々で、角(かく)鍔、丸鍔、車鍔、粢(しとぎ)鍔、葵鍔などの名がある。つみは。〔色葉字類抄(1177‐81)〕
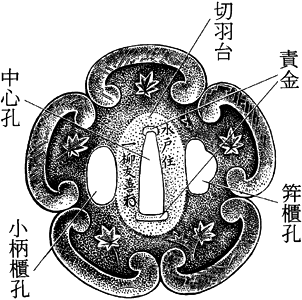 鍔①
鍔①
- ② 釜(かま)の胴のまわりに、ひさしのようにうすく張り出した部分。
- ③ 帽子の下部の周囲に張り出した部分。
- ④ 限度。かぎり。
- [初出の実例]「銀に鍔なし島原」(出典:雑俳・万歳烏帽子付合大全(1703))
- ⑤ 担子菌類の子実体の柄の上部に見られる①のような付属物。かさの裏面のひだをおおって保護していた内被膜が、かさが開く時に一部がちぎれて残ったもの。これの有無、着生する位置、永存性か否か、形、質、色、大きさなどは分類上の特徴となる。テングタケ類は特に大きくて有名。
つみ‐は【鍔・鐔】
普及版 字通 「鍔」の読み・字形・画数・意味
鍔
17画
[字訓] つば
[字形] 形声
声符は咢(がく)。〔玉
 〕に「刀
〕に「刀 なり」とあり、剣刃や剣端、刀のみね、剣稜をいう。わが国では刀のつばの意に用いる。
なり」とあり、剣刃や剣端、刀のみね、剣稜をいう。わが国では刀のつばの意に用いる。[訓義]
1. やきば、きっさき、刀のみね。
2. つば。
3. 鍔鍔は高いさま。
4. きし、がけ。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕鍔 ヤキバ・ハ 〔
 立〕鍔 ヤキハ・ツバ・モトリ 〔字鏡集〕鍔 ヤキハ・ツルギ・カタチ・ハ
立〕鍔 ヤキハ・ツバ・モトリ 〔字鏡集〕鍔 ヤキハ・ツルギ・カタチ・ハ[熟語]
鍔鍔▶
[下接語]
鉛鍔・垠鍔・剣鍔・皓鍔・淬鍔・染鍔・霜鍔・挺鍔・氷鍔・鋒鍔・
 鍔・
鍔・ 鍔・廉鍔・斂鍔
鍔・廉鍔・斂鍔出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
関連語をあわせて調べる
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新



